�m�l�d�m�t�n
![]() �@�X�^�[�E�E�H�[�Y�^�t�H�[�X�̊o���@(2015.12.21.)
�@�X�^�[�E�E�H�[�Y�^�t�H�[�X�̊o���@(2015.12.21.)
![]() �@�G�[���I�@(2015.12.4.)
�@�G�[���I�@(2015.12.4.)
![]() �@�~�P�����W�F���E�v���W�F�N�g�@(2015.11.23.)
�@�~�P�����W�F���E�v���W�F�N�g�@(2015.11.23.)
![]() �@�p���R��̈�Y�����l�@(2015.10.26.)
�@�p���R��̈�Y�����l�@(2015.10.26.)
![]() �@�}�C�E�C���^�[���@(2015.10.26.)
�@�}�C�E�C���^�[���@(2015.10.26.)
![]() �@�A�f���C���A100�N�ڂ̗��@(2015.10.6.)
�@�A�f���C���A100�N�ڂ̗��@(2015.10.6.)
![]() �@�i�C�g�N���[���[�@(2015.10.6.)
�@�i�C�g�N���[���[�@(2015.10.6.)
![]() �@�W�����E�E�B�b�N�@(2015.10.2.)
�@�W�����E�E�B�b�N�@(2015.10.2.)
![]() �@�r�b�O�Q�[���^�哝�̂Ə��N�n���^�[�@(2015.10.2.)
�@�r�b�O�Q�[���^�哝�̂Ə��N�n���^�[�@(2015.10.2.)
![]() �@�����킹�͂ǂ��ɂ����@(2015.7.29.)
�@�����킹�͂ǂ��ɂ����@(2015.7.29.)
![]() �@�^�[�~�l�[�^�[�F�V�N���^�W�F�j�V�X�@(2015.7.29.)
�@�^�[�~�l�[�^�[�F�V�N���^�W�F�j�V�X�@(2015.7.29.)
![]() �@�A���X�̂܂܂��@(2015.6.14.)
�@�A���X�̂܂܂��@(2015.6.14.)
![]() �@���݂�����̍�@�@(2015.5.7.)
�@���݂�����̍�@�@(2015.5.7.)
![]() �@�ނƔޏ��̃Z�I���[�@(2015.3.18.)
�@�ނƔޏ��̃Z�I���[�@(2015.3.18.)
![]() �@�o�[�h�}���@���邢�́i���m�������炷�\�����ʊ�Ձj�@(2015.3.18.)
�@�o�[�h�}���@���邢�́i���m�������炷�\�����ʊ�Ձj�@(2015.3.18.)
![]() �@�Q�O�P�T�N�I�X�J�[�i�C�g�E�E�H�b�`���O�I�@(2015.2.27.)
�@�Q�O�P�T�N�I�X�J�[�i�C�g�E�E�H�b�`���O�I�@(2015.2.27.)
![]() �@�Z�b�V�����@(2015.2.21.)
�@�Z�b�V�����@(2015.2.21.)
![]() �@�`���[���[�E�����f�J�C�@�ؗ�Ȃ閼��̔閧�@(2015.2.18.)
�@�`���[���[�E�����f�J�C�@�ؗ�Ȃ閼��̔閧�@(2015.2.18.)
![]() �@�Q�O�P�S�N�i���́j�x�X�g�W�I�@(2015.2.13.)
�@�Q�O�P�S�N�i���́j�x�X�g�W�I�@(2015.2.13.)
![]() �@�_�͎��̂��@(2015.1.15.)
�@�_�͎��̂��@(2015.1.15.)
![]() �@�U�˂̃{�N���A��l�ɂȂ�܂ŁB�@(2015.1.15.)
�@�U�˂̃{�N���A��l�ɂȂ�܂ŁB�@(2015.1.15.)
![]() �@�`�m�m�h�d�^�A�j�[�@(2014.12.27.)
�@�`�m�m�h�d�^�A�j�[�@(2014.12.27.)
![]() �@�t���[���[�@(2014.12.27.)
�@�t���[���[�@(2014.12.27.)
![]() �@�S�[���E�K�[���@(2014.11.8.)
�@�S�[���E�K�[���@(2014.11.8.)
![]() �@�C�R���C�U�[�@(2014.11.8.)
�@�C�R���C�U�[�@(2014.11.8.)
![]() �@�u�ǃh���v�Ɓu���ւ̒鉤�v�@(2014.9.28.)
�@�u�ǃh���v�Ɓu���ւ̒鉤�v�@(2014.9.28.)
![]() �@�W���[�W�[�E�{�[�C�Y�@(2014.9.28.)
�@�W���[�W�[�E�{�[�C�Y�@(2014.9.28.)
![]() �@�t�����N�@�@(2014.9.28.)
�@�t�����N�@�@(2014.9.28.)
![]() �@������w�A�i��x�@(2014.7.18.)
�@������w�A�i��x�@(2014.7.18.)
![]() �@�P�[�v�^�E���@(2014.7.18.)
�@�P�[�v�^�E���@(2014.7.18.)
![]() �@�R�O�O���X���[�n���h���b�h���鍑�̐i���@(2014.6.28.)
�@�R�O�O���X���[�n���h���b�h���鍑�̐i���@(2014.6.28.)
![]() �@�}���t�B�Z���g�@(2014.6.28.)
�@�}���t�B�Z���g�@(2014.6.28.)
![]() �@�I�[���E���[�E�j�[�h�E�C�Y�E�L���@(2014.6.28.)
�@�I�[���E���[�E�j�[�h�E�C�Y�E�L���@(2014.6.28.)
![]() �@�m�A�^�̏M�@(2014.5.25.)
�@�m�A�^�̏M�@(2014.5.25.)
![]() �@�C���T�C�h�E���[�E�B���E�f�C���B�X�^�����Ȃ��j�̉��@(2014.5.25.)
�@�C���T�C�h�E���[�E�B���E�f�C���B�X�^�����Ȃ��j�̉��@(2014.5.25.)
![]() �@�l�N�X�g�E�S�[���I�^���E�Ŏ�̃T�b�J�[��\�`�[���@0��31����̒����@(2014.4.13.)
�@�l�N�X�g�E�S�[���I�^���E�Ŏ�̃T�b�J�[��\�`�[���@0��31����̒����@(2014.4.13.)
![]() �@�w�I�[���E�C�Y�E���X�g �`�Ō�̎莆�`�x�Ɓw�u���[�W���X�~���x�@(2014.4.13.)
�@�w�I�[���E�C�Y�E���X�g �`�Ō�̎莆�`�x�Ɓw�u���[�W���X�~���x�@(2014.4.13.)
![]() �@����ł���͖������@(2014.3.17.)
�@����ł���͖������@(2014.3.17.)
![]() �@�Q�O�P�S�N�I�X�J�[�i�C�g�E�E�H�b�`���O�I�@(2014.3.17.)
�@�Q�O�P�S�N�I�X�J�[�i�C�g�E�E�H�b�`���O�I�@(2014.3.17.)
![]() �@�Q�O�P�R�N�i���́j�x�X�g�P�O�I�@(2014.1.25.)
�@�Q�O�P�R�N�i���́j�x�X�g�P�O�I�@(2014.1.25.)
![]() �@�G���@�̍����@(2014.1.25.)
�@�G���@�̍����@(2014.1.25.)
![]() �@�E�H�[���t�����[�@(2013.12.22.)
�@�E�H�[���t�����[�@(2013.12.22.)
![]() �@�r�t�H�A�E�~�b�h�i�C�g�@(2013.12.22.)
�@�r�t�H�A�E�~�b�h�i�C�g�@(2013.12.22.)
![]() �@�[���E�O���r�e�B�@(2013.11.22.)
�@�[���E�O���r�e�B�@(2013.11.22.)
![]() �@�w�O�����h�E�C�����[�W�����x�Ɓw�Q�K���Y�x(2013.11.22.)
�@�w�O�����h�E�C�����[�W�����x�Ɓw�Q�K���Y�x(2013.11.22.)
![]() �@�V�g�̏��Y�l�@�o�C�I���b�g���f�C�W�[�@(2013.9.27)
�@�V�g�̏��Y�l�@�o�C�I���b�g���f�C�W�[�@(2013.9.27)
![]() �@�_�C�A�i�@(2013.9.27)
�@�_�C�A�i�@(2013.9.27)
![]() �@�E�����@�����F�r�`�l�t�q�`�h�@(2013.9.15.)
�@�E�����@�����F�r�`�l�t�q�`�h�@(2013.9.15.)
![]() �@�����ꂴ����@(2013.9.15.)
�@�����ꂴ����@(2013.9.15.)
![]() �@�z���C�g�n�E�X���A���苒�@(2013.8.22.)
�@�z���C�g�n�E�X���A���苒�@(2013.8.22.)
![]() �@�A�b�v�T�C�h�_�E���@�d�̗͂��l�@(2013.8.22.)
�@�A�b�v�T�C�h�_�E���@�d�̗͂��l�@(2013.8.22.)
![]() �@�I��̃G���y���[�@(2013.7.25.)
�@�I��̃G���y���[�@(2013.7.25.)
![]() �@���[�}�ŃA���[���@(2013.7.2.)
�@���[�}�ŃA���[���@(2013.7.2.)
![]() �@�w�J���e�b�g�I�l���̃I�y���n�E�X�x�Ɓw�Q�T�N�ڂ̌��y�l�d�t�x�@(2013.7.2.)
�@�w�J���e�b�g�I�l���̃I�y���n�E�X�x�Ɓw�Q�T�N�ڂ̌��y�l�d�t�x�@(2013.7.2.)
![]() �@�V�g�̕����O�@(2013.5.4.)
�@�V�g�̕����O�@(2013.5.4.)
![]() �@�v���C�X��r�����h��U��p�C���Y�^�h���@(2013.5.4.)
�@�v���C�X��r�����h��U��p�C���Y�^�h���@(2013.5.4.)
![]() �@�I�Y�@�͂��܂�̐킢�@(2013.3.22.)
�@�I�Y�@�͂��܂�̐킢�@(2013.3.22.)
![]() �@�W�����S�@�q���ꂴ����@(2013.3.4.)
�@�W�����S�@�q���ꂴ����@(2013.3.4.)
![]() �@�Q�O�P�R�N�I�X�J�[�i�C�g�E�E�H�b�`���O�I�@(2013.3.4.)
�@�Q�O�P�R�N�I�X�J�[�i�C�g�E�E�H�b�`���O�I�@(2013.3.4.)
![]() �@�t���C�g�@(2013.2.11.)
�@�t���C�g�@(2013.2.11.)
![]() �@�N���E�h�A�g���X�@(2013.2.11.)
�@�N���E�h�A�g���X�@(2013.2.11.)
![]() �@�Q�O�P�Q�N�i���́j�x�X�g�V�I�@(2013.2.11.)
�@�Q�O�P�Q�N�i���́j�x�X�g�V�I�@(2013.2.11.)
![]() �@���C�t�E�I�u�E�p�C�^�g���ƕY�������Q�Q�V���@(2012.12.30.)
�@���C�t�E�I�u�E�p�C�^�g���ƕY�������Q�Q�V���@(2012.12.30.)
![]() �@���E�~�[���u���@(2012.12.30.)
�@���E�~�[���u���@(2012.12.30.)
![]() �@�`���C�X�I�@(2012.11.24.)
�@�`���C�X�I�@(2012.11.24.)
![]() �@�̂ڂ��̏��@(2012.10.26.)
�@�̂ڂ��̏��@(2012.10.26.)
![]() �@�G�N�X�y���_�u���Y�Q�@(2012.10.26.)
�@�G�N�X�y���_�u���Y�Q�@(2012.10.26.)
![]() �@�A���S�@(2012.10.23.)
�@�A���S�@(2012.10.23.)
![]() �@�\�n�̒n�������@(2012.9.17.)
�@�\�n�̒n�������@(2012.9.17.)
![]() �@�v�H���@(2012.9.17.)
�@�v�H���@(2012.9.17.)
![]() �@�g�[�^���E���R�[���@(2012.8.21.)
�@�g�[�^���E���R�[���@(2012.8.21.)
![]() �@�v�����e�E�X�@(2012.8.21.)
�@�v�����e�E�X�@(2012.8.21.)
![]() �@�X�m�[�z���C�g�@(2012.7.15.)
�@�X�m�[�z���C�g�@(2012.7.15.)
![]() �@�A�x���W���[�Y�@(2012.7.15.)
�@�A�x���W���[�Y�@(2012.7.15.)
![]() �@�����E�f�C�@�Q�R�N�̃��u�X�g�[���[�@(2012.5.30.)
�@�����E�f�C�@�Q�R�N�̃��u�X�g�[���[�@(2012.5.30.)
![]() �@���i�C�e�b�h�@�~�����w���̔ߌ��@(2012.5.30.)
�@���i�C�e�b�h�@�~�����w���̔ߌ��@(2012.5.30.)
![]() �@�W�����E�J�[�^�[�@(2012.4.18.)
�@�W�����E�J�[�^�[�@(2012.4.18.)
![]() �@�a�����������v���������^�u���b�N���z���C�g�@(2012.4.18.)
�@�a�����������v���������^�u���b�N���z���C�g�@(2012.4.18.)
![]() �@�A�[�e�B�X�g�@(2012.3.7.)
�@�A�[�e�B�X�g�@(2012.3.7.)
![]() �@�Q�O�P�Q�N�I�X�J�[�i�C�g�E�E�H�b�`���O�I �@(2012.3.6.)
�@�Q�O�P�Q�N�I�X�J�[�i�C�g�E�E�H�b�`���O�I �@(2012.3.6.)
![]() �@�q���[�S�̕s�v�c�Ȕ����@(2012.1.28)
�@�q���[�S�̕s�v�c�Ȕ����@(2012.1.28)
![]() �@�Q�O�P�P�N�i���́j�x�X�g�T�I�i2012.1.28.)
�@�Q�O�P�P�N�i���́j�x�X�g�T�I�i2012.1.28.)
![]() �@��a���m�̉�����R�{�@(2011.12.28.)
�@��a���m�̉�����R�{�@(2011.12.28.)
![]() �@���~�b�g���X�@(2011.9.24.)
�@���~�b�g���X�@(2011.9.24.)
![]() �@�Č��w���l�܂ł̋����i�f�B�X�^���X�j�x�@(2011.9.21.)
�@�Č��w���l�܂ł̋����i�f�B�X�^���X�j�x�@(2011.9.21.)
![]() �@�X���[�f�C�Y�@(2011.9.18.)
�@�X���[�f�C�Y�@(2011.9.18.)
![]() �@���̘f���F�n���L�@(2011.9.18.)
�@���̘f���F�n���L�@(2011.9.18.)
![]() �@�g�����X�t�H�[�}�[�@�_�[�N�T�C�h�E���[���@(2011.8.29)
�@�g�����X�t�H�[�}�[�@�_�[�N�T�C�h�E���[���@(2011.8.29)
![]() �@�u���b�N�E�X�����@(2011.5.9.)
�@�u���b�N�E�X�����@(2011.5.9.)
![]() �@�g�D���[�E�O���b�g�@�i2011.3.28.)
�@�g�D���[�E�O���b�g�@�i2011.3.28.)
![]() �@�킽���𗣂��Ȃ����@(2011.3.28.)
�@�킽���𗣂��Ȃ����@(2011.3.28.)
![]() �@�c�[���X�g�@(2011.3.13.)
�@�c�[���X�g�@(2011.3.13.)
![]() �@���̏�̃��v���c�F���@(2011.3.13.)
�@���̏�̃��v���c�F���@(2011.3.13.)
![]() �@�����i�E�F�C�Y�@(2011.3.13.)
�@�����i�E�F�C�Y�@(2011.3.13.)
![]() �@�Q�O�P�P�N�I�X�J�[�i�C�g�E�E�H�b�`���O�I�@(2011.3.6.)
�@�Q�O�P�P�N�I�X�J�[�i�C�g�E�E�H�b�`���O�I�@(2011.3.6.)
![]() �@�p�����̃X�s�[�`�@(2011.2.13.)
�@�p�����̃X�s�[�`�@(2011.2.13.)
![]() �@�Q�O�P�O�N�i���́j�x�X�g�P�O�I�@(2011.2.7.)
�@�Q�O�P�O�N�i���́j�x�X�g�P�O�I�@(2011.2.7.)
![]() �@�u���[���E�A�p�[�g�@(2011.2.5.)
�@�u���[���E�A�p�[�g�@(2011.2.5.)
![]() �@�������@(2011.1.20.)
�@�������@(2011.1.20.)
![]() �@�\�[�V�����E�l�b�g���[�N�@(2011.1.20.)
�@�\�[�V�����E�l�b�g���[�N�@(2011.1.20.)
![]() �@�u���[�r�[�E�U�E�u�[�r�[�v�ɖ߂�
�@�u���[�r�[�E�U�E�u�[�r�[�v�ɖ߂�
![]() �@�g�b�v�y�[�W�ɖ߂�
�@�g�b�v�y�[�W�ɖ߂�
| �X�^�[�E�E�H�[�Y�^�t�H�[�X�̊o�� �@�@STAR WARS:THE FORCE AWAKENS �i�Q�O�P�T�N�A�āA�����F�ъ����j  �@����͂�A�悩�����A�Ђƈ��S�B���͂r�v�t���[�N�ł͂Ȃ�����ǁA���̓`���I�ȃV���[�Y�̐V�삪���܂�ɃV���{���f�L��������A�z�����̃f�B�Y�j�[�݂̂Ȃ炸�A�f��E�S�̂ɂ悩��ʔg�y���ʂ��y�т����ł�����ˁB���̃G�s�\�[�h�V���y��_�ȏ�̂��̂Ɏd�オ�������Ƃ��A�܂��͂��Ƃق������B �@����ς�O���̒m�b��V�������͓����ׂ�����ˁB���U��͉�����W���[�W�E���[�J�X�P�l�̍\�z�����ɂ������̂���������A���ɃG�s�\�[�h�P�`�R�́A�܂����̉��Ƃ������A�����Ԃ�Ƌߎ���I�ɂȂ��Ă����B�r�v���ɖ������f��w�t�@���{�[�C�Y�x�ł��A�Ō�ɃG�s�\�[�h�P���ς��o��l���������A���������ʕ��G�ȕ\������Ă������B �@���̓_�A�{��̓��[�J�X���琢�E�ς�����������āA��O�҂��q�ϓI���v���t�F�b�V���i���ɍ�肠�������́B�l�I�Ȏv������ɍS�D����Ă��Ȃ���ł��ˁB���Ƀf�B�Y�j�[�͓O��I�Ƀu���C���X�g�[�~���O���Ȃ���X�g�[���[����i�߂邱�ƂŒm���Ă��邩��A�ē�r�{�Ƃ��ăN���W�b�g���ꂽ�l�X�͂������A�����̗D�G�ȃX�^�b�t�̏W���m���������܂ꂽ���̂Ƒz�������B�ɋ}�������Ȃ����ǂ݂Ȃ������A�N�V�����V�[���ɁA�P�R�U���ԁA�ދ�����Ƃ��낪�Ȃ������B �@�p�i����ŐH���Ȃ��ǓƂȏ������C�i�f�C�W�[�E���h���[�j�́A���܂��ܑ����荇�������{�b�g�u�a�a�W�v�����l����~���A�X�g�[���g���[�p�[�̒E�����t�B���i�W�����E�{�C�G�K�j�Ƌ��ɃI���{���D�ʼnF����Ԃ֓����B��x�͓G�ɕ߂܂������Ǝv������A���ꂽ�͓̂`���I�ȉp�Y�ŁE�E�E�B �@�{����т��c���͉B�ق������[�N�E�X�J�C�E�H�[�J�[�T���B����Ȃ̂ɂƌ����ׂ����A�����炱���ƌ����ׂ����A���[�N�̓o��������ς�����ς�B���V���[�Y�̉p�Y�n���E�\���i�n���\���E�t�H�[�h�j�͏��Ղ��犈���A���C�A�i�L�����[�E�t�B�b�V���[�j�͒��ՁA���������ēo�ꂳ�����̂ɁA���[�N�����͏o�Ă��Ȃ���ˁB���������ă}�[�N�E�n�~�������~�낳�ꂿ������́H�ƐS�z�ɂȂ����قǂ��B �@�������A����͞X�J�ōŌ�̍Ō�Ƀn�~�����o��B�Z���t�͈ꌾ���Ȃ��������A����Ȃ�Ɍ�����p�Ō���Ă��ꂽ�̂ŁA���V���[�Y�̃t�@�����z�b�Ƌ����Ȃʼn��낵���Ƃ����Ƃ��납�i�t�@���̒��ɂ��ŋ߂̔ނ̗l�q��m��l�͏��Ȃ������͂��ł�����ˁj�B �@�����ł��A�����Č����ɂ��G�s�\�[�h�U����R�O�N�B�A���\�j�[�E�_�j�G���Y�A�P�j�[�E�x�C�J�[�A�s�[�^�[�E���C�q���[����܂ގ�v�ȃL���X�g���A�S�����݂̂܂܂œ�����������������Ƃ����̂́A�قƂ�NJ�Ղɋ߂����Ƃ��B �@�Ƃ͂����ނ�́A���͂����ł͂Ȃ��B�V�V���[�Y�������ς�̂̓f�C�W�[�E���h���[�ƃW�����E�{�C�G�K���B���������Ȗʗ����ƃC�M���X�a��̃A���g�����͓I�ȃ��h���[�͋P������B��v�Ȗɉp���l�o�D���N�p����V���[�Y�̓`���́A�{��ł��p������Ă����B �@����Ŋ���̂Ȃ��N���[���������X�g�[���g���[�p�[�́A����ł͐��g�̐l�ԂɁB�����ɓ����邱�Ƃ���l���Ă����t�B�����A���C���������̂����Ĉ�]�A��n�ɔ�т��ނȂA������ԉ߂��邮�炢�̒�ԂȂ��ǁA����ς苹���M���Ȃ�킯�ŁB �@���Ȃ݂ɃG�C�u�����X�̓e���r�E�̏o�g�����A�ߔN�̕č��̃e���r�h���}�ł́u�J���[�u���C���h�I�v�Ȉِl��J�b�v���i�����I�ȏ�Q��F���E����������ł������̂ł͂Ȃ��A�l��Ό��̂Ȃ����z�I�Ȑ��E�ς̒��Ō��ہE��������ِl��J�b�v���j�������Ă���Ƃ����B�������e���r�h���}�Ȃ�Ƃ������A���̃��K�q�b�g�E�V���[�Y�ňِl��J�b�v���������̂����e����قǁA�č��̑�O�̓��x�����Ȃ̂��H�@����Ƃ����_�̕���������邽�߂ɁA�Q�l�͗F�l�W�ŏI��邱�ƂɂȂ�̂��H�@���Ȃ��Ƃ��{��ł́A���C�̓t�B���̂��ł��ɂ����L�X���Ȃ������B�č��̎Љ���_�̊ϓ_������A�Q�l�̍���̊W�ɒ��ڂ������B �@�����P�p�����ꂽ�̂��u���Ƒ��q�̕���v�Ƃ����`�����B���V���[�Y�̃_�[�X�E�x�C�_�[�ƃ��[�N�ɑւ���āA�{��ł̓n���E�\���̑��q���Í��ʂɗ������i�ނ́g���l�l�[���h�̓J�C���E���������A�{���̓x���炵���B������x���E�P�m�[�r���������̂��H�j �@���肽���͋���̏��l�^�ւ̖ڔz����Y��Ȃ��B�t�@������x�͕����Ȃ���C���ς܂Ȃ� "I've got a bad feeling about this."�͑����i�K�Ńn���E�\���Ɍ��킹�����A"May the Force be with you"�͏I�ՂɂȂ��ă��C�A�Ɍ��킹���B�u�S�~���Ӌ@�v�ɂ������ƐG��āA�t�@�����N�X���Ƃ����Ă�����B �@���C�A���u�t�H�[�X�Ƌ��ɂ���v������������̓��C�ŁA���̎q�A�ǂ����t�H�[�X�̎�����炵���B���O�����C�A��J�C���E�����Ɏ��Ă��āA���ʂɍl������ނ�ƌ����W�ɂ���͂����B�������Řb���i�ނɘA��āA�����̓��̒��ł́u���C�͒N�H�v�u���C�͒N�H�v�u���C�͒N�H�v�ƁA�ǂ�ǂ��ǂ�ǂ��^�₪�c�����Ă������B����͂������A�G�s�\�[�h�W�̂��y���݂Ƃ������Ƃ̂悤�ł���B �i�Q�O�P�T�D�P�Q�D�Q�P�D�L�j �G�[���I�@�@LA FAMILLE BELIER �i�Q�O�P�S�N�A���A�����F�Óc�R�I�q�j  �@����A�o�Ŏ掟��Ђ̓��̂��Q�O�P�T�N�̔N�ԃx�X�g�Z���[�\���Ă����i�W�v���Ԃ͂Q�O�P�S�D�P�P�D�Q�V�`�Q�O�P�T�D�P�P�D�Q�U�j�B�ǂ����Ȃ痈���܂ő҂��āA�P���P������P�Q���R�P���܂ł̐��������\���Ă��������̂ɂƎv���̂����A����͂܂��A�ǂ��ł������B �@�����т����炱�����̂́A�P�ʁu�Ήԁv�Q�ʁu�t�����X�l�͂P�O���������������Ȃ��v�Ɏ����ŁA�R�ʂɁu�Ƒ��Ƃ����a�v�������Ă������ƁB���͖��ǂ����ǁA�V���L���Ȃǂ��������A���������W������e�̖{�ł���ˁB�Ƒ��W�ɂ��Ďv���Y�݁A�����ɋ~�������߂悤�Ƃ���l�X�����̒��ɂ͂���Ȃɑ吨������H�@���������{���R�Ԗڂɂ�������Ă��܂����̍����āA���������E�E�E�B �w�G�[���I�x�����j�[�N�Ȃ̂́A�g��Q�ɕ������Ɍ��C�Ɋ撣���Ă��鏭���h�ł͂Ȃ��A�g��Q�����Ƒ��ƎЉ�Ƃ̐ړ_�ɂȂ��Ă��錒��ȏ����h����l���ɐ��������Ƃ��낤�B��Q�����������H����������ꂾ���Ŕ��k�ɂȂ邪�A��Q�����Ƒ����c���ĉH�����Ă���������`���̂͂��Ȃ�g���b�L�[���B �@����ł��{��̍���́A���M���O��D��������y���ȃ^�b�`���ѓO���邱�ƂŁA���̓������܂��N���A���Ă���Ǝv���B���y���t�̍��܂�{�[�C�t�����h�̋��܂ւ̐肱�݂��Ђǂ����r���[�Ȃ̂Łu����v�̔��e�ɂ͓���Â炢���A���������e���r�ɖڂ��Ԃ�Ώ\���ɐS���܂銴����ɂȂ��Ă���B �@�W���҂̉ƒ낪�\�\�H��̂Ԃ��荇������Z�b�N�X���̐����C�ɂ��Ȃ������߂Ɂ\�\����҂ɂƂ��Ă͂Ђǂ����邳���Ƃ����͖̂ʔ������_�B���ۂ̂Ƃ���͂ǂ��Ȃ̂����������Ȃ����A�ςɐ����͂�����̂ŏ��Ă��܂����B �@���_�Ƃ̖��|�[���E�x���G�͂Ђ��Ȃ��Ƃ�����������R�[���X���ʼn̂̍˔\�����o����A�ږ�̋��t�Ƀp���̉��y�w�Z����悤���߂���B�Ƃ��낪�x���G�Ƃ͗��e����������s���R�B�����������o�Ă����ΉƑ������邾�낤���A���������Ƒ��ɉ̂����Ă��̏�������[�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B�Y���ɁA�|�[���͉̂�������߂邱�Ƃɂ���̂����E�E�E�B �@�I�ՁA�|�[�����Ƒ��̑O�ʼn̂��V�[�����Q��B�P��ڂ͍��Z�ł̔��\��ŁA�G���b�N�E�����e�B�S�ē͓r�����特���������A�ϋq�����̕s���R�ȉƑ��̗���ɒu�����B���͂̐l�X�����т��A�܂��������Ă���̂ɁA���������ɂ͂��ꂪ�`���Ȃ��˘f���Ƃ��ǂ������B�������͖����̂Ă������ƁA���̖��Ɋ��Y���Ȃ��Ƒ��̗����ɋ������A�������Ƃ����v���ɒ��ށB �@�Q��ڂ͓y�d��Ŏ����ӂ������y�w�Z�̓��w�������B�������Ƒ��ɂ͈ˑR�Ƃ��Ė��̉̐��͕������Ȃ����A�|�[���͂ӂƎv�������A��b�ł��̉̎���ʖ͂��߂�B�u�l�͗�����B�������Ȃ��v�ƁB �@�����Ă݂�u���͂���̂ɔ�ׂ��Ɂv�����������A���ɔ�߂����ӂ��u�l�炪�������������t�v�Łu�����납�炱����ցv�`�����킯�ł��ˁB���̐Ȃ̗��ׂŁA���̎q�����������苃���Ă����̂��ނׂȂ邩�Ȃ��i�c�O�Ȃ���ǂ�������̘A��ł͂Ȃ��������j�B �@���̉f��̌���LA FAMILLE BELIER�͒P�Ɂu�x���G��Ɓv�Ƃ����Ӗ������A���肽�������{�̃|�b�v�o���h�ɂ��Ă̒m���������Ă����Ƃ��v���Ȃ��̂����A�|�[�������������������̐��b�����Ă������ƂƂ����܂��āA��d�ɂ��������̂�����Ƃ��̃q�b�g��u�x�d�k�k�v��A�z�������i�������B���{�̔z����Ђ��w�G�[���I�x�Ƃ����M��������̂����ɔ[���ł��ˁB �i�Q�O�P�T�D�P�Q�D�S�D�L�j �~�P�����W�F���E�v���W�F�N�g�@�@THE MONUMENTS MEN �i�Q�O�P�R�N�A�āA�����F���Y���ށj   �@�������j�������c�E�����̂��Ƃ����߂Ēm�����̂́A�t�F�����[���̈�i�u�G��|�p�v�Ɋւ���h�L�������^���[�̎����|������Ă��鎞�������B���̊G�͈�x�T�C����������ĕʂ̉�Ƃ̏�����������ȂǁA���Ƃ��Ɛ���ȉ^�������ǂ��Ă͂����̂����A�Q�O���I�ɓ����ăi�`�X�̎�ɗ������B����𑼂̂P���_�ɂ��y�Ԍ|�p�i�Ƌ��ɒD�҂����̂��A���R�̕ʓ����u���j�������c�E�����v�������Ƃ����킯�B �@�������j�������c�E�����̂��Ƃ����߂Ēm�����̂́A�t�F�����[���̈�i�u�G��|�p�v�Ɋւ���h�L�������^���[�̎����|������Ă��鎞�������B���̊G�͈�x�T�C����������ĕʂ̉�Ƃ̏�����������ȂǁA���Ƃ��Ɛ���ȉ^�������ǂ��Ă͂����̂����A�Q�O���I�ɓ����ăi�`�X�̎�ɗ������B����𑼂̂P���_�ɂ��y�Ԍ|�p�i�Ƌ��ɒD�҂����̂��A���R�̕ʓ����u���j�������c�E�����v�������Ƃ����킯�B�@�����A�m���ɋ����[���j���ł͂���̂����A�����|��̎Q�l�����Ƃ��Ďߓǂ݂������o�[�g�E�l�E�G�h�[�����w�i�`���D���p�i���~���@���ꕔ���u���j�������c�E�����v�̐푈�x�i�����Ёj�́A�������đދ��������B���̓_�A�n���E�b�h�͐��E�̂�����ϋq���y���߂�悤�i���邢�͐��E�̂�����ϋq�����������悤�j�A�����Ƃ���͂����܂݁A�ދ��ȂƂ���͋r�F���ď��ɉf�扻���Ă����B���ʁA���́w�~�P�����W�F���E�v���W�F�N�g�x�́A�l�ނ̈�Y�i�܂��́A�������G��⒤���j����邽�߂ɖ������Ő��ɏ�肱��ł������j�����̐S�ӋC��������`���A�T�X�y���X�ƃ��[���A�����Ղ�̉���ɂȂ����B �u���ꕔ���v�Ƃ͌������̂́A���j�������c�E�����͋����ȕ��m�ł͂Ȃ��A�Ƃ��ɒ��N���}�������p�⌚�z�̐��Ƃ������B�W���[�W�E�N���[�j�[�ƃ}�b�g�E�f�C�����͂Ƃ��������A�r���E�}�[���C�A�W�����E�O�b�h�}���A�{�u�E�o���o���Ƃ�������Ԃ�i�Ƃ������A���̔����Ȃ������Ɠ˂��o�������j������A�퓬�\�͂�����̕����łȂ����Ƃ͂����킩��B �@����Ȕނ炪���l�ƃt�F�����[���̌����������Ȃ������̖{���Ɏז����������ꂽ��A�G�R�ɖ���_��ꂽ�肵�Ȃ���A�i�`�X���������������p�i�̉B���ꏊ����S���ĒT�肾���Ă����B�����ɂ͗F��ƐM�O������A���܂ƍċN������A������ƃJ�^���V�X������B���łɌ����Ȃ璆�N�̗]�T�ƈӒn������B�h���}�̗v�f�Ƃ��Č����Ă���̂́u����v���炢�����A����͎j�������Ƃɂ��Ă���ȏ�A����ɑ����킯�ɂ͂����Ȃ����낤�B �@�����ɂ́u�G��|�p�v�͂������A�w���g�̍Ւd��A�~�P�����W�F���̃s�G�^�ȂǁA���ۂɗ��D���ꂽ���ƂŒm������p�i���������o�ꂷ��B����炪�l�ԃh���}�̏�����Ƃ��Ă����ʓI�Ɏg���Ă���̂����ꂵ���B �@�ނ��ꂵ�����N�j�����̕���ɗB��Ԃ�Y���Ă����̂��A�P�C�g�E�u�����V�F�b�g��������t�����X�l���p�و����B������������̕�����|�p��������S�͐l��{�B���ꂾ���ɓ����͕ČR�̈Ӑ}���^���̂����A�}�b�g�E�f�C�����̐����ȑԓx�Ɏ���ɐS���J���Ă����B���}���X�����~�߂����Ō�̃f�B�i�[�́A���������œ˂�����Ȃ���l�̕��ʂƈꖕ�̎₵����`���ďG��B�~���������̖��ɂ̓t�����X�l���D���N�p���Ăق����������A�~������Ȃ���u�����V�F�b�g�̍d���ȉ��Z�͑f���炵�������B �@�Ƃ���ł��̉f��A�Q�O�P�R�N�̐���Ȃ�ˁB������Q�N�������Ă�����{���J�����Ȃ�āA�ŋ߂ł͒������^�C�����O���B��������i�ɂ͂e�n�w�ƃR�����r�A�̃��S���ǁ[��Ɠ����Ă���̂ɁA�z����Ђ͂e�n�w�ł��\�j�[�E�s�N�`���[�Y�ł��Ȃ��A�����ȃv���V�f�B�I�B �@��ނ��n����������̔z����Ђ͎���o�����A���J���̂��Ȃ��Ȃ����܂�Ȃ������̂��낤���B�����ǃW���[�W�E�N���[�j�[���ēE�r�{���肪�����Ƃ����b�萫�����������낤���A�L���X�g���w�I�[�V�����Y�x�V���[�Y����u���s�������������݂����Ȃ��̂Ȃ̂ɁB �@�������v���V�f�B�I�͌��I�ȍ�i����������Љ�Ă���Ă����ЂŁA�l�I�ɉ����܂ނƂ���͂Ȃ��B���������ꂾ���L�����N�^�[�悵�A�X�g�[���[�悵�̉f��Ȃ̂�����A��肪�����Ղ��`��������āA�����̌���ɔz�����Ăق��������B��������߂�킹�Ă��܂����{�̗m��s��̌�����āA������ƐS���Ȃ��Ƃ��낪����B �@�Â��B���ɉB����Ă����~�P�����W�F���̃s�G�^���A���j�������c�E�����̎�Ŗ��邢���̒��ɉ^�яo����Ă����V�[���́A��]�ւ̗\���Ƒu�����ɖ����Ă����B�������������ăi�`�X����D�҂��ꂽ�|�p�i���A���ׂĖ{���̎�����ɖ߂��ꂽ�킯�ł͂Ȃ��B  �@���̃N�����g�̌���u�A�f�[���E�u���b�z���o�E�A�[�̏ё��v���A�č��ɓ��ꂽ���_���l�Ƒ��ɂ͕Ԋ҂��ꂸ�A�E�B�[���̔��p�قɎ�������邱�ƂɂȂ�B�Ԃ��Ȃ����J�����w�����̃A�f�[���@����̋A�ҁx�́A��������߂����Ƃ����V���̕s���̐킢��`������i�����A����͕ʂ̘b�B �@���̃N�����g�̌���u�A�f�[���E�u���b�z���o�E�A�[�̏ё��v���A�č��ɓ��ꂽ���_���l�Ƒ��ɂ͕Ԋ҂��ꂸ�A�E�B�[���̔��p�قɎ�������邱�ƂɂȂ�B�Ԃ��Ȃ����J�����w�����̃A�f�[���@����̋A�ҁx�́A��������߂����Ƃ����V���̕s���̐킢��`������i�����A����͕ʂ̘b�B�i�Q�O�P�T�D�P�P�D�Q�R�D�L�j �p���R��̈�Y�����l�@�@MY OLD LADY �i�Q�O�P�S�N�A�ā��p�����A�����F�`�I�L�^���j �@�t�����X�ɂ́u���B�A�W�F�v�ƌĂ��Ɠ��̕s���Y�����̌`�Ԃ����邻���ŁA������g���Δ����͎��ʂ܂ł��̕����ɏZ�ݑ����A�����肩�疈�����z�̎x�����i�����g�j����邱�Ƃ��ł���B�t�ɔ�����̑����猾���Ȃ�A����肪�����ɂ���Ύx�����z��}�����A�����������Ƃ��ꂾ�����z�̋���Ȃ���Ȃ�Ȃ��d�g�݂��B����Ӗ��A����I�ɂ����M�����u���ł��ˁB �@�ɒ[�ȗ�ł́A�X�O�������������炱�̃r�A�W�F�ʼnƂ����S�V�̌��ؐl���A�R�O�N�������g���������������A��������Ɏ���ł��܂����Ƃ������b������i�����͂��̂Q�N��ɃM�l�X�̒����L�^��ł����ĂĎ��j�B�Ɖ��̎��������������Q�O�`�R�O�N�ƍl�����Ă�����{�ł́A������ƍl�����Ȃ��V�X�e���ł͂���B �@�o�c�R�A�q�Ȃ��A���Y�Ȃ��̃_���_���l���𑗂�}�e�B�A�X�i�P�r���E�N���C���j�́A�a�����������e����p���̃A�p���g�}���𑊑����邱�ƂɂȂ�B�����A�p���g�}���蕥���Đl�������Z�b�g�Ƃ���ɕč��ł̕�炵�����������ēn�����邪�A�����ɂ̓��B�A�W�F�̔����ł���V�w�l�}�e�B���h�i�}�M�[�E�X�~�X�j���Z��ł��āE�E�E�B �@�Ƃ������������炵�āA���łɐl���쌀�Ƃ��Ă̊��Ғl�\�������A���ꂪ�[�݂𑝂��̂́A���̃A�p���g�}�����}�e�B�A�X�̕��e�ƃ}�e�B���h�̈��̑��������Ƃ킩���Ă��炾�B�Q�l�͂��ꂼ��ɉƒ�������Ȃ���A�݂����ň��̐l�Ǝv����߁A���炭�s�ϊW�𑱂��Ă����B �@�}�e�B�A�X�����e�Ƒa���������̂����̂��߂ŁA���̕�e�Ɏ��E���ꂽ�߂����ߋ����B�}�e�B���_�Ɠ������閺�̃N���G�i�N���X�e�B���E�X�R�b�g�E�g�[�}�X�j���A�c���������e�̕s�ςɏ����Ă������A���ł͎������Ȏq����j���ƊW�����g�ɁE�E�E�B �@����̓C�X���G���E�z���r�b�c�ē����珑�������䌀�B���ꂾ���Ƀ}�e�B�A�X�ƃ}�e�B���h�A�}�e�B�A�X�ƃN���G�����킷��b�̖��x���ɂ߂č����B �u�v�͗T�������痣�����Ȃ������B���Ȃ��̂��ꂳ����[���̏ゾ�����̂ł��傤�v�ƈ��т��Ƃ���̂Ȃ��}�e�B���h�ɁA�u�[���Ȃ��Ă��Ȃ������v�Ɣ�������}�e�B�A�X�B�����P�Ȃ���⍦���̉��V�ɂ����A��������l�̉�b���ɂ��Ă݂���z���r�b�c�̎�r�͋ɏゾ�B�ǂ�������ꂼ��ɐH���Ȃ��L�����Ȃ̂����i���Ȃ݂ɖ��O�����Ă���̂͋��R�ł͂Ȃ��j�A�s�v�c�Ɨ��҂ɍD���Ɛe�ߊ����N���B���D�̐�����킴�ł��ˁB �@�_���j�̍Đ����T���߂ɗ\��������G���f�B���O���D�܂����B�}�e�B�A�X���������Ă������e�́A�ǂ����P�Q�O�O�����[���̃A�p���g�}�������ł͂Ȃ��A�����S�̒ɂ݂𗝉���������p�[�g�i�[���A���������Ĉ₵�Ă��ꂽ�悤���B �i�Q�O�P�T�D�P�O�D�Q�U�D�L�j �}�C�E�C���^�[���@�@THE INTERN �i�Q�O�P�T�N�A�āA�����F�ݓc�b�q�j  �@�i���V�[�E�}�C���[�Y�ē����ӂ̏����R���f�B�B�����K�v���Ȃ��̂ɘV��̂ނȂ�������C���^�[���ɉ��債��������V�O�j�̃x���i���o�[�g�E�f�E�j�[���j�ƁA�Ɩ���̕K�v����ł͂Ȃ����̂o�q�헪�̂��߂ɍ���҃C���^�[�����ق����h�s��ƂƂ̃~�X�}�b�`�Ԃ肪�킹��B�f�E�j�[������҂����������A��Ă���ƂɔE�т��ރV�[���Ȃ́A�ނ��ƍ߉f��ɏo�Ă����Ⴉ�肵���̃p���f�B�ł��ˁB �@�������͏����f�悾����A�N���W�b�g���ł̓f�E�j�[�����M���ł��A�{���̎�l���̓A���E�n�T�E�F�C���B�Ⴍ���ăt�@�b�V�����T�C�g��n�݂��A���������Ɏv����W���[���X���A�o�������x���`���[�L���s�^������ӂɐ��܂Ȃ��v����˂��������A��Ǝ�w�̕v�Ǝq���Ƃ̊Ԃɂ����ܕ���������A��e���������Ďd���Ȃ���ƁA���ʂ̐l�ƔY�݂͓����B�ϋq�Ȃ̂n�k���A�ːF�����̃I�X�J�[���D�ɂ����Ƌ����ł���H�v���{����Ă���B �@����ȃW���[���X���A�����͂܂��������Ăɂ��Ă��Ȃ������x���ɁA����ɐM���ƍD�����Ă����B���̂�����̋ؗ��Ă̎茘���́A�����ŋr�{�������}�C���[�Y�Ȃ�ł͂��B �@���̌����ƌ�����̂��A�o����̃z�e���ŃW���[���X���x���ɕv�̕s�ς�Q���V�[�����낤�B�u�����C�Â��Ă��邱�Ƃ�v�͂܂��m��Ȃ��B���̂܂ܖ₢�߂��ɂ����A���̎������ɖ߂�邩������Ȃ��v�Ɛԗ��X�Ȑ^���f�I����W���[���X�B����ɑ��Č��悾���̍m���Ԃ��Ȃ��x���B�g�f�L�鏗�h�̎コ���̂�������n�T�E�F�C�ƁA�ɉ�����f�E�j�[�����ǂ�������܂��A�ƂĂ���ۓI�ȃV�[���ɂȂ����B �@�n���E�b�h�f��͌×��A�u�j�ɂƂ��ēs���̂������v�����`���Ă������A�t�Ɂu���ɂƂ��ēs���̂����j�v�����o�ꂳ����̂��}�C���[�Y��i�̓������B�w�����K����x�R��A�w�z���f�C�x�R��B���R�A�{��ł��W���[���X�̕v�͍Ō�Ɏ���߂����������A�����𐿂��i���łɌ����A�x�����S�Ȃ��v�������鈤�ȉƂŁA�W���[���X�̎�݂ɂ�����͂��Ȃ��B�W���[���X�����v��x���̕����o�c�҂Ɍ����Ă��܂����Ȃ�ăA���`�E�t�F�~�j�X�e�B�b�N�ȑ�c�~�ɂ��Ȃ��Ă��Ȃ��j�B �@�����Ń��^�V�I�ɋ����[���̂́A�������炢�̊ϋq�����́u�v�̎Ӎ߂Ō�����v�Ƃ��������ɔ[������̂��A���B�ӊO�ɑ������ȋC�����Ȃ����Ȃ����A�����������Ƃ��o�������v�w���{���Ɂu���̎������v�ɖ߂����̂������H�@�x������炸���Č�����Ƃ���A��������������ƂȂ̂ł́B �@�v�w�W�Ƃ����̂́A�s�ςɌ��炸�������Ƃ��������Ƃ��Ђ�����߂ėl�X�Ȃł����Ƃ����邽�тɕϗe���A�����āu���̎������v�ɖ߂邱�Ƃ͂Ȃ��̂ł͂���܂����B���Ƃ��Y�ꂽ�i���邢�͋������j�ӂ�͂ł��Ă��A�N���Ă��܂������Ƃ͈ꐶ�����邱�Ƃ͂Ȃ��B�����������܂܁A�v�w�́u���̎������v�Ƃ����W��s�f�Ɍ��ђ����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ȃ��B �@����̌o���Ɋ�Â��Ȃ��A�Ɛg�j�̂܂��������ӔC�Ȋ��z�ł͂���܂����B �i�Q�O�P�T�D�P�O�D�Q�U�D�L�j �A�f���C���A100�N�ڂ̗��@�@THE AGE OF ADALINE �i�Q�O�P�T�N�A�āA�����F�Γc�q�j  �u�����V�l�v�u�V��j�Y�v�u�V�l�z�[���ł̋s�ҁv�u��엣�E�v�Ƃ������b��ɐG��邽�сA�ǂ����Đl�Ԃ͂���ȂɎ��˂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����낤�Ǝv�킸�ɂ����Ȃ��B�s���Ǐo��O�̒i�K�ŁA���ʂɃP�K��a�C�Ŏ��ʂ��Ƃ��ł����Ȃ�A�{�l���Ƒ����ǂꂾ���K���ł��邱�Ƃ��B���܂薳�łɈ�w�B�����Ă��܂��̂��l�����̂ł��ˁB �@�P�X�O�W�N�ɒa�������q���C���̃A�f���C���i�u���C�N�E���C�u���[�j�́A�Q�X�̎��ɂ��鎖�̂ɑ����A���̓I�ȘV�����~�܂��Ă��܂��B�������łP�O�V���}�����Q�O�P�T�N���݂���\��̎Ⴓ�Ƒ̌n��ۂ����܂܁B�����Ƃ��A�������Ƃ���͂Ȃ��킯�ŁA�l�\��̍��ɐl�̎����̍ޗ��ɂ��ꂩ���A�ȗ����S�����𑱂��Ă���B���͂ɋ^���Ȃ��悤���N�����ƂɏZ�������O���ς��Ȃ���A���l���F�B����炸�ɉ��\�N���̍Ό����ǓƂɉ߂����Ă����킯���B �@�X�g�[���[�͋r�{�Ƃi�E�~���Y�E�O�b�h���[�̃I���W�i���B�ޏ��̏Ǐ���Ĉ�w�I�ɐ����ł���̂��Ȃ�Ė��Ȃ��Ƃ͕��������Ȃ����B�������łP�O�O�]�N�ɓn�鐼�m�̃��[�h�ƃt�@�b�V�������A�������g�S�V�b�v�K�[���h������ւ������ւ���I���Ă����i���l�͑O���̂���U�O�N��t�@�b�V�������D���j�B �@����Җ�肪�Ȃ�����ҁg���h�ɂȂ�̂��ƌ����A���������̂Ɠ��]�������邩��ɑ��Ȃ�Ȃ��B�Ƃ��낪�A�f���C���̃P�[�X�ł́A���̂��V�����邱�Ƃ͂Ȃ�����ŁA�m���ƌo���͂ǂ�ǂ�ςݑ�����A�N��Ƌ��Ɍ����Ȃ��Ă����B�����뎞�Ԃ͂����Ղ肠�邩��A���Ƃ��Ή��J���ꂾ���ĕ��ł����Ⴄ���A���@�͂͂ǂ�ǂ�s���Ȃ��Ă����킯���B �@���S�����Ȃ�������낤���āH�@���S�z�Ȃ��B���̐́A�R�s�[�@����������̃[���b�N�X�Ђɑ���𓊎������������ŁA�ߐH�Z�ɂ͂܂������s���R���Ȃ��i���܂��ݒ肾�j�B�V��j�Y���F�m�ǂ��_�o�ɂ������B�A�f���C���ɂƂ��Ă̍���Җ��Ƃ́A����Ȃ��ƂɘV��������������l���i�G�����E�o�[�X�e�B���j�Ɋւ�邱�ƂȂ̂��B �@����Ȕޏ����M��ɂ���Ƃ���ɗ�������i������̃~�L�[���E�n�[�X�}�������܂����Ⴆ�Ȃ��̂��c�O�j�B��ˎ����̌���u�̒��v��m����{�l�Ȃ�A�A�f���C�����܂�������l�̘V���Ǝ���������Ȃ��牽���N������������̂��Ǝv���Ƃ���B�������r�{�͂����ł��X�g�[���[�ɍI�݂ȂЂ˂�������A��������܂�ׂ��Ƃ���Ɏ��ʂ�����B �@�ŏI�Ղ́A�����f��������ꂽ�ϋq�ɂƂ��ẮA���\�蒲�a�Ɍ�����͂��B����ł��q���C�������邱�Ƃ��玩���̑̂̕ω��ɋC�Â��G���f�B���O�ɁA�P�P�R���Ԃɓn���ă��C�u���[�̊����Ȕ��e�Ɍ�����Ă����ϋq�́A�v�킸�����ȏ݂�R�炵�A�P�ӂ̏j���𑗂邾�낤�B��������Âɍl���Ă݂�A�q���C�����u������l�Ƌ��ɘV���Ă����K���v����ɓ��ꂽ�㏞�́A�����ď������͂Ȃ��킯�����B �i�Q�O�P�T�D�P�O�D�U�D�L�j �i�C�g�N���[���[�@�@NIGHTCRAWLER �i�Q�O�P�S�N�A�āA�����F�H�j  �@������w���̍��͂S�N���ɂȂ��Ă���A�E�������n�߂�悩�����̂�����ǁA�����͂R�N�����瓮���o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��悤�ł��C�̓ŁB���N�͓���̉��֓���x�点�����̂́A�O���n��Ƃ������삯����̂ŗL�����������Ă��܂����Ƃ��B �@��Ƒ��͗\��̗̍p�l���𑁂߂Ɋm�ۂ������̂��낤���A������o�������ē�����w���͓�����킯�ŁA���Ƃ���T�������͓̂�x��Ԃ��B�w���̑��ɂ��Ă��A��������������Ђ̌o�c���X�����X�N�͏�ɂ���킯�ŁA���܂葁�߂ɓ�����o���Ă�����Ă����ꂵ���Ȃ����낤�B��͂�݂̂����ɂS�N���̉Ă��炢���烈�[�C�h���Ŏn�߂�̂����������Ɏv���邯�ǂȁB �@�A�E�����Ɋւ��Ă���ȏ�ɖ�肾�Ǝv���̂́A�u���Ȃ��̒����͉��ł����H�v���́u�u�]���@�͉��ł����H�v���́u���̉�Ђʼn�����肽���ł����H�v���̂Ƃ��������肫����Ȏ���ŁA�ʂ����Đ����Ȑl���]�����ł���̂��Ƃ������ƁB�����̎���ł킩��̂́u���C�v�ł͂Ȃ��u���C�̂���ӂ����\�́v�ł���A�u�l���v�ł͂Ȃ��u�l�������o����\�́v�ł���B���Ȃ͐�����O�ŁA�S�ɂ��Ȃ��Ȃ��Ƃ������̂��Ђǂ����Ȃ��̂�����A���Ԋ�Ƃł̖ʐڎ����͎S�邽����̂������B �w�i�C�g�N���[���[�x�̎�l�����C�X�i�W�F�C�N�E�M�����z�[���j�́A����Ƃ͐����̒j�B�`���̃G�s�\�[�h���ނ̐l�Ԑ���[�I�ɕ\�����Ă��ďo�F���B�����ݎ��ނ�ʂ̉�Ђɔ��肳���ɍs�������C�X�́A���낤���Ƃ������̐ӔC�҂Ɂu�����ق�Ȃ����v�Ɣ��肱�ނ̂��B��������肷��̂ł��Ȃ��A������������̂ł��Ȃ��A�u�ߍ��͋ΕׂȐl�Ԃ����Ȃ��B���͋ΕׂŔS�苭���l�Ԃł��v�݂����Ȋ����ŁA�������ʂ̋��E�҂��������ʂ̏A�E�ʐڂŌ����悤�Ȃ��Ƃ��������Ⴀ���Ⴀ�Ƃ܂������Ă�B���̓��i����������ł����D�_�����B �@���̌�����C�X�͉�l���ƂɁA�\�����Ȃ������h�����ǂǂ����Ŏ蕨�߂����r�W�l�X���_��l���ς���l��������B�₪�Ă킩���Ă���̂́A�ނ��C���^�[�l�b�g�̖�����w�u���ł������o�����̂��Ƃ������ƁB�����̌��_��������j�ł͂��邪�A���Ȃ��Ƃ����ƂłȂ��Ƃ͌����Ȃ��悤���B �@���������C�X�́u�{�ł����ǂv�Ƃ��u�l�b�g�u���ł����������v�Ƃ����`�ł͂Ȃ��A�܂�ł��ׂĂ������̃I���W�i���̍l���ł��邩�̂悤�Ɋm�M�������Č��˔\�̎�����Ȃ�ˁB�A�E�ʐڂɓ������Ƃ̒S���҂́A���Ԃ������g�O�����h�Łg�㏸�u���̋����h�w���ɏo��ƁA�ӊO�ɂ�����Ɠ�����o���Ă��܂��̂ł͂Ȃ����Ǝv���B �@�����A���������ُ퐫�i�҂��̗p���Ă��܂���Ƃ̒S���҂��u�~�X�v��Ƃ��Ă���̂��ƌ����A�K�����������Ƃ�������Ȃ��悤�ȋC�����邩��A���̖��͓���B���ۂ̂Ƃ���A���C�X�݂����ȓz���c�ƐE�ɐ�����A���������Ɋ�������A�������ʼn����������肵�āA���������������т����������ȋC���������ˁB �@�������Ƒ��o�c�̗��ƂȂ������肷��ƁA���ςȏp��ʼn�Ђ��ۂ��Ə�����ꂩ�˂Ȃ����炲�p�S�B�����E���̐��̃p�p���b�`�ƂȂ������C�X���A���[�J���j���[�X�ǂ̃f�B���N�^�[�i���l�E���b�\�j�Ɏ�����A���͂̐l�Ԃݑ�ɂ��Ȃ��玟��ɂ̂��オ���Ă����B �@�v�n�v�n�v�́u�n���E�b�h�E�G�N�X�v���X�v�Ŗ{��̏Љ���������ɂ́A�Ă����胁�f�B�A�̃Z���Z�[�V���i���Y��������������i���Ǝv�������A�ǂ������ꂪ���ł͂Ȃ��悤���B����͂Ȃ����m�\�͍����A�l�ԊW�i�Ƃ�킯�͊W�j�̋@���ɂ͉s�q�����ϗ��ς̂܂�łȂ��l�����������M�����z�[�����G��B���̔o�D�A�{���ɖ�I�Ȃ��ˁB �@�{����ςĂ�����A�r���E�Q�C�c��X�e�B�[�u�E�W���u�Y�������ƃ��C�X�Ɠ��ނُ̈퐫�i�҂������낤�ȂƎv���Ă����B �i�Q�O�P�T�D�P�O�D�U�D�L�j �W�����E�E�B�b�N�@�@JOHN WICK �i�Q�O�P�S�N�A�ā��������A�����F����L�K�j  �@�T�O�����L�A�k�E���[�u�X���u�E�������E���E�����v�Ƃ������ǂ���ŋv�X�ɃJ�b�R�����Ƃ�������������B�ނ̉�����^�C�g�����[�����A���Ԃƈ����̖���D�������V�A���E�}�t�B�A�����������Ɠ|���Ă����B �@�K���t�@�C�g�Ƃ����̂͒ʏ�A���̋�����u���Ă����̂����A�ނ̃A�N�V�����͏e��Ў�̔�����B�l�������犴���������w���x���I���x�̃N���X�`�����E�x�C���Ƃ͈Ⴂ�A�P�l�̓G�Ɏ��ߋ�������Œ�Q�`�R���͂Ԃ�����ŁA�D�L�����̍����~�߂Ă����B �@�ʔ����̂́A�܂�ʼn����̃M���h�i���Ǝґg���j�̂悤�Ɂu�E�����̃R�~���j�e�B�v���������Ă���_���B���V�A���E�}�t�B�A���ق��h�q����A�E�B�����E�f�t�H�[��������E�B�b�N�̐e�F�܂ŁA���̉f��̓o��l���͎E��������B�N�����s�������̂��A�ނ�̊Ԃł͓��ʂȋ��݂����ʂ��A�S�������̃��[����m�`������čs������B���܂ɂ����j��҂�����ƒ��ԓ��̝|�Ɋ�Â�������Ă��܂��B �@���ł�����Ȃ̂́A����ȎE����������p�̃z�e��������Ƃ���B�ނ�͂P�̑g�D�ɑ����Ă���킯�ł͂Ȃ��A�����܂ł��l���Ǝ�̃M���h������A�˗�����Ό݂��ɎE���������Ƃ�����B���������̃z�e���̒������́A�E���͌�@�x�̈��S�n�тƂ����ݒ�B�]�ƈ�����A�q�����ׂĐS���Ă��āA�N�������܂݂�̕��ŋA���Ă��Ă��A�t�����g�}���́i���Ƃ��Γy�؍�ƈ����D���炯�̕��ŋA���Ă������̂悤�Ɂj��F�ЂƂς��Ȃ��B�q���m���݂��̐E�Ƃ͏��m�̏ゾ����A���̂ɓ����Ȃ��ނ�̌����͂����V�j�J���ȏ��ށB �@�f�����邤���ŁA���E�ς����ɍ\�z���邱�Ƃ��ǂ�قǑ�������������Ă����P�{�B�@�@ �i�Q�O�P�T�D�P�O�D�Q�D�L�j �r�b�O�Q�[���^�哝�̂Ə��N�n���^�[�@�@BIG GAME �i�Q�O�P�S�N�A�t�B�������h���p���ƁA�����F���c���}�j  �@�@��Ńe���U�������č��哝�́i�T�~���G���E�k�E�W���N�\���j���t�B�������h�̎R���ɒP�g�ŕs�����B���R�o������P�R�̏��N�i�I���j�E�g���~���j�Ƌ��ɖ�̐X�Ō����̃T�o�C�o�����E�E�E�Ƃ����̂�������A���̓A�N�V������T�o�C�o���̕������A�������w�I�ȑ��ʂ��Ր��ɐG���B �@��l���̏��N�̕�炷�R�~���j�e�B�ł͎�̔\�͂ɂ���Đl���]�����������l�q�B�w�q�b�N�ƃh���S���x�̎�l���͕����h�I�ȕ����̉��l�ς��߂��ڂŒ��߂Ă������A������̃I�X�J���N�͎��������e�̂悤�Ȉꗬ�̃n���^�[�ɂȂ肽���Ƃ����˂����A���ꂪ�ʂ������t���X�g���[�V�����ɋꂵ��ł���i���̉f��A���Ȃ�̒�\�Z�ŎB�e�����炵���A�R�~���j�e�B�̏������͏o�Ă��Ȃ��B�j�����͕��e���܂߂đS�����R�[�J�\�C�h��Ȃ̂ɁA�Ȃ����剉�̎q�����������S���C�h�炾�j�B �@�ē̃����}���E�w�����_�[�́A����ȏ��N�̗h���S�������ɂ���������Ă���B���e�̎Ⴂ���̎ʐ^�������哝�̂ɁA�u�N�Ƃ������肾�ȁv�ƌ����ď��N��������ւ炵���ȏΊ�͂ǂ����낤�B�P�l�Ŋl�������ʉߋV��ɗՂ��N���A���炩���ߕ��e���l�����u�d����Łv�����Ă��ꂽ�̂��ƒm�������̋��J���Ǝ��]�́E�E�E�B �@�������N�͂���ȁu�d���݁v�ɔw�������āA����̒m�b�ƗE�C�𗊂�ɂ����Ƒ傫�Ȋl���i�r�b�O�Q�[���j��ǂ��Ă����B �w���C�Y�E�����i�[�x�̂悤�ȃn���E�b�h���x�`�f��ɔ�ׂ�Β�\�Z�Ԃ肪�ڗ����ǁA�r�����m�����Ă܂��������Ȃ�����������ƈႢ�A������͕����⏬������\���ɗ�����������B��͂�f����́\�\������x�͂����ł���ɂ���\�\�Ō�͂�������Ȃ��悤�ŁB �i�Q�O�P�T�D�P�O�D�Q�D�L�j �����킹�͂ǂ��ɂ����@�@HECTOR AND THE SEARCH FOR HAPPINESS �i�Q�O�P�S�N�A�p=��=��=��A�A�����F�Γc�q�j  �@�䂪�Ƃōw�ǂ��Ă���V���ɂ͐l�����k�̗�������A�������܂��܂ȃ^�C�v�̑��k�����Ă���B�Ƃ��������m�Ɍ����Ȃ�A���܂�����^�C�v�̑��k�����x�����x�����x�����x���J��Ԃ��f�ڂ���Ă���B �u�v�̂R�O�N�O�̕s�ς������܂���v�Ƃ������k�Ɓu�v�̐e�ʂ������ł��܂�܂���v�Ƃ������k�����̑o�����ȁB���̂Q�̃p�^�[�������Ō��X�̑��k�����̔������炢���߂Ă����Ȃ�������i�����܂ł����̑̊��ł��j�B����ȂɌ����Ȃ�ʂ���A�Ǝ��Ȃ�ЂƂ��ƂŕЕt�����Ⴄ���ǁi��҂̑��k�����āA���ۂɂ͕v�̐e�ʂ������Ȃ�Ȃ��āA�v�������Ȃ�ˁj�B �@���̑��̑��k�ɂ��Ă��A�܂��A������Ȃ��Y�݂��������Ƒ������ƁB���̂�����Ȃ����̂ɂ��������A����͂ɂ������߁A�킴�킴�Ԃ̑��l�ɑ��k���Ă��悤�Ƃ����l������قǓr��Ȃ�����Ƃ��������ɂ͋C�������Ȃ�i���܂�ɐM�����������ƂȂ̂ŁA���͑��k�����̂��Ȃ�̕����͒S���L�҂̑n��Ȃ̂ł͂Ȃ����Ƃ��A���͖����ɋ^���Ă���j�B �@�҂̒��ɂ���������������Ă���l�����āA���Ƃ���Ƃ̏o�v���B�Y�Ȃǂ́A�����ɂ߂đ��k�҂��̂̂������B�ǂ������̐l�A��ʐl�̂��ē����̗J�����炵�����Ă���Ƃ����v���Ȃ��B����Ō��e�������炦�邾���ł����������ȏ��������A���̃I���W�A�Ƃ��Ƃ����̂��������ȑf�l���̖ⓚ�W���o�ł܂ł��Ă��܂����B����Ȗ{�A���������N�������낤�H �w�����킹�͂ǂ��ɂ���x�̎�l���w�N�^�[�i�T�C�����E�y�b�O�j���A�����h���̐��_���͈�Ƃ��Ė��������u�����͕s�K���v�Ƒi���銳�҂����̌��t���Ă��邤���ɁA�v�c���Ɛꂿ�Ⴄ��ł��ˁB�ŁA�K���Ƃ͉��Ȃ̂������T�[�`�������Ȃ�A�悭�ł�����������̃N�����i���U�����h�E�p�C�N�j���c���Đ��E�̗��ցB �@��C�ł́u���Ŕ�����ō��̍K���v�𖡂킢�A�`�x�b�g�ł͍��m�ɋ�������B�A�t���J�ł͕����g�D�ɝf�v�E�ċւ���A���T���[���X�ł͊w������̗��l�ƍĉ��B �@���̉ߒ��Łu�K���Ƃ͂Q�l�̏����Ɉ�����邱�Ɓv�u�K���Ƃ͂��ׂĂ�m�肷���Ȃ����Ɓv�Ƃ������̂��[���̂��悭�킩��Ȃ��g�������ʁh�𒅁X�ƃm�[�g�ɂ������߂Ă����w�N�^�[�B �@�Ƃ��낪�A�t���J�̕����g�D�́A�u�K���̃��T�[�`�v�Ȃ�ċY�ꌾ�͐M���Ȃ��B�u�{���͉����ړI�ȂH�v�Əe��˂������āA�w�N�^�[�͂��Ɂu�l���K���ɂȂ肽���v�Ɩ{����R�炷�B�u������K���Ƃ͉�����m�肽����v�ƁB �@�����ɗ������āA�l����h�邪���̌������Ă��܂��ƁA����܂ł̉��l�ς�D�揇�ʂ��傫���ς���Ă��܂��l�����Ȃ��Ȃ��B�w�N�^�[�̏ꍇ�͂������A���[�e�������N�́u�����v�̃p�^�[���������B �@���̏I���ɔ]�Ȋw�̎�����ɂȂ����w�N�^�[�́A�u�X�e�B�b�t�E�A�b�p�[�E���b�v�X�v�̉p���l�炵���A�낭�Ȋ����\���Ȃ��B�Ƃ��낪�N��������̓d�b�����r�[�A�l�X�Ȋ���D��Ȃ����G�ȁu�K�����v��������̂��B�����Ĉ����鏗���ɁA����������扄���ɂ͂��Ȃ��A�N���]�ނƂ���q������낤�ƍ�����B�܂Ńx�`���x�`���ɂȂ������̃V�[���̃y�b�N�ƃp�C�N���ǂ�����ƂĂ����܂����āA�Ђ˂��т��ϋq�ł��鎄���v�킸�u���炢�����v���B �@�ēE�r�{�̃s�[�^�[�E�`�F���\���͕�����|�̃M���O�������Ղ�Ɛ��肱�݂A�w�N�^�[�̗����i���X�K�͂̑傫�ȁj���[�h���[�r�[���ɒǂ��B���[�h���[�r�[�ɂ͑����荇�����l�X�Ƃ̐G�ꍇ�����t�����B�P�l��������w�N�^�[���s����X�ő�x���i�X�e�����E�X�J���X�K���h�j�⍂�m�i�ɐ쓌��j�A���i�W�����E���m�j�A�]�Ȋw�ҁi�N���X�g�t�@�[�E�v���}�[�j��Ə����A�N���̔ނ�ɐl���̓��ē�������Ă����B���J�m���̃g�j�E�R���b�g���܂߁A�����w���Ȃ��Ȃ����ō��ۓI�ł��ˁB �u�l�͒N�����K���ɂȂ�\�́^�����^�`��������v�Ƃ����̂����肩��̃��b�Z�[�W�B���ƑP�ӂɕ�܂ꂽ�A�P�ٌ��J���S����ɂ��܂��Ǎ삾�����B �@����͂���Ƃ��āA����ɐ����������Ă��Ȃ����́A�ǂ��ōK������������悢�̂��H�@�l�����k�ɓ������Ȃ��ƃ_��������H �i�Q�O�P�T�D�V�D�Q�X�D�L�j �^�[�~�l�[�^�[�F�V�N���^�W�F�j�V�X�@�@TERMINATOR: GENISYS �i�Q�O�P�T�N�A�āA�����F�H�j  �@���O��`�p�̂��̎ʐ^�����������ŁA�l�^�o���̌x���͂��͂�s�v���낤�B�W�F�C�\���E�N���[�N���W�����E�R�i�[�������邱�Ƃ͒N�������O�ɒm���Ă����B �@�V���[�Y�����肪����f���Ƃ���ɂ���Ă͂����Ȃ����Ƃ�����B����̓t�@���Ɉ�����Ă����o��l�����A������Ȃ��ޏꂳ������A���ɐQ�Ԃ点���肷�邱�Ƃ��B �w�G�N�X�y���_�u���Y�R�x�ŏ��o�ꂵ���b�h�`�v�����̃n���\���E�t�H�[�h�́A�u�O�C�̃`���[�`�i��P�`�Q��ɏo�Ă����u���[�X�E�E�B���X�j�͂ǂ������H�v�ƕ�����āA�u�z�̓A�E�g�E�I�u�E�U�E�s�N�`���[�ɂȂ����i�u�ٓ��ɂȂ����v�Ɓu�V���[�Y���牺�낳�ꂽ�v���������M���O�j�v�Ɠ����Ă����B�����A���̂��炢�͂܂������h�ł��ނ��낤�B �@�t�@���Ƃ��č������Ⴄ�̂́A�����Əd�v�ȓo��l���̏ꍇ�B �@���Ƃ��s�u�V���[�Y�́w�X�p�C����x�̂��납��A�W���E�t�F���v�X�͎�l���̖����ƌ��܂��Ă����̂ɁA�f��w�~�b�V�����F�C���|�b�V�u���x�̑�P��ł͂������肻������B�����ӊO���͂��邾�낤���ǁA�ǂ��l�������ĕ��Q�̕����傫���ł���I �@���邢�́w�G�C���A���R�x�̏ꍇ�A��Q��ł���������ȑ��݊��������������j���[�g�Ɛ�m�q�b�N�X�������p���Ȃ������I�@�ēɃf�r�b�h�E�t�B���`���[���N�p���Ȃ���A���̍�i���V���[�Y�����Ă̖}��ɑ����̂������͂Ȃ��B �@�ŁA�w�W�F�j�V�X�x���B���łɂS��ڂ܂ō��ꂽ���̂��g�V�N���h���邱�Ǝ��̂ǂ����Ǝv�����A�܂��Ă�W�����E�R�i�[���@�B�R�̑��ɐQ�Ԃ����������A�V���[�Y�̍������Ђ�����Ԃ����Ⴄ����Ȃ�����A�����I �w�X�^�[�E�E�H�[�Y�x�̃A�i�L�����_�[�N�T�C�h�ɗ����邱�Ƃ��t�@�����e�F�����̂́A���ꂪ�R�O�N�z���̊���H�����������炾�B�Ƃ��낪���́w�W�F�j�V�X�x�ł͂����Ȃ肠�̐�`�ʐ^�����J����A����ɂЂǂ����Ƃɂ͌����ł��W�����E�R�i�[�������ɂ��ċ@�B�R�Ɏ�肱�܂ꂽ�̂��Ƃ����̐S�v�̓_�ɖ����̂��������͂Ȃ��I �@�V���[�Y�̐��݂̐e�ł���W�F�[���Y�E�L���������́u���ɂƂ��ĂR��ڂ̃^�[�~�l�[�^�[���v�Ȃ�Ă����ɂ���`�L�̂���^���𑗂��Ă�������ǁA�{���ɂ���Ŕ[�����Ă���̂��ˁH �i�Q�O�P�T�D�V�D�Q�X�D�L�j �A���X�̂܂܂��@�@STILL ALICE �i�Q�O�P�S�N�A�āA�����F�����t�q�j  �@���e�Ɋ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ͑��X���邪�A����ɑ����Ă��̍ł�����̂�������Ȃ�A�W�O��ɓ����������{�P���Ɏ������Ă���Ă��邱�Ƃ��낤�B�Փ˂��邱�Ƃ������̂œ������Ȃ����������ɕ�点��Ƃ�����������邪�i�j�A�������̍������̏ۂ��Ď��̖{���������Ƃ炦��Ȃ�A���l�����Ƒ����Ɨ������������c�ނ̂͋ɂ߂Č��S�Ȃ��Ƃł͂Ȃ����Ǝv���B �@�Y��������X�ɂ͐S�Ȃ����t�ɂȂ��Ă��܂��đ�ςɐS�ꂵ�����A�p�j������A�\�͂��ӂ�����肷��Ƒ������̂͒n�����B�䂦�Ɏ��͉��E�l��Ƃ��Ă��܂��l�X���Ƃ��Ă��ӂ߂�C�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�����܂ōs���Ȃ��Ă��A��엣�E�ȂǂƂ����ǂ��l���Ă������\���Ɍ�����I����]�V�Ȃ��������X�������Ă���B����ł͉�삷��Ƒ��̐l���������䂭�܂��B���̍��̐��{�͎{�݉����ݑ����D�悵�悤�Ƃ��Ă��邪�A����Ȃ��͕̂s���Y�����Ȃǂɂ���ē����Ȃ��Ă��H�ׂĂ���������K���ɂ�����������ґ�Ȃ̂ł͂���܂����B �w�A���X�̂܂܂Łx�̓����q���C���i�W�����A���E���[�A�j�͂T�O�ɂ��Ď�N���A���c�n�C�}�[�a��鍐�����B����w�̋���������������Ă�������B���������̕a�C�͈�`���Ȃ̂������ŁA�����̌��ʁA�����ɂ����q������Ă���Ɣ��o�B���ʁA�A���X�͎������g�̌˘f����ꂵ�݂��肩�A�䂪�q�ւ̍߈����܂Ŕw�������ނ͂߂ɂȂ�B �@����҂̃��T�E�W�F�m���@�͐_�o�Ȋw�҂ŁA�A���c�n�C�}�[����Ƃ̊ւ����[���B�A���X����͂̐l�X�̌����ɂ��A�����炭����҂����ۂɌ����������Ⴊ���f����Ă���̂��낤�B���Ƃ��A���X�̎厡��H���B�u�m�I���x���̍����l�قǁA�s���̖��������܂�����������Ă��܂��̂ŁA�늳����������ɂ����v�B�Ȃ�قǁA��������Ȃ�B �@���邢�͕a�C��鍐���ꂽ�A���X�H���B�u�������K���Ȃ�悩�����B�K���Ȃ�p���������Ȃ��v�B���`��A���̋C�����A�悭�킩��Ȃ��B �@�����Ƃ��A�P�O�P���̉f�悪�I��邱��ɂ́A�u�p���������v��������悤�Ȏ��ӎ��̓q���C���̐S��������Ă���B�������Ƒ��̊�▼�O���킩��Ȃ��Ȃ�A�����̃A�C�f���e�B�e�B�����B���ɂȂ��Ă��܂��̂��B�����̓��L�𓐂ݓǂ݂��đ傰�ɂȂ��������A�u����A���Ȃ��Ɖ����ł������C������v�Ǝӂ�̂�����A�������{�������Ƃ��o�J�o�J�����Ȃ邾�낤�B �@�܂��Ǐy����������A�A���X�͏����̎����Ɍ����āA���p�̃p�\�R���Ƀr�f�I�E���b�Z�[�W���c���B�u�ȉ��̎���i���Z����q�ǂ��̐l���Ȃǁj�ɓ������Ȃ��Ȃ�����A�����邱�Ɓ������s���Ȃ����E�E�E�v�B�Ƃ��낪�Ǐ�̐i�A���X�́A�ߋ��̎������Ō�̌ւ�Ƒ����������đ������A����ȁu���ɂ̎w�߁v���������ɐ��s���邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂��B���Ƃ����ߊ쌀���낤���B �@�����A�{��͔ߊ쌀���B�r�F�̂��������ЂƂŁA�����Ƃ����Ɛ[���ȉf��ɂ��ł����͂������A�����ē̃��`���[�h�E�O���b�c�@�[�ƃE�H�b�V���E�E�F�X�g���A�����h�́A���������I�������Ȃ������B�A���X���钆�ɓ��h���ďn�����̕v���������N��������A����̃g�C���������炸�ɂ��R�炵�������肷��V�[���������邪�A�{���̏C����͕`����Ă��Ȃ��B�W�����A���E���[�A�ɃA�J�f�~�[�剉���D�܂������炵���ɂ��ẮA�����Ԃ�ƃI�u���[�g�ɂ���܂ꂽ���₩��(�܂��͐��ʂ邢�j�f�悾�����Ƃ�����ۂ��c��B �@�����A�{��ň�ԋ��낵���̂́A���͉f�悪�������Ă���̓W�J��������Ȃ��B�v�ƒ��j�͈���������t�Ƃ��ẴL�����A��Nj����A�ǂ��ł��������i�P�C�g�E�{�X���[�X���͂܂���j�͑o�q�̎q��ĂŎ��t�B���̂��߃G���f�B���O�ł́A�G���[�g��Ƃ̂͂ݏo���҂��鎟���i�N���X�e���E�X�`�����[�g��������͂܂���j���A���D�ɂȂ閲�𒆒f���āA���̂��߂ɐe���ɖ߂�B�\�ʓI�ɂ͘a���ƉƑ����ɕ�܂ꂽ���k�ł���B �@�����T�O�Ƃ����N��ݒ���l����A�A���X�͍���R�O�N�ȏ�i�A���X�̂܂܂��Ȃ�ʁA��������A���X�ł͂Ȃ��Ȃ�����ԂŁj����������\��������B���̊ԁA�����̓L�����A���ς߂��A�������ł����A�q�ǂ������Ă��A�Љ�Ƃ̂Ȃ����f���ꂽ�܂܁A�i���܂��ɂ́j��e������Ő����Ă������ƂɂȂ邾�낤�B �@���̓_�ւ̑z���͂������邩�ǂ����ŁA�{��̊ӏ܌㊴�͂����Ԃ�ƈ�������̂ɂȂ邾�낤�Ǝv���B �i�Q�O�P�T�D�U�D�P�S�D�L�j ���݂�����̍�@�@�@STILL LIFE �i�Q�O�P�R�N�A�p���ɁA�����F�吼���q�j  ���̖����̌����̐Εǂ� �J�r�Ŕ������Ȃ��Ă��Ď��ɐ▭�B �@�������͓��퐶���̒��ł��܂��܂ȏ��i������ǁA���̒��ɂ͈��̕p�x�ŕs�Ǖi���������Ă��āA�ԕi������A���������߂���A�����Q���肵���肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ�����Ƃ����̂́A�N�����o������m���Ă���Ƃ���B���̂��ߎ����ԕi�^�����ƂȂ����Ƃ��Ɏ����ō���^�^���^��������̂�����Ƌ�ނȂǂ́A�Ȃ��Ȃ��C�y�ɔ������Ƃ��ł��Ȃ��i�������Ŏd���p�̈֎q�͂��͂�{���{�����j�B �@����ɖ��Ȃ̂��Z��ŁA�����Ƃ���ɂ��ƁA�s�ǂɂ͌����C���őΉ��ƂȂ�A�˂��Ԃ����Ƃ��ł��Ȃ���������Ȃ��ł����B���ɕ������̂ɖ��͂Ȃ������Ƃ��Ă��A�Z��Ȃ�Ă��̂͗אl�����N�f�i�V�ł�������܂��s�Ǖ����ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA���͎����Ɗ�]�Ƃ������̂��܂����������Ƃ��ł��Ȃ��B�w�q�[�g�x�̃��o�[�g�E�f�E�j�[���̂悤�Ɂu���o���Ȃ�����R�O�b�t���b�g�ō���тł���v���ݐ����̕�����قNjC�y�ł���B����ɂǂ������Z�܂�������Ƃ������ƂŁA�����Ƃł͉䖝�ł��Ȃ��͈͂̂��Ƃ܂ŋt�ɉ䖝�ł����Ⴄ�ʂ������Ȃ��ł����ˁB �@�Ƃ��낪���{�������Љ�̓x�����߂Ă����ɘA��āA����u�ꐶ���݂ł�����v�Ƃ͊����Â炭�Ȃ��Ă����B�Ȃ��Ȃ�Ǝ傪�Ƌ��V�l�ɕ�����݂��̂�������悤�ɂȂ��Ă��邩��B�܂��A�����ł��Ȃ��b�ł͂Ȃ��B�g��肪����̂��ǂ������킩��Ȃ��X�q���������̂Ŕ������ꂽ��A�Ǝ��Ǘ���Ђ����č���܂���ˁB���͎��̃A�p�[�g�ł�����Ɏ������Ⴊ�Q�������Ă������̂������ŁA�O��̌_��X�V�̂Ƃ��ɂ͂��ɂȂ������ɕۏؐl�̊m�F�����ꂽ�B����Ȏ��������������Ƃ�S�R�m��Ȃ������̂ŋV�������i�����Љ�A����ׂ��j�A�|����Ȃ̂ŏڂ����b���͍̂T�����B �w���݂�����̍�@�x�͌ǓƎ��𐋂����ҁi����҂Ɍ��炸�j�̐g�Ӑ�����S�����郍���h���̒n���������W�����i�G�f�B�E�}�[�T���j����l���B�N�������瑽�Z���������߂ɃV�l�X�C�b�`����ŏ�f���͂Ƃ��Ƃ����ɍs���Ȃ��������A�^�ǂ��q���[�}���g���X�g�V�l�}�L�y���̌����f�Ɋ��肱�߂��B�̂Ō����Ȃ烍�[�h�V���[�قŌ������A������Ŋς����o���B �@�W�����͘A�����Č���̃A�p�[�g�ɏo�����ƁA�Ǘ��l�ƈꏏ�Ɉ�i�����A������肪����ɉ����������ċߐe�҂�{���B�ǂ����Ă�������Ȃ���Ύ��瑒�V����z���āA���҂��B�ߐe�҂����������ꍇ�ł��A����ɂ���Ă͑��V�̔�p����A�ނ炪�Q�邽�߂̗���܂ŏo���炵���B�������A�p�[�g�̐��|����Č����o��̂��낤�B���{�ɂ����������V�X�e��������A�Ǝ傪�Ƌ��V�l�Ƃ̌_����a�邱�Ƃ��Ȃ����낤�ɂȂ��ƁA���͊ӏܒ��ɍl���邱�Ƃ����肾�����i�������{���Ƀ����h���̖����ɂ�������������T�[�r�X�����݂���̂��͕s���B�}�[�K���b�g�E�T�b�`���[���^����ɐ��Ă��܂������ȋƖ����j�B �@�ē̃E�x���g�E�p�]���[�j�͑O���A��������Ǝ��Ԃ������ăW�����̎d���Ԃ�Ɛ������A�܂�͐l�ƂȂ��`���o���B�`�����炵�ĉp��������A�M���V�������A�J�g���b�N�̑��V�R�A�`�������B�W�����͈�i���q���g�ɂ��̐l���D�����������y��I�сA���̐l�̐l�����̂��钢���������A���E�҂ƂQ�l�A�h�ӂ������Ď��҂𑗂�B�ǂ�ȑ���������u�ĂȂ��A�^���ɐE�������Ȃ��W�����B�Ȃ�Ă����l�Ȃ낤�B �@�ł��A���ꂾ������Ȃ��̂��A���̍�i�̖ʔ����Ƃ���B���̃W�����N�A���҂����̐��O�̊�ʐ^������Ɏ����A��A�l�I�ȃA���o���ɐ������Ă����ˁB���������̎����猩��A���肤�ׂ��炴����������E�E�E�Ƃ������A�������ϐl���B�d���ő����荇�����i�H�j���҂ɁA�܂�ŗF�l�ɑ���悤�Ȉ���������Ƃ́E�E�E�B �@�[�H�̓c�i�ʂ��J�|�b�ƎM�ɂ��������́{�g�[�X�g�P���{�����S�P�{�g���B����Ȃ��̊ʂ��璼�ڐH�ׂ�Ⴂ������Ȃ����Ǝv���̂����A�Ⴂ�����ɂ��K���u�~�X�^�[�����v�ƌĂт�����p���a�m�̃W�����́A�H���i�v�L����������ƃe�[�u���ɃZ�b�g���A�i�C�t�ƃt�H�[�N�Ńc�i�ʂ�H�ׂ�B�����炭�͏\�N����̂��Ƃ��B �@���̃W�������ˑR�̉��ق������n���ꂽ���Ƃ��畨�ꂪ���������B�Ō�̎d���ƂȂ������҃r���[�̋ߐe�ґ{���ɁA���ɂ������ĔM������W�����B�i���Ԃ�����āj�p���e�n���щ��ނ̐s�͂ŁA�V�U�ǓƂɎv��ꂽ�r���[�̐l��������ɖ��炩�ɂȂ��Ă����B�u���҂P���v�Ƃ������v�����ł����Ȃ������V�l�ɁA�ʂ�L���ŁA�����Ԃ�j�V�r�ȉߋ������������ƁA�����ɂ͊m���Ȍ��Ə�̂Ȃ��肪���������Ƃ���������ɂȂ�B �@�����ɏ\�N����̂��Ƃ��������W�����̐l���ɂ��ω��̒����������B�ǓƂ���ɂ��������Ă����ނ��A��������W���D�ӂ�������A���ɂ��Ȃ��f�[�g�̖��B�������R�C���ɂ͕K������������̂ŁA����n��Ƃ��ɂ͕K���E�E���E�E�Ǝ��U���Ĉ��S�m�F���Ă����W�������E�E�E�B �@�G���f�B���O�ʼnc�܂��Q�̑��V�̃R���g���X�g���ǂ��ɂ�����B�r���[�̓W�������T�����Ă��ߐe�҂�F�l�����ɑ����A�����P�̑��V�ɂ͗�����҂��Ȃ��B�����A�C�^���A�o�g�̃p�]���[�j�͉p�����̃V�j�J���ȃ��[���A���ѓO���邱�ƂȂ��A��߂���҂͕����Ƃ����^�����ȃ��b�Z�[�W�ōŌ����߂��B�ǓƂȃW�����́u�F�l�v�����́A�{���ɔނɊ��ӂ��A������Ă����킯�ˁB �@���̃��X�g�V�[�������āA�u�����A�悩�����v�Ǝv���邩�ǂ����͐l���ꂼ��B����̐��E�Ȃ�Ă��̂�M���Ȃ����Ȃ́A�w�}�W�b�N�E�C���E���[�����C�g�x�ŁA�R�����E�t�@�[�X������}���I�ȍ�����`�҂��A���̂ɂ������f��̖�������x�͐_�ɋF�肩���Ȃ���A����ł̂Ƃ���Łu�_�Ȃ��邩��v�Ɖ�ɕԂ�V�[���̕��ɋ��������B �@�Ƃ͂������̂Q��i�A�_��V����M����p�]���[�j�ƁA����Ȃ��̂�тقǂ��M���Ȃ��E�f�B�E�A���������ꂼ�����Ă��Ȃ���A�ǂ�����l�Ԃ��\�\���̑P�ӂ����_���܂߂ā\�\�m�肷��`���[�~���O�Ȉ��ɂȂ��Ă���B�ʔ������̂ł��ˁB �@�Ƃ���Ŏ���̐��E��M���Ȃ������A�����A�p�[�g�Ŏ��l�̘b���̂��|�����āA���������Ė������Ă�H �i�Q�O�P�T�D�T�D�V�D�L�j �ނƔޏ��̃Z�I���[�@�@THE THEORY OF EVERYTHING �i�Q�O�P�S�N�A�p�A�����F���Y���ށj  �@�{�P�b�Ɩ{��̂��Ƃɕ����ׂĂ�����u�t�������Y�v�̖��O�����ɕ����B����ł��̐l�͉��y�ƂȂ���Ȃ��A���m�ɂȂ�悩�����̂ɂƎv�����B���łɑ��q���n�J�Z�i�����͉��ł������j�Ɩ��t����A�u�͂����E�͂����E�͂����v���B�ӂƌ��ɏo���Ă��������Ă݂���A�ǂ������킯�����̃c�{�ɓ����Ă��܂��A�Q�����炢�����o���Ȃ������B���R�ƂR��J��Ԃ��̂ł͂Ȃ��A�u���E���E�������v���ӎ����Ă����ƃC���g�l�[�V������t����̂��R�c�B���Ȃ������ɏo���Č����Ă݁B �@�o�J�b�͂��Ă����A���̉f��̊��z���ꌾ�Ō����u���̓^�C�~���O�v�ł����ˁB���������A�z�[�L���O���m�̉f����������z�����ꂩ��ƃc�b�R�܂ꂻ�������A������o�J����Ȃ����甎�m�̌�����Ɛт��ڏq���āA�h�p�P�T�O�ȉ��̊ϋq�点����͂��Ȃ��B�ނ���ނƍȃW�F�[���̊W���ɏœ_���i��A���Ղ̕v�w�̕���Ɏd���ĂĂ���B �@�����A�u���Ղ̈��̕���v�ł͂Ȃ��A�u���Ղ̕v�w�̕���v�ɂȂ��Ă���̂��~�\�Ȃ�ˁB���̂Q�l�A�Ȃ�Ɖ��\�N���A��Y������ɕʂ�Ă��܂��̂��B���m�̎������ɂ��ĉ����m��Ȃ��������́A�ނɍȎq���������Ƃɂ����������A�v�Ȃ����N�ɂȂ��Ă��炻�ꂼ��ɐV�������������������Ƃɂ����Ƌ������B �@�W�F�[���i�t�F���V�e�B�E�W���[���Y�j�͑̂̎��R�������O�̃z�[�L���O�i�G�f�B�E���b�h���C���j�Əo��A�������ʂɗ��ɗ�����B���̃W�F�[�������͂̔����������ė]���Q�N�Ɛ鍐���ꂽ���m�ƌ��������̂́A�܂��A���̂��߂���������������Ȃ����A�����Ŕ��m���̂Ă���ǐS�̙�ӂł����Ɛh���Ȃ�Ɗ��������߂ł����������낤�B�����Ɛ���������������Ȃ�A�u�����Ől���̂����̂Q�N���̂ĂĂ��A�܂��Ⴂ������߂���v�ƌv�Z�����̂�������Ȃ��B �@�Ƃ��낪���m�͂Q�N�ł͎��ȂȂ������B���ǁA�v�Ȃ͗�������܂łɂQ�U�N���A��Y�����ƂɂȂ�B����ł̓W�F�[���̋C�����������̂���������ʂ��Ƃ��낤�B �@�Ђǂ������Ƃ��l�łȂ����Ƃ��������ᔻ�͓�����܂��B�W�F�[���Ƃāu�v���������˂����v�Ȃ�Ă��Ƃ́i���Ԃ�j�l���Ȃ������͂����B�����A�ޏ��͂������ʂ̊w�����������B���̔ނ��������ʂł͂Ȃ��Ȃ������_�ŁA�Q�l�̈��̋A���͌����Ă����̂��B�S�T�L���̏����ƌ��������j�����A�U�O�L���ɂȂ�����������C�����������̂Ɠ������ƁB�N�ɂ��ᔻ�ł��邱�Ƃł͂Ȃ��B �i���̈���ŁA���m�����N���Q���Ă��Ȃ���A�������Đ��N�ŗ������Ă��܂����\��������̂�����A�v�w�̉��Ƃ����̂͂܂��Ƃɂ����ē���j �@����ł��Q�U�N�����������R�̂P�́A���m�����B�\�͂��ێ����Ă������Ƃɂ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B �@�Z�b�N�X���X�v�w�����Ȃ��Ȃ��A���������ꂪ���قLjُ킾�ƌ��Ȃ���Ȃ����{�̎Љ�ɂ���ƃs���Ɨ��Ȃ���������Ȃ����A�Q�����ʂɂȂ�������͂∤�͂Ȃ��ƍl����̂����E�W�����B�����炱���w�V���S���ɐ��܂�āx�̃g���E�N���[�Y�́A���������B�\�͂��������ƒm�����Ƃ��A�u�����N����������Ă��炦�Ȃ��v�Ƌ������B �@���Ƀz�[�L���O���m�����B�\�͂������Ă�����A���̉f��͂��Ȃ�Ⴄ����ɂȂ��Ă����悤�Ɏv���B �@���āA�W�F�[���͑��̒j���̌��ɋ������B��Q����������N�̔��m���Ƃ���c���ꂽ���Ƃ����Ƃ���Ȃ��Ƃ͂Ȃ��āA���x�͌���Ö@�m�̏����Ɉ������̂ł���B�����ۂ����܂�Ƃ͂��̂��Ƃł��ˁB �@�v���w�C���Ԗ��x�̃n�r�G���E�o���f�����A�w�������͒��̖�������x�̃}�`���[�E�A�}�����b�N���A�w�Z�b�V�����Y�x�̃W�����E�z�[�N�X���A�S�g�̎��R����������ɂȂ��Ă���A�f�G�ȏ����Ƒf�G�ȊW�ɂȂ��Ă���킯���B�܂��A�u�f�G�ȏ����v�Ƃ��������ɂ��Ă͉f��ł�����˂Ƃ����g���W���Ȃ��R�����g���ł���킯�����A�u�f�G�ȊW�v�Ƃ��������͂��Ȃ������b�ł͂Ȃ����낤�i���Ȃ݂Ɉȏ�̉f��͂��ׂĎ��b�����ɂ����b�j�B �@�ނ������������Ö@�m����m�̏��������́A�ނ炪�u�D�G�Ȑ��k�^�D���̎��Ă銳�ҁv�ł��������炱���䂩��Ă���B�t�Ɍ����Ȃ�A�ނ炪����ȂƂ��ɏo������̂ł͂����炭���ɗ����Ȃ������B���͈قȂ��̂ƌ����ׂ����A�o��̓^�C�~���O�ƌ����ׂ����B�Ƃɂ�������������i�Q�́\�\���Ȃ��Ƃ���������h�����A�����h�����m��Ȃ��������Ɂ\�\��]�ƗE�C��^���Ă����B �@��������ŁA�u����Ȃӂ��ɐ����Ă������炢�Ȃ�E���Ăق����v�Ɩ]�w�~���I���_���[�E�x�C�r�[�x�̃q�����[�E�X�����N�ɋ������o����̂��܂������B���̓_�ŁA�̂̎��R�������Ă����Ȏ����̏�Ǝ����̓����m�ۂ��邱�Ƃ̂ł����z�[�L���O���m�́A�H�L�̍K���҂��ƌ�����̂�������Ȃ��B �i�Q�O�P�T�D�R�D�P�W�D�L�j �o�[�h�}���@���邢�́i���m�������炷�\�����ʊ�Ձj BIRDMAN OR (THE UNEXPECTED VIRTUE OF IGNORANCE) �i�Q�O�P�S�N�A�āA�����F��c���T���j  �@�A�J�f�~�[�����̌�Ŗ{��̎��ʂ��ςāA�Ȃ�قǍ�i�܂͖���Ă����̂��ȂƉ��߂Ĕ[�������B���Ƃ��Ύi��̃j�[���E�p�g���b�N�E�n���X���p���c�P���ŕ���ɓo�ꂵ���M���O�͂��̂܂ܖ{��̃p���f�B�������̂��i�����Ƀh�����̔��t���������̂��P�Ȃ�w�Z�b�V�����x�̃p�N���ł͂Ȃ������킯�ˁj�B �@�I�[�v�j���O�̃V���[�ŃW���b�N�E�u���b�N���u�����̂̓X�[�p�[�q�[���[�f�����v�ƃ{�������̂��A���̉f��̐��E�ς𗬗p�������̂������B �@������i�܂̃v���[���^�[�ɃV���[���E�y�����o�Ă������_�ŁA�w�Q�P�O�����x�̊ēɉh�����P�����Ƃ�\�z����ׂ��������B �@���̃A���n���h���E�S���T���X�E�C�j�����g�D�ḗA�w�Q�P�O�����x��w�o�x���x�Ō������悤�Ȏ��Ԏ��̎��R�ȑg�ݑւ����ʗ_�J�Ȃ��Ăl���B�������{��ł͋t�ɑS�҂P�J�b�g�Ɍ�����悤�ȘA���B�e���̗p���A�����ڂƂȂ������N�o�D�̂����낤�Ă₪�Ĕ߂����ꓬ��ǂ����B �@�ڂ������̂́A�J�����͂����Ɖ���Ă���i�悤�Ɍ�����j�̂ɁA���Ԃ��K�X��ԂƂ���B���Ƃ��Ίy�����o���o�D��������̒ʘH������Ă����̂��ړ��B�e��N���[���V���b�g�Œǂ��Ă����ƁA�X�e�[�W�ɏo���Ƃ���ŗ����̌������n�܂��Ă����肷��B �@�}�C�P���E�L�[�g���������l���̃��[�K���́A�q�[���[�f��ňꐢ���r�������Ɩ�������B���̓��C�����h�E�J�[�o�[�̏���������r�F��������ɕ����������Ă���B������������̃X�g���X�͕��A�t���l�ɂ������i�G�}�E�X�g�[���j�Ƃ̊W�����܂��������A�G�S�̋�������o�D�i�G�h���[�h�E�m�[�g���j�ɂ͂������B���N�̊�@�̌����ł���B �@���̒j�A�I�[�v�j���O�ł͂����Ȃ���V���Ă��邵�A�O���͂܂Ŏg����l�q�B�������C�j�����g�D�́A���ꂪ�����Ȃ̂��A�ނ̓��̒������ŋN���Ă��邱�ƂȂ̂����Ō�܂Łi���ꂱ���{���̃��X�g�V�[���܂Łj�������Ȃ��B�ϋq�͉��x�����Ɋ�����Ȃ���A�ނ̐l����������̎�Ō@��N��������Ȃ��Ȃ�B �@�q�ǂ����u�z����̗F�B�v�̒��ō��o�����Ƃ�����悤�ɁA�ނ̖ڂɂ͂��Ď������������X�[�p�[�q�[���[�̃o�[�h�}���������Ă���B�u�������́v�ƌ�肩����o�[�h�}���̐����������Ă���i�`���̃V�[���ł͂��̐����N�̐����킩�炸�ɖʐH������j�B���낻�댈�ʂ������Ǝv���Ă���̂����A���傹��͎����̈ꕔ������A���[�K���ɂ̓o�[�h�}����藣�����Ƃ��ł��Ȃ��B �@�C�j�����g�D�͗L�͂Ȕo�D�������݃A���R�~�f��ɏo�Ă���n���E�b�h�̌��������A�l�C�̗������o�D�̂Ȃ�ӂ�\��ʂ������Ԃ�����A�f��l���������Ɠ����ɑA�]���Ă��镑��l�̕��G�ȐS������B�V���[�r�Y�E�̊y�������l�^�̃I���p���[�h�ŁA���L�V�R�o�g�̃A�E�g�T�C�_�[�ɂ悭�������܂ŏ������Ǝv���قǁB����A�ނ���A�E�g�T�C�_�[�����珑�����̂��ƕ]����ׂ����B �@�N���������Ă�������ǁA�R�N�O�̃A�J�f�~�[��i�܂́w�A�[�e�B�X�g�x���A�Q�N�O�̍�i�܂́w�A���S�x���A�L���Ӗ��ł̉f��E�̓������́B���������W�������Ŗʔ�����i������A�������A�J�f�~�[������獂���]�������̂́A�ǂ������͕ʂɂ��āA����Ӗ��A���R�Ȃ̂�������Ȃ��B �i�Q�O�P�T�D�R�D�P�W�D�L�j �Q�O�P�T�N�I�X�J�[�i�C�g�E�E�H�b�`���O�I  �@���N�̃A�J�f�~�[�����̓u�_�y�X�g�Ղ�Ɏn�܂��āA���L�V�R�Ղ�ŏI���W�J�B�Ƃ��ɍő��̂X����Ƀm�~�l�[�g����Ă����Q��i�̂����A�O���́w�O�����h�E�u�_�y�X�g�E�z�e���x����ȁA���p�A�ߑ��f�U�C���A���C�N�̊e�܂𗧂đ����Ɋl�����A�I�Ղ́w�o�[�h�}���@���邢�́i���m�������炷�\�����ʊ�Ձj�x����i�A�ēA�r�{�A�B�e�Ƃ�������v�ȏ܂�Ɛ肵���B �@�Ƃ��낪���́w�o�[�h�}���x�͎剉�j�D�A�����j�D�A�������D�̊e�܂ł��m�~�l�[�g����Ă����̂ɁA�o�D����̎�҂̓[���B�n���茻�ۂ��N�����Ȃ��A����Ӗ��A�o�����X�̎�ꂽ�I�l�������Ƃ������������B �@�����Ĕo�D����𐧂����̂́A�O����̃S�[���f���O���[�u�܂�S�Ĕo�D�g���܂���܂��Ă����{�������B�ɂ�������炸�S�������I�X�J�[�Ƃ����̂��A���N�̖ڗ�����������������Ȃ��B �@�����j�D�܂̂i�E�j�E�V�����Y�͂���܂ʼnf��E�ł̑傫�Ȏ��т��Ȃ��������A�w�Z�b�V�����x�̉����ŏ��̉h�����ˎ~�߂��B �@�������D�܂̃p�g���V�A�E�A�[�N�G�b�g������܂��傫�ȏ܂͏��߂āB�w�U�˂̃{�N���A��l�ɂȂ�܂ŁB�x�Ŏ�܂��������ł�����܂����A�X�s�[�`�̒��Łu�q�ǂ��̕��e�����v�Ɋ��ӂ�����Ă����̂��A���Ă̕����̈Ⴂ�����������Ėʔ��������i���Ȃ݂Ɂu���e�����v�̂P�l�̓j�R���X�E�P�C�W�j�B �@�剉�j�D�܂̃G�f�B�E���b�h���C���́w���m�Ɣޏ��̃Z�I���[�x�Ńz�[�L���O���m�ɕ������̂��]�����ꂽ�B�����Ȃ���A�J�f�~�[�܂ł͏�Q�҉��Z�������B���̐l�A���܂�����҂̖��������Ă����̂Łi�č��ł́w�K���̉��F���n���J�`�x�ŕ��c�S��̖����������ߋ����j�A�Ă�������܂�����҂Ȃ̂��Ɗ��Ⴂ���Ă������A��܃X�s�[�`�ł͑f���ɂ͂��Ⴎ�D�N�B�C�[�g���Z����P���u���b�W�Ƃ����o�����[���́A�p���̂��V����܂ł͂Ȃ����B �@�剉���D�܂̃W�����A���E���[�A�͂T�x�ڂ̃m�~�l�[�g�ŏ���܁B��������A���c�n�C�}�[���҂́u��a���Z�v��ꂽ�B�n�������ǂ��ԂƂ������c���Ă������D���A���͂ȃ��C�o���̂��Ȃ������N���Ɍb�܂ꂽ�i�D���B �@�������č��N�̔o�D����͑S�������l�ŁA�R�l���č��l�B�������N�͊O���l��}�C�m���e�B�ɐȊ�����Ă������������������ɁA�t�ɒ��������ƂɊ�����B �@�j�[���E�p�g���b�N�E�n���X�̎i��͂܂��܂���X�B�Q�C�Ɓw�S�[���E�K�[���x���݂̃W���[�N�����������̂́A�܂��A�\�z���ꂽ�Ƃ���ł͂���B �@��N�̃z�X�g�̓I�[�v�j���O�łЂƂ�����q�Ȃ��������Ă���̂ɓ���̂��ʗႾ�������A�~���[�W�J���o�D�̃n���X�͂����Ȃ�̗w�V���[�ɁB�r���ŃA�i�E�P���h���b�N�ƃW���b�N�E�u���b�N���������A���ɋq�Ȃ����߂�B�u���̉f��E�̓A���R�~�f��ƃ����C�N���炯�B�����}�l�[�ɃS�}�����Ă�v�Ɗy�������M���O���̂����u���b�N�́A�P���h���b�N�ɒǂ��͂���āA���̌�͋q�Ȃ�����������i�j�B �@�e�G��g�������i�H�j�𗘗p�������o���Â�ɋÂ��Ă����B�V���[�̍Ō�ɑ吨�̃_���T�[���������悤�Ɍ������̂́A���̊ϋq�ɂ͂ǂ������Ă����̂��B�L�[���E�i�C�g���C��U�����h�E�p�C�N���������悤�Ȋ�����Ă����Ƃ������Ƃ́A����ł������Č������̂��낤���B �@�s�v�c�Ƃ����A�n���X���u��҂̗\�z����ꂽ�v�Ə̂������������̏I�ՂɂȂ��ĊJ�����Ƃ���A�i���̔����O�l���̃X�e�[�W��ɂ������ɂ�������炸�j���̖�̃n�C���C�g�V�[������ǂ�����L�����J�[�h�����X�Əo�Ă����̂ɂ͋��Q�B���N�̃e�[�}�̓}�W�b�N�������̂��H �@���Ղɂ����ǂ��낪���ʁB��N�̎����ŃC�f�B�i�E�����[���̖��O���ԈႦ���W�����E�g���{���^�́A���N���������肾����ĎӍ߂���͂߂ɁB �@���f�B�E�K�K�͌��J�T�O���N���}�����w�T�E���h�E�I�u�E�~���[�W�b�N�x�̃e�[�}�Ȃ��I�����B�K�K������Ȃɉ̂����܂��ƒm��Ȃ��������́A�u����Ȃ�W�����[�E�A���h�����[�X�ɂ������Ȃ������ˁv�Ǝv���Ȃ��猩�Ă������A�K�K�͌ォ��o�Ă����{�l���Љ��̂Ɂuincomperable�i�䌨������̂̂Ȃ��j�W�����[�E�A���h�����[�X����ł��v�ƁB�������ł��ˁB �w�C�~�e�[�V�����E�Q�[���x�ŋr�F�܂���܂����O���A���E���[�A�́A��l���̃��f���ƂȂ����A�����E�`���[�����O�i�R���s���[�^�̔����ҁj�����I�n�D�䂦�ɕs���������������Ƃɂ��ƊA�u�l���\��̂���Ɏ��E��}�������A�������Ė��邢�ꏊ�ɗ��Ă��B���ꏊ���Ȃ��Ǝv���Ă����҂�A���̂܂܂ł����B�����P���Ƃ�������v�ƌ��A���̖��Ԃ̊������ĂB �@�I�Ղ́w�o�[�h�}���x�̓ƒd��B�A���n���h���E�S���T���X�E�C�j�����g�D�ē̓I���W�i���r�{�܁A�ē܂ŗ��đ����ɃX�s�[�`�ɗ����A��i�܂̃v���[���^�[�̃V���[���E�y���Ɂu�ނɃO���[���J�[�h��������̒N���H�v�ƃc�b�R�܂��n���������B����ɑ��ăC�j�����g�D���u���n�̃��L�V�R�l�Ɍ����ɁB�ږ����Ƃ͂������Ăł�������v�ƁA���L�V�R�l�Ƃ��Ă������������ꖋ���B�Ƃ͂����Ō�͘b�����Ƃ��Ȃ��Ȃ��āA�剉�j�D�܂����}�C�P���E�L�[�g���Ƀ}�C�N�������Ă����B�B�e���͊m�����������Ɠ`������Q�l�����A�Ƃ肠��������͂��Ă��Ȃ������Ƃ������Ƃ��B �Z�b�V�����@�@WHIPLASH �i�Q�O�P�S�N�A�āA�����F�Γc�q�j  �@�܂��o�u�����̂��Ƃ������ƋL�����Ă��邪�A�e���r�̃h�L�������^���[���������j���[�X���������ŁA�Q�`�R�l�̎Ⴂ�n�k���C���^�r���[����Ă���̂��������Ƃ�����B�ޏ����������X�Ɍ�����̂́u�ŋ߂͖��������Ă���j�̐l�����Ȃ���ˁv�u��������Ȃ疲�������Ă���l����Ȃ��ƃC������v�Ƃ������ƁB �@���͂����a��������Ȃ��炻�̏��������̌��t���Ă����B�g�����������j�h�͖��̎������ŗD�悾����A���Ȃ���Ƒ���厖�ɂ͂��Ȃ����ǂˁA�ƁB �@���剹��ɓ��w�����W���Y�h���}�[�u�]�̃j�[�}���i�}�C���Y�E�e���[�j�́A���R�[�`�̃t���b�`���[�i�i�E�j�E�V�����Y�j��������o���h�ɗU���ėL���V�B�������t���b�`���[�͒c�������|�Ŏx�z����\�N�������B��������l�i�G���𗁂т����A�e���|���Ⴄ�Ɩj��@���ꂽ�j�[�}���́A��t�҂ɂȂ邽�߂Ɏ肪���܂݂�ɂȂ�قǂ̗��K���d�ˁA���ɂ͂��̍�����邽�߂ɖ��̊댯�����`���͂߂ɁE�E�E�B �@�{��͐V�l�ēf�C�~�A���E�`���[���̎��`�I�ȕ���Ȃ̂��Ƃ��B�X�P�W���[���̓s���łP���P�W���Ԃ��B�e�����Ƃ�������A�j�[�}���ƃt���b�`���[�̋S�C����l�q���A���Ȃ������Z�����ł͂Ȃ�������������Ȃ��B �@�˔\�Ƃ����̂͗��n�̌��ŁA���邩��K���Ƃ͌���Ȃ��B�w�u���b�N�X�����x�̃i�^���[�E�|�[�g�}�������āA�Ȃ܂��˔\���Ȃ�����C�̂Ƃ肱�ɂȂ邱�Ƃ��Ȃ��������낤�B�{��̃j�[�}�������̓_�͓����ŁA�t���b�`���[�̖ڂɗ��܂�قǂ̎��͂����Ȃ���A���Ԃ�s���y�c���ǂ����ňꐶ�y�����h������@���Ă�����ˁB �@�ꗬ�̉��t�ƂނƂ����ώ��Ɏ��߂��ꂽ�t���b�`���[���܂��A���炩�Ȑl�i�j�]�҂��B�j�[�}���ɑ���u�Q�����炢�ڂ������A�W�����炢���݂��ɂ���v�Ƃ����䗦�́A�܂��ɂc�u�j�̉����䗦�B���ˑ��W�ɂȂ��ĉ����Ă��R���Ă����������j�ƕʂ���Ȃ����������̂��Ƃ��A�y�c�������͔ނɕt���]���B�Ȃ����H�@���̍˔\�������Ă��邪�䂦�ɁA����Őg�𗧂Ă����Ƃ��������̂Ă��Ȃ����炾�B �@�Z�\����̂��߂ɐ��k���������������肩�A���̗����x���Ȃ��c�����C����ɒǂ����Ƃ����������N�\�j���A�i�E�j�E�V�����Y�͈��|�I�ȑ��݊��ʼn����Ă���B�A�J�f�~�[�����j�D�܃m�~�l�[�g�����R�̉��������A���{�̉^�������o�������҂����ɂƂ��ẮA���Ɍ����ꂽ�l�����������肵�āB�u�O�b�h�E�W���u�i��o�����j�v�Ȃ�ĊÂ�����낢�_�ߌ��t�������Ă����璴�ꗬ�͐��܂�Ȃ��B����Ȕނ̌��t�ɂ͈�ʂ̐^�����܂܂�Ă��邾���ɁA���Ղȕ]���������Ȃ����G�ȃL�����N�^�[�ł͂���B �@�Ƃ͂������̓j�[�}���̕ϖe�Ԃ�̕��ɁA���S�����ꂽ�B�{���͎��������͂�D�悷��^�C�v�������j�[�}�����A�t���b�`���[�ɉA���Ȏ�t�ґ������������邤���ɁA�l�����Ƃ��߂���A�R���Ƃ����肷�邱�Ƃ��C�ɂ��Ȃ��G�S�C�X�e�B�b�N�Ȑl�ԂɂȂ��Ă����B �@�܂��V���C�ȃi�C�X�K�C����������ɗE�C���ӂ���Đ����������K�[���t�����h�ɂ��A���̂킸���P�`�Q�T�Ԍ�Ƀj�[�}���͂����������B�u�N�Ɖ���Ă��Ă��h������o���h�̂��Ƃ���l���Ă��܂��B�N�͂����s���Ɏv���ċ�������{�����肷�邾�낤�B����ł͑���܂Ƃ��ɂȂ邩��A�l��͕ʂꂽ���������v �@���̎����̂��߂ɂ��ׂĂ��]���ɂ����j�[�}���́A�������t���b�`���[�̃p���n���w���Ŕj�łɒǂ�����A���Ƀu�`���B���ꂪ�N���]���́u�]�v�ɓ�����킯�����A��������u���v�Ɏ���܂ł̌o�܂ɁA�قƂ�ǂ̊ϋq�͗\�z���O����A���|����邾�낤�B �@�}�S�̃X�|�R�������q��f��Ƃ͈Ⴂ�A�{��ł́u�����ݍ������Q�l�̐S�����ɒʂ������v�Ȃ�ė\�蒲�a�͋N����Ȃ��B�j�[�}���ƃt���b�`���[�͑����݂ƃG�S���G�X�J���[�g�����Ă����A�����Ƌ����Ǝt�툤�ɂ���Ăł͂Ȃ��A�w������h���������ƂŎ����̖����ݏo���Ă����B�G���f�B���O������X���P�X�b�̉��t�V�[���́A���т��悤�ȋْ������B�t���b�`���[�͂P�l�̓V�˂𐢂ɑ���o�����̂��A����Ƃ��������ɕ������̂��H �@�j�[�}�����D�����Ɩ����A���͍D���ł͂Ȃ��Ɠ����邾�낤�B �@���ꗬ�̌|�p�Ƃ����ꗬ���肦�邽�߂̃G�S��F�߂邩�Ɩ����A���͕ԓ��ɋ�����B �@���������Ȃ��Ƃ��j�[�}�����f�e�Ɍ��������t�́A���̓��e�ɂ����Ă��A�����ޏ��ɗ����ɍ������Ƃ����s�ׂɂ����Ă������������B�}�C�z�[���p�p�͒��ꗬ�̐E�Ɛl�ɂ͂Ȃ�Ȃ��̂��B �@���̂n�k�����͍����A�j�[�}���قǂ̗������������Ȃ��x���`���[��Ƃ̌o�c�҂̑�@��ʼn��ʕv�w�������Ă���̂��낤���B����Ƃ����܂ł����Ă���̏o�Ȃ������Ƃ̗����A�p�[�g�ŗ{���Ă���̂��낤���B �i�Q�O�P�T�D�Q�D�Q�P�D�L�j �`���[���[�E�����f�J�C�@�ؗ�Ȃ閼��̔閧�@�@MORTDECAI �i�Q�O�P�T�N�A�āA�����F�Γc�q�j  �@���������p���M���̔��p�������f�J�C�i�W���j�[�E�f�b�v�j�A���s��q���A�C���[���E�A�h���[�݂����ɖ��f�̂Ȃ�Ȃ����̍ȃW���A���i�i�O�E�B�l�X�E�p���g���E�j�A�w�����ォ��W���A���i�ɍ���Ă�l�h�T�i���A���E�}�N���K�[�j�A�����f�J�C�Ɍ�����Ă�瀂���Ă�������s�����s���g�̐�ώ����i�|�[���E�x�^�j�[�j�B�������Ď�v�ȓo��l������ׂ������ŁA�܂�Ȃ��f��ɂȂ�Ȃ����Ƃ͌���ς݂ł���ˁB �@���͂��܂����r���߂͂���������ŁA���ȉƂȂ̂ɏ��D���B����ȃ����f�J�C���i�`�X�̉B���������S���̊G��ǂ��A�p���A���V�A�A�č����삯�܂��B���X�o�Ă���e���������A�ǂ����������ЂƕȂ��ӂ��Ȃ�����A���ŁA�X�g�[���[�͓�]�O�]�B���Ƃ��Č����Ȃ�w�I�[�X�e�B���E�p���[�Y�x���T���قǃ\�t�B�X�e�B�P�[�g���������̂ƁA�h�i���h�E�d�E�E�F�X�g���[�N�́u���}�����̃W�����Z�b�V�����v�ɉp�����������������̂𑫂��ĂQ�Ŋ���E�E�E���āA�������A�ʓ|���B�ʔ�������Ƃɂ����ς�I �@�f�b�v�ƃp���g���E�͕č��l�����A�ǂ�����ߋ��ɉ��x���p���l�ɕ����Ă��邩��A�p���a��͂���̕��B�Q�l�̋U�A�N�Z���g���Ă���ƁA�����̉p���l�ł���}�N���K�[�ƃx�^�j�[�̔����܂ł��R���ۂ��������Ă��邩��s�v�c�ł��B �@�č��l�ē̃f�r�b�h�E�R�[�v�́A�i���S�ł͉p���l�̔������o�J�ɂ��Ă���j�{���̊ϋq�Ɍ����āA�킴���a������������Ă���ƌ����B�f�b�v�Ƃ́w�V�[�N���b�g�E�B���h�E�x�ȗ��̊獇�킹�����A�f�b�v���肫�̉f��Ɏd���Ă��A�A���T���u���f��Ƃ��Ă܂Ƃ߂��̂��吳���B�ēƂ��T�X�y���X�f��̋r�{�ƂƂ��Ă̎d���������l�����A�R���f�B�̉��o�����܂�������ł��ˁB �@����̓L�����E�{���t�B���I���Ƃ�����Ƃ�������70�N��̃V���[�Y���Ƃ��B�����ŃX�g�[���[�̂��������Ɂu�̂ǂ����Ō����v�悤�Ȗ��킢���������B���{�ł͂��ăT�����I���ɂ���i�{��̌���ł͂Ȃ��G�s�\�[�h���j�P�������o�Ă����炵�����A���̉f��̌��J���@�ɃV���[�Y�̂S��i�����ׂĖ|��o�ł���Ă���B��������������Q�b�𒍕������Ƃ���ł��i�{��͑�P�b�j�B �@�f�b�v���g������w�ɖ���A�˂Ă��邱�Ƃ����A�f��̕��������L���X�g�ł��ЃV���[�Y�����Ăق����Ȃ��B �i�Q�O�P�T�D�T�D�P�W�D�L�j�@ �Q�O�P�S�N�i���́j�x�X�g�W�I �@�ߔN������Ƃ܂�����Ȃ����Ǝv���Ă��邱�Ƃ�����B����͉f��̃^�C�g���������ς�o�����Ȃ��Ȃ����^�o����C���Ȃ��Ȃ������ƁB�Ⴂ����ɂ͉��ł���A�o���悤�ƈӎ����Ȃ��Ă�����ɊC�n�ɋL������܂�����ˁB�Ƃ��낪���̂Ƃ���A�ӎ��I�Ɋo���悤�Ƃ��Ȃ����Ƃ͉��ЂƂ��ɍ��܂�Ȃ��B �@�f��̃^�C�g���Ɋւ��Ă������B�ǂ�ȂɊς����f��ł��u�o�D�������o�Ă��邠��v�Ƃ����F�����Ȃ��ꍇ�������Ȃ��Ă����B�����Č���̑����Ń`�P�b�g���u�Ԃ�����i����������A����Ŗ����͎���������B�l�b�g�\�������ꍇ�Ɏ����ẮA���ꂱ���u�o�D�������o�Ă��邠��v�̂܂܂Ń`�P�b�g�����Ă��܂��B �@���̂��߂��A�������ăx�X�g�P�O�Ȃ��������Ƃ��ĂP�N���̊ӏ܃��X�g�����Ԃ��ƁA�u����ȉf��A�ς��������H�v�ƃ|�J���Ƃ����Ⴄ��i��������������B���N�Ō����Ȃ�A���Ƃ��w���x���W�E�}�b�`�x�w���[���E�T�o�C�o�[�x�w�킽���͐����Ă�����x�w�E�B�[�N�G���h�̓p���Łx�w�t���C�g�E�Q�[���x�����肪�����������B�ʍ�Ȃ�Ƃ������A�w���[���E�T�o�C�o�[�x�̂悤�Ƀx�X�g�P�O�ɓ���Ă����������Ǝv����i�̃^�C�g�������Y��Ă���̂�����A�ǂ��ɂ����������̂ł���B �@�f�ڂ͗�N�ǂ���u�ǂ��������v�ł͂Ȃ��A�u�ӏ܂������v�ł��B��������{�y�[�W�Ɋ��z���A�b�v���Ă���̂ŁA���Q�Ƃ̂قǂ��B �i�ӏܑ����V�W�{�j �P�@�G���@�̍��� �Q�@����ł���͖����� �R�@�C���T�C�h�E���[�E�B���E�f�C���B�X�^�����Ȃ��j�̉� �S�@�m�A�@�̏M �T�@�P�[�v�^�E�� �U�@�t�����N �V�@�S�[���E�K�[�� �W�@�t���[���[ �i�Q�O�P�T�D�Q�D�P�R�D�L�j �NjL�i�Q�O�P�T�D�T�D�V�D�j �X�@�Ȃ���ĉƑ� ���J����P�T�J���x��łv�n�v�n�v�Ŋӏ܁B�����݂̂���E�F�����C�h�ȃR���f�B�ɔ��ΘA���������B �_�͎��̂��@�@GOD'S NOT DEAD �i�Q�O�P�S�N�A�āA�����F�H�j  �@�t�����X���u�V�������[�E�G�u�h�v�ւ̏P���������ӊO�ɑ傫�Ȕg����L���Ă���B�t�����X�S�y�Ŕ��e���W��ɎQ�������l�͂R�V�O���l�����Ƃ��B�p���̃f���ɂ͉��B�e���̎�]���Q�������B�����A�u�킽���̓V�������[�v���f���Q���҂̍������t�ɂȂ��Ă����̂ɂ͈�a�����������l�������l�q�B �@���Ƃ��P�^�P�Q�t���ǔ��V���ł́A���������w�҂̎���b�q���u���̕W��ɏ��Ȃ��l���u���Ă��ڂ�ɂ���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv����v�ƌ��A�l���w�҂̃G�}�j���G���E�g�b�h���u���A�t�����X�Ŕ�������w�e�����X�g�ɂ��݂���x�ƎƂ߂��A�܂������ɑ����v����u�t�����X�ł͎�ނɉ����Ă��Ȃ��v�Ƃ����B�v�͂�����Ƃ��u���l�̏@�����R�P�ɂ�������悭�Ȃ���v�Ƃ������ӌ��Ȃ�ł��ˁB �@�����̍l���ɂ͈��̌h�ӂ����ǁA���̈ӌ��͏����Ⴄ�B�����A���̃T�����[�}����V�l�A���w����|��Ƃ��R�P�ɂ���͈̂�������A�������Ƃ���Ȃ��ł���ˁB�ł��@���͕�����Ȃ��P�̌��Ђł���A���Ђ́i�����Ƃ�o�ϐl�Ɠ����悤�Ɂj���h�₩�炩���A�Ď���ᔻ�̑Ώۂɂ��Ă�����B�Ƃ������A�ނ���ϋɓI�ɂ���ׂ��Ȃ�B �@���������@���Ȃ�Ă��̂̑��݈Ӌ`��F�߂���̂́\�\�����l���������\�\�u�_�l������v�ƐM���邱�ƂŁA�����������l�ɗD�����Ȃ��Ƃ��A�P�l�ł͎��ĂȂ��E�C�����Ă�Ƃ��A�������v���Ƃǂ܂��Ƃ������|�W�e�B�u�Ȍ��ʂ����҂����ꍇ�݂̂��B���l������߂�Ɩ�������A�M�҂�ɂ߂��ĐM�S�������悤�Ȑ_�l��������A����Ȃ��͎̂E���Ă��܂������������B���͊�{�I�ɁA�_�l���@�����M���l�Ԃ̐�����K���ɂ͂܂������K�v�̂Ȃ����̂��Ǝv���B �E�E�E�ƁA�����N���ɂ�����ʼnf��]�Ɉڂ낤�B�w�_�͎��̂��x�͖��炩�ɃL���X�g���E�h���o���E���삵���v���p�K���_�f��ł���B����͎����Ό����炻�������̂ł͂Ȃ��A�f��̍��莩�g������������|�̎������o���Ă���i�v���p�K���_�Ƃ������t�͂������g���Ă͂��Ȃ�����ǁj�B �@���_�_�̓N�w��������u�_�͎��v�Ǝ��ɏ����悤���v���ꂽ�N���X�`�����̊w���W���V���́A��������ۂ������ʁA�����Ő_�̑��݂�_����悤�����āE�E�E�B �@�r�b�O�o���̗��_�Ƒn���L�̋L�q�����Ă���̂͏�X�w�E�����Ƃ���ŁA�W���V�������̂�������Ƃ�������ɍŏ��͂��������Ƙ_�ɂ�����B�����ƃW���V���̂R��̑Ό���ʂ��Č����̂́A�Í��̂��܂��܂ȗL�_�_�Ɩ��_�_�̃_�C�W�F�X�g�B�r�{�Ƃ������������ɂ悭���_�������Ă܂��ˁB �@�������Ō�ɂ́u�_�͎��݂���v�Ƃ��������Ȍ��_�Ɏ������ނ킯�����A�ꌏ���W�Ɍ������o��l�����ǂ����ł�����ƂȂ����Ă���Q�����̃X�^�C���������ꂽ��A�W���V�����_�̑��݂��g���h���Ă݂���N���C�}�b�N�X�ł͍ٔ����̎�@���ؗp���ċ�������肱�߂���ƁA�����̃g���f���f��Ƃ͈�����悷��i�ɂȂ��Ă���B �@����ł��@����ے肷�鋤�Y��`������̗��w�����_�̑��݂�M����������A�C�X�������k�̏������Ȃ����L���X�g���ɋA�˂���������肷��̂�����A�܂��A���Ȃ莆��d�́u����v�ł͂���܂����B �@�`���Ɂu�@���͌��Ђ��v�Ə��������ǁA�{��ł͖��_�_�̋��������Ђ̑��ɗ����Ă��āA�u�_�����ƔF�߂Ȃ��ƒP�ʂ����Ȃ���v�ƃp���n�����d�|����B�Ƃ��낪���X�g�V�[���ł͗��ꂪ�t�]�B���̂ŕm���̋����́A�����킹���q�t����u�_�ɂ������Ĉ��炩�ɂ������Ȃ����i���_�̑��݂�F�߂Ȃ��ƓV���ɍs���Ȃ���j�v�ƌ���ꂿ�Ⴄ�̂ł���B������ċ��ɂ̃p���n������ˁB �@�ł����A�V���Ȃ�Ă��Ԃ�Ȃ���B�l�͎���y�Ɋ҂邾���B���_�⍰�Ȃ�āA�]���̉��w������d�C�M���������z�ɉ߂��Ȃ��B����͂���ő������̂��Ǝv�����ǁA�]���������~�߂�ΐ��_�����ł��邾�낤�B �@������v���ƁA����Ȃ�ĉ��̕K�v�������ł��傤�ˁB�y������Ȃ�u��̂߂�ꏊ�v�Ƃ��Ă̕�͕K�v��������Ȃ����A�Α����嗬�̂��̍��ł͂�������Ӌ`�͂Ȃ��B�̐l�͈₳�ꂽ�҂̐S�̒��Ɂi�P�j�����Ă��邩�i�Q�j���Ȃ����̂ǂ��炩���B�i�P�j�Ȃ炱�Ƃ���ɋ��{�̂��߂̏��݂���K�v�͂Ȃ����A�i�Q�j�Ȃ�Ȃ�����K�v�Ȃ��ł��傤�B �@�������łɂ́A��ǂ��납��D���W�߂Ă����Ȃ��Ă��܂�Ȃ��Ȃ��B���ȂE������A�u���ꏊ�ɍ����ĕ�����́A�U�����낾�̂Ƃ����������ɂȂ�B�Α���̌W������ɎY�Ɣp�����Ƃ��ď������Ă��炦�Ώ\������B �i�Q�O�P�T�D�P�D�P�T�D�L�j �U�˂̃{�N���A��l�ɂȂ�܂ŁB�@�@BOYHOOD �i�Q�O�P�S�N�A�āA�����F��c���T���j  �@��N�P�P��������{���J����Ă������̉f��B���炷����ǂ�ł����܂�ʔ���������Ȃ����A�P�U�T���Ƃ�����f���Ԃ��������邵�ŁA�ς�̂̓p�X���悤�Ǝv���Ă����̂����A�S�[���f���O���[�u�܂�����Ă��܂������̂�����A�������A�ςȂ��킯�ɂ͂����Ȃ��Ȃ����B �@���`���[�h�E�����N���[�^�[�ē��A�ŏ��͂U���������N����l���ɁA�����L���X�g�łP�Q�N�����ď������B��i�߂��h���}�Ȃ̂����E�E�E�B �@���ɂ����͂Ȃ������̂��ȁH�Ƃ����̂�����ہB�P�Q�N�����ĎB�����Ƃ����������A�h���}��`���邽�߂̎�i�ł͂Ȃ��A���ȖړI�����Ă��܂��Ă���B��ʓI�ȉf��ł͔N��̈Ⴄ�q�����g���ĂP�l�̓o��l���̐�����`�����A�Ȃ�����ł͂����Ȃ������̂��A�Ȃ������N���[�^�[���{��̎�@���̗p�����̂����ǂ��ɂ��͂�����`����Ă��Ȃ��B�����̃R�P�̈�O���A�������̓A�C�f�A�|�ꂾ�����̂��H �@�X�[����V�j���b�N�̓_�`�������A�u�������Ȃ��B�悭�c��Ȏ��Ԃ������Ă��ꂾ���̂��̂�`������Ȃ��v�Ƃ͎v�����ǁA��������đ��̋Z�@�̊G���D��Ă���Ƃ͊����܂����ˁB�{����ςāA��������Ɏ������z���o�����͎̂��������낤���B �@�������Ȃ̂́A�G�s�\�[�h�̃h���}�������܂�ɔ������ƁB�����z���ɕ�e�̍č��A�����V�̕��e�Ƃ̌𗬂ɁA�w�Z�ł̌�F�B�ʔ��������ł������ȗv�f�͂��낢��Ɛ��肱�܂�Ă���̂ɁA�����N���[�^�[�͂��Ƃ���ɋ���������킹����h�L�h�L�����悤�Ƃ����肹���A�\�ʂ��Ȃł邾���Œʂ�߂��Ă����B���ǁA��Ԏ��̓��Ɏc�����̂́u�Ƒ����Ėʓ|���������̂���ˁv�Ƃ����g���ӂ����Ȃ����S�������B �@����Ȃ疈�N�B�e���Ȃ��ŁA�R�N�Ȃ�T�N�Ȃ�Ԋu���A�X�̃G�s�\�[�h�������ƌ@�艺���������悩�����̂ł́B �@���������t�����X�f��́w�ڂ��Z�U�[�� �P�O�Δ� �P���R�X�����x(03)�́A����Ȏ�@�łT�N���Ƃɑ��҂������Ƃ����G�ꂱ�݂������͂������A���ǒP���ŏI����Ă��܂����悤���B�\�t�B�X�e�B�P�[�g���ꂽ�y�����R���f�B�����������Ɏc�O�B �i�Q�O�P�T�D�P�D�P�T�D�L�j �`�m�m�h�d�^�A�j�[�@�@ANNIE �i�Q�O�P�S�N�A�āA�����F�Γc�q�j  �w�U�E�C���^�r���[�x�ς����Ȃ��B�\���̎��R����邽�߂���Ȃ��B�W�F�[���Y�E�t�����R�ƃZ�X�E���[�Q���̂��o�J�f�悾����ς����B �@�k���N����l���Ȃ����Ƃ����Ȃ���A�R�T�Ԃ��炢�S�ăg�b�v�P�O�ɓ����Ă�����ƖY���ꂿ�Ⴄ���x�̉f�悾�����Ǝv�����A����Ȃ����u��`�v�����ꂽ��\�j�[�Ƃ��Ă��ɂ��y�����낤�B �u���J���~�͌�肾�����v�ƃ\�j�[��ᔻ�����I�o�}����́A����Ŗ{���Ƀe�����N������ǂ��������Ȃ̂��낤�B�č��̑哝�̂́u���R����邽�߂Ȃ瑽���̋]���͊Îׂ����v�ƌ�����̂�����H�@���f�B�A���u���������f����ςɂ����ȏ�́A�e���ɑ����Ă��ϋq�̎��ȐӔC���v�ƁA�I�o�}��i�삷��̂�����H�@�ǂ�������{�ł͂ƂĂ��l�����Ȃ����B �@���̃\�j�[����������Q�e�Ɍ��J����̂��A�����u���[�h�E�F�C�E�~���[�W�J���̂Q�x�ڂ̉f�扻��i�w�`�m�m�h�d�^�A�j�[�x�B����ł͓��{�ł����N�̂悤�ɏ㉉����Ă��邩��A���q�����A��Ă����������������낤�B �@���\�ȗ��e�Ɉ�Ă��Ă���P�O�̌ǎ��A�j�[�́A�ӂƂ������Ƃ���h�s���҂̃X�^�b�N�X�ƒm�荇���A�s���I�ł̎x�����A�b�v��_���ނɈ�������邱�ƂɁE�E�E�B �@���������ƕ���ł̍L�������邽�тɁA�q���C���̃r�W���A�����������_�T���ƃ}�C�i�X�C���[�W������Ă����̂����A�f��ł��ςĔF�������߂��B���₢��A�y�����~���[�W�J���ł���A����B �@�L���ȁu�g�D�����[�v���͂��߁A���邢�Ȃ��Ȃ��Ȃ����ꂼ��ɑf�G�B�ǎ��������|�������Ȃ���x��p�ɂ͎v�킸�݂����ڂ�邵�A�}���n�b�^���̊X�H��ɂ�����Q���͂��ꂼ�U�b�c�E�G���^�[�e�C�����g�Ƃ�������B �@�ړ_�̂Ȃ��������Ȑ��̑�������ƕn�����ǎ����A������̉��ŕ�炷�������J����݁E�E�E�Ƃ����A���v�X�̏����I�Ȃ��Ƃ��b���A���͌����Č�������Ȃ��B���̒��ɂ͐����w�I�ɂƂĂ��s���R�Ȉ�Â��g���āu�䂪�q�v�������낤�Ƃ���l�X�����邯��ǁA�{�q�����炤�Ƃ����I�������ł���Ό������Ăق������́B�S���e�n�̎����{��{�݂ɂ́A����Ȃ��Ȃ���҂��Ă���q�ǂ��������吨���܂��i���͌��������Ȃ̂ŁA�{�݂̕�炵�������Ђǂ��͂Ȃ��ƐM���Ă��邯��ǁj�B �@����ł�W�Q�N�̃W�����E�q���[�X�g���łƂ̍ő�̈Ⴂ�́A�q���C���Ƒ�������̃L�������A�t���J�n�ɕύX���ꂽ���ƁB�A�j�[���̃N���x���W���l�E�E�H���X�ƁA�X�^�b�N�X���̃W�F�C�~�[�E�t�H�b�N�X�́A���Ɉ��肵���̂ƃ_���X���I����B �@�r�b�`�ȗ��e���̃L���������E�f�B�A�X�ƁA�X�^�b�N�X�̔鏑���̃��[�Y�E�o�[�������R���f�B�G���k�Ԃ��������Ĕ����B�n���E�b�h�̉f���Ƃ͓��{�́u���q�v�Ȃ�ĊT�O�͒m��Ȃ��͂������A�o�[���̃L�����͕�����Ȃ����q�������B �@����ݒ���P�X�R�O�N��̑勰�Q������A����̘b�ւƏĂ������ꂽ�B�Q�O�O�S�N�́w�Z�����[�x�ł́u���������A�g�ѓd�b�œ��悪�����̂���v�Ƃ������x���ŋ��������̂����A���̂P�O�N�ԂŋZ�p�͂���ɒ����̐i���B�r�m�r���X�g�[���[�̃J�M�������Ă���B �@����N�������̔��M�҂ɂȂ鎞��B�L���l�͂ǂ��ɍs���Ă��f�l�̃X�}�z�́g����h�ɂ��炳��A�摜���łr�m�r�ɃA�b�v�����B�w�S�[���E�K�[���x�ł͂��ꂪ����̕a���̂P�Ƃ��ĕ`����Ă������A�X�}�z���[�J�[�̃\�j�[������E�z������{��͂r�m�r�ɂ��m��I���B �@���Ƃ��X�^�b�N�X���A�j�[��I����̐�D�ɂ��悤�ƍl�����̂��A���܂��ܔޏ������������Ƃ��P�s�Ƃ��ă��[�`���[�u�ɃA�b�v���ꂽ����B�q���C�����f�v�����I�Ղł́A�ǎ����Ԃ����X�ƃc�C�b�^�[�ɃA�b�v�����摜��ǂ��āA�A�j�[�̋��ꏊ��˂��Ƃ߂Ă����B�����E�E�E�B �@�����܂��A�h�s���s�̎����猩��A�ǂ���{���ɂ������ł���B�ł��{���ɕK�v���ƌ����A���[�`���[�u���c�C�b�^�[���\�\���������X�}�z���\�\���炸�����Ȃ��B �@�������~�߂ēd�C������Ȃ��Ƃ����̂Ȃ�A������Ȃ��r�m�r��X�}�z�Q�[����S���@�������Ⴆ������ˁB�ŁA���̕��̓d�C�ō���n�т̐���������A�ቺ�낵���̎��̂��h����B�Q�[���J����Ђœ����Ă���D�G�Ȃh�s�L�b�Y�������A���̍˔\�������ƗL�Ӌ`�Ȃ��ƂɌ�����Ⴀ��܂����B���Ƃ��A�C���X�I�[���}������ʼn����p�Z��@���J������Ƃ��E�E�E�B �i�Q�O�P�S�D�P�Q�D�Q�V�D�L�j �t���[���[�@�@FURY �i�Q�O�P�S�N�A�p�A�����F���Y���ށj  �@���̂Ƃ�����ɂ����d���𑱂��Ă���f�r�b�h�E�G�A�[�ē��A�u���b�h�E�s�b�g���剉�Ɍ}���đ��햖���̉��B�����`�����l�ԃh���}�B �@�E�H�[�_�f�B�[�i�s�b�g�j���������Ԃɔz�����ꂽ�V���m�[�}���i���[�K���E���[�}���j�́A���̋Ɍ��Ƀp�j�b�N���N�������E�E�E�B �@���͎��q���̑��q�̂��ɕ�����L�ɂ������������������Ȃ������̂ŁA���̉f��ŏ��߂Đ�Ԑ�̏ڍׂ�m���ĉ��x���u�ց[�v�Ƌ������B �@�܂��͐�Ԃɂ���ȂɊJ�����i�n�b�`�j�������Ƃ͒m��Ȃ������B�^���b�g�i��]�C���j�̏�ɂ����P�ӏ��������Ǝv������A���͂T�ӏ����U�ӏ��������ł��ˁB �@����ɓx�̂��ꂽ�̂́A�@�e�e��ΐ�ԖC���т��т���т������ŁA�e��Ԃ̎w�������n�b�`����㔼�g���o�����܂ܐ���Ă������ƁB���ꂶ�ᖽ�����������Ă�����Ȃ��ł���B�A���}�W���݂����Ɏԓ��ɂ������Č�킷���Ȃ������̂��H �@�ΐ�ԖC��H����ă^���b�g�������Ƃ����������Ԃ̃r�W���A�����������B�܂�Ŏa�B���b���т�����ȖC�e������悤�ŁA��Ԃ����G�ł͂Ȃ���ł��ˁB �@�@�e����������g���e���N�����B��Ԃ̏ꍇ�͎����̈ʒu�����炷�f�����b�g���A�Ə����C�����₷���Ȃ郁���b�g�̂ق������킯���B�w�v���C�x�[�g�E���C�A���x�̖`���ŕ`���ꂽ�u�������т��e�e�v�̃V���b�g�ɂ��C�G����Ռ��������B �@�r�{�����˂��G�A�[�ḗA���ꂢ���Ƃł͂��܂Ȃ����̋��낵���A�X��������ł����Ɗ��ʂ���B�N�[�������Ȃ��i�`�X�E���[�Q���g�̎q�ǂ��������ČR��Ԃ�����܂ɂ���V�[���ȂǁA����܂ł̐푈�f��ł͌������Ƃ��Ȃ������B �@�������탁�b�Z�[�W��`����ɂ��Ă��A���{�̉f���ƂȂ��Q�҈ӎ������ς��̃G�s�\�[�h�荞�ނƂ��낾�낤���A�G�A�[�̓u���s���͂��߂Ƃ���ĕ��ɂ����������Ȏc�s�s�ׂ��������ˁB�������グ�ē��~���Ă����h�C�c�����ˎE����B�G���̈�̂���r���v������������܂߂ɒD���i�Ƃ��������ށj�B�W���l�[�u�����������������̂���Ȃ��B�������l�L���X�g���k�̃h�C�c���ɑ��Ă��������Ȃ̂�����A�����m����Ŕs�����鎄�����̑c���������ǂ�Ȗڂɑ��킳�ꂽ�̂��z���ł��悤�Ƃ������̂��B �@������݂��l�������̂��낤����A�ČR������ᔻ����͕̂s�����낤�B�P������̂͐푈�Ƃ͐l�Ԑ���D�����̂��Ƃ������ƁB�����Ĉ�x�n�߂Ă��܂��A�s���̗��D�A���C�v�A���Y�A�s�E���|���āA�����ł����Ƃ���Ȃ�����~���ł��Ȃ��Ƃ������ƁB �@�{��͐푈�����̘b������A�u���s�̏㊯�Ȃǂ́u�h�C�c�R�߁A�Ȃ�����Ȃ�~�����Ȃ��H�v�ƃ{�����̂����A����ɑ��ău���s�́u���Ȃ��Ȃ炵�܂����H�v�Ɣ��₷��B�ނ͗��ꂪ�t�ł��~�����Ȃ��B�{�y�ʍӂ������{�l�����Ԃ��Ȃ��B�������������̌R����{��������A�y�X�ɔᔻ������͂ł��Ȃ����낤�B�č��̐�̐���r�I�a�m�I�������̂́A�����̌��ʘ_�ɉ߂��Ȃ��B���̓_�ł͐��\���l���V�x���A�ɗ}�������\�A�̑Ή��̂ق����A�����炭���E�W���ɋ߂������B �@����ȋ��낵�����ϋq�ɂȂ肩����đ̌�����̂��A���[�K���E���[�}�������鎖�����̐V�����B�ނ͖`���A�u���s�̖��߂Ŗ���R�̓G�����ˎE��������B�u����Ȃ��Ƃ������邭�炢�Ȃ�A�������l���E���Ă���I�v�Ƒi�����ނ��A����������Ɋ��o�i�Ƃ������l�Ԑ��j��ݖ������Ă����B�ނ̖𖼂��u���ʂ̐l�v�u�N�ł��Ȃ��l�v��A�z������m�[�}���������̂͏ے��I���B�m�[�}���͂����P�l�̎��A�P�O�N��̂��Ȃ���������Ȃ��B �@�h�C�c�̂��钬���ח��������ĕ������̖T�ᖳ�l�Ԃ�ɂ��C���`�ȋC���ɂ�����ꂽ�B�ϋq�̊���ړ�����ׂ��u���s�ƃm�[�}�����A���Q�l�̉Ƃɉ䂪����œ��肱�ށB�u���s����u���O�������Ȃ��Ȃ牴�����b���܂����v�ƌ���ꂽ�m�[�}���́A�u����Ȃ��Ƃ������Ȃ��v�Ƃł������̂��Ǝv������A���ɕ��C�ł��̉Ƃ̖��ƐQ���Ⴄ��ˁB���������A�E���ɂ͒�R�����Ă����C�v����̂͂n�j�Ȃ̂���B �@�p������̐}�ƍ������Ă͂����Ȃ��B����͎����������u�S�{�ĉp�v�Ƌ���A����ł���h�C�c�l���B�m�[�}���̏ꍇ���`���I�ɂ͋^�������̑̍ق�����Ă͂������i�M�d�ȗ��≌��������Ă���Ă͂������j�A�������Ƃ��ď����̑��ɋ��ނƂ����I�����͂Ȃ������͂����B�č��̒n���c���A���炪���{�R�̏]�R�Ԉ��w��ᔻ�ł���̂��H �@�N���C�}�b�N�X�͌̏Ⴕ����ԂP���łR�O�O�l�̓ƕ��Ɛ키�X�C�T�C�h�E�~�b�V�������B�w�����̃u���s�Ɂu�ǂ����ɉB��Ă��Ă������v�ƌ���ꂽ�̂ɁA�S�l�̕����͒N�ЂƂ蓦���Ȃ��B�ŏ��͘Q�Ԑ߂��Ǝv��������ǁA�퓬���n�܂��Ă݂�Ȃ�قǁu�ǂ����ɉB��āv������悤�ȏ���Ȃ������B �@�ނ�͂���\���H�����点��Ɩ������Ă����̂����A���ǂ͎�肫��Ȃ������B����Ȃ̂́A���ꂪ���������ŕČR���P�ށE�E�E�Ƃ������ƂɂȂ�̂��Ǝv������A��閾�����炠������F�R������Ă������ƁB��������Ȃ��������ŏ\���H����炳�ꂽ�̂��B����ɂ��ẮA�ŏ��͋r�{�̌����Ǝv�������ǁA���ł͏����Ⴄ���z�������Ă���B�����炭�푈�Ƃ́A�������s�𗝂Ȃ��̂Ȃ̂��B �@���āA���̍�i�A�����ł͐��ɓ������܂ꂽ�l�Ԃ̏X���⋰�낵����`���Ă��āA���ɔ���I�������ƌ����Ă����B�Ƃ��낪�X�g�[���[�̏c���̕����ł́A�m�[�}�������m�Ƃ��Ă�������������ɂȂ��Ă����ˁB�낭�ɐl���E�����Ƃ��ł��Ȃ��������������A�t�@�b�N�E���[�Ƌ��тȂ���G�����@�e�|�˂ł���悤�ɂȂ�܂����B����q���āA���Ԃ�����悤�ɂȂ�܂����B�p�`�p�`�p�`�A�ƁB �@�v���w�v���C�x�[�g�E���C�A���x�ł́A�W�F���~�[�E�f�[�r�X������C���e�����m���A�m�[�}�����l�ɑO���̌����ɐG��ċꂵ�B�ނ��Ō�ɕ������P���̏e�e�̋�X������z�N����ɂ��A�m�[�}�����Ō�Ɍ}���������͂��������Â����ɉ߂����悤�ɂ��v����B���̒��q���ƁA�i���ꂾ���̏C��������������ɂ�������炸�j�ނ͂����炭�u�L�ɂȂ肽���v�Ƃ͎v��Ȃ����낤�B �i�Q�O�P�S�D�P�Q�D�Q�V�D�L�j �S�[���E�K�[���@�@GONE GIRL �i�Q�O�P�S�N�A�āA�����F���Y���ށj  �@�����O�ɂ͗��ڂ��J���Ă悭�悭���������߂�B����������t�ɕЖڂ���Ă����B����Ȍ��t�������ΐl�����Y�t���邯��ǁE�E�E�B �@�j�b�N�i�x���E�A�t���b�N�j�̍Ȃ̃G�C�~�[�i���U�����h�E�p�C�N�j���T�N�ڂ̌����L�O���Ɏ���玸�H�B����̗l�q�͉��҂��ɘA�ꋎ��ꂽ�悤�ɂ����������A�x�@�͎���Ƀj�b�N�ɋ^���̖ڂ������Ă����B���f�B�A�͋����{�ʂɃj�b�N�ւ̐l�i�U���܂Ŏn�߁E�E�E�B �@�Ƃ������Ղ������ēW�J���ǂ݂������Ȃ��́A���Ԃ�\�z�𗠐���B�{�삪�����o���̂́A���e��v�������m�炸�ɂ����G�C�~�[�̒�m��ʐS�̈ł����炩�ɂ���Ă��炾�B��i�̐�����A���܂�ڂ����������킯�ɂ͂����Ȃ����A�ق�A����t���́u�m���E�F�C�̐X�v�Ƀs�A�m���t���Y�_�{���ɂ����T�C�R�������o�Ă��܂�����ˁB�G�C�~�[�����傤�ǂ���ȋ�ɗ��ȓI�ŁA���l�𑀂邱�Ƃɒ����Ă���B���܂��Ɉ����̂悤�ɓ��������B �@�n���ɕ����Ȃ��͔̂ޏ�����ʓI�ȈӖ��ł́u�����v�ł͂Ȃ����Ƃ��B�����Ȃ�P���̊ϔO�������Ă���B�������Ƃ��Ƃ킩������ŁA�����Ĉ������Ă���B�w�|���]���x�̃A���W�F���[�i�E�W�����[�������������B�A���g�j�I�E�o���f���X�����炵���̂͊��S�ɋ��ړ��Ă��B�����w�|���]���x�̌��l�^�ł���w�Â��Ȃ�܂ł��̗����x�̃J�g���[�k�E�h�k�[�u�́A�������������Ă���Ƃ������o�͂܂����������Ă��Ȃ������B�����S�̂܂܂ɐU�镑�����ƂŁA���͂̒j������j�łɓ������̂��B��O�҂Ƃ��Ē��߂Ă��āA�ǂ��炪��苰�낵�����͖��炩���낤�B �@�{��̃G�C�~�[�̏ꍇ���A�S�ɂ���͎̂���̋��h�S�ƁA����Ȃ��҂ւ̗��₩�ȓ{�肾���B�u�����v����̉��l��ł���Ȃ�A����ɋt�炤���͂̃o�J�ǂ�����̂́u�����v�ł͂Ȃ��킯���B�Q���ԂQ�X���̒���ȍ�i�����I���鍠�ɂ́A�����������́g���r�b�`�h�̓ŋC�ɓ��Ă��A�������Ղ��Ă���͂����B �@���U�����h�E�p�C�N�Ƃ����p���l���D�́A���������Ă͉������A����܂œY�����̂悤�Ȗ��������Ă��Ȃ������i�f��f�r���[���{���h�K�[���Ƃ����̂��ے��I���ȁj�B�Ƃ��낪�ē̃f�r�b�h�E�t�B���`���[�́A���[�X�E�E�B�U�[�X�v�[��������̎剉��z�肵�ĉf�扻�����l��������i�ł���ɂ�������炸�i����̓M���A���E�t�����̓��������j�A�����ď��獇�킹�̃p�C�N���N�p�����B���������ј\�s���̂悤�ɂ������Ȃ��͂Ȃ����A�C�O���f�B�A�̕]�͈����Ȃ��l�q�B�w�����h���X�̏��x�w�X�̔��x�w�댯�ȏ�x�Ƃ����������f��́A���ꂼ��̎剉���D�̑�\��ɂȂ��Ă��邪�A�{��͂ǂ����낤���B �@�����̖\�����o�����ɁA�G�C�~�[�͎���ւƕ������ǂ�B�Ȃ̖{����m��A���͂∤�̎������j�b�N�́A�u���̂܂܃E�\�Ōł߂����������𑱂������Ȃ̂��v�Ɩ₤���A����ɑ���G�C�~�[�̒Z���������{��̃L�����B�����҂̂��Ȃ��͐S�_���₷���낤���A�v�킸�����o�����낤���A����Ƃ��[�����Ȃ������낤���B �i�Q�O�P�S�D�P�P�D�W�D�L�j �C�R���C�U�[�@�@THE EQUALIZER �i�Q�O�P�S�N�A�āA�����F���Ԉ����j  �@�߂Ȃ��s����������Y��D���悤�Ƃ����Ƃ��A�ǂ�����Ƃ��Ȃ����`�̖���������āA���������ƈ��҂�������Ă����B�X�[�p�[�}����X�p�C�_�[�}���̂悤�ȃR�~�b�N�̐��E�Ȃ炻��������Ƃ͎v���̂����ǁE�E�E�B �@���o�[�g�E�}�b�R�[���i�f���[���E���V���g���j�̓z�[���Z���^�[�œ������Â��Ȓj�B���������Ƃ��ǍD�ȊW��ۂ��Ă��邪�A����E�Ԃ悤�ɌǓƂɕ�炵�A�[��̃J�t�F�Ŗ{��ǂށB �@���͂��̒j�A���b�h�`�̍H����Ő퓬�\�͂����Q�B�e���i�C�t�������������ɁA�g�߂ɂ�����̂œG���u�E�����Ⴄ��ł��ˁB���Ԃ�b�h�`�ł̓W�F�[�\���E�{�[���݂����Ȏd�������Ă����̂��낤�B �@���̃}�b�R�[�����[��̃J�t�F�Œm�荇�������w�e���[�i�N���G�E�O���[�X�E�����b�c�j�̋ꋫ�������˂āA�q���̃��V�A�E�}�t�B�A����|����̂�����̎n�܂�B�P�s�ɖڊo�߂��i�H�j�}�b�R�[���́A���܂�����Ȃ��̂ɊX���p�g���[��������A�݂����ߗ�����鈫���x���炵�߂��肵�n�߂�B����A���V�A�E�}�t�B�A�̌����߂́A���j�f�a�̃e�f�B�i�}�[�g���E�\�[�J�X�j��č��ɔh�����A�艺���F�E���ɂ����Ɛl��T�����邪�E�E�E�B �@���V���g���ƃA���g�����E�t�[�N�A�ē̃R���r�́w�g���[�j���O�f�C�x�ȗ��B����̃��V���g�������V�A�E�}�t�B�A�ɎE����鈫���x���������ăI�X�J�[����������Ƃ��v���ƁA�{��̐ݒ�͉���畡�G���B �@�A�N�V�����f��ł͂����ɖ��͓I�Ȉ����`�ł��邩���J�M�B���̓_�A�w�r�̂悤�Ȏ��X���Ń}�b�R�[���̐g��������o���A���X�ƒǂ��l�߂Ă����e�f�B�̃L�����͌��������������B �@����������Ă��l�^�炵�ɂ͓�����܂����A���̎�̉f��̎�l���͐�Ɏ��ȂȂ��B�}�b�R�[�����Ō�̓��V�A�E�}�t�B�A�̖{���n�ɏ�肱�݁A�{�X�L������|���B�Ƃ������A�E���B��������ɂ͌�q���吨����킯�ŁA�}�b�R�[���̋�������ɂ͎r�݁X���B���ɍ��ꂽ�f��Ȃ�A�����őu��������͂��B�ł��{��Ɋւ��ẮA���`��A�r�����炾���l���ւ̊���ړ�������Ă�����ȁB �@�X�̓����⑳���荇�������w�̂��߂Ɉꔧ�E���ł��邤���͂܂��悩�����B�����}�b�R�[���͐l�����͈̔͂��L���A���܂��ɂ̓C���^�[�l�b�g�ō��育�Ƃ��W����n���B�،͂炵�䎟�Y�ƈ���āu�������ɂ͊ւ��̂˂����Ɓv�ɂ����˂����ނ̂ł���B���܂��ɔނ͎ӗ炳����炸�A�ނ���e���[�ɂ͑��������Ă�����B���̓��@�͂������������H�@�P�ɐl���E�����������Ȃ̂��H �@��͂胊�A���Ȏ�l�����X�[�p�[�q�[���[��������ƁA�P���̋��e���C���������ƃR�~�b�N�f��Ƃ͈���Ă����ˁB�����炭����������l���������炱���A���A���ȃX�[�p�[�q�[���[���́w�L�b�N�E�A�X�x�̂悤�ȃp���f�B��i�ɂȂ肪���Ȃ̂��낤�B�u���`�v�͈�ؓ�ł͌��Ȃ��B���ǂ̂Ƃ���A�u�b�V���e�q���C���N�ɍU�߂��̂��u���`�v�̂��߂������킯�ŁB �i�Q�O�P�S�D�P�P�D�W�D�L�j �u�ǃh���v�Ɓu���ւ̒鉤�v �@���̍��̎�҂����̊Ԃł́A�u�ǃh���v������̃V�`���G�[�V�����ɂȂ��Ă���炵���B�ŋ߂ɂȂ��Ă��̂��Ƃ�m��A���͓V�n���Ђ�����Ԃ�قNj������B�����ėm��������ꂽ�҂ɂƂ��āA�ǃh���́u���̓o��l�����C���ȓz�ł��邱�Ƃ������L���v�����炾�B�����ŕǃh������z������Ƃ�����A����͒ʏ�A�q�[���[�ł͂Ȃ��A�e�\�E�����E�����n�̘e���Ȃ�ˁB �@���ꂪ�ǂ��łǂ��Ԉ���ē���̃V�`���G�[�V�����ɂȂ��Ă��܂����̂��B�l�C���悩�����ɂ���������ʂ��������̂�����H �@�Q�P���I�̏��q������A���Ⴂ�����Ί�l�j�ɂ���ȟT�������̐��Ɏ������܂ꂽ��A�{�f�B�Ɉꔭ�Ԃ����݂����Ȃ�Ȃ������H �@���{�l���āA���Â��ςȍ����ł���B  �@���~�x�݂ɒ��w���̉����q�̉Ƒ��Ɖ������A�w�z�b�g���[�h�x�̘b�����Ă����B�������A���w���Ƃ����̂͂��������f�悪�������N�����������ƁA�v�킸����R�炵�Ă��܂����i��p�̕��̈Ӗ��Łj�B �@�����N�ɂȂ������̖ڂɂ́A�\���҂����������ŃN�\������Ȃ��f��ł��邱�Ƃ͗e�Ղɑz���������ǂˁB �@�\���҂Ƃ����͈̂�ʂɁA�܂�Ȃ��f��ł����������ʔ������Ɍ����Ă��܂����́B���̗\���҂����Ă����w�\���������̂�����A�{�҂������ɂЂǂ����킩�낤�Ƃ������̂��B �@�ł��A�܂��A������B���w���ɂ͂܂��܂����Ԃʂɂ���]�T�������Ղ肠��B�������������g�A�u���{�f��͋㕪��Ђ܂�Ȃ��v�Ƃ����P���Ȏ����ɋC�Â����͎̂Љ�l�ɂȂ��Ă��炾�����B �@�ŋ߂͍��Z�������������邱�Ƃ����A�M����m��������ς����āA�ӏ܊��{���Ƃ����B����ł��܂Ɋ��Ⴂ���āu�ǃh���v���A�{�f�B�Ɉꔭ�H�炤�̂����ʂ���Ȃ��B�T�l�ɂP�l���炢�͋��L�������Ă����Ί�l���q�����邩������Ȃ����B 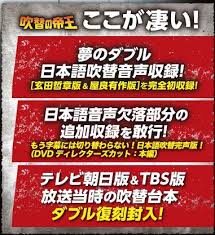 �@������Ǖ��ɂ��čŋߒm�����̂����A20���I�t�H�b�N�X �z�[�� �G���^�[�e�C�����g����u���ւ̒鉤�v�Ƒ肵���u���[���C�E�V���[�Y�������[�X����Ă���悤���B �@����܂łɁw�R�}���h�[�x�w�_�C�n�[�h�x�w�X�s�[�h�x�w�v���f�^�[�x�w���{�R�b�v�x�ȂǁA�f��j��Ɏc��l�C�삪��������Ă���B �@���łɉ��x���ς�������肶���E�E�E�ƕ���Ȃ���B���́u���ւ̒鉤�v�̔���́A�t�W�e���r�u�S�[���f���m�挀��v�A�e���r�����u���j�m�挀��v�A�s�a�r�u�U�E���[�h�V���[�v�ȂǂŃI���G�A���ꂽ�ۂ̐��֔ł��A�P�{�ɕ����i�I�j���^���Ă���_�ɂ���B �@���R�Ȃ����{���Ⴆ�ΐ��D���Ⴄ�B�����g�ɍ��킹�ăJ�b�g���ꂽ�������Ⴄ�B����ׂ�ƁA�܂�ŕʂ̉f��݂����Ɏv����ӏ�������Ƃ����B �@������̐���̐��֖|��҂͂����������������Ȏd�������Ă����l�������̂ŁA���ɂȂ��Ă���Ȍ`�ł��炵�҂ɂ����̂͂������f���Ǝv���Ă��邩������Ȃ��ȁB �@���������ƂɁA���̃V���[�Y�͋ƊE�̏펯���邭�炢�̔���s���������Ă���̂��Ƃ��B�����̐��֔ł�����ׁA������y�������Ƃ����l���A���ꂾ�������Ƃ������Ƃł��ˁB �@�����ǁA�ʂ��Ŋς���e�o�[�W�����̈Ⴂ�͂قƂ�ǂ킩��Ȃ��Ǝv�����B�{�C�Ŕ�r����Ƃ�����A��ʂ��Ƃɋ���ĕ����̐��։�������ׂȂ���Ȃ�Ȃ��B����Ȃ��������Ȃ��Ƃ�����t�@�����{���ɉ���l������̂��낤���H �@���{�l���āA���Â��ςȍ����ł���B �i�Q�O�P�S�D�X�D�Q�W�D�L�j �W���[�W�[�E�{�[�C�Y�@�@JERSEY BOYS �i�Q�O�P�S�N�A�āA�����F�Γc�q�j  �@�j���̗������ċC���������ł���ˁB�����܂�����X�R�����N�̉̂��Ă���ƁA���̂��тɁu�A�z����Ȃ����A�����́v�Ǝv�����Ⴄ�B�����o�Ȃ��Ȃ�A�L�[���������ƁB �@�Ƃ��낪���Ԃɂ͂��������y�Ȃ�]���������������悤�ŁA�r�[�W�[�Y�Ȃꎞ�͂��̂���������Ă����B�m�y�I���`�̎��̓o���h����m��Ȃ��������ǁA�u�V�F���[�v�̃t�H�[�E�V�[�Y���Y�����[�h�V���K�[�̃t�@���Z�b�g��ɂ��Ă�����ł��ˁB �w�W���[�W�[�E�{�[�C�Y�x�͂��̃t�H�[�E�V�[�Y���Y�̉h���ƕ����`�����W�c�`�L�f��B���y�ɑ��w�̐[���N�����g�E�C�[�X�g�E�b�h�ē��A�����̃u���[�h�E�F�C�E�~���[�W�J�����r�F�����B �@�ꌩ���Ċ������̂́A���̉f��͋q��I�Ԃ��낤�ȂƂ������ƁB�V���̔����̎����傾���P�l�ł͐��ɏo��ˊo�̂Ȃ������t�����L�[�A���n��͂��܂��������ȃg�~�[�A�����̑��݊��̔����ɕs�����点�Ă����j�b�N�A�R�l�Ƃ͏��������̂������{�u�ƁA�m���ɂS�l�̃����o�[�̌��ƊW���͉A�e�L���ɕ`�����܂�Ă���B�ނ�̗F��ƕs�a��Ԃ����܁X�̃G�s�\�[�h�������[���B �@�����A���̋����[����^�ɖ��키���Ƃ��ł���̂́A�t�H�[�E�V�[�Y���Y�̃����o�[�₻�̕ϓ]�����A���^�C���ɒm���Ă����A�č��̃x�r�[�u�[�}�[����Ɍ���ꂻ�����B�x�r�[�u�[�}�[����ł���A�����̒m��t�H�[�E�V�[�Y���Y�Ƃ��̉f��̃t�H�[�E�V�[�Y���Y�Ƃ̈�v��M���b�v���y���݁A����������ӊO���ɐZ�邱�Ƃ��ł��邾�낤�B�f��̊y���ݕ������w�I�Ȃ�ł��ˁB �@����ɑ��āA�t�H�[�E�V�[�Y���Y�����A���^�C���Œm��Ȃ��i���邢�́A�t�H�[�E�V�[�Y���Y���܂������m��Ȃ��j���{�̊ϋq�́A���̉f����A���ꎩ�̂Ƃ��Ċӏ܂��邵���Ȃ��B�u�ʐ��v��m��Ȃ��l�ԂɂƂ��Ắu��b�v�����ĂȂ�����A�y���ݕ����P�w�I�ɂȂ炴��Ȃ��̂ł���B �@����ɉ����āA�C�[�X�g�E�b�h�ē͕���ł̃L���X�g�����̂܂܋N�p�����B�܂�͉f��E�ł͖����̔o�D�������B�����ʼn̂킹�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������炻���Ȃ����̂�������Ȃ����A�f��Ƃ��Ẳɂ����邱�Ƃ͔ۂ߂Ȃ��B �@�S�l�̃����o�[���������i���[�^�[�Ƃ��ăJ�����Ɍ�肩���Ă��鉉�o���A����Ȃ��a���͂Ȃ���������Ȃ����A�f�悾�ƃ��A���e�B�����Ȃ���B �@����ɉ����A�U�O�N��̃o���h������y�Ȃ���������Ȃ��B�S�l�̃����o�[�i�{�[�J���A�x�[�X�A�M�^�[�A�L�[�{�[�h�j�����낢�̃X�e�b�v�݂Ȃ��牉�t����X�^�C�����A���̖ڂŌ���ƃ_�T�����Ƃ��̂����Ȃ��B�t�H�[�E�V�[�Y���Y���Ė{���ɂ���Ȃ��Ƃ��Ă����̂�����A����Ƃ�����͕���ł̉��o�Ȃ̂�����H �@���łɌ����A�t�����L�[���g�V���̗����h�Łu�A�C���C���`�C�v�ȂǂƉ̂��̂͂���ς�s�C���B�����o�Ȃ��Ȃ�A�L�[�������Ă���`�I �i�Q�O�P�S�D�X�D�Q�W�D�L�j �t�����N�@�@FRANK �i�Q�O�P�S�N�A�p���A�C�������h�A�����F�H�j  �@��̎ʐ^�Ńf�J���}�X�N�����Ԃ��Ă���̂��A�Ȃ�ƃ}�C�P���E�t�@�X�x���_�[���B�ނ�����ɋN�p���Ȃ���A���j�[�E�A�u���n���\���ē͍Ō�̐��������u��o���v�������Ȃ������B �@�~���[�W�V�����Ƃ��Đ�������̂����������W�����i�h�[�i���E�O���[�\���j�́A���܂��ܒ��ɗ����C���f�B�[�Y�o���h�ɂЂ��Ȃ��Ƃ����������B�Ў����}�X�N�����Ȃ����[�_�[�̃t�����N�i�t�@�X�x���_�[�j�ɖʐH�炢�A�o���h�����o�[�Ƃ̓˂��ʂ��������������������胆�[�`���[�u�ɓ��e����W�����B�₪�ē���͔������ĂсA����t�F�X�ɏo���ł��邱�ƂɂȂ�̂����A�W�����̌����S�Ƃ͗����Ƀo���h�i�ƃt�����N�̗����j�͕���Ɍ������E�E�E�B �@�V�����[�𗁂т�Ƃ��ɂ̓}�X�N���G��Ȃ��悤�Ƀr�j�[���܂����Ԃ��A�H���͗��������X�g���[�ŋz���B����ȃt�����N�̐l�����������ِF�����A���������킩���Ă���͔̂ނ����_��a��ł��邱�ƁB �@�����Ɉ����������Ă��܂��l�͑吨���邪�A�ނ̏ꍇ�̓}�X�N�Ɉ����������Ă����ł��ˁB�\��̍�����}�X�N����邱�Ƃ��ł����ɂ���̂Ɂi�A�b�v�ɂȂ�ƃ}�X�N�ɕ�C�̂��Ƃ��������肵�Č|���ׂ����I�j�A��������Ԃ��Ă������͐l�O�ʼn̂����Ƃ����C�B����ǂ��납��l�ɂ͂���т̂��Ȃ����y��������B �@��͂�ʉ@���̂���}�l�[�W���[���͂��߁A�ϐl���낢�̃����o�[�ƍs�������ɂ��Ă��邠�����͎��Ȏ������ʂ����Ă����t�����N���A�W�����Ƃ�������҂̖�S������S�ɐG�ꂽ�r�[�ɁA���낭���l�i����Ɍ������Ă��܂��^�������߂����B �@�O�Ɂw�E�H�[���t�����[�x�̔�]�ł��������Ƃ���A���_��Q��Ȃ��̃l�^�Ɏg���͔̂������Ǝv���̂����A�悭�ł����f��ł���������Ƃǂ����Ă��������Ă��܂��B �@�t�����N�̗���ƃW�����̗���A�ǂ���ɐg��u���Ă��ɂ݂��������ɂ͂����Ȃ�����B�}�X�N�̌����ڂ����ŃA�z�f�悾�ƌ��߂��Ȃ��łق����B �i�Q�O�P�S�D�X�D�Q�W�D�L�j ������w�A�i��x �A�i�Ɛ�̏����@�@FROZEN �i�Q�O�P�R�N�A�āA�����F���Y���ށj  �@���Ƃ��i���̂Ȃ����Ƃł���B �@��l�C�̗�̎��̂��u�����S�[�v�Ɖ̂����u���b�g�E�C�b�g�E�S�[�v�Ɖ̂����ŁA�v�w���܂ł����Ⴄ�l�������A���̓��{�ɂ͂���炵���B �@�l�����̌Z��o�̐��オ�u���b�g�E�C�b�g�E�r�[���ǂ����ă����r�[�ɂȂ��H�v�Ɠ���Y�܂����̂́A�����I���O�̂��Ƃł͂Ȃ��������B �@���͕K�������u�p��̎��Ƃœǂݏ��������łȂ��A�����Ƙb��������������ׂ����v�Ƃ����ӌ��ɂ͗^���Ȃ����ǁA�����������������Ɗm���ɂ�����K�v���ȂƎv�����Ⴄ�B �@�����ˁA���ϓI���{�l�̉p��͂͑�w�������s�[�N�ɒቺ����̂�����B����͓��퐶���̒��ʼnp����g���@���K�v���ɖR�������Ƃ������ł����āA�p�ꋳ��̂�����Ƃ͊W�Ȃ��B �@�]���āA���Ƃ��p��̎��ƂŁu�b�������v���������Ƃ���Łi�����Ă��ꂪ��ՓI�ɐ��������Ƃ���Łj�A�Љ�̌��ς��Ȃ���A����ς���{�l�͑�w�������s�[�N�ɉp��͂������S�[�����Ă��܂����낤�B �@�ŁA�w�A�i��x���B�������̂Ƃ���A���̂R���ɕ����Ĉȗ��A�ߔN�ł͈�Ԃ̑�q�b�g��i�ɐ����B���܂�������J�������Ă��钆�ŁA�������u���[���C�������[�X���ꂽ�B������A�r�b�N�J�����̔����ł��̃����S�[�����ꂽ�̂ŁA�x�܂��Ȃ���]�������Ă������Ǝv��������B �@�m���ɂ悭�ł����f��ł���ˁB���Ƃ̎o���̈��Ɗ������厲�ɁA�����̉^����`���A�F��𗍂܂����X�g�[���[�͏o�F�B���҃A�j������̃I�X�J�[��܂��ɒB����Ȃ��B �@���������{�Ńq�b�g�����ő�̗v���́A���̃X�g�[���[�ł��L�����N�^�[�ł��Ȃ��A�����S�[�ł��邱�Ƃ͖��炩�B�{���A�q�������̃A�j����i���A�u����̂܂܁v�ɐ������Ȃ��i�Ɗ����Ă���j���������̑傢�Ȃ�x�����W�߂Ă���\�}�ł���B �@�Ƃ͂��������ł��̎��̂��̂�����l����ƁA�u�Ȃ�ŋ��������́H�v�Ǝv��Ȃ��ł��Ȃ��B �@����͑��l�Ɋ�Q���y�ڂ�����\�͂��B������Ȃ��Ȃ����q���C�����A���ꂩ��͑��҂Ƃ̊W�����ĂЂƂ�Ő����Ă������Ɖ̂�������A����ΊJ���������u����������v�̐錾���B �@�䂪���{�̏��������͖{���ɂ����ɋ������Ă���̂��낤���H�@���`��A�����͎v���Ȃ��B�v�������Ȃ��B �@�����A�����łȂ��Ƃ���ƁA�����S�[�ɐ������������́A���̉f��ɂ����邠�̃V�[���̈Ӗ������𐳂����ǂ߂Ă��Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ�B �@���ƂƂ��ĉf��Ɋւ�铖���Ƃ��ẮA�ǂ�������������Ƃ��Ǝv���B �i�Q�O�P�S�D�V�D�P�W�D�L�j �P�[�v�^�E���@�@ZULU �i�Q�O�P�R�N�A���A�����F�H�j  �@��A�t���J���a�����܂��A�p���g�w�C�g������̂��Ă�������A�ǎ��h�̔��l�����X�ƃI�[�X�g�����A�ɈڏZ���Ă���Ƃ����V���L����ǂ��Ƃ�����B�ǂ�����z�Ƃ�����ŁA�p��̒ʂ��鍑������A�d���������₷�������̂��Ƃ����B �@�Ⴉ�������́u����������Ɏc���ăA�p���g�w�C�g�̔p��ɐs�͂��Ă��������̂Ɂv�Ǝv�������̂����A��������Y��Ă������̌����A���̉f������ĂӂƎv���������B �@�P�[�v�^�E���ŎႢ�����S�E�����B�w�i�ɂ͖��m�̖�����ł���炵���B�A���i�t�H���X�g�E�E�B�e�J�[�j�A�u���C�A���i�I�[�����h�E�u���[���j�A�_���i�R�����b�h�E�P���v�j�炪�{����i�߂�ƁA�A�p���g�w�C�g�̉A���������鋐��ȉA�d�������т�����E�E�E�B �@����̓t�����X�̍�Ƃ��t�����X��ŏ������N���C�����ҁB�t�����X�l�̃W�F���[���E�T���ḗu��A�t���J���̂��̂��L�����N�^�[�v���Ɗm�M���A��A�ŃI�[�����P�����p���i�Ɏd���Ă��B�t�����X���{�Ȃ���A�E�B�e�J�[�ƃu���[���ȊO�̃L���X�g�ƁA�X�^�b�t�̑唼�͓�A�l���Ƃ����B �@�T���ē̃L�����N�^�[���`�ɂ͐���������B�A�p���g�w�C�g�ŐS�g�ɐ[���������A���B������������{�c�̒ʂ����u���C�A���B�K�����Ò��̍Ȃ��������_���B���i�̈Ⴄ�R�l�̌Y�����A���ꂼ��Ƀ��A���Ȑl���Ƃ��ăX�N���[���ɋ�������B���T���ꂽ�u���[���ƁA�������j�ƍč����悤�Ƃ��Ă��錳�ȂƂ̊W�������ɂ����B �@�l�I�ɂƂĂ������[�������̂́A�R�l�̌Y�����z�[���p�[�e�B������V�[���B�ނ�̏��������Đl�퍷�ʎ�`�҂��������Ƃ���A�_���̍ȁi���l�j�͎��Ɉߒ������ɂ������낷�B�u�����Ȃ��v�ƕ���ȂɁA�u�ނ����������������̂͂����ł̓A����������v�ƍ������Ԃ��_���B�u���C�A���������ւ̌������B���Ȃ����A���l�̃A���́u�ނ������x���Ɏ�藧�ĂĂ��ꂽ�v�Ɖ��₩�Ɍ��B �@�������A����̓t�B�N�V���������ǁA���́u�Ӂ`��A�����������̂��v�ƔF�������߂��B�������{�ŕ�炵�Ă���ƁA���ƂȂ���A�̔��l���S���A���ʎ�`�҂������悤�ȃC���[�W����������B�ł��A�����ɂ͂��낢��ȍl���������l�������̂��낤���A���̃V�[���ɗނ����b�����Ď��ɂ͌��킳��Ă���̂��낤�B �@�ނ�̉�b����A���Ă̍��ʎ�`�҂������A�@�I�ȉ��͂��ĎЉ�̒����ɋ����葱���Ă��邱�Ƃ��킩�����B�����Ă݂�A�u�����Ȃ̂��낤�ȁB���������ȁv�Ǝv�����ǁA���̉f������Ȃ�����̌�����m�邱�Ƃ͂Ȃ��������A���������l���Ă݂邱�Ƃ����Ȃ��������낤�B �@���Ȃ݂ɃI�[�����h�E�u���[�����P�R�܂Ŏ������Ǝv���Ă����j���i���͈�Ă̕��j�́A�u�A�p���g�w�C�g�ւ̔��Ή^���ł��Ȃ�悭�m��ꂽ�����o�[�v�i�{�l�k�j�������̂��Ƃ��B�u���[���ɂƂ��āA�u���C�A���͉�����ׂ����ĉ������������̂�������Ȃ��B �@�������c�s�ȃV�[��������̂łq�P�T�w��ɂȂ��Ă��܂������A�������������Ă��邱�̐��E�̈�[��m�邽�߂ɁA�����̐l�ɊςĂق�����i�ł���B �i�Q�O�P�S�D�V�D�P�W�D�L�j 300���X���[�n���h���b�h���鍑�̐i���@�@300:RISE OF AN EMPIRE �i�Q�O�P�S�N�A�āA�����F�ъ����j �@���Ƃ��������Ȃ��ƂȂ���A����V�[���ŃJ�����Ɍ�����юU��̂ł���B �@����A��d�̈Ӗ��ł���������ˁB�f��Ƃ����̂͒ʏ�u����͌����ɋN�����Ă��邱�Ƃł���B�J�����ŎB�������̂��Ⴀ��܂����v�Ƃ������Ɋ�Â��č���Ă���B������B�e���A�{���Ƀ����Y�Ɍ��Ђ���юU�����肵����A�������m�f�ŎB�蒼���ƂȂ�B �@����Ɍ����Ȃ炱�́w�R�O�O�x�V���[�Y�́A���҈ȊO�͑S���b�f�Ƃ����Ă��ߌ��ł͂Ȃ���i���B�b�f�łȂ��͎̂��ۂɔo�D���g�ɂ����ߑ��ƁA�莝���̏�����炢�̂��́B��ɂ��錕�����āA�����������爬�肾�����{���ŁA���g�͂b�f��������Ȃ��B �@���R�A��юU�錌���Ԃ��Ȃ�Ă��̂́A���ׂă|�X�g�v���_�N�V�����ŕ`�����b�f���B������J�����ɔ�юU�点�Ă݂���i�悤�ɕ`���Ă݂���j�V�ѐS�A�Γ_����������z�c�P�����������Ƃ���ł��B �@�R�O�O�l�̃X�p���^�����P�O�O���l�̃y���V�A�R���}���������O��w�R�O�O���X���[�n���h���b�h���x����V�N�B���̑��҂ŕ`�����̂͂��̌���k���Ǝv������A�O��̐킢�Ɠ����i�s���Ă����ʂ̐퓬�������炵���B���ʈꎟ�����i�����j��n���Ɛ��o�Ŏ����ɂ́A�܂��������m�̕���ł������B �@�O��̃G�s�\�[�h��o��l���Ƃ̗��݂������̂ŁA�i���E�j�̋��ȏ��ł͂Ȃ��O����j�\�K���Ă���ς�Ƃ悢��������Ȃ��B �@���̑�Q��ł̓A�e�i�C�̗E�҃e�~�X�g�N���X���R���A�M���V���A���R�𗦂��ăy���V�A�C�R�ƌ��˂���B�����A�����ǂ���D���g���ˁh������̂��ނ�̉��̎�B�����Ɂu����ł͎��E����悤�Ȃ��̂ł��v�ƌ����A���R���u�����Ƃ��v�Ɠ�����̂��A�Ȃ�Ƃ����̃V���[�Y�炵���B �@�{��̎��ʂ��ς�����́A��V�i�C�Œ����D���x�g�i���D�ɐ���ɑ̓�������J��Ԃ��Ă����B����������R�@�����q���@�Ɉُ�ڋ߂����ȂǂƂ���j���[�X���B�u����ł͎��E����悤�Ȃ��̂ł��v�Ƃ������Ƃ��A�ނ�ɂ͂킩���Ă��Ȃ��̂��낤���H�@�o���܂ł��ł���Ă���̂��H �@�剉�̃T���o���E�X�e�C�v���g���͉f��E�ł͂܂����тɖR�������A�O��̃W�F�����h�E�o�g���[�ɂ����ʒj�L���A�j�炵���������Ă����B�y���V�A�R�̏����R�A���e�~�V�A�i�G�o�E�O���[���j�Ƃ̃Z�b�N�X�V�[���Ȃǂ́A�܂��Ɂu�����P�̐킢�v���B �@�y���V�A�Ƃ������̃C�����ł���A�C�����̏��������͍����`���h���ƃC�X�����̉����ɂ�����߂ɂ���Ă���B����ȃC���[�W�����ɂ���̂ŁA�Ȃ��A���e�~�V�A�̓x�[���Ŕ����Ă������Ȃ��̂��낤�Ǝv��������ǁA�l���Ă݂���̎���A�܂��C�X�������͐������Ă��Ȃ���ˁi�L���X�g�������j�B���ʈꎟ�����i�����j��n���Ɛ��o�Ŏ����́A�����ɂ͂��̂��ƂɁE�E�E�A���A���������������B �i�Q�O�P�S�D�U�D�Q�W�D�L�j �}���t�B�Z���g�@�@MALEFICENT �i�Q�O�P�S�N�A�āA�����F�Óc�R�I�q�j �@���������ɒ[����ɒ[�ɐU��邱�Ƃ͂Ȃ��̂ɂȁA�Ǝv���B �@���킢�������̔\�Ȃ��v�����Z�X�����q�l�Ɍ����߂��čK���ɁB����ȃf�B�Y�j�[�`���̃X�g�[���[�́A�����̐l�Ɉ���������ŁA�t�F�~�j�X�g�̓{�������A�p���f�B�̉a�H�ɂ��ꂽ�肵�Ă����B �@�f�B�Y�j�[�̎p�����ς��n�߂��̂́w���@�ɂ������āx(07)�̂����肩�炾�B���̃Z���t�E�p���f�B�Ƃ��v�����i�ł́A�`�Ƃ̕���u���q�l�̃L�X�v���������A�q���C���͎���̎�ʼn^�����J���˂Ȃ�Ȃ��Ȃ�B �@���̌�ɍ��ꂽ�f�B�Y�j�[�f��́A�w�v�����Z�X�Ɩ��@�̃L�X�x�w���̏�̃��v���c�F���x�w�A�i�Ɛ�̏����x�ƁA���Ƃ��Ƃ����X���B�q���C���Ɏ�̐����������邱�ƂɈّ��͂Ȃ����A�������q�l��S���𗧂����ɂ��Ȃ��Ă�������Ȃ����ˁB���������ܒ��I�ȗ��Ƃ��ǂ���͂Ȃ��̂��낤���B�{����ςāA�v�킸�u�܂����v�ƂԂ₢�Ă��܂�����B �@���̍�i�̓A�j���f��w�����X�̔����x(59)���A����̈����}���t�B�Z���g�̎��_����`�����������́B�A�j���łł́u�����v���������A�i�z����Ђ���z��ꂽ���ӏ����ɂ��j�{��̃}���t�B�Z���g�͂����܂ł��u���ȗd���v�Ȃ̂��������B�u�����v�Ɓu�d���v�͂ǂ��Ⴄ�̂��A�Ȃ��u�����v�ł͂����Ȃ��̂��́A�悭�킩��Ȃ��B �@�������A���W�F���[�i�E�W�����[�ɂƂ��Ă͓��[�؏���̕��A��B�j�����Ƃ��点�����݂̂��郁�C�N�ŁA�f�B�Y�j�[�f��炵����ʃo�g���A�N�V�����܂Ō����Ă����B �@�Ⴋ�}���t�B�Z���g���A�D�ӂ����l�Ԃɗ����A�������ꂽ���Ƃ�m�����V�[���͈����B�A���W�[�̋�ɂƔߒQ�ɖ������ԚL�́A�f�B�Y�j�[�f��ł͂��ĕ����ꂽ���Ƃ̂Ȃ��������������͂����B �u���̎q�͂P�U�̒a�����ɉi���̖���ɗ�����B��������̂͐^���̃L�X�����v �@�{����ς�q�ǂ������́A���Ԃ�q���C���̂��̎��f���A���t�ǂ���Ɏ�邾�낤�B�u�悩�����A��������@������v�ƁB �@����ȃC�m�Z���g�Ȏq�ǂ������ɁA���ɂ�����ăf�B�Y�j�[���u�^���̃L�X�Ȃ�Ă���Ⴕ�Ȃ��̂�B�܂肠��͉i���ɉ����Ȃ��Ȃ̂�v�Ȃ�Č����Ă������̂��B �@���l���u�^���̐l�v�Ȃ�Ă��̂�M���Ă���A���̓o�J���X�g�[�J�[���Ǝv�����ǁA������Ƃ����āu�^���̃L�X�v�����݂��Ȃ��Ƃ��v��Ȃ��B�����������̂͂R�N�ɂP�炢�i���w�A���Z�A��w�łP���ăy�[�X�ł����ˁj�������̂��ƍl���Ă����ƁA�X�g�[�J�[�ɂ��Ȃ炸�A�V�j�J���ɂȂ肷���邱�Ƃ��Ȃ��A���傤�ǂ������~�Ȃ̂ł͂Ȃ����ȁB �@���A��������Ɗ����҂͍������Ⴂ�܂��ˁB �i�Q�O�P�S�D�U�D�Q�W�D�L�j �I�[���E���[�E�j�[�h�E�C�Y�E�L���@�@EDGE OF TOMORROW �i�Q�O�P�S�N�A�āA�����F�˓c�ޒÎq�j �@�����Ȃ�őO���ɕ��肱�܂ꂽ�����E�̌R�l���A���ʂ��тɏo���O���Ƀ^�C�����[�v���A�܂������P������蒼���B�o���������Ƃ͋L������邽�߁A����ɗD�G�ȕ��m�ɂȂ��Ă����E�E�E�Ƃ������{���̂r�e����������B �@�����g�͎��ʂ��ςȂ���w���̓f�W���E�u�x�Ɓw�T�O��ڂ̃t�@�[�X�g�L�X�x�Ɓw�E�H���e�b�h�x���������悤�ȃX�g�[���[���Ǝv��������ǁA���̂����ɁA�͂��ƋC�������B�Ⴂ����ɂƂ��ẮA����̓o�g���Q�[���Ȃ̂��Ɓi�u���ɃQ�[�v�Ƃ��Ă�邻���ł��ˁj�B �@����ꏊ�܂Ői�����A�u�����v���E���ꂽ�烊�Z�b�g����B�������̏ꏊ�܂œ��������ł܂��i�݁A���x�͈Ⴄ�����i�H�������B�E���ꂽ��܂����Z�b�g���āA�������̏ꏊ�ցE�E�E�B �@�ē̃_�O�E���C�}���́u�������̏ꏊ�܂œ��������ł܂��i�݁v�̕������_���I�݂ȏȗ��ŏ������A�ދ��������������邱�Ƃ��Ȃ��B�ނ���J��Ԃ����t��Ɏ�����M���O�����A�n�[�h�ȃV�[���Ə��ɗ��������Ă���B �@��l���̃E�B���A���E�P�C�W�i����m�̌��쏬���ł̓L�����E�P�C�W�Ƃ������O�������Ƃ��j���������g���E�N���[�Y�͂������Ɏ茘���B�`���ł́u����Ȃ�Đ^�������߂�v�Ƃ������f�B�A�S�����Z�̒j�炵���Ȃ����A�܂��I�Ղɂ����Ă͐l�ނ̑��S��S������m�̎g�������ߕs���Ȃ�����������B �i�����u��m�v�ł͂Ȃ��u�������v������A�`���̃P�C�W�Ɠ�������ɂȂ�����A�u�K�ޓK���ōs���܂��傤��v�ƌ��ꂵ���i�������Ȃ邾�낤���ǁj �@���̃w�i�`���R��m��b���鏗��m���^���������̂��A�i�A���W�F���[�i�E�W�����[�ł��~�V�F���E���h���Q�X�ł��Ȃ��j�G�~���[�E�u�����g���B�w�v���_�𒅂������x�Ń������E�X�g���[�v�́g�z��h�����Ă����ޏ��̂ǂ�������m��˂�H�ƁA���ʂ��ς�O�͎v��������ǁA�ӊO��A���قǂ̈�a���Ȃ��B �u�P�K�����邭�炢�Ȃ玀��Ń��Z�b�g����v�ƃ��^�͌����A���ۂɉ��x���P�C�W���ˎE����B���C�}���ē͂�����M���O�Ɏg������A�ϋq�ɃV���b�N��^������Ɗɋ}���݁B���̂ւ�̎�ǂ́wMr.&Mrs. �X�~�X�x�ŏؖ��ς݂��B �@���^�ɂƂ��Ă͉���тɏ��Ζʂ����A�P�C�W�͉��S������^�Ɖ�A�ǂ�ǂ�[���m���Ă����B�����Ɋ�ȃ��u�X�g�[���[���G�肷��B�r�e�A�N�V�����̊�b�\���ɃR���f�B��}���X�̗v�f�܂œ��ꂱ�A�ꗱ�ʼn��x���I�C�V�C��y�삾�B �i�Q�O�P�S�D�U�D�Q�W�D�L�j �m�A�^�̏M�@�@NOAH �i�Q�O�P�S�N�A�āA�����F�˓c�ޒÎq�j �@�č��̃L���X�g��������`�҂́A�����̋L�q�����ׂĎ����ł���Ǝ咣���A�w�Z�Ői���_�������邱�Ƃɋ��������Ă���炵���B�����ǃK�����I��R�y���j�N�X���u�n���͂��܂�����V�̂̂P�ɉ߂��Ȃ��v�ƋC�Â������_�ŁA���łɔނ�̎咣�͔j�]���Ă��Ȃ��ƁA�w�m�A�@�̏M�x�̓����������Ȃ���v�����B �@�����ł͓V�n�n������n�܂�n���L�̃_�C�W�F�X�g�ł��}�������̂�����ǁA��ʂɉf��̂͂����������ۉF���X�e�[�V����������̍��x������Ղ����ۂ��n���̎p�B���ꂪ�_�̎��_���Ƃ���Ȃ�A�_�͉F���̈ꕔ�ł����Ȃ��B�g�s�s���Ȑ^���h�͐i���_��������Ȃ��ł���B �@�_�[�����E�A���m�t�X�L�[���m�A�̔��M�̉f����B�����ƕ����āA�w�t�@�E���e���@�i���ɂÂ����x�̂悤�ȃ��P�̂킩�����̂��Q���ԂP�W����������ꂽ�炽�܂��Ȃ��Ǝv�����f��W�҂͑��������͂��B �@�����A����͍K���ɂ��ĞX�J�������B�m�A�i���b�Z���E�N���E�j���_�̌[������V�[�������A�����ƌ��z�����ڂȂ��ڍs����A���m�t�X�L�[�ꗬ�̖��p�I���A���Y���ŎB���Ă������A���Ոȍ~�͐��S�ƎאS�A���Ǝg���A�l�Ԃ̋����Ǝコ��^���ʂ���`�����A���ɏd���ȍ�i�Ɏd�オ���Ă����B �@�Z�b�g�Ƃb�f��g�ݍ��킹�����M�����݊����B���݂̐��@�Ɋ��Z����ƍ����P�S���[�g���~���Q�Q���[�g���~�S���P�R�R���[�g���Ƃ�������Ȗؑ��\�������A�����X�N���[���ɍČ����Ă���B �w�G�o���E�I�[���}�C�e�B�x�ŃX�e�B�[�u�E�J���������������M�́A�����������̂���`������Ă����Ǝv�����A���b�Z���E�N���E�����͕̂����ǂ��蒷���`�̔��B���Ǒ��u�͂Ȃ��A�������������܂Ő��ʂɕ����Ă���������Ƃ����v�ɂȂ��Ă����炵���B�����Ă݂�Δ[�����B���E�̂��ׂĂ����v���A��������ȂǂȂ��̂�����B �@�����ɏW�܂��Ă��閳���̒��b��A�R�N�O�Ȃ���{���J�ł��Ȃ��������낤�Ǝv�����^���̂b�f���A���Ȃ�̗͍�B�Ƃ͂����A���m�t�X�L�[���ł��͂𒍂����̂́A��͂�l�ԃh���}�̃p�[�g���낤�B �@�m�A�̔��M�̕�����āA��ʂɂ͂ǂ����߂���Ă���̂��낤���H�@���͂Ă�����A�m�A���悫�l�Ԃ�����_�̓{�肩��ی삵�A������̎���c�����̂��Ǝv���Ă����B �@�m�A�̉Ƒ������l���B������{���i�G�}�E���g�\���j�́A�q�����Y�߂Ȃ��̂̎��������M�ɏ���Ă����̂��ƔY�B���j�i���[�K���E���[�}���j�̓p�[�g�i�[�����Ȃ����Ƃɋꂵ�B �@�������m�A�̍l���́i�܂�A���m�t�X�L�[�̉��߂́j����Ă����B���悢���^����������ƁA�m�A�͉Ƒ������M�ɏ悹�A���낵�����ӂ𖾂����̂��B�l�Ԃ�łڂ��̂��_�̈ӎu���B��X���Ō�̐l�ނɂȂ�ƁB �@�Ƃ��낪�{�������j�̎q���h���ɋy�сA�m�A�́w�u���b�N�E�X�����x�̃i�^���[�E�|�[�g�}����낵���A�ώ��̃g���R�ɂȂ��Ă����B����Ȃ鐢�オ���܂�邱�Ƃ̂Ȃ��悤�A�Ԃ�V���E���ƌ��������B �@�m�A��ᔻ���A�̌��t�𗁂т���ȁi�W�F�j�t�@�[�E�R�l���[�j�B���e�ɕ���������钷�j�B�u�P�l������I�ꂽ��Ȃ������̂��v�Ƌl�₷�鎟�j�B�u�g�����ʂ����Ǝv��ꂽ����I�ꂽ�������v�ƕԂ��m�A�B�L���X�g�w�̍D���������āA�I�Ղ̑Η����͑����l�܂�قǔZ�����B �@�m�A�̂������Ɓi���邢�́A���Ȃ��������Ɓj�͐����������̂��B����͎������ɂ͂킩��Ȃ��B�Ƃɂ����Ō�ɁA�{���͎����������āu�_�͂��Ȃ���I�сA�l���~�����ǂ����̑I�����ς˂��̂��v�ƃm�A�Ɍ��B����͂ЂƂ�m�A�݂̂Ȃ炸�A�������炦���l�ޑS�̂ɂƂ��Ă̋~���ł����낤�B �i�Q�O�P�S�D�T�D�Q�T�D�L�j �C���T�C�h�E���[�E�B���E�f�C���B�X�^�����Ȃ��j�̉� �@INSIDE LLEWYN DAVIS �i�Q�O�P�R�N�A�āA�����F�Γc�q�j  �@�G�b�W�̗������T�X�y���X���g�{�Ɓh�ɂ��A����I�ɑ��������ɒ���ł݂���R�[�G���Z��̐V��́A�P�X�U�P�N�̂m�x�̃t�H�[�N�E�V�[����ɂ������y�f��B �@���b�N�̂��鎞��Ɉ�����M�҂́A�t�H�[�N�\���O�ƕ����ƁA���R�Ɂu���d���܂Ԃ����āv�Ƃ��u���߂���̃o�X�͑���v�݂����ȃ������ăk�������̂�A�z���Ă��܂����ǁA�t�H�[�N����ԂƂ������y���������オ���邱�Ƃ��A���̉f��ōĔF��������ꂽ�B �@��l���̃��[�E�B���i�I�X�J�[�E�A�C�U�b�N�j�̓f���I�̑����Ɏ��Ȃ�āA�\���������n�߂�����B�Ƃ��낪���R�[�h�͂܂��������ꂸ�A���J�m�̃W�[���i�L�����[�E�}���K���j����͐Q���ɐ��̔D�P����������B�c�L���Z�ޏꏊ���Ȃ����[�E�B���́A�Ȃ������l�̎����L��A��ăO���j�b�W�E�r���b�W�����܂悤�͂߂Ɂc�c�B �c�c�Ə����ƁA�Ȃ��ߎS�ȉf��̂悤�ɕ������邩������Ȃ����A���ۂɂ̓g�z�z�n�̃��[���A�ɖ����������ȃR���f�B�B���_���炯�̎�l�����A�ǂ������킯�����߂Ȃ��B �@������{�̃z�[�����X�̊F����Ƃ͈Ⴂ�A���[�E�B���ɂ͋C�ɂ����Ă����Ƒ���F�l��������������l�q�B�ނ̐l���Ȃ̂��A����̐��_�Ȃ̂��A�Ƃɂ����l���A���Ƃ��Ȃ邳�ƁA�O�����ɂȂ�邱�Ɛ����������B �@�f��]�_�Ƃ̎ŎR���Y�����u���\�ł͂Ȃ��̂ɕs���ŁA�������ߎS�Ƃ����قǂł��Ȃ��������������Â��Ă���j�v�Ə����Ă���̂����Ɏ����B�H���Ȃ����[�E�B�����C�Â����ėF�l���b�l�\���O�̎d���ɌĂ�ł��ꂽ��A�V�J�S�̃v���f���[�T�[���g���I�̌��������߂Ă��ꂽ�肷��̂����A�����̉��y�����Ȃ������Ȃ����[�E�B���́A���������U���ɂȂт��Ȃ��B �@���̂����D���ɓ]�E���悤�Ƃ����肷��̂�����i��������s����j�A���Ƃ������������ł���B�c�Ƃ̃Z���X���[���Ȃ̂́A�M�҂Ƃ��Ă��g�ɂ܂����Ƃ���ł͂���ȁB �@�剉�̃A�C�U�b�N�̓W�����A�[�h���y�@���o�Ă��邻���ŁA�̂��M�^�[�����ւȂ��B �@�}���K�����̂��I���Ă��邪�A��Ԃ̌��ǂ���͛s�܂��ꂽ���Ƃ�m���ă��[�E�B�����N�\�~�\�ɂ������낷�V�[���̕����낤�B�u���͐G����̂�S���N�\�ɕς����Ⴄ�g�t�~�_�X���h��I�v���āA�J���C�C�炵�Ă����܂Ō����܂����i�j�B �@�C������Ȃ�����A�u�D�P�͑o���̐ӔC�ł���v�ƍ������Ԃ����[�E�B�����܂��I�J�V�C�B����ł��u�����p�͊��芨�Łv�Ȃ�Č���Ȃ��̂�����A���h�Ȃ���ˁB�u�萶����������������v�I�Ȃ��ꂢ���Ƃ́A�R�[�G���Z��͌���Ȃ��킯���B �@�̐S�̉��y�ɂ��Ắc�c�B�u�����ɂ��Ă���v�Ƃ��A�������s���Ɨ��Ȃ��y�Ȃ���B��͂�M�҂ɂ̓t�H�[�N�\���O�͍���Ȃ��悤�ł��B �i�Q�O�P�S�D�T�D�Q�T�D�L�j �l�N�X�g�E�S�[���I�^���E�Ŏ�̃T�b�J�[��\�`�[���@0��31����̒��� NEXT GOAL WINS �i�Q�O�P�S�N�A�p�A�����F ���c �֕v�j  �@��̃\�`�ܗւ́A���_���m���ƌ����Ă������{�̏��q�I�肪�������Ŗ����ɏI��������Ƃ��ċL������邾�낤�B���̂����W�����v�̍����I��͔҉�̃`�����X���Ȃ��܂܋A�����邵���Ȃ��������A�t�B�M���A�X�P�[�g�̐�c�I��̓V���[�g�v���O�����̕s���Ń��_����]�ƂȂ����ɂ�������炸�A�������ɂȂ邱�Ƃ��������邱�Ƃ������A�t���[�ňꐢ���̉��Z���������B�����̊ϋq�����������A�{�l������̊��S���ł��낤�ޏ��̃t���[�����āA���͎v�����B���ꂼ�u�l�N�X�g�E�S�[���E�E�B���Y�v�̐��_���ƁB �w�l�N�X�g�E�S�[���I�^���E�Ŏ�̃T�b�J�[��\�`�[���@0��31����̒���x�́A���̃L�����A�ŏ��߂ĂƂȂ錀����J��i�B�M��͎������̂悤�ɒ����Ȃ������A����́uNEXT GOAL WINS�i�l�N�X�g�E�S�[���E�E�B���Y�j�v�Ƃ����B �@����u���̃S�[�������������߂�i�����j�v�Ƃ������Ӗ������Ȃ̂ŁA�ŏ��͂Ă�����A�u���͏��ĂȂ��Ă�������߂��Ɏ��̂P�_��_���Ă�������B���̂P�_�������Ɩ����̏����ɂȂ�����炳�v�I�Ȓ��ۓI�|�W�e�B�u�u����\�����t���[�Y���Ɖ��߂��Ă����B �@�Ƃ��낪�|���Ƃ̓r���Ŕz����Ђ���͂������������ăr�b�N���B�܂�ňႤ�Ӗ��Ȃ�ł��ˁB �@�x�ݎ��ԂȂǂ𗘗p���čZ��ŃT�b�J�[������p�ẴK�L���`�������́A�Ԃ��Ȃ����ƊJ�n�̏�����Ƃ������ԂɂȂ�ƁA�����Ȃ�u�l�N�X�g�E�S�[���E�E�B���Y�i���̂P�_�A���Ώ����j�v�Ɛ錾���邱�Ƃ�����̂��Ƃ����B����ƁA�����܂ł̃X�R�A�Ƃ͊W�Ȃ��A���̂P�_��������`�[�������҂ɂȂ��̂������ȁB�o���G�e�B�ԑg�̃N�C�Y�R�[�i�[�Ȃǂł��Ȃ��݂̈ꔭ�t�]���[���ł��ˁB �@���̃h�L�������^���[�f��ŏœ_�����Ă���̂́A���ۃT�b�J�[�A���i�e�h�e�`�j�ɉ����ȗ��A��x��������ŏ��������Ƃ��Ȃ��ė̃T���A�̑�\�`�[���B�I��͑S���A�}�`���A�ŁA�Z�p�ǂ��납�X�O���ԃv���[����̗͂��Ȃ��B�g�����X�W�F���_�[�̃f�B�t�F���_�[��������̂�����A���͂͐����Ēm��ׂ��B����ł��ނ�͐܂�Ȃ��S�ƌ��������͂�����ɁA�v�t�\�I�̑啑��ɒ��ށB �@�������Җ]�̏��������ȒP�Ɏ�ɓ���͂����Ȃ��A�`�[���͎S�s���J��Ԃ��B�������ނ�͕��炸�A����܂��Q�[���ɗՂ݁A�����Ȑi����������A�����傢�ɏj���̂��B�u���i�͂X�_����鑊����W�_�ɗ}�����v�ƑO�������ނ�̃A�}�`���A�E�X�s���b�g���܂Ԃ����B����Ȕނ�̂����炩���ɁA���������`�����݂������m�l�̊ē��A�������|�W�e�B�u�ȉe�����Ă����B �@�T���A�̕�����`���Ɍւ�����I�肽���ƁA�v���t�F�b�V���i���Y����M��S�ē��A�݂������ߍ����Ȃ��珟���ȏ�̂��̂���ɂ��Ă����W�J������₩�B �i�Q�O�P�S�D�S�D�P�Q�D�L�j �I�[���E�C�Y�E���X�g �`�Ō�̎莆�`�@�@ALL IS LOST �i�Q�O�P�R�N�A�āA�����F�Ð��R�I�q�j �u���[�W���X�~���@�@BLUE JASMINE �i�Q�O�P�R�N�A�āA�����F�Γc�q�j  �@��l��炵���n�߂Ă���̍Ό��̕����A�e�Z��ƕ�炵���Ό��������łɒ����Ȃ��Ă���B���R�Ȃ���ƌ����ׂ����A�����Ƃ茾�Ɋւ��Ă͂�����Ƃ������ЂɂȂ����B���������A�傫��������ΓƂ茾�ɂ͂R�̗ތ^������悤�Ɏv���B �P�j�������ɔ������� �@�e���r�̂��V�C���˂�����Ɂu�����͒g�������Ă��o�������������v�ƌ����āu�́`���v�Ɖ�������A�d�q�����W�Ɂu�s���s���i�ł�����j�v�ƌ����āu�ق��ق��v�ƕԎ������肷��p�^�[���B�A�u�Ȃ��x�F�� �Q�j���ɕ������Ƃ����ɏo�� �u���܂����I�v�Ƃ��u�����Ȃ��v�Ƃ��u�����͐��j���������H�v�Ƃ��u������Ɩ��������������ȁv�Ƃ��A�����������肪�Ȃ��B���ɂ͉�������z�i�ϑz�H�j���Ȃ���A�V�[���ɉ������g�Z���t�h���A���F�i���킢��j�t���Ō����Ă��܂����Ƃ�����B�A�u�Ȃ��x�F�� �R�j�s�ׂƂ��v�l�Ƃ��W�̂Ȃ����t���A�������Ȃ������炱�ڂ�� �@���܂�ɌʁE��̓I�ŗᎦ������̂����A���Ƃ��ΐ��������Ȃ���A�d�ԓ��Ōo�������s�����ȏo�����̂��Ƃ��l���Ă��āA�����Ƃ��d�ԓ��̏o�����Ƃ��W�̂Ȃ����t���|�����Əo��B�������r�[�Ɂu�Ȃ�ʼn��A����Ȃ��ƌ������́H�v�Ǝ���Ђ˂�̂����A���R�������ς�킩��Ȃ��B�A�u�Ȃ��x�F��⍂ �w�I�[���E�C�Y�E���X�g �`�Ō�̎莆�`�x�����I���������|��W�҂��^����ɍl����̂́A�u���̉f��̖|��҂͐��K�̃M��������������̂��낤���H�v�Ƃ�����_�ɐs���邾�낤�B �@��ʂɎ����|��̃M�����͉f��̏�f���ԂŌ��܂�B�}�V���K���E�g�[�N���y���i�ł��A�ǖقȎE�������ނ���Ǝd����i�߂��i�ł��A��f���Ԃ������Ȃ�M�����̋��z�������ł���B �@���������̍�i�̏ꍇ�́A�������ɂ��̑匴���̓K�p�����߂����B�Ƃ����̂��B��̏o���҂ł��鑘������b�g�}���i���o�[�g�E���b�h�t�H�[�h�j���A�P�O�U���̏�f���Ԓ��A�O�����������J���Ȃ����炾�B �@�����C��f��ł���w���C�t�E�I�u�E�p�C�^�g���ƕY�������Q�Q�V���x�Ɣ�ׂ�ƁA���̑Δ�͔��ɑN���B������ł͎�l���̏��N����L�ތ^�Q�j�̓Ƃ茾���ӂ�Ɍ��ɂ������肩�A�`��ȃ��m���[�O�܂œ����Ă����B �@�Ƃ��낪���b�h�t�H�[�h�͋ꋫ�Ɋׂ��Ă��_���ł��Ȃ��A�v�f�ǂ���Ɏ����^��ł����삷��ł��Ȃ��A�ق��đD�̂̌����ǂ��A�Z���V�������Ō��݈ʒu�𑪒肵�A�R�����ʋl�ŕ������B���b�g�̒m���̂Ȃ��ϋq�͊��S�ɒu������E��ǂ����B��l���̉Ƒ��W��E�ƁA�o�`�n��ړI�n�A�P�l�őD�������Ă��闝�R�Ȃǂ��A�Ō�܂Ŗ�������邱�Ƃ͂Ȃ��B�w�I�[���E�C�Y�E���X�g�i���ׂĎ���ꂽ�j�v�Ƃ����^�C�g���́A�ǂ△���@����������l���̋����݂̂Ȃ炸�A�ϋq�̐S������\���Ă��邩�̂悤���B �@�~�j�}���Y���̋ɒv�Ƃ����Ίm���ɂ��̂Ƃ��肾���A�i�E�b�E�`�����_�[�ēi�r�{�������j�̂��̐헪�͂�����ƕ]��������ȁB�L�����A�̐ē��Z���t�ŕ����c��܂���p�������Ȃ������悤�ɂ������邼�B���̏Ȃ�A���ʂ͂����ƓƂ茾����������B �@�E�f�B�E�A�������v�X�ɕč���ɎB�����w�u���[�W���X�~���x�́A�x���̍Ȃ̍��������A�n�������̉Ƃɓ]���肱���N�����̔ߊ쌀��`���B�z����Ђ͂Ȃ����V���A�X�h���}�Ɛ�`���Ă��邪�A���Ԃ̓V�j�J���ȃR���f�B���B �@�P�C�g�E�u�����V�F�b�g��������o�ƁA�T���[�E�z�[�L���X�������閅�́A�����Ȃ����Ă��Ȃ��������A���i���l���s�H����Ⴂ�B���l�̎o�͓w�͂����Ȃ��̂ɕx���Ɍ����߂��A���ׂĂ����������܂��A�G���[�g�j�ɃA�v���[�`����Ă���B��J�m�炸�Ȃ����Ɏ��ȃ`���[�ŁA�H�U��̂����Ƃ��ɂ͖����������Ă��������ɁA�����Ă��炤���Ƃɂ͉��̋^��������Ă��Ȃ��B �w�V���f�����x��w���A���x�Ƃ͈Ⴂ�A������̃A�����͕Ԃ����Ŗ����o�b�T���B������͕i�̂Ȃ������蒅�āA�_���j�Ƃ��肭�����V���̕��������B�������e�̌��ň���Ă��A���ǂ͈�`�q�̍������������B�l���Ƃ́A���ɕs�����Ȃ��̂炵���B �@����A�{���ɂ������낤���B�s���ɓ������Ă���悤�Ɍ�����o���A�悭����Ζ{���̍K���Ƃ͉������B����Ȃ���Ȃŕs����X�g���X�����߂��݁A�l�O�Ńx���x���ƓƂ茾������ׂ肾���n���B �@�O�q�̂Ƃ���A���͂⎄���Ƃ茾�̌��Ђ����A���̂Ƃ���͂��̃q���C���ƈ���āA���j��������������ɂ��������Ɠ��e��F�����邵�A���j�����l�ɕ����ꂽ��Ԗʂ��邾�낤�ȂƂ̎��o������B�����Ԃ₭�悤�Ȓm�I�ň����邵���Ƃ茾�ƃA�u�Ȃ��Ƃ茾�Ƃ̕�����ڂ́A���͂��̂�����ɂ���̂�������Ȃ��ˁB �i�Q�O�P�S�D�S�D�P�Q�D�L�j ����ł���͖������@�@12 YEARS A SLAVE �i�Q�O�P�R�N�A�āA�����F�������Y�j  �@��T�͐l�퍷�ʂ⍑�Ѝ��ʂɊւ��Q�̃j���[�X�����Ԃ��ɂ��킵���B�܂��͉Y�a���b�Y�̃T�|�[�^�[���A�ϋq�Ȃ̓�����Ɂu�W���p�j�[�Y�E�I�����[�v�Ƃ������f�����f�����ꌏ�B �@���̒��ɂ͂܂��A�ʔ����l�����܂���ˁB���̃`�[���̊ē͂ǂ��l�Ȃ̂�H�@������͍��ʎ�`�҂���Ȃ��āA�����̃A�z�ł���B���b�Y�̎В����䂪�g�̎��Ԃł��邩�̂悤�ɎӍ߂��Ă������ǁA�ނ���u���̒��ɂ���ȃA�z������Ƃ͎v���܂���ł����v�ƁA���l���̂悤�ɃR�����g����ׂ��������B �@�Q�ڂ͌����}���ق̃A���l�E�t�����N�W�{���A�������j��ꂽ�ꌏ�B���{�ɂ���Ȑ^�ʖڂȔ����_����`�҂�����Ƃ͎v���Ȃ������̂ŁA��k�����ɔŌ��̎��쎩�����Ǝv�����قǂ��������A��������ǂ����{���̍��ʎ�`�҂ł͂Ȃ��A���_��Q�҂̂������Ƃł����Ƃ������Ȗ������ɂȂ肻�����B �@���{�̉f��E�ł��A���̏t�͍��l���ʂ��ނɂ����͍삪�Q�{�A�����ĕ���ꂽ�B���̂����w�哝�̂̎����̗܁x�͂قƂ�ǎЉ�Ȃ̕����ށB�u���f���ƂȂ����l�����������ɍ��ꂽ�����f��͖ʔ����Ȃ�Ȃ��̖@���v�̎���ƂȂ��Ă����̂��ɂ��܂��B�ڂ��������̂̓��r���E�E�B���A���Y���A�C�[���n���[�A�W�F�[���E�t�H���_���i���V�[�E���[�K���A�A�����E���b�N�}�������i���h�E���[�K����̂������胁�C�N�Ԃ肮�炢���i�W�����E�L���[�U�b�N�̃j�N�\���͖���������E�E�E�j�B �@����A�w����ł���͖�����x������ɂ���̂́A���̂P�O�O�N�O�̂P�X���I�O���B���Ȃ킿�A�����J�[�����z�����錾���o���O�̎���ł���B�f�v����A�암�̔_���ɔ���Ƃ��ꂽ��l���̃\�������i�L�E�F�e���E�C�W���t�H�[�j�́A�v���b�g�Ƃ����ʂ̖��O�𖼏�炳��A���`��i�C�t�ɂ��т��Ȃ���A�P�Q�N���̋��ɑς���B �@�\���҂ł́uI don't want to survive. I want to live.�v�Ƃ����\�������̌��t���A�������ӂ̕\���̂悤�ɐ����Ă�������ǁA�{�҂�����ƑS�R�j���A���X���Ⴂ�܂��ˁB����͝f�v���ꂽ����̎�l�����A�u�������т����Ȃ甒�l�ɋt�炤�ȁv�Ə������Ă��ꂽ���Ԃɑ��A�u���͐����O�ɂ͍Ȏq�Ǝ��R�ɕ�炵�Ă����B�g�������т�h���ƂȂ������Ȃ��B���ʂɁg�����āh��������v�ƃ{�������t�������̂��B �@�����A�f�v�����ȑO�̃\�������͓z��ł͂Ȃ��A���R�Ȑg����L���鉹�y�Ƃ������B���l���ʂ����e���鑼�̉f��Ɣ�ׂāA�{�삪���Ƀ��j�[�N�Ȃ̂͂������B �@�������͕č��̍��l���F��l�ɓz�ꂾ�����A�s�K�������A�������F��l�Ɍ��������l�������E�E�E���̂悤�Ɏv���Ă��邯��ǁA���ۂ͓������l�̒��ɂ��z��Ǝ��R�l��������ł��ˁB����͕��G���B �@��f���ԂP�R�S���̂��̉f��̒��ŁA���l�͐₦�ԂȂ����g����A�������܂�A�ڑł���A�i��A���C�v�����B�������{���ɐȂ��̂́A�\�������ƈꏏ�ɝf�v���ꂽ�j���A���ՂŁg�e�Ȃ���l�l�h�ɏ����������V�[���ł���A���̂Ƃ����c���ꂽ�\���������A���x�͐e�����Ȃ������z��̃p�b�c�B�[�i�A�J�f�~�[�������D�܊l���̃��s�^�E�j�����S�j��u������Ɏ��R�̐g�ւƖ߂��Ă����G���f�B���O�������B �@�\���������Ȏq�̌��ɖ߂������̌����́A�ʂ����ăn�b�s�[�G���h�ƌ�����̂��B�ނ����O�⑸�����������Ƃ��A�암�̔_���ł͉��\���l���̃v���b�g��p�b�c�B�[���������g����A�������܂�A�ڑł���A�i��A���C�v���ꑱ�����B �i���͓̏z�����錾���o����Ă��傫���͕ς�炸�A�w�哝�̂̎����̗܁x�̎�l���́A�ڂ̑O�ŕ��e��_����ɎˎE����Ă���B�Q�O���I�ɓ����Ă���̘b���j �@���Ȃ݂ɃC�W���t�H�[��j�����S�A�_������������x�l�f�B�N�g�E�J���o�[�o�b�`��}�C�P���E�t�@�X�x���_�[�A�ē̃X�e�B�[�u�E�}�b�N�C�[����́A��������č��l�ł͂Ȃ��B����͉ʂ����ċ��R�Ȃ̂��A����Ƃ����������f��ɕč��l���o������Ȃ��^�o���Ȃ�����������Ă���̂��A���̓_���ǂ��ɂ������������ĂȂ�Ȃ��B �i�Q�O�P�S�D�R�D�P�V�D�L�j �Q�O�P�S�N�I�X�J�[�i�C�g�E�E�H�b�`���O�I  �@���N�̃A�J�f�~�[�����̍C�����Ȃ����āA�����������������̂��낤�H�@�i��̃G�����E�f�W�F�l���X�̓Q�C�ł���A�Q�C�͈�ʂɃI�V�����Ƃ���Ă���ɂ�������炸�A���`��A�_�T�������B �@�q�ȂŃX�^�[�ƋL�O�ʐ^�H�@����A�c�C�b�^�[�ɓ��e�H�@�s�U��{���Ɏ�����Ⴄ�H�@���N�̃W���[�N��Ƃ����͂�قǃA�C�f�A�s���������炵���B�����^���̍����h���X��^�L�V�[�h�ɐH�ׂ��ڂ����Ƃ�S�z���Ȃ���d���Ȃ��s�U��������Ă����X�^�[�������C�̓ł��������A���M�z�����`���Ă����u���s���i�A�z�ȃW���[�N�Ɍ}�������Ƃ����_�Łj�j���������ˁB �@�m�~�l�[�g���Ȃǂ��猩��ƁA���N�̏܃��[�X�́w�[���E�O���r�e�B�x�w����ł���͖�����x�w�A�����J���E�n�b�X���x�̎O�b�Ƃ����̂��A�����ς�̉��n�]�B�Ƃ��낪�S�̔o�D���傷�ׂĂɃm�~�j�[�𑗂�o���Ă����w�A�����J���`�x�́A�ӊO�ɂ������ɏI������B �@����ɑ����ĂƂ������Ƃł�����܂����A�j�D����͏������W�����b�h�E���g�[�A�剉���}�V���[�E�}�R�m�q�[�ƁA�w�_���X�E�o�C���[�Y�N���u�x���̃_�u����܁B�X�s�[�`�̍Ō�ɉƑ��̖��O�����Ȗ����I�ɗ����҂��������ŁA���g�[�̓V���O���}�U�[��������e�ւ̊��ӂ����C���ɐ�����A��������Ƃ����X�s�[�`�������B �@�}�R�m�q�[�̃X�s�[�`���A���N�̎����S�̂̃e�[�}�u�q�[���[�v�ɗ��߂��A�悭����ꂽ���́B��܂ł���Ƃ����S���A���O�ɂ��Ȃ苭�������Ă����ƌ�����B �@�剉���D�܂́A��i�܂Ƃ͗��܂Ȃ��w�u���[�W���X�~���x�̃P�C�g�E�u�����V�F�b�g�B�ē̃E�f�B�E�A�����i�r�{�܂Ƀm�~�l�[�g�j�����ɗ��Ă��Ȃ����Ƃ́A���͂�b��ɂ����Ȃ������ȁB �@���^�N�V�I�ɂ͋��N�̃x�X�g�삾�����w�[���E�O���r�e�B�x�́A�����̏��Ղ��特���A���o���ʁA�B�e�Ȃǂ̋Z�p�n����𒅁X�Ɛ��e�B�ҏW�܂ł̓A���t�H���\�E�L���A�����ē���҂̂ЂƂ�ƂȂ������A�X�s�[�`�͖{�E�̕ҏW�}���ɏ������B�܂��ē܂ƍ�i�܂̑�����c���Ă������߂����A���҂ǂ���Ɋē܂��l���B�ǂ����X�s�[�`�������тꂸ�ɂ��B �w����ł���͖�����x�̓��s�^�E�j�����S�̏������D�܂ɉ����āA�r�F�܂ƍ�i�܂��Q�b�g�B���l�o�D�̃E�B���E�X�~�X����i�܂̃v���[���^�[�Ƃ��ēo�d�������_�ŁA�W�҂͎�܂��m�M�����ɈႢ�Ȃ��B �@�u���s�͓���̃v���f���[�T�[�Ƃ��ăI�X�J�[����ɁB����̋L�҉�ł́u���j�𗝉����邱�Ƃ͑���B�߈����������邽�߂ł͂Ȃ��A�������͉��҂ł������̂��A���ǂ�Ȗ�������Ă���̂���m�邽�߂ɂˁv�ƁA���l�ێ�w�ւ̔z�������肠��Ƃɂ��ރR�����g���c�����B���M���z�������A���͂₽���̃X�^�[�o�D�ł͂Ȃ��A���������Ђ̋C�z����̎В�����ł��ˁB�w�e���}�����C�[�Y�x�̂��̎��ȃ`���[�Ȏ�҂��A�����Ԃ�Ƒ�l�ɂȂ������̂ł��B �i�Q�O�P�S�D�R�D�P�V�D�L�j �Q�O�P�R�N�i���́j�x�X�g�P�O�I �@�Q�O�P�R�N�͉f�惉�C�^�[�̂��d�����J�X�x�Ə�ԂɂȂ��Ă��܂��A�ӏܖ{�������N�Ԃ肩�łQ���ɂƂǂ܂����B���ʂł͂Ȃ������Ŋς���i�����Ȃ�̐��ɁB �@�f�ڂ͗�ɂ���āu�ǂ��������v�ł͂Ȃ��A�u�ӏ܂������v���B�P�O�{���A���ɂW�{���č��f��B�c��w�V�g�̕����O�x�Ɓw�A�b�v�T�C�h�_�E���@�d�̗͂��l�x���p��̍�i����������A���N�͉��B�F�̔����x�X�g�I�ɂȂ����i���{�F�͖��N�����j�B �i�ӏܑ����X�X�{�j �P�@�t���C�g�@FLIGHT �Q�@�N���E�h�E�A�g���X�@CLOUD ATLAS �R�@���[�����C�Y�E�L���O�_���@MOONRISE KINGDOM �@�E�F�X�E�A���_�[�\���ē��A�͂���҂̏��N�Ə����̋삯����������`�����A�L���[�g�ŐȂ��A�w���e�R�Œg���Ȉ�ҁB���N���܂͂����ɂ��Ă����q�ǂ��������A�I�ՂɂȂ��Ĉ�]�A�Q�l�̖����ɂȂ��Ă����W�J���Ƃ��Ă��D�����B �@�S�R�_�C�E�n�[�h����Ȃ��x�����������u���[�X�E�E�B���X�̍Ⴆ�Ȃ��������f�G�i�`�e�����H�j�B����Ȃ̂́A�g���̂Ȃ����N��{���ɐe�g�ɃT�|�[�g����ނ��A�S�n����H�ׂ����Ă��i�ɂȂ�ƁA�f�J���t�����N�t���g���P�{�����߂ăS�����ƎM�ɐ��邾���Ȃ�ˁB����ł����͂̊ϋq������͘R�ꂸ�B���ϓI���{�l�̐H�������āA������I�J�V�C�Ɗ����Ȃ��قǃI�J�V���Ȃ��Ă���̂������H �S�@�v���C�X��r�����h��U��p�C���Y�^�h���@THE PLACE BEYOND THE PINES �T�@�V�g�̕����O�@THE ANGEL'S SHARE �U�@25�N�ڂ̌��y�l�d�t�@�@A LATE QUARTET �V�@�A�b�v�T�C�h�_�E���@�d�̗͂��l�@UPSIDE DOWN �W�@�V�g�̏��Y�l�@�o�C�I���b�g���f�C�W�[�@VIOLET & DAISY �X�@�[���E�O���r�e�B�@GRAVITY �P�O�@�E�H�[���t�����[�@THE PERKS OF BEING A WALLFLOWER �i�Q�O�P�S�D�P�D�Q�T�D�L�j �G���@�̍����@�@THE IMMIGRANT �i�Q�O�P�R�N�A�ā����A�����F���c���q�j  �@���͂P�X�Q�O�N��A�ږ��D�ɏ���ă|�[�����h����j���[���[�N�ɓn���Ă����G���@�i�}���I���E�R�e�B���[���j�́A�a�C�̖��ƈ���������A���R���킩��Ȃ��܂ܓ��������ۂ����B��������Ă����u���[�m�i�z�A�L���E�t�F�j�b�N�X�j�́A�����R�����ɘd�G�����点�ăG���@���������A�Z�܂��Ǝd���𐢘b����̂����E�E�E�B �@�c���ꂩ��J��Ԃ��ږ��̌������ꂽ�Ƃ����W�F�[���Y�E�O���C�ḗA�����̕�����X���݂������ɍČ����Č������E�E�E�悤�Ɏv���B�Q�O�N��̃j���[���[�N���������Ƃ̂Ȃ����ɂ͐��m���ɂ��Ă̔��f�͂����˂邯�ǁA�����N�オ����̃N�����g�E�C�[�X�g�E�b�h�ē�w�`�F���W�����O�x�Ɠ��l�A���A���e�B�͏\���������B�f��ɂƂ��ĕs���Ȃ̂́A���m�������M�ߐ��Ȃ̂��B �@�t�F�j�b�N�X�͖{��ł��܂��A�������̋������Z�ŕ��G�ȓo��l����������Ă݂����B���̃u���[�m�Ƃ����j�A�ŏ��̂����͉������̂��������Ȃ��̂������ς�킩��Ȃ��B�E�E�E����A�����Ⴄ�ȁB�f��̕��@���炷��A���炩�ɉ������j�Ȃ̂��B�����ǁA���ꂪ���܂�Ɍ��������Ȃ��̂�����A�f��������ꂽ�ϋq�قǁu������t��ɂƂ��āA�{���͂����l�ł����Ɩ������p�^�[������Ȃ��́H�v�Ƌ^���Ă��܂���ˁB �@���Ƃ��G���@�����������˂�V�[���B�u���[�m�̓G���@�����ł͂Ȃ��A���l�̏����������A�p�[�g�ɏZ�܂킹�A����ŗx�点�Ă���i�������ł���H�j�B���ꕶ�̃G���@�́A���������q���̂��߂ɏo���������������A�����ƂP�����h���Ă��܂��B�u���[�m�͂�������Ƃ��߁A�ӂ点��̂����A���܂ꂽ���̏��̑Ώ������܂�ɋC�����āA����ȋ����̂���肾�����u���[�m������قLj����l���Ƃ͎v���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂��B �@�u���[�m���G���@�ɑ̂点��̂́A���̒���̂��Ƃł���B �@����i�Ƃ������A���݂̊��o���炷��L���o���[�H�j�ŃV���[�̎i��Ȃǂ����Ă���u���[�m�����A�I�[�i�[�ƃP���J���ď�������A��ďo�Ă����Ă��܂��Ƃ��������ƁA����̏]�ƈ��ł͂Ȃ��A�_���T�[�����w�ł��鏗�������^�����g�Ƃ��Č���ɏo�������Ă���}�l�[�W���[���q���Ȃ�ł��ˁB �@�I�ՂɂȂ��Ă킩���Ă���̂́A�u���[�m���P�ɓ����R�����ŃG���@���g�X�J�E�g�h���������ł͂Ȃ��A�����Ɣڗ��㩂��d�|���Ă������ƁB���͂��̓��@�ŁA�������u��ʂ̏��w�v�𑝂₵���������Ƃ����̂����邾�낤���ǁA�ނ͖��炩�ɃG���@�ɍ���Ă������ˁB�Ƃ��낪����̃G���@�͏I�n��сA������ۂ������u���[�m��M�p���Ȃ��B�G���@���u���[�m�ɂق�����A����������������E�E�E�Ȃ�Ĉ����ȃh���}�Ɏd���Ă��Ă��Ȃ����A�u���[�m�̃L�����̕��G������w�ۗ��B �@�u���[�m�̏������͊F�A�g�ЂƂňږ����Ă����҂���B�H�ׂĂ������߂ɂ͂��ꂢ���ƂȂnj����Ă����Ȃ��B���̓_�́A����ɂ��Ă����f��v�w�ɔw���������A���Ƃ�����������낤�Ɩz������G���@�����l���B �@�G���@���܂߂����������A���x���u���[�m�ɂ��āuI need him.�i���ɂ͔ނ��K�v�Ȃ́j�v�ƌ����̂��S�Ɏc�����B�P�l�ł͋q�����Ȃ����A���Ɏ��Ă���蓦�����ꂽ��A�\�͂��ӂ���邩������Ȃ��B�u���[�m���D���Ȃ킯�ł͂Ȃ����ǁA�������ɂ͔ނ��K�v�Ȃ́E�E�E�B �@����������͈����鏗���Ɂu�A�C�E�j�[�h�E���[�v�ƌ����Ă��A�f���Ɋ�ׂȂ��悤�ȋC�����邼�B�Ƃ����āA�u���Ȃ����D���B�ł����ɕK�v�ł͂Ȃ���v�ƌ�����̂��A����͂���Ŏ₵�����̂��낤�B �@�|�b�v�\���O�̐��E�ł́u�A�C�E�j�[�h�E���[�v�Ɓu�A�C�E���u�E���[�v�Ɓu�A�C�E�E�H���g�E���[�v�͂قƂ�Ǔ��`�̂��̂Ƃ��ă��t���C�������X���ɂ��邪�A���Ƃقǂ��悤�ɈӖ�������͈̂Ⴄ�̂��B�O���f����Ė{���Ɂu�������p�ꋳ�ށv�ł��ˁB �i�Q�O�P�S�D�P�D�Q�T�D�L�j |
| �E�H�[���t�����[�@�@THE PERKS OF BEING A WALLFLOWER �i�Q�O�P�Q�N�A�āA�����F�Γc�q�j  �@�č��̎������w��ǂ�ł���ƁA7th grade����8th grade���̂Ƃ����o��l�������ʂɏo�Ă���̂ŁA�|��Ƃ̒[����Ƃ��Ă͂��]�v�Ȃ��Ƃ��l���Ă��܂��B7th grade�͂��̂܂܁u�V�N���v�Ɩׂ����A����Ƃ����{���Ɂu���w�P�N���v�ƒu��������ׂ����ƁB �@�펯�I�ɂ́u�ǎ҂ɗ]�v�Ȃ��Ƃ��l���������ɂ���Ȃ�ǂ܂���v�Ƃ����̂��|���Ƃ̃v���C�I���e�B������A�u���P�ł�����Ȃ��v�Ƃ������_�ɗ��������̂����A���ɂ͂���ł͂��܂������Ȃ��P�[�X�����邩��Y�܂����B���Ƃ�����7th grade�̎q���A�u�~�h���X�N�[���ɓ����ĂR�N�ځv�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ���i���ɖ��L����Ă���ꍇ�ł���B �@���̃~�h���X�N�[���Ƃ����̂����{�̊w���ɂ͂Ȃ��T�O������A�ƂȂ�Ƃ������������ˁB���{�ł������w�Z�̍��w�N���璆�w�Z�̓r�����炢�܂ł̎q���ʂ��w�Z���B �@�Ȃ��|��Ƃ�����������J�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ����ƁA�����{���Z�O�O���̋K�͂Ƃ����č����A���̌�̊w�����v�Łu�G�������^���[�X�N�[���S�N�v�u�~�h���X�N�[���S�N�v�u�n�C�X�N�[���S�N�v�Ƃ����敪���ɏC�����鐖���ɂ��邽�߂��i�č��͒n���̌��\���傫���̂ŁA�K�������S���I�Ɏl�l�l���œ��ꂳ��Ă���킯�ł͂Ȃ����j�B���{�̒��w�����p��̎��ƂŐ^����Ɋo����u�W���j�A�E�n�C�X�N�[���v�Ƃ������t���A�č��ł͎���ɂȂ����炵���B �w�E�H�[���t�����[�x�̎�l���`���[���[�i���[�K���E���[�}���j�̓n�C�X�N�[���ɓ���������B�������X�N�[���J�[�X�g�̍ʼn��w�ɒ��ނ��Ƃ��o�債�Ă��āA���w���̓����炳�������u���ƂP�S�U�O����������ށv�Ȃ�čl���Ă���B �@���q�Ȋϋq�́A�����Łu��H�@�P�S�U�O���H�v�ƁA����Ђ˂邱�Ƃ��낤�B�����A�ނ̃n�C�X�N�[�����S�N���Ȃ�ł��ˁB�i�]�k�Ȃ���C�O�h���}�wglee�^�O���[�x�̕�������炩�ɂS�N���̍��Z���j �@�\�z�ǂ���ɎS�߂ȏo�����ƂȂ����`���[���[�̍��Z�����́A�������p�g���b�N�i�G�Y���E�~���[�j�ƃT���i�G�}�E���g�\���j�̌p�Z���ƒm�荇���Ă����ς���B���ԁA�p�[�e�B�[�A�����ė��B�`���[���[�͏��߂��炠����߂Ă������̂��A���X�Ǝ�ɂ��Ă������ƂɂȂ�B�������ނɂ͏�ɐ��_�̕a�����܂Ƃ��Ă��āE�E�E�B �@�G�}�E�g�n�[�}�C�I�j�[�h�E���g�\�������߂ĉ�ʂɓo�ꂷ��V�[�����Ȃ��Ȃ��ɑN�B�ē̃X�e�B�[�u���E�`���{�X�L�[�̓`���[���[�̎��_�ʼn�ʂ����A��l�����������̂Ɠ����������ϋq�ɂ��^���Ă���B�w�k.�`.�R���t�B�f���V�����x�̃L���E�x�C�V���W���[�����́u���Ԃ�J�b�g�v�����Łi�ƌ����Ă͉������j�I�X�J�[��������悤�ɁA�����̔����̏��o��V�[���́A�ē�B�e�ēɂƂ��ē��Ƙr�̌������̂P���ƌ�����B �@����̓`���{�X�L�[�ē��g�̎�ɂȂ�x�`�������B�w��������搉̂��Ă��邩�Ɍ�����p�g���b�N��T�����A�����ăX�N�[���J�[�X�g��w�̏Z�l�ł͂Ȃ��A���ꂼ��ɃQ�C��ƒ���\�͂Ƃ�������������Ă���̂��|�C���g�B �@�C�^���Ă݂��݂�������i������Ⴂ�f��t�@���ɂ͐ϋɓI�Ɋ��߂����Ǝv�����ǁA��l�����S�̕a������Ă���Ƃ����ݒ�͂�����Ƃ����Ƃ������ˁB���j�����𔒌��a�Ŏ��Ȃ���f�悪�����Ȃ̂Ɠ��l�ɁA���_�a��Ȃ��̃l�^�Ɏg���̂��������B �i�����͌����Ă��w�t�B�b�V���[�E�L���O�x��w���E�ɂЂƂ̃v���C�u�b�N�x�̂悤�Ȍ��삪�����ΐ��܂�Ă��܂�����A����͂�߂��Ȃ��낤���ǁB����Ɠ����ł��ˁj �@�����P�c�b�R�~������Ȃ�A�p�g���b�N�̒��Ԃ����́i�`���[���[�������T����A���ۂɂ��������ƂɂȂ�ʂ̏��q���܂߂āj�݂�ȍŏ㋉���Ȃ�ˁB���Ă��Ƃ́A���{���Ɍ����Β��R�ƍ��R�̊W���B�Ȃ̂Ɍ����ł͑Γ��ȗ���ŎO�p�W�ɂȂ�����A�`���[���[���T���ɕ����������肵�Ă��邩��A�ǂ��ɂ���a�����E�E�E�B �@�l�I�ɂ͂ނ��낻�̔N����������Ăق��������B�㋉���ɓ����N���̒j�̎q���Ă̂́A�������ăh���}�`�b�N�Ȃ̂�����B �i�Q�O�P�R�D�P�Q�D�Q�Q�D�L�j �r�t�H�A�E�~�b�h�i�C�g�@�@BEFORE MIDNIGHT �i�Q�O�P�R�N�A�āA�����F���Y���ށj  �w�r�t�H�A�E�T�����C�Y�@���l�܂ł̋������f�B�X�^���X���x(95)�̂X�N����w�r�t�H�A�E�T���Z�b�g�x(04)���ς��Ƃ��ɂ́A�u�����Ԃ�ƖY�ꂽ����ɑ��҂���������̂��ȁv�Ǝv�������̂����A�������X�N���o�Ă��̑�R����ς����܊�����̂́A�u�����̂������Q��ڂ��������肶���H�v�Ƃ����ӊO���B���ꂾ���������Ƃ�A���̗��ꂪ������������悤�ɂȂ����Ƃ������Ƃł����ˁB �@�Ƃ����킯�ő�D�����������F�ɍĉ��C���Ŏ��ʂ��ς��̂����A���`��A���̃W�F�V�[�i�C�[�T���E�z�[�N�j�ƃZ���[�k�i�W�����[�E�f���s�[�j�������Ă��Ă��u�����Ƃ����E�X�m���v�ɂ͏��ĂȂ��������B �@�Q�l�͑O��̒���ɑo�q��݂��A�����͂��Ă��Ȃ����̂́A�p���ňꏏ�Ɏq��Ă����Ă���l�q�B�Ƃ��낪�W�F�V�[���č��ɖ߂邱�Ƃ��l���͂��߂����Ƃ���A�Z���[�k�Ƃ̊Ԃɂ����ܕ����E�E�E�B �@�V���[�Y�̓����ł���r�b�N������悤�Ȓ��ƁA�قƂ�Njx�݂Ȃ���X�ƌ��킳���_�C�A���O�͌��݁i�����̏��Y����A�����l�ł��j�B�W�F�V�[�ƃZ���[�k���Ԃő���Ȃ��牄�X�Ƃ�����ׂ肷��I�[�v�j���O�߂��̃V�[���i��̎ʐ^�j�Ȃǂ́A�P�̃J�b�g���P�S���Ԃ������B�ǂꂾ���m�f���o���ĎB�蒼�������Ǝv���ƋC�������Ȃ邵�A������������ꔭ�Ō��߂���������Ȃ��Ǝv���ƁA����������߂��ċ��낵���B�i�㕔���Ȃł��ƂȂ����Q���ӂ�����Ă����Q�l�̎q�����������j �@�z�[�N�ɂ��A�u�ǂ�����Ă���ȓ�����Ƃ��ł����̂��ƕ�����邯�ǁA���̂��Ƃ͂Ȃ��A�����猌�������o�������ɂȂ�܂Ń��n�[�T�����J��Ԃ��������v�Ȃ̂��Ƃ��B���`���[�h�E�����N���C�^�[�ē��܂߂��O�҂̐M���W�Ȃ����Ă͂ł��Ȃ��d�����ȁB �@�����A�M���V���̃��]�[�g�n��Ƃ��邱�̂P�O�W���̍�i�ŕ`����Ă���̂́A���ǂ̂Ƃ���A���ӊ����}�����l�\��J�b�v���̃��[�e�B���ȓ���ł����Ȃ���ˁB�����ɂ͑�P��̂Ƃ��߂��悤�ȏo����Ȃ��A��Q��̂��ꂵ�p�������̍ĉ���Ȃ��B����̂͐����L�ɖ������Ȃꍇ���Ƃ���Ⴂ�A�����ė\�蒲�a�I�Șa�������B�������Q�l�̂ǂ��炩�����C�ł����Ă��ꂽ��A�܂������h���}�ɂȂ����̂ɁB �@��P��̃G�s�\�[�h��O��ɁA�Z���[�k�́u���̎��Ɨ�Ԃ̒��ŏo�������A���������Ă����H�v�Ǝ��₵�A�W�F�V�[�́u���̖l�ɗU��ꂽ��A�ꏏ�ɗ�Ԃ��~�肽�����H�v�Ɛq�˂�B���������A���N�J�b�v���ɂƂ��Ă���͋傾�B�����āi�P�j��ɓ����̓m�[�����A�i�Q�j�����Ƀm�[�Ɠ����Ă����݂��ɓ�����͉̂����Ȃ�����B �@���ɂ����N��ِ̈��̗F�l���ق�̂킸���Ȃ��炢�邯��ǁA�������ɗe�F�͐����C���i���݂��l���j�B��������������v���Ă��܂����Ƃ�����B�u�Ⴂ�����炱����m���Ă��邩�獡���F�B�Â��������Ă邯�ǁA�����߂ďo������Ƃ�����m�l�̈���o���ɏI����Ȃ��v�ƁB�v����Ɏ��̔N��́A�e�F��ۂĂ�قǎႭ���Ȃ����A�O�����l�����Ɗ�����قnj͂�Ă����Ȃ���ł��ˁB�u�l���ɓK����͂Ȃ��v�Ȃ�Ă��ꂢ���Ƃ��ƁA���̍ɂ��Ď����ł��܂��B��҂�����A��������Ȃ獡�̂��������B �@����Ȏc�O�ȍ�i�̒��ł��낤���ĐS�Ɏc�����̂́A�W�F�V�[�ƃZ���[�k���z�e���ŏՓ˂���I�Ղ̃V�[���i��������j�B�u�Ǝ��ƈ玙�̂��߂ɁA���̓L�����A�≹�y�������]���ɂ��Ă����́v�ƃu�[�����Z���[�k�ɁA�W�F�V�[�͂���Ȃӂ��Ɍ������B�u����������Ȃ����B���匾���Ă鎞�Ԃ͂������A���̋C�ɂȂ�ł��邾��v �@�z������ɁA���Ԃ���ă����N���C�^�[��z�[�N���������Z���t�ł͂Ȃ��A�f���s�[�������Ɍ����ď��������ȂႠ��܂����B�ޏ��̌��𑽏��m���Ă���l�ԂƂ��āA���ƂȂ������v���B �@����͂Ƃ������A����Ȃ��S��͂���Ȃ���Ȃ��B�����Ă��ꂩ��X�N�������Ƃ��Ă��A���Ԃ�Q�l�̊W�͂͂��̂܂܂��B�ŊJ��Ƃ��ẮA���Ƃ��W�F�V�[�������������Ȃ��Ȃ��āA�Ƃ�č��ɖ߂��ăz�[�����X�ɂȂ��Ă���E�E�E�Ȃ�ēW�J���l�����邪�A����̓����N���C�^�[�̎���͈͂ł͂Ȃ����낤�B �@�r�{�����˂�z�[�N�ƃf���s�[���K�����������Ɉӗ~�I�ł͂Ȃ��悤�Ȃ̂��A��l�܂�������Ă��邩�炩������Ȃ��ˁB �@�ł����Ɏ��́w�r�t�H�A�E�Ȃ�x�������Ȃ�A����܂ł̂X�N�Ԃ́A�����Ƃ����Ƃ����Ԃɉ߂������Ă��܂��낤�Ȃ��B �i�Q�O�P�R�D�P�Q�D�Q�Q�D�L�j �[���E�O���r�e�B�@�@GRAVITY �i�Q�O�P�R�N�A�āA�����F���Y���ށj  �@�\���҂��ٗl�ɖʔ����f��Ƃ����̂́A���X�ɂ��Ė{�҂����I�������ŁA�u�\���҂Ō��������ȊO�̓N�Y�������ȁv�Ƌ������ꂽ�������̂����A���́w�[���E�O���r�e�B�x�͐����Ȃ���O�̂P�ł���B �@�\���҂Ɍ���Ƃ���A�D�O�������̉F����s�m���F���f�u���i�j�ꂽ�l�H�q���̂�����j�ɂ���ꂳ���Ƃ��낪���[�B�����A�e�ۂ̂悤�ȉF���f�u�����J�����ƍ~�蒍���A�F����s�m�̖��j����A�T���h���E�u���b�N�����ӂȂ��F����Ԃɓ����������̂́A�����܂ł��A�ق�̔��[���B �@���̌���P�s���`��蔲����A���̊�@���K��ĂƁA�������ǂ��낪�ڔ������B�����E���̂ŏڂ����͏����Ȃ����A�V���g������F���X�e�[�V�����ւƕ�����ڂ��A��Ɋ�����T�o�C�o���E�V�`���G�[�V�������A�Ă͕Ԃ��g�̂悤�ɃT���h���Ɗϋq���P���B �@�r�{�E�ē̃A���t�H���\�E�L���A�����͊ɋ}�̕t�������܂��ƂɍI���B�l�ԁA�ْ������ςȂ��ł̓T�X�y���X�ɑ��銴�����ݖ����Ă��܂��Ƃ��낾���A�{��̏ꍇ�͒o�ɂƋْ��̈Ĕz���▭�Ȃ̂ŁA�T���h�����s���`�Ɋׂ邽�тɁA�ςĂ��邱����̃A�h���i�����l���}�㏸�B�ԈႢ�Ȃ����N�̃i���o�[�P�f��ł���B �@�{��̉������������āA��P�ɃJ�������[�N���������I�@�Ȃɂ�����͏㉺�����E���Ȃ��F����ԁB�n��Ńh���[�B�e������悤�ȓ��I�ȓ����ł͂Ȃ��A�O�����I�ɋ߂Â��A����A�オ��A������A��肱�ށB������P�J�b�g�ŎB�������̂悤�ɐ�ڂȂ��A�X���[�Y�ɁB �@��ʑ̂ƂȂ�o��l�����܂��A���d�͋�Ԃ��O�����I�ɕ����сA������A����Ă��邩��i������ő������ɂȂ��Ă���̂́A�F���D�̑��c�Ȃɍ����Ă���Ƃ����炢�̂��̂��j�A���̉f���͂ǂ�ȃN���[���V���b�g�ł��B�e�ł��Ȃ����G�Ȃ��̂ƂȂ�B �@�Q�c�łł��\���Ɋy���߂�Ƃ͎v�����A�R�c�������Ă������đ��͂Ȃ���i���ƕۏ��悤�B �@�{��̑�Q�̃Z�[���X�|�C���g�́A�R�c��i�ɂ͒������A�l�ԃh���}�̕����������������Ă��邱�ƁB �@�T���h���������郉�C�A���E�X�g�[���́A��t��{�ƂƂ���V�ẲF����s�m�ł���l�q�B�܂��߂Ŏd���M�S�����A���܂�Ќ�I�ł͂Ȃ��B�����̃R�����X�L�[�i�W���[�W�E�N���[�j�[�j�Ƃ̉�b�̒��Ŏq�������̂ŖS�����Ă��邱�Ƃ��킩���Ă��邪�A�v�ɂ��Ă͂Ђƌ����G�ꂸ�A���C�A���Ƃ����j���O�ɂ��Ă��炩����Ɓu���͒j�̎q��]��ł����v�Əq������n���B�ǂ����F����s�m�ɂȂ��Ă��Ȃ�����Ȃ�ǓƂȃI�o�T���������̂ł͂Ȃ����Ǝv�킹���ˁB����A�ނ���ǓƂ��������炱���\�\��Ɏv������̂�S�c��ɂȂ���̂��n���ɉ����Ȃ��������炱���\�\�F���ɏo�čs����������l�Ȃ̂��B�u�ʂɉF���̑������ɂȂ��Ă���������ˁv�ƁB��������Ζ��̂Ƃ���ɍs������A�ƁB �@����ȃ��C�A����s�m����̐▽�̊�@�Ɍ������đ��X�ɂ�����߂邩�Ƃ����ƁA�����Ă���Ȃ��Ƃ͂Ȃ��̂ł���B�ǐ����ɂ������ɂ�����Ȃ��Ȃ��Ă��A�������P�l�ł킸���ȉ\����T���A�E�C�ƒm�͂������A�������т邽�߂Ƀx�X�g��s�����B���x���A���x���A���x���B �@�l�ԂɂƂ��Đ����邱�Ƃ̓f�t�H���g���B�u������Ӗ��v�Ȃ�Ă��̂����낤���Ȃ��낤���A���������{�\�ɏ]���čs����������B�{��͂���ȃV���v�������͋������b�Z�[�W��`���Ă���Ă���Ǝv���B �@�z�C�ł�����ׂ�ȃR�����X�L�[�́A�S��B���̌o���ƁA�L���x�ʂ̎����傾�B�C���������ɐi��ł���Ԃ̓��C�A���ɑa�܂�C���������ނ��A�ЂƂ��ыɌ���ԂɊׂ�ƁA��ÂɃ��C�A�����܂��A���B���A���҂̕��@���������ށB �@�����P�x�������C�A����������߁A�����邱�Ƃ���~��悤�Ƃ������ɂ��A�v��ʕ��@�Ő��ւ̊����߂�����B�N���[�j�[�ɂׂ͖����B���ʎ��ł��̃V�[���̂������Ă�����A�}�炸���܂Ԃ���������Ƃɂ��B�����u������R�c�f��v�Ȃ�Ă��̂����낤�Ƃ͎v��Ȃ������B �@�Ӑ}�����킯�ł͂Ȃ��̂����A���ʂ��ς��͎̂�c�����ۉF���X�e�[�V�����Ɂg���C�h���������������B�{��̕�����܂����ۉF���X�e�[�V�����̋ߕӂȂ̂ŁA���̓T���h����N���[�j�[�̔w�i�ɂ́A�����̃V�[���Œn������ʂ��ɂȂ��Ă���B �@�ɂ�������炸�A���j���ꂽ��_�f���s�����肵����A���邢�̓V���g����X�e�[�V��������ꂽ��A�l�͌����Đ����ł��Ȃ��B�A��Ȃ��B�Ȃ܂������̋�̘͂b�ł͂Ȃ������ɁA�F���̋��낵���������������Ĕ����Ă���B��c����A�ǂ����������ŁB �@�{��̖M��́w�[���E�O���r�e�B�x�i�d�̓[���j�����A�����Gravity�i�d�́j���B�S�̂Ƃ��Ă͖M��̕������e�ɂӂ��킵���悤�Ɏv���邪�A���X�g�V�[���ł�gravity�����Ɍ��ʓI�ɕ`�ʂ���Ă���B����̓��C�A�����Ăђn����\�\���̐��\�\�ɂȂ��~�߂�ꂽ���Ƃ̏ے��ł����������낤�B �@���̏o���������A�o�Ă���o�D�͂������̂Q�l�B��f���Ԃ͂X�P���B����ł���Ȍ��������Ă��܂��L���A�����ēɂ́A���͂�V���b�|��E�������Ȃ��B�҂Ă�B���Ă͂u�e�w�ɋ��������肷���āA�ق��̖��҂��ق��Ȃ��������E�E�E�i�Ȃ킯�Ȃ��j�B �i�Q�O�P�R�D�P�P�D�P�W�D�L�j �O�����h�E�C�����[�W�����@�@NOW YOU SEE ME �i�Q�O�P�R�N�A�����āA�����F�ъ����j �Q�K���Y�@�@2 GUNS �i�Q�O�P�R�N�A�āA�����F���c���q�j �@�������N�A�e���r�ŗ������m��̃X�|�b�g�b�l���{���ɏ��Ȃ��Ȃ����B�ȑO�͂P�N���o���o��������Ă�����ۂ����邪�A���̂Ƃ���ċx�݂₨�����̂�������ꂽ�u���b�N�o�X�^�[�f�悵���X�|�b�g�b�l���ł���Ȃ��B �w�O�����h�E�C�����[�W�����x�Ɓw�Q�K���Y�x�́A�ǂ�����h�h��Œɉ��ȃG���^�[�e�C�������g��i�B������A�N�V��������́A�Ђƍ��Ȃ�^����ɃX�|�b�g�b�l���ł���Ă����^�C�v�̍�i�Ȃ̂����A�܂������̉��Ȃ��������B �@�����Ȃ�ƁA�킴�킴�f��G��������A�f���]�T�C�g���̂������肷��R�A�ȉf��t�@���ȊO�́A�����̍�i�����J����Ă��邱�Ƃ���m�炸�ɏI����Ă��܂���ˁB���������ʔ����f��Ȃ̂ɉ��Ɛɂ������Ƃ��낤�B���R�A�������L�т��A���̍�i�̐�`��N�����A�܂��܂��X�|�b�g�b�l���ł���Ȃ��Ȃ�B����Ŏ��̍�i�̋���������B���z�ł���B �w�O�����h�E�C�����[�W�����x�͓�̍����̎�ŏW�߂�ꂽ�S�l�̃}�W�V�������A���ꂼ��̓��ӋZ����g���ċ�s�������D������A�������ȑ���������o���������肷��ɉ�杁B�}�W�b�N�Ƃ����̂́A���ʂ͉f��Ō��Ă��ʔ��������Ƃ��Ȃ��킯�����i�E�T�M�̂��Ȃ��J�b�g�ƁA�E�T�M����ꂽ�J�b�g��ҏW�łȂ������킯�ł�����ˁj�A����͂��̓_�܂�����ŁA�Ȃ����y���߂�C�����[�W�������l�Ă��Ă���B�e��w�������낢�����A�����̓��@�Ɛ��̂��ӊO���\�����i������Ɩ�������������Ⴀ�邯�ǁj�B �w�Q�K���Y�x�݂͌��̐��̂�m��ʂ܂ܖ���g�D�ɐ������Ă����c�d�`�ƊC�R�̑{�������A����J���e���̋������D�������Ƃ����������ɁA�G�Ɩ����̑o������ǂ���n���ɂȂ�B�b�h�`�������ɗ���Ŏl�b�B���{�@�ւ�����Ƃ����đP�ʂł͂Ȃ��A�����̂͋C�S�̒m��Ȃ��݂������Ƃ����ِF�̃o�f�B���[�r�[���B���������苦�͂�����ƂQ�l�̊W�͓�]�O�]�B���[�����X�Ȋ|���������y�����B �i�Q�O�P�R�D�P�P�D�Q�Q�D�L�j �V�g�̏��Y�l�@�o�C�I���b�g���f�C�W�[�@�@VIOLET & DAISY �i�Q�O�P�P�N�A�āA�����F�{��^���j  �@�S�̂ɓ��{�̉f���Ƃ́A��ɑ�������i���B�点��ƁA�ϋq��u������ɂ����ދ�����܂�Ȃ��}��ɂ��Ă��܂������B�Ƃ��낪�C�O�ɂ́A��Ɛ��⎩���̎u���i���邢�͕Ό��j��O�ʂɉ����������A�����ƃG���^�[�e�C�j���O�ȍ�i�Ɏd���ĂĂ̂���r�p������B�w�G�^�[�i���E�T���V���C���x�̃~�V�F���E�S���h���[��A�w�L�b�N�E�A�X�x�̃}�V���[�E���H�[���́A�܂��ɂ��̓T�^��ƌ����邾�낤�B �w�V�g�̏��Y�l�@�o�C�I���b�g���f�C�W�[�x�̃W�F�t���[�E�t���b�`���[���A����Ȍn���ɘA�Ȃ�f���Ƃ̂ЂƂ�ɂȂ邩������Ȃ��B�w�v���V���X�x�̋r�{�ł��m����ނ����̏��ē�̃��`�[�t�ɑI�̂́A�����[�^�ŃJ�}�g�g�ȎE�����R���r�B�قƂ�nj`�e�����̂悤�Ȗ���I�ݒ肾���A�Ȃ��Ȃ��ǂ����āA���ƃo�C�I�����X�A�Ȃ��Ƒu���������������A���̂�����Ɏd�オ���Ă���B �@�^�C�g�����[���̃o�C�I���b�g�ƃf�C�W�[�́A����y�Ȏd�����������Ȃ��A�w���A���o�C�g�̂悤�ȎE�����R���r�B������́A�R�O��ɂȂ��Ă�������̃A���N�V�X�E�u���f���ƁA��l���ۂ��炾���Ȃ��炢�܂��~�h���e�B�[���̃V�A�[�V���E���[�i�����B �@���̂Q�l���܂��A�����������炠��Ⴕ�Ȃ��B�^�[�Q�b�g�̗����ɓ��肱�͂������A�҂��Ă�Ԃɂ�������Q�����Ă��܂��n���B�^�[�Q�b�g��������̂����ʂ̃W�F�[���Y�E�K���h���t�B�[�j�����ɁA�ǂ��Ȃ邱�Ƃ��ƃh�L�h�L����B�i���̌�̓W�J�̂��������Ƃ�������I�j �@�t���b�`���[�ḗA�ϔN�̖ϑz�E�E�E����A�ϔN�̃A�C�f�A���������Ƃ���ɂԂ����̂��낤�B�Ȃ���Ȃ�ɂ��v���̎E�������A�~���N�́u�Ђ��v��@�̉��ɂ���B�^�[�Q�b�g�ƈӋC�������āu�����������̂悢�悢�悢�v������B�����|�����M�����O�c�̌��̊C�ł[���Ɗ����ėV�ԁB����͂�A����ȃL���C�Ő��_�N��̒Ⴂ�E�����́A�����▋�ɂ͂��Ȃ������i�L���C�ȎE�������������A���_�N��̒Ⴂ�E�����������������A�L���C�Ő��_�N��̒Ⴂ�E�����ƂȂ�Ƃ��Ȃ�H�L���j �@�Q�l�̂����ł́A�N���̃o�C�I���b�g�͔�r�I������Ă��āA�l�ɂ͌����Ȃ��h���ځi���ԂI�\�s���܂ށj�ɂ������Ă��Ă���l�q�B����̃f�C�W�[�̓Z�b�N�X���݂̃W���[�N���������Ȃ��I�{�R�ƁA�l���o���̍��͑傫���B �@�������e���}�ƃ��C�[�Y�������ł������悤�ɁA�����炭���̍L�����̒��ŁA�o�C�I���b�g�̓f�C�W�[�ƁA�f�C�W�[�̓o�C�I���b�g�Ƃ����Ȃ���Ȃ��B���̒ɂ��قǂ̌ǓƊ��ƁA���j�ɂ��������Q�l���J���O���Œ���Ă��邾���ɁA�f�C�W�[�́g��߂�����h�����炩�ɂȂ�㔼�̓W�J���A�傢�Ɏ������̋C�����܂���B �@�ʔ����f��Ƃ����̂͏o��������ϋq�̕@�ʂ��Ƃ炦����̂����A�u���f���ƃ��[�i������m�̃R�X�v���ŃM�����O�̑��A�ɏ�肱�ޖ{��̃I�[�v�j���O���C���p�N�g��B�������ē͂��̃o�C�I�����X�ƃA�N�V�����̂͂��܂ɁA�f�C�W�[�̔閧�ɂȂ��镚���܂ł�������Ǝd���B�����Ă������Ă��q�O�}�̂悤�ɓːi���Ă����j�B�����ƑΛ�����G�����ł͂Ȃ��A�f�C�W�[�́g���蓖�āh�܂Ń`���b�`���Ǝn������o�C�I���b�g�̈�l�̃V���b�g�B�ォ�炻���̈Ӗ��ɋC�Â��āA�ڂ��Ƃ��ϋq�͐���������낤�B �@��f���Ԃ͂W�W���B������ƕ�����Ȃ��C�����邪�A�Â��X�i�b�N�͂��̒��x�̗ʂł��傤�ǂ����̂����ȁB �i�Q�O�P�R�D�X�D�Q�V�D�L�j �_�C�A�i�@�@DIANA �i�Q�O�P�R�N�A�p�A�����F�˓c�ޒÎq�j  �@�`���[���Y�c���q���s�l�C�Ȃ̂������ȁB�G���U�x�X�����S����́A�c���q�����āA���̃E�B���A�����q�����ʂɏA����Ƃ���ӌ�������ƕ����B���R�́u��炪�_�C�A�i�܂𗠐�A�������A���ɒǂ����A���܂����l�Ȃ������N�㏗�Ȃƍč���������v �@�ł������A����̉��������Ȃ��́H�@�c���q�͂��̔N�㏗�������ƑO����D����������B�ł��J�~������͕ʂ̒j�ƌ������āu�{�E���Y�v�l�v�ɂȂ��Ă����B�w�����[�W���̎���Ƃ��Ȃ�A�R�l�ł���{�E���Y�����őO������ɂ�����A��Ȃ��ă����h�����ɗH����������肷��A��Q�͔r���ł����킯���B �@�Ƃ��낪����Ȗ�Ȏ���͍��͐́A���͂₻��͋�����邱�Ƃł͂Ȃ��B�����Ń`���[���Y�N�́A�d���Ȃ��ʂ̏����ƌ��������킯�ł���B���E�҂Ƃ��Ă̋`��������l�I�ȍK����������߁A��������Ԃ悤�Ȍ��h���̂����������܂Ɍ}�����B�������čD���ł��Ȃ������̂ɁB �@���͗���ă_�C�A�i�܂͖S���Ȃ�A�J�~���v�l������ă{�E���Y���Ɨ��������B�N���̂Ƀ����h�����ɑ���Ȃ��Ă��A�D���ȑ���ƍč��ł�������������킯���B��������j�����Ă������������Ȃ��́B�C�M���X�l���āA�P�c�̌����������Ȃ��B �@�E�E�E�ƁA�Ȃ���������Ȋ��z������̂��Ƃ����ƁA�w�����E�~�����́w�N�B�[���x�ł̓_�C�A�i�܂������̈�������������B����ł͉����p�~�_�҂̃u���A�i�}�C�P���E�V�[���j�܂ł��A�_�C�A�i�܂��u�����Ɍ�둫�ō������������v�ƍ��]���A�G���U�x�X������i�삵�Ă���B �w�N�B�[���x�����ăt�B�N�V����������A�K�������t�F�A�ȗ���ŃZ���t��������Ă���킯�ł͂Ȃ��̂����A�悢�f��ɂ͂��ꂾ���e���͂�����Ƃ������Ƃł��ˁi���ꂾ���ɂ���Ӗ��A�댯���Ƃ�������j�B �w�N�B�[���x�̓_�C�A�i�܂����̎���������̏�`�����f�悾�������A�w�_�C�A�i�x�͔ޏ��̍Ŋ��̓��X�ɖ��������]�`�f��B���{�ł͎��̎Ԃɓ��悵�Ă����h�f�B�E�A���t�@�C�h���̂��Ƃ��肪�����b�ɕ��Ă������A���̎����A�ޏ����ł��������̂́A�ǂ����p�L�X�^���o�g�̃J�[���Ƃ����S���O�Ȉゾ�����炵���B�{��ł̓_�C�A�i�܂��J�[����t�ɐS���X���A���ǂ͎����ꂸ�ɂ������ČǓƂƐ�]��[�߂Ă����l�q�������ɕ`����Ă���B �@�h�C�c�o�g�́\�\�]���ă_�C�A�i���g��炪�v�����Z�X�h�Ƃ͂Ƃ炦�Ă��Ȃ��\�\�I���o�[�E�q���V���s�[�Q���ḗA�̐l���^���邱�ƂȂ��A������������v�Z���������Ȃ������g��̏�����������B�_�u���s�ς̍�����A���͓I�Ȑl���x�������Ȃǂ̃G�s�\�[�h�̉A�ɁA���Ȏ����̕����͍����A�������ꂸ�ɂ��炾�A�g�����Z���u�h�̂����肪�̂����B �@�剉�̃i�I�~�E���b�c�́A�n�炪����قǃ_�C�A�i�Ɏ��Ă���킯�ł͂Ȃ��̂����A���̓����I�Ȕ��^�ƕt���@�̂������ŁA�ꕔ�̃X�`�[���ʐ^�Ȃǂ͖{�l�ƌ��܂����قǁB��ڂÂ����̕\���b�����̓������A�������茤�����A���Z�Ɏ����ꂽ�悤���B �i���m�Ȏ��́A�_�C�A�i�܂���������̃E�F�C�r�[�Ȕ��^�����Ă�����̂Ǝv���Ă������A�Z�b�g���Ă��Ȃ��Ƃ��͕��ʂɃy�^�b�Ƃ����X�g���[�g�E�w�A�Ȃ�ł��ˁB�j �@�J�[����t�i�w�k�n�r�s�x�̃T�C�[�h���ƃi���B�[���E�A���h�����[�X�j�̗����S����Ȃ��Ȃ��ɕ��G���B�u�l���̃v�����Z�X�v�Ɍ����߂�ꂽ�̂͌˘f���Ɠ����ɗD�z���������邱�Ƃł����������낤���A�{�a�������̂�������͍̂D��S�ƑI���ӎ��������邱�Ƃł����������낤�B�����ނ͌��ǁA�p�p���b�`�̕W�I�ɂȂ�̂̓S�������ƁA�v�����Z�X�ɂ��Ă��܂��B �@�v�����Z�X�E�t�@���̊ϋq�̖ڂɂ͐g����ȁu��蓦���j�v�ɂ��f�肩�˂Ȃ����A�ނ��_�C�A�i�ɐ[���肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ����R��Ӗ��͂Ȃ��킯�Łi�����̃C�X�������k�Ƃ����Ă͂Ȃ����猈�f������j�A���l���ᔻ�ł��邱�Ƃł͂Ȃ��낤�B �@���ǂ̂Ƃ���A�_�C�A�i�͂Q�x�ڂ̒j�I�тɂ����s������ȁE�E�E�ƁA�v�����Z�X�Ɠ����N���܂�̕����́A�g���ӂ����Ȃ����S������̂ł������B �i�Q�O�P�R�D�X�D�Q�V�D�L�j �E�����@�����F�r�`�l�t�q�`�h�@�@THE WOLVERINE �i�Q�O�P�R�N�A�āA�����F����L�K�j  �@ �@ �@�f��⏬���A�|�b�v���y�Ƃ������G���^���̐��E�ł́A���i�̂���ō������i���ӊO�Ȏx�����Č���E����E��\��ɍՂ�グ��ꂽ��A�P�Ȃ�e���������͂��̃L�������V���[�Y�̈�Ԑl�C�ɂȂ��Ă��܂����肷�邱�Ƃ�����B�w������тƁx�Ȃǂ͖��炩�ɑO�҂̗Ⴞ���A���N�^�[���m��E�����@�����͂������ߌ�҂̍D�Ⴞ�낤�B �@���N�̃A���R�~�́u�w�|�����v�����߂ĉf�扻���ꂽ���_�ł́A�E�����@�����Ƃ����L�������A�������q���[�E�W���b�N�}�����A�ǂ�����f��t�@���ɂ͖����̑��݁B���̂��ߔނ̕��e�����A�R�~�b�N�Ɏ����邱�Ƃ��ŗD��ɂ����ߎS�ȗL�l�i��E�j�ɂȂ��Ă����B �@�Ƃ��낪�E�����@�����ƃW���b�N�}���̑o�������W���[�ɂȂ��Ă����ɘA��āA�������ɂ��̔��^�ł͋��s�����Ƀ}�C�i�X�ɂȂ�Ƃ����ӎ����e�n�w�����ɓ������̂��낤�B�ނ̕��e�͂ǂ�ǂ�C�����Ă������B�{��Ɏ����āi�㍶�j�̃��b�N�X�ɂȂ����̂����A�A���R�~�̃t�@���⌴��҂́u����Ȃ̃E�����@��������Ȃ���v�Ǝv���Ă��邩������Ȃ��ˁB �@���łɌ����A�A���R�~�̃t�@���⌴��҂́u����Ȃ̂w�|��������Ȃ���v�Ƃ��v������������Ȃ��B�Ȃɂ��{��ɓo�ꂷ��~���[�^���g�́A�E�����@�����ƈ������̃o�C�p�[�̂݁B�X�s���I�t��P��́w�E�����@�����F�w�|�l�d�m �y�d�q�n�x�i����́gX-MEN ORIGINS: WOLVERINE�h�j���A�Z�C�o�[�g�D�[�X�A�K���r�b�g�A�f�b�h�v�[���Ƃ������{�Ƃ̃V���[�Y�ɂ��o�ꂵ�Ă��Ȃ������~���[�^���g�E�L�����𑱁X�ƏЉ���̂ɔ�ׂ�ƁA���炩�ɘH�����C�����ꂽ�������B �@�^�C�g�������Ă��A���肩����M�肩����g�w�|�l�d�m�h�����������Ă���B���̂��Ƃ���A�z�����̂́A�w�_�[�N�i�C�g�x�̐���w���^�C�g������g�o�b�g�}���h����������Ⴞ�B�����Ɍ���A���R�~�̘g���яo���A�V���Ȃr�e�V���[�Y��n�삵�悤�Ƃ�������̐^���Ȉӎu��������͎̂��������낤���B �@����̐^���Ȉӎu�́u���{�v�Ƃ����f�ނ̈������ɂ����ĂƂꂽ�B�S�҂̂قƂ�ǂ͓��{�����䂾���A�x�m�R�E�|�ҁE���o���X���[�͂Ȃ��i�E�҂͏o�Ă������ǁj�B����ɕ`�����̂͑��㎛�ł̑嗧�����ɁA�p�`���R����u�z�e���ł̓����s�A�C�ӂ̊����̓��{�Ɖ��ȂǂȂǁB�X�e���I�^�C�v�ɑ��邱�ƂȂ��A����ł��Đ▭�ɓ��{�I�ȃA�C�e���E���䂪��肠�����Ă���B �@���u�z�̃t�����g�̂�����u�_���_���A�p��͂킩��Ȃ���v�̈�_���肾������A�E�����@���������тɔ��𗧂Ăē{��ꂽ�肷��̂��A�����ē�r�{�Ƃ̎��̌��Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv�킹�ď����B�z������ɁA���Ȃ�̓��{�ʁi�܂��͓��{�l�j���X�g�[���[�̌`���v���Z�X�ɎQ�^���Ă����̂ł͂���܂����B����炪�����炷���_�ɔ�ׂ�A���w���璷��s���̐V�������o���Ⴄ���炢�͏������ꂾ�B �@���̐V�����̉����̏�ŃE�����@�����ƃ��N�U���키�V�[���͒��Ղ̃L���B�i�q�̋��͂������Ȃ������炵����Ԃ̃f�U�C���͉ˋ��A�������Ēe�ۗ�Ԃ�����A�ق��̍�i�ɏo�Ă����ԏ�̃A�N�V�����Ƃ̓X�s�[�h�����Ⴄ�B�����̗͂ŃS���S�����������Ȃ���A�E�����@�����͒܂��A���N�U�̓h�X�������ɓ˂��h���A�]�����~�߂�B���A���e�B�͊F���ł�����̂́A���Ȃ��Ƃ��I���W�i���e�B�͏\���������ƌ����Ă����B �@����ɂ��Ă����{������̍�i�Ȃ̂ɁA�L���X�g�̒��ɐ^�c�L�V�ЂƂ肵�����{�Ŋ���o�D�����Ȃ��Ƃ����̂́A�����ɂ��₵���B���Ƃ��E�����@��������{�ɌĂт悹����ƉƁE��u�c�̖��Ȃǂ́A���̋C�ɂȂ������ł��d���o�D�Ă�ꂽ�͂��Ȃ̂����i���̎Ⴂ����o�����̏��Ⓧ���∻�썄�ɂ�点�Ă��悩�����j�B �@����ɕ�������{�l�����������̂́A�����炭���n�č��l�ƃA�W�A�n�č��l�A�����ĉ��ĂŊ���Q�l�̓��{�l�t�@�b�V�������f�����B���ꂾ�����{�̌|�\�E�ɂ͉p��̂ł���l�ނ����Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂��낤�i���Ɏn�܂������Ƃł͂Ȃ����j�B �@�����A�t�Ɍ����Ȃ���{�ł̋����A�b�v������_���āA���ՂɗL�����{�l�o�D���L���X�e�B���O������͂��Ȃ������Ƃ������ƁB�����܂ł�����w�̖ڐ��͐��E�s��ɂ������B�����ɂ��܂��A�ނ�̐^���Ȉӎu�����ݎ��ׂ���������Ȃ��B �i�Q�O�P�R�D�X�D�P�T�D�L�j �����ꂴ��� �i�Q�O�P�R�N�A���j  �@�����m�N�����g�E�C�[�X�g�E�b�h�̊ēE�剉�ŃA�J�f�~�[�܂̍�i�܂Ɗē܂���܂�������̃����C�N�ŁB�I���W�i�������܂�ɑ傫�ȑ��݊����������ɁA�������ē��炱�̊�悪�������܂ꂽ���A���[�i�[���{�@�l�̃v���f���[�T�[�́A�{�Ђ����[�J�����̋����o���Ƃ͂ƂĂ��v���Ȃ������Ƃ����B �@���ē͐����J��̕�����A�����ېV���̉ڈΒn�ɒu���������B�J��Ԃ��Ȃ��l�H�I�Ȓ������䂾���ɁA�k�C���ɍ��ꂽ�L��ȃI�[�v���Z�b�g�́u�܂�ʼnf��̃Z�b�g�̂悤�Ȓ����݁v�ɂȂ��Ă���B�������������Ȍ����������ǁB �@���āA�����C�N�ł̃f�L�₢���ɁH�@�Q�O�N�O�Ɍ���Ŋς��I���W�i���ł͂��͂₤��o�������A�悭�������̂ŁA���������P�[�X�ł͂����Ă�������̑O��Ƀe���r�ōĕ��������B���Ȃ�J�b�g���ꂽ�o�[�W�����ł͂��邪�A����ׂĂ݂�Ɨ��ē��ǂ��P���A�ǂ���ς��Ă���̂����킩���ċ����[���B �@���ē̓X�g�[���[�W�J�Ƃ��������I�ȕ����ƁA�X�̃Z���t�Ƃ��������I�ȕ����ł́A�����قnj��T�d�����悤���B�o��l�����قƂ�Ǒ�������������肵�Ă��Ȃ��B �@�t�ɓƎ�����ł��o�����̂́A�ꕔ�̓o��l���̖����B���Ƃ��I���W�i���łł͑���������l���̃}�j�[�i�C�[�X�g�E�b�h�j���A�Ⴂ�܋��҂��̃L�b�h�i�W�F�[���Y�E�E�[�����F�b�g�j����d���̗U�����A�̂̑��_�l�b�h�i���[�K���E�t���[�}���j�𒇊ԂɈ������ށB����A�����C�N�łł͐̂̑��_�̋���i���{���j����l���̏\���q�i�n�ӌ��j��U���A������������҂̌ܘY�i���y�D��j������ɂ��ė���Ƃ����\�}�ɂȂ��Ă���B �@�������Ȃ��ς����̂��͊ē{�l�ɕ����Ȃ��Ƃ킩��Ȃ����ƂȂ̂����A���ʂɍl����X�g�[���[�ɃA�C�k���ʂ̖��肱�ނ��߂̕������낤�B�}�j�[�͗��璆�̎q�������̐��b���l�b�h�̍Ȃɗ��ނ��A�\���q�̓A�C�k�l�ł���S�Ȃ̎��Ƃɗa����B�I���W�i���łł͓��ɐ�Z�����ʂ̖��ɂ͐G����Ă��Ȃ����A�����C�N�łł̓A�C�k��e������a�l�̖T�ᖳ�l�Ԃ肪�P�̃T�u�e�[�}�ƂȂ��Ă���B �@�����]�v�ȉ��M�ƌ�����������낤���A�ݓ��R���A���Ƃ����ē̏o���Ɨ��߂Č������Ȃ��ᔻ��W�J����y������悤�B�����A�����ł��^���������C���_�́A����Ƃ͕ʂ̂Ƃ���ɂ���B �@�I���W�i���ł̓g���K�[�n�b�s�[�ȏ]���̐������ɑ���A���`�e�[�[�ł���A�K���}���̓q�[���[�Ȃ���Ȃ��A�l���E�����Ƃ͊ȒP�Ȃ��Ƃł��J�b�R�������Ƃł��Ȃ��Ƃ������b�Z�[�W��`������̂������B�����āA����ɗ��߂Đl�Ԃ̎コ�A�X���A�c������e�͂Ȃ��\���������̂������B �@�����炱���A�l�b�h�͓G���̕ۈ����i�W�[���E�n�b�N�}���j�ɍ��₳���ƁA�Ō�̓}�j�[�̐g���𖾂����Ă��܂����̂��B���邢�̓}�j�[�́A�������u���q���܂ŎE�����}�������v���Ƃɂ��Ĉ�̃G�N�X�L���[�Y�������A�����u�q�������ɂ����͌���Ȃ��ł���v�ƍ��肵���̂��B �@�Ƃ��낪���ḗA����Ɏ��ʂ܂Ō������点�Ȃ������B����ɂ͂Ȃ͂������́A�\���q�����q���܂ŎE�����Ɖ\�����͔̂G��߂�������Ȃ��ƏL�킹���B����ł͂܂����ł���B����ł̓q�[���[���B�g�����ꂴ��ҁh�ł͂Ȃ��A�g�����꓾��ҁh�ɂȂ肩�˂Ȃ��ł͂Ȃ����E�E�E�B
�G���h�E�I�u�E�z���C�g�n�E�X�@�@OLYMPUS HAS FALLEN �i�Q�O�P�R�N�A�āA�����F���Y���ށj �z���C�g�n�E�X�E�_�E���@�@WHITE HOUSE DOWN �i�Q�O�P�R�N�A�āA�����F�e�n�_�i�j  �@�A���Ɖ߂���ΔM����Y���B �@�X�D�P�P�e���̒���̓n���E�b�h�����l���[�h��F���������A���N���߂����������s�@���ė�����p�j�b�N�f���A���w�r���������f�B�U�X�^�[�f�悪����n�߁A���x�ɂ��Ĉ��肪�߂������N�́w�G���h�E�I�u�E�z���C�g�n�E�X�x�Ɂw�z���C�g�n�E�X�E�_�E���x�ƁA�č��́g�{�ہh���Q�x���N�����ꂽ�B �@���̂��Ƃ͎����������č��������_�I�V���b�N�⋰�|���璅���ɔ����������邱�Ƃ������Ă���B�u�A���Ɖ߂���ΔM����Y���v�Ƃ������Ƃ킴�̓l�K�e�B�u�ȈӖ��Ŏg��������������ǁA�����ł͑f���ɂ悩�����ł��˂ƌ����Ă����Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B �@�����A�č��l�̐��_�������S�ɂX�D�P�P�ȑO�ɕ��������Ƃ����ƁA�����Ă���Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B�����[�I�Ɏ����Ă���̂��f��̒��̓G�����B����f��ł̓h�C�c���A���f��ł̓\�A��\�V�C�ɓG���ɂ��Ă����n���E�b�h���A�X�D�P�P�e�����牽�N�����Ă��A����ɃC�X�����ߌ��h��G���Ƃ���f������Ȃ���ˁB �@�č��͕L��A�h�C�c�ɂ��\�A�ɂ��{�y��N������邱�Ƃ͂Ȃ������B�X�D�P�P�e���͓Ɨ��푈�ȗ����߂āA�č��{�y���G�ΐ��͂ɍU�����ꂽ���Ⴞ�����B���̋��|����⑊���̂��̂��������낤�B �@���������̓G�ΐ��͕͂č����ɐ[���Â��ɐ������Ă����҂����ł���A���̈ӂ��p���҂������������Ȃ�@���_���Ă��邩������Ȃ��B�ނ���h������悤�ȉf��i����͑P�ǂȃC�X�������k�ւ̔��Q���������˂Ȃ��f��ł�����j�͂ƂĂ��|���č��Ȃ��A��点���Ȃ��Ƃ����̂��A�n���E�b�h��č��l��ʂ̋��ʔF���Ȃ̂��낤�Ƒz�������B �@�Ƃ����킯�ŁA�w�G���h�x�̈����͖k���N�A�w�_�E���x�̈����͋��ړ��Ă̕č��l�ƍߎ҂Ƃ����\�}�ɂȂ��Ă���B�k���N�͕č��Ńz�[���O���E���E�e�����N�����\�����Ⴂ�������A���̂Ƃ���n���E�b�h�ł͐l�C�i�H�j�̓G���B�P�O���Ɍ��J�\��́w���b�h�E�h�[���x�ł��A�P���ɂ��ĕč��S�y���̂��Ă����i���肦�ˁ[�j�B �@����ɂ��Ă��A�Ȃ��ĔN�ɂQ����z���C�g�n�E�X����̂���邩�ˁB�n���E�b�h�ł͎��Ƃ��ĉZ��̊�悪�����i�s���邱�Ƃ�����̂����A�i�Љ�̕č��œ��쑛�����N���Ă��Ȃ��Ƃ����̂��A�܂��s�v�c�B�Ȃɂ����̂Q��A�z���C�g�n�E�X�̌x���g�b�v�������i���ꂼ��A���W�F���E�o�Z�b�g�ƃ}�M�[�E�M�����z�[���j�ł���_�܂œ����Ȃ���B �@�����A��掩�͓̂��H�ł��A�f�L�ɂ͂�͂荷�����悤�ŁA���ʔ����̂́w�_�E���x�̕��B�w�G���h�x�̓q�[���[�i�W�F�����h�E�o�g���[�j���哝�́i�A�[�����E�G�b�J�[�g�j���Ђ�����܂��߂ŁA���������q���C�Y�����@�ɂ��B����w�_�E���x�̓q�[���[�i�`���j���O�E�e�C�^���j�Ƒ哝�́i�W�F�C�~�[�E�t�H�b�N�X�j�̊|�����������[�����X�ŁA�o�f�B�f��̎���B���̂ւ�͂��ꂼ��̊ēi�A���g�����E�t�[�N�A�ƃ��[�����h�E�G�����b�q�j�̌��̈Ⴂ���o���悤���B �w�G���h�x���w�_�E���x���z���C�g�n�E�X�Ɋւ��铤�m���������ς��ŁA�����̂���l�ɂ͊y�����B�����č��łv�t���������P�X�X�S�N�Ƀz���C�g�n�E�X���������Ă�������ǁA������Ɖ������������ȁB �@����i�̂悤�Ȏ�i���g���A�m���Ƀz���C�g�n�E�X��苒����i���Ȃ��Ƃ��U������j���Ƃ��s�\�ł͂Ȃ������Ɏv����̂ŁA�x���W�҂͎��Ȃ�ʋ������X�����v�����̂ł͂Ȃ��������B �i�Q�O�P�R�D�W�D�Q�Q�D�L�j �A�b�v�T�C�h�_�E���@�d�̗͂��l�@�@UPSIDE DOWN �i�Q�O�P�Q�N�A�������A�����F����L�K�j  �@�ˋ�̐��E��`�����r�e��t�@���^�W�[�f��ł��A���̖{�����g���i�h�ł���ȏ�A��i�̐��E�ςɂ͑�Ȃ菬�Ȃ茻�������f�����B�č��Ŋi���_�c�����܂т������Ȃ����ߔN�́A�x�߂�҂ƕn�����҂����Z�n���A�O�҂���҂���悷��Ƃ����ݒ�̍�i���ڗ��悤�ɂȂ����B �@�����C�N�Łw�g�[�^�����R�[���x�͕x�T�w���C�M���X���A�n���w���I�[�X�g�����A���ɏZ�݁A�n�j���т��G���x�[�^�[�Ō�҂��O�҂ɒʋ����B���̏H�Ɍ��J�́w�G���W�E���x�ł͕x�T�w���O����ɋ���ȉq�����ׁA������Q�[�e�b�h�E�R�~���j�e�B�̂悤�ȗ��z�����`������B �w�A�b�v�T�C�h�_�E���@�d�̗͂��l�x�̕���́A�ǂ����̍P���n�ɂ���o�q�̘f�����B�Q�̐��͉�b���ł���قǂ̋�����������Ă��Ȃ����A�u��̐��E�v�ɂ͕x�T�w���Z�݁A�u���̐��E�v�ɂ͕n���w���Z��ł���B���̐��E�̏��N�A�_���́A��̐��E�̏����G�f���ɗ���������A�x�����Ɉ����������B�P�O�N��A�A�_���i�W���E�X�^�[�W�F�X�j�͊댯�����m�ŏ�̐��E�ɐ������邪�A�G�f���i�L���X�e���E�_���X�g�j�͋L���������Ă��āE�E�E�B �@�ʂ̐�������Ƃ͂����Ă��A�������͌��݂̒n���ƕς��Ȃ��B�ēE�r�{�̃t�A���E�\���i�X�ɂ́A���Ȑ��������n�����邱�ƂŁA�ϋq�ɃT�[�r�X���悤�Ƃ����Ӑ}�͂Ȃ������悤���B �@�����ɖ{��̃L���ƂȂ��Ă���̂́A�u��̐��E�v�Ɓu���̐��E�v�̏Z�l���A���ꂼ�ꎩ���̐��̏d�͂Ɏx�z�����Ƃ����ݒ�B���̂��߁A���Ƃ��u��̐��E�v�̏Z�l���u���̐��E�v��K�˂�A�u��ɗ����Ă����v���ƂɂȂ�B�����h���ɂ͑̂ɏd������邩�A���̐��E�̏Z�l�ɂ��܂��Ă��Ă��炤�����Ȃ��B �@�o�q�f�����A���͌����ɂ����݂��邪�A�d�͂͏�Ɏ��ʂ̑傫�����ɂ�����Ƃ����̂������̖@���B�f���`�̏Z�l������Ƃ����āA�f���a�̏d�͂��Ȃ��ȂǂƂ������Ƃ͌����ɂ͂Ȃ��B����ł����̔�Ȋw�I�Ȑݒ���������ƂŁA���Ƃ��Ώ�̎ʐ^�̂悤�Ȕ������V�[�������܂ꂽ�B�I�[�o�[�n���O������R���u��ɗ����Ă����v�G�f�����������߁A�_���X�g�́w�X�p�C�_�[�}���x�ɑ����g�t���܃L�X�h�����邱�ƂɁE�E�E�B �@���O�Ƀv���X������ǂ��_�ł́A���̃����E�A�C�f�A�łǂ��܂Œ��ڂ̉f�悪����̂��Ɣ��M���^���������A�\���i�X�ē͂��܂����Ƙb��c��܂��A��Q���z���郍�}���X�ɃR���f�B�A�����ᔻ�ɂ�����Ƃ����A�N�V�����܂Ő��肱��y��Ɏd���Ă��B�剉�̂Q�l�����ɍD���x�̍����o�D�����ɁA�������f��ɂȂ肻���ȗ\��������B �@�����NJēA�u���̐��E�̕����ɐ����ԐG��Ă���ƔR�Ă��N�����v�Ƃ����ݒ�ɂ����̂ɁA�A�_������̐��E�̃n���o�[�K�[��H�ׂ���A�G�f�������̐��E�̃J�N�e�������肷��̂͂n�j�Ȃ�ł������H �i�Q�O�P�R�D�W�D�Q�Q�D�L�j �I��̃G���y���[�@�@EMPEROR �i�Q�O�P�Q�N�A�āA�����F�Γc�q�j  �@���{�l�ɂ́i���Ɍ���̓��{�l�ɂ́j�������ɂ������A�č��ɂ͐��̉p�Y��哝�̂ɂ������Ƃ������_��������B�ނ炪�����͂ɒ����Ă���Ƃ͎v���Ȃ����A�����^�c�̎����͗L�\�ȃu���[�����S�����炢���Ƃ������z�Ȃ̂��낤�B �@����哝�̂̃W���[�W�E���V���g�����炵�ČR�l�����A�ߔN�ł͑���E��펞�̍ō��i�ߊ��������h���C�g�E�A�C�[���n���[����R�S��哝�̂߂��B�p�ݐ푈���̕ČR�g�b�v�������R�����E�p�E�G���͈ÎE������ďo�n��f�O�������A�ꎞ���A�ނ��u�č����̍��l�哝�́v�ɐ����@�^�����܂������Ƃ͋L���ɐV�����B �@�����I��S���قƂ�ǂȂ������Ƃ����A�C�[���n���[�Ƃ͑ΏƓI�ɁA��S���X�������Ƃ����̂��A�����R�̍ō��i�ߊ��������_�O���X�E�}�b�J�[�T�[���B�f�g�p�̃g�b�v�Ƃ��ē��{�̐�̓����ɓ��������ނ́A���鐭���I�ȓ��ɒ��ʂ���B�W���b�v�ɍ��ݍ����̕č����͓V�c�́g��h��v�����邪�A���l�_���܂����Y�����悤�Ȏ��ԂɂȂ�Γ��{�����͖������~�����A�̂Đg�̃��W�X�^���X�ɏo�邩������Ȃ��B�V�c�����Y���Ă����Ȃ��Ă����g�̐����I���ꂪ�h�炮�B���āA�ǂ�����H �@�����Ń}�b�J�[�T�[�i�g�~�[�E���[�E�W���[���Y�j�͈�v���Ă��A�S�ӔC���������Ԃ������œ��{�ʂ̃t�F���[�Y�y���i�}�V���[�E�t�H�b�N�X�j�ɓV�c�̐푈�ӔC�����肳�����E�E�E�Ƃ����̂��A���́w�I��̃G���y���[�x�̑�g���B �@�㔼�ɂ́A�ʉ������̃I���G�A��j�~����Ƃ���R�����A�^��������D�����߂ɍc�����U������i�I�j�Ƃ������A���������g���f���n�̃t�B�N�V�������}������Ă��邪�A�����̊ϋq�̒��ɂ́u�ւ��A���������j������������ł����v�ƉL�ۂ݂ɂ��Ă��܂��҂����Ȃ��炸�������ł͂���B �@���{�̉f�搻���Ђ͕s�h�߂ɖ����̂�����Ă��i�H�j�����ċߑ�̓V�c���f�扻���Ȃ����A�{��͕č����{�B�̕�����҂̕Љ��F���Y�����a�V�c�ɕ����A�����ɐb�����Ȃ��ČR�l�ƑΛ�����S�ׂ����A���{�����ւ̐ӔC�������A�������ꂵ�����͋C�������ĕ\�����Ă���B�ڋʂƂȂ�}�b�J�[�T�[�Ƃ̉��ʂȂǂ́A�C�b�Z�C���`���V�c�q���q�g�����������V�A���{�́w���z�x(05)�ɂ��ʂ�����߂�����Ă��邪�A���Ă��āA���ۂ̏��a�V�c�̋����͂ǂ��ł������̂��B �@�s�[�^�[�E�E�F�[�o�[�ē̉��o�ɂ͗��_�����B�߉q�����i������r�j�A�،ˍK��i�ɕ��듁�j�Ƃ��������݂̗v�l����A�t�F���[�Y�̈��������{�����A���i�����f从q�j�Ƃ��̕��e�i���c�q�s�j�Ƃ������ˋ�̐l���܂ŁA���悻���͂Ɍ�����L�����N�^�[����Ȃ�ˁB �@�A���Ȃ�̐����Ȃ���G�L�]�`�b�N�ł��Ȃ��A���m�l�ł���t�F���[�Y���Ȃ����̏����Ɏ䂩�ꂽ�̂����܂�œ`���Ȃ��B�r�{�Ƃ�����A�q���C���Ȃ���A�C�̗������Z���t�̂ЂƂł������Ă���Ă����B �@�����T���߂ȃL�����N�^�[�ł��w�^��̎�����̏����x�̃X�J�[���b�g�E���n���\���͂���Ȃɖ��͓I�������̂ɂƁA���{�l�Ƃ��ă{���L�̂ЂƂ����ꂽ���Ȃ������A�l���Ă݂�E�F�[�o�[�ɂ́w�n���j�o���E���C�W���O�x�Ńw���ȓ��{�l����{������`�����O�Ȃ�����̂������B �@����ȍႦ�Ȃ����{���o�D�w�̒��ɂ����āA��ԁi�Ƃ������A�B��j�P���Ă����̂��Ĕ��،M���B�V�c��⍲����{�������Ƃ��āA�Z�т��|�����������Ƀt�F���[�Y��}�b�J�[�T�[�Ɠn�荇���A�Ƃ����G�X�Ƒ�����͂��炩���Ă݂�����̐[���͂܂��ɐ�i�B �@���������l�������ۂɂ����Ȃ�f�g�p���u�W���b�v���ꂸ�v�Ǝv�������낤���A�{����ς��č��̊ϋq���u�s�v�c�̍��A���{�v�ւ̊S���D���x�����߂��͂����B�Ĕ������J��҂����ɖS���Ȃ����̂��c�O�łȂ�Ȃ��B �@���Ȃ݂ɔނ��������։���O�Y�͎��݂̐l���ŁA�{��̃v���f���[�T�[�ł���ޗNj��z�q�̑c���Ȃ̂��Ƃ����B���{�l�L�����̒��ŗB��A���͓I�������̂��v���f���[�T�[�̐g���Ƃ����̂́A�ʂ����Č̈ӂȂ̂����R�Ȃ̂��B�܂��A����̓v���f���[�T�[�Ƃ��Čւ�ׂ����ƂȂ̂��A�@���������ޗNj�����ɂ��Ў��₵�Ă݂������̂ł���B �i�Q�O�P�R�D�V�D�Q�T�D�L�j ���[�}�ŃA���[���@�@TO ROME WITH LOVE �i�Q�O�P�Q�N�A�ā��Ɂ����A�����F�Γc�q�j  �@�X�g�[�J�[�E�l�̃j���[�X�����тɁu�Ȃ��ĐԂ̑��l������قLj�����̂��H�v�Ɨ���s�\�̋C���ɂȂ�B�u����A����Ȃ͈̂�����Ȃ��v�ƌ����l�����邩������Ȃ����A���Ƃ��u�����v���̑��̌��t�Ō����������Ƃ���ŁA������葼�l���d�v���ɂȂ��Ă��܂��Ă���Ƃ�����{�\���͕ς��Ȃ��B �@�l�ԁA��ԑ厖�Ȃ͎̂����̕�炵�ł���A�����̍K���ł���A�����̍��Y�ł���A�����̐M�p�ł���B�Ȃ̂ɂȂ����̐l�����́A����Ȏ��ԂƘJ�͂��₵�A�Љ�I�����������A�ʂĂ͎������Y�����ɓ���Ă܂Łi���邢�͔ƍs��Ɏ��E���Ă܂Łj�A�Ԃ̑��l�ɂ���قǍS�D���Ă��܂��̂��B �@��������Ȃ��A���͐̂̃K�[���t�����h���ǂ����Ă��悤�ƑS�R�S�Ȃ����ǂˁB����A�N�������������炱���u����҂͓��X�ɑa���v���Č�����ł���B �@�����Őӂ߂���ׂ��́u�^���̐l�v���́u�Ԃ����v���̂Ƃ����ʃ{�������܂���₷�������ɐ������ޏ����Ƃ▟��Ƃ�f���Ƃ������Ǝv���ȁB �@�܂Ƃ��ȓǎ҂ɂ͂��Ȃ����Ă���������Ǝv�����A���Ȃ������Ȃ��̔z��҂ƌ��������̂́A���肪�^���̐l����������ł͂Ȃ��A�P�Ȃ�^�C�~���O�Ə�������̔z�܂��B�m�荇���̂��Q�N�A�O��ɂ���Ă�����A���Ȃ��͂��Ȃ��̔z��҂ƌ����Ȃ��Ă��Ȃ��i���������Ⴄ�j�B���Ȃ��̔z��҂Ɠ������炢�i���邢�͂���ȏ�Ɂj���Ȃ��Ƃ��܂��s���l�́A���Ȃ��̎��͂������Ă��W�l�͂���i�����炱���ǍD�ȕv�w�W���ێ����Ă����ɂ́A�s�f�̓w�͂��K�v�Ȃ킯�ł���j�B �@�܂��Ă�P�ɂ��t���������������̑��肪�^���̐l�ł��낤�͂����Ȃ��ł���B���܂��܈ꎞ�I�ɑ����荇���������߂ɂ��ꂾ���|���ڂɑ��킳���̂�����A�X�g�[�J�[�����̔�Q�҂̕��X�ɂ͖{���ɓ�����ւ����Ȃ��B�j�R���X�E�X�p�[�N�X��A�ӔC�����I �@�A�����J�E�o��A�����h���A�o���Z���i�A�p���ʼnf����B���Ă����E�f�B�E�A�������A�V���ȕ���ɑI�͉̂i���̓s�A���[�}�B�A�����̃R���f�B���āA���ɂ͌y�����ĂP�W�O�O�~�����̂����������Ȃ��悤�ȍ�i��������ǁA����͏��̒��ɂ��^�����܂A�o�����X�̂悢�Q�����Ɏd�オ���Ă���B �@�o�ꂷ��̂͂���ȍ�������������B ���������̃K�[���t�����h�̗F�B�Ɏ䂩�ꂿ�Ⴄ���w�� ����������̉f��X�^�[�ƒm�荇���ĕ����オ��V���̍� �����w���Ȃ��ƋU��H�ڂɂȂ�V���̕v ���L���ɂȂ����r�[�ɏ��V�т��n�߂钆�N�I���W �@�A�����́u�^���̐l�v�Ȃ�ĉR���ς��͐M���Ă��Ȃ�����A�o��l�������́i�ЂƂƂ�����������Ɂj�������ƕ��C����B���́u�ЂƂƂ�����������Ɂv�Ƃ����̂��|�C���g�ŁA���킸���C�����Ⴄ�l�Ԃ�������T�C�R�p�X���B�����Ď��̈ӌ��ł́A�u�^���̐l�v��M���鎋�싷��ȘA�����A�x�N�g���͐^�t�̃T�C�R�p�X�B���C���������Ƃ��Ƃ͕ʂɎv��Ȃ�����ǁA�����������������������ԐM�p�ł���C�����邼�i�������u�ЂƂƂ�����������ɕ��C�����Ȃ��v�Ƃ����I�������肾�낤�j�B �@���C�̑��肾���ĉ^���̐l�Ȃ��Ⴀ��Ⴕ�Ȃ��B���w���i�W�F�V�[�E�A�C�[���o�[�O�j�������̂͒m�������Ԃ�̎��ȃ`���[���i�G�����E�y�C�W�j�����A�V���Ȃ��g��������Ⴄ�f��X�^�[�͍D�F�ȃf�u�e�����B���ڔ��ځB�X�g�[�J�[�����̔Ɛl�����ɂ��N���������Ă�����悩������ˁB���̒��x�̏��A���܂�Ƃ��邶��Ȃ��̂��āB �i����͈�ʘ_��_���Ă���̂ł���܂��āA��Q�҂̕��X����M����Ӑ}�͂���܂���B��Q�҂̕��X�����ہA�������Ƃ�Ɛl�Ɍ����Ă���Ǝv���j �@���w������H�ɗ����тɌ���āu���s�v�ɃX�g�b�v�������悤�Ƃ���l���̐�y�i�A���b�N�E�{�[���h�E�B���j���ʔ����B�ꉞ�����̌��z�ƂƂ��đ��݂���̂����A����������I�ŁA�w�V�b�N�X�E�Z���X�x�̃u���[�X�E�E�B���X�̂悤�Ɏ��͂̐l�ɂ͌����Ă��Ȃ��l�q�B�Z�@�Ƃ��Ă͂�����u�S�̐��v�u�ǐS�̐��v�Ƃ��ċ@�\���Ă���̂����A�A�����̂����͋��ȏ��ǂ���ł͂Ȃ��A���Ƃ��l��H���Ă���B �@���C���O�̐V���ȂɁu��炸�Ɍ��������A����Č��������������v�ƌ��킹�Ă���̂��܂�����B���Ԃł͐��Ƃ���Ă��邱�̋����ɏ悹���āA�ǂꂾ�������̐l���{���������]�V�Ȃ�����Ă��邱�Ƃ��B����Ȑ��Ԃ̕��������������A�����ꗬ�̃V�j�J���E�R���f�B�B���̐l�̓��͘V���Ȃ��ȁB �i�Q�O�P�R�D�V�D�Q�D�L�j �J���e�b�g�I�l���̃I�y���n�E�X�@�@QUARTET �i�Q�O�P�Q�N�A�p�A�����F�I���Ƃݎq�j �Q�T�N�ڂ̌��y�l�d�t�@�@A LATE QUARTET �i�Q�O�P�Q�N�A�āA�����F���Y���ށj  �@���N�̃A�J�f�~�[�����́u�f��Ɖ��y�v���e�[�}�Ƃ������ƂŁA�V���[���[�E�o�b�V�[�ƃo�[�u���E�X�g���C�U���h���������肾���āA���N�̃q�b�g�Ȃ��I�����Ă����B����͂����̂����A���ꂼ��̉̂��o�����Ă����������l�A���Ȃ��Ȃ�������Ȃ��������H�@�̂͂���Ȃɂ��܂������̂ɂ˂��E�E�E�B �@���y�Ƃ̐h���Ƃ���́A���O����Ⴂ���Ɠ����p�t�H�[�}���X�����҂���Ă��܂��Ƃ���ł͂���܂����B�V�����X�|�[�c�I��ɂ͒N������Ȃ��Ƃ����҂��Ȃ��̂ɁA�V�������y�Ƃɂ͊��҂���B�ؗ͂��x���ʂ�������̂�����A����͖����ȑ��k�Ȃ̂����B �@����ȘV���̔߈������̂߂��̂��A�_�X�e�B���E�z�t�}�������K�z���́w�J���e�b�g�x�B����ƂȂ�u���y�Ɛ�p�̘V�l�z�[���v�́A�����ǂ����ʼn̂≉�t���N��������A��������y�������낤�ȂƎv�킹��ꏊ���B �@���̔��ʁA�������Ă��鉹�y�Ƃ����́A��������̈⍦��C�o���W�������������܂܁B���͂�l�C�̍��Ƃ����͎̂c���Ȃقnj��R������̂�����A��ɗ����Ă����҂̓v���C�h���̂Ă�ꂸ�A���ɂ����҂͔ڋ��ɂȂ�A�����҂ɂƂ��Ă͂Ȃ��Ȃ��V�r�A���낤�ȂƎv�킹��B �@����Ȍ�������̊����ɏœ_���i�����̂��A����̂悭�����w�Q�T�N�ڂ̌��y�l�d�t�x���B�t�B�[�`���[����Ă���̂͐��E�I�ɕ]���̍������y�J���e�b�g�ŁA�N���̃`�F���i�N���X�g�t�@�[�E�E�H�[�P���j�����ނ�\���������Ƃ���A�Q�T�N���̂����݂���C�ɘI�悷��B��Q�o�C�I�����i�t�B���b�v�E�V�[���A�E�z�t�}���j�͑�P�o�C�I�����i�}�[�N�E�C�o�j�[���j�̈������Ė��ł��邱�Ƃɕs����R�炵�A�Ȃł���r�I���i�L���T�����E�^�[�i�[�j�������ɖ������Ȃ����Ƃɂ����B�u�E��v�̊m���Ɏ������̃S�^�S�^�������N���āA�J���e�b�g�͕���̊�@�ɁE�E�E�B �@���y�ƊE�̑f�l�ɂƂ��ẮA�u�ւ��I�v�Ǝv���悤�ȃZ���t��G�s�\�[�h���������肱�܂�Ă��ċ����[���B��Q�o�C�I�������u���V�[�Y���͈Õ��ł�낤�v�ƌ����A��P�o�C�I�����́u�y���ɏ����������ɂ����v�z���\���v�Ɣ�����i�����N���V�b�N�̉��y�Ƃł���`���Ⴄ�̂ˁj�B�㊘��T���`�F���́A�Ӓ��̌����X�J�E�g����Ƃ��A�u�N�̂Ƃ���̓s�A�m�g���I�����炤�܂��`�F���͕K�v�Ȃ����낤�v�ƁA���o�𔗂�i�ւ��A�����������̂��j �B �@�����S�҂̃��`�[�t�ƂȂ��Ă���x�[�g�[�x���́u���y�l�d�t�ȑ�P�S�ԁv�����j�[�N���B���I�Ȃ��Ƃ͂悭�킩��Ȃ����A�x�[�g�[�x�����S�V�y�͂�r��邱�ƂȂ����t���ׂ��ƌ����c�������߂ɁA���t�҂̓`���[�j���O�������Ă����̂����m�Ńv���[�𑱂��邩�A���f���ă`���[�j���O���邩�ŔY�ނ̂��Ƃ����B����Ȋy�Ȃ̐��i���A�����݂̍L����S�l�̊W�ƃ����N���A�[�݂̂���l�ԃh���}����肠���Ă���B �@�ēE�r�{�̃��[�����E�W���o�[�}���͂��Ƃ��ƃN���V�b�N�ɑ��w���[���l�Ȃ̂��Ǝv������A���͖{��͐V���Ȏ�ނɂ���č�肠�������̂ł���炵���B�`�F���������ĉ��U���������l�d�t�c�A���������o�[����҂������Ă���Ɖ\�̂������l�d�t�c�A�Q�l�̃o�C�I���j�X�g����P�Ƒ�Q�����݂ɒe���Ă���l�d�t�c�Ȃǂ����f���ɁA��l�������̎l�d�t�c����肠�����B �@�N���V�b�N�̉��y�Ƃ͗B��Ƒ������璷�������B��l���������u�l���̑�P�S�ԁv���A���ꂩ��f���Ȃ���t�ő����Ă����̂��낤�B �i�Q�O�P�R�D�V�D�Q�D�L�j �V�g�̕����O�@�@THE ANGEL'S SHARE �i�Q�O�P�Q�N�A�p�������x���M�[���ɁA�����F���c���q�j  �@�h���J���́w�₳�����L�X�����āx�̓��[�v����B �@�Q�O�O�S�N�Ƀ����[�X���ꂽ���̋ȁA���ł��N�ɂP�x���炢�ǂ����̂��X�̗L���ŕ������Ă��邱�Ƃ�������ǁA�����A���̂��тɂR���Ԃ��炢���̒��ŃO���O���O���O���������[�v��`�����Ⴄ�B �@�����f�B��̎��ɌJ��Ԃ��̃p�^�[�����������߂��A����Ƃ��P�ɖ��Ȃł��邽�߂��A������Q���O�ɃW���̗L���Œ����Ă���A�u����炵�`�w���₵�`�v�u���łā`��������ā`�v�ƁA�P�����A���̒��ʼnQ�����������Ă���B �@���̒��Ń��[�v���Ă��邾���ł��d�����͂��ǂ�Ȃ��̂Ɂi�t���[�����X�ɂf�v�͂Ȃ��B�Ӑ}������A�x�͂������邪�i��j�j�A����ɍ���̂́A�������a�����݂����ɏ���߂āu�Ȃɂ������`���`��o���ā`�v�Ƃ��u���Ɂ`����ꂽ��`���`�v�Ƃ��̂����Ⴄ���ƁB��l��炵�����炢���悤�Ȃ��̂́A�Ƒ��������炯�������p���������Ǝv���B �@���ł���ȃ}�N����U�������Ƃ����ƁA�P���E���[�`�ēɂ́w�₳�����L�X�����āx�Ƃ������삪����������B�����ĐV��w�V�g�̕����O�x���A�����O���X�S�[��ɂ����Ǎ삾�����B �@����ɂ��Ă����[�`�͂��܂���ˁB���̍�i�A�u�\�͓I�Ȑ��������h���d�}���̎�҂��A�l�l�̂��̂𓐂ނ��ƂŐl���̈ꔭ�t�]��}��b�v�Ɨv�邱�Ƃ��ł�����ǁA�ɂ�������炸�ӏ܌�̐S�����͑u���ɂ��ĉ������B �@�����Ȃ錴���̂ЂƂ́A��l���̃��r�[�����܂��l�X�̑��`���f���炵�����Ƃ��B���Ƃ����r�[�̎q���Y�ޗ��l�̃��I�j�[�́A���ăP�K����������Q�҂Ƀ��r�[��������ƌ������킹�A�u���Ȃ����X�����Ȃ��Ȃ�A�����Ƃ�ł��̎q����Ă�v�ƁA���r�[�ɔ���B�ی�ώ@���̂悤�Ȏd�������钆�N�j�n���[�́A�n�����Ɩ��m�䂦�ɓ����O��Ă�����҂����Ɛ^���Ɍ��������A�e�g�ɂȂ��Ď�������ׂ̂�B �@���[�`�Ƌr�{�̃|�[���E���o�[�e�B�́A���������l�X�ƃ��r�[�Ƃ̐G�ꍇ�����A���Q�̃��[���A�������Ȃ���A�y���ɒԂ�̂ł���B���K�L�ǂ��̍X���Ɏ��S�Ȃ����g�ރn���[���A�u�������Ƃ͐܂荇�������́H�v�ƃ��r�[�ɕ�����āA���t��������Ⴄ�V�[���Ȃ�āA�ڗ����Ȃ����ǐȂ���ˁB���܂��Ȃ��B �@���r�[�̃^�[�Q�b�g���M����̍����E�C�X�L�[�̈ꕔ�������Ƃ����_���A�����ЂƂ̃g���b�N�B�M����E�C�X�L�[�Ƃ����̂́u���e�ʁ������b�g���v�ƌ����Ɍ��܂��Ă�����̂ł͂Ȃ��炵���A�I�[�N�V�����O�ɂ����������l���̐l���e�C�X�e�B���O�����Ă�����Ă���B�܂��A�]�݂̕i����ɓ���邽�߂Ȃ瑽���̖@��}�i�[�͔Ƃ��Ƃ����R���N�^�[�̋��z�Ԃ����������̂ŁA�킸���ȗʂ������ߎ�郍�r�[�̍s�ׂ��A���ΓI�ɂ��������Ȃ��̂ɂ͌����Ȃ��Ƃ����d�|���ɂȂ��Ă���B �@�����ЂƂ����Ȃ�A�E�C�X�L�[�͒M�ŏn������Ă�����Ԓ��ɁA���R�ɏ������������Ă������̂Ȃ̂��Ƃ��B���ꂪ�܂�́u�V�g�̕����O�v�Ƃ����^�C�g���̖{���̈Ӗ��Ȃ̂����A���r�[�������߂��E�C�X�L�[���A���I�j�[��n���[���͂��߂Ƃ��钇�Ԃ����ɖ]�O�̍K���������炷�̂�����ƁA������܂�����Ӗ��A�V�g�̕����O�ł������̂��Ǝv���Ă���̂ł���B �@���Ȃ݂ɂ��̉f��A�őO��̈�Ԓ[�����Ƃ������Ƃ����Â炢�ȂŌ���͂߂ɂȂ����B��f�J�n�S�O���O�ɑ����ɒ������̂����A�������ꂪ�Ō�̂P�Ȃ����������ȁB�����Ȃ�Ɖ^�������̂������̂��悭�킩��Ȃ��B �@����ł����̂͂T���P���̉f��t�@�����Ӄf�[��������������ł͂Ȃ��A���ꂪ����e�A�g���V�l�}�ّO�̍Ō�̏�f��i������B �@���̌���A�V�l�R�������y����ȑO����A�q�Ȃ̒i����傫��������ϊӏ܂��₷���v�������B�������ɒP�ٌn�V�A�^�[�Ƃ��Ă̑S�����}�����b����K�[�f���V�l�}�╶�������E�V�l�}���A�O��̐l�̓��ŃX�N���[���̉������B��Ă��܂��u���Ԃ��I�v�I�Ȑv�������̂Ƃ̓G�����Ⴂ���B �i���Ȃ݂Ƀ��E�V�l�}�̏�f��i�ɏc���������̂��̂������̂́A��������������ʂ̉����ɕ\������ƁA�O�̐l�̌㓪���łقƂ�Ǔǂ߂Ȃ��Ȃ邩�炾�j �@����͒P�Ƀe�A�g���V�l�}���ق��邾���ł͂Ȃ��A�g�Ǝ�h�̃z�e�����m������̂����đւ��ɂȂ�炵���B�����ǁA�����̉f�拻�s������l����ƁA�V���ȃr���ɂ܂��f��ق�����\���͒Ⴛ���ł��ˁB�i�q�̉w���班���������炻���p�ɂɒʂ����킯�ł͂Ȃ�����ǁA���I�Ȍ��ꂪ�܂��ЂƂ�����̂͂�����Ǝ₵���B �i�Q�O�P�R�D�T�D�S�D�L�j �v���C�X��r�����h��U��p�C���Y�^�h�� �@THE PLACE BEYOND THE PINES �i�Q�O�P�Q�N�A�āA�����F�H�j  �@�x�m�g�c�s�ɏZ��ł����c���݂̂���A�e�ɘA����A�T�[�J�X�ɍs�����悤�Ȋo��������B�܂����S�������Ȃ����̍��������炵���A�����܂ł��u�T�[�J�X�ɍs�����o���v�ł͂Ȃ��u�T�[�J�X�ɍs�����悤���o���v�ł����Ȃ��̂����A����ł����o�ł͂Ȃ��ƌ������̂́A�o�C�N�ɏ�����l�����a�����[�g���̋��Ԃ̋����ő�����|���A�i����́u�����悤���o���v�ł͂Ȃ��j�u�����o���v�����邩�炾�B �w�v���C�X��r�����h��U��p�C���Y�^�h���x�Ń��C�A���E�S�Y�����O��������̂́A�܂��ɂ��̌|���ړ��V���n�Ō�����j�B����̂͂��̔ނ��ӊO�ɑ����ޏꂵ�Ă��܂��̂ɂ́A�q�b�`�R�b�N�́w�T�C�R�x�Ɠ��l�ɋ�������邪�A����͕���̍\���Ɛ[���ւ���Ă���B��f���ԂP�S�P���̂��̍�i�A�f��R�{���̓��e�Ȃ̂ł���B���邢�͂R�b����Ȃ�A�쏬�����A�P�{�̉f��Ɏd���Ă��Ƃ�����ۂ��B �@�ŏ��̃p�[�g�̓S�Y�����O������j�Ō^�̒j���[�N���A�m��Ȃ��Ԃɂł��Ă������q�Ƃ��̕�e���~�[�i�i�G�o�E�����f�X�j��{�����߂ɁA��s�����Ɏ����߂�b�B����͂����̕����ɂ͈Ⴂ�Ȃ��̂����A���łɑ��̒j���ƈ��肵����炵��z���n�߂Ă������~�[�i�́A�ނ��o���̐n�̂悤�ȃ��[�N���ƑP�I�Ɏ��������Ɗւ������ڂ��Ƃ��邱�Ƃɍ��f����B �@��Q�̃p�[�g�́A���[�N��ǂ��Ă����V�Čx���̃G�C�u���[�i�u���b�h���[�E�N�[�p�[�j���A���s�����x�@�g�D�̒��ŋ��n�Ɋׂ�A���ƌւ����邽�߂ɗ����オ��b�B�Ƃ����Ă��G�C�u���[���g�A�~�X�^�[�E�A�����J�I�Ȑ��`���ł͂Ȃ��A�ނ���v�Z�����j�ł��邾���ɁA�ς�҂̓X�g�[���[�ɒP���ȑP���̕������Ă邱�Ƃ��ł��Ȃ��B �@��R�̃p�[�g�͂P�T�N��B�X�|�C�����ꂫ�����G�C�u���[�̑��q���A�܂�����炷���[�N�̑��q�Ɉ������e����^���Ă����B���[�N�̑��q�́A�����̕��e�ƃG�C�u���[�Ƃ̈�����m��A���Q�S�������点��B�l�I�ɂ́u����̃J�^�J�i�\�L�{�_�T������v�Ƃ����p�^�[���̖M��͍D���Ȃ��̂����A�{��́u�h���v�̓X�g�����D�ɗ������B �@�S�Y�����O�ƃN�[�p�[�́A�������N�Ђ��Ђ��Ɛl�C�㏸���ŁA���������U���Ă��炦�Ă��邵�A�����d���ʼn����Ă�����B�����ēE�r�{�̃f���N�E�V�A���t�����X�́A����ȂQ�l�̃X�^�[���Ɉˑ����Ȃ��A���ɂ܂��߂ȉ��o�������B���[�N�ƃG�C�u���[�Ƃ����L�����N�^�[�ɂ́A�P���ȑP�ƈ��Ƃ̓_�ł͊����Ȃ��A�l�Ԃ̕��G�ȋƂ��_�Ԍ�����B �@�V�A���t�����X�̐^�������S�Y�����O�ƃN�[�p�[�ȏ�ɔ��f����Ă���̂��A�G�o�E�����f�X���B�n���E�b�h�f��ɓo�ꂷ�郉�e���n�����́u�z�b�g�ŃS�[�W���X�v���u�������ږ��v�̂ǂ��炩�ł���ꍇ�������̂����A�����f�X�͌��킸�ƒm�ꂽ�O�҂̓T�^�B�Ƃ��낪�{��̔ޏ��́A�������o��̃V�[������S�R���l�Ɍ����Ȃ���ˁB�X�b�s���ۂ����A���͌��܂��Ă��Ȃ����A�����L�ӂ�Ղ�B����ł��i�Ƃ������A����䂦�Ɂj�����f�X�͊m���Ɉ��ނ����B�������₩�ɕ�炵�Ă������������Ȃ̂ɁA�^�C�v�͈Ⴆ�NjƂ̐[���Q�l�̒j�ɐl��������������郍�~�[�i���������B �@���~�[�i�ƌ������A���[�N�̎q�����䂪�q�Ƃ��Ĉ�Ă鍕�l�j���R�t�B�i�}�n�[�V�����E�A���j�̑��`�������B�ϋq�͓����A�S�Y�����O�Ɋ���ړ����ĊςĂ��邩��A�u�V���O���}�U�[�̎�݂ɂ�����ŁA���~�[�i�����̂ɂ��Ă��܂����C���ȓz�v���Ǝv���̂����A���ɂ��炸�B���ۂ̂Ƃ���A���ߓI�ȃ��[�N��A��S�I�ȃG�C�u���[�Ƃ͑ɂ��Ȃ��A����Ίϋq�̗ǐS�̉��g�Ȃ̂��B�R�t�B�����}�Ȃ�����ЂƂ��ǂ̐l���Ƃ��ĕ`����Ă��邩��A���t�̒[�ɐl�퍷�ʈӎ����̂�������G�C�u���[�̑��q���A�Ȃ��̂��ƃN�\�b�^���Ɍ�����B �@�h���}���������ł͂Ȃ��A�A�N�V�������o�ْ̋������Ȃ��Ȃ��̂��́B���ł��������郋�[�N�ƒǐՂ���G�C�u���[���A�������h���J�����Œǂ����V�[���͈������B�|�X�g�v���_�N�V�����ł��Ȃ�̃R�}�������Ă���̂ł͂���܂����B���̂��߂Ɋϋq�͐S�I�����h�邪����A��ʂ���ڂ𗣂����Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�B �@���Ȃ݂ɕ���ƂȂ�̂̓j���[���[�N�B�̓c�ɒ��X�P�l�N�^�f�B�ŁA���z�[�N��ɗR�����邱�̒������p��ɒ����Ɓu�v���C�X�E�r�����h�E�U�E�p�C���Y�i���̌������̏ꏊ�j�v�ɂȂ�̂��Ƃ��B���`��A����Ȃ��̂����̂܂ܖM��Ɏg���Ă��Ȃ��B��͂�V���v���Ɂw�h���x�ł����Ăق������������B �i�Q�O�P�R�D�T�D�S�D�L�j �I�Y�@�͂��܂�̐킢�@�@OZ: THE GREAT AND POWERFUL �i�Q�O�P�R�N�A�āA�����F���Y���ށj  �@�����m�w�I�Y�̖��@�g�x(1939)�̑O��杁B�������|���̃y�e����Y�������I�Y�������ɂ��āu�̑�Ȗ��@�g���v�̍��Ɏ��܂����̂����A�V�S�N�̎����o�ĉ�肷�������B �@�R�X�N�ł̒��쌠�̓��[�i�[�������Ă���̂������ŁA����̃f�B�Y�j�[�łɂ͋���ɂ����������̃��`�[�t���o�Ă��Ȃ��B�Ƃ͂����u�������E�̓��m�N���A�I�Y�̍��͑��V�R�F�v�Ƃ����R�X�N�ł̃L���Ƃ�������A�C�f�A�����̂܂ܓ��P�i���p�H�j����Ă��邠����ɁA�m�I���L�����s�ޖ����Ɠ�����\��Ă��܂��ˁB �@�P�X�W�V�N�́w�C�[�X�g�E�B�b�N�̖��������x�ł́A���̂���{�������V�F�[���A�~�V�F���E�t�@�C�t�@�[�A�X�[�U���E�T�����h���̋������b����Ă��A�{��ł̓~�V�F���E�E�B���A���Y�A���C�`�F���E���C�Y�A�~���E�N�j�X�������ɕ����Ĕe�������B �@���C�Y�ƃN�j�X���o���Ƃ����ݒ�͉��ƂȂ��[�����B��̌n��������������ˁB�ʔ����Ǝv�����̂́A���{�l�̃C���[�W�ǂ���A���̂Q�l���u���������v�ɁA�����ăE�B���A���Y���u���������v�ɃL���X�e�B���O����Ă��邱�ƁB�u���ǂ���v��u�L�c�����ρv�ɂ��ӂꂽ���m�����̒��ɂ����Ă��A����ς�N�b�L�������Z����͖����C���[�W�A�ۂ������n���Ȋ�͐����C���[�W�ł���炵���B �@�q�[���[�ƊԈႦ��ꂽ�������A��x�͉����̔���͂��������A�����Ȃ�ł͂̓��Z�����Đ^�̃q�[���[�ɁB�悭����ؗ��Ăƌ����Ă��܂�����܂ł����A���������X�g�[���[�͍��܂ƍċN�A���Ȕے�Ǝ��ȍm��̃o�����X����悭�ۂĂ�̂ŁA���R�Ɋϋq���爤�����i�ŋ߂ł̓A�j���f��́w�����S�x�������f�L�������j�B �@�W�F�[���Y�E�t�����R������`���P�Ȋ�p�t���A�������I�Y�̍��Ŗ��@�g���ɍՂ�グ���A�����ƕ���ɂ��ėL���V�B�������������ɂ́A����ȃI�Y�̔ڏ����͂����ʂ��B���n�ɗ������ꂽ��l���́A������̂��߂ł͂Ȃ��A�����ɋꂵ�ޖ��O�i�ƁA����̌ւ�j�̂��߂ɗ����オ��E�E�E�B �@�T���E���C�~�ēƋr�{�Ƃ����́A�I�Y���������E�Ŏg���Ă����X�q��ԁA�ڒ��܂Ƃ�������p�̏�������A���̂܂܉f��̏�����Ƃ��Ă��������B�I�Y���Ō�Ɏg���u��Z�v���A�R�X�N�ł̃X�g�[���[�ƌ����Ƀ����N�������A�C�f�A���f���炵���B �@�����̏�������䂦��͎������啨���Ɓi�������́A�啨�ɂȂ��Ɓj���Ⴂ���Ă��邱�ƁB���������ɂȂ��Ď������Ȃ݂�A�ӊO�ɑ啨���m��Ȃ����Ƃ����Ēm���Ă���B�����ɗF��̗͂�������ΕS�l�͂��E�E�E�ƁA�Ȃ���������f�B�Y�j�[�f��̏p���Ƀn�}�����C�������A�㖡�͌����Ĉ����Ȃ��B������̃T���E���C�~�ɂ܂ł���ȉf����B�点���Ⴄ�����肪�A�f�B�Y�j�[�����̐^�́u���́v�Ȃ�ł��傤�ˁA�����ƁB �i�Q�O�P�R�D�R�D�Q�Q�D�L�j �W�����S�@�q���ꂴ����@�@DJANGO UNCHAINED �i�Q�O�P�Q�N�A�āA�����F���Y���ށj  �@����ς�^�����e�B�[�m�̉f��͖ʔ����킠�B �w�W���b�L�[�E�u���E���x(97)�ȍ~�͊����̂̂悤�ȉf�����ē��Ă����Ǝv������A�O�X�N�́w�C���O�����A�X�E�o�X�^�[�Y�x�Ŋm�M�ƓI�ȍău���[�N�B�����ĂR�N��̖{��ŁA�܂��܂��f��t�@���̊��т���������B �@�����[���̂́w�C���O�����A�X�`�x�Ńi�`�X�h�C�c��O��I�Ɉ��ʂɂ����^�����e�B�[�m���A���x�́u���l���ʂ̂Ȃ��h�C�c�v�Ƃ̑Δ�łP�X���I�̕č����l�Љ�����ʂɂ��Ă���Ƃ���B�����A�f���ʔ������邽�߂Ȃ牽�ł�����Ȃ�ł��ˁB�z������ɁA�^���͋`���ɋ���ĂƂ��A�Љ�����e�������Ƃ��ł��̂Q����B�����킯�ł͂Ȃ��Ǝv���B�i�`�X�����l���ʂ��A�ނɂƂ��Ă͉f���ʔ������邽�߂̑f�ށB���̂����ς肵�������́A�����������������قǂ��B �@����ɂ��Ă��č��Љ�����x�����ɂȂ�������ł��B�ق�̔����I�O�ɍ��l�����l���Ƃ������R�Ŕ����ɂ��Ă������ŁA����ȉf�悪����Ȃ�āB���Ƃ��P�X�W�W�N�́w�~�V�V�b�s�E�o�[�j���O�x�́A���l�o�D�̃W�[���E�n�b�N�}���ƃE�B�����E�f�t�H�[���u�l�퍷�ʂƐ키�q�[���[�v�Ɏd���ĂȂ���ΐ��삷�邱�Ƃ��ł��Ȃ������B���l���j�j�j���������f�����������āA�N���������o���Ȃ��������A�N���ςɂ����Ȃ��������낤���炾�B �@�������Q�P���I���}�������A���l�o�D�̃W�F�C�~�[�E�t�H�b�N�X�����l���E���܂���w�W�����S�x������Ă��A�^�����j�j�j�ɋ������ꂽ�Ƃ������悤�ȃj���[�X�́A���̒m�����`����Ă��Ȃ������B�I�o�}���哝�̂ɂȂ����i�Ȃꂽ�j�̂́A�P�ɔނ̌l�I�Ȏ�����l�C�Ɉˋ����Ă���̂ł͂Ȃ��A�č��̔��l�Љ�S�̂����e�ɂȂ����i���邢�́A�܂Ƃ��ɂȂ����j�\��Ȃ̂��낤���B �@�܋��҂��̃V�����c�i�N���X�g�t�E���@���c�j�́A�܋���̊��m��W�����S�i�t�H�b�N�X�j��z�ꏤ���甃�����B�������W�����S��z��ł͂Ȃ��A�܋��҂��̑��_�Ƃ��ċ����A�㔼�̓W�����S�̍Ȃ��߂����߂ɁA��_����L�����f�B�i���I�i���h�E�f�B�J�v���I�j��ɑ������łE�E�E�B �w�C���O�����A�X�`�x�̂P�T�Q���ɑ����A�{����P�U�T���̒��ڂ����A�^���̉f��͒��������������邱�Ƃ��A���C���Â����邱�Ƃ��Ȃ��B����͂������A�N���̂���X�g�[���[�A�Ȃ̂���o��l���A���͓I�ȃ_�C�A���O�̑�����ʂ��B �@�����ȂƂ���A�����l�܂�悤�Ȍ�����́w�C���O�����A�X�`�x�̕������������Ǝv�����A���Ƃ��Α�_����Ɍv������j��ꂽ�Ƃ��납��A���܂݂�̌��������Ɏ���܂ł̗���͋ٔ������Q�B�܂��A�W�����S�ƍȂ̓��S��`������z�V�[���Ȃǂ́A�����炭�P���ɂ������Ȃ��f���Ȃ̂ɁA�u�������������̓����s�v�̃h���}��N��Ɉ�ۂÂ���B �@�O������v���b�g�̃J�M�ɂ�����A�M���O�̃l�^�ɂ����肷��^���̗V�т́A�{��ł����݁B����́u�O�����b���Ȃ��č��l�v�ւ̎��s�E�����ł�����킯���B �@�L�����f�B���t�����X���Ԃ�ƕ����āA�V�����c�����q�悭�t�����X���b���o���ƁA�L�����f�B�̎�芪�������������x���B�u�L�����f�B�̓t�����X�ꂪ�b���Ȃ��B�s�@���ɂȂ邩��p��Řb���v �@�h�C�c�ږ��̓z�ꂾ�����W�����S�̍Ȃ́A�h�C�c�ꂪ�b����̂ŁA�L�����f�B���~�́u�A�z�ȕč��l�ǂ��v�ɋC�Â��ꂸ�ɁA�V�����c�ƌv���b��������B �@�J���I�o���������t�����R�E�l���ɂ́A�C�^���A�������ׂ点�āA�}�J���j�E�F�X�^���ւ̃I�}�[�W����������B�u���O�̒Ԃ�͂c�i�`�m�f�n�B�c�̓T�C�����g���v�Ɩ����t�H�b�N�X�ɁA�l���́u�킩���Ă�v�B�����A��������ȁB�ނ��u����W�����S�v�Ȃ���B �@��w���݂̘b��������ЂƂB���������̑O�ɃL�����f�B���~���������悤�Ƃ����V�����c���A����Ȃ��Ƃ������B�u�̋��̃h�C�c�ł̓A�E�t�E���H�[�_�[�[�[���Ƃ����ʂ�̈��A��������A����͌����ɂ́w�܂�����܂Łx�Ƃ����Ӗ����B���Ȃ��ɂ͓�x�Ɖ�����Ȃ�����A�������킹�Ă��炨���B�O�b�h�E�o�C�v �@��ʂ̓��{�l�Ɂu�p��ŕʂ�̈��A�͉��ƌ����܂����H�v�Ɩ₦�A�命���̐l�́u�O�b�h�E�o�C���v�Ɠ������Ȃ��������H�@�����ĉ��Đl�Ƙb���߂����ɂȂ��@������Ă������A�ʂ�ۂɑP�ӂ��ӂ��u�O�b�h�E�o�C�v�������āA����̖ڂ�_�ɂ����Ă��܂��B �@���������L�p�ȉf��͂��В��w���ɂ����Ăق����Ǝv���̂����A�����Ǝc�O�A�{��͂q�P�T�w�肾�������B �i�Q�O�P�R�D�R�D�S�D�L�j �Q�O�P�R�N�I�X�J�[�i�C�g�E�E�H�b�`���O�I  �@�A�J�f�~�[�܂͎��Ƃ��Ēn���茻�ۂ̂悤�ȗl����悷�邱�Ƃ�����̂����A���N�͂܂��������̔��B�������Ȃ��Ƃɍ�i�܁A�ē܁A�o�D�S�܂̌v�U�̃I�X�J�[�����A���ׂĈقȂ��i�ɕ��z����錋�ʂƂȂ����B �@�S�����ʎZ���Ă��A�S����𐧂����w���C�t�E�I�u�E�p�C�x���ő��ŁA�w�A���S�x�Ɓw���E�~�[���u���x���R����A�w�����J�[���x�Ɓw�W�����S�x���Q����B���N�̃I�X�J�[�E���[�X�́u�n�C���x���Ȓc�q���[�X�v�Ƃ����Ђƌ��œ����Â�����̂ł͂Ȃ����B �@�����j�D�܂́w�W�����S�x�̃N���X�g�t�E���@���c���A�R�N�O�́w�C���O�����A�X�E�o�X�^�[�Y�x�ɑ����^�����e�B�[�m��i�ł̎�܁B�^���̍�i�ȊO�ł͂���قnj����Č����Ȃ�����A���̉f���Ƃ͂��̃I�[�X�g���A�l�o�D�̐��������������ЂƂ悭�킩���Ă��Ȃ��̂�������Ȃ��B �@�������D�܂͖{���������w���E�~�[���u���x�̃A���E�n�T�E�F�C������Ȃ�l���B�i�^���[�E�|�[�g�}���Ɠ����ŁA�n�T�E�F�C���u�����̔��l�v�̔��e���璅���ɔ����o���Ă����B�v���[���^�[�߂��W�R�̃N���X�g�t�@�[�E�v���}�[���u�m�~�j�[�����Ƃ͂��ꂩ��o������R�O��i�̂ǂꂩ�ŋ����������ˁv�Ƃ��܂����̂ɂ͔��B �@�剉�j�D�܂́w�����J�[���x�̃_�j�G���E�f�C�����C�X�B�X�s�[�`�ł͉p���l�̎������č��哝�̂������A�č��l�̃������E�X�g���[�v���T�b�`���[���p����������������A�u��������������ł��v�Ƃ����W���[�N�Ɏd���Ă��B �@�剉���D�܂́w���E�ɂЂƂ̃v���C�u�b�N�x�̃W�F�j�t�@�[�E���[�����X���A�w�[���E�_�[�N�E�T�[�e�B�x�̃W�F�V�J�E�`���X�e�C����}���Ċl���B���̂Q�l�A���ɑ�����ɂ��݂����Z�������������B �@�����č��N�̔o�D�w�̎�܃X�s�[�`�͔����B���@���c�͉��Z�ƂȂ�Ɗɋ}���݂Ȃ̂ɁA�f�ł̂���ׂ�͍T���߂����A�f�C�����C�X�͂͂�����b�����肾�B�n�T�E�F�C�ƃ��[�����X�̓X�s�[�`���p�t�H�[�}���X�̏�ɂ���قǃX���Ă��炸�A���Ƃ����Ċ��ɂ܂��Ēe����ł��Ȃ��A���S�n�̂܂܌^�ʂ�̊��ӂ��q�ׂ邾���ɂƂǂ܂����B �@���̓_�A����ł����̂́A�w�A���S�x�̃v���f���[�T�[�Ƃ��č�i�܂��l�������x���E�A�t���b�N���B��������A�X�L�����_�������������������A�ē܂̃m�~�l�[�g�������N�̎����B����ȏ��X�̟T��������Ă̎�܂����������ɁA�u������Ǒ��l�����ނȁv�u�l���A�K���ł��̂߂���邯�ǁA�厖�Ȃ̂͗����オ�邱�Ɓv�Ƃ��������t�ɂ́A�ނ́g���h���������Ă����B�������Ԃ����Ȃ蒴�߂��Ă����͂��Ȃ̂Ɂu�ǂ��o�������f�B�v����o���Ȃ������̂́A��ẪA�J�f�~�[����猩�Ă������I�ȃX�s�[�`�i���邢�́A�������̎���X�s�[�`�j���������炾�낤�B �@�ē܂́w���C�t�E�I�u�E�p�C�x�̃A���E���[���A�w�u���[�N�o�b�N�E�}�E���e���x(05)�ɑ����Q�x�ڂ̎�܁B�m���ɑf���炵����i�ł͂��������ǁA���`��A���̉f��Ɏ剉�����̂́A���Z�̌o�����Ȃ������Ⴂ�j�D�ƁA�b�f�̃g�������B������̋L�҉�ŃA�t���b�N�������Ă������ǁA���N�̊ē܂ł́w�[���E�_�[�N�E�T�[�e�B�x�̃L���X�����E�r�O���[�A�w���E�~�[���u���x�̃g���E�t�[�p�[�A�w�W�����S�x�̃N�G���e�B���E�^�����e�B�[�m�炪�m�~�l�[�g����R�ꂽ�B�A�J�f�~�[����̖ʁX�A������Ɗ���Ă炢��������Ȃ����ȁB �i�Q�O�P�R�D�R�D�S�D�L�j �t���C�g�@�@FLIGHT �i�Q�O�P�Q�N�A�āA�����F�e�n�_�i�j  �@����̓t���C�g�i��s�j�̉f��ł͂Ȃ��B�\���҂ŃC���[�W����悤�Ȕ�s�@���̂̉f��ł��Ȃ��A�p�C���b�g�̉f��ł����Ȃ��B����̓A�����̉f��ł���B �@��l���̃E�B�g�J�[�i�f���[���E���V���g���j�́A�����������Ƃđ�𗁂тāA�斱�̒��ɂ��}�����B���܂��ɋ@���ɓ����Ă�����A��������q�p�̃~�j�{�g�������Ⴄ�n���B����s�\�ɂȂ�����s�@�������s���������ăq�[���[�ɂȂ������Ǝv������A��������A���R�[�������o����đ{���̑ΏۂɁE�E�E�B �@�ϋq�ɂƂ��ăg���b�L�[�Ȃ̂́A���̂̌����͋@�̂̕s��ł���A�E�B�g�J�[�͌����ɑ����̖����~�������c�̒B�l���ƒm���Ă��邱�ƁB��������ނ̉���������̂��B�����Ŏ������̓n�b�ƋC�Â��̂��B�����ς���ĎԂ��^�]����̂��i���Ƃ����̂��N�����Ȃ��Ă��j�ƍ߂Ȃ̂�����A�����ς���ė��q�@�𑀏c����̂͂����Əd�߂���ˁA�ƁB �@�������E�B�g�J�[�͖җ�Ɉ�����������B�ے�A�U��A�_�B��B�����̏斱���ɂ������ɗL���Ȕ��������߁A�ېg�̖S�҂̂悤�ɂȂ�B���x������f�Ƃ��Ƃ����݂邪�A�A�����̔߂����A���͈ˑ��ǂȂ���Ȃ��Ƌ��ق��A���ǂ͌��̖؈���ɁB�����������邤���ɁA���̒����ψ���̒Nj��̖���́A�E�B�g�J�[���痣��Ă����B�����Ă���̂́w�g���[�j���O�f�C�x�ň��t�̌����s�������f���[�����B�ϋq�́u�܂��������@�̔������������蔲���Ă��܂��̂��v�Ǝv�������E�E�E�B �@�����A�w�t���C�g�x�́w�g���[�j���O�f�C�x�ł͂Ȃ������B�u�U��̌����v���ؖ����ꂩ�����Ō�̌�����ŁA����̕ېg�̂��߂ɂ͂���قǃE�\���d�˂��E�B�g�J�[���A�u�����Ȃ��́v���������ɐ^�������̂��B �@���̐́A�u�o���܂�߂܂����A����Ƃ��l�Ԃ�߂܂����v�Ƃ��������L�������������ǁA�E�B�g�J�[�͍Ō�̍Ō�Ɂg�l�ԁh�ɂƂǂ܂邱�Ƃ�I�B�u���ƂP�E�\�����Ή������Ȃ��p�C���b�g�𑱂���ꂽ�̂ɁA���̃E�\�����Ȃ������v�ƌ��E�B�g�J�[�̓Ɣ����A�ς�҂̐S�ɐ[�����S���ĂыN�����B�l���ǐS���т����Ƃ̓���Ƒ������A��������ƍl�������Ă����Ǎ�ł���B  �@�b�͕ς�邪�i�{���͕ς���Ă��Ȃ��̂����j�A���̍�i�̓E�B�g�J�[�̏�̃V�[���Ŗ����J����B�f��̕��@���炷��A���̒m���x�̒Ⴂ�A�h��ȗe�e�̃��e���n���D�i�i�f�B�[���E�x���X�P�X�j�������鑊����́A�Ȃ�X�e�f�B�ł͂Ȃ��A�����E�i�C�g�E�X�^���h���B �@�Ƃ��낪���̑�����A���̊��ɉ�ʂɉf��߂��Ȃ̂ł���B�f���������Ȃ��ϋq�Ȃ炻�̃E���g���S�[�W���X�ȃo�X�g�Ɍ��Ƃ�邾���ŏI��邩������Ȃ����A�x�e�����̉f��t�@���̓��ɂ͏����Ȉ�a�����ނ��ނ��Ɖ萶���o���B���̌�̃V�[���Ŕޏ��������̂b�`���Ɣ�������ɋy��ł��A���̈�a���͊��S�ɂ͕��@����Ȃ��B �@���o�[�g�E�[���L�X�ē̐[�d�������킩��̂́A���̂Q���Ԍ�ɃE�B�g�J�[��������Ő^������������i�ɂȂ��Ă��炾�B�f���Ƃ��āA����ȂƂ���܂Ōv�Z���ăV�[����g�ݗ��ĂĂ����ł��˂��B �i�Q�O�P�R�D�Q�D�P�P�D�L�j �N���E�h�E�A�g���X�@�@CLOUD ATLAS �i�Q�O�P�Q�A�āA�����F������q�j  �@����͂�A�������낵���X�P�[���̑傫�ȍ�i���B��f���ԂP�V�Q���A�ēR���A����͂P�X���I����Q�S���I�ɂ܂�����U�̎���B �@��������Q�{���R�{�ɕ����č���Ă����ƌ��������Ȃ�Ƃ��낾���A�e����̕���Ɠo��l�������ڂɃ����N�������Ă��邩��A�����������Ȃ������̂��낤�B����ł��P�N�[���̃e���r�h���}�Ɏd���Ē����A�����������������Ȃ����Ǝv���Ȃ����Ȃ��B �@����̓f�C���B�b�h�E�~�b�`�F���̓��������B�㉺���e�R�V�U�y�[�W�������삾����A���̂��炢���ڂɂȂ�̂���ނȂ����B�������������������ɁA��f���Ƀg�C���ɍs�������Ȃ�q�����o�������B�������肩������g��ł��邩��A�߂��Ă������ɂ͂�������u���Ă��ڂ�ɂ���邩������Ȃ��B �@���ہA�g�C���ɗ����Ȃ����������傢�ɍ��������B���ꂩ��ӏ܂������́A���߂Ċe����̒��S�l�����N�������ł��������Ă����ƁA�����ԓ����ł��邾�낤�i�O��`������ƃg���E�n���N�X���S�҂̎���Ɏv���邪�A���̂悤�Ƀ~�X���[�h����Ă��܂��ƁA�����炭�X�g�[���[�����܂����ɓ���Ȃ��j�B �@�P�X���I�̓쑾���m�œz�ꐧ�x�ɋ^�O���o����ٌ�m�i�W���E�X�^�[�W�F�X�j�B �A����O�̃X�R�b�g�����h�œV�ˍ�ȉƂɎt�����鉹�y�Ɓi�x���E�E�B�V���[�j�B �B�P�X�V�O�N��̃A�����J���C�݂Ō����̕s����Njy����L�ҁi�n���E�x���[�j�B �C���ネ���h���ŃC���`�L�o�ŎЂ��c�ޘV�ҏW�ҁi�W���E�u���[�h�x���g�j�B �D�ߖ����̊؍��ŃE�G�C�g���X�Ƃ��Đ����郌�v���J���g�i�y�E�h�D�i�j�B �E���������̃n���C�Ől�ޑ����̌������炳�ꂽ���M�����i�g���E�n���N�X�j�B �@���ゲ�ƂɎЉ�w�i�͂܂�ňႤ���A�f��̃W�������������猾���Ă����j���A�q���[�}���h���}�A�Љ�h�A�~�X�e���[�A�R���f�B�A�r�e�A�A�N�V�����ƁA�{���ɂ����������Ϗ�ԁB �@����ł��āA���ׂĂ̎���̃X�g�[���[�́u�}���v�Ɓu��R�v���j�ɂȂ��Ă��āA���ꂼ��̃v���b�g�Ɠo��l���i�����ď�����j��������܂����ŋ��������B�U�̂��ꂪ�V���N���������Ȃ���A�傫�ȃJ�^���V�X�Ɍ������ă_�C�i�~�b�N�ɋ삯�オ���Ă����N���C�}�b�N�X�͈������B �@�ēE�r�{�������Ŗ��߂��̂́w�}�g���b�N�X�x�̃E�H�V���E�X�L�[�Z��E�E�E���߃E�H�V���E�X�L�[�o��ƁA�w�p�t���[���@����l�E���̕���x�̃g���E�e�B�N���@�B�D�����R�l�����Ă悭���܂Ƃ܂����Ǝv������A��L�̇@�D�E���E�H�V���E�X�L�[�o��A�A�B�C���e�B�N���@���S�����A���s���ĎB�e�����������i���̊W�ŁA�B�e�ēƔ��p�ē��Q�l���N���W�b�g����Ă���j�B �@���ʂƂ��āA�E�H�V���E�X�L�[�̎������ƁA�e�B�N���@�̔Z��������������A�������̈��Ɏd�オ�����B �@�ʔ����̂́A��L�̂U�l�Ƀq���[�E�O�����g�A�q���[�S�E�E�B�[�r���O�A�W�F�[���Y�E�_�[�V�[�����������v�L���X�g���A�e����̂��ꂼ��Ⴄ�o��l�����A���ɂ͖{�l�Ƃ킩��Ȃ��悤�ȃ��C�N���{���ĉ��������Ă��邱�ƁB �@�������e�ɉ�������ɂ́A�n���E�x���[�����l�ɕ�������A�q���[�S�E�E�B�[�r���O�������ɕ�������A�W���E�X�^�[�W�F�X���؍��l�ɕ�������ƁA���ʂ�l��̘g�������݉z���Ă��܂��B�G���f�B���O�̃^�C�g���o�b�N�Łg�햾�����h������A�u���A���̐l�������̐l�������́H�v�ƁA���C�ɂƂ�ꂸ�ɂ͂����܂��B  �@�����Ƃ��A���ꂼ��̃L���X�g��������̂́u���������������ʂ̐l���v������������A�W���E�X�^�[�W�F�X�ƃy�E�h�D�i�͇@�ł��D�ł��J�b�v���ɂȂ�A�q���[�E�O�����g�͂ǂ̎���ł��}���҂̑��Ƃ�����ɁA�����̐������͕ۂ���Ă���B�����炱���A���鎞��̐l���̃��m���[�O���A�ʂ̎���̃V�[���Ɉ�a���Ȃ����Ԃ���Ƃ�������Ƃ���������̂��B�E�H�V���E�X�L�[�ƃe�B�N���@�́A����͑�ςȘJ��ɂ��Ĉӗ~��ł���B �i�Q�O�P�R�D�Q�D�P�P�D�L�j �Q�O�P�Q�N�i���́j�x�X�g�V�I �@�Ȃ�Ńx�X�g�P�O�ł��x�X�g�T�ł��Ȃ��A�x�X�g�V�Ȃ�I�E�E�E�Ƃ͌��������Ȃ��B �@���̃��x���ő��肵����V��i���c�����̂ŁA���ƂR��������A�Q������肷��̂��ʓ|�ɂȂ����B���������A�l�̂g�o�Ȃ���B �@��N�ǂ���A�f�ڏ��́u�ǂ��������v�ł͂Ȃ��A�u�ӏ܂������v���B�V�쒆�T��͕č��f��Ȃ̂ɁA�����邱�Ƃ��A�č����傽�镑��ɂ�����i�̓t�����X�f��́w�A�[�e�B�X�g�x�����������B �w�̂ڂ��̏�x�́A���{�f��Ƃ��āw�[��̊X ���̍��x(07)�ȗ��̃����N�C���B���̍ɂȂ�ƁA�ق�̂Q���Ԃł��l���ʂɂ������Ȃ�����A�ǂ����Ă��M��͌h���C���ɂȂ�̂����A����͋M�d�ȏE�����������B �i�ӏܑ����P�P�P�{�j �P�@�A�[�e�B�X�g�@THE ARTIST �Q�@�����E�f�C�@�Q�R�N�̃��u�X�g�[���[�@ONE DAY �R�@�̂ڂ��̏� �S�@�g�[�^���E���R�[���@TOTAL RECALL �T�@�A���S�@ARGO �U�@���C�t�E�I�u�E�p�C�^�g���ƕY������227���@LIFE OF PI �V�@���E�~�[���u���@LES MISERABLES �i�Q�O�P�R�D�Q�D�P�P�D�L�j ���C�t�E�I�u�E�p�C�^�g���ƕY�������Q�Q�V���@�@LIFE OF PI �i�Q�O�P�Q�N�A�āA�����F�Óc�R�I�q�j  �@�m��ɂЂǂ��M��������͖����ɂ��Ƃ܂��Ȃ�����ǁA�������߂��̑o�����Ȃ��̂́A �P�j��������̂܂܃J�^�J�i�ɂ����A���ϓI���{�l�ɂ͈Ӗ��s���̃^�C�g�� �Q�j�������炵��������Ԃ牺�����^�C�g�� �Ƃ����Q�ތ^���낤�B �@�Ƃ��낪�ǂ������A���̗�����g�ݍ��킹���ň��̖M�������ꂽ�f��ł���Ȃ���A���́w���C�t�E�I�u�E�p�C�^�g���ƕY�������Q�Q�V���x�́A���ЂƂ����N�����Ɋ��߂����Ǎ�Ȃ̂ł���B �@�p�Ƃ����������̌o�c�҈�Ƃ��A�C���h����J�i�_�ɈڏZ����r���ŊC��ɑ����B�n�C�e�B�[���̑��q�������ЂƂ�~���{�[�g�Ő������т邪�A�V�[�g�̉��ɂ��֖҂ȃx���K���g��������ł��āE�E�E�B �@�܂��͎�l���p�C�̑��`�������B�{�̖`���ɓ���O�Ƀe���|�悭����鐶�������́A���ꎩ�̂��P�{�̉f��Ɏd���Ă���قǁB�q���Y�[���k�̉ƒ�ɐ��܂�Ȃ���A�L���X�g����C�X�������ɂ����X�ƐS�������Ⴄ�u�ςȎq�v�Ԃ肪����U�����A����͂������������痈����̂ł͂Ȃ��A�l���݊O�ꂽ�^�����̏��Y�B����Ȕނ̎v���I�Ȑ��i�́A��̖`��������̂ɂ��傢�ɗ͂ɂȂ�B �@���N�ɂȂ������\�N��̃p�C��������C���t�@���E�J�[�����܂���i�B���ɑT�ⓚ�̂悤�Ȏ��������镗�ς�肾�����͓I�Ȑl�����A�����Ԃ�B�҂ɋ�������B �@�ē͑�p�o�g�̃A���E���[���B�C���h�ƒ������������傭���ɂ���Ɠ{���邩������Ȃ����A���m�v�z�̃G�b�Z���X����i�̃q�_�ɐD�肱��ŏG��B���Ă̊ē��B���Ă�����A���̍�i�A�܂������Ⴄ���̂ɂȂ��Ă����̂ł͂���܂����B �@�N���E�f�B�I�E�~�����_���B�e�����f�����A�܂�����ۂނقǑf���炵���B���̃V�[���̔��́A�N���Q�̌Q��̋P���A�Â��ȃv�[���ɍL���閲���B���̈��|�I�ȉf�������A�u��̊C��v��u�Y���҂�H�ׂ铇�v�Ƃ���������ȃv���b�g�����A���ɗ��ł�����B �@���낵���x���K���g�����͂��߁A�����ɓo�ꂷ��n�C�G�i�A�V�}�E�}�A�N�W���A�g�r�E�I�Ȃǂ̓��������͂�������b�f�����A���͂���ʂƌ������邱�Ƃ͂قƂ�Ǖs�\���B �@�J�b�g�ւ��̎��ɁA�O��̉f���̈ꕔ���������c���g�V�сh���A�f��t�@���̖ڂ��������Ƃ��낤�B �@���āA�~���{�[�g�ɓ��悵���V�}�E�}��I�����E�[�^�����H��ꂽ��́A�x���K���g���ƃp�C�̃^�C�}���������B�p�C�͕K���ŋ������A�������H���Ȃ����߂ɁA�g����H�킹��B�ŏ��͎��s�ƌ����݈Ⴂ�̘A���B����ł��p�C�͏����������A���܂��A�����Ȃ��Ă����B���̐����̋L�^�́A�Ⴂ�f��t�@���ɂ����Ɖ������w���悤�B �@����ɂ��Ă��A��m��Y�����邾���Ŗ������Ȃ̂��B���߂ăg�������Ȃ���A���������y�ɋ������ꂽ�̂ɂƎv���Ƃ��낾���E�E�E�B �@�I�ՂɂȂ��ăp�C�̌�郂�m���[�O�����ɈӋ`�[���B�u�g�������Ȃ���Ύ���ł����B�g���ɑ��鋰�|���ْ����݁A�G�T���m�ۂ��邱�Ƃ���X�̖ڕW�Ƃ��Đ�����ꂽ�v �@�Ȃ�قǂ�����������Ȃ��ȂƎv���B����������Ƃ����y�ȓ���I��҂��}���ɎЉ�I�p�l�ɂȂ��Ă��܂�����A�t�Ƀ{�P�V�l�ɉƎ��𗊂�r�[�ɃV���L���Ƃ����Ƃ���������͂悭���ɂ���Ƃ���B�R�����V���ł͂Ȃ�����ǁA�l�ɂ͑�����䅓�h����K�v�Ȃ̂�������Ȃ��B �@���������A�Ј������g����u���b�N��Ƃ̌�����Ɏg����ƍ�����ǁB �i�Q�O�P�Q�D�P�Q�D�R�O�D�L�j ���E�~�[���u���@�@LES MISERABLES �i�Q�O�P�Q�N�A�p�A�����F�Γc�q�j  �@����͌��킸�ƒm�ꂽ�r�N�g���E���S�[�̂P�X���I���w�B�{���t�����X�ł͂��т��щf�扻����Ă��āA�W�����E�M���o���A���m�E�o���`�����A�W�������|�[���E�x�������h�ȂǁA������������d�����剉�߂Ă���B �@���A��r���Ėʔ����̂́A�p��łŐ���N���߂��r���E�A�E�O�X�g��i�i�X�W�N�j���낤�B
�@����̊ēg���E�t�[�p�[�ƃ��b�V���́w�p�����̃X�s�[�`�x�ō��ӂɂȂ������B�X�W�N�ł̔\�ʂ̂悤�ȃW���x�[���͗D��ăn�}��������������ɁA�������ōĉ�������I���������蓾���͂������A�t�[�p�[�͗�O�ȃ��b�V���ł͂Ȃ��A�M���ۂ��N���E�̕���I�B �@�����X�W�N�łƍ���Ƃ̍ő�̈Ⴂ�́A�����܂ł��Ȃ���҂��~���[�W�J���ł��邱�Ƃ��B�������t�[�p�[�́A�u�Z���t�ɉ̂��������܂��v�`���ł͂Ȃ��A�u�S�҂��̂Ői�߂�v�`���ɂ���������B���̂��ߒʏ�̉f�掚���Ȃ�Α̎��ɂȂ�͂��̉̂̉̎����A����̏ꍇ�͂��ׂĐ��̎��̂܂܂ɂȂ��Ă���i�������łȂ��ϋq�̊F����ɂƂ��Ă͂ǂ��ł������b���낤���j�B �@�~���[�W�J���f��ł͈�ʂɉ̂�ʎB��ɂ���P�[�X�������悤�����A����ł͎ŋ������Ȃ�����ۂɉ̂��A��������̂܂��^�����Ƃ����B���̂��߂������Ă��A�u�̂��ėx���āv�Ƃ����~���[�W�J���f��̃X�e���I�^�C�v�ɔ����A����̖��҂����͗x��Ȃ��B�R�[���X�̏�ʂ��������̐U��t�����������Ă��邪�A�\���̃V�[���ɂȂ�ƁA�_�j�[�E�R�[�G���̃J�����͂Ђ�����̂���̊�ɓ����B��肱�Z�b�g��ߑ����A�s���g�̍���Ȃ��g�w�i�h�ɂ��Ă��܂��B����Ӗ��A���낵���ґ�Ȃ��Ƃł���B �@�̂�ʎB��ɂ��Ȃ��������ƂŁA���Ƃ��A���E�n�T�E�F�C�̈�Ԃ̕������ǂ���ƂȂ�w����Ԃ�āx�Ȃǂ��A�Ƃ���ɂ�艹�����Ԃꂽ��A�ז��ȃu���X���������肷��B�ł͂��ꂪ���s���������Ƃ����ƁA�����͋t���B���������̏��̗���ɂ���āA�t�@���e�[�k�̔ߒQ���A�o���W�����̌��ӂ��A�G�|�j�[�k�̏���A�������Ċς�҂̐S�ɋ��������̂ł���B�����炭�̓Z���t�ȏ�̐����͂������āB �@�~���[�W�J���ł̓X�g���[�g�v���[�قǂ̃��A���e�B�͗v������Ȃ��̂ŁA�X�W�N�łɔ�ׂčו���[�܂�C���B�Ƃ��낪�X�W�N�ł��ςċ^��Ɋ��������Ƃ��A����ŕX����������������B �@���̂ЂƂ��A�o���W�����͂Ȃ��ی�ώ@���t�P�čs��������܂����̂��A�Ƃ������Ƃ��B�_���̈��ɐG��Đ^�����ɐ����悤�ƌ��߂��̂Ȃ�A������Əo���̋`���ɕ������ƍl����̂����ʂł͂Ȃ��̂��B �@�����A�_�����킷�Ւd�̑O�Łu���܂ł̃o���W�����͎̂ĂāA�V���ɐ��������̂��v�Ɖ̂��A�O�Ȏ҂̐g����j��̂Ă�W���b�N�}�������Ă�����A���ׂĂ��X�g�����D�ɗ������B�u�����A�����ȋ�̐C�䂪����A�g���Ȃ��ł������������ˁv�Ȃ�ĂЂ˂��ꂽ�c�b�R�~�́A���̍ہA����Ȃ��Ă��悩�낤�B �@���{�l�I�Ȋ��o�ł́A������A�o���W�����͐_���ɕԗ�ɍs���ׂ��ł͂Ȃ����ƍl�����Ⴄ�̂����A���S�[�͂�����������ɂ͂��Ȃ������悤���B���Ԃ�L���X�g�̈��Ƃ͂����������̂ł͂Ȃ��̂ł��傤�ˁB �@������̃A�J�f�~�[�����ŏ����ȋ����������Ă��ꂽ�W���b�N�}���ƃn�T�E�F�C�̗��݂��A����̑傫�Ȍ��ǂ���B�����A�X�W�N�ł����Ă���������Ă��A�Ȃ��o���W�������t�@���e�[�k�ɂ���قǂ̐e��������̂����A�悭�킩��Ȃ���ˁB�ނɂƂ��ăt�@���e�[�k�́u���w�ɐg�𗎂Ƃ������]�ƈ��v�ɉ߂����A����ȏ�ł�����ȉ��ł��Ȃ��킯�ł���B �u�������䂦�Ɉ������v�Ƃ����`���������Ă����Έ�ԃC�[�W�[�ɗ����ł���̂����A�A�E�O�X�g���t�[�p�[���K���������������x�^�ȉ��߂͍̂��Ă��Ȃ��B�Ȃ���܍߂̂��߂Ȃ̂��A�l�Ƃ��Ă̓���A�_�̑P���Ȃ��҂Ƃ��Ă̎��߂Ȃ̂��B����������Ɖf���Ƃ������A���S�[�̈Ӑ}��ʂ肩�ˁA�����ăj���[�g�����ȕ`�����������Ȃ��̂�������Ȃ��B �@��f���Ԃ́A�X�W�N�ł��P�R�R���ŁA���삪�P�T�W���B�����ɍו���[�܂��Ă��A�̂̕������~���[�W�J���͒����Ȃ�B��������ōۗ����ĈႤ�̂́A�G���f�B���O�̂܂Ƃߕ����B�X�W�N�ł̓W���x�[�������疽�������Ƃ���Łi�܂�̓o���W�������ߋ��̂��т����犮�S�ɉ�����ꂽ�Ƃ���Łj�I��������A����͂������炪���ɒ����B �@�R�[�b�g���i�H���ɍ���Ȃ��g���́j�}���E�X�Ɉς˂Ď���p���������o���W�����́A�t�@���e�[�k�̌��e�ɓ�����A�_�̌䋖�֏�����Ă����B�����ɂ���̂͌����ł�����ł͂Ȃ��A���������������B������������͔ߌ��Ȃ̂��A�͂��܂��n�b�s�[�G���h�Ȃ̂��B�u�_�̌䋖�v�ɂȂ��̓���������Ȃ���L���X�g���k�ɂƂ��ẮA�i���ɉ����Ȃ���ł���B �@����ł��ً��̓��{�l�q���A�����܂ł̂Q���Ԕ��̉́A�́A�̂ɐS�h���Ԃ��A�i�]�����D�ӂ��Ɍ����j�������鏀�����ł��Ă����B�W���x�[�����g�𓊂������ꂩ�珬��肷��悤�ɗ�������i����܂��������Â炢�j�j�[�\���́u�Đ��v���́A��ڂ��I�����W���b�N�}���́u���v�̕����A�m���ɕ���̒��߂�����Ƃ��āA���Ր��ɐG���̂�������Ȃ��B �i�Q�O�P�Q�D�P�Q�D�R�O�D�L�j �`���C�X�I�@�@SWING VOTE �i�Q�O�O�W�N�A�āA�����F�������q�j  �@���{�ł͐�T�A��c�������O�c�@�����U�����B�~�����u�A���V�ԃO�`���O�`���A���A�A�[�X����A�k�Е����m�[�A�C�f�A�ƁA����}�ɂ͐����S���\�͂͂��납�A���݉��l�����Ȃ����Ƃ����łɂ͂����肵�Ă���킯������A�Ƃ��ƂƑI���ő�s���A�l�U�A��̂Ɍ������Ă������������B �@�܂��A�m���ɉ��B�̋��Z��@���Ôg�A�^�C�̍^���Ȃǂ͖���}�̐ӔC�ł͂Ȃ��̂�����ǁA���ꂾ���ɂ������āu���g�̎�������o����݂̂̂Ȃ炸�A�]�v�Ȗ�Ђ܂ň����鎥�v�Ƃ̈�ۂ������Ȃ�B������ېV�ɂ����Ȃ���^�I�ɂȂ炴������Ȃ����A�Ƃ肠�����R�N�Ԃ́u�����v�͑ł��~�߂Ƃ��ׂ����낤�B �@�Ƃ͂����A��c����A���U���P�T�ԁA���������[�I�@���ӍՂ̌�Ɋ������オ��Ƃ�����N�̃p�^�[����M���ėl�q�������߂���ł�����A���̂P�T�Ԃŋ}���ɉ~���E�������i�s�B���͂┽�����|���ĉI舂Ɏ���o���Ȃ������ɂȂ��Ă��܂����B�g�z�z�z�z�E�E�E�B �@�C�̌������̕č��ł́A������{�ɃI�o�}�哝�̂��đI�B���O�̗\�z�ł͂��Ȃ�̐ڐ�ŁA�I���l���������j�[���Ƃ܂����������ɂȂ�\������荹�����ꂽ�B �@���̃P�[�X���܂��ɉf��Ɏd���Ă��̂��A���{�ł͌��ꖢ���J�ƂȂ��Ă��܂����w�`���C�X�I�x���B���͍ŋ߁A�v�n�v�n�v�ŊςāA���܂�̃f�L�̂悳�ɋ������B����Ȗʔ����ď㎿�ȉf�悪�c�u�c�X���[�ɂȂ����Ⴄ�Ȃ�āi�������P�r���E�R�X�i�[�剉�Ȃ̂Ɂj�A���{�̉f��t�@���͕s�K����Ȃ��B �@����͂Q�O�O�W�N������A�v�͑O��̑哝�̑I�ɏ�����������Ƃ������ƂɂȂ�B���a�}���i�P���V�[�E�O���}�[�j�ƁA����}���i�f�j�X�E�z�b�p�[�j�̓��[�����h�R�B���鎖��瓊�[�������ł��Ȃ������V���O���E�t�@�[�U�[�̃o�Y�i�R�X�i�[�j�̍ē��[�ɂ��ׂĂ�������邱�ƂɂȂ�B�Ƃ��낪���̃o�Y�A�I���l�o�^�����Ă��Ȃ�����������ŁE�E�E�B �@�ē��[�܂ł̂P�O���ԂɁA���w�c�̓o�Y����肱�����Ɩz���B�m���|���̃o�Y�̉��C�Ȃ��Ђƌ��ɐU���āA����}��₪����֎~��ږ��r�˂�i������A���a�}��₪���ی쐭��⓯�����e�F��ł��o������ƁA�����Ƃ͐^�t�̎咣�����n�߂�B���̂�����͓�吭�}�������œo�ꂳ������č��Ȃ�ł͂̃u���b�N�ȃM���O�B�ˋ�̐��}�������i���Ԃ�j�g���Ȃ����{�f��ł́A��������������邱�Ƃ͖]�߂Ȃ��B �@�����Ƃ����{�̕��ϓI�ȉf��t�@�����u���a�}���ێ�A����}�����Ƀ��x�����v�Ƃ����\�}��m���Ă��邩�ƂȂ�ƁA���`��A�m��Ȃ����Ȃ��B�m��Ȃ��ƂȂ�Ə��Ȃ��B���̓_�ł͂c�u�c�X���[����ނȂ����B �@�����A���́w�`���C�X�I�x�A�ɍ\���Đ�������Ƃ��R�P�ɂ��邾���̉f��ɂ͏I����ĂȂ��B���ꂼ��̑I���Q�d�i�l�[�T���E���C���ƃX�^�����[�E�g�D�b�`�j�ɂ����̂�����Đߑ��̂Ȃ��咣�����邯��ǁA�����Ƃ��z���Ă͂����Ȃ�����̑O�ł̓M���M�����݂Ƃǂ܂�̂ŁA�ӏ܌㊴�͈ӊO�ɑu�₩�B�����哝�̑I���������f��ł��A�w�X�[�p�[�E�`���[�Y�f�[�x�ȂǂƂ͈Ⴂ�A�l�ԂƂ������݂ւ̊�{�I�ȐM���������������ˁB �@����A�Q�l�̑I���Q�d���ٌ������Ɂu���z�����̂��������������A�܂��͑I���ɏ����Ȃ��Ⴛ��������ł��Ȃ��v�ƌ��̂��A���Ȃ���ʐ^�����܂�ł��čl����������B �@�R�N�O�̖���}�͗��z������ď���������A���̎����ɂ܂������B�����̏O�@�I�͉ʂ����Ăǂ�Ȍ��ʂɂȂ�̂��B�A�z�Ȗ��}�h�w��swing vote�i�����[���{��̌���j���W�߂ĈېV������i�E�E�E�Ȃ�Ĉ��������͊��ق��Ăق������ǁB �i�Q�O�P�Q�D�P�P�D�Q�S�D�j �̂ڂ��̏� �i�Q�O�P�P�N�A���j  �@�킸���T�O�O�̕��͂ŁA�Q���̖L�b�R����ď����W�J�����҂�����`�������X���X�̕���B���U�߂̃V�[�����Ôg��A�z������Ƃ��āA���J�����炭���щ��тɂȂ��Ă����A���킭�t���̍�i���B �@����E�z���T�C�h�Ƃ��ẮA���̐��U�߂̃X�y�N�^�N����A�剉�̖쑺�ݍւ̌|�B�҂Ԃ��傢�ɏ̗g���Ăق����̂��Ɛ��@���邪�A���Ƃ��Ă͂��������v���X���̕������͂ނ���A�x�[�V�b�N�Ȑ퍑�E��U�߂��̂Ƃ��Ă̗v�f�����Q�ɖʔ��������B �i�����������U�߂��ĕ⋋�H��f���߂ɍs�����̂ł���A�{��ɕ`����Ă���悤�ɓG�w��G���������������߂ɂ����̂ł͂Ȃ��ł��傤�j �@�k�����ɂ��Đ키�U������Ȃ���A���͂�������J�邵�悤�Ɩژ_�ޏ��B���̗����a����Ȃ���A�y�d��ŊJ������߂��Ⴄ����Ȃ����i�쑺�j�B���������u�s�폟�v�Ɍ��݁A����Ɏ����������ƍ�����炷�Γc�O���B���������k���ȓo��l���̕`�ʂ��A���̂܂܋N���ɔ�X�g�[���[�𐄐i�����Ă����B �@���`�Ɍ��������_�s�A�����^�C�v�̎R���q�[�A���Ő키���{���M�ƁA�Ɛb�����̊�Ԃ�����m�ρX�B���ꂼ��̌�������������������Ղ�Ɨp�ӂ���Ă���B �@�����P�����[���̂́A�g�����Ƃ�������l�ɂ͂܂����������̋y�Ȃ�����̒��œW�J�����l�ԊW�̖��B�ǂ�����v�Ȏ��݂͂�Ȑe�����ۂ��̂����A���Ə��A���ƉƐb�́A�����Ď�]�̃��C���݉z�����A�䂪�g���̂ĂĎ�ɂ����B���̖��i�đq�ށX�j���炸�v���Ă���炵����オ�A�Ō�Ɉ��Ȃ�ʁu�퍑�̘_���v�œ����Ƃ�����A����̊ϋq�Ƀ������R���b�N�ȊS�Q�𑣂����낤�B �@���Ȃ݂Ɍl�I�ɂƂ��Ă���ۂɎc�����̂́A�đq�P���Ɨ��ł��鐬�{���M�̃R�N����ӂ�Ƃ���B�S���̏��q������A�j�̎q���ӂ鎞�́A����Ȃӂ��ɋC�����悭�ӂ낤�ˁB �i�Q�O�P�Q�D�P�O�D�Q�U�D�L�j �G�N�X�y���_�u���Y�Q�@�@THE EXPENDABLES 2 �i�Q�O�P�Q�N�A�āA�����F�ъ����j  �@���₠�A�ʔ��������Ȃ��B�C���e���Ԃ������̎q�ɂǂ�ȂɃo�J�ɂ���悤�ƁA�j�͂��������h���p�`���̂���D���B�l�̌܂̌��킸�ɓ˓��A�~�o�A���������߂�I�[�v�j���O����A��������������܂ꂽ�B������ꂽ�u�e�w�Ȃɗ��炸�A�̂Ȃ���̃X�^���g�ƁA�x�[�V�b�N�Ȃr�e�w�Ō�����A�N�V�����������x��B �@�X�g�[���[�Ɋւ��Ă��A�O��̂悤�ȃN�T���q���[�}�j�Y���i�̂悤�Ȃ��́j�����邱�ƂȂ��A�V���v���Ȓ�������ʼn��������B�X�^���[�����剉�ɓO�����i�܂�͊ēE�r�{��{�E�ɏ������j�̂́A���炩�ɐ����������B �@�g���̂Ăɂ����b���̈Ӓn��`������P��́A�f��E�Ŏ��ۂɎg���̂Ăɂ���Ă������[�g���E�A�N�V�����o�D�����ɂƂ��Ė{���ɓq���������Ǝv���B�Ȃɂ����܂�Ɏ��s�I�B�w�^������Ίϋq�̎����A�َE�����\���������ɂ������B�Ƃ��낪���̎��s�����ʔ����ƁA�ӊO��A�X�}�b�V���q�b�g���L�^�B���Ď҂̃X�^���[���͂������芔���グ�邱�ƂɁB �@�������őO��ł͗F��o���i�Ƃ������X�^���[���ւ̋`���o���H�j�ɂƂǂ܂��Ă����u���[�X�E�E�B���X��V�������c�F�l�b�K�[���A����ł͖{�i�Q��B�O��ւ̏o������������W�����E�N���[�h�E�o���E�_���ƃ`���b�N�E�m���X���A���̏L����k���������A����͏o�������������B�S������������A�M�����̍��v��������ɂȂ������B �@����ŃL���X�g�w�̕��ϔN��Ǝg���̂ēx�͂܂��܂��A�b�v�B���̂����X�^���[���́A�킴�킴�V�������������̃��A���E�w���Y���[�X�𑁁X�ɑޏꂳ���A�u����̓I���W�Ղ�̉f��Ȃ̂��v�Ƃ̈�ۂ�O����ɋ������Ă݂����B �@�����A�V�������m���X���������ɓ��̂��g���A�N�V�����͗}���C���ŁA�����ς�}�V���K�����Ԃ������̂݁B�����ăt�@�C�g�A�N�V�����̒��S��S���̂́A�W�F�C�\���E�X�e�C�T����W�F�b�g�E���[�Ȃǂ̎��i�H�j�������B �@�Ƃ�킯�X�^���[���̕������߂�X�e�C�T���́A�I���W�A���̂��������A��̂����A�N�V�����𑶕��Ɍ����A�V���[�Y�̉A�̗��Ė��҂ƂȂ��Ă���B�ނ����Ȃ�������A���̃V���[�Y�A�ƂĂ������Ȃ����낤�ȁB �@�������Ȃ��̂ŁA��P��̐����̂������ŁA���̃V���[�Y���玩�s�̏L�����قƂ�Ǐ������B���邢�́A���s���M���O�ɏ������Ƃ����ׂ����B �@����ł��u�g���̂Ă�ꂽ���[�g���E�A�N�V�����o�D�̗J�D�v�����̃V���[�Y�̔���Ȃ̂�����A��R��ɂ��Ƃ����[�A���E�j�[�\���Ȃ��Ă�ł��Ȃ��łق����Ȃ��B �@�����E�M�u�\���Ȃ炢�������ˁi�j�B �i�Q�O�P�Q�D�P�O�D�Q�U�D�L�j �A���S�@�@ARGO �i�Q�O�P�Q�N�A�āA�����F���Y���ށj  �@�Ȃ�Ƃ���i���j���x���E�A�t���b�N���B�قƂ�ǂ̐l�͑O����������������߂Č���͂�������A�ŏ��͒N���������ς�킩��Ȃ������ˁB �@�C�����v���̂��Ȃ��̂P�X�V�X�N�ɁA�݃e�w�����̕č���g�ق��苒���ꂽ�������w�i�B�l���ɂȂ钼�O�ɃJ�i�_��g�̎��@�ɓ������U�l�̊و����A���P�n���ɗ����J�i�_�l�̉f��X�^�b�t�Ɏd���Ăč��O�E�o�������A�b�h�`�Lj��̊�V��Ȏ��b�����ɂȂ��Ă���B �@�P�X�V�X�N�Ƃ����Ύ��͑�w��������A�����̕�����Ȃ�Ɍ����͂��Ȃ̂����A���͂قƂ�NjL���ɂȂ��B���ꂾ���������E�̏o�����������킯�ł��ˁB �@�Ƃ��낪�A���̉������E�̏o�������A�R�O�N�ȏ�̎��ԓI�����܂ʼn����ĕ`�������̉f�悪�A�ӊO��ӊO�A���̋ɓ��̊ϋq���������݁A��Ɋ����点��̂ł���B�v���ɕ���������C�����Q�O�̃G�l���M�[���A�Ɍ���Ԃɒu���ꂽ��g�و������̋��|���A�ނ���~���Ƃ��郏�V���g���̏ő����A���|�I�ȃ��A���e�B�������Ĕ����Ă���B �@�剉�Ɗē����������x���E�A�t���b�N�́A�w�U�E�^�E���x�Ɉ��������A���ɂ����d���������B�����ɂ́u�ēȂT���ł��ł���v�Ƃ����y�������I�ȃZ���t���o�Ă��邪�A�ǂ����āA����ł́u�o�D�̗]�Z�v���Ȃ�ĊԈ���Ă������Ȃ��B �@�b�h�`�Lj��̃g�j�[�i�A�t���b�N�j�́A�U�l�̋~�o���ʂ������߁A���낤���Ƃ��U�̉f�搻����ł���������B�n���E�b�h�̃v���f���[�T�[���ق��A�����n�т�Ƃ���r�e�f��̋r�{���A��X�I�ȋL�Ҕ��\�ɁA�o�D�̃L���X�e�B���O�E�E�E�B �@���̃}�[�N�E�g�E�F�C���́A�u�����ƃt�B�N�V�����̗B��̍��́A�t�B�N�V�����ɂ͐M�ߐ����K�v���Ƃ������Ƃ��v�Ƃ��������f�����Ƃ����B �@�f�悪�ł����������ƃC�������Ƀo����Α�g�و��̖��͂Ȃ�����A�g�j�[�͂��̐M�ߐ��𑝂����߂ɁA�Ƃ��Ƃ�s��ȃE�\�������̂��B �@�������Đ��{�����ɂ́A�u����ȃo�J�o�J������킪��������͂����Ȃ��v�Ƃ������Έӌ����Q�������B���s����Ίو����������J���Y�������肩�A���ێЉ�̏������B�댯��`���Ď���e�w�����ɐ��������g�j�[���A�y�d��Ńn�V�S���O����āE�E�E�B �@��������X�g�[���[�͋}�����B���E�����̂Ă܂��Ƃ���g�j�[�̎g�����ƃv���t�F�b�V���i���Y�����A�ς�҂̋���M������B �@�U�̌o�����ËL���ďo���R�����p�X���悤�Ƃ���و��A��x�̓V�����b�_�[�ɂ������Ȃ���v���ɋ��͂���q�������̎�ŕ�������Ă�����g�و��̎ʐ^�A���蔭�Ԃ����g�j�[�̂��߂ɊO���ꂽ�n�V�S�������������Ɩz�������i�B�����ɂ͗ǎ��̃T�X�y���X�̗v�f�������Ղ�Ƌl�܂��Ă���B�K���B �@�E�E�E�ƁA�̎^���Ē��߂������Ă��܂��Ă������̂����A���̔��ʂŁA�f��̌��̖L�x�Ȋϋq�Ȃ�A�{����ςĂ���Ȃ�[�����邱�Ƃ͂Ȃ����낤�Ƃ��v����B�Ȃɂ����N���e�w�����ɋΖ����Ă�����g�و��������A�Q���O�ɓ����������Ƃɂ��悤�Ƃ����̂ł���B �@�p�X�|�[�g�̓�����̓g�j�[������U������̂����A�����͂ق�̐��b�̃J�b�g�ŏ����B�����J�[�h�͂Q�����ʂ̖{�[�����p�ӂ������̂́A�C�������ǂɕۊǂ���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ����[�͓��R�A���݂��Ȃ��B�܂�A���Ǒ���������̋U�������j�ꂸ�A�Ȃ������[�̕�������ɂ��Ȃ��Ƃ������Ƃ�O��ɂ����A���낵�����͖{��̍��Ȃ̂ł���B �@�����T�X�y���X�f��̋ؗ��ĂƂ��Ă͂��܂�ɂ��G�ŁA����ԈႦ���]�������ꂩ�˂Ȃ��Ƃ���Ȃ̂����A�Y��ĂȂ�Ȃ��̂͂��ꂪ���b���Ƃ������ƁB�O�q�̃}�[�N�E�g�E�F�C���̌��t�́A�����ł������Ă���B���ꂪ���b�ł������A�M�ߐ��Ȃ₤�Ă�����[���Ȃ��̂ł���B�����A���̍��Ő����������������B �i�Q�O�P�Q�D�P�O�D�Q�R�D�L�j �\�n�̒n�������@�@IN DARKNESS �i�Q�O�P�P�N�A�Ɓ��|�[�����h�A�����F�g����ގq�j  �u���������s�ސT�����v�Ƃ����G�N�X�L���[�Y�t���ł����Ό����̂́A�u�z���R�[�X�g�f��ɂ͌��삪�����v�Ƃ������ƁB������ߔN�́A�h�C�c�ȊO�̍��ł̃��_���l���Q��\�I�E��������f�悪�����Ȃ��Ă���B �@�|�[�����h�̏����ēA�O�j�F�V���J�E�z�����h���B�����w�\�n�̒n�������x���A����Ȍn���ɑ�����P�{�B�����̕n���������J���҂��A�n�������ɐg���B�������_���l�̈�c���A���J���ɂ킽���Ďx���������b�����ɂȂ��Ă���B �@�Ƃ͂������̕���͒P���Ȕ��k�Ƃ��Ă͏�����Ă��Ȃ��B��l���̃\�n���炵�āA�����C���̂������A�R�\�D�ҋƂɐ����o���j�B����m������n�������Ƀ��_���l�������܂����̂��A�h�C�c�R�ɒʕĕ������炤���A���_���l�������������������ׂ���Ɠ����炾�B �@���_���l�̒��ɂ��Η��┽�ڂ�����A�\�͂◘�Ȏ�`������B�u�C�̓łȔ�Q�ҁv�Ƃ�����ʓI�ȂƂ炦���ł͂Ȃ��A���G����������������l�ԂƂ��ĕ`����Ă���_�������B �@�z�����h�ḗA�i�`�X�̐�̉��Œn���Z�����r�N�r�N���Ȃ����炷����̋�C���s���������B�h�C�c���̓{����A���_���l�ǂ��납�A�L���X�g���k�̃|�[�����h�l�܂ł�������̂悤�ɎE����Ă��܂���펞���B�\�n�Ƃ��̍Ȏq�����x�ƂȂ���̐▽�̊�@�Ɋׂ�B���̂��тɎ������́A�䂪���Ƃ̂悤�Ɏ�Ɋ�������B �@���̐�ڂ����̐�ڂƂ���ɂP�x�̓��_���l�����̂Ă�\�n���A���̒��̂P�l���h�C�c���ɂ��܂肩����ƁA�v�������Ȃ��s���ɏo��B�����H�����^�сA���_���l�����̊�{���y��ڂɂ��邤���ɁA���R�ɏ�ڂ����̂��B���_���l�̃��[�_�[�ɋ���n���A�u�݂�Ȃ̑O�ł�����B�����Ŏx������j���Ǝv��ꂽ���Ȃ��v�ƌ����R�\�D�̋��܂��A�I�J�V�����������B �@�I�X�J�[�E�V���h���[�قǒ����ɂ͂Ȃ�Ȃ��������̂́A���������l�X�������˂āu���Ȃ�P�Ӂv��ڊo�߂������j���A�m���ɂ����ɂ����݂����B�i�`�X�̐�̂���������ŁA�Â�����������͂��o���Ă��郆�_���l�����̎p�́A�Í��̎�������낤���Đ������т������S�̂��ے����Ă��悤�B�ނ�ɉَq���ӂ�܂��\�n�Ƃ��̍Ȃ��A�l�ԑS�ʂւ̐M�����������Ă�B �@�����Ƃ��A�z�����h�ē��g�́u����͌ʂ̎���ł����āA�������畁�ՓI�ȋ��P�͌��o����Ȃ��v�ƁA����������O�Ȍ����������̂�����ǁB �@�{��̃v���X������ǂ�Ŏv�����̂́A�u���������Ȃ烆�[���Q�O�P�Q�̑O�ɁA������ς��������v�Ƃ������ƁB �@�{�N�U�`�V���Ƀ|�[�����h�ƃE�N���C�i���T�b�J�[�̉��B�I�茠�����Â������Ƃ́A�܂���X�̋L���ɐV�����B�����A���̋��ÁA���͗���������₵����������u�Ȃ�ŁH�v�Ƌ^��Ɋ����Ă����B���Ă̋��Y���ɑ�������Ƃ͂����A�E�N���C�i�͋��\�A�̈�p���B����܂Ń��[�������Â��Ă����I�����_���x���M�[��A�X�C�X���I�[�X�g�����A�Ƃ͖��炩�ɖѐF���Ⴄ�B �@�����{��̉���ɂ��A�f��̕���ƂȂ����|�[�����h�̂̃��u�t�́A���ł̓E�N���C�i�̂̃��r�E�ɂȂ��Ă���Ƃ����B���r�E�Ƃ����A���[���̊J�Ós�s�̂P�ł͂Ȃ����B �@���̓s�s�̋A���͂Q�O���I�ɓ����Ă��炾���Łu�Z�]���]�����v�Ƃ����B���̊ԁA�E�N���C�i��|�[�����h�A�h�C�c�A�\�A���̗L��������肵�A�����\�����傫������ւ�����B�E�N���C�i�ƃ|�[�����h�́A�K�������K���ł͂Ȃ����j�ɂ���āA�[�����т��Ă�����ł��ˁB �@�����P���{�l�Ƃ��ĕ��G�Ȏv��������̂́A���ł́u�x�ꂽ���X�v�ƌ���ꂪ���ȓ����̈�s�s�ɁA�P�X�S�R�N�̎��_�ōL��E���G�ȉ����Ԃ���������Ă������ƁB���{�̒n���s�s�ɉ����������y���n�߂��̂́A�ق�̂R�O�N�قǑO���炾�B�s�s�J���̒��ʼn��ɏd����u�����Ƃ����މ�̈ӎ��̍����A���Ƃ������[���B �i�Q�O�P�Q�D�X�D�P�V�D�L�j �v�H���@�@TYRANNOSAUR �i�Q�O�P�P�N�A�p�A�����F�ݓc�b�q�j  �@���̐���ɂƂ��āu�v�H���v�Ƃ��Ί��G���̗̉w�ȂȂ̂����A����͂܂������킵���Ȃ��f��Ɏ����킵���Ȃ��M����������́B�Q�O�P�P�N�̓������ۉf��Ղŏ�f���ꂽ���ɂ́A���肻�̂܂܂́w�e�B���m�T�E���X�x�Ƃ����^�C�g������������A������C���[�W����Ⴂ���B�����Ƃ��A�u�e�B���m�T�E���X�v�����̃C�M���X�f��̓��e��I�m�ɕ\���Ă��邩�Ƃ����A�S�R����Ȃ��Ƃ��Ȃ��̂�����ǁB �@�r�{�E�ē͔o�D�̃p�e�B�E�R���V�_�C���ŁA�₳���ꂽ��l���͔ނ̎��������f�����Ƃ����B�����A��i���ꌩ���Ċ�����̂̓P���E���[�`��i�A�Ƃ�킯�w�}�C�E�l�[���E�C�Y�E�W���[�x�Ƃ̗ގ������B �@��l���̖��́u�W���[�v�Ƃ����̂����W���Z�t�B������͓̂����s�[�^�[�E�~�������B�n���s�s�ŌǓƂɕ�炷�J���ҊK���̒��N�j���A�g�g���Ⴂ�h�̒��Y�K���̏��ƐS��ʂ킷�W�J���ς��Ȃ��B �@���̃W���Z�t�Ƃ����j���{���ɍ������I�b�T���ŁA��������ł͂��ꂩ��\�킸�P���J��B���ɂ͔�������đ�P�K�����A�܂����鎞�ɂ͏Փ��I�Ɏ��������R��E���B���܂�g�߂ɂ��Ăق����Ȃ��A�Ƃ�킯�����̎����ł͂����Ăق����Ȃ��l�����B �@����ȍr�����ɍ������ވ�̌����ƂȂ�̂��A�`�����e�B�̌Ò����œ����M�S�[�����A�n���i�i�I���r�A�E�R�[���}���j�B�Ђ˂���҂̃W���Z�t�͍ŏ��������݂�A�����A�n���i�̐S��������̂����A�v��̏�͉B���Ȃ��B�l�Ȃ̃n���i���A�v�̖\�͂ɑς����˂āA����ɃW���Z�t�𗊂�悤�ɂȂ�B �@�R���V�_�C���̓W���Z�t�ȏ�̃��N�f�i�V���Q�l�z���āA�ϋq�̐S���������W���Z�t�Ɉ�����B�P�l�̓n���i�̕v�W�F�[���Y�ŁA�����P�l�̓W���Z�t�̌������ɏZ�ރV���O���}�U�[���������������肾�B �@�W���Z�t�͂������A�n���i���A���邢�̓V���O���}�U�[�̑��q���Ђǂ����Ƃ������̂��~�߂��Ȃ��B�ߌ��̓W���Z�t�̎�̋y�Ȃ��Ƃ���Ői�s���A��������x��ɂȂ��Ă���B����ɐS���d������̂́A��x��ɂȂ�O�Ɏ��ԂɋC�Â����Ƃ��Ă��A�₳����W���Z�t�͖،͂炵�䎟�Y�̂悤�ɒm��ʊ�����߂��̂ł͂Ȃ����Ǝv�킹�邱�Ƃ��B�W���Z�t�͂����܍߂����邩�̂悤�ɂQ�C�ڂ̌����E���A�ނȂ�̗��Ƃ��O������̂����B �@�l�^�𖾂����A�n���i�͖\�͓I�ȕv���E�Q����B����������̓n���E�b�h�f��ł͂Ȃ�����A�W���Z�t�́u���ƈꏏ�ɓ����悤�v�Ȃ�Ă��Ƃ͌���Ȃ��B �@����ł��ʉ�ɍs�����W���Z�t�ɑ��ăn���i��������A�߂������������悤�Ȕ������͂ǂ����낤�B���O�̃V�[���܂ŃA�U���炯�̃q�h���炾�����̂́A���̃G���f�B���O�̌��ʂ��ő���ɂ��邽�߂������悤���B �@�����ǁE�E�E�ƂЂ˂��ꂽ�ϋq�͍l�����Ⴄ��ˁB�O���̔������ʂ̔���̌�����ƌ�������̉f����́A��������Ȃ��Ǎ����̂Ȃ��Ό�����Ȃ��ł������H �i�Q�O�P�Q�D�X�D�P�V�D�L�j �g�[�^���E���R�[���@�@TOTAL RECALL �i�Q�O�P�Q�N�A�āA�����F�ъ����j  �@���������A�����������C�N����E�E�E�Ǝv������A�|�[���E�o�[�z�[�x���ē��A�[�m���h�E�V�������c�F�l�b�K�[�剉�̃I���W�i���ł���A���łɂQ�Q�N���̍Ό�������Ă�����ł��ˁB�������Ƃ�킯���B �@����ƍł��ς�����͎̂�l���̋U�ȃ��[���[�̖������B�V���ȃ��[���[�́A�V�����łŃV�������E�X�g�[�����������U�ȂƁA�}�C�P���E�A�C�A���T�C�h�������������x�@�����ЂƂɂ����L�����ɂȂ��Ă���A�R�����E�t�@�������������l�����v���t�F�b�V���i���{�p�[�\�i���ȗ��R�Ŏ��X�ɒǂ��߂�B �@������̓��C�Y�}���ē̎��̍Ȃł���P�C�g�E�x�b�L���Z�[���ŁA���ꂪ�܂��A�Ȃ�Ƃ��V����Ȉ����Ԃ肾�B�ޏ����w�A���_�[���[���h�x��w���@���E�w���V���O�x�̂悤�ȃA�N�V�����f��ɏo�n�߂����͉������C���[�W�ƍ���Ȃ��Ȃ��Ǝv�������̂����A���ۂ́w�p�[���E�n�[�o�[�x��w�Z�����f�B�s�e�B�x�Ō����������h���Z�̕����A�ނ���J�}�g�g�������̂�������Ȃ��B �@�W�F�V�J�E�r�[�������������`�̐�m�̃����[�i�ł͂Ȃ��A�������[���[�������̍Ȃɉ��������A���������͓I�ɎB��B���C�Y�}�������������ςȐl���B �@����ݒ���傫���ύX���ꂽ�B�V�����łł͉ΐ����㔼�̕���ɂȂ��Ă������A�����C�N�łł͉��w�푈��̒n��������B�l���Z�߂���́A�n���̑ɂɈʒu����u�u���e���A�M�v�Ɓu�R���j�[�v�����ɂȂ��Ă���B �@���C�Y�}���́w�u���[�h�����i�[�x�����ΎG�ȁu�R���j�[�v�ƁA�w�t�B�t�X�E�G�������g�x���̃z�o�[�J�[����щ��u�u���e���A�M�v�A�����ė��҂����ԋ���G���x�[�^�[�́u�t�H�[���v�Ƃ����R�̈قȂ郍�P�[�V�����ŁA���ꂼ��^�C�v�̈Ⴄ�A�N�V�������\�z���Č������B��l�����x��������|����ŏ��̃A�N�V�����Ȃǂ́A�����ăX�s�[�h����}���ē����̑N�₩�����ۂ������鉉�o�B���ɐꂪ�����B �@���Ȃ݂ɕ���̖`���A�R���j�[�ŕ�炷�J���҂̃_�O���X�E�N�G�C�h�i���̓u���e���A�M�̒�����J�[���E�n�E�U�[�j�ƁA���[���[�̕v�w�́A���ɃA�����J�p���b���Ă���B�t�@�����̓A�C�������h�o�g�ŁA�x�b�L���Z�[���̓����h�����܂�B�ꖕ�̈�a���������A�u�A�����J�f�悾����A�����J�p��Ȃ̂ˁv�ƁA����ɔ[�����Č��Ă�����A�U�Ȃ̉��ʂ�E���̂Ă��r�[�ɁA���[���[���C�M���X�p��Řb���������B�Ȃ�قǁA�ޏ��̐��̂̓u���e���A�M�̊����������̂��B �@����A�L���������ꂽ�N�G�C�h�͂��Ƀn�E�U�[�̃A�C�f���e�B�e�B�����߂��Ȃ������̂ŁA�t�@�����͂����ƃA�����J�p��̂܂܁B����܂��[�����B �@�����C�N��Ŋy�����̂́A�V��̍��肪�A���I�}�[�W���A������̃t�@���ւ̃T�[�r�X�Ƃ������ׂ��u�V�сv�����Ă��邱�ƁB �@���̃��C�Y�}���Łw�g�[�^���E���R�[���x�ɂ��A�o�[�z�[�x���łɓo�ꂵ���u�g���v�������ς����v��u�f�u������v�i�������������ŁA����̃t�@���Ȃ�킩��͂��j���A�V�[���������ς��Č����B �@�u���e���A�M�̃A�N�V�����V�[���̂ЂƂł���G���x�[�^�[���g�����V�`���G�[�V�������A����̍Ō�̑Ό����X�P�[���A�b�v���������̂ɈႢ�Ȃ��B �u�j�̊��v���u���̗܁v�ɐݒ�ւ������V�[�����������B�����̂�����́A�V��������ׂāA�T���Ă݂Ăق����B �@���C�Y�}���ł��o�[�z�[�x���ł��A������т����͕ς��Ȃ��B����́u�ߋ��̎����ł͂Ȃ��A���݂̎�����������Ȃ̂��v�Ƃ������b�Z�[�W���B �@�����A�o�[�z�[�x���łł͍Ō�ɃE���g�����̂ǂ�ł�Ԃ����p�ӂ���Ă��āA���ꂪ�X�g�[���[���킩��₷�����锽�ʁA�u�l�Ԃ̃A�C�f���e�B�e�B���āA����ȊȒP�ɕς�����i�ς��Ă����j���̂���Ȃ��ł���v�Ƃ�����a��������ł����B �@�V��ł͂������ɂ��̓_�̎蓖�Ă��Ȃ���Ă���B����Ɠ����ǂ�ł�Ԃ���҂��Ă����I�[���h�t�@���͏�������������H�킳��邪�A�����C�N�łŏ��߂Ă��̕���ɐG���ϋq�ɂƂ��ẮA�m���ɂ��̕�����l���ɋ������₷�����낤�ȁB �i�Q�O�P�Q�D�W�D�Q�P�D�L�j �v�����e�E�X�@�@PROMETHEUS �i�Q�O�P�Q�N�A�āA�����F�˓c�ޒÎq�j  �w�A�x���W���[�Y�x�w�}�_�K�X�J���R�x�w�_�[�N�i�C�g���C�W���O�x�w�g�[�^���E���R�[���x�E�E�E�B �@���Ă���N�̂��Ƃ��A�ċx�݉f��͑��҂ƃ����C�N�̃I���p���[�h�������B����Ȓ��A�����ѐF������Ă����̂́i���邢�́A�ѐF���Ⴄ���̂悤�ɐ�`����Ă����̂́j�A���h���[�E�X�R�b�g�ḗw�v�����e�E�X�x���B �@�����냁�C���R�s�[���u�l�ނ͂ǂ����痈���̂��v������A�N�����āw�Q�O�O�P�N�F���̗��x�̂悤�ȓN�w�r�e��A�z���܂���ˁB�Ƃ��낪���ʂɍs���ăr�b�N���B�ǂ����猩�Ă��ِ��l�p�j�b�N�r�e�Ȃ̂ł���B �@�����������ِ̈��l�p�j�b�N�r�e�ł͂Ȃ��B�u�E�F�C�����h�v�Ƃ������̓o��l���A�������ȍs��������A���h���C�h�A�]���ɂȂ�����̂̑ԗl�B���������A�����͂ǂ�����ǂ��������āA���ăX�R�b�g���B�����w�G�C���A���x�̃v���N�G���i�O���k�j����B����Ȃ炻���ƁA��`�i�K���疾�����Ă���Ȃ��ƁB �@�z����Ђ��Ȃ��������Ȃ��������ƍl���Ă݂�ɁA�ЂƂ��ɃG���f�B���O�ɏo�Ă���u����v�̃T�v���C�Y���ʂ����߂����������炾�낤�B�������u����v�͏��n�̌��ƌ����Ȃ����Ȃ��B �w�G�C���A���x��m��Ȃ��w�́A���������u����v�����Ă������Ȃ��B�t�Ɂw�G�C���A���x���悭�m��w�́A�O�q�̂悤�ȕ�������A���ꂪ����̃v���N�G���ł��邱�ƂR�Ɏ@�m����B���́u�����v�́A�f��t�@���Ƃ��Ă̗D�z����ւ������������̂��B�����Ɂu����v����������B�u�Ȃ��v�Ǝv���B�u�o���Ȃ������Ă킩��̂Ɂv�ƁB �@�O���k���Ɛ�`������Łu����v���o���Ȃ玩�R�ȗ��ꂾ�B�������O���k�ł��邱�Ƃ��B������Łu����v���o������A�ނ���w�G�C���A���x�̓�Ԑ����ɑ��Ă��܂��B �@��Ƃ̃��g�����́A�˔\���͊������ӔN�A�Ⴂ���ɕ`��������̖͎ʂ��悭�`���Ă����Ƃ����B����ȍ�i���B���Ă��܂�����A���h���[�E�X�R�b�g���܂��A�ӔN�̃��g�����Ɠ����������Ƃ�܂��B�o��l���̓�̍s�����A��������������Ȃ��܂܂ɏI����Ă���A���I������ϋq�͒��Ԃ���Ȏv��������Č�����o��͕̂K���B �@�X�R�b�g�������̂��A�z����Ђ������̂��A�L���X�g�̒m���x�́w�G�C���A���x����قǍ����̂ɁA���Ƃ��c�O�ȑ��ɂȂ����B �i�Q�O�P�Q�D�W�D�Q�P�D�L�j �X�m�[�z���C�g�@�@SNOW WHITE AND THE HUNTSMAN �i�Q�O�P�Q�N�A�āA�����F�Óc�R�I�q�j  �@���N�͔���P�f�悪�Q�{�����Č��J�����B���ʂ���̂̓q���C���i�ł���͂��j�̔���P���A�p��̕��ɑ受�D���N�p����Ă���Ƃ������ƁB�U���Ɍ��J���ꂽ�w�X�m�[�z���C�g�x�͔���P���N���X�e���E�X�`�����[�g�Ōp�ꂪ�V���[���[�Y�E�Z�����A�X���Ɍ��J�́w����P�Ƌ��̏����x�͔���P�������[�E�R�����Y�Ōp�ꂪ�W�����A�E���o�[�c���B���������X�V�N�ł́w�O�����E�u���U�[�Y�^�X�m�[�z���C�g�x���A����P�������̃��j�J�E�L�[�i�Ōp�ꂪ�V�K�j�[�E�E�B�[�o�[�������B �@�Q�{�̐V��͓�������Ƃ͎v���Ȃ��قǃg�[�����Ⴄ�̂ŁA����ׂĂ݂�̂����ꋻ�B�w����P�Ƌ��̏����x�̃^�[�Z���ḗA�W�����A�E���o�[�c�̃R���f�B�G���k�Ԃ�����A���邢�f�B�Y�j�[�E�^�b�`�Ɏd�グ�Ă���i�l�C�T���E���C�������o�[�c�̈�̉Ɨ��������Ă��鎞�_�ŁA�|���b�ɂ͂Ȃ蓾�Ȃ���ȁj�B �@����A�V�l�ē̃��p�[�g�E�T���_�[�X�����K�z�����������w�X�m�[�z���C�g�x�́A�Ƃɂ����^�ʖڈ�ӓ|�B�V���[���[�Y�E�Z�����Ƃ������D�͌��X���[���A�̃Z���X���ŁA�w�����O���A�_���g�x�̂悤�ȉf��ł����R���f�B�ɂ����˂��l������A�����Ă����ǂ�ǂ�u�V�сv�Ɍ����������ɍs���Ă��܂���ł��ˁB �@�Ɨ����𐺍��ɓ{�����Z�����͊m���ɈЈ������_�ŁA�q�Ȃɂ��邱����܂ŗ݂��y�Ȃ��悤�ɂƐg�������߂Ă��܂�������ǁi�H�j�A�������������ɂ���قNjC����Ȃ��Ă��������Ȃ����Ǝv���̂́A�����s�^�ʖڂȂ�������ł͂���܂��B �@�Ή��l�q�̃r�r�b�h�Ȉߑ����f����w����P�Ƌ��̏����x�ɁA�����̉A�T�ȐF�������x�z�I�ȁw�X�m�[�z���C�g�x�ƁA�r�W���A���ȉ�ʍ\���̈Ⴂ�ɂ��ڂ��������B �@�ʔ����̂́A�������A�ǂ���̍�i���t�F�~�j�Y����O�ʂɉ����o�����u�Q�P���I�̔���P�v�ɂȂ��Ă��邱�ƁB�q���C���͉��q�l�̑��͂ɂ��������ł͂Ȃ��A���畐�������āA���낵���p��ɔ�����|���B �@����ƈ���āA�u���q�l�̃L�X�v�����Ȗ��͂������J�M�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��_�����ʂ��B�N���X�e���P�͉��q�l�ȊO�̒j�ɂ���đh������A�����[�P�Ɏ����Ă͋t�ɉ��q�l�̕��͂��������Ă݂���B �@�p�ꂪ�G�X�e�ɂ������ރV�[�����A���������ɐ��肱�܂ꂽ�B�ǂ���̏������Ⴓ�Ɣ��������ێ����邽�߂ɂ��Ȃ�ٗl�ȍs�ׂɋy�Ԃ̂����A����܂���i�̃g�[���f���āA���o�[�c�̂͏��A�Z�����̂͐g�̖т��悾�B �w���[�h�E�I�u�E�U�E�����O�x��w�n���|�^�x�̃p�N�����ڗ���҂����A�Z�����̓����V�[�����w���������`�x(83)�̉Ė}������̂�����v�킹���̂́A�������ɋ��R�̈�v���������E�E�E�H �i�Q�O�P�Q�D�V�D�P�T�D�L�j �A�x���W���[�Y�@�@MARVEL'S THE AVENGERS �i�Q�O�P�Q�N�A�āA�����F����L�K�j  �@����͂�A�������͋Ƃ��B�Ȃɂ��������U�l������W�c���B���܂��ɂ��̂U�l���A���ꂼ��Ɨ������A���R�~�ɂ���đn�����ꂽ�g�����h�L�����ŁA��������w�i���A���i���A���A���e�B�̓x�������܂������Ⴄ�B �@�Ƃ��낪�ēE�r�{�̃W���X�E�E�F�h���́A�e�l�ɂ���Ȃ�̌������^���A�傫�Ȕj�����ꗂ����������Ȃ��ЂƂ̌�y��Ɍ����A�d���ďグ�Ă��܂����B�{��̉��~���ƂȂ����w�A�C�A���}���x�w�L���v�e���E�A�����J�x�w�}�C�e�B�E�\�[�x�ɃE�F�h������؎Q�����Ă��Ȃ����Ƃ��l����A����͋��ٓI�ȉ����Ƃ͌����܂����B �@�֒f�̃��[���z�[��������Ȑ_���L������A���ە��a�ێ��g�D�u�V�[���h�v�̊�n����A���E��j��͂��������l�����L���[�u�𓐂ݏo���E�E�E�Ȃ�ăX�g�[���[�́A�܂��A�����Ă��܂��ǂ��ł������B�ʔ����Ȃ�̂́A��������ʋ���Ȍ����������q�[���[�������A�V�[���h�̖{���ɏW�����Ă��炾�B �@�w���ψ��^�C�v�̃L���v�e���E�A�����J�ƁA�U���Ƃ̃A�C�A���}�����Y�P�Y�P������Ԃ������B�A���K�[�E�}�l�[�W�����g�ɕ��S���钴�l�n���N���A�A�C�A���}����������B�_�̍��̉��q�\�[���l�Ԃ��������A�l�ԃL���������̓��L�̌Z�ł���\�[��ӂ߂�B�v���������z�[�N�A�C�ƃu���b�N�E�B�h�E���A�G�����ɕ�����ĎE�������B�_�o�킩����e��܂ŁA�Q���ԂQ�S���̍�i�̒��ɁA���[�����X�ȑΌ��V�[���⋻���̃o�g���A�N�V�������Ă��肾�B �@���l�^�̃R�~�b�N�ɂȂ��݂��Ȃ����{�l�ɂ́A���X�ɂ��ăA���R�~�f��͎��]�̃^�l�B����ł����́w�A�x���W���[�Y�x�Ȃǂ��ςĂ���ƁA�ꕔ�̃A���R�~�f�悪�܂�Ȃ��̂́A�A���R�~�����삾����ł͂Ȃ��A�f��̍�肪�w�^������Ȃ̂��ƁA���߂ĔF����������B �@�X�J�[���b�g�E���n���\�����u���b�N�E�B�h�[�ɋN�p�����Ӌ`�͍��ЂƂ킩��Ȃ��������A�A�C�A���}�����̃��o�[�g�E�_�E�j�[�E�W���j�A��L���v�e���E�A�����J���̃N���X�E�G�o���X�͂܂��ɓK���B�}�j�A�b�N�ȂƂ���ł́w�}�C�e�B�E�\�[�x�ɑ����ă��L�����������g���E�q�h���X�g�����A��煂�������������łȂ��A�S�̎コ�₸�邳�����\�����ďG�킾�����B�w��̔n�x�ł͍����Ȏm�������������̂R�P�̃C�M���X�l���ҁA���ꂩ��ӊO�ɉ����邩���B �i�Q�O�P�Q�D�V�D�P�T�D�L�j �����E�f�C�@�Q�R�N�̃��u�X�g�[���[�@�@ONE DAY �i�Q�O�P�P�N�A�āA�����F�Óc�R�I�q�j  �@��w����ɒm�荇�����ЂƑg�̒j�����A���N�V���P�T���ɏœ_���i���āA�Q�R�N�Ԃɂ킽���_�ϑ��B����ȋؗ��Ă������A�ǂ��������ăo�[�i�[�h�E�X���C�h����́w�Z�C���^�C���E�l�N�X�g�C���[�x���v���o���B �@�����A���́w�����E�f�C�x�ɂ͓���ƌ���I�ɈႤ�_������B�w�Z�C���^�C���`�x���N�ɂP�x�̕s�ϖ���̃h���}�������̂ɑ��A������͎�l���̒j�����K���������̓��ɉ���Ă��Ȃ��̂��B����ăJ�����͂��ꂼ��̐l������ށu�F�B�J�b�v���v���A���ɂQ�V���b�g�ŁA���ɕʁX�ɒǂ������邱�ƂɂȂ�B �@��l���y�A�̐ݒ�ɂ��ߋ���̉e�����B�f�N�X�^�[�i�W���E�X�^�[�W�F�X�j�͏㗬�炿�̃{���{���A�G�}�i�A���E�n�T�E�F�C�j�͂�������҂̒��Y�K���Ƃ���A�ǂ��������ăG���b�N�E�V�[�K����w���鈤�̎��x�̌n�����낤�B����E�r�{�̃f�C���B�b�h�E�j�R���Y�Ƃ����l�A�Ȃ�����e�������̉ߋ�����~�L�T�[�ɂ����āA�u������I�v�ƂP�̍�i�Ɏd���Ă��悤�Ȉ�ۂ�����B �@�Ƃ͂����A���̃~�L�T�[�͂Q�P���I�̃~�L�T�[���B����w�i�ɂ������ƌ���̎Љ������������B�P�X�T�O�`�V�O�N���ɂ���w�Z�C���^�C���`�x�́A��l���̒j������\�㔼�ɂ��Ă��ꂼ��R�l�̎q�����������B�P�X�V�O�N�ɔ��\���ꂽ�w���鈤�̎��x�ł́A�I���o�[�ƃW�F�j�[�͊w���������A�j���ٌ�m�ɂȂ�Ə��͉ƒ�ɓ������B �@����A����́u���������g���A���v�̊��Ԃ���������������B�f�N�X�^�[�ƃG�}���A���߂Č��t�����킵�����Ɉ�x�͓����x�b�h�ɓ���Ȃ���A�u�F�B�ł��邱�Ɓv��I������B�Q�l�̊W���傫���i�W����̂́A�O�\������ɂȂ��Ă���̂��Ƃ��B �@�����̒n�ʂ�E�ƈӎ����ς��A�����������ɒj�ɐH�킹�Ă��炦��^���炢�����鎞��ł��Ȃ��Ȃ����B���˂�������G�}���A�Ƃ肠�����̓E�F�C�g���X�̐E�ɏA���B��������Ȃ���������������I�Ȏd���ɖ��v���A���i�������Ă����u�^�ʖڂ����v�̎p�́A�Ȃ������Ƃ������B����ɔ�ׂ�ƁA�e���r�E�ŋȐ��������߂Ă����f�N�X�^�[�̃G�s�\�[�h�́A���X�瑊�I�ɉ߂���B �@�{��̖��͂������ۂ�������͉̂�b�̖����B�G�}�̈����z������`���ɗ����f�N�X�^�[���A�u�����̃h���}�����Ă����x�b�h���ȁv�Ƃ��炩���A�G�}�́u�Z�҂ƃz���[�����v�Ȃ�Đ�Ԃ��B �@�f�N�X�^�[�̂����肪���_�ɒB���������ɂ́A�u�S���爤���Ă�B�ł������D������Ȃ��v�ƁA�ϋq�̋Ր��ɐG��錾�t���G�}�������B �@�����ē̃��l�E�V�F���t�B�O�́A����ȃt�@�j�[�Ōy�₩�ȃ_�C�A���O��A�I�V�����ŐȂ����Ƃ���A�����ӂ̃A���j���C�Ȗ��t���ŗ��������B �@�Q�R�N�Ԃ̕��ꂾ����A�G�}�ƃf�N�X�^�[�������ɍ��Ƃ��Ă����B�P������̓�\�ォ��A�ڐK�ɃV���̖ڗ��l�\��ւ̕ϑJ�́A�r�e�f��̓��ꃁ�C�N�قǂ����Ƃ����̂ł͂Ȃ�����ǁA�X�^�b�t�̊m���Ȏ�r���f���Ă���B �@����̓C�M���X�Ȃ̂ŁA�A���E�n�T�E�F�C�͕č��l���w�����ڏZ�҂̐ݒ肩�Ǝv������A���Ȃ肵�����肵���C�M���X�a����I�B���܂��Ƀ_�T�_�T�ȏ��w�����������������ƂւƁA������܂��g�ϐg���D�h�̖{�̂����Ă݂����B �@�W���E�X�^�[�W�F�X�̕����A�J���ҊK�����������w�A�N���X�E�U�E���j�o�[�X�x�Ƃ͂܂������Ⴄ�㗬�p���b���Ă��āA���Ƀq���[�E�O�����g���ƍ��o������B �@�D�������Ă�Ȃ�Ƃ��Ƃƌ��������Ⴆ�悩�����Ɣᔻ����̂͗e�Ղ����A�قǂ悭���y����O�ɒM����o���Ă��܂������C���́A����ł����������Ȃ��͂����B�N�������]�Ȑ܂���������u���������g���A���v�̎���ɂ����āA�G�}�ƃf�N�X�^�[�̃��}���X�͊ϋq�̗l�X�Ȋ��S��U�����낤�B �@���ꂾ���Ɂu�Q�R�N�̃��u�X�g�[���[�v�̍Ō�̂T�N�Ԃ��A�قƂ�ǖ����e�ɂȂ��Ă��܂����̂��ɂ��܂��B�f�C���B�b�h�E�j�R���Y��A�����������ȕ���̏I��点�����v�����Ȃ������̂��E�E�E�B �i�Q�O�P�Q�D�T�D�R�O�D�L�j ���i�C�e�b�h�@�~�����w���̔ߌ��@�@UNITED �i�Q�O�P�P�N�A�p�A�����F�{��^���j  �u�T�b�J�[�̕ꍑ�v��W�Ԃ���C���O�����h�́A���č��ۃT�b�J�[�A���i�e�h�e�`�j���狗����u���A���[���h�J�b�v�ɂ��Q�����Ă��Ȃ������B�{�C�Ŗ��G�Ǝv���Ă����̂��A�w�^�ɎQ������Δn�r�������Ǝv�����̂��A�Ƃɂ����v�t�ɎQ�킵�n�߂��̂͂P�X�T�O�N�̑�S����i�P���Q�s�ŃO���[�v���[�O�s�ށj���炾�B �@�N���u���x���ł��A�T�T�|�T�U�V�[�Y�����甭���������B�J�b�v�i�`�����s�I���Y���[�O�̑O�g�j�ɁA�O�N�x�D���̃`�F���V�[�͎Q�킵�Ă��Ȃ��B���̗��V�[�Y���ɂ̓}���`�F�X�^�[�E���i�C�e�b�h�����[���b�p�̕���ɗ����Ă��邪�A�ǂ���瓖���̉p���T�b�J�[����i�e�`�j�͂���������v���Ă��Ȃ������悤�ł��ˁB �w���i�C�e�b�h�@�~�����w���̔ߌ��x�ɂ́A���̂�����̎����[�I�ɐ������V�[��������B�e�`�̈ӌ��ɔ����ĉ��B�J�b�v�ɎQ�킵�悤�Ƃ���}�b�g�E�o�X�r�[�ēi�_�O���C�E�X�R�b�g�j�ɁA�e�`�̖������V�R�ƌ������̂��B�u���B�J�b�v�ւ̎Q���͂܂���Ȃ��B���N�̃`�F���V�[�̂悤�Ɏ��ނ����Ă��B�ǂ����Ă��o��Ƃ����Ȃ珟��ɂ���������A�������[�O�̓��������Ȃǂ̕X�͈�ؐ}��Ȃ��v �@�}���t�̉����@���ė�����������u�~�����w���̔ߌ��v��m��l�͑������A���̔w�i�ɂ��������N���u�Ƃe�`�Ƃ̑Η������������Ƃ�m��l�́A�K�����������͂Ȃ��͂����i�����m��Ȃ������j�B �@�P�X�T�W�N�Q���U���A�O���Ƀx�I�O���[�h�ł̃`�����s�I���Y�J�b�v���X�������I�����}���t��s�́A�����ɗ���������~�����w���̋�`�ōė����Ɏ��s�B�W�l�̃��M�����[�I��������B����ւŖ߂����̂ł͍������[�O�̎��̎����ɊԂɍ���Ȃ����߁A�`���[�^�[�@����z�������䂦�̔ߌ��������炵���B���݂̍q���@�̂̐��\���l����Ƒz�������Ȃ����A�����͂����������ゾ������ł��ˁB �@�e���r�E�o�g�̃W�F�[���Y�E�X�g�����O�ḗA���̒��O�̋@���̋ٔ���A�ė�����̑s�₳�𔗗͖��_�ɕ`�����B�s�b�`��ł͘������܂��Ă����f�j�̃n���[�E�O���b�O�i�x���E�s�[���j���A���������g�I�ɐ����҂��~�����Ƃ���p������łB���ׂĂ݂���A����͎��ۂɒm��ꂽ�G�s�\�[�h�炵���B �@���̔ߎS�Ȏ��̃V�[��������ŁA�O���ɂ͎Ⴋ�{�r�[�E�`���[���g���i�W���b�N�E�I�R���l���j�̃T�N�Z�X�E�X�g�[���[���A�����Č㔼�ɂ̓W�~�[�E�}�[�t�B�[���ēi�f�C���B�b�h�E�e�i���g�j�𒆐S�Ƃ���}���t�̍Đ�杂��z�����B �@�`���[���g���͌��킸�ƒm�ꂽ�}���t�̃��W�F���h�ŁA�N���u�Ƒ�\�̑o���Ŋ���B�����}���t�̖����߂Ă���B�u�~�����w���̔ߌ��v�������������A�ނ͂Q�P�ŁA��ՓI�Ɍy���ōς��̂́A�S�ɐ[���������B �@�T�b�J�[�N���u���ނɂ����f��ł���Ȃ���A�{��ɂ̓Q�[���̃V�[�����قƂ�ǂȂ��B����͗\�Z��P�[�V�����̐���Ƃ������A�o�D�̉���ȃv���[�Ŋϋq�����炯���������Ȃ��Ƃ̐[�d���������������߂��낤�B�������V�[���̒[�X�ɁA�����̃T�b�J�[����芪���������������Ƃ̂����B����̓r�b�O�r�W�l�X�Ɖ��������݂̃v���T�b�J�[�Ƃ͑傫���قȂ���̂��B �@���Ƃ��悤�₭��R���肵���`���[���g���́A�p�u�Ő�y�ɓB���h�����B�u�T�b�J�[�I�肾�Ȃ�Ė����Ȃ�B�T���P�T�|���h���Ꮧ�̎q������Ă��Ȃ��B��H���z�ǍH���ƌ����Ƃ��v�B���݂̃v���I��͔z�ǍH�̉����{�A�҂��ł���̂��B���������n���̃p�u�Ŗʂ�����Ȃ��Ȃ�Ă��ƁA���蓾�Ȃ���ˁB �@�o�X�r�[�ē̑ԓx�͋����I�ŁA�܂�œƍَҁB�ǂ��炩�Ƃ����Ƌ������e���̏����Ɍ�����B�I��̒��ɂ́A���b�J�[���[���ǂ��납�A�s�b�`�ɏo�钼�O�̒ʘH�Ńp�C�v������炷�҂��E�E�E�B �@���M�����[�̑唼���������ԂɁA�N���u�̃t�����g�̓`�[���̈ꎞ�x�~���l���邪�A����ɔ������̂����ē̃}�[�t�B�[�������B�����ɎQ�����Ă��Ȃ������ނ́A�d�������o�X�r�[�ē̑�s�ƂȂ�A�Č��ɐs�͂���B��̂̈������A���n�œ��@����҂̃P�A�A�⑰�ւ̑Ή��ƁA�P�l�ʼn��������Ȃ��ނ̐��ӂƍs���͂ɂ͓���������B �@�������A�{���̓x���`�ł̎d�����B�}�[�t�B�[�͑��̃N���u����R�l�̑I�������A���[�X�̎����ʂɔ��F�B����ȊW�ߌR�c���A�e�`�J�b�v�̌����ɂ܂œ����B���������N���u�̕��݂��A���ӂ̂��߂Ƀs�b�`�𗣂�Ă����`���[���g���̍Đ��Ƃ����������B �@���Ƃ��Ǝ��O�̈琬�I��Ő�͂̑唼���܂��Ȃ��Ă����N���u�����炱���ł������Ƃ��낤�B�C�^���A��X�y�C���̃r�b�O�N���u�͂��̎����A���łɊO���l�I������Ŕ���������Ƃ������Ƃ��n�߂Ă����B���A���E�}�h���[�h��`�b�~�����œ����ߌ����N�����Ȃ�A�}���t�̂悤�ɂP�O�N���o�����ăg�b�v���x���ɕԂ�炭�Ƃ��������͐����Ȃ�������������Ȃ��B �i�Q�O�P�Q�D�T�D�R�O�D�L�j �W�����E�J�[�^�[�@�@JOHN CARTER �i�Q�O�P�Q�N�A�āA�����F�X�{���j  �@�T���E���[�V���g�����w�^�[�~�l�[�^�[�S�x�w�A�o�^�[�x�ɗ��đ����ɏo���������Ƃ��A�ǂ������킯���n���E�b�h�ł́A�������̔o�D�����X���̃G���^�[�e�C�������g���ɑ����đ唲�F�����Ƃ������Ƃ�����B �@�e�C���[�E�L�b�`�������剉��́w�W�����E�J�[�^�[�x�Ƒ�Q��́w�o�g���V�b�v�x����������{�œ������J�B�R�P�ɂ��Ď��Ȃ�ʐl���̏t���}�����B���O���������ł̓s���Ɨ��Ȃ��������A���̐l�A�w�E�����@�����x�̃K���r�b�g�Ȃ�ł��ˁB �@���́w�W�����E�J�[�^�[�x�A����̓G�h�K�[�E���C�X�E�o���[�Y���P�O�O�N�O�ɏ������ÓT�I�X�y�[�X�I�y���́u�ΐ��̃v�����Z�X�v���B���N����ɏ��X�ɓ���Z���Ă������X�Ȃ�A�n���������ɔł̃J�o�[�C���X�g���]���ɍ��肱�܂�Ă��邾�낤�B �w�W�����E�J�[�^�[�x�Ƃ����M��́A����i����l���̖��O�j�����̂܂ܕЉ����ɂ������̂����A�z�����̃f�B�Y�j�[��A����ł́w�ΐ��̃v�����Z�X�x�̖|�Ăł��邱�Ƃ͂��납�A�ǂ�ȃW�������̉f�悩����킩��B�����������A�W�����E�J�[�^�[�Ƃ����A�^����Ɏv�������Ԃ̂́w�d�q�x�̃h�N�^�[�E�J�[�^�[�����E�E�E�B �@����R���m�̃W�����E�J�[�^�[�́A�C���f�B�A��������ē��������A����A�ΐ��ւƏu�Ԉړ����Ă��܂��B�����͂S�{�r�̗ΐF�l��Ԃ����̐ԐF�l���݂��Ɍ��͑������J��L����헐�̐��B�d�͂̏����ȉΐ��Ŕ���I�ɐg�̔\�͂����߂��J�[�^�[�́A�ΐF�l�̃^���X�E�^���J�X�ƗF������Ԉ���A�ԐF�l�̃f�W���[�E�\���X�����ƈ��������悤�ɁE�E�E�B �@�ēE�r�{�̃A���h�����[�E�X�^���g���͍ŐV�s�̂u�e�w�����B����ȉ�₵���ΐF�l��A�W�{���̔n�Ƃ������ٌ`�̃N���[�`���[�����A���ɑ��`���A���������B �@�P��vs���ʂ̒P���ȍ\�}�ł͂Ȃ��A�ΐ��̕������ꂼ��̍R���◠��A�����⌠�d�p���������������d�w�I�ȃX�g�[���[�B�e�����̉��l�ς�i�����������肱�܂�Ă��āA�h���}�Ƃ��Ă̊����x�������B �@�n���Ő��̂Đl�̂悤�ɐ����Ă�����l�����A�ِ��Ŗ`�����d�˂邤���ɁA���̐�������̋��ꏊ�Ǝv����߂Ă����S���`�ʂ��D�܂����B �@�ΐ��Ɋւ���Ȋw�m���̕n��ȁ\�\�悭�����Ζ��̂���\�\����ɏ����ꂽ���ꂾ���ɁA�c�b�R�~�ǂ���͂Ă���B�ΐ��͒n����肸���Ɖ��x���Ⴂ�̂ɁA��n�͂܂�ŎܔM�̍������B �@�ԐF�l�͌��͂Ƃ���q��@�����قǂ̉Ȋw�͂������A���Ă���̂͌Ñネ�[�}���̕��B����ł��āu���̌��͎ア���獂����ׂȂ��v�ȂǂƁA�ςȂƂ���ŗ������ʂ��Ă���B �@�d�͂��P�O���̂P�̊��ɍs�����J�[�^�[�́A���ق̃W�����v�͂ŐԐF�l��ΐF�l�Ɉ�ڒu�����̂����A��������ΐ��l�����Ă��������������炢���ׂĂ������͂����B �@���̎�̍�i�ŋ����[���̂́A�ٕ��������̌��^�̂悤�Ȃ��̂�������Ƃ���B�����̎d������ł́A�ӊO�Ȋ����₨�����݂����킦��B �@�J�[�^�[�ƃ^���X�E�^���J�X�����߂ďo������V�[���ł́A���t���ʂ��Ȃ��܂܂ɁA�݂��̖��O��`���������Ɨ��҂������B�^���X�E�^���J�X�̂j�x�i��C�ǂ߂Ȃ��j�Ԃ�����܂��āA�R�~�J���ł����͂��ȃ_�C�A���O�����킳���B �@�����f�W���[�E�\���X�́A�J�[�^�[�ɑ��z�n�̖͎��}�������A�u�������䂪���A�o���X�[����v�Ɛ����B����ŏ��߂ăJ�[�^�[�́A���ِ̈����ΐ��ł��邱�Ƃ�m��A�����Ȃ�Ƃ��n�ɑ����������C���𖡂키�B�u���͑�R�f���̒n�����痈���v�ƍ�����ƁA�����́u�W���X�[�����痈���́H�v�Ƌ��Q�B���̃V�[���Ȃǂ͌��t�╶��������Ă���ɒʂ�������i�͂���ƁA�ς�҂Ƀ|�W�e�B�u�Ȏv�����������B �@���Ȃ݂ɓ������J�́w�o�g���V�b�v�x�́A�L�b�`��������C�R�m�����A���ڂ������Ă������{�̎��q���i��쒉�M�j�Ƌ��͂��A�G�C���A���̐N�����͂˂���Ƃ����ؗ��āB���̂�����͂ǂ��������ăJ�[�^�[�ƃ^���X�E�^���J�X�Ƃ̊W��A�z����̂����A���Ă݂�Ɠ��{�l�́A�f�J����ƂS�{�̘r���������̗ΐF�l�̖������Ă��Ƃ��E�E�E�B �i�Q�O�P�Q�D�S�D�P�W�D�L�j �a�����������v���������^�u���b�N���z���C�g�@�@THIS MEANS WAR �i�Q�O�P�Q�N�A�āA�����F���Y���ށj  �w�W�����E�J�[�^�[�x�͌��肻�̂܂܂̖M������č�i���e���킩��Ȃ����Ă��܂����Ⴞ���A������́w�a�����������v���������^�u���b�N���z���C�g�x�́A���肪�a�����������v���������Ȃ̂��Ǝv������A�S�R�W�Ȃ���I �@�����THIS MEANS WAR�́u����͐푈���v�Ƃ����Ӗ������B���l�Ɣ��l�̘b�ł��Ȃ���A���ʂƑP�ʂ̘b�ł��Ȃ��{��ɁA�Ȃ����̖M���t�����̂��B���߂āu�u���b�N���z���C�g�v�����ɂ��Ă����Ⴂ���̂ɁA�Ȃ�Łu�a�����������v���������v�܂ŕt����̂�A�ʓ|�������Ȃ��E�E�E�ƁA���{���̉f�惉�C�^�[�Ɖf��G���ҏW�҂��{���������Ƃ��낤�B �@���S�C�Ȃb�h�`�R���r���P�l�̓��������Ƀt�H�[���E�C���E���u�B�݂��̃f�[�g���ז����邽�߂ɁA���������@�q�����ŐV����������E�E�E�Ƃ����E�����p�A�N�V���������u�R���f�B�B���炷�������ǂ߂Ίς�ɑς��Ȃ��ʍ�ɂ��v���邪�A�ӊO��A�ē̃}�b�N�f�̓A�N�V�����A���u�A�R���f�B�̂��ׂĂɖڔz����s���͂����A��X�̃f�[�g���[�r�[�Ɏd���ĂĂ����B �@�b�h�`�R���r�i�e�c�q�ƃ^�b�N�j�ɕ������̂̓N���X�E�p�C���ƃg���E�n�[�f�B�A�Q�l�Ɉ�����郍�[�����Ƀ��[�X�E�E�B�U�[�X�v�[���Ƃ����z�w�B���[�������u��ҏ��v�Ƃ����C���[�W�ɂȂ�Ȃ��̂́A�r�{�Ɖ��o�̋Z�̍Ⴆ���B���i�e�X�g���Ƃ����ޏ��̐E�Ƃ��A�ӊO�Ɉ��}�ގ��ɖ𗧂����Ⴄ�̂����ǂ���B�����̊ϋq�Ȃ�A���[�X������ւ������ւ��g�ɂ܂Ƃ��t�@�b�V�����ɂ��ڂ�������邾�낤�B �@�e�c�q�ƃ^�b�N�̃L�����ݒ�̓o�f�B���̉������B�w�o�b�h�{�[�C�Y�x�V���[�Y�̃E�B���E�X�~�X�ƃ}�[�e�B���E���[�����X�������ł������悤�ɁA���邢�́u���ˉ���v�̏�����Ɗi�������ł���悤�ɁA�e�c�q�͓Ɛg��`�̃v���[�{�[�C�ŁA�^�b�N�͌����ȍȎq�����i�������o�c�C�`�j�B�s��ȃ��[�������D����J��L���钆�ɂ��A�Q�l�̌��̈Ⴂ���ɂ��ݏo��B �u���[�����͂ǂ�����I�ׂ܂���ł����v�Ȃ�ē��a���������ł͂Ȃ��A�Ō�͂�������P�l��I��ł���̂��D���x��B���̑I�ѕ����܂��A�A�N�V�����̃N���C�}�b�N�X�ƍI���ɃV���N������Ă���B �@�R�O��̔o�D���g���āA���������o�J�����]�T���A���{�f��ɂ��~�����Ȃ��B�E�E�E�ƌ��������Ƃ��낾���A���{�̉f���Ƃ���������ƁA�{���̑ʍ�ɂȂ����Ⴄ�낤�Ȃ��B �i�Q�O�P�Q�D�S�D�P�W�D�L�j �A�[�e�B�X�g�@�@THE ARTIST �i�Q�O�P�P�N�A���A�����F�������Y�j  �@�t�����X�l�́u��炱���͕����̒��S�v�Ƃ��������������A����̐��E���č��𒆐S�ɉ��n�߂Ă�����i�܂�́A���{�l���ނ̍����u���t�����X�v�ȂǂƂ��Ă͂₳�Ȃ��Ȃ��Ă�����j�A������O���Ȃǂ̗l�X�ȏ�ʂŕč��ɑR�ӎ���R�₵�A���ɕč������ɔ���Ȏ�����������B �@�Ƃ��낪���́w�A�[�e�B�X�g�x�́A�T�C�����g����g�[�L�[�ɕς�鎞��̃n���E�b�h���A��̔���∫�ӂ������邱�ƂȂ��A�X�g���[�g�ɏ̂����ِF�̃t�����X�f��B�r�{�E�ē̃~�V�F���E�A�U�i���B�V�E�X�́A�A�J�f�~�[�܂̎�܃X�s�[�`�Łu�R�l�̐l���Ɋ��ӂ������B�r���[�E���C���_�[�ƁA�r���[�E���C���_�[�ƁA�r���[�E���C���_�[���v�ƌ�������炢�̐l������A���T�[�`�̂��߂ł����ł��Ȃ��A��������Â��ǂ�����̃n���E�b�h�f��ɐZ��A���ꂱ��ł����̂��낤�B �@�����A�Q�O�N��̃n���E�b�h�ւ̃I�}�[�W�����A�����̃T�C�����g�f��Ɏd���ĂĂ��܂����Ɣ��z�����̂́A�܂��Ƃɂ����ăR�����u�X�̗��B������o���G�e�B�ԑg�̂P�R�[�i�[�Ƃ������Ȃ炢���m�炸�A���E�s��̊ӏ܂ɑς��钷�҉f��ɏ������Ă݂����̂�����A�A�U�i���B�V�E�X�̌��т͏������Ȃ��B �@��l���͔p��䂭�T�C�����g�f��ɂ������A�����Ԃ�Ă�����䏊�j�D�i�W�����E�f���W�����_���j�B�q���C���̓g�[�L�[���̔g�ɏ���ăX�^�[�ւ̊K�i���삯�オ���Ă����V�i���D�i�x���j�X�E�x�W���j�B�����ƗF��A����Ƒ��h���Ȃ������ɂȂ����Q�l�̔����ȊW���A��̃Z���t�����ŕ\���������҂̉��Z�A�ē̉��o�ɐ�������B �@�Q�l���o������A�N�V�����A�X�����[�A�r�e�Ȃǂ̑��ʂȌ��������܂��y�����B�V�[���̂��������ɂ́A���N�̃n���E�b�h�X�^�[�ւ̃I�}�[�W����A�I�[���h���[�r�[�̃p���f�B������߂��Ă���B�c�u�c�������ہA���T�f���ł����Ղ������t���������B �@�A�U�i���B�V�E�X���I���Ȃ̂́A�{������S�ȃT�C�����g�ɂ͂����A�Q�̃V�[���ɂ̂݁A���ʓI�Ɂu���v����ꂽ���ƁB �@�P�̓g�[�L�[�f��̓o�ꎞ�Ɏ�l�������鈫�����B����܂ł̃V�[���ɂ̓X�R�A�ȊO�́u���v�͓����Ă��Ȃ������̂ɁA�����ł����Ȃ�O���X���Ԃ��荇������A�d�b�̃x���������o���B���̒��̎�l���͂��̉��ɂƂ܂ǂ��A���̂̂��킯�����A�悭�l����A����A����������ˁB��ʂ̃T�C�����g�f��Ɂu���v���Ȃ��̂́A�����܂ł��ϋq���猩�Ă̘b�ł����āA�����̓o��l���͕��ʂɁu���v�̂��鐢�E�ɐ����Ă���B���̂����t��ɂƂ��āA�P�̃M���O��n���Ă݂����A�U�i���B�V�E�X�̔��z�͂̌�������B �@�Q�߂̓��X�g�V�[���ŁA�剉�̃W�����E�f���W�����_���͂������ꌾ�A�i�����Ȃ���j���������Z���t�����ɂ���B�g�[�L�[�ɓK���ł����Ɂu���v�̂��閲�ɂ��̂̂����ނ��A�����Ԃ�A��蓹���������ɁA���Ɏ��甭���������B�����ɔނ��g�[�L�[���҂Ƃ��čĐ�����\��������̂́A���Ȃ��������������ł͂���܂��B �@���ꂪ�ǂ�ȃZ���t�ł��邩�͂����ĕ����邪�A�Ƃɂ����f���W�����_���͂��̈ꌾ�����ŁA�A�J�f�~�[�剉�j�D�܂���������B �i�Q�O�P�Q�D�R�D�V�D�L�j �Q�O�P�Q�N�I�X�J�[�i�C�g�E�E�H�b�`���O�I  �@ �@�@�Â��ǂ��n���E�b�h���̂����t�����X�f��́w�A�[�e�B�X�g�x�ƁA�f��n���L�̃t�����X�l�ē��̂����n���E�b�h�f��́w�q���[�S�̕s�v�c�Ȕ����x�B�{�N�͂���ȂQ�삪�I�X�J�[�E���[�X�̘b��̒��S�ƂȂ��Ă��������ɁA�����S�̂̃R���Z�v�g���u�f�戤�v�ɐ������Ă����悤���B���T�̍��ԍ��Ԃɍ������܂��C���^�r���[�f���ŁA���[�X�E�E�B�U�[�X�v�[����I�[�E�F���E�E�B���\�����͂��߂Ƃ���f��l�������A���g�̉f�戤������Ă����̂��n���Ȃ����ۓI�������B �@�����̏��Ղ́w�q���[�S�́`�x���Z�p�n�̂T����𗧂đ����Ɋl���B�n����I�ȑ叟�����\���������B�������I����Ă݂�A��i�܁A�ē܁A�剉�j�D�܂��܂ނT������l�������w�A�[�e�B�X�g�x�̊����ɁB�T�C�����g�f��ł��邾���ɁA�t�����X�f��ł���Ȃ���A���ꂪ�ܑ����̏�Q�ɂȂ�Ȃ������B �@�W���[�W�E�N���[�j�[��u���s���������Ď剉�j�D�܂��l�������W�����E�f���W�����_���́A�o�D�Ƃ������R���f�B�A�����{�Ƃ�����������A�܂��ɃV���f�����{�[�C�̐S�����B�Ƃ͂����T�C�����g����̑�X�^�[�Ƃ����L�������A���Ɍy���ɁA���Ɉ��ɉ������˔\�͖{���B �@�ē܂̃~�V�F���E�A�U�i���B�V�E�X���A�t�����X�f��E�ɂ����Ă������قǂ̎��т͎����Ă��Ȃ��l���B���قȋK�i���v�����A������������x���ł�肨���������ƂŁA�����炭�͖{�l���\�z�O�ł������낤�L�����A�̑傫�ȃu���[�N�X���[�𐬂��������B �@�������D�܂́w�w���v�@�`�S���Ȃ��X�g�[���[�`�x�̃I�N�^���B�A�E�X�y���T�[���A�w�A�[�e�B�X�g�x�̃x���j�X�E�x�W�������������B �@�����j�D�܂́w�l���̓r�M�i�[�Y�x�̃N���X�g�t�@�[�E�v���}�[���W�Q�ɂ��Ċl���A���E�ȃX�s�[�`���I�����B���������u�l�Ԃ��D���A�d�����D���v�Ƃ����^�C�v�̐l�����炱���A���܂ł��B�������ɂ���Ă������ł��ˁB �@�剉���D�܂́w�}�[�K���b�g�E�T�b�`���[�@�S�̏��̗܁x�̃������E�X�g���[�v���Q�X�N�Ԃ�R�x�ځi�����P�x�͏����܁j�̎�܁B�X�s�[�`�ł͂̂�������u�����҂́w�܂�����������x�Ƃ���������������v�ƁA��ė\�h�������B �@���̌��ʁA�剉�j�D�܂́u�O���l�v�A�������D�܂́u���l�v�A�����j�D�܂́u�V�l�v�ƁA�ߔN�Ɠ��l�A�o�D����͌������t���̔o�D�̎�܂��ڗ������B �@�i��͂X��ڂƂȂ�r���[�E�N���X�^���B�����̓G�f�B�E�}�[�t�B�̋N�p�����܂��Ă����̂����A�����v���f���[�T�[���~����������Ŏi��҂��ύX�ɂȂ����B �@������������f���Ă��A���`��A�ǂ������N�̓W���[�N���s��B��N�̂悤�ɕ�������ď��]����Ƃ������W���[�N���A�i��҂�����v���[���^�[��������܂�o�Ȃ������B�i��҂̌��́A�W���[�N��Ƃ����ɂ����h��^�����̂��H �@����Ȓ��ŏ��グ�������Ȃ��l���́A�r�{�܂̃v���[���^�[�Ƃ��ēo�ꂵ���A���W�F���[�i�E�W�����[�B�����O�h���X�̃X���b�g����s���R�ɂ��ݑ����̂������闧���p�́A�����̃M���O���Ǝv������A��܂��߂������悤���B��܂����w�t�@�~���[�E�c���[�x�̋r�{�Ƃ̂P�l���A��������������p�N���Ă����B �@�P�T�Ԍ�A�����m�̂����瑤�ł����{�A�J�f�~�[�܂̎������B�����̐V���Ō��ʂ����ċ����܂�����B�Ȃ�Ɓw�����ڂ̐�x���P�O�����B �@���̉f��A�o�J�ȕ�q�����ɂ킽���čȎq����i������܂�Ȃ��j�j�̎q����D�P���Ă��܂��Ƃ������у��m�̃X�g�[���[�ŁA�����炪����ړ��ł���L�����N�^�[���A���悻�P�l���o�ꂵ�Ȃ��B�ɂ�������炸��i�܁A�ē܁A�r�{�܂Ǝ�v����𑍂Ȃ߂ɂ������肩�A�o�J���P���͏������D�܂ɁA�o�J���Q���͎剉���D�܂ɋP�����B���[��A���{�f��E��A����ł����̂��H �i�Q�O�P�Q�D�R�D�U�D�L�j �q���[�S�̕s�v�c�Ȕ����@�@HUGO �i�Q�O�P�P�N�A�āA�����F����T�q�j  �@���̃}�[�e�B���E�X�R�Z�b�V�����������f��H�@�������R�c�H�@�������s���������Ȃ��Ɖ��^�I�Ȏv���Ŏ��ʂɑ����^�̂����A�\�z�͂������ɗ���ꂽ�B���������f��Ƃ��āA�R�c�f��Ƃ��āA�����ā����f��Ƃ��������ȃW����������������������f�悻�̂��̂Ƃ��āA�{��͑f���炵���㎿�Ȉ�삾�����B �@����͂P�X�R�O�N��̃p���B���e��S���������N�q���[�S�i�G�C�T�E�o�^�[�t�B�[���h�j�́A�w�̎��v��ɉB��Z�݁A�������ǂ��ɂ��������тĂ���B�ǎ��@�̕�炵�͔ߎS������A�����Ɍ�����킯�ɂ͂����Ȃ��̂��B������A�I���`�����œ��݂��͂��炱���Ƃ����q���[�S�́A�X��̃W�����W���i�x���E�L���O�Y���[�j�Ɍ�����A���e�̈�i�̃m�[�g�����グ���āE�E�E�B �@�����R�c�ł��W�F�[���Y�E�L����������i�̂���́u���Ԃ��I�v�Ƌ��т����Ȃ�悤�ȃV���{�����������A������̓P�����������Ղ肾�B�q���[�S���w�\���̑厞�v�̂˂��������ĕ����I�[�v�j���O�ł́A���̖��{�̂悤�ȋ@�B���̉��s���A����A�ΎG�����A���ߊ����ɂ��ɂ������������ĕ`�����B�X�R�Z�b�V�͂������A�B�e�ēƔ��p�ē��A�{���ɂ����d�������Ă��ꂽ�B �@���������̃T�V���E�o�����E�R�[�G���̒������⍂���@���A��ʂ����яo���Č�����悤�ȃJ�b�g���B����ς�R�c��i�ɂ́A���������V�ѐS���Ȃ��ƂˁB �@�I���`�����̓X��W�����W�����A���͉f��n���L�̎��݂̊ēA�W�����W���E�����G�X�������Ƃ킩��ɋy�сA�ǓƂȏ��N�̃T�o�C�o��杂Ɏv��ꂽ����́A�u���������V�ˁv�̈̋Ƃ��̂���]�`�f��Ƃ��Ȃ��Ă����B�������ŏ�f���Ԃ͂P�Q�U���ƁA�q�������f��Ƃ��Ă͏������߂ɂȂ��Ă��܂������A������ł��A�ʔ�����A�����Ă��B �@�W�����W���̗{���̃C�U�x�����������̂��A�w�L�b�N�E�A�X�x�ň�������グ���N���G�E�O���[�X�E�����b�c���B�A�g�����^���܂�Ȃ���A��������C�M���X�a����K���B�t�����X�l�̖�������A�����J�p�ꂾ���ĕʂɂ��܂�Ȃ����낤�Ƃ��v�����A���̃L���X�g���S���C�M���X�l�������a������킹����ł��ˁB �@���w�����̃C�U�x���́A�ӂƂ�����b�̒��Łu�q�[�X�N���t�v��u�f�r�b�h�E�J�b�p�[�t�B�[���h�v�������o���A���邢�͐Ԗт̃A���Ɠ��l�ɁA�����r�b�O���[�h�i�����ē���P��j���g���āA�w�Z�ɍs���Ă��Ȃ��q���[�S�̖ڂ𔒍�������B �@�C�U�x���ɖ{��ǂ܂Ȃ��̂��Ɩ���A�q���[�S���p���Ă��܂����V�[�������邪�A�Q�[�����������Ă���q�Ȃ̎q���������A�����悤�ɒp���Ă���邾�낤���B �@����A�C�U�x���̓C�U�x���ŁA�@�B������╨��肪���ӂȃq���[�S�Ɉ����ڂ������A�u�������܂�Ă��������͉��H�v�Ɩ₤�B�q���[�S�͂���ȃC�U�x�����̎��v��ɓ����A����Ȃӂ��Ɍ��̂��B�u�@�B�ɂ͗]���ȕ��������Ȃ��B���ׂĕK�v�ȕ����肾�B��������p���̊X�߂�ƁA�܂�łP�̋@�B�݂����Ɍ�����B�l���������̈ꕔ�Ȃ���A�����Ǝ����̖����Ƃ������̂�����͂�����v �@�N�Ⴂ�I�[�f�B�G���X�́A�܂����������҂���m�炸�A�Ƃ�����C�U�x���Ɠ����Y�݂���������B�q���[�S�̃Z���t�͂���Ȏq�������ɉ��₩�Ȉ��S���Ǝ��ȍm�芴��^����A�f���炵���ǐS�I�ȃ��b�Z�[�W�ł͂Ȃ����낤���B �i�Â��C�^���A�f��́w���x�ɂ��A����Ƃ�������̃Z���t�������������j �@�f��̗��j���̂��A�ÓT���w���̂��A�l�Ԃ̉��l��\�����̂��邱�̍�i�B���w�Z���w�N�̉䂪�Â��q�Ɖ����q�ɁA���ЂƂ����E�������P�{���B �Q�O�P�P�N�i���́j�x�X�g�T�I �@�Q�O�P�P�N�͊ӏ܂����f��̖{�����X�V�{�ɂƂǂ܂�A���N�Ԃ�ɂP�O�O�{���������B�����{��k�Ђ̉e���Ŏ��ʂ��i�肱���ƂƁA�{�Ɓi�|��j�����ƖZ�����������Ƃ��������B �@���ꂪ����������Ƃ����킯�ł��Ȃ��̂����A��N���̂g�o�ɏ����Ă����x�X�g�P�O���A���N�̓x�X�g�T�ɍ팸���邱�ƂɁB�u���v�������i���������A����͐k�Ђ�������������ʂɋՐ��ɐG�ꂽ�Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A�P�Ȃ���R���낤�Ǝv���B �@���Ȃ݂Ɂw�T���̌��x�w�E�B���^�[�Y�E�{�[���x�w�킽���𗣂��Ȃ��Łx�́A��������������ۉf��Ղœ��{�ɏ����ڌ����������̂́A�n���ȉf��ł��邽�߂��A������J�����܂łɂ��Ȃ�̎��Ԃ�����������i�B����ł��c�u�c�X�g���[�g�ɂȂ炸�ɍς̂́A�������ۉf��Ղł̍D�]�����������߂��낤�Ǝv���B �@�ŋ߁A�n�Ւ����C���̓��f��Ղ����A���̈Ӗ��ł͊J�Â����Ӌ`���ʂ����Ă���ƌ�����̂ł́B �P�@�w�u���b�N�X�����x �Q�@�w���u���h���b�O�x �R�@�w�T���̌��x �S�@�w�i���̖l�����x �T�@�w�E�B���^�[�Y�E�{�[���x ���_�@�w�킽���𗣂��Ȃ��Łx ��a���m�̉�����R�{ �@���̏H�͖{�Ƃ����ɖZ�����A���z�[���y�[�W���X�V���Ă���]�T���Ȃ������B���̊ԂɌ��J���ꂽ�w�E�B���^�[�Y�E�{�[���x�w�J�E�{�[�C���G�C���A���x�w�����S�x�Ȃǂ͂���������z���L���ɒl�����i�������̂����A���͂�^�C�~���O���������̂Ŋ������悤�B�j���̒��Ɠ��l�A���̒��A���荇�킹�ł��ˁB �@����A�ӏH���߂��Ă����a���m�ɗނ�����삪�R�{�����Č��J���ꂽ�̂́A���R�Ƃ͂������ڂ����Ƃ���B��������{�̓�a���m�Ƃ͈Ⴂ�A�����Ƃ��������邱�Ƃł͂Ȃ��A�����邱�Ƃ̑�����`���邱�ƂɎ�Ⴊ�u����Ă���_�������B ���u���h���b�O�@�@LOVE AND OTHER DRUGS �i�Q�O�P�O�N�A�āA�����F�H�j  �@�W�F�C�~�[�i�W�F�C�N�E�M�����z�[���j�͔����Ԃ��Ȃ��o�C�A�O�����������蔪���Ŕ���܂���Z�[���X�}���B�}�M�[�i�A���E�n�T�E�F�C�j�̓C�[�W�[�ȃZ�b�N�X����������̂́A�j���Ɛ^���ȊW�����Ԃ��Ƃ�����Ă���p�[�L���\���a���ҁB�Q�l�͏o����āA���ɗ����A�ʂ�āA�Ăт������āE�E�E�B �@�������Ă��炷�����������Ɩ{���ɒ��ȃ��u�X�g�[���[�Ɏv���Ă��܂���������Ȃ��B�ł��r�{�E�ē̃G�h���[�h�E�Y�E�B�b�N�́A�N�Y�j�̐S�ɏ���萶���Ă����ߒ���A���ɉ��a�ɂȂ������̐S������ɊJ����Ă����l�J�����A���ɕ`�ʂ����B���̊ēA�ߔN�́w���X�g�T�����C�x�w�f�B�t�@�C�A���X�x�Ȃǂ̍����ȍ�i���D��ŎB���Ă����l�Ȃ̂����A�i���p�ȍ�i���B�点�Ă��A����Ȃɂ��܂������B �@�����ɂ̓p�[�L���\���a�����錵�����������A��������Ɠ��ꂱ�܂�Ă���B���҂̑��ɎQ�������W�F�C�~�[�́A�����Œm�荇�������N�j����u�Ȃ͎���Ɏ����ł͂Ȃ��Ȃ��Ă����B���͍Ȃ������Ă邩��ς��邯�ǁA�N�͂܂������O�Ȃ���ʂꂽ���������v�ƒ�������āA��傷��B �@����ł��Ō�ɃW�F�C�~�[�́A�u�N�ƂQ�l�����������������v�Ɛ��S���ӁA�C������f�I���A�}�M�[�͂������A�ϋq�̔M���܂����U���̂��B�o���҂��u���v�ł͂Ȃ��u���v�Ɍ����킹�邱�Ƃł��A�����Ƌ�������f��͍���̂��Əؖ������A�P�ٌ��J�����܂�ɂ��ɂ�����{�B �T�O�^�T�O�t�B�t�e�B�E�t�B�t�e�B�@�@50/50 �i�Q�O�P�P�N�A�āA�����F�Γc�q�j  �@�����ɃK�������������r�{�Ƃ̃E�B���E���C�T�[���A���g�̑̌����V�i���I��������i�B�^�C�g���́u�T�N���������ܕ��ܕ��v�Ƃ����Ӗ����B �@�����^�o�R�����Ȃ����W�I�Lj��̃A�_���i�W���Z�t�E�S�[�h���������B�b�g�j�́A�Q���ɐ��̃K���鍐����B�K�[���t�����h�͏d�ׂɑς����ꂸ����Ă����A�S���I�ȃT�|�[�g�����Ă����͂��̃Z���s�X�g�͎Ⴍ�Ăǂ��ɂ�����Ȃ��B�e�F�i�Z�X�E���[�Q���j�͐e�g�ł͂��邪�A�u�K�����l�^�Ƀi���p����v�Ȃǂƌ��������܂�ɔj�V�r�B�S�z���܂����e�͏d�����A�R�K���܂͌����Ȃ����E�E�E�B �@���g�̑̌����h���}������ƁA�ǂ����Ă���ς��甲���o�����A�q�ϓI�Ȗʔ������o�����Ƃ͓���B�����{��́A�L�����N�^�[�Ƃ����A�G�s�\�[�h�Ƃ����A�����ȏ�̎d�オ�肾�B�����炭�����̑唼�́A���b�ł͂Ȃ��n��Ȃ̂��Ǝv����B���[�T�[�̏ꍇ�́A�����������a������A�e���̂��������[�Q���ɋr�{�������߂��Ă��������Ȃ̂ŁA��������u���҂̎��_�v�������Ď��������Ă����̂�������Ȃ��B �@���{�l�̂R���̂P���K���ɂ�����ƌ����鍡�A�A�_���Ɠ����悤�ȑ̌�������l�X�͑����������낤�B�{��͂���Ȋ��҂����i�Ɛ��ݓI���҂����j�ɁA�C�̎������̃q���g���A���邢�͏����ȗE�C��^���Ă����B��킭�͎��̐e�����l�X��A�S�������l�X���A���C�T�[�i���A�_���j�Ɠ������̂T�O���Ɋ܂܂�Ƃ��B �i���̖l�����@�@RESTLESS �i�Q�O�P�P�N�A�āA�����F�������Y�j  �@���l�̑����ɕ��ꂱ�ނ̂���̃C�[�m�b�N�i�w�����[�E�z�b�p�[���f�j�X�E�z�b�p�[�̈⎙�������Łj�́A������A���V���Ɍ��Ƃ��߂�ꂽ�Ƃ�����A�i�x���Ƃ��������i�~�A�E���V�R�E�X�J�j�̋@�]�ɋ~����B����ɋ������l�߂�Q�l�����A�A�i�x���͖����K���ɖ`����Ă��āE�E�E�B �@�������͌��肠�閽����g�ł���Ȃ���A�����͂���Ȃ��ƁA�Ƃ�ƈӎ����Ă��Ȃ��B�ϋq�̑�\����C�[�m�b�N���A�A�i�x���ɗ]���R�J�����ƕ������ꂽ���A�u�R�J������t�����X�ꂾ���Ċw�ׂ邵�A�}�����o�����Ēe���邳�v�ƁA�Ђǂ��Ȍ��t��Ԃ��B�������̂R�J�������ɉ߂��������A�C�[�m�b�N�̒��ʼn������ς��B�����Ď���������ʂ��ŋ��Ɏd���Ă�A�i�x���̈���ɁA�{�C�ŕ��𗧂Ă�̂��B�K�X�E���@���E�T���g�ḗA���r���[�Ɏ��ɂƂ���ꂽ�N�\�K�L���A���̑���ɖڊo�߂Ă����v���Z�X���A���ɂ݂��݂��������ʂ����B �@�^����B�ς������̂悤�ȁu�s�v�c�����v�n�����������郏�V�R�E�X�J���܂����͓I�B�Ƃ�킯��ۂɎc��̂́A�n���E�B�[���̖�A�ޏ����u�d���̏����v�ɕ����A�u���̃A�i�x���Ƃ��������͔��������v�u�����Ă���̂��v�ƃC�[�m�b�N��₢�߂�V�[�����B�ޏ��͂���Ȏŋ����݂����Ƃ�ɂ��ƊāA�X�g���[�g�ɂ͕����Ȃ�����̖{���������o�����Ƃ���B���Ƃ��I�V�����ȋr�{�i�W�F�C�\���E�����E�j�ł���B �@�{�e�ŏЉ��R��i�̂����A���ۂɓ�a���҂����Ɏ���͖̂{�삾���B���{�f��ƈ���āA�m���̕a�l�����܂�ɍۂɉ��X�ƈ��Ɗ��ӂ����ɂ���Ȃ�ăx�^�Ȃ��܂��傤�����V�[���͂Ȃ����A����ł��ăV���~���Ƃ����]�C���c���Ă����B �i�Q�O�P�P�D�P�Q�D�Q�W�D�L�j ���~�b�g���X�@�@LIMITLESS �i�Q�O�P�P�N�A�āA�����F�H�j  �u���ق̐V��v����ɓ��ꂽ�삯�o���̍�ƃG�f�B�i�u���b�h���[�E�N�[�p�[�j�́A���������˂Ă�����i����ӂŏ��������A���ő�ׂ����ď��������B�Ƃ��낪���̖�ɂ͊댯�ȕ���p�������ɁA�����_���E��������ǂ���͂߂ɂȂ�E�E�E�B �@�A�����E�O�����̃x�X�g�Z���[�w�u���C���E�h���b�O�x�����삾���������A��i�Ƃ��Ă̊����x�͂��Ȃ�r���B����ł��f�B�e�[���ɂ����������[���_���������̂ŁA�����ďЉ�Ă݂����B �@������̖�m�y�s�S�W�́A�����Q�O�������g���Ă��Ȃ��l�Ԃ̔]���P�O�O�����p������̂��Ƃ��B�ē̃j�[���E�o�[�K�[�́A�g�g�p�O�h�Ɓg�g�p��h�ʼnf����Ɩ��̎�����ς��A�ǂ���������肵����l�����ʐl�̂悤�ɃV���[�v�ɕς��p��\�������B �@�ʔ����̂́A�g�g�p�O�h�ɂ͂ނ��ꂵ������L���A�������U�炩�����肾�����G�f�B���A�����Ȃ����r�[�ɐg�Ȃ�𐮂��A�����̑�|�����n�߂��Ƃ���B��͂�u�^�������琬���҂͐��܂�Ȃ����Ă��ƂȂ�ł��傤���ˁB�ł�����A�j���g���Ɨ��̂ǂ��炪��Ȃ낤�H �@���Ȃ݂ɂm�y�s�S�W�́A�N������ł��R�O�b�Ō����ڂ������D����́B�E�����ɒǂ�ꂽ�G�f�B�̌��ȁi�A�r�[�E�R�[�j�b�V���j���A������ꗱ���ނ��ƂŊ�@��E����W�J�͑N�₩�������B �@�����Ƃ��A�m�y�s�S�W�����҂������Ȃ�̂́A�ߋ��ɖڂɂ�������Y�p�̒ꂩ�炷�����グ�A���̊W����I�m�Ɍ���������炵���B�ƂȂ�ƁA�낭�ɖ{���V�����ǂ܂��A�Q�[�����肵�Ă���A���̏ꍇ�́A����ł����~�b�g���X�i���x�Ȃ��j�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��̂�������Ȃ��ˁB �i�Q�O�P�P�D�X�D�Q�S�D�L�j �Č��w���l�܂ł̋����i�f�B�X�^���X�j�x�@�@BEFORE SUNRISE �i�P�X�X�T�N�A�āA�����F��c���T���j  �@���̒��ɂ͋C�ɓ������{�����x���ǂݕԂ�����A���N�������]�[�g�ɏo�������肷�����ȕ�������悤�����ǁA���͗ǂ������������m�ւ̍D��S�������̂ŁA���肠�鎞�Ԃ₨�������m�̂��̂ɐU�������̂́A�ǂ��ɂ���������Ǝv�����Ⴄ�B �@�f��ɂ��Ă�����͕ς�炸�A�ǂ�ȂɊ���������i�ł��A���łɂP�x�����f��ɂ́A�Ȃ��Ȃ��H�w�������Ȃ��i�d���ŕK�v������Εʂ����j�B �w���l�܂ł̋����i�f�B�X�^���X�j�x���A���̂������Ԃ����Ǝv���A�^��@�ɓ�����ςȂ��ɂ��Ă�����i�������̂����A�����͑䕗�P�T�������c�f�B���Ԃ̌o�ϊ����������P�����炢�A�����D���`����߂Ă��悩�낤�ƁA���̂P�X�X�T�N��i���v�X�ɍČ������̂������B�^�悵�����t������Q�O�O�W�N�P�P���P�Q�����B�R�N�߂����A���͉������Ă����̂��H �@����̗�ԓ��ŏo������A�����J�j�q�W�F�V�[�i�C�[�T���E�z�[�N�j�ƃt�����X���q�Z���[�k�i�W�����[�E�f���s�[�j���A�E�B�[���̊X�����Ă��Ȃ��Ԃ���Ȃ���A����ׂ��Ă���ׂ��ĐQ�Ă���ׂ�Ƃ����A�[�I�Ɍ������ꂾ���̉f��Ȃ̂����A���`���[�h�E�����N���C�^�[�ē̏����ꌩ�Ƃ�Ƃ߂̂Ȃ��_�C�A���O�ɂ́A�����ɖ��Z���t������߂��āA�\�t�B�X�e�B�P�[�V�������_���B�݂��̉��l�ς�����ς�O�����Ɍ���W���āA����ς肢����ˁE�E�E�ƁA�����܂ł͏����̂Ƃ��̊��z�̍Ċm�F���B �@�����̂Ƃ��������Ă����̂́A���͂��ꂪ�u�W�����[�E�f���s�[�̉f��v�ł��������ƁB�z�[�N�ƃf���s�[�̒m���x���ׂ�Γ������������炩�ɑO�҂̕����ゾ���A���ꂪ�p��Ō����A�����J�f��ł��邱�Ƃ����܂��āA�����̊ϋq�́u�f���s�[���q�������C�[�T���E�z�[�N�̉f��v�Ƃ������������Ă����Ǝv���B �@�Ƃ��낪���҂́w�r�t�H�A�E�T���Z�b�g�x��A�f���s�[���ēE�r�{�E�剉�߂��w�p���A���l�����̂Q���ԁx��������ł́A������������i�������Ă����ˁB �@���Ƃ����R�[�h�X�̋����������łQ�l���������鏘�Ղ̃V�[���B�W�F�V�[�̓L�X�����Ⴈ�����Ɩ����Ă���̂����肠�肾���A����肪�����A�ڂ�����������Ɩڂ����炷�B�Z���[�k�͖��炩�ɂ��̉��S�ɋC�Â��Ă���A�����Łu����H�v�ƗU���Ă���B�W�F�V�[���{���ɃL�X������A�u���_�A�������v�Ƃ��S�ɂ��Ȃ����Ƃ����������ɁB�Ⴉ�肵�z�[�N�ƃf���s�[�́A�Ƃ��ɂ���Ȕ����Ȏd����\���\������̂��܂��Ƃɂ��܂��I �@�E�B�[�������̑�ϗ��ԂŎ��ۂɏ��L�X����V�[�������āA�������Ă������Ń��S���S������ǂ�ł��邾���̃W�F�V�[��K�ڂɁA�Z���[�k�̕�����u�L�X�������́H�v�Ə����D�B �@�W�F�V�[���u�w�^���v�Ə��̂͂��₷�����A�j���̊W�Ȃ�Ă��̂��炢�̃o�����X�ł�����Ȃ��������H�@�f�[�g�������������_�ŁA�j�q�̂��������Ƃ͂킩���Ă���B����A���q���ǂ��܂ł��������͂킩��Ȃ��B�ƂȂ�Βj�q�����������i�܂��Ă�f�[�g���C�v�j������A���q���ӎv�\���������������I���B����Ƃ��A����������͕̂M�҂����H�������炩�B �@�X�g�[���[�̐��i���i�܂�͎���j���Z���[�k�ł��邱�Ƃ́A�u�d�b�������v�̃V�[���Ɏ����Ĉ�w���m�ɂȂ�B���ꂼ�ꂪ�ʂ̗F�B�Ɠd�b�Řb���ӂ������Ƃ����V�т̒��ŁA�Z���[�k�͎������ŏ�����W�F�V�[�Ɏ䂩��Ă������Ƃ𖾂����̂��B�ϋq���o���Ă���̂́A�W�F�V�[���Z���[�k��r�����Ԃ����悤�ƌ����ɐ����������Ƃ���������A�Z���[�k�̂��̂��肰�Ȃ������́A�V���[���b�N�E�z�[���Y�̓�����̂悤�ɂ��������B �@�₪�Ĕ��N��̍ĉ��ĕʂ��Q�l�i���̖��ʂ����ꂽ���́w�r�t�H�A�E�T���Z�b�g�x�̒��Ō����j�B�����ŋ����[���̂́A�G���f�B���O�̃J�b�g���z�[�N�ł͂Ȃ��A�f���s�[�ɂȂ��Ă������Ƃ��B��͂胊���N���C�^�[�ɂƂ��āA���̉f��̓f���s�[�̂��̂�������ł��ˁB �u�d�b�������v�̒��̃Z���t���C�ɂȂ��āA�����P�x�I�[�v�j���O�ɖ߂��Ă݂�A���`��A�m���ɗ�Ԃ̒��ōŏ��ɐ����������̂̓W�F�V�[�����A�O���̂��Ƃ�ŏI����Ă��Ă����������Ȃ��͂��̉�b���A�Z���[�k�̕����Ȃ��ł��B�v�Z���v�Z�Ɗ��������Ȃ��A�����N���C�^�[�̎����̋r�{�ɂP�{�Ƃ�ꂽ�B �i�Q�O�P�P�D�X�D�Q�P�D�L�j �X���[�f�C�Y�@�@THE NEXT THREE DAYS �i�Q�O�P�O�N�A�āA�����F���Y���ށj  �@�����̍߂œ������ꂽ�Ȃ�E�������邽�߁A���}�ȋ��t�������Ȍv������グ�A����ƍ߂Ɏ����߂Ă����B����Ȕ���ȋؗ��Ă������Ă����t�����X�f���w���ׂĔޏ��̂��߂Ɂx(08)�́A����̓n���E�b�h�����C�N�ł��B �@�t���b�h�E�J�o�C�G���ē����I���W�i���ł̃f�L��������G�킾�����̂ŁA�����ɖ���̃|�[���E�n�M�X�Ƃ����ǂ��A���������I���W�i�������i�͍��Ȃ����Ɗ뜜���Ă����̂����A���`��A����ς�˂��Ċ������B�A�N�V�����V�[����傪����ɂ�����A�ׂ��Ȑݒ��́u�I�J�Y�v�𑝂₵���肵�����ƂŁA��f���Ԃ͂X�U������P�R�T���ւƑ啝�ɐL�т����A�ύX�_�͂�������}�t�ɓ����镔���B�n�M�X�͍����ɓ����镔���ŐV�����o�����Ƃ��ł��Ȃ������B �@�č��̊ϋq�ɂƂ��Ă̓t�����X��̖���������␁���ւ��Ō��Ȃ��Ă��ނƂ������_�����邾�낤���A���{�l�Ȃ�I���W�i���ł����邾���ŏ\�������B �@��l���Ƀ��b�Z���E�N���E���N�p�����̂�����̂ЂƂB�I���W�i���ł̃o���T���E�����h���͖{���ɍႦ�Ȃ��I�W�T���ŁA�命���̕��}�Ȋϋq�́A�傻�ꂽ�s�ׂɑ���˂����ޔނ̋��|��ْ����A�܂�ʼn䂪���Ƃ̂悤�Ɋ����Ƃꂽ�B �@����A�N���E�͌��킸�ƒm�ꂽ�O���f�B�G�[�^�[�ł���A���r���E�t�b�h�B�܂�͒N�����F�߂�^�t�K�C���B�����Ȃ珗�ЂƂ�E�������邮�炢�y�������E�E�E�Ɗϋq�Ɋ������������_�ŁA���̍�i�̖��͔͂�������ƌ��킴��Ȃ��B �@��l���̕��e���Ђǂ������Ȃ̂́A�I���W�i���ł̐ݒ�P�B�v�X�Ɍ���u���C�A���E�f�l�q�[�����������o���Ă����B �@�Ȗ��̓G���U�x�X�E�o���N�X�����������A�I���W�i���łƓ����_�C�A���E�N���[�K�[���N�p���Ă��ʔ��������̂ɁB �i�Q�O�P�P�D�X�D�P�W�D�L�j ���̘f���F�n���L�@�@RISE OF THE PLANET OF THE APES �i�Q�O�P�P�N�A�āA�����F�˓c�ޒÎq�j  �@�P�X�U�W�N���J�́w���̘f���x�́A�r�e�f��̋������̂ЂƂƌ����Ă������낤�B�ސl�����l�Ԃ��x�z���邻�̐��E�́A�r�W���A���I�ɂ��v�z�I�ɂ��Љ�ɑ傫�ȏՌ���^���A�����̑��҂����ꂽ�B �w���̘f���F�n���L�x�́A���̍����ɗ����Ԃ�A�Ȃ��n�������̂悤�ȏ�Ԃɗ����������̂����������O��杂��B�A���c�n�C�}�[�a�̐V��𓊗^���ꂽ�`���p���W�[�̐Ԃ�V�V�[�U�[���A��������ɘA��A�l�ԕ��݂̒m�\���l������B���������q�̂悤�ȊW�����Ȋw�҂������������A�T���̎��e�{�݂ɓ����ꂽ���A�V�[�U�[�̐S�ɍ��݂Ƒ����݂��萶���E�E�E�B �@�o�ꂷ��ސl���̓��{�b�g�ł�������݂ł��Ȃ��A�o�D�̉��Z��\����R���s���[�^�[�Ɏ�肱��łb�f���������́B���̃��A�����ɂ͐�������B �@�V�[�U�[�����Ԃ̃T���𗦂��āA�������N�����Ă���̃X�y�N�^�N���͈����B�T���t�����V�X�R�̎s�X�n��S�[���f���Q�[�g�u���b�W��ɁA�q�g�ƃT�����S�ʑΌ����J��L����B�U�W�N�łł́u�n�ɏ�����T���v�Ƃ����G�Â炪���Ɉ�ۓI���������A�{��ł��ő�̃N���C�}�b�N�X�V�[���ł��ꂪ�g���A�q�Ȃ������̂�ڂɕς���B �@�l�I�ɋ����[���̂́A���e�{�݂�E�������T���R�c���A�^����ɐ����Ђ��P�����ƁB�ނ�ɂƂ��Đ����Ђ́A�u�����������s�������G�v�ł������A�u���������𗘌��ɂ��Ă��ꂽ���l�v�ł�����͂����B�ɂ�������炸�A���̖\���B�ނ�́u�����Ȃ炴��ҁv�ɂȂǁA�Ȃ肽���Ȃ������Ƃ������Ƃ��B �@���������Ώ����w�A���W���[�m���ɉԑ����x�̎�l���`���[���[���A�m�b�x��̎�����V�˂ɕς����Ȋw�҂������A�傢�ɍ��̂������B �@�ł��A�҂Ă�B�T�����������^���ꂽ�̂́A�A���c�n�C�}�[�a�̎��ÖB��������A����ŏǏ��P�����A���c�n�C�}�[�a���҂́A�����Ђ����ނ̂��B���ނׂ��Ȃ̂��B �@�`���ŗ���̐��E�I�茠�ɏo���s�X�g���E�X�I��́A���\�̂悢�`������������[�J�[������ł͂��܂��B����A��w�̔��B�ŁA��̑O�Ȃ���炩�Ɏ��˂��͂��̊��҂��i����Ӗ��Łj�s�K�ɂ���������Ă���B�`���[���[�ƃs�X�g���E�X�̊Ԃ̂ǂ��ɋ��E���������ׂ��Ȃ̂��A���ɂ͗e�Ղɓ������o���Ȃ��B �i�Q�O�P�P�D�X�D�P�W�D�L�j �g�����X�t�H�[�}�[�@�_�[�N�T�C�h�E���[�� TRANSFORMERS: DARK OF THE MOON �i�Q�O�P�P�N�A�āA�����F�H�j �@�Q�O�P�P�N�̉ċx�݉f��͂ǂ��ɂ��喡�ȍ�i���ڗ��������A���̍ł�����̂�����B�O����Ɏd���Ă�悤�ȑf�ނ��˂��B�����Ă݂�I���`���̐�`�f�悾���B����ȑ�^�ʖڂȉf��ɂ��Ăǂ�����H�@���J�����ƃ��^���N����l���ɏ����f������悤�Ȃ��̂��B �@����ł��S�Ăő�q�b�g����̂�����A�����Ȃ��ЂƂ�̓��{�l���A����ȂƂ���ł��݂������āA�S�}���̎�������ɂ����Ȃ�Ⴕ�Ȃ��B���{�ł́u��҂��Ԃɏ��Ȃ��Ȃ����v�ƌ����ċv�������A�A�����J�ł͖{��ɉ����A�w�J�[�Y�Q�x��w���C���h�E�X�s�[�h�@�l�d�f�`�@�l�`�w�x���ɂ߂čD���B��͂肠����́A�܂��܂��ԎЉ�ł���A�܂�́u�Ԃ̓J�b�R�����v���̂ł��葱���Ă���̂��B �@�Ƃ͂����A�������̐ݒ�͂܂��܂��G��B�ă\���U�O�N��ɋ����Č���ڎw�����̂́A�F�����猎�̗����ɔ����u�����v���悷�邽�߂������Ɛ�������B�Ȃ�قǁA���ꂪ�{���Ȃ�i�{���Ȃ킯�Ȃ����j�����̗������{�̐q��ł͂Ȃ��͂̓�����ƁA���̌�̋}���ȔM�̗�ߕ����[���ł��悤�Ƃ������̂��B �@�E�E�E�Ɨ_�߂����ł����Ƃ���A���߂Č��ʒ������ʂ������A�[���X�g�����O�D���ƃI���h������s�m���A���j�������Ɍ��ʂ��s�����s���������Ă����V�`���G�[�V�����Ɍ����������������B��ȃ��P�ˁ[����I �@�ł����̃I���h��������͂m�`�r�`�̂��̕����ŃJ���I�o�����Ă�������A���̕��уV�[���ɂ��{���Ă��Ȃ��݂����ł��ˁB �i�Q�O�P�P�D�W�D�Q�X�D�L�j �u���b�N�E�X�����@�@BLACK SWAN �i�Q�O�P�O�N�A�āA�����F���Y���ށj  �@�O��́w���X���[�x�ł̓��A���ɓO�����f���ƃX�g�[���[�e�����O�Ń��[�g�����X���[�̔߈���`�����_�[�����E�A���m�t�X�L�[�ē��A����ł͈�]���ċ����̂��킢��˂������A�|�̖��{�ɂ͂܂����Ⴂ�o�����[�i�̋��C��˂��l�߂�B�I�[�v�j���O�̃_���X���炵�āA�����Ȃ�b�f����g�����f��I���������ځB�A���m�t�X�L�[�͓Ƃ�悪��ȏ�ʓW�J�̘A���Ŋϋq��u���Ă��ڂ�ɂ����w�t�@�E���e���x(06)���A�����ł͂��܂����ʋ��t�ɂ�����ۂ��B �@�剉�̃i�^���[�E�|�[�g�}���́A�u�ʔ��݂̂Ȃ��D�����v�ƌĂ��̂������Ƃ����A��삲�ƂɃk�[�h�ɂȂ�����A�V�哪�ɂ�����ƁA�����̃`�������W���J��Ԃ��Ă������D�B����Ȕޏ������́w�u���b�N�E�X�����x�ʼn����Ă���̂́A�e�N�j�b�N�����\�����Ȃ����̂́A������z����������\�����邱�Ƃ��ł����ɑ��H�ɓ����Ă��܂����D�����̃o�����[�i���B�����ɂ���Ă͉��Ƃ�����ȃL���X�e�B���O�ł͂Ȃ����B �@�ʔ����̂́A�������Ń|�[�g�}����D�P�������U��t���t�̃x���W���~���E�~���s�G���j���_���T�[���ŏo�����Ă��邱�ƁB�r�{���������A���m�t�X�L�[�́A�Q�l�̒���m���Ă��m�炸���A�|�p�ē��̃o���T���E�J�b�Z���̌�����A�u����Ȗʔ��݂̂Ȃ��o�����[�i�ƐQ�����Ǝv�����H�v�Ȃ�Ă��Ƃ��A�~���s�G�i��������_���T�[�j�ɐq�˂����Ă���B�剉���D��ǂ��l�߂Ă���Ȃ�D���������o�����Ƃ���f��ēȂ�̐[�d�Ȃ̂��A�P�Ȃ�y�������̃W���[�N�Ȃ̂��E�E�E�B �@����̃��`�[�t�ɂȂ��Ă���̂́A���^�Ȕ����ƁA�d���ȍ������A�ЂƂ�̃v���}�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��u�����̌v���B�D�����̃q���C���A�j�i�́A�u���������Ȃ�N��I�ԁv�ƌ|�p�ēɌ����Ȃ���A�����̉��Z�ō��i�_�����炦���ɋ�Y����B �@�T�����������Ă��܂��A�j�i�͏��D���Ȍ|�p�ē�A�~���E�N�j�X��������z���ȃ��C�o���A�����[�́g�O���h���āA�����̃_���X�ɂ��܂��ڊo�߂Ă����̂����A������Ƃ����Ă�߂�ߏ�������I�Ȑ�������Ȃǂ�z�����Ă͂Ȃ�Ȃ��B�����ŕ`�����̂́A���Ȏ����̖S�҂ƂȂ����ЂƂ�̏����|�p�Ƃ́A�g�̖т̂悾�悤�ȑ��Ƌ��C�̋O�Ղ��B �@�A���m�t�X�L�[�́u�f��̒��ł̌����v�Ɓu�q���C��������ϑz�v�Ɓu�f���Ƃ������鋕�\�i������x��|�[�g�}���̔畆�ɍ����H���������Ă����肷��j�v���I���ɐ�ւ��Ȃ���A���x�ƃe���V�����̍����s���ȕ��ꐢ�E�ɁA�ς�҂��ׂĂ𗍂ߎ��B �@�O��̃A�J�f�~�[�剉���D�܂��l�������|�[�g�}���̋��C�͂������A�~���E�N�j�X�����U���閂�����܂��Ƃɂ����ăZ���Z�[�V���i���B�I�X�J�[�̍�i�܂́w�p�����̃X�s�[�`�x�ɂ����ꂽ���A�����A�J�f�~�[����Ȃ�A�������ƂȂ�������𐄂��B �g�D���[�E�O���b�g�@�@TRUE GRIT �i�Q�O�P�O�N�A�āA�����F����L�K�j  �@�W�����E�E�F�C�����I�X�J�[���l�������w�E�C����ǐՁx(69)���A�ӊO�ɂ��R�[�G���Z�킪�����C�N�E�E�E�Ƃ͂��т��ѓ`�����Ă��邪�A����̃q���C�������Q�Q�̃L���E�_�[�r�[���������Ƃ́A���܂����Ă��Ȃ��B�����A�w�����������x�Ɏ剉����O�N�̃L���E�_�[�r�[���B���͍��Z����w�̍��Ƀe���r���f���ꂽ�̂������o�������邪�A�L���A���킢�������B���͂ǂ����Ă��邱�Ƃ��B �@����ł͂��̃q���C�����A�B�e���ɂ͂P�R�������w�C���[�E�X�^�C���t�F���h�������A�A�J�f�~�[�܂̏������D�܂Ƀm�~�l�[�g���ꂽ�B���̎q���Ȃ��Ȃ��Õ��Ȋ炾���ŁA���Ƃ��w�L�b�N�E�A�X�x�̃N���G���O���[�X�E�����b�c�Ɠ����ゾ�Ƃ͂ƂĂ��v���Ȃ��B �@�q���ł��镃�e���ق��l�ɎE���ꂽ�������A���Ɉ�̂��������ɂ���Ă���̂�����̎n�܂�B�u�ꂳ��͋����Ă��肾���玄�������v�ƌ��P�S�́A���e���������E�}�̑�����C��R��̉ƒ{�����炵������Ǝ�藧�Ă����肩�A�E�Q�Ƃ�ǐՂ��Ă����ۈ������ق��B����������̌��҂����钆����A�u�Ɛl���߂�ɂ��悤�Ɩ��߂鐳�`�h�v�ł͂Ȃ��A�u�����ǂ�̍r����ҁv��I�сA����ǐՍs�ɉ����̂��B���̌`���̃e���K�����n�b�g�����Ԃ��āB �@���̐NJ�̕ۈ����R�O�o�[�����������̂��A��N�w�N���C�W�[�E�n�[�g�x�ŃI�X�J�[�ɋP�����W�F�t�E�u���b�W�X�B�����Ɛl��ǂ��e�L�T�X�E�����W���[�ɂ̓}�b�g�E�f�C�������������B �@���m�̃u���b�W�X�ɏo���̃I�t�@�[���o�����Ƃ��A�R�[�G���Z��́u�w�E�C����ǐՁx�̃����C�N�ł͂Ȃ��A���쏬���ɒ����ȉf����B�肽���v�Ƙb�����Ƃ����B�����悤�ɂ���Ắu���������̓Ǝ��F���o���v�Ƃ�����R�����g�����A�ǂ����Z��̐^�ӂ͋t�������炵���B �@�{��ł̓R�[�G����̃I�t�r�[�g�Ȋ��o�͗}�����A�ނ���q���C���̐^���������A�Ђ��ނ������������鉉�o���Ȃ���Ă���B�w�C���[�E�X�^�C���t�F���h�Ƃ�����ނāA����͈��ȏ�̐��������߂��ƌ����邾�낤�B�������Ƃ��āA�`��杂Ƃ��āA�����ĔN���ʂ����M�������Ȃ̕���Ƃ��āA�{��͍������̍�i�Ɏd�オ�����B �@�Ƃ͂����ו��ɂ̓R�[�G���Z��炵�����B����͖��ǂȂ���A�N�}�̖є�𒅂������Ȏ���҂Ȃǂ́A�����炭�Z�킪�n�삵���L�������낤�B �@���邢�́u�I�I�J�~�ɐH����̂͌����v�Ƃ�����m���̈��}�ɁA�R�N�o�[�����u�����̂߂Ă��v�Ɩ��A���������V�[���B��̂���u����R�O�o�[���ɁA�^�������ȃq���C���͓��R�R�c����̂����A�ۈ����̓����͂����ɂ��R�[�G����i�̂��ꂾ�B�u���͒n�ʂ������Ă��Č@��Ȃ��B�������Ăق����Ȃ�ĂɎE����Ȃ���v �u�g���K�[�E�n�b�s�[�v�Ƃ������t�����邪�A�{��̓o��l�������͎��ɂ悭�e�����B����Ƃ��āi�܂�e����⌈���Łj������ł͂Ȃ��B�Y��ɋr��_���ăo���B����ǂ��������߂Ƀo���B�����ɂ��鑊��ɍ��}�𑗂낤�ƃo���B���}�������������ƃo���B �@���{�ł͂�����A�������P���Ă����ƍߎ҂��������x�����A�ٔ��Őh�������߂������Ƃ������肾�B����ȑi�ׂ́A���C���h�E�E�F�X�g�̂c�m�`�����A�����J�l�ɂ́A�Ƃ��Ă������ł��Ȃ����낤�Ǝv���B �킽���𗣂��Ȃ����@�@NEVER LET ME GO �i�Q�O�P�O�N�A�p���āA�����F�˓c�ޒÎq�j  �@��̎ʐ^�̃L�����[�E�}���K���̔��^�A�Ȃ����������ł��ˁB�����q�ǂ��̍��ɂ́A�����������^���������̐l�������������������悤�ȋC������B���邢�͏��������C���X�g�Ō����L�����A���Ɏc���Ă���̂��낤���B �w�킽���𗣂��Ȃ��Łx�́A����ȂQ�O���I�㔼�̃C�M���X�炵���ꏊ��ɂ������Ɗ����̐l�ԃh���}�B�����������͌����̃C�M���X�Ƃ͖��m�ɈႤ�A�u�����Ƃ͕ʂ̂ǂ����v�ɐݒ肳��Ă���B�X�g�[���[�I�ɂ͂r�e�F�����Ȃ�Z�����A����̃J�Y�I�E�C�V�O���́A�����܂ŏ����w�Ƃ��Ă�����������B �@�L���V�[�i�L�����[�E�}���K���j�A���[�X�i�L�[���E�i�C�g���C�j�A�g�~�[�i�A���h�����[�E�K�[�t�B�[���h�j�̂R�l�́A�c���n�т̊�h�w�Z�ŁA�c�����납�狤�Ɉ�����B���̊w�Z�̐��k�����͐S�g�̌��N�Ǘ���O�ꂳ��A��l�ɂȂ�����u�v���s����߂��B�N�ɉ����u�v����̂��͂����������炩�ɂȂ��Ă���B����ɘA��A�ނ�̔w�����ߍ��ȉ^���ƁA�������E����w���i�i�ɐi��ł���炵�����̃p���������[���h�́A�c���Ȉَ��������炩�ɂȂ�B �@�N���[������_����ۂɂ́A�ނ�̐l�����ǂ��ʒu�Â��邩�̋c�_�������Ă͒ʂ�Ȃ��B�I���W�i���Ɠ�����`�q�����N���[���́A�ʂ����ăI���W�i���Ɠ����̐l������������̂��B�{��̕���ƂȂ����u�����Ƃ͕ʂ̂ǂ����v�ł́A���̖������ς��Ɗ����A�N���[����s���Ȃ����l�Ԃ��ǂ��ƈʒu�Â��Ă����ł��ˁB �@�}�C�P���E�x�C�ḗw�A�C�����h�x�ł́A�����悤�ȉ^����w���������A���E�}�N���K�[�ƃX�J�[���b�g�E���n���\�����A�B���ꂽ�^����m���ē��������݂��B�Ƃ��낪������̃N���[�������́A���炩���߂��̎�����m�炳��Ă��Ȃ���A�l�X�Ƃ���������B�l�o�[�E�M�u�A�b�v�Ƃ��镗���̒��ŕ�炵�Ă��X�ɂ́A�L���V�[��̐Â��Ȓ��O�����ɒɂ��B �@�펯�I�ɍl����A���̓��������R���Ȃ��i�]���ăA�N�V�������J�^���V�X���Ȃ��j���ꂪ�A�ʔ����G���^�[�e�C�������g��i�ɂȂ�Ƃ͑z�����Â炢���̂�����B�������r�{�̃A���b�N�X�E�K�[�����h�Ɗē̃}�[�N�E���}�l�N�́A����R�l�̗F��ƎO�p�W��@�ׂɕ`�ʂ��A�ϋq�̊�����u�s���v�̈����݂ɐ[���ړ������邱�Ƃɐ��������B �@���̍�i�́A�o��l���̎c���ȉ^����`���Ɠ����ɁA���������ĉf��E�̎c����������������ɂ���B�}���K�����T���߂ōD���x�̍����L���V�[����������̂ɑ��A�i�C�g���C�������郋�[�X�́u�g�D�[�V���[�Y�ɉ�e������Ӓn�����v�I�Ȗ��B�Ƃ��ɂP�X�W�T�N���܂�̂��̂Q�l�A�w�v���C�h�ƕΌ��x(05)�ł̓i�C�g���C������ŁA�}���K�����[���������B�����ɂ͂��Ȃ������邩�A��]�����邩�ŁA���Ȃ��̐��i���f�f�ł��邩������Ȃ��B �c�[���X�g�@�@THE TOURIST �i�Q�O�P�O�N�A�ā����A�����F�˓c�ޒÎq�j  �@�W���j�[�E�f�b�v�ƃA���W�F���[�i�E�W�����[�Ƃ����D���x���Q�̂Q�l�������������ɂ�������炸�A���̍�i�A�S�Ăł̋��s���т͂��Ȃ�̕s�U�������炵���B�����g�͉��N�̃n���E�b�h�f��̃e�C�X�g�ɐZ��A���������y����Ŋӏ܂����̂����A�������f��r�W�l�X�Ƃ����̂͂P�{�P���Q�ɂȂ�Ȃ����E�ł���悤���B �@�W�����[��������G���[�Y�́A�N�ɂ����m���Ă��Ȃ����Z�ƍߎ҃A���N�T���_�[�̏�w�B�x�@�̖ڂ������������ăx�l�`�A�Ɍ��������ޏ��́A�A���N�T���_�[�Ɣw�i�D�̎����A�����J�l�c�[���X�g�̃t�����N�i�f�b�v�j�ɐ��������A�J���t���[�W���ɗ��p���悤�Ƃ���̂����E�E�E�B �@�嗤���f�S�����ŃW�����[���f�b�v���g�ނ�h�V�[�����Ƃ��Ă��I�V�����B���C�ŋM���I�ȃG���[�Y�ƁA��C�ŕ����I�ȃt�����N�����킷��b�ɁA�����͂��ƂȂ����[���A���Y���B �@�W�����[����C�̐N�̕@�ʂ������f��ƌ����A�����Ɂw�E�H���e�b�h�x���A�z����邪�A�ނ��땵�͋C�����Ă���̂́A�g���E�N���[�Y�����钳������ʐl�̃L���������E�f�B�A�X���댯�Ȑ��E�Ɉ������肱�w�i�C�g���f�C�x�̕��B�G���[�Y�Ɗւ�������߂ɁA�t�����N�̓}�t�B�A���疽��_���A���E��Y�̃x�l�`�A�����H�ڂɂȂ�̂����A�g���E�N���[�Y�Ɠ��l�A�ޏ��͂���ȃt�����N�����E���ɂ͂��Ȃ��B �@����A�A���N�T���_�[�̑ߕ߂Ɍ������グ�郍���h���x�@�́A�t�����N�̖��ȂLj�ڂ��ɂ��Ȃ��B���̂�����́w�k�k���ɐi�H�����x�ň�ʐl�̃P�C���[�E�O�����g�����{�@�ւɌ��̂Ă�ꂽ�o�܂�f�i�Ƃ�����Ƃ���B�{��ɂǂ����N���V�b�N�ȃe�C�X�g����������̂́A����ȘA�z�������̂������������Ȃ��B ���ȉ��̓l�^�o���ł��� �@�����A�K�x�Ƀ������n���E�b�h�X�^�C����ۂ��Ȃ�����A�{��͌ÓT�I�Ȋ������܂�^�~�X�e���[�ɂ͏I����Ă��Ȃ��B�G���[�Y�͂������A�c�ɂ̒��w���t�̃t�����N�܂ł��A�\���ӂ��̊�������Ă���B �@���ꂪ���炩�ɂȂ����I�ՁA�G���[�Y�ƃt�����N�̊W�����N�����Ɨ��Ԃ�̂����ǂ��낾�B�ׂ����_�̐������ɂ��ẮA�܂��A���邳�����Ƃ������Ȃ���ȁB�����h�����������t�����N�̐��`�ɖƂ��āB �@�����ƁA�����h���������Đ��`�����̂́A�炾���������̂�����H�@�t�����N�������z�e���Ɉ������G���[�Y�́A�x�@�ɃL�X�V�[��������������ƁA�ނ��������ƃ\�t�@�[�ɒǂ����̂����A�����Q�Ă�����ǂ��Ȃ��Ă������B�����́g�C�h������́g���h�Ƀs�b�^�����ƁA�ʂ����ăG���[�Y�͋C�Â������낤���B (2011.3.12.�L�j ���̏�̃��v���c�F���@�@RAPUNZEL�iTANGLED�j �i�Q�O�P�O�N�A�āA���ցF�����݂����j  �@�P�X�R�V�N�́w����P�x���琔���āA�L�O���ׂ��T�O��ڂ̃f�B�Y�j�[�E�A�j���B�����Ƃ���ł���H�Ƃ����C�����邪�A�w�g�C�E�X�g�[���[�x�w�t�@�C���f�B���O�E�j���x�w�v�`�k�k�E�d�^�E�H�[���[�x�Ƃ������s�N�T�[��i�́A�f�B�Y�j�[�̔z���ł��Z������Ă��Ȃ���ł��ˁB �@����̃q���C���́A���C�o���̃h���[�����[�N�X�Ђ��w�V�����b�N�R�x�ňꑫ��ɓo�ꂳ���������P���ƃ��v���c�F�����B��e���x�閂���̎�ŁA�c���̍����瓃���ɓ�ւ���Ă����̂����A�D�_�̃t������菓����Ă������Ƃ���A���ɊO�ɏo�閲�����Ȃ��邱�ƂɁE�E�E�B �@�r�{�̃_���E�t�H�[�Q���}���́A���ʂȖ`���ƌ��I�Șe��w���I�݂ɔz���āA����Q�l�̐S�̕ω��������I�ɕ`�����B�u�O�͊댯������v�Ƃ�����e�̌��t���Ȃ��ΐM���A�Ȃ��͎����̗E�C�̂Ȃ����瓃���ɂƂǂ܂��Ă������v���c�F���́A�O�̐��E�Ŏ��R�ƐӔC��m�������Ƃ���A�傫�������Ɍ����ĕ��ݏo���B �@����A�ŏ��͗��ȓI�ȓ��@�i���v���c�F���̔��̖��͂����ɂȂ�ƌ����j����q���C���ɋ߂Â����t�����́A�w���[�}�̋x���x�̃O���S���[�E�y�b�N��낵���A����ɐ^�̈��ɖڊo�߂Ă����B �@�����ē̃l�C�T���E�O���m�ƃo�C�����E�n���[�h�́A�R�c�̓��������ɐ������āA�������̖���ʂ�D�肱�B���Ƃ����v���c�F�������߂ē��̊O�ɏo��V�[���B�������A�͂ˉ��A��C���A��n��̊�����ޏ��̍��g�����A��ʂ������������Ă��ӂ�o���A�ςĂ��邱����̐S�����������B �@���邢�̓��v���c�F���ƃt�������A�̃{�[�g��ŁA��ɏオ���������̃����^���߂�V�[���B�����ɂ͂Q�c�̉f���ł͂����炭���킦�Ȃ��A���z�I�Ȕ�����������B �@�����A�{��̍ő�̃L���́A���̂Q�l���Ō�Ɍ����鑸�����ȋ]���̍s�����낤�B���̂Ƃ���A���ȋ]�����R��ɐ������f���i�͑|���Ď̂Ă�قǂ���̂����A���̑唼�́u�h���ꂩ�����i�����ꂩ�����j���l�̑O�ɐg�𓊂������v�Ƃ��u�G�̃��{�b�g�i�]���r�j����Ƃ��������邱�Ƃł݂�Ȃ��~���v�Ƃ�����������܂�Ȃ��p�^�[�����B������܂����ʂɃq���C�b�N�ɉ��o������̂�����A�����Ă��͊ςĂ���ƃA�z�������Ȃ��Ă���B �@�{��̏ꍇ�͂����ł͂Ȃ��B�t�����̖����~���㏞�ɁA���ɂ��������ꐶ�𑗂낤�ƌ��ӂ��郉�v���c�F���B�����͂������ƁA���̕���̈˂��ė���ՂƂ������ׂ��u������́v��j��t�����i����̓t�����̈����^�����v���c�F���ɂƂ��āA����ȏ�Ȃ����̏ؖ��Ƃ��Ȃ��Ă���j�B �@�m���̃t�����̑�_�ȍs�ׂ������u�ԁA���͎��ʎ��Łu�����I�v�Ɛ����グ���̂����A�݂����v�����Q�l�̍s���ɂ́A�ӊO���ɉ����A�n�E�w�����[�̌���u���҂̑��蕨�v�ɂ��C�G����\�t�B�X�e�B�P�[�V�������������B (2011.3.12.�L�j �����i�E�F�C�Y�@�@THE RUNAWAYS �i�Q�O�P�O�N�A�āA�����F�����z�q�j  �@�����i�E�F�C�Y�Ƃ����A�������Z����Ɉꐢ���r�����K�[���Y�o���h�B�ޏ���̂��Ƃ����߂Ď��ɂ����̂́A�N���X���[�g�̃Z�L�l�N���A�u��������B���[�h�{�[�J���̏��̎q���̂��Ȃ���ǂ�ǂ�E���ŁA�����p�ɂȂ����Ⴄ��v�Ƌ����C���Ɍ��̂����Ƃ��������B �@���Ȃ�O�[�O�������[�`���[�u�Œ��ׂ�Έꔭ�����A�����̓C���^�[�l�b�g���l�s�u�����݂����A����Șb������Ă��u�ց[�v�Ɠ�����ق��͂Ȃ��B�Ƃ͂����A�قǂȂ��G����R�[�h�W���P�b�g�Ŕޏ������̃r�W���A�����m��킽��A�������N���X���[�g�̃g�V�G����W���[���E�W�F�b�g�Ɠ������^�����Ă���܂łɂȂ����B �@�{��͂��̃����i�E�F�C�Y�̌���������U�܂ł��A�q���q������悤�ȋٔ����ŕ`������i�B����̓{�[�J���̃V�F���[�E�J�[���[���������`�L�ŁA�M�^�[�̃W���[���E�W�F�b�g�����쑍�w���߂Ă���B �@�n�C�e�B�[���N��̃g�b�v���D�ł���_�R�^�E�t�@�j���O�ƃN���X�e���E�X�`�����[�g���A���ꂼ��V�F���[�ƃW���[���������Ă���̂����ǂ���B�q���o�g�̂Q�l���A���Ɖ����ƃh���b�O�ɓM�ꂽ�����o�[�̎��������_�ɉ����A���Y���ۂ��L�X����A�V�[���܂Ō����Ă���B �@�ēE�r�{�̃t���[���A�E�V�W�X�����f�B�́A�����o�[���̏��̑����A�}�l�[�W���[�Ƃ̊m���A�Ƒ��Ƃ̔����ȊW�A�X�^�[�ł��邱�Ƃ̏d�ׂȂǁA�����}�����\��̏��������̗l�X�ȔY�݂�v�����P�O�V���Ԃɋl�߂��B�m�y�ɂ͑a���������ɂƂ��Ă��A���R�[�h�i�b�c�ł͂Ȃ��j����͂��������m��Ȃ������ޏ������̎������_�Ԍ����āA���Ƃ������[���B �@�Z�L�l�N�́u�̂��Ȃ���E���ł����v�ƌ��������A�{����ς邩����A�V�F���[�̓X�e�[�W�ɏオ��i�K����r�X�`�F�ƃK�[�^�[�x���g�p���B�������A���̉������b�N�́A���{���������������ɐ��݂����ꂽ���̂������Ƃ́B���`�ށA�m��Ȃ������B �@�V�F���[���W���[�����قڑS�҂Ń������Ă��āA�l�C�A�C�h���ł���Ȃ���A�قƂ�ǏΊ�������邱�Ƃ��Ȃ��B�\��㔼�̐��_�I�L���p�ŁA�ꐶ���ȏ�̌o����w�����Ă��܂������������̂��߂����A�ɂ݂��ċ▋����`����Ă���B (2011.3.12.�L�j �Q�O�P�P�N�I�X�J�[�i�C�g�E�E�H�b�`���O�I  �u�ߋ��̖�����̂���v���e�[�}�ɂ������N�̃A�J�f�~�[�����́A�ߔN�ł��L���Ɏc��Ȃ������I�X�J�[�i�C�g�Ƃ��ċL�������i�H�j�̂ł͂���܂����B �@�܂��͎i��̃W�F�[���Y�E�t�����R���_���_�����B�����̑O�ɂ͂Ȃ��ނ��z�X�g���ɑI�ꂽ�̂��킩��Ȃ��������A���I����Ă����܂��ɂ킩��Ȃ��B��{��Ƃɂ��낢��ƃW���[�N��U���Ă͂������A�S�R�����̃Z���t�ɂ��ĂȂ�������ˁB������b�R���^�C�c�p�������Ă͂������A���ǂ̂Ƃ���A�ނ̓A���E�n�T�E�F�C�Ƃ����g�����ւ��l�`�h�̈������Ė��ł����Ȃ������B �@�n�T�E�F�C�͎��g���k�[�h���I�����ŐV����l�^�ɂ�����A�Q�N�O�Ƀq���[�E�W���b�N�}���Ɖ������p�t�H�[�}���X�̗��o�[�W�����������Ă��ꂽ�肵�Č������Ă͂������A���`��A������ƃX�x��C���B�p�[�g�i�[�����������g����j��������A�ޏ��������ƈ������������낤�ɁB �@�������D�܂̃v���[���^�[�ɃJ�[�N�E�_�O���X���o�Ă����̂ɂ́A���т�����B�O�N�̏����j�D��҂����߂�̂��P��Ȃ̂����A���[���b�p�l�̃N���X�g�t�E���@���c�͒f�����̂��A����Ƃ��Ă�Ȃ������̂��B���܂��ɔ��\�Ƃ����^�C�~���O�ŁA�_�O���X���ĎO�{�P�����܂����̂ɂ͏������A���̉��Ȃ����̘b���Ԃ�͎�A�V�X�����炵�������������̂��ۂ߂Ȃ��B�����ƁA���ܒ��ׂĂ݂���A�_�O���X�͂X�S���B�X�e�[�W�ɗ����Ă邾���ł����h�Ȃ��̂��B �w�U�E�t�@�C�^�[�x�Ŏ�܂��������b�T�E���I�̃X�s�[�`�́A�܂��A�����������ƁB����ł��u�ǂ��o���~���[�W�b�N�v���肾�����A���N�͎��Ԑ������Ȃ������̂��Ǝv������A���̕���̃X�s�[�`�ł͂����Ɩ��Ă����B�A�J�f�~�[����͔o�D���Ԃɂ͗D�����Ƃ������Ƃ��B�����������I�͂e�Ŏn�܂�����֎~�p������ɂ��Ă��܂������A�S�Ăɒ��p�����`�a�b�͂ǂ����������̂��B �@�������D�܂Ƃ̃o�����X����������߂��A�����j�D�܂̃v���[���^�[���A��N�̏������D�܂̃��j�[�N�ł͂Ȃ����[�X�E�E�B�U�[�X�v�[�������߂��B��҂́A��������w�U�E�t�@�C�^�[�x����N���X�`�����E�x�[���B���̐l�A�������������i�ł́u�e���ɐH���Ă����v�Ƃ����Ε]�������̂����A�e�ɉ��ƑS��������������ŋ�������B�Q�O�O�W�N�ɂ͎���Ǝo�ɖ\�͂��ӂ邢�A�x�@�ɒʕ�Ă���̂����A��͂�Ƃ����ׂ����A�X�s�[�`�̒��ɔޏ���ɑ��銴�ӂ̌��t�͂Ȃ������B �w�u���b�N�E�X�����x�Ŏ剉���D�܂��ˎ~�߂��i�^���[�E�|�[�g�}���́A����Œm�荇�����U��t���t�ƍ��A�D�P���̐g�̏�B��͔��������������A�X�s�[�`�ł͗��e�A�}�l�W���[�Ɏn�܂��āA�����b�N�E�x�b�\����}�C�N�E�j�R���Y��̉��l�A��܍�̊ē���J�����N���[�Ɏ���܂ŁA�Q�R�l���̌l������ǂ݂Ȃ������Ċ��ӂ�������B���D���ˁA���낢��ȈӖ��ŁB �@�剉�j�D�܂ɋP�����̂́A��N�́w�V���O���}���x�ɑ����A���m�~�l�[�g�ƂȂ����R�����E�t�@�[�X�B���N�́w�p�����̃X�s�[�`�x�ŁA�ނ͂܂���i�ƕ]�����グ���B�X�s�[�`�̖`���A�u���܃L�����A�̒��_���z�����i�����ɓ������j�v�Ƃ��܂��ď���U�������A���̐l�A���{�̊w��Ō����Ύ��Ɠ��w�N���B�܂��܂�������Ă���������B�����ƁA������A�i�^���[�E�|�[�g�}���̃L�����A�ɂ��Ă��������Ƃ������܂����E�E�E�B �@���̌��ʁA�o�D����͂S�Ƃ��A�O����̃S�[���f���O���[�u�܂ƈ�v���閳����ԂɁB����ɑ��č�i�܂Ɗē܂ł́A�S�[���f���O���[�u�܂𐧂����{���́w�\�[�V�����E�l�b�g���[�N�x��}���āA�w�p�����̃X�s�[�`�x���h�����B�w�p�����`�x�͋r�{�܂ɂ��P���A�I�X�J�[���S�l���B�I�X�J�[�i�C�g�̏I�Ղ́A�C�M���X�a�肪�X�e�[�W��Ȋ����錋�ʂɁB �@�ނ�̃X�s�[�`���܂��悩�����B�g���E�t�[�p�[�ḗA��e���炱�̍�i�̑��݂�m�炳�ꂽ���Ƃ𖾂��������ƂŁA�u���̘b�̋��P�́A��e�̌��t�ɂ͎����X������Ă��Ƃ���v�ƒ��ڂ��C�����Ղ�ɒ��߂�����B �@�r�{�̃f�r�b�h�E�T�C�h���[���E�B�b�g���_�B�����Ƃ���U�O���Ă������Ȕނ��A�u���e������Ӑ��^���ƌ����Ă��܂����v�Ɛ�o���ƁA��ꂩ��g���ȏ����R�ꂽ�B�w�p�����`�x�͋h���ɔY�W���[�W�U����`�����l�ԃh���}���������A�T�C�h���[���܂��h�������������l���Ƃ����B�����b�T�E���I�̎����̒��ゾ�������A�T�C�h���[�͂��������u�����Ɋ��ӂ��܂��B�����b�T�E���I�̂悤�Ȃe���[�h����������g�����̂ɁA�����h�����ɕ����߂Ȃ��ł����������v�Ƃ�����B�h���̐l�͒m�\���Ⴂ�ƌ�����ꂪ�������A�T�C�h���[�̃E�B�b�g�����������ŁA���ꂪ�u�펯�̃E�\�v���Ƃ킩��B �@���N�̌���̓����́A���b�����Ƃɂ�����i�������������ƁB��v�����Ɛ肵���w�p�����`�x�w�U�E�t�@�C�^�[�x�ɉ����A�w�\�[�V�����`�x�Ɓw�P�Q�V���ԁx����i�܌��ɓ����Ă����B �@���݂́i���ɑ������́j�l�������f���ɂ����f��́A���X�ɂ��ă��f���ɂ����˂������̂ɂȂ肪���Ȃ̂����A�����̍�i�͂��̎�́u�L�݁v�����������Ȃ������B�����������̈���������悤�Ɏv���B �i2011.3.6.�L�j �p�����̃X�s�[�`�@�@THE KING'S SPEECH �i�Q�O�P�O�N�A�p�����A�����F���Y���ށj  �@���̃h�C�c�ł́A�q�g���[���^�����邱�Ƃ͂������A�q�ϓI�ɘ_���邱�Ƃ����A���炭�^�u�[�Ƃ���Ă����B���������U�T�N���o�����N���獡�N�ɂ����āA�x�������̃h�C�c���j�����قŁA���߂ăq�g���[���e�[�}�ɐ��������ʓW���J���ꂽ�B�W�����̒��ɂ̓q�g���[�̉f�����܂܂�Ă������A�����[�����Ƃɓ����͗�����Ȃ������Ƃ����B�u�ނ̐��͍��ł����ȗ͂�������v���������B�i�ǔ��V���Q�Ɓj �w�p�����̃X�s�[�`�x�́A�h������������̃C�M���X���A�W���[�W�U���i�R�����E�t�@�[�X�j�ƁA�^�j��Ȍ���Ö@�m�i�W�F�t���[�E���b�V���j�Ƃ́A�����������ْ��ɖ������𗬂�`�����q���[�}���h���}�B�����ł́A�W���[�W�U�����c�����i���݂̃G���U�x�X�Q�����j�ƂƂ��Ƀq�g���[�̃j���[�X�f�������āA�u�Ȃ�Č����Ă�́H�v�u�킩��Ȃ����A�����͏�肾�ˁv�Ȃ�ĉ�b�����킷�V�[��������B �@�W���[�W�ɂƂ��ĕs�K�������̂́A�Z���̃G�h���[�h�W�����A���������o�c�C�`�č������Ƃ̗���I�сA�������Ƒވʂ��Ă��܂������ƁB�������Đl�O�Řb���̂�������肾�����W���[�W���A�a�X�Ȃ��牤�ʂɏA������Ȃ��Ȃ�B���̂�����̔ނ̋����Y�݂��A�{��ł͗]���Ƃ���Ȃ��`����Ă��ďG�킾�B�I�Ղɂ͌���Ö@�m�������i���������Ƃ����o���A����̃h���}���𑝂��Ă���B �@������E�B���X�g���E�`���[�`���Ƃ��������݂̃Z���u���A�j���[�X���f�B�A�ł͐�Ɍ����Ȃ��悤�Ȑl�Ԃ�������������Ă���̂����ǂ���B�������̓t�B�N�V�����ł͂��邪�A�����̂��킢���ǂ̂�����ɂ���̂��ƍl����̂��ʔ����B �@���ł��w���i�E�{�i�����J�[�^�[���������W���[�W�̍Ȃ̃G���U�x�X�́A�C�M���X�����Ɉ�����Ȃ���P�O�Q�܂Ő������G���U�x�X�c���@�̃C���[�W���̂��́B�������ƃE�B�b�g�ɖ������l�����͍D���x��傾�B���������w�N�B�[���x(06)�ł��A�V���r�A�E�V���Y���N�V�����c���@�������A���ɂ��������o���Ă��������B �@�C�M���X���I�[�X�g�����A�̐���Ȃ���A�{��͕č����ł��]���������A�A�J�f�~�[�܂ł���i�܁A�剉�j�D�܂��͂��߂Ƃ���P�Q����Ƀm�~�l�[�g����Ă���B�Ƃ͂����A������Ŗ{����̎^����̂ɂ́A�ꖕ�̂��߂炢�������Ȃ��ł͂Ȃ��B�����Ă���A�h�C�c�f��w�킪�����q�A�q�g���[�x(07)�̓�Ԑ����L����ˁB �@�p�u���b�N�X�s�[�`�̂ł��Ȃ��i�ł��Ȃ��Ȃ����j���Ǝw���҂��A���ЂƂ͖����̊O���l�i�ٖ����j�ɗ���A�����ȁu���Áv����������Ƃ�����{�\���͂܂���������B���܂��ɉp�������I�[�X�g�����A�l�̕����ɗ���Ƃ����R�`���̐ݒ�́A�q�g���[�����_���l�ɗ���Ƃ����A�`���̐ݒ�ɔ�ׂāA�i�i�ɃC���p�N�g��������i�����ɓ����̃I�[�X�g�����A���u���Y�n�v�̃C���[�W�������Ă����ɂ��Ă����j�B �@�����Ƃ��A�J�f�~�[����̒��ɂ́A�h�C�c��f��́w�킪�����q�A�q�g���[�x���ς��҂͂��������͂Ȃ����낤����A���n�]�ǂ���Ɂw�p�����̃X�s�[�`�x���I�X�J�[�i�C�g��Ȋ����邱�ƂɂȂ邩������Ȃ����B �@�|��Ƃ炵�����Ƃ����܂ɂ͏����Ă����܂����ˁB �@���ʂ�������̌Z�����o�c�C�`�����Ɏ���Ȃ��]������Ă���U�}�����āA�u������������ŌZ�オ�������肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ɁA����܂ʼn������Ă����̂ł����H�v�ƁA�W���[�W���ꌾ��悷��V�[��������B�����������A�u����ȏ��Ƃ����������āA�����͉��܂Ƃ͔F�߂Ȃ��B�Z�M���g�`������đވʂł�������A�h�����̖l�������ɂ��ꂿ�Ⴄ���炵�����肵�Ă�v�Ƃ������Ƃ��B �@�K�C�E�s�A�[�X������G�h���[�h�W�����A����ɓ����ĞH���B�uKinging.�v �@���ʎ��ł�����Ə����B�ЂƂ������ׂ̐Ȃ̏��������������Ă����B�������u���̖��߁v�Ƃ������ɕϓN�̂Ȃ���ɂȂ��Ă�������A�Ԃɋ��܂ꂽ�j���́A�Ȃ������ŗ��e��������R�ꂽ�̂��ƁA�s�v�c�Ɋ�������������Ȃ��B �@�A��Ă��玫���Ŋm�F���Ă݂����A��͂�king�Ƃ������t�������Ƃ��Ďg����Ƃ��́A�u�`�����ʂɏA������v�Ƃ����������I�ȗp�@���嗬�ŁA�u���̖��߂��ʂ����v�Ƃ����Ӗ��ł̎g�p�@�͂��܂��ʓI�ł͂Ȃ��������B �@�܂肱��̓G�h���[�h�W���́i�Ƃ������r�{�Ƃ́j���܂����~悁B���āA�f���|��ƂƂ��ẮA������ǂ��������{��ɂ���ׂ����B �@�j���A���X�Ƃ��čł��߂��̂́u�Ȋw����v��u��������v�ȂǂƓ������z�ŁA�u�����Ă��v�ƌ��킹�邱�Ƃ��B���������̖�ł́A�����ɂ��Ă����ւɂ��Ă��킩��ɂ����̂ŁA������Ǝ��p�ɂ͓K���Ȃ��B �@�G�h���[�h�̂��̂ЂƂ��Ƃɂ́A�E�Ƃ����̑�������R�ɑI�ׂȂ����ƌ���́A���}�ƒ��O�ƈꖕ�̓�����肳���������Ă���B�Ƃ���Ȃ�A�E�ƂȂ炴����̂������ɂ��E�Ƃ炵���\������̂��A�ЂƂ̐헪�Ƃ��Ă��肾�낤�B �@���Ă��ƂŁA���Ȃ��u���l�Ƃ��v��������̗p���邩�ȁB (2011.2.13.�L�j �Q�O�P�O�N�i���́j�x�X�g�P�O�I �@���N���P�����{�Ɂu�L�l�}�{��x�X�g�e���v�����\����Ă���B���N�A�����̃����L���O�ɂ͈ӊO�Ȏv������������̂����A���N�͂��Ƃ̂ق����������̍�i�����������B �@���{�f��Ɏ����ẮA�L�l�{�x�X�g�P�O�̂��ׂĂ��i�I�j�����B�O���f��͂������ɂU�{�A�ςĂ������A��������x�X�g�P�O�ɐ����悤�ȍ�i�Ƃ͎v���Ȃ��B�U�ʂ́w�₽���J�Ɍ��āA�̏e�e���x�Ȃ͂Ƃʍ삾�������A�V�ʂ́w�N���C�W�[�E�n�[�g�x�́w���X���[�x�̈������R�s�[�ɉ߂��Ȃ������ł͂Ȃ����B �@�ƁA�y�����ۂɂ��݂����Ƃ���ŁA���̃x�X�g�P�O����I���Ă����܂����B �P�@�w�P�V�̏ё��x �@������|�p�ɑ��鍂���Ȃ�������ƁA�u�t�����X�l�ɂȂ肽���I�v�Ƌ��ԃ~�[�n�[�����������q���C�������Ƀt���b�V���B�ޏ��Ə������t���u�������w�Ԃ��Ɓv�̈Ӌ`���߂����ē��킹���_���́A���Ɏh���I�������B �Q�@�w�q�b�N�ƃh���S���x �u�����̓_�����v�ƃC�W���Ă����Ƃ��ɂ͖{���Ƀ_���_�����������N���A�u�l�ɂ��ł���v�ƋC�Â����Ƃ�����A���R�ɏ����g�ɕς���Ă����B�S���̏��N������A���Ђ��̍�i�ŏ��ɐ��]�i�H�j����Ă���B��s�V�[���̃_�C�i�~�Y�����o�F�������B �R�@�w�t�@���{�[�C�Y�x �@�������肵���c���i���J�O�́w�G�s�\�[�h�P�x������N�G�X�g�j�Ɖ����i�w�X�^�[�E�E�H�[�Y�x�V���[�Y�ւ̈��j���S�҂��т��Ă���̂ŁA�g�p���f�B�̂��߂̃p���f�B�h�ɑ��Ă��Ȃ��B�n�C���x���ȃM���O�̘A���Ɋ������唚�B �S�@�w�U�E�E�H�[�J�[�x �@�Ō�ɖ��������u���̎����v�ɂ͓V�n���Ђ�����Ԃ�قNj������B�P�ɈӊO�Ȃ����ł͂Ȃ��A�����̎��Ɨʂ����[����Ȃ������_���������I �T�@�w���|�����x �@���z�̐l�H���킪���y�����ߖ������A�����͖L���ɍ\�z�B�I�Ղ̎������ɁA�������Ȉ�a�������肱�܂��A�Ō�ɂ����������Ă݂����ۂ��N�₩�B �U�@�w�i�C�g���f�C�x �@���̂Ƃ���n���ڂ������g���E�N���[�Y�ƃL���������E�f�B�A�X���A�v�X�ɃX�^�[����S�J�B�A�N�V�����悵�A�M���O�悵�A���}���X�悵�̉��삾�����B �V�@�w�R�����C���ƃ{�^���̖����x �@���e�������ǂ��ӔC���B�R�Ƃ��Ĉ��������A���[�e�B�[���̏������������ЂƂ�Ŗ����̂��݂��ɖ߂��Ă��������Ղ̃V�[���ɐS�ł��ꂽ�B�������̍����A��q�̍s���Ƃ͂����ԈႢ�܂��ˁB �W�@�w�L�b�N�E�A�X�x �X�@�w�]���r�����h�x �P�O�@�w���ׂĔޏ��̂��߂Ɂx (2011.2.7.�L�j �u���[���E�A�p�[�g�@�@INCENDIARY �i�Q�O�O�W�N�A�p�A�����F�H�j  �@�~�V�F���E�E�B���A���Y�͉p�ꂪ���܂��B �@�A�����J�l�Ȃ��瓖����O���ƌ����Ȃ���B�A�����J�l�����ʂɘb���Ă���̂́A�����ɂ͕Č�ŁA�p��ł͂Ȃ��B �@�C�M���X�l�̖�������A�����J�l�o�D�Ƃ����A�ߔN�ł̓O�E�B�l�X�E�p���g���E��j�[�E�[���E�B�K�[�̖��O���^����ɕ����Ԃ��A�ޏ������̃A�N�Z���g�́i���Ȃ��Ƃ����̎��ɂ́j����قǃC�M���X�l���ۂ��͋����Ȃ������B �@�Ƃ��낪�{��̃E�B���A���Y�́A�`���̃��m���[�O���炵�ă����h���̘J���ҊK�����̂��́B�����^�i�B�Ő��܂ꂽ�Ƃ����̂ɁA�悭�����ꂾ���̃A�N�Z���g��g�ɂ����B��������������ł��傤�ˁB �@�z����Ђ͖{���d���T�X�y���X�Ƃ��Đ�`�������悤�����A���ۂ̂Ƃ���̓C�X�����ߌ��h�̎����e���ŕv�Ƒ��q���������Ⴂ��e�i�E�B���A���Y�j���A��͂�傫�Ȕ߂��݂�w�������A���u�l�e�^�҂̍Ȃ⑧�q�ƕs�v�c�Ȃ��ɂ�������ł����Ƃ����A���������^�ʖڂȖ���N���܂�i�B�����������h���Ńe�����p�����Ă����̂́A�������N���O�̂��Ƃ�����A�����������@�����������͔ۂ߂Ȃ��B �@�Ƃ͂����w�u���W�b�g�E�W���[���Y�̓��L�x(01)�Ń��K�z�����������V�������E�}�O�A�C�A���ēE�r�{��S�����Ă��邾���ɁA�{��ɂ̓f�B�e�[���Ɋ��ɋ����[���_�������B �@���Ƃ��u�Ⴂ��e�v�i���ꂪ�E�B���A���Y�̖𖼂��j�́A�v�Ƒ��q���T�b�J�[�ϐ�ɑ��肾�������ƁA���A���E�}�N���K�[������Ԓj�̃W���X�p�[������ɘA�ꂱ�݁A�e���r�̃`�����l�������̎����̒��p�ɍ��킹�Ă���B �@�Q�l���L�b�N�I�t�Ɠ����ɑg�ق�����n�߂�̂͒P�ɉf��I�ȋ��R�����A�l���Ă݂�A��������_���i�����Ƃǂ̂��炢�ŋA���Ă��邩�����Ȃ萳�m�ɗ\�z�ł���킯���B �@�����Ƃ��C���O�����h�̃T�b�J�[�ϐ�q�́A�����I���̂P�T�����炢�O�ɂȂ�ƁA�Ђ����`�[���̏��s�ɂ�����炸�A�����ł����悤�ɋA�肾���B�C�M���X�̐l�Ȃƕ��C������\��̂�����́A���̓_�A�\���ɗ��ӂ��ꂽ���B �@�C�[�X�g�G���h�̘J���ҊK�������ɁA�x�@�ɋ߂�u�Ⴂ��e�v�̕v�̓A�[�Z�i���̃t�@���B���Y�K���̃A�N�Z���g�Řb�����̏�i�̃e�����X�i�}�V���[�E�}�N�t�@�[�f���j�́A��͂�ƌ����ׂ����A�`�F���V�[�̃t�@�����i�e���r�ɉf�����ΐ푊��̃��j�z�[���́A�ǂ����Ă��`�F���V�[�̂���ł͂Ȃ��������j�B �@���ꂪ�i�ނɂ�āA�e�����X�̓e���̏�������ł��Ȃ���e�^�҂��j�����Ă������Ƃ��킩���Ă���B�����Łu�Ⴂ��e�v�ɖ₢�߂�ꂽ�ނ������ĞH���B�u�X�^�W�A���Ńe�������邱�Ƃ͂����A�ǂ̃X�^�W�A�������킩��Ȃ������B�����̎����𒆎~�ɂ����肵�����p�j�b�N�ɂȂ�I�v �@����ʂł͌����ĂȂ��̂����A�����Ȃ�Ƃ��C���O�����h�̃T�b�J�[�����m��g�Ƃ��ẮA��������Ȃ�ƃj���}��������ꂽ�B �@�Ԓj�W���X�p�[�̐l���`�ʂ��ʔ����B�E�Ƃ̓^�u���C�h���̋L�҂ŁA�r�͈ꗬ�炵���A���Ȃ�H�U��̂�����炵�Ԃ�B�^�u���C�h���Ƃ����̂́A����S�V�b�v��������A�����ňꗬ�ɂȂ��Ƃ����̂́A���{�̌|�\���|�[�^�[�Ɠ��l�A�l�ԓI�ɂ͂����������ׂ�����Ƃ������Ƃ��B �@���̔ނ��A�u�Ⴂ��e�v�̉ƂŁu�t�B�b�V���t�B���K�[������Ă����邯�ǁA�����H�ׂ�H�v�ƕ�����A�u�����A�H�ׂ����ƂȂ�����v�Ɠ������ł��ˁB �@�C�M���X�l�̃t�B�b�V�����`�b�v�X�D���͓��{�ł��悭�m���Ă��邪�A���͂���A��Ƃ��ĕn�����J���ҊK���̐H�ו����B�t�B�b�V���t�B���K�[�͂��������ɑ�O�I�ɂ����Ⓚ���i�B�}�O�A�C�A�ḗA���̒Z�����Ƃ肾���ŁA�W���X�p�[�̐H���Ȃ��l����A�ނƁu�Ⴂ��e�v�Ƃ̃o�b�N�O���E���h�̈Ⴂ������ɂ��Č������B���̃V�[���������J���ҊK���̊ϋq�͊F�A�u�Ⴂ��e�v�Ƃ������蓯���悤�ɁA�u�����A���傤���Ȃ��ȁv�Ƃ����\����ׂ��ɈႢ�Ȃ��B (2011.2.5.�L�j ������ �i�Q�O�P�O�N�A���j  �@�����̉f�扻��i�̋ɂ߂čK���Ȑ����Ⴞ�낤�B���C�ȔN�㏗�ƁA�_���_���ȔN���j�̋Ȑ܂ɖ������\�N�����A�Q�n���̃��[�J���F�����A�Ȃ��`������i���B �@���ʂ��ӏ܌���N�R�H�q�̓���������ǂ��A���쒆�̂قƂ�ǂ��ׂẲ�b�����A�����܂Ŋ܂߂Ă��̂܂܋r�{�Ɏ�肱�܂�Ă���̂ɂ͊��Q�����B �@���܂��ɋr�{�̍������K�́A�u�z����̐l���v�ȂǂƂ��������Ƃ̓Ƃ�悪��������ς�Ɛ؏��������A����ɂ͂Ȃ��G�s�\�[�h�̕t����A���ʓI�Ȑݒ�̕ύX���{���āA��i�ւ̋����x�����߂Ă���B�����ȋr�F�̎�ۂ��ƌ����Ă����B �@���łɌ����A�����N�R�H�q�Ƃ��������ƁA��l�̂ƎO�l�̂̋敪�����O�_�O�_�����A�P�s�����ɂ�鎞�Ԃ̌o�߂̕\�����A�ʏ�́u�����̕��@�v�ɂ��Ȃ��Ă��Ȃ��B�ق��̐l�̏��������܂�ǂ܂��ɏ����ƂɂȂ��Ă��܂����^�C�v�̐l�Ȃ̂��낤���H �@�剉�̂Q�l���\�����Ȃ��B�N���j���̐��{���M�́A���Ղ̃i�C�[�u�A���Ղ̂����݁A�I�Ղ̐������A��������Ɖ����������B �@�N�㏗�ɕ��������c�L�I�́A����܂ł̃A�C�h���̊k�������������悤�ȉ��Z�����]�A���߂āu���D�v�̉��Z�������Ă���B�P�ɉ�����Z�b�N�X�V�[������������Ƃ������Ƃł͂Ȃ��A���Z�҂Ƃ��Ă̊o�傪����������ƂȂ����B �@���l�f��o�g�̋��q�C��o�̂��܂��̂��A�L�I�����A�L�X����������肻���������B���{�A�����܂������I (2011.1.20.) �\�[�V�����E�l�b�g���[�N�@�@THE SOCIAL NETWORK �i�Q�O�P�O�N�A�āA�����F���Y���ށj  �@�E�H�[�N�}���ƌg�уQ�[���@�́u���E��ς������[�h�E�C���E�W���p���v�̑o���ƌ����Ă͂��邪�A�ǂ������̂Q�̔����i�A���̒���֗��ɂ�����́A�l�Ԃ�s�����ɂ�������ւ̍v�����傫�������悤�Ɏv���ĂȂ�Ȃ��B�Z�p���i������ɂ�A���̓����͉����������B���N��̒n���ɂ́A���o�����ƃj���e���h�[�ň�����Љ�[���̎�҂����ӂ�Ă���ɈႢ�Ȃ��B �@�������A����Ȏ���̐\���q��������������A�W�F�V�[�E�A�C�[���o�[�O�ɏ���o�D�͂��Ȃ��i�����Ƃ����A����A�قߌ��t���j�B�O��́w�]���r�����h�x�ł́A�������������т邱�Ƃ������l���āA���O�̃��[�����������ȂɌ��炵�Ă����N���B�����Ė{��ł́A����r�m�r�i�\�[�V�����E�l�b�g���[�L���O�E�T�[�r�X�j�́u�t�F�C�X�u�b�N�v��n�݂��铪�]�������Ȃ���A�l�Â������͂���������w�^�ȐN�̖��ŁA���قȎ������������B �@�ē̃f�r�b�h�E�t�B���`���[�́A���̎��݂̓V�˃}�[�N�E�U�b�J�[�o�[�O�ƁA���́i���j�F�l�����Ƃ̑i������A�ǂ���ɂ������ꂷ�邱�ƂȂ��ϋq�̑O�ɒ���B��l���ւ̋�����U�����Ƃ������ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ������ɁA�A�C�[���o�[�O�̐l�Ԗ��̔����̂悤�Ȃ��̂��Ȃ���w�ۗ������B�ނɃA�C�f�A�𓐗p���ꂽ�Ƒi����G���[�g�w�����A�u�t�F�C�X�u�b�N�ʼn����l�̗F�l����낤�ƁA�U�b�J�[�o�[�O���g�ɂ͂T�l���炢�����F�l�͂��Ȃ�����Ȃ����v�Ɠf���̂Ă�̂���ۓI���B �@�����A�w�]���r�����h�x��w�\�[�V�����E�l�b�g���[�N�x�̎�l�������ꂾ���̐l���Ȃ�A�������͗�����Ƃ肽�ĂĖʔ����Ƃ͊����Ȃ����낤�B�s�����Ȑl�����������Ȃ�A�~�q���G���E�n�l�P��[�X�E�t�H���E�g���A�[�̃N�\�f����ς�Ώ\�����B �w�]���r�����h�x���B�ꂽ����ɂȂ��Ă����̂́A�����{�ʂɌ������N���A�I�ՁA�u�q�[���[�ɂȂ낤�Ƃ���ȁv�Ƃ�������ɉۂ����S����j���āA���ꂽ�����~�����߂Ɋ�n�ɔ�т��ނ���B �@���l�ɁA�w�\�[�V�����E�l�b�g���[�N�x�ōł��n�b�Ƃ�������̂́A�����̉ߒ��Őe�F��������̂āA���͂̐l�Ԃ��ׂĂɘ����Ȋ�������Ă�����l�����A�t�F�C�X�u�b�N��Ō����l�Ɂg�F�����h�Ƃ��Ă̏��F��\�����݁A�����܂ł����܂ł��҂�������p���B �@���̃��X�g�V�[���Ɏ����āA�������͂ӂƍl����̂��B�U�b�J�[�o�[�O���t�F�C�X�u�b�N�����A�����Ɉ�āA�K���Ŏ�����̂́A�P�Ȃ���ׂ��⎩�Ȏ����̂��߂ł͂Ȃ��A�ޏ��Ƃ̂Ȃ����ۂ��ꂪ�B��̎�i����������ł͂Ȃ������̂��ƁB����̒��ՁA�W���X�e�B���E�e�B���o�[���[�N������i�b�v�X�^�[�̑n�Ǝ҂��u���߂ĐQ�����̂��ƂȂǂ�������Y��Ă��܂����v�ƌ��̂́A�ǂ���炱�̃��X�g�V�[���Ƃ̑Δ�̂��߂������炵���B �@����w�]���x(82)�̃��X�g�V�[���ł́A�|�[���E�j���[�}��������ٌ�m���A�����𗠐����i���������݂���Ȃ��j�V���[���b�g�E�����v�����O���炩������Ȃ��d�b�ɁA�o�悤���o�܂����ƌ��߂��˂āA�Ăяo�������������X�Ɩ炵�������B �@�͂܂���������Ă���̂����A�w�\�[�V�����E�l�b�g���[�N�x�̒��Ԃ���ȃG���f�B���O�����āA�ӂƁw�]���x�̂��̖�����v���������B (2011.1.20.) |