| �@���N�ƌĂ��N��ɂȂ����B�Ⴂ�����炳���ĉ^���_�o�̂������ł͂Ȃ������̂ŁA�̗͂�^���\�͂̐����͂��قNJ����Ȃ��̂����A�L���͂̐����͖ڂ����肾�B �@���Ƃ��Ή�b�̓r���ŁA�ӂƂ��鏗�D�Ɍ��y�������Ȃ����Ƃ���B�Ƃ��낪�u�ق�A���̏��D�������A���O�Ȃ����A�ق�A���ꂾ��A����E�E�E�v�ƌJ��Ԃ��Ă݂Ă��A����ɖ��O���o�Ă��Ȃ��B �@�d�����Ȃ��̂ŁA�u�ق�A���̃_���i�����҂ł����E�E�E�v�ƌ����o�����A���x�̓P�l�X�E�u���i�[�Ƃ������O���o�Ă��Ȃ��B����Ȃ�Əo����������悤�Ƃ��邪�A���̂̌����ɂP���v���o���Ȃ��B�قƂ�ǜ����̐l�ł���B �@���̓_�A�z�[���y�[�W�Ƃ������f�B�A�́A�Y�ꂽ�������蒲�ׂď��������B���̏��D�ɂ��Ă����S���Č��y�ł���Ƃ������@���B�����ƁA���O�Ȃ����B�ق�A���ꂾ��A����E�E�E�B |
�m�l�d�m�t�n
![]() �@���̓X�e���C�h�@(2025.9.16.)
�@���̓X�e���C�h�@(2025.9.16.)![]()
![]() �@�^���S�̌���@(2025.9.16.)
�@�^���S�̌���@(2025.9.16.)![]()
![]() �@�X�g�����W�E�_�[�����@(2025.8.8.)
�@�X�g�����W�E�_�[�����@(2025.8.8.)
![]() �@�e�P�^�G�t�����@(2025.7.21.)
�@�e�P�^�G�t�����@(2025.7.21.)
![]() �@�e���}���䂭�I�@�X�R�̂₳�������x���W�@(2025.6.19.)
�@�e���}���䂭�I�@�X�R�̂₳�������x���W�@(2025.6.19.)
![]() �@�T�u�X�^���X�@(2025.5.26.)
�@�T�u�X�^���X�@(2025.5.26.)
![]() �@�i�n�h�j�`�@���Ƌ��C�̃o�����[�i�@(2025.5.14.)
�@�i�n�h�j�`�@���Ƌ��C�̃o�����[�i�@(2025.5.14.)
![]() �@�ْ[�҂̉��@(2025.5.7.)
�@�ْ[�҂̉��@(2025.5.7.)
![]() �@�A���W�F���g�������@(2025.4.25.)
�@�A���W�F���g�������@(2025.4.25.)
![]() �@�g�d�q�d �����z�����@(2025.4.23.)
�@�g�d�q�d �����z�����@(2025.4.23.)
![]() �@�~�b�L�[�P�V�@(2025.4.15.)
�@�~�b�L�[�P�V�@(2025.4.15.)
![]() �@���c�I���@(2025.4.3.)
�@���c�I���@(2025.4.3.)
![]() �@�`�m�n�q�` �A�m�[���@(2025.3.20.)
�@�`�m�n�q�` �A�m�[���@(2025.3.20.)
![]() �@�����Ȃ��ҁ^A COMPLETE UNKNOWN�@(2025.3.20.)
�@�����Ȃ��ҁ^A COMPLETE UNKNOWN�@(2025.3.20.)
![]() �@�Q�O�Q�T�N�I�X�J�[�i�C�g�E�E�H�b�`���O�I�@(2025.3.11.)
�@�Q�O�Q�T�N�I�X�J�[�i�C�g�E�E�H�b�`���O�I�@(2025.3.11.)
![]() �@���A���E�y�C���`�S�̗��`�@(2025.2.19.)
�@���A���E�y�C���`�S�̗��`�@(2025.2.19.)
![]() �@�U�E���[���E�l�N�X�g�E�h�A�@(2025.2.19.)
�@�U�E���[���E�l�N�X�g�E�h�A�@(2025.2.19.)
![]() �@�Q�O�Q�S�N�i���́j�x�X�g�P�O�I�@(2025.1.2.)
�@�Q�O�Q�S�N�i���́j�x�X�g�P�O�I�@(2025.1.2.)
![]() �@���{�b�g�E�h���[���Y�@(2024.12.18.)
�@���{�b�g�E�h���[���Y�@(2024.12.18.)
![]() �@�z���C�g�o�[�h�@�͂��܂�̃����_�[�@(2024.12.13.)
�@�z���C�g�o�[�h�@�͂��܂�̃����_�[�@(2024.12.13.)
![]() �@�h���[���E�V�i���I�@(2024.12.2.)
�@�h���[���E�V�i���I�@(2024.12.2.)
![]() �@���^�C���X���b�p�[�@(2024.12.2.)
�@���^�C���X���b�p�[�@(2024.12.2.)
![]() �@�V�r���E�E�H�[�@�A�����J�Ō�̓��@(2024.10.22.)
�@�V�r���E�E�H�[�@�A�����J�Ō�̓��@(2024.10.22.)
![]() �@�G�C���A���F�������X�@(2024.9.19.)
�@�G�C���A���F�������X�@(2024.9.19.)
![]() �@�t�H�[���K�C�@(2024.9.13.)
�@�t�H�[���K�C�@(2024.9.13.)
![]() �@�c�C�X�^�[�Y�@(2024.9.13.)
�@�c�C�X�^�[�Y�@(2024.9.13.)
![]() �@�f�b�h�v�[�����E�����@�����@(2024.9.13.)
�@�f�b�h�v�[�����E�����@�����@(2024.9.13.)
![]() �@�t���C�E�~�[�E�g�D�E�U�E���[���@(2024.7.23.)
�@�t���C�E�~�[�E�g�D�E�U�E���[���@(2024.7.23.)
![]() �@�w�N���C�G�b�g�E�v���C�X�x�̐��Ԋw�@(2024.7.20.)
�@�w�N���C�G�b�g�E�v���C�X�x�̐��Ԋw�@(2024.7.20.)
![]() �@�N���C�G�b�g�E�v���C�X�F�c�`�x�P�@(2024.7.19.)
�@�N���C�G�b�g�E�v���C�X�F�c�`�x�P�@(2024.7.19.)
![]() �@�z�[���h�I�[�o�[�Y�F�u���Ă��ڂ�̃z���f�B�@(2024.7.9.)
�@�z�[���h�I�[�o�[�Y�F�u���Ă��ڂ�̃z���f�B�@(2024.7.9.)
![]() �@�S�̈��@(2024.6.10.)
�@�S�̈��@(2024.6.10.)
![]() �@�}�b�h�}�b�N�X�F�t�����I�T�@(2024.6.10.)
�@�}�b�h�}�b�N�X�F�t�����I�T�@(2024.6.10.)
![]() �@������v���e���_�[�@(2024.5.16.)
�@������v���e���_�[�@(2024.5.16.)
![]() �@�}���E�|���̂Q�O�����@(2024.4.29.)
�@�}���E�|���̂Q�O�����@(2024.4.29.)
![]() �@�p�X�g ���C�u�X�^�ĉ��@(2024.4.29.)
�@�p�X�g ���C�u�X�^�ĉ��@(2024.4.29.)
![]() �@�S�[�X�g�o�X�^�[�Y�^�t���[�Y���E�T�}�[�@(2024.4.29.)
�@�S�[�X�g�o�X�^�[�Y�^�t���[�Y���E�T�}�[�@(2024.4.29.)
![]() �@�I�b�y���n�C�}�[�@(2024.4.5.)
�@�I�b�y���n�C�}�[�@(2024.4.5.)
![]() �@�Q�O�Q�S�N�I�X�J�[�i�C�g�E�E�H�b�`���O�I�@(2024.3.12.)
�@�Q�O�Q�S�N�I�X�J�[�i�C�g�E�E�H�b�`���O�I�@(2024.3.12.)
![]() �@�l�N�X�g�E�S�[���E�E�B���Y�@(2024.3.12.)
�@�l�N�X�g�E�S�[���E�E�B���Y�@(2024.3.12.)
![]() �@�T���E�Z�o�X�`�����ցA�悤�����@(2024.2.12.)
�@�T���E�Z�o�X�`�����ցA�悤�����@(2024.2.12.)
![]() �@����Ȃ���̂����@(2024.2.12.)
�@����Ȃ���̂����@(2024.2.12.)
![]() �@�͂�t�@(2024.2.12.)
�@�͂�t�@(2024.2.12.)
![]() �@�_���E�}�l�[�@�E�H�[���X��_���I�@(2024.2.12.)
�@�_���E�}�l�[�@�E�H�[���X��_���I�@(2024.2.12.)
![]() �@�Q�O�Q�R�N�i���́j�x�X�g�X�I�@(2024.1.13.)
�@�Q�O�Q�R�N�i���́j�x�X�g�X�I�@(2024.1.13.)
![]() �@�E�H���J�ƃ`���R���[�g�H��̂͂��܂��@(2023.12.17.)
�@�E�H���J�ƃ`���R���[�g�H��̂͂��܂��@(2023.12.17.)
![]() �@�R�J�C���E�x�A�@(2023.10.19.)
�@�R�J�C���E�x�A�@(2023.10.19.)
![]() �@�G���U�x�[�g�P�W�V�W�@(2023.9.9.)
�@�G���U�x�[�g�P�W�V�W�@(2023.9.9.)
![]() �@�t�@���R���E���C�N�@(2023.9.9.)
�@�t�@���R���E���C�N�@(2023.9.9.)
![]() �@�A�X�e���C�h�E�V�e�B�@(2023.9.9.)
�@�A�X�e���C�h�E�V�e�B�@(2023.9.9.)
![]() �@�T��}�[���E�@(2023.8.6.)
�@�T��}�[���E�@(2023.8.6.)
![]() �@�E�[�}���E�g�[�L���O�@�������̑I���@(2023.6.14.)
�@�E�[�}���E�g�[�L���O�@�������̑I���@(2023.6.14.)
![]() �@����ł����͐����Ă����@(2023.6.14.)
�@����ł����͐����Ă����@(2023.6.14.)
![]() �@�s�`�q�^�^�[�@(2023.5.27.)
�@�s�`�q�^�^�[�@(2023.5.27.)
![]() �@�`�h�q�^�G�A�@(2023.4.26.)
�@�`�h�q�^�G�A�@(2023.4.26.)
![]() �@�U�E�z�G�[���@(2023.4.26.)
�@�U�E�z�G�[���@(2023.4.26.)
![]() �@�Q�O�Q�R�N�I�X�J�[�i�C�g�E�E�H�b�`���O�I�@(2023.3.14.)
�@�Q�O�Q�R�N�I�X�J�[�i�C�g�E�E�H�b�`���O�I�@(2023.3.14.)
![]() �@�t�]�̃g���C�A���O���@(2023.3.14.)
�@�t�]�̃g���C�A���O���@(2023.3.14.)
![]() �@���ׂĂ��܂������܂��悤���@(2023.3.5.)
�@���ׂĂ��܂������܂��悤���@(2023.3.5.)
![]() �@�A���r�A���i�C�g�@�O��N�̊肢�@(2023.3.5.)
�@�A���r�A���i�C�g�@�O��N�̊肢�@(2023.3.5.)
![]() �@���̂����@(2023.1.30.)
�@���̂����@(2023.1.30.)
![]() �@�L�����[�v�l�@�V�ˉȊw�҂̈��Ə�M�@(2023.1.28.)
�@�L�����[�v�l�@�V�ˉȊw�҂̈��Ə�M�@(2023.1.28.)
![]() �@�Q�O�Q�Q�N�i���́j�x�X�g�P�O�I�@(2023.1.10.)
�@�Q�O�Q�Q�N�i���́j�x�X�g�P�O�I�@(2023.1.10.)
![]() �@�A���X�e���_���@(2022.11.10.)
�@�A���X�e���_���@(2022.11.10.)
![]() �@�X�y���T�[�@�_�C�A�i�̌����@(2022.10.18.)
�@�X�y���T�[�@�_�C�A�i�̌����@(2022.10.18.)
![]() �@�k�`�l�a�^�����@(2022.10.10.)
�@�k�`�l�a�^�����@(2022.10.10.)
![]() �@�����ƋU���@(2022.10.1.)
�@�����ƋU���@(2022.10.1.)
![]() �@�u���b�g�E�g���C���@(2022.9.11.)
�@�u���b�g�E�g���C���@(2022.9.11.)
![]() �@�x���t�@�X�g�@(2022.4.10.)
�@�x���t�@�X�g�@(2022.4.10.)
![]() �@�I�[�g�N�`���[���@(2022.4.10.)
�@�I�[�g�N�`���[���@(2022.4.10.)
![]() �@�Q�O�Q�Q�N�I�X�J�[�i�C�g�E�E�H�b�`���O�I�@(2022.4.10.)
�@�Q�O�Q�Q�N�I�X�J�[�i�C�g�E�E�H�b�`���O�I�@(2022.4.10.)
![]() �@�K���p�E�_�[�E�~���N�V�F�C�N�@(2022.3.26.)
�@�K���p�E�_�[�E�~���N�V�F�C�N�@(2022.3.26.)
![]() �@�I�y���[�V�����E�~���X�~�[�g�^�i�`���\���������@(2022.3.26.)
�@�I�y���[�V�����E�~���X�~�[�g�^�i�`���\���������@(2022.3.26.)
![]() �@�R�[�_�@�����̂����@(2022.2.18.)
�@�R�[�_�@�����̂����@(2022.2.18.)
![]() �@�t�����`�E�f�B�X�p�b�`�@(2022.2.12.)
�@�t�����`�E�f�B�X�p�b�`�@(2022.2.12.)
![]() �@�S�[�X�g�o�X�^�[�Y�^�A�t�^�[���C�t�@(2022.2.12.)
�@�S�[�X�g�o�X�^�[�Y�^�A�t�^�[���C�t�@(2022.2.12.)
![]() �@�Q�O�Q�P�N�i���́j�x�X�g�P�O�I�@(2022.1.8.)
�@�Q�O�Q�P�N�i���́j�x�X�g�P�O�I�@(2022.1.8.)
![]() �@�Q�O�P�U�`�Q�P�N�́u���[�r�[�E�U�E�u�[�r�[�v��
�@�Q�O�P�U�`�Q�P�N�́u���[�r�[�E�U�E�u�[�r�[�v��
![]() �@�Q�O�P�P�`�P�T�N�́u���[�r�[�E�U�E�u�[�r�[�v��
�@�Q�O�P�P�`�P�T�N�́u���[�r�[�E�U�E�u�[�r�[�v��
![]() �@�Q�O�O�U�`�P�O�N�́u���[�r�[�E�U�E�u�[�r�[�v��
�@�Q�O�O�U�`�P�O�N�́u���[�r�[�E�U�E�u�[�r�[�v��
![]() �@�Q�O�O�Q�`�T�N�́u���[�r�[�E�U�E�u�[�r�[�v��
�@�Q�O�O�Q�`�T�N�́u���[�r�[�E�U�E�u�[�r�[�v��
![]() �@�l���������������������f�ڂ̉f��]��
�@�l���������������������f�ڂ̉f��]��
![]() �@�g�b�v�y�[�W�ɖ߂�
�@�g�b�v�y�[�W�ɖ߂�
|
���̓X�e���C�h LOVE LIES BLEEDING �i�Q�O�Q�S�N�A�p���āA�����F�����b�q�j  �@�N���X�e���E�X�`�����[�g�̊炾�����āA����ς荂�M�ȍc���q�܂Ȃ���Ȃ��A�₳����A���܂����i����ł��������悤�ƌ����ɂ������ł��銴���́j�����悭��������ˁB �@�ޏ����{��ŕ�����̂́A�����œK���ɐ����悤�Ȕ��^�������A�g���[�j���O�W���̎x�z�l�̃��Y�r�A���A���[�B��e�͎��H���A���e�͗��ҋƂɎ����߁A�o�͂c�u�v�ɋ��ˑ��ƁA�ƒ���̕��G�������[�Ȃ��B�����Ƀ{�f�B�r�����ւ̏o���ڎw���W���b�L�[�i�P�C�e�B�E�I�u���C�A���j�����ꒅ���A�Q�l�͋}���Ɏ䂩�ꍇ���āE�E�E�B �@�f��͂��܂莖�O������ꂸ�Ɋςɂ������Ƃɂ��Ă���̂ŁA���܂Ɂu��n�Y���������v�ƃK�b�N�����邱�Ƃ����邯��ǁA�t�Ɂu���A���������b�������́H�v�ƁA�����Ӗ��ŋ�������邱�Ƃ�����B �w���̓X�e���C�h�x�͊��S�Ɍ�ҁB�ӏܑO�̃C���[�W�ł́A�Ă�����u�K�[���E�~�[�c�E�K�[���������ɂ����X�|������v���Ƃ���v���Ă������A���Ոȍ~�͋��낵���n�[�h�R�A�ȃN���C���E�T�X�y���X�ւƂ˂���Ă����B���[�̕��e���̃G�h�E�n���X�������n�Q�������т̈ٗl�ȕ��̂ŏ��o��V�[������������̂́A�܂������ɒB�ł͂Ȃ������킯�ˁB �@�V���[�g�o�[�W�����̊��z�͈ȏ�ł���A����Ȃ��ɖʔ�����삾�����B�ȉ��́A���łɍl�����I�}�P���z�ƁA�����ďd�v�ł͂Ȃ��c�b�R�~�B �@���A���Y������ɂ��������ɁA�W���b�L�[���u�X�e���C�h�܂̉e���v�Ƃ��������ł͂Ƃ��Ă��[���ł��Ȃ��悤�Ȃr�e�I�ϖe��ُ�s����������V�[�����Q�`�R�ӏ�����A�Ȃ������������������Ă���B�������Ɠ��ꊴ���l���Ă����B �@�����Ă���ƌ����A�u�}�b�`���Ȓj�����S��`�ɑ��鏗������̔��R���v�Ƃ��v��ł������Ȃ��̍�i�̒��ŁA�ē��[�Y�E�O���X�A�r�{�x���j�J�E�g�t�B�E�X�J�Ƃ����A�t�@�[�X�g�l�[�����炵�Ă����炭�������낤�Ǝv����R���r�́A���[�̎o�i�W�F�i�E�}���[���j�ɂ����܂Ŗ\�͕v��i�삳���A�������Ă����ˁB �@����䂦�ɖ\�͕v�炵�߂����̃��[�ƃW���b�L�[�����҂ɂ���A�u�����̘A�сE�����v�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��\�}�B�����������[�ɕЎv������e���̃��Y���A���Ȓ��S�I�ȁA���܂�A�ъ��ɂ͍v�����Ȃ��L�����������B �@���ʁA�{��̓��Y�r�A���f��ł���Ȃ���A�����f��Ƃ��Ă̕]���͓��ɂ����Ƃ����A������ƒ������ʒu�Â��̍�i�ɂȂ��Ă��銴���B �@���̍��葤�̈Ӑ}�͉��Ȃ�ł��傤�ˁH�@�u�A�^�V��A�j���������č����ȋ�ʂz�����Ƃ���ʼnf�������Ă܂����A���ꂪ�����H�v���ĂƂ���Ȃ̂��ȁB �i�Q�O�Q�T�D�X�D�P�U�D�L�j �^���S�̌�� MARIA �i�Q�O�Q�S�N�A���A�����F��ӂ����݁j  �@�x���g���b�`�́w���X�g�^���S�E�C���E�p���x(1972)�ő�䏊�}�[�����E�u�����h�̑�����ɔ��F���ꂽ�}���A�E�V���i�C�_�[�̕]�`�B���X�^�[�_���ɂ̂��オ�������̂́A�쒆�̉ߌ��Ȑ��`�ʂ̂������Łu�F�����D�v�ƌ�����悤�ɂȂ������ʁA����ɐ��_�I�ɕs����ɂȂ�c�B �����݂̖�����������Ɂ� �@�����r�{���肪�����W�F�V�J�E�p���[�ḗA�w���X�g�^���S�E�C���E�p���x�̐��V�[�����A���ς��i��ς��A�N�₩�ɍ�i�Ɏ�肱�B �@����ӏ��ł́u����͎B�e��ʂȂ�ł���v�Ɩ�������`�ŁA�܂��ʂ̉ӏ��ł͌��������Ƃ����ɂ͂킩��Ȃ����炢���˂ɁB �i�V���i�C�_�[���̃A�i�}���A�E�o���g�����C���l�R�ȓ����̌`�Ԗ͎ʂ�������V�[�������̂P�B�l���ŗ����~�܂�����A�������ƑO�i�����肷�铮��̊ɋ}�����A�l����_���l�R�ȏ�Ƀl�R�炵���j �@�����A�ł����Q�����̂́A���ƌ����Ă��V���i�C�_�[���x���g���b�`�ƃu�����h�Ɂu���܂������v�ɂ����ꖋ���낤�B���`���[�h�E�M�A���ł����킹�����ŕ�Δ��̂ӂ���߁A�W�����A�E���o�[�c���f�Łu������I�v�ƁE�E�E�݂����ȉ��炵�����̂���Ȃ��B�قƂ�ǐl�i�I���W�A���_�I���C�v�ƌ����Ă��悢���炢�B �@�p���[�ē͂�����A�u�r�{�ǂ���̃e�X�g�V�[���v���u�r�{�����̖{�ԃV�[���v�̏��Ō����Ă����B�Ȃ�Ɛe���I���ȃX�g�[���[�e�����O���B �@�V���i�C�_�[���Ȃ��߂������āA�����V�[���̎B�e�ɖ߂点�����Ƃ̃J�b�e�B���O���܂��G��I�@�p���[�́u�V���i�C�_�[���{��Ɣ߂��݂�����ĉ��Z�𑱂��܂����v���́A�t�Ɂu���D�Ƃ��ĊJ�Ⴕ�܂����v���̂ƒ��X���������������Ȃ��B�x���g���b�`�́u�A�N�V�����v�̐������������u�ԁA�u�����h���̃}�b�g�E�f�B�������u�������f�悾�v�ƃV���i�C�_�[�̎����ɐ������݁A���̙��߁A�ӂ��ƃV�[�����グ��B �i����ȃl�^�o���߂������Ƃ�������̂��A���ۂ̃V�[���̐��ۂ������J�b�R�悳�ɔ�ׂ�A���̕��͂ȂǃS�~�����炾�j �������ɂ܂�� �����₩���]�~�� �@�]�k�Ȃ���A�f���|��Ɍg���҂̗���ŋC�ɂȂ������Ƃ���_�������B �@���Ӑ[���F����͓������炨�C�Â����낤���A�P�{�̉f��̒��łQ�ȏ�̊O���ꂪ�g���Ă���ꍇ�A���C���̌���ȊO�̃Z���t�͒ʏ�A�����������ł�����i��F���N�̓��Ɋ��t���j�B �@�Ƃ��낪���̍�i�A�V���i�C�_�[�ƃu�����h���b���Ƃ��ɂ͕���Ɖp�ꂪ�`�����|���ɂȂ��Ă���̂ɁA�����̏�łȂ����������ʂ��Ă��Ȃ���ł��ˁB �@�t�����X�ł̎B�e�ɗՂč��l�u�����h�ƁA�ނɋC���g���V���i�C�_�[���A����ꍑ��Œʂ��A����̌��t�œ`���邩�Ƃ���������ɂ��������ȋ@�����������̂����A�p���ꂪ�����������Ȃ��ϋq�ɂ́A���ʓI�ɂ��ꂪ�͂��Ȃ������͂��B�Ȃ�Ƃ��������Ȃ����Ƃ��B �i�����|��҂��g�͏K���I�ɃZ�I���[�ɏ]�����Ƃ������낤����A�����炭�z���Ȃ萻��Ȃ�̈̂��l���A�u����Ɖp��������ŋ�ʂ���ɂ͋y���v�Ƃ̌�����������̂ł͂Ȃ����Ƒz������j ���㔼�̕s���Ȏ����� �@���āA�{��̖M��́w�^���S�̌�Łx�����A�w���X�g�^���S�E�C���E�p���x�����ɏo�����ƁA���Ȃ킿�q���C����������u�Ղ��D�v�ɂȂ�����A�w���C���Ɉˑ������肵�Ă����㔼�̓W�J�ɂ́A���̂Ƃ���A����قNJς�ׂ����̂͂Ȃ��B���̎����ɓo�ꂵ�A�V���i�C�_�[�Ɛe�������ԏ��q�w���k�[���Ɏ��_�l�����ڂ��Ă��܂��悤�ȃV�[���������āA�O���̃L���̂��鉉�o�Ƃ̊Ԃɂ��Ȃ�̗�������������B �@���̈Ӗ��Ŗ{��́A�u�^���S�̌�v�Ƃ������A��`�I�ɂ́u�^���S���x���Ă��邳�Ȃ��̕��䗠�v���_�Ԍ��邽�߂̉f�悾�ƍl����̂������Ȃ̂��낤�Ǝv���B �@�ƁA�����܂ł����Ƃ��炵�����Ƃ������Ă������ǁA���͎����w���X�g�^���S�x�͖����B�����A�܂�ŋ����̂Ȃ�����������A�@��������為�Њς����Ǝv���悤�ɂȂ����̂́A�ԈႢ�Ȃ��p���[�ē̎�r�ł���B �i�Q�O�Q�T�D�X�D�P�U�D�L�j �X�g�����W�E�_�[���� STRANGE DARLING �i�Q�O�Q�R�N�A�āA�����F�����v���j  �@����͂܂����܂����C���f�B�[�Y��i���a���������́B�X�����[�Ƃ��Ă��p�Y���[�Ƃ��Ă��j�i�̃f�L�ɂȂ��Ă���B�ē��_�u���剉�̔o�D�w�����߂Č��閼�O���������A�{��ň�����ڂ��ꂽ�Ƃ����̂����Ȃ�����B �@�I�[�v�j���O�^�C�g���̒i�K�ŁA���i�E�B���E�t�B�b�c�W�F�����h�j�̖𖼂��u�U�E���C�f�B�i�i���j�v�A�j�i�J�C���E�K���i�[�j�̖𖼂��u�U�E�f�[�����i�����j�v�ł��邱�Ƃ��A�h�f�J�������������Ď������B�ォ��U��Ԃ���ꂪ�ϋq�������������P��㩂��B �@�U�͗��ā����n��V���b�t���Ƃ����Â����\�����A�܂������ɒB�␌������Ȃ��B�e�͂ɂǂ�ȃv���b�g��z�u���邩���A������ǂ�ȏ��ԂŒ��邩���A���̂̌����ɍl��������Ă�B �@����Ɋւ�����͓��Ɍ��J����Ă��Ȃ��悤�Ȃ̂ŁA�ēE�r�{�̂i�s�E�����i�[�̃I���W�i���E�X�g�[���[���Ǝv�����A�l�I�ɂ͋r�{�܂̃I�X�J�[��^���Ă������Ǝv���قǂ��B �@����Ȃ킯�ŁA�I�[�v�j���O�͂����Ȃ��R�́B�ϋq�́A�Ԃ��n�b�`�o�b�N�ɏ���������A�����s�b�N�A�b�v�E�g���b�N�ɏ�����j�ɖҗ�ɒǐՂ���Ă���܂��������ɕ��肱�܂��B �@���̃`�F�C�X�̃X�s�[�h���A���^�̌��ʉ��A�������킸�ɃV���b�g�K�����Ԃ������j�A�����炪�瓦���f�����A����ɂ͖\�͓I�ȃw�r���^�̃X�R�A�I�@�ǐՌ��̔w�i�◝�R�͂����ς�킩��Ȃ��܂܂����A��������X�͕Ў����ڂ𗣂��Ȃ��Ȃ��Ă���B �@����ȗ���̂܂܂ɑ�T�͂ɔ�сA�������Ɋϋq���u�����������̂Q�l�͂Ȃ�ł���ȏC����ɓ˓�����������́H�v�ƋC�ɂȂ肾�����Ƃ���ŁA�o�����������P�͂�B���̂�����܂ł́A�ϋq�͊ē̕~�������H�ɉ����ă��C�h�ɏ���Ă镶���ǂ���́u���q����v���B �@�Ƃ��낪���̑�S�͂ŁA�i�����A��������̂܂ܐi���Ɍ�������R�͂Ƒ�T�͂̊Ԃ̑�S�͂Łj�Ƃ�ł��Ȃ��N���]���́u�]�v�������o����A���͂�ϋq�͖ق��ă��C�h�ɐg��C���Ă��邱�ƂȂǂł��Ȃ��Ȃ�B�����Ď����̔]�~�\�������o��قǍ�����]�����āA�S�̑��̔c���ɂ���w�߂�킯�ł��ˁB �@���̂�����A���ʂ̉f��Ȃ�u���̓W�J��\�z����v�Ƃ������ƂɂȂ�킯�����A�{��̏ꍇ�A�����Ɏ����ĉ������C�ɂȂ�̂́A�������u��Q�͂ɉ����������̂��v���B�ē͒����ǂ���ɂ����ɖ߂�A�Ō�ɓ{���̑�U�͂ւƂȂ��ꂱ��ł����B �@�U�͗��Ăł��邱�Ƃ��A����܂��I�[�v�j���O�^�C�g���̒i�K�Ŗ�������Ă����̂������Ȑ[�d�����������B���͂܂ł���̂��킩��Ȃ���A���l�C���̃��C�h�ɏ�����܂܂ł����ϋq�����������͂��B�������U�͗��Ă��Ƃ��炩���߂킩���Ă���A�ϋq�͋N���������Ƃ̈��ʊW���A�\���I�����l�߂ŗ\�z�������Ȃ�B �@�i�s�����i�[�́A��������Ċϋq�̓��Ɏ��X�Ƌ^�����������ẮA�▭�ȏ��Ԃł��̉������Ă����̂ł���B���܂��B �@���������X�g�[���[�e�����O��̖��͂ɏ���Ƃ����Ȃ��̂��A�{��̃L�����N�^�[�̋����B �@���̒��ɂ́w�[�A�E�E�B���E�r�[�E�u���b�h�x��w�S�[���E�K�[���x���P��߂́w�^�[�~�l�[�^�[�x�̂悤�ɁA������郔�B�����̔�є����ċ���Ȍ��ɂ���Ă������������������������Ă����^�C�v�̍�i������B�ς鑤�́i���Ȃ��Ƃ�����ɂ���Ԃ́j���ׂ�P���Ȃǂǂ��ł��悭�Ȃ��āA��m�炸���̃s�J���X�N�Ԃ�ɉ��Ƃ�����ł��܂��B �@�{������炩�ɂ���Ȍn���ɑ������삾�낤�B�����玄�����́A��l�����D���������������A�Ƃɂ������̖`�������͂����ɂ͂����Ȃ��Ȃ�̂��B �@���Ȃ݂ɎB�e�͔o�D�̃W���o���j�E���r�[�W�����߂Ď肪���������B�o�����̃J�[�`�F�C�X�̔��͂͑O�q�̂Ƃ��肾���A�Ƃ���ǂ���w�o�E���h�x�ɑ�\����鏉���̃E�H�V���E�X�L�[�Z���i�̂悤�ȃV���b�g���}������Ă��Ėʔ��������ȁi�����A�ނ炪�{���́g�Z��h���������̘b�ˁj�B �i�Q�O�Q�T�D�W�D�W�D�L�j �e�P�^�G�t���� F1 �i�Q�O�Q�T�N�A�āA�����F����L�K�j  �@���N�̉ċx�݉f������ǃg���E�N���[�Y�ƃu���s�����I���ĂȂ���ł���B �@�O�҂͂l�h�V���[�Y�̍ŐV��ŁA�����Č�҂́w�e�P�^�G�t�����x�ŁA���ꂼ��T�}�[�V�[�Y���̖��J�����������B �@���̂Q�l���n���E�b�h�̓V�ӂ�����Ă���A�����������\�N�̍Ό��������Ă���̂��B�u����ꂽ�R�O�N�v���o�����Ă����̂́A���炩�ɓ��{�o�ς����ł͂Ȃ��B �@�܂��A�u����������ł��~�߂ɂ����v�Ƃ݂�ȂɎv���Ȃ�����l�h�𑱂���N���[�Y�����A��{�A�V���[�Y���ɂ͔w�������Ă���u���s�̕��������A�N�x�̒ቺ�͗}�����Ă͂��邪�B �i�N�x�̒ቺ�̓��C�X�s���W�����E�E�B�b�N�������B�V���[�Y���̑唼���O����Ȃ̂͗��R�Ȃ����Ƃł͂Ȃ��B�X�^�[��������Ȃ��V��̃A�C�f�A���s�����Ă���ȁA�n���E�b�h�j ���u�e�P�f��v�ɂ��Ȃ������[�d�� �@���āA������N���[�Y�́w�g�b�v�K���E�}�[���F���b�N�x�Ɠ����W���Z�t�E�R�V���X�L�[�ē����K�z����������w�e�P�^�G�t�����x�́A�����[�����ƂɁu�e�P�ɑ�ނ�������f��v�ł͂��邪�A�u�e�P�f��v�ł͂Ȃ���ł��ˁB �@���͉f���|��̎d�����肪����g�Ȃ̂ŁA�ߋ��ɃJ�[���[�X���̃h�L�������^���[�̎�����琁�ւ���S���������Ƃ�����̂����A�܂��A�N���[���m�̐��p�ꖞ�ڂ̉�b���A�Ԃ̃��J�̘b��炪�Ă���ŁA�L���u���^�[���������m��Ȃ����n�|��҂͉��������B �@�Ƃ��낪�w�e�P�^�G�t�����x�ł́A�}�V����J�̏�����p�������ȂǂقƂ�ǐ�������A�e�P�I�茠�̃��[����V�X�e�������ꂢ�ɏȗ��B����Ɉ����̃u���s�̐헪���f�ɏœ_���i���Ă����ł��ˁB�������Ŏ��̂悤�ȃy�[�p�[�h���C�o�[�ł��A�Ō�܂Ŗ����Ȃ炸�ɂ��B �@�s�b�g��ƂɎ����ẮA�N���[�̎d���Ԃ�ȂقƂ�ljf���Ȃ��B��ʂɂ͉^�]�Ȃ̃h���C�o�[���f�����܂܁A�^�C�����͂߂鉹�����K�R���A�W���b�L�������鉹�����h�^���ŏI���B���̃R���}�P�b��ɂ͎Ԃ�����o���Ă����B���̕ҏW�ʂ̌����ƃX�s�[�h���ɂ́A���͂�������Ȃ��B �@�K�`�̂e�P�t�@���ɂ́A�����╨����Ȃ��������낤���A��y�f��̍���Ƃ��Č����ȑI���������̂��m���B�����ĉf��t�@���ɐ�߂�e�P�I�^�N�̔䗦�Ȃ�āA�P���ɂ������Ȃ����炢�ł���H ���肤�̂͐헪����Ȃ��� �@����̑�́u�听�����˂��V���V�˃��[�T�[���A�听�ł����ɂ���ᑢ�V�˃��[�T�[�Ƒg��ʼn�������ʂ����b�v�Ƃ܂Ƃ߂��悤���A�l�I�Ɉ�ԕ]���������̂́A�u���s���u���̎ᑢ����ĂĂ�낤�v�Ȃ�Đe�S���A����ۂ����������Ă��Ȃ��Ƃ��낾��ˁB �@�`�[���̈�Ԏ�͂����܂ł����l�ŁA�|�C���g�l���̂��߂Ȃ�ᑢ�̏��ʂ��オ��悤�v�炢�����邪�A��{�A���O�͉��̃T�u���Ƃ����ԓx�B�@���R�[�`�₨���v�l�݂����ɁA���Ђ�݂̓��ݑ�ɂȂ�C�Ȃ��炳��Ȃ��B �@�剉�o�D����������˂�ƁA���X�ɂ��Ď����̃L�������u�l�i�ҁv�ɐݒ肵�����Ċϋq�̎����̂����A���̓_�ł��u���s�͌����������B �@���[�X�̐헪�Ɋւ��Ă��A�P�Ȃ�X�s�[�h�����A�x�������ł͂Ȃ��A�̈ӂɒᑬ���[�X�Ɏ������ށu��҂̕��@�v���ڗ����܂�����ˁB����͂������A����Ȏ��{�͂ƁA�����\�̃}�V���������C�o���`�[���Ƃ̍������������Ă���킯�����A�o���l���ő�̕���Ƃ���V���h���C�o�[�̃L�������A�ł����Ă�헪�ł��������B �@�헪�ƌ����A�����̍���c�Ŏᑢ���[�T�[���u�l����s�����āA���Ƃ͂��܂��s���悤�肨���v�Ƃ܂Ƃ߂��Ƃ��ɁA�u���s���u�肤�̂͐헪����Ȃ��iHope is not a strategy.�j�v�Ƌꌾ����V�[�����B �@���̓`�ōs���A���̉f��̍��肽�����u�u���s�����o���Ƃ��āA���Ƃ̓q�b�g����悤�肨���v�ł͂Ȃ��A�����Ɛ헪�𗧂Ă��킯���ȁB �������ċ߂��I�g�i�̊W�� �@�e��w�Ŗڂɂ����̂́A�P���[�E�R���h�����������`�[���̃e�N�j�J���E�f�B���N�^�[�i���Ԃ�̃i���o�[�Q�̃|�W�V�����j�B�u���v�ɏ]���ău���s�Ǝ���ɋ������l�߂Ă��������邯��ǁA���݂��ɂ��������N�����A�F�������d���̕����厖������A��ڍ���Ȃ�ăA�z�Ȃ��Ƃ͊Ԉ���Ă����Ȃ��B �@���Ƃ����ĐF�����瑲�Ƃ���قnj͂�Ă����Ȃ��āA�V���ȏo��ɂ̓I�[�v���ȃX�^���X�B�K�R�I�ɂ��̊W�̓����E�i�C�g�E�X�^���h�ɂ���������̂ɂȂ�̂����A�����̂Ƃ�������߂���ƁA���̂Q�l�����̑���ɂ͌����Č���Ȃ��S�̓����A���Ȃ킿�����▲���������A���݂��ɂ����͑f���ɑł������Ă��邱�Ƃ��킩��B �@���`��A�f�G�ȊW���B�u���s���u�p���ɖ������č��l�v�ł��邱�Ƃ��A�����ċ߂��Q�l�̐▭�ȋ������������o������ɂȂ��Ă��邩�ȁB �@�R���h���́w�C�j�V�F�������̐���x�ł��A�����C�����Lj���[���A�������m�I�Ŏ��������𖣗͓I�ɉ����Ă��������B�����Ƒ����̏o��������������D����̂P�l�ł��ˁB �@�����g�����������ȃ��[�g���ɂȂ��Ă���̂ŁA�ǂ����Ă��w�T�u�X�^���X�x�̃}�[�K���b�g�E�N�A���[�݂����ȃL���L�����q�����A���������A����������A������Ɛl���ɔ��Ă����肷�鏗���Ɏ䂩��邱�Ƃ������Ȃ�B �@������ƑO�̉f��ł����Ȃ�A���Ƃ��w�f�n�`�k�I�x�̃A���i�E�t���G����A�w�T�C�h�E�F�C�x�̃o�[�W�j�A�E�}�h�Z���������������B �@�{�e�̒��߂�����ɁA����̃}�h�Z�������C���ɉ��������l���^�̂����̂܂܈��p���Ă݂܂��傤���i�r�{�͂������A�A���N�T���_�[�E�y�C���j�B �u�������C�����J����Ȃ�A���̓��ɊJ�����ꍇ�Ƃ͖����Ⴄ�B�Ȃ��Ȃ烏�C���͐����Ă��邩��B���C���͏n���𑱂��A�����Ȃ��̂ɂȂ��Ă����B�����Ē��_�ɒB����ƁA�s��I�ɗ��n�߂�B���̂Ƃ����܂����ʂقǔ��������̂�v �i�Q�O�Q�T�D�V�D�Q�P�D�L�j �e���}���䂭�I�@�X�R�̂₳�������x���W THELMA �i�Q�O�Q�S�N�A�ā��X�C�X�A�����F��s����j  �@�W���b�N�E�j�R���\���ƃ��[�K���E�t���[�}�����v�剉�����w�ō��̐l���̌������x(2007)�́A�����K�����҂̐��X�̃g�z�z���ŗǂ̃Z���X�E�I�u�E���[���A�ŏ��̂߂��A����ł��Č����̊��҂����̑������������������Ȃ����Ƃ̂Ȃ������A�ɂ߂ėǐS�I�ȉ��삾�����B �@���́w�e���}���䂭�I�x���ςȂ��犴�����̂́A�u����́w�ō��̐l���̌������x�̘V�l�g�z�z�ł��ˁv�Ƃ������ƁB �@�T�^�I�ȃI���I�����\�łP���h�����p�N��ꂽ�X�R�̃q���C���A�e���}�i�W���[���E�X�L�b�u�j���A���̒D�҂ɏ��o���b�Ȃ̂����A�͎̂v���ǂ���ɓ����Ⴕ�Ȃ����A�x�@���Ƒ����u�������������ƂɊ��ӂ��Ă�����߂��Ȃ��v�̈�_����B �@�����ŗF�B�̏�������悤�Ɠd�b�������܂���̂����A�m��Ȃ������Ɏ���ł����z���A���@���ē����Ȃ��Ȃ��Ă���z������ŁA�N������ɂȂ�Ⴕ�Ȃ��B���܂��ɂ͓�������ɂQ��d�b����������肵�āA���̂�����̉��o�ƕҏW�̖��͕�����|�������B��Âɍl����u�����낤�āA�₪�Ĕ߂����v���ƂȂ�ł����ǂˁB �@��ނȂ��e���}�́A�V�l�z�[���Z�܂��̗F�l�x���i���`���[�h�E���E���h�g�D���[�j����d���X�N�[�^�[�������Ɏ�o���A����Ŕ��{�P�����𑗂��Ă���ʂ̗F�l���猝�e�𓐂݂ƁA���̂�����̓��[�h���[�r�[�̕����B���������A���������s���͂��B �@����Ƀx������肩�������D�ŋ��͂��Ă���邱�ƂɂȂ�A�o�f�B���[�r�[�̗l�����悵�Ă����B �@�Ƒ��̑{���̖ڂ�A�����ł͂P���h���������������j��ǂ��l�߂ƁA��d�̃T�X�y���X�������������Ă����Q�l�E�E�E�B �@�ēE�r�{�̃W���V���E�}�[�S�����́A���҃f�r���[�Ƃ͎v���Ȃ��ǂ��d���������B�G���f�B���O�܂Ŋς�ƁA�e���}�ƒ��̗ǂ������q�̃_�j�G�����A�}�[�S�����̃A�o�^�[�Ȃ̂��Ƃ킩��B�����炱���A�_�j�G�����e���}�̃o�f�B�ɂ͂��Ȃ������̂�������Ȃ��ȁB �@�����ē�������Ȃ�A�X�R�̃q���C�����i�P�j��������ɂ��������ȋ��������s�ł��邱�ƂƁA�i�Q�j�X�}�z��������g�����Ȃ��邱�Ƃ��B�W���[���E�X�L�b�u���g�͑������B�҂Ȃ낤���ǁA�����͂��������g�z�z�Ȑݒ�ɂ��Ă��ꂽ�����A��胊�A���e�B���o����������Ȃ��B �@�E�F�����C�h�ȃR���f�B�����ɁA�����������̂�����҂��N�p��������ƃq�b�g�����悤�ɂ��v�����A�����͏��ē�B����Ŗڈ�t���������B �i�Q�O�Q�T�D�U�D�P�X�D�L�j �w�T�u�X�^���X�x�ŃA�C�f���e�B�e�B�Ƃ͉������l���� THE SUBSTANCE �i�Q�O�Q�S�N�A�āA�����F���Y���ށj  �@�A�J�f�~�[�����̃I�[�v�j���O�E�p���f�B�[�Ŏ�肠�����Ă������炢������A�č��{���̉f��ƊE���ɂ��A�{�삪�����ȏՌ���^�������Ƃ�����������B �@�T�O�̒a�����Ƀt�B�b�g�l�X�ԑg�̃z�X�g�����~�낳�ꂽ�G���U�x�X�i�f�~�E���[�A�j�́A�������ȍĐ���Â�����Ԃ�p�����ɂ�����A�҂��҂��̎Ⴋ���g�X�[�i�}�[�K���b�g�E�N�A���[�j����ɓ����̂����E�E�E�B �@�Ƃ����킯�ŁA�����A�ӏܑO�̗\�z�Ƃ͈Ⴂ�A�G���U�x�X���g����Ԃ�̂ł͂Ȃ��A�����܂ł��u���g�v��������ł��ˁB �@�A�J�f�~�[�����Ŏg���Ă����̂́A�ޏ��̔w�����Z�~�̗c���݂����ɂς����芄��āA�������瓯�����炢�̑傫���̕��g�����邸�锇���o���Ă���V�[���B���Ƃ���f�J���������t�����P���V���^�C�����ɖD����������܂߂āA���Ղ��瑊���G�O���V���b�g�������B �@���̑O��̃V�[���ł̓��[�A���N�A���[���t���k�[�h�B�җ�߂��i���N��j�ɂ��Ă̓{�f�B���C���̕���̏��Ȃ����[�A�����A�������\���̃A�b�v�ɂȂ�ƁA�畆�̕ϐF�₩�������B���Ȃ��B��ɂ�����������ꂽ�ϋq�̖ڂɁA�ォ��o�ꂷ��N�A���[�̂��A�Ղ���Ղ�̂������A�ǂ�قNjP���ĉf�邱�Ƃ��I �@�ŁA���̃X�[�Ƃ������g�̐ݒ肪�A�����������s����`�I�����A�悭�����Ύv�l�����Ƃ��Ă����Ԃ鋻���[���B��̂ƕ��g�͂P�T�Ԃ��ƂɌ�ւ��Ȃ���Ȃ炸�A������������Ă���Ԃ́A��������͈ӎ��������A���ŏ��ɓ]������Ă���B������u�����v�Ȃ���A�������Ƒ厖�ɂ��Ă���Ă�������Ȃ����Ǝv�����A�G���U�x�X���X�[���A�݂����x�b�h�ɐQ��������͂��Ȃ��B �@�X�[�͎���ǂ��V���ȃt�B�b�g�l�X�ԑg�̃z�X�g�ɂȂ�A�G���U�x�X�������i�ނǂ��납�A�i�����ǂ���j�䂪���Ƃ̂悤�Ɋ�ԁB�ł��A���̐ݒ�ŁA�G���U�x�X�����O������Ⴄ���̕��g�ɁA�ǂ����Ď��ȓ��ꉻ�ł���̂��́A���Ȃ��B �@�����ăX�[���ǂꂾ�����悤�ƁA��̂ł��鎩�������Ă͂₳���킯�ł͑S�R�Ȃ��̂ł�����ˁB����ǂ��납�A���������ɓ]������Ă���Ԃ́A�X�[���������Ă���̂������F���ł��Ă��Ȃ��i�܂�L���͓������Ȃ��j�B �@���̓_�̓X�[�̕��������ŁA���炩�ɃG���U�x�X�Ƃ͓Ɨ���������������Ă���B���������g�ł��邱�Ƃ͎��o���Ă��āA�{�p��ׁ̍X�������[���ɂ͏]����ł��ˁB�Ȃ��Ȃ�A�P�����Ƃɕ�̂��璊�o�����h�{���������Ȃ��ƁA�g�̂́u����v���ێ��ł��Ȃ��Ȃ邩��B �@�������X�[���u�P�T�Ԍ�ցv�̃��[�����Ȃ�������ɂ��n�߂����ƂŁA���Ԃ����X�ɈÓ]���n�߂�B�����Ƃ͂����茾���Ă��܂��A�G���U�x�X�̗e�e���u�h���A���E�O���C�̏ё��v�݂����ɋ}���ɘV������B���̂�����̃��C�N�Z�p�����A�I�X�J�[��܂��[���̒���e�N�ɐ���������B �@�����A�X�g�[���[�������܂Ői�ނƁA�͂��ƐU��Ԃ炸�ɂ͂����Ȃ��B������������ā[�ƁA���[�A���ŏ��Ɍ������畆�̕ϐF�₩�������A�N�A���[�́u���v��u�Ղ���Ղ�v���A�S�����C�N��B�e�Z�p�̎�����������ˁ[�́H �@�Ă�[���A���������Q�l�̃k�[�h���̂��t���b�f�ŕ`�������́i�܂��͕ʐl�̃k�[�h�f���̊炾�������o���ʂœ\��ւ������́j�������̂�����E�E�E�B �@���[�ށA���悢�扽��M�����炢���̂��킩��Ȃ����̒��ɂȂ��Ă��܂����ˁB���Ȃ݂ɃG���h�N���W�b�g�ɂ́A���[�A�̃X�^���h�C���i����j�Q���ƃN�A���[�̃X�^���h�C���P���̖��O���������Ă����B������ɃX�^���h�C�������f�掩�̂͒������Ȃ��킯�����A�{��Ɋւ��Č����A���Ȃ��Ƃ���̌����Ȃ��A���O���ŏ��ɓ]������Ă����k�[�h�V�[���͑����������������Ȃ��Ȃ��ċC�����Ă�B 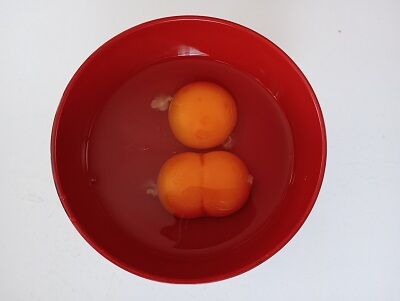 �@�]�k�Ȃ���A����͐���A���܂��܉䂪�ƂŊ��������̎ʐ^�B���̂�́u���g�v���Ă��B���̒l�i���オ���Ă�������A����ȁu�I�}�P�v�����̂͊�������Ƃł͂���E�E�E�̂����A�w�T�u�X�^���X�x���ς��킸���R����Ƃ����āA�H�ׂ�̂Ɉꖕ���S�O���o�������Ƃ͌����܂ł��Ȃ��i���łɊӏ܂������Ȃ�Ӗ������킩��ł��傤���ǁj�B �i�Q�O�Q�T�D�T�D�Q�U�D�L�j �i�n�h�j�`�@���Ƌ��C�̃o�����[�i JOIKA �i�Q�O�Q�R�N�A�p=�j���[�W�[�����h�A�����F�Óc�R�I�q�j  �@�{���V���C�E�o���G�c�ւ̓��c�ڎw���ĒP�g���X�N���ɓn�����\��̕č��l�o�����[�i�́A�ߍ��ȕ����Ƃ�邹�Ȃ����܂̋L�^�B �@�q���C���̃W���C�i�^���A�E���C�_�[�j���T�O�O�O�l�ɂP�l�̓�ւ�˔j���A�������c���������܂ł̑O�������́A�ǂ����������T�^�I�ȃX�|���h���}���B�������̂���G�s�\�[�h�������̂ő喞���Ƃ܂ł͌����Ȃ����A���o�̃|�C���g�͉��������Ă���̂ŁA�\�����i�_�͏o���邾�낤�B �@����Ȃ����ɗ��₩�ȃ��C�o���A�����I�ȋ��t�ɗ��K�����m�̑��̈������荇���A�O��̌l���K������A�g�D�V���[�Y�Ɂi��Ԃ̉�e�Ȃ�ʁj���ꂽ�K���X���d���܂��V�[��������B�A�E�F�C�Ő키�ؚ��ȃq���C�������A����Ȃ����V�A��ŋ��t�Ɂu�`�����X������Ɓv���k�����郁���^���̋����������Ă���B �@���t���H���R���i�n���߂̃��C�N�ɓO�����_�C�A���E�N���[�K�[�j�̎��B���܂��V�r����B�u�ɂ݂�������̂���тƎv���v�Ƃ��A�u�l���ł�����x�̃`�����X�����ݎ��B���̂��߂̓w�͂��ł��Ȃ��҂͋���v�Ƃ��A�����̐l�����o���炷��Ɩ��炩�Ƀ����n�����ꂷ��Ȃ��ǁA�X�|������̐��E�ςɂ͌������Ȃ��v�f�ł͂���ȁB �@���������܂��s���Ă��Ȃ��Ƃ��ɂ́A�Ƒ�����̓d�b�ɂ��o�悤�Ƃ��Ȃ��W���C�B�}�}�ɋ������ċC�𐰂点��������Ȃ����Ǝv���l�����邾�낤���A���ɂ͋����ł���S�̓����������B �@���Ȃ݂ɑ����̃o���G�h���}�ł́A�ܐ悩��o������̂��āA�X�g�[���[��̂��Ȃ�傫�ȁu�����v�ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv�����A�{��ł͂قƂ�ǃE�H�[�~���O�A�b�v�i�K���猌�܂݂ꂾ�����B���b�����Ƃɂ����f�悾�Ƃ������A�{���̃o���G�w�Z�ł́A���ꂪ����Ȃ낤���H �@���Ăĉ����āA�u�č��l�͖{�̗p����Ȃ��v�Ƃ����{���V���C�̕s�������A�W���C�ɂ͏d���̂�������B�{��̒�ԂƈႤ������T���Ƃ���Ȃ�A�܂��ɂ������B�l�^�𖾂����A�W���C�̓��V�A���Ђ�ړ��Ăɒj���_���T�[�ƌ������A�s�̗p���������ʂ��Ђ�����Ԃ��B�����A������Ƃ���̐������͂������ƞB���ɕ`���āA���͕č��l�ł��邱�ƂȂ̂��A�P�Ɏ��͕s���Ȃ̂����킩��Ȃ����Ă����������A����Ƃ��Ă̐[�݂͏o����������Ȃ��ˁB �@�㔼�͈�]���ē]���ƍċN�̕���B���ꂾ����J���ă{���V���C�̒c���ɂȂ����̂ɁA�č��l������i���H�j�Q���̖��������炦�Ȃ��B�u�\�����x�肽���Ȃ�p�g������T���v���āA�h�K��[�g���b�N�̎���̗x��q����H �@�W���C�͌��ǁA���ꂪ�ł����Ƀ{���V���C����ǂ��A�v�������������āA���|���ɂ܂œ]���B�����ɂ���Ɣg�p����ȃp�[�g�����A���͂���قǖʔ��݂͂Ȃ��B���b������d���Ȃ��낤���ǂˁB �@�X�g�[���[�ɍĂуG���W����������̂́A�q���C���̑O�Ƀ��H���R�����ēo�ꂵ�Ă��炾�B���K���̎���ɂ͓z��Ɛ_�l�̂悤�ȊW�������Q�l�����A�W���C���{���V���C���狎�������A���͂₠��Ӗ��A���u�����Ǝ҂̂悤�ȊW�ɕς���Ă���B �@�Ō�ɐV���ȃR���N�[���ɒ��W���C�́A���NJo��ŗx�邩�A�������邩�̕����ꓹ�ɁB��҂�I�ꍇ�̖}�f�Ȗ������A�q���C���́i��z�Ȃ�ʁj��z�V�[���Ō������W�F�[���Y�E�l�C�s�A�E���o�[�g�\���ē̉��o������B �u�l���ł�����x�̃`�����X�v�����ݎ�邽�߂Ȃ炷�ׂĂ��]���ɂ���̂��A�A�X���[�g��\���҂̐��i�����j�B�q���C���̃��f���ƂȂ����W���C�E�E�[�}�b�N�i�Ō�Ɏʐ^���}�������j�Ƃ悭�����^���A�E���C�_�[���A�Ō�̃X�e�[�W�ł�����������ɑ̌����Č������B �@���Ȃ݂Ƀo���G�V�[���̐��ւ́A�G���h�N���W�b�g���������A�E�[�}�b�N���g�����߂Ă����悤�ł���B �i�Q�O�Q�T�D�T�D�P�S�D�L�j �ْ[�҂̉� HERETIC �i�Q�O�Q�S�N�A��=���A�����F���Y���ށj  �@�����̍ە������˂Ɗ뜜���Ȃ���ςɍs�������A�\�z�͗ǂ����ɗ���ꂽ�B �@�{��i�ċցj���n�܂�O�̏@���ⓚ���炵�āA������������@���S�ʂɓ��ɊS�̂Ȃ��ϋq�ł������Ȃ��������ރX���[�Y�Ȍ����B�w�^�ȉf���ƂɎB�点����A�o�������狏���肵���Ⴂ�����ȓ��e�ł����ǂˁB �@�A���Ɋm�F���Ă݂���A�R���r�Ŋē߂��X�R�b�g�E�x�b�N���u���C�A���E�E�b�Y�́A�w�N���C�G�b�g�E�v���C�X�x�̌��āE�r�{�ɉ����āA�w�U�T�x�̃��K�z���������Ă����̂������B����A�m���ɓ�����A�T�X�y���X���ƃL�����N�^�[���`�̗��ʂŁA���ɂ悭�ł�����i��������B �@�����������̕z���ɂ������ރV�X�^�[�E�p�N�X�g���ƃV�X�^�[�E�o�[���Y�́A�ڂ��������𐿋����Ă����j���[�h�̉Ƃ�K�˂邪�A���������ւɌ����������A�g�ѓd�b�̓d�g���Ւf����Ă��āE�E�E�B �@�o�����̖ⓚ�ɂ͔������������I�ȑ��ʂ����邪�A���������ϋq������ړ�����ׂ��Ώۂ��M�k�̏��q�����Ȃ̂�����A����ړI�̉f��łȂ����Ƃ͖��炩���B�b���i�ނɘA��Ă킩���Ă���̂́A�q���[�E�O�����g�̉����鈫�ʂ��A�@���S�ʂɑ��ċ^�������m�Ȃ̂��Ƃ������ƁB�ނ����B�����C�J�ꂽ���_�͂Ƃ������Ƃ��āA���̘_���Ɛ�N�ɂ͈��̐����͂�����B �@���͕|����Ȃ̂œr���œo�ꂷ��u�a���ҁv�̊炪�����Ȃ��������A�{��͏��R���鋰�|�f��Ƃ������A�Q�l�̃����������q�i�\�t�B�[�E�T�b�`���[�ƃN���G�E�C�[�X�g�j�̃T�o�C�o���E�X�����[�Ƃ��Ă̐F�ʂ��Z���B �@���ƂɁA����܂Ŋċւ�_�����d�|����������A�g�̓I�\�͂ɑi���邱�Ƃ̂Ȃ��������[�h���A���߂Ă��̈�����z����u�Ԃ̓��˂��A�����ĉ��o��ҏW�̐�ɂ͑���ۂށB �@�ēR���r�͂܂��A���Z�����ɂ��܂������B�������̏�����i���Ɏ��]�Ԃ̗֗��ߏ��j�̎g�����ɂ͐�����������A���鍇�����t�̎g�����ɂ͎v�킸�u�u���{�[�I�v�ƁB �@���Ȃ݂Ɋċւ����Q�l�̏��q�����A�V�X�^�[�E�o�[���Y�̓{�[�C�b�V���Ŏ��M�̂���^�C�v�A�V�X�^�[�E�p�N�X�g���̓K�[���[�ł��܂苭�C�ɏo���Ȃ��^�C�v�B�����A�ǂ��炪�������т�̂ł��傤���E�E�E�ƁA�����̐l�ɂȂ��Ȃ����o���Ă����܂��傤���i��������ʂ̂𖾂����Ă��܂������ƂɂȂ��Đ\����Ȃ����A�������������Ō��Ă��Ȃ��Ȃ��ʔ�����삾�B���Ȃ݂ɃN���W�b�g���̓o�[���Y���̃T�b�`���[����j�B �i�Q�O�Q�T�D�T�D�V�D�L�j �A���W�F���g������ THE MINISTRY OF UNGENTLEMANLY WARFARE �i�Q�O�Q�S�N�A��=�p=�g���R�A�����F�q��Վq�j  �@���܂Ɂu���݁v���x���̍�i�����邯��ǁA�n�}��߂��ۂ��ʔ����K�C�E���b�`�[��i�ɂ����āA����͖��炩�Ɂu������v�̕��ށB��f�ِ������X����ڂ������̂����������Ȃ��B �@�j���Ɋ�Â��p�R��̋ɔ�����A�C�A���E�t���~���O�Ȃǂ��g���₩���h�ɂ��ĉf���������_�ł́w�I�y���[�V�����E�~���X�~�[�g�x�Ɠ��H�B�������e�C�X�g�Ɋւ��Ắw�C���O�����A�X�E�o�X�^�[�Y�x�̕����������Ղ�悹�܂����Ƃ����ɉ��삾�B �@�܂����M�����ɂ����Ȃ��̂́A�����̏��Z���Ŏ剉�����w�����[�E�J�r���̃J�b�R�悳�I �@���ł��I�[�v�j���O�̗m���V�[���̎��ɗ���A�����̌Ăяo�����ČR�Y�����݂����ȂƂ��납��A�s����Ă������́i�܂�A���n��Ō����A�ނ�����̗���̒��ɏ��߂ēo�ꂷ�鎞�́j�V�[�����������B �@�����Ⴍ����̔�����Ђ��̕��e�A�]���Ƃ͖����̛Z�тȂ������A����ł��ď_�炩�Ȑ����A�m�I�ȃL���O�Y�E�C���O���b�V���B�Ȃ����A�u���܂ł������Ă��������v������Ƃ���A�{��̃J�r���̐����܂��ɂ��ꂾ�B �@�J�r���͂���܂ŃX�[�p�[�}���i�@�j��w�A�[�K�C���x�̕q�r�X�p�C�i�A�j�Ȃ������Ă�������ǁA����������܂�l�Ԗ������������Ȃ����������B�J�r���̑̋��f�̊炾�������Ă�����A�v���f���[�T�[��ē�����������������U�肽���Ȃ�̂������͂Ȃ��C�����Ȃ����Ȃ��B  �@���b�`�[���g�A�Q�O�P�T�N�́w�R�[�h�l�[�� U.N.C.L.E.�x�ł́A�J�r���ɂ���قǖʔ��݂̂Ȃ��i�|���I���E�\�����i�B�j�����������Ă����悤�ɋL�����Ă��邪�A���̂P�O�N�̊Ԃ̂ǂ����Ō������ς������ł��傤�ˁB�����Ȃł����蔯���点���肹���ɁA���[���A�Ɛl�Ԗ��̂���L������^����A�J�r�������ɖ��͓I�ɂȂ邱�Ƃ������B �@�P�ʂ������h�C�c�R�̒[�����o�^�o�^�E���܂���i�����Ӗ��ł́j�I�o�J�f��̒��ɂ����āA�J�r���������x�ꂽ�G�����u�����v�Ƃ��������Ō������Ă��V�[�����ƂĂ������B �@�����i�Łu�`�[���̓��]�v���̕��m�ɂ��܂ЂƂ���̏ꂪ���Ȃ������͕̂�����Ȃ��������A���̕��A�X�E�F�[�f���o�g���Ƃ����������m���|��Ƀi�C�t�ɉ��ł�������̒��l�I�ȓ����Ŋϋq�̎��ڂ����炤�B �@�h�C�c�R���Z���̃e�B���E�V���o�C�K�[�́A�w�C���O�����A�X�`�x�̃N���X�g�t�E�o���c�ɕC�G�������ς��Ǝc�E�����������A�u�G�����苭���f��͖ʔ����v�̖@�����������B���ۂɃh�C�c�l�ł���V���o�C�K�[���N�p�����̂��������Ă���B �@�t�ɔނ��ė����郆�_���n�̏��X�p�C���ɁA���e�B�[�m�̃G�C�T�E�S���U���X���g���Ă����̂͂ǂ����Ǝv�������A�܂��A�������c�b�R��ł�����L�����Ȃ���ȁB �@�����Ă��̐l�A�r�W�l�X�E�[�}���𖼏���ăV���o�C�K�[�ɋ߂Â����̂ɁA�̎�⏗�D���Ȃ���Ƀp�[�e�B�[�̃X�e�[�W�ʼn̂����Ⴄ���A���̃p�[�e�B�[�ɃN���I�p�g���̉����ŏo�����Ă������̂ɁA�X�e�[�W��ł͂Ȃ������ʂ̃h���X�𒅂Ă�����ƁA���Ƀc�b�R�~�ǂ���͂�����ł�������́i�j�B �@�ޏ����̂��A���邢�Ȓ������̎��̕s���ȁu�}�b�N�E�U�E�i�C�t�v�ɁA�ߑs���E�s�Ȍ������������Ԃ��A�N���C�}�b�N�X�̓G�D���D�����J�b�g�o�b�N�Ō����Ă������o�͋ٔ����\���B �@����ɂ��Ă��A���W�O�N�������Ă���̂ɁA���܂��ɂ��������f�������Ă��܂��h�C�c�l���炢�B�܂��A���̂ւ�͒��ɂ��܂��ɔ����h���}�����ꂿ�Ⴄ�䂪�������l�Ȃ̂����B �i�Q�O�Q�T�D�S�D�Q�T�D�L�j �g�d�q�d �����z���� HERE �i�Q�O�Q�S�N�A�āA�����F�`�I�L�^���j  �@���o�[�g�E�[���L�X�ē̎�����B�č��̂���ꏊ���A��_�J�����Ŏ�����z���ĎB�葱���܂����Ƃ����̍قŒԂ����A�������̉Ƒ��̓_�`���B �@�������ł͋���������覐Ő�ł���Ƃ���܂ł����̂ڂ邪�A�u�����v�̎�|�����m�ɂȂ�̂́A��_�J�������u���ꂽ�Ƒz�肳���ʒu�ɁA�ꌬ�̉Ƃ����Ă��Ă���B�J�����ʒu����͂��̉Ƃ̋��Ԃ��Ƃ炦���A���O�ɂ͐A���n����̗��h�Ȃ����~���펞�����Ă���̂ŁA����ɉ����ċ��Z����Ƒ��⋏�Ԃ̉ƍ�����ς���Ă��A�J�������������ɂ��Ă��Ȃ����Ƃ����������B �@�t�Ɍ����J��������ւ�邱�Ƃ͂Ȃ��̂ŁA�A�b�v�̉悪�~������ʂł́A�o��l���̕����J�����̕��ɕ��݊���Ă���B�t���[���O�i�J�����̔w����܂ށj�ɂ��A���̉Ƃ̕ʂ̕��������݂���Ƃ����z�肾�B �@���̉Ƃ����Ă���O�̐�Z���̉Ƒ��Ȃǂ��o�Ă��邪�A���Ă�ꂽ���Ƃ̉ƂɏZ�ނ̂́i���̋L�����Ă���͈͂ł́j�S�̉Ƒ����B �i�P�j�����Ԃ��Ȃ���s�@�ɖ����̕v�ƁA�������₩�ɒ��߂�� �i�Q�j��O�̖L���Ȏ���̔����ƕv�w �i�R�j���ɂ��̉Ƃ��w�������v�w�i�|�[���E�x�^�j�[���P���[�E���C���[�j�ƁA�e���ɏZ�ݑ����钷�j�v�w�i�g���E�n���N�X�����r���E���C�g�j �i�S�j�قڌ���ɂȂ��Ă���Z�ݎn�߂����l��Ɓ@ �@���̂����i�Q�j�̕v�w�����͂����ƒ��ǂ��A�₪�Ĕ������F�߂��Ƃ��������ŏ��������Ɍ��������A���̉Ƒ��͏�ɍK�������ς��Ƃ͂������A����Ⴂ�⊋����ʗ��ɂ���������B���n����W�����u�����Ȃ���A�悭���P�O�S���̏�f���ԂŁA���̑��l�E���ʂȕ�����܂Ƃߏグ�����́B �@�Ƒ����ƂɉƋ��d�����i�̎�ނ��A�L�x�����ς��A����Ŏ���̗l�����_�Ԍ�����̂������[���B�d�b�@�̕ϑJ�Ȃǂ͂��̓T�^�ł��ˁB �@���̗����\����������P�̑��u�Ƃ��Ďg���Ă���̂��A�e����ɈÂ��e�𓊂����������s�a�B���Ƃ��i�P�j�ł̓C���t���G���U�A�i�S�j�ł͐V�^�R���i�Ől�����ʁB �@����Ɂi�S�j�ł́A�^�]�Ƌ�����藧�ĂƂ��������̏\��̑��q�ɁA�����Ȃ���A�������x���ɎԂ��~�߂�ꂽ�Ƃ��̐S�����A���ɓ���ׂ�����ċ������ނ�ł��ˁB�u�����ċt��킸�A�f���ɉ^�]�Ƌ����o����B�����̎��Ɍ������܂܁A�O���[�u�{�b�N�X����������ƎԌ������o�����B�ʂ�ۂɂ͏Ί�ŁA������˂��炦�v�B�����A�������Ȃ��Ɩⓚ���p�Ōx���ɎˎE���ꂩ�˂Ȃ�����ŁA������܂��L���Ӗ��ł́u�a���v�ƌ����邩������Ȃ��ˁB �@���Ȃ݂Ɏ������i�R�j�̉Ƒ������Ɍ�����ꂽ���Ƃ����i�w�t�H���X�g�E�K���v�x�ł̓G�C�Y���n���N�X�ƃ��C�g���������킯�����j����܂������ɂ�����̕a���ł���F�m�ǂ��B���̎���̗��s�a�Ƃ͈���āA�����ɐl�͎��ȂȂ����A������}�V���Ƃ����ƌ����Ă���Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B �@�`������u��_�J�����v�Ƃ������t���g���Ă�������ǁA���̃J���������ۂɂ͂Q�x�����B�P�x�ڂ̓I�[�v�j���O�̐��b�ԂŁA���̖ڂ̍��o�łȂ���A�J�����ʒu���������Ɖ��~�����悤�Ɍ������i�w�i���������ゾ����A�����[�g�����炢�����������͂��݂Â炢�̂�����ǁj�i�ł��A�����ŃJ���������Ӗ��͂Ȃ��悤�ɂ��v����̂ŁA�{���Ɏ��̍��o��������Ȃ��j�B �@�Q�x�ڂ̓G���f�B���O�ŁA������͂�����Ƃ����햾�����̉f���ɂȂ��Ă���B���Ԃ̒�_�f�����炢���Ȃ�P�W�O�x��]���A����܂Ō����ĉf�邱�Ƃ̂Ȃ������L�b�`���Ȃǂ����������Ǝv������A�J�����͂��̂܂܌�ނ��A�܂����������ʉ߁i�I�j�B����ɃN���[�����h���[���ɓ��ڂ��ꂽ���̂悤�ɍ����ɕ����オ��B����ƁA���̐��ɒP�Ƃő��݂��邩�̂悤�Ɍ����Ă������̕���̃Z�b�g�̂悤�ȉƂ̎��͂ɂ��A���͂т�����ƕ��݂����Ă���ł������Ƃ����炩�ɂȂ��ł��ˁB �@���̏u�ԁA�u�ˋ�̓���ȉƑ������v�̃G�s�\�[�h�W���������̉f�悪�A��C�ɂ����̕��Ր���тсA�u�������v�̕���ɓ]����̂��B������܂��m���Ƀ[���L�X�E�}�W�b�N�Ȃ̂��낤�ȁB �i�Q�O�Q�T�D�S�D�Q�R�D�L�j �~�b�L�[�P�V MICKEY17 �i�Q�O�Q�T�N�A�āA�����F����L�K�j  �@�\���҈ȊO�̎��O������ꂸ�ɉf����ӏ܂��邱�Ƃ������̂ŁA�u���̎�̂r�e���͌���ɂ��}��ɂ��Ȃ蓾���ˁv�Ɣ����뜜���Ȃ���ӏ܂ɗՂB �E�E�E�̂����A��l���̃R�s�[���o�ꂷ�邠����i�N���]���́u�N�v���I��鍠�j�ɂ́A�������O�҂��Ɗm�M�ł����B�����ăX�g�[���[�e�����O�����Q�ɂ��܂����́B �@�₪�ăG���h�N���W�b�g���o���Ƃ��ɁA���߂ă|���E�W���m��i�������ƒm��A�����A�������ɂ��܂��˂Ɣ[����������B �@����͉������Ȑ����ƕv�ȁi�}�[�N�E���t�@���ƃg�j�E�R���b�g�j�������鐯�ԈڏZ�D�B���t�@���͂����Ό������点�A���������̂��Ƃ��u�`���[�`�i�����ł́u���c�v�j�v�ƌĂԂ��A���̂��тɎ�芪������u�J���p�j�[�i��Ёj�v�ƒ��������B���āA����ɓ��������̃p���f�B�[�����B �@�����Ƃ��A��ʉ���̈ڏZ��]�҂͓��ɉ����̐M�҂Ƃ����킯�ł͂Ȃ�����������A�v�ȂƂ��ẮA���������I���O���Ă������Â���Ȃ̂�������Ȃ��B �@��l���̃~�b�L�[�i���o�[�g�E�p�e�B���\���j�́A�n���Ŏ؋����ɒǂ��A���̉F���D�ɃG�N�X�y���_�u���i�g���̂Đl�ԁj�Ƃ��Đ��肱�j�B���̂��߁A�F����Ԃ�ڏZ��̐��Łu�Y�z�̃J�i���A�v�̂悤�Ȏd�����������A���x������ł́A�u���v�����g�v�����B�{���n�܂�i�K�ł͂P�V��ڃ~�b�L�[�ɂȂ��Ă��邩��A���̃^�C�g���Ȃ�ł��ˁB �@�ƂȂ�A����͍L�`�́u�N���[�����r�e�v�ɕ��ނ����̂��낤���A���ɂ͂�����A�{��ł́u�I���W�i���ƃR�s�[�Ƃ̑����v���́u�l�Ԃ��ǂ��Ƃ��ẴN���[���̔߂��݁v���̂Ƃ������N�\�^�ʖڂȒ�ԃe�[�}�͓��܂�Ȃ��B �@�Ȃ��Ȃ�~�b�L�[���g���A�����������ʂ��Ɓi�y�уN���[�������J��Ԃ����Ɓj�����m�̏�ŁA�G�N�X�y���_�u���Ɏu�肵�Ă��邩��B���ہA�u�I���W�i���̃~�b�L�[�v�́A���ꂪ�����ɓ���͂邩�ȑO�̉�z�V�[���ŁA�{�l�[���̏�Ŏ���ł���B�X�g�[���[��́A���̏d�v�����^�����Ă��Ȃ��B �@�܂�ނ́A���\�̃X�g�[���[�̓����ɂ����Ďg���̂Ăł���݂̂Ȃ炸�A�f��̍\�����u��S�̕ǁv�̊O�����璭�߂��ꍇ�ɂ����Ă��g���̂ĂȂ̂ł���B �@�Q��ڈȍ~�̃~�b�L�[�������A�����L����A�C�f���e�B�e�B��������u�����v�������ɍĐ������̂�����ƁA�C���̂��߂Ɏ��ʂ��Ƃ���ɋ��������������Ȃ��B�P�W��ڂ��\��O�ɑ����a������������Ƃ������A�P�V��ڂ������u�����v�Ɓu�R�s�[�v�Ƃ̔ꐫ���l�ʂ��邪�A�|���E�W���m�́A�����͂�����Ɨ������Ⴄ�B �w�A�C�����h�x��w�킽���𗣂��Ȃ��Łx�Ƃ��������̃N���[�����ł́A���Ƃ��N���[���ł����Ă��I���W�i���̐l�ԓ��l�Ɏ��ʂ��Ƃ����ꂽ�茙�������肵�A���̂��Ƃ������ăh���}���n�܂��Ă����킯���B�Ƃ��낪�{��́A����Ƃ͐����̘H���������đI��ł���B����̊i���ɂ���Ƃ���A�u�l�̍s�����ɓ�����Ԃ̎R�v�B���̋t�]�̔��z���A�{���B�ꖳ��̃N���[���r�e���炵�߂Ă���̂ł��ˁB �@���ւ̎������n�i���猇��������ȃI�t�r�[�g�Ȏ�l����}��ɁA�|���E�W���m�́A�u���b�N���[���A���ڂ̕�����e���|�悭�]�����Ă����B���E�̃X�e�B�[�u���E���A������Ԃ��邭�Ĕڋ��ȃL�����ɐݒ肵�Ă���Ƃ�����A�ނ炵���Ă����̂ł͂Ȃ��������B �@�^�ʖڂ���蕿�̓��{�l�⒆���l�̊ē��č��f��̃��K�z����C���ꂽ��A���ʂ͓����l�ɖׂ�����U�����Ⴂ���������ǁB �@�~�b�L�[�ɗ��ޘe���R�l���A���Ȃ킿�F���D�̌x������̃i�I�~�E�A�b�L�[�A�Ǘ�����̃A�i�}���A�E�o���g�����C�i���Ƃ��璲�ׂ���w���̂��Ɓx�Ɏ剉���������`�̏��D�������j�A�Ȋw����̃��K�l�����̃p�b�c�B�E�t�F�����́A���傤�ǃX�p�C�X�K�[���Y�݂����Ɂu���L���^�C�v�̏��q����肻�낦�Ă���܂��B�ǂȂ��ł����C�ɓ���̎q��������܂���v�ƌ�������B �@���Ȃ݂ɂ��̂R�l�̉�����L�����́A�č��f��ł���ɂ�������炸�A�C�M���X�p����a��i����قǏ㗬�ł͂Ȃ����A����Ƃčʼn��w�ł��Ȃ��l�̂���j�Řb����ł��ˁB�A�b�L�[�ȊO�͉p���l�ł͂Ȃ��̂Ɂi�o���g�����C�̓��[�}�j�A���܂�A�t�F�����̓X�y�C�����܂�j�A������ʔ����I�����B�p�ꎩ�̂ɊS�̂�������́A���̋������y���ނ̂��ꋻ�B �@���̂����o���g�����C�ƃt�F�����̃L�����́A�~�b�L�[�ɑ��ē��Ɉ��ӂ������Ă��Ȃ��ɂ�������炸�A�G�N�X�y���_�u���ł���ނ̐l������ɂ͂܂��������ӂ�Ȃ��B���̂ւ�̃u���b�N�Ԃ肪�A���^�V�I�ɂ͈�ԃc�{�ł����B �i�Q�O�Q�T�D�S�D�P�T�D�L) ���c�I�� CONCLAVE �i�Q�O�Q�S�N�A��=�p�A�����F�n�ӋM�q�j  �@�����炢�̔N��ɂȂ�ƁA�l���ʼn��x�������̋��c�I���i�R���N���[�x�j�����Ă��Ă���킯�����A�����ʔ����Ǝv���̂͗��������̎��ނ��Ȃ��炵�����ƁB �@����䂦�Ɋe��������Ǝv���L���i�ҁi���@���j�ɏ���ɓ��[���A�ߔ��������l��������Ȃ��ƁA���Ƃ��i�P�j�ʼn��ʂ́u���ҁv���O�����Ƃ��i�Q�j��ʂQ�l�Ō��I���[�����邱�Ƃ��ł����A���������c�ʼn��X���[���J��Ԃ����ƂɂȂ�B �@�ŁA����Ȃ����ł�����l�X�Ȏv�f�Ŋe�l�̕[�������A���x�ڂ��ɂ͌���������̂�����A������܂��t�ɖʔ����Ǝv���B �@�{��͂���ȋ��c�I����`��������������Ƃ����A�A�J�f�~�[�܂̋r�F�܊l����i�B���ꂾ���ɁA��������ƍ\������Ă͂���̂����A�o��l���̑唼�������N�j���Ȃ̂ŁA�N���N���c������̂ɋ�J����B������������O�̃y�[�W�����Ԃ������̂����A�f��ł͖𖼂Ɖ��������҂���v�����邾���ł���ς��B�����̕��̗\�K�p�ɁA�����łЂƂ������Ă݂悤�B �@���C�t�E�t�@�C���Y����������l���́A�i�p���l���Ȃ̂��C�^���A�l���Ȃ̂����ǂ킩��Ȃ��������j�A���@���̒��ł͍ŏ�ʂ������炵���A�I���Ǘ��ψ����̂悤�Ȗ����B�������v�h�̃X�^�����[�E�g�D�b�`���������c�ɐ��������̂����A�g�D�b�`�͈ӊO�ɐl�]���Ȃ��A�ނ���t�@�C���Y���g�ɑ����̕[�������Ă��܂��i�O�q�̂Ƃ���̑I�����x������A�����������Ƃ��N����̂ł��ˁj�B �@�t�ɃZ���W�I�E�J�X�e���b�g�͎狌�h�ŁA���Ƃ����l���@���ɓ��I�̖ڂ����邱�Ƃɂ��s���ȗl�q�B�t�@�C���Y�ƃg�D�b�`�́A�J�X�e���b�g�ɂ�点����͂ƁA���قǐe�����͂Ȃ��W�����E���X�S�[�𐄂����Ƃ��邪�A�ŗL�͂̍��l���@���Ɠ��l�ɁA���X�S�[���܂��X�L�����_��������Ă��āE�E�E�B �@���E�҂����Đl�Ԃ�����A��S������Η~������B�g�D�b�`���t�@�C���Y���ŏ��́u���͋��c�ɂȂǂȂ�C�͂Ȃ��v�ƌ����Ă����̂ɁA���ǂ͖{�S���̂������Ă����̂����낵�����A�����������B�u���@���Ȃ�N���������̋��c���i���c�A�C��ɖ���閼�O�j�����߂Ă���v�Ƃ����g�D�b�`�̃Z���t���A��������Ȃ�Ǝv�킹��B �@�G�h���[�h�E�x���K�[�ḗA�����ꂽ�o�`�J���{�ł�����ȑ����h�H���A���Â��A�d�A���̖\����������������ƌ����A�l�Ԃ̖{�������Ԃ�o���B�V�X�e�B�i��q���Ȃǂ����܂�{���炵�������Ă��Ȃ������̂͏����ӊO���������A�ߑ��⏬����Ȃǂւ̂������͐����Ɍ���ꂽ�B �@�ŏI�ՂɃX�g�[���[�ɕ��肱�܂��Q���̔��e�i���ۂ̂��̂Ɣ�g�I�Ȃ��́j�́A�����������B�_���E�u���E������́w�V�g�ƈ����x�Ɠ��l�A�a���̂悤�ɋ��c�I���𐧂����o��l�����A���͍ő�̔閧������Ă���̂�����A�G���h�}�[�N�܂Ŗڂ������Ȃ��B �@�������������̐��@�����ɁA�����̔o�D�J�����X�E�f�B�G�X���N�p�����̂́A���̐��@�������̌˘f�����ϋq�ɂ�����킹�悤�Ƃ����ē�L���X�e�B���O�S���҂̐[�d�������B �@�ނ��u�X�C�X�̃N���j�b�N�v��\�Ă����Ƃ��������i�Ƃ������~�X���[�h�j���d���܂�Ă����̂ŁA���͂Ă�����L���X�g���ł͑�߂Ƃ����u����v������ł���̂��ȂƎv���Ȃ���ςĂ������A���`�ށA���ۂ́u�������v�ł������B �@�Ō�ɁA�R���N���[�x�̊J�n�ɍۂ��āA�t�@�C���Y�����@���ꓯ�ɏq�ׂ��������Љ�����B�u�m�M���邱�Ƃ͊댯�Ȃ��Ƃł���A��ɋ^�O�����ׂ����v �@�ƑP�I�Ȋm�M�ɓ˂��������ꂽ�v�[�`����g�����v�A�l�^�j���t�Ƃ������N�Y�ǂ��ɁA�����ĉ{�������҂����������̃N�Y�ɂ����Ɗm�M�������Ă��܂������Ɍ����ɁA�u�����̍l����s���ɂ����Ƌ^�O�����Ă�v�ƁA���͐S���猾��������B �@�A�[�����B �i�Q�O�Q�T�D�S�D�R�D�L) �`�m�n�q�` �A�m�[�� ANORA �i�Q�O�Q�S�N�A�āA�����F�g����ގq�j  �@�A�J�f�~�[�������E�H�b�`���O���A����ɂ��̌�ɖ{����ӏ܂��āA���Â������������B�J���k���ۉf��Ղ̃p�����h�[�����A�A�J�f�~�[�܂̂T�����܂��A�ЂƂ��ɃV���[���E�x�C�J�[�ē̐l���̎����Ȃ�Ȃ����A�ނ̐l�D���̂��鐫�i�ƁA�f��|�p�ւ̏�M���A���͂̐R������A�J�f�~�[�����˂��������Ẳ�����������Ȃ����ƁB �@���ꂷ�Ȃ킿�A��i���̂ւ̏̎^�ł́A�K�������Ȃ��B �@��f���ԂP�R�X���̂��̍�i�A�ŏ��̐��\���Ԃ����q���C���̃A�j�[�i�A�J�f�~�[�剉���D��܂̃}�C�L�[�E�}�f�B�\���j���ʂ̗`�ɏ��ߒ���`�����V���f�����X�g�[���[�����A���̌�͈�т��ĕ�����Ɍ��������������s�R�̂悤�ȗl����悷���ˁB �i�P�j��������̌䑂�i�C���@���́A�e��㌩�l�ɔ�����āA�S���I�ɂ������I�ɂ��g���Y���������B�܂�ō��̂Ȃ��j�������B �i�Q�j���̃C���@����T���o�����߂ɁA�A�j�[�̓C���@���̌㌩�l�Ƃ��̎艺�ɒ�������������܂킳���B�C���@��������������A�����Ɍ��������̎葱�����J�n�����̂�m��Ȃ��炾�B �i�R�j���̉ߒ��ŗV�ђ��ԂƂ���������F���M���Ō���Ă͂��Ȃ����Ƃ�˂�������B �i�S�j���V�A�����肱��ł����Ƃɂ͍��Y�ړ��ẴN�Y����������A�܂�Ŏ��������Ȃ��B �@����ȋ�ŁA�i�l�^�𖾂����Đ\����Ȃ����j��t�]���ǂ�ł�Ԃ����N����Ȃ��B�ӊO�ȏ����l������Ȃ��B �@�������l�_��Ŗ����J���Ȃ���A�w�v���e�B�E�E�[�}���x�̃W�����A�E���o�[�c���n�b�s�[�G���h����������̂Ƃ͈Ⴂ�A�A�j�[�͎��͂ł͍R�����Ƃ̂ł��Ȃ������ɂ��邸��Ɖ���������āA�Ō�Ɂi�����ȊO�́j���ׂĂ��������ƂɂȂ�B���̃t���X�g���[�V�����͂������肩�B �@�s�҂̔߈��������Ɋ��Y�������Ȃ��A����͕���Ȃ̂��B �@�����Ńx�C�J�[�ē����o�Ɏ��s���Ă����̂ł͂Ȃ����Ƌ^���� ����|�C���g�ɐG��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@�A�j�[��A���c�̒��̉����[�C�S�[���i�A�J�f�~�[�����j�D�܌��̃��[���[�E�{���\�t�j���A�A�j�[�͎�噂̂悤�Ɋ������̂����A�f��������ꂽ�ϋq�̖ڂɂ́A�ӊO�ɂ����z�ł���C�S�[���ɁA�q���C��������ɂق�����Ă������ăp�^�[�������������Ȃ̂ł���B �@�Ƃ��낪�ϋq�̗\�z�ɔ����āA���̌��������̃p�^�[�����A�x�C�J�[�͈���ɂ��ǂ낤�Ƃ͂��Ȃ��B�ɂ�������炸�A�Ō�̍Ō�ɂȂ��āA���˂ƌ����ɂ͂��܂�ɓ��˂ȍs�����A�j�[�Ɏ�点����̂�����A�ςĂ��邱����͂ǂ����߂�����悢���̂��˘f���Ă��܂��B�ʂ����Ă���̓x�C�J�[�̃~�X�Ȃ̂��A����Ƃ��m�M�ƂȂ̂��H �@�����܂ł̂��V���Ă����܂��ł��Ă����Ȃ�A�����悤�ɂ��ׂĂ����������Ɍ������w�}�b�`�X�e�B�b�N�E�����x�̃j�R���X�E�P�C�W���A�Ō�̍Ō�ɂ������Ȋ�]����ɂ��������Ƃ������ƃJ�^���V�X�����킦���͂��Ȃ��ǂˁE�E�E�B �i�Q�O�Q�T�D�R�D�Q�O�D�L�j �����Ȃ��ҁ^A COMPLETE UNKNOWN A COMPLETE UNKNOWN �i�Q�O�Q�S�N�A�āA�����F�Γc�q�j  �@�{�u�E�f�B�����̓`�L�f�悪���삳��邼�ƕ����āA�u�������v�ƐF�߂��������l���A�i�{���A�����J�Ȃ炢���m�炸�j���̓��{�ɂǂꂭ�炢����̂��H �@���łɊҗ���߂������ɂƂ��Ă����A�f�B�����́u���w���̍��ɒ������K���́w�w���X�̋i���X�x�ɂ������Ɩ��O���o�Ă����l�v�ł����Ȃ��B�K�����̂������炢�����炻��܂łɑ�q�b�g�Ȃ͏o�Ă����̂��낤���A�q�ǂ��͗m�y�Ȃ����Ȃ����A���̌�͂����A�������풮�����y�V�[���Ƀf�B�����̋Ȃ����ꂱ��ł��邱�Ƃ͂Ȃ��Ȃ����B�܂��āA�����ƎႢ�w�ɂ����Ă���B �@����Ȃ킯������A���͂��́w�����Ȃ��ҁx���A�`�L�f��ł����y�f��ł��Ȃ��A�f�B����������O�p�W�̉f��Ƃ��Ċӏ܂����Ă�������B �@�e�B���V�[�E�V��������������f�B�����́A�l�C�̎�̃W���[���E�o�G�Y�i���j�J�E�o���o���j�Ɏ䂩������A��ʐl�V�����B�i�G���E�t�@�j���O�j�Ƃ�������킷�B �@�˔\�Ɍb�܂�A�������ł���������o���Ă���o�G�Y�́A�����́u���킢�����v�ɂȂ����Ȃǂ��炳��Ȃ��A��������}�C�y�[�X���т��f�B�����Ǝ��ɏՓ˂���B�����Č����ɂ���ẮA�ނ̍˔\����������B����ł��f�B�����́i�|�p�ʂƃZ�b�N�X�ʂ̗����́j�h�������߂āA�o�G�Y�Ƃ̕t�������ꂸ�̊W�𐴎Z���悤�Ƃ͂��Ȃ��B �@�˔\�̂���j�́A�˔\�̂��鏗�Ɏ䂩�����́i�t���܂��^�Ȃ�j�B���̍˔\�������Ɠ�������̂��̂ł���Ȃ珮�X�Ȃ�ł��ˁB �@����̃V�����B�͂���قNj���ȉ�i���j�������Ă��Ȃ�����A���炬�����߂����Ƃ��A�f�B�����͂������ɍs���킯���B�h������邩�A���炬����邩�A������Ēj���W�̉i���̃e�[�}�ȂႠ��܂����B �@�[���猩��Γs���̂������ɂ���Ă��銴���̃V�����B�����A������Ă��Ȃ��킯�ł��Ȃ������₱�����B �@���܂��܂��̉f��ł́\�\�����炭�j���̒ʂ�Ȃ낤���ǁ\�\�V�����B���w�T�o�C�r���O�E�s�J�\�x(1996)�̃t�����X���[�Y�E�W���[�̂悤�ɁA�����ƌ��ʂ��铹��I��ł���B�Ƃ͂������̒��ɂ́i�����ł���t�B�N�V�����ł���j�V�����B�E�^�C�v�̏������Ō�̏��҂ƂȂ镨�ꂾ���Ă��ӂ�Ă�B�������A�����ɋ؏����͂Ȃ��B �@����ȂR�l�̊W�̒��ŁA�l�I�Ɉ�ԍD���������̂́A�܂��^�C�g���ʂ�́g�����Ȃ��ҁh�������Ⴋ�f�B�������A���߂ăo�G�Y�Əo��V�[�����ȁB �@�o�������܂����N���u�Ńo�G�Y�̋Ȃɒ�������Ă����f�B�����́A����ւ��ɃX�e�[�W�ɏオ��ƁA�O�U��̂l�b�̒��ŁA�u�������W���[���E�o�G�Y�ɂ�����x������B����A�Ȃ����������ĈӖ������ǂˁv�Ȃ�āA�Ƃ����炩�������Ƃ��v�킸�������Ă��܂��킯�ł���B �@����ƁA�M�^�[�P�[�X�������ēX����o�čs�����Ƃ��Ă����o�G�Y���A�u����A�������Ȏq���o�Ă��ˁB��������������P�Ȓ����Ă����Ă�낤������v���Ċ����ŁA�X�e�[�W�̋߂��Ɉ����Ԃ��Ă���i�����ăf�B�����̍˔\��m��j�B �@��͂�l�ԁA�u���̐l�A�f�G���ȁv�Ǝv������A�Ƃ肠�������ɏo���Ȃ�A�_�����ŃA�v���[�`���Ă݂��肷�邱�Ƃ��̗v�Ȃ�ł��ˁB �@���Ȃ݂ɎB�e�̃t�F�h���E�p�p�}�C�P���́A�����������s���̂���X���ł̂���ȓ������A�œ_�����̒Z�������Y�ŎB���Ă���B����ƃo�G�Y���o���̕��ɉ�������ƁA���̎p�������Ə������Ȃ�A�t�Ƀf�B�����̕��i���q�Ȃ̎������̕��j�ɖ߂��Ă���ƁA�����Ƒ傫�������Ă���d�g�݂Ȃ�ł��ˁB���j�J�E�o���o���̂�������Ƃ��������̕�������܂��āA���Ɉ�ۓI�ȃV�[���ɂȂ��Ă����B �i�Q�O�Q�T�D�R�D�Q�O�D�L�j �Q�O�Q�T�N�I�X�J�[�i�C�g�E�E�H�b�`���O�I  �@���N�̃A�J�f�~�[�����͌��n���ԂR���Q���̖�ɊJ�Â��ꂽ���A��N���C�u�i�����ʖ�Łj�Ƙ^��i�����Łj�ŃI���G�A���Ă����v�n�v�n�v���A���N�͂����Ȃ鎖��A�P���x��Ŏ����ł����A������I�����C���z�M�݂̂Œ���̐��ɁB �@����Ƀ��C�u���p�͂m�g�j�q���ōs��ꂽ�悤�����ǁA�����ʖ�łł͕��������̂ł͂Ȃ����Ƃ͂킩�肫���Ă���̂ŁA��ނȂ������܂ő҂��A���܂��ɋM�d�ȃf�[�^�ʐM�ʂ��R�f�a�����₵�āA�v�n�v�n�v�I���f�}���h�Ŋӏ܂���d�V�ƂȂ����B ���ߔN�ł͏o�F�̎����� �@�Q�O�Q�R�N�Ɏ��{���ꂽ�n���E�b�h�̋r�{�Ƒg���Ɣo�D�g���̃X�g�̂�����ŁA�Q�O�Q�S�N�̊O���f��V�[���͔����u���Ƃ�v�̏�ԂɁB �@���R�A����̃m�~�l�[�g��i�ɂ́A�ǂ��炩�Ƃ����ƃ��C���X�g���[������O�ꂽ���i��č��ȊO�̐���f�悪����������A�o�D�܂̃m�~�j�[�������a�߂̖��҂��č��l���ڂɂ����B �@����Ȃ��Ƃ������č��N�̃A�J�f�~�[�����ɂ͂���قǑ傫�Ȋ��҂�����Ă��Ȃ������̂�����ǁA���₢��A�Ȃ��Ȃ��ǂ����āA�ߔN�ł͂��Ȃ�f�L�̗ǂ����ނ������̂ł͂Ȃ����B �@���̈���ƂȂ����̂͊ԈႢ�Ȃ��R�i���E�I�u���C�G���̎i��Ԃ�B�W���[�N�������Ď�v�ȃm�~�l�[�g��i����҂���ۂ悭�Љ���I�[�v�j���O�̃g�[�N����A�������u�����͂ł���v�Ǝv�킹���B �@�{�u�E�f�B�����̓`�L�f��ł���w�����Ȃ��ҁx�ɐG�ꂽ������ł́A�u����f�B�����͗��Ă��Ȃ����ǁA���Ɍ������Ă��킯���Ⴀ��܂���v�ƌ����āA�f�B�������Q�O�P�U�N�̃m�[�x�����w����ɉ��̔����������A���E�����f���������Ƃ�������炩���B �@�������Ǝv���A�k�`�x�O�̑�K�͂ȎR�Ύ��̌�ŁA���������ؔ��Ȏ��T���Â����Ƃ̈Ӌ`���A�N�����i���Ȃ��Ƃ��A�Ă��o���ꂽ�l�X�ȊO�̒N�����j�[���ł��錾�t�œ`���Ă݂����B �@�R���f�B�A�����i��҂����Ă���Ƃ������̃I�u���C�G���A�I�X�J�[�����̃z�X�g�̂悤�ȑ���͏��߂Ă������悤�����i���T�̒��Ղɂ́A���̓_���i���[�^�[�Ƀc�b�R�܂��M���O������j�A���̌�̒�����ł��A�C��肷���邱�Ƃ��A�t�ɕi�ʂȂ����Ƃ��Ȃ��A���Ȃ���������Ȃ��Ă����Ǝv���B �@�������A�ނ̂��߂ɃW���[�N���������X�s�[�`���C�^�[�����̗L�\������藎�Ƃ��Ȃ��B���̓_�Ɋւ��Ă��A���N�͗�N�ȏ�̃��x���������Ǝv���B ����v����́w�`�m�n�q�` �A�m�[���x���Ȋ��� �@�O�q�̂Ƃ���n���ȍ�i����̂ƂȂ�������̒��ŁA���n�]���͂邩�ɒ�������i���������̂��w�`�m�n�q�` �A�m�[���x�������B �@�U����Ńm�~�l�[�g���ꂽ�����A��i�A�ēA�剉���D�A�r�{�A�ҏW�̎�v�T����𐧔e�B�J���k���ۉf��Ղ̃p�����h�[����i�Ƃ͂����A�O����̃S�[���f���O���[�u�܂ł͖�������������A�����ɖ{�삪�A�J�f�~�[����̉���ɓˏo���Ĉ�����Ă����̂����킩��B �@���̍�i�A���͓��{�ł��܂��ɐ�T��������J����Ă���̂����A�\���҂₠�炷�������Ă�����قǖʔ������ł͂Ȃ����A���҂͑S�����������A�V���[���E�x�C�J�[�ē��̑O��w�t�����_�E�v���W�F�N�g�x�ɂ͓��Ɋ������Ȃ��������ŁA���^�V�I�ɂ̓p�X���悤���Ǝv���Ă����B�����ǁA���̎�܌��ʂ�������ꂽ��A���������f��قɑ���Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ��ˁB �@�x�C�J�[�ē͋r�{�A�ҏW�A��������炱�Ȃ��Ă����̂ŁA�s���S��A�d��Ŏ�܃X�s�[�`���s���Ă���B�����āA���̂��тɐl�D���̂���i�C�X�K�C�Ԃ�������Ă��ꂽ�B�ҏW�܂̃X�s�[�`�Łu�g�ēh���_���ɂ����������̍�i���A�l���ҏW�ŋ~������v�ƌ������Ƃ��ɂ��킹�����A�����������̂͊ē܂̃X�s�[�`���B �u�l��͊F�A�f��قʼnf�悪�D���ɂȂ����B�݂�Ȃʼnf����ς�̂́A����ł͖��킦�Ȃ��f���炵�������̌��ł���A���E�̕��f�������鍡�����d�v���B�f��ق͋�킵�Ă���B�x����͉̂�X���B���Ƃ����Ȃ��ƕ����̈ꕔ��������B�z����Ђ͉�����������J����ɍl���Ăق����v �@����ȃX�s�[�`������āA�n���E�b�h�̏Z�l���ӋC�Ɋ������ɂ����悤���B�x�C�J�[�ēA�f��l�Ƃ��Ă݂̂Ȃ炸�A�R�~���j�P�[�^�[�Ƃ��Ă��f���炵���B����Ȕނ̐l����l�������A�J�f�~�[����Ɉ�����Ă��邩�炱���A���̖�͎��Ȃ�ʁw�A�m�[���x�Ղ�ɂȂ����̂�������Ȃ��ˁB �@�����A�f���f��ق̏����͊y�ςł��Ȃ���������Ȃ��ȁB���̖���i��̃I�u���C�G�����A�b�l�����Ɂu��X�V�ҁg�R���e���c�h�����𑱂��܂��v�ƃ{�P��ꖋ���������B�m�~�l�[�g��i�ɂ��z�M��i�������Ă���B �@����̐V�����ʂŁA�u�����̎�҂����͉f��قłQ���Ԃ����ƍ����Ă���̂���ɂɊ�����悤�ɂȂ��Ă���v�Ƃ����L����ǂƂ��ɂ́A�����f��t�@���̂P�l�Ƃ��ē���������B ���o�D����͂��u���߁v�� �w���A���E�y�C���`�S�̗��`�x�ʼn��n�]�ǂ���ɏ����j�D�܂���܂����L�[�����E�J���L���́A�Ȃւ̊��ӂ̃X�s�[�`�ŏ킹���B�u�P�N�O�A�w�G�~�[�܂���܂�����R�l�ڂ̎q�ǂ����~�����ȁx�ƍȂɌ�������A�Ȃ͎�܂���Ƃ͎v���Ă��Ȃ������悤�ŁA�w������x�ƈ����������������B���̌�Ɂw���͂S�l�~�����x�ƌ�������A�Ȃ́i�����f�����Łj�w�I�X�J�[���������ˁx�ƌ��������ǁE�E�E�i�ƌ����āA��ɂ����I�X�J�[��������j�v �@���̃X�s�[�`���āA�����̒��ՂɁA�v�Ƌ��ɒZ�Ҏ��ʉf��܂����������A�u���̎�܂𗝗R�Ɏq�ǂ��͍��܂��ǂˁv�ƌ����āA��������ʂ��B �@�������D�܂́w�G�~���A�E�y���X�x���]�[�C�E�T���_�i�ŁA������O���킩��\�z���ꂽ�Ƃ���B�o�D�S����̎�҂̒��ŗB��̗L�F�l�킾�����ޏ��́A���܂ɂނ��тA�u�c��͂P�X�U�P�N�ɕč��ɗ����B���͌ւ荂���ږ��̎q�v�ƁA�h�~�j�J�n�Ƃ��Ă̏��̎�܂���сA�u���[�`���X�E�O���V�A�X�v�ƃX�y�C����ŃX�s�[�`����߂��������B �@�剉���D�܂͍ŏI�Ղɐ����r�ꂽ�w�A�m�[���x�����̒��A������}�C�L�[�E�}�f�B�\������܁B�����A����܂Ŏ�ܗ��͂��납�A�o���삷��قƂ�ǂȂ������}�f�B�\���́A�I�X�J�[���]���肱��ł���Ƃ͗\�z�����i�O����ł́w�T�u�X�^���X�x�̃f�~�E���[�A���D���������j�A�܂Ƃ܂����X�s�[�`���p�ӂ��Ă��Ȃ������͗l���B �@�剉�j�D�܂��G�C�h���A���E�u���f�B�i�w�u���[�^���X�g�x�j�́A�Q�O�O�Q�N�́w���̃s�A�j�X�g�x�ɑ����A�Q�x�ڂ̎�܁B�X�s�[�`�̎n�܂�͊����}�f�Ȃ��̂��������A�ǂ��o���~���[�W�b�N���肾������ɂȂ��āA����������Ɏ~�߂����A���b�Z�[�W���̂��邱�Ƃ����n�߂��B �u�g���E�}��푈�A�}�����Ă���l�X�A�����_����`��l�퍷�ʂɂ��炳��Ă���l�X���ق������B�l���肤�̂́A��茒�S�ŁA�K���ŁA�C���N���[�V�u�Ȑ��E���B�ߋ����瓾���鋳�P�́A�����݂�}���Ȃ���Ԃɂ��Ă����ȂƂ������Ƃ���v �@�������A����͏A�C�ȗ��A�c�d�h�i���l���A�������A��ې��j������p�����ɓP�p���Ă���g�����v�����ւ̃A���`�e�[�[���낤�B�u���f�B�A���̂���Ƃ�����������B �@���ɐ����F���ڗ����������Ă����̂́A�ҏW�܂̃v���[���^�[�߂��_�����E�n���i�ŁA�o�d�����u�E�N���C�i�ɉh������I�v�ƈꌾ�B���Ȃ݂ɂ��̐����O�ɂ́A�����̃[�����X�L�[�哝�̂ƕč��̃g�����v�哝�̂��A�z���C�g�n�E�X�ňٗ�̌��_�����������肾�����B �@���҃h�L�������^���[�܂���܂����w�m�[�E�A�U�[�E�����h�@�̋��͑��ɂȂ��x�̍��肽���́A�u�p���X�`�i�l�̎��R�ƈ��S�������A�C�X���G���l�̈��S�ɂȂ���v�ƁA�e�C�X���G����ӓ|�̕č��̐����ᔻ�����B����ȍ�i�ɃI�X�J�[��^����Ƃ���ɁA�n���E�b�h�̉��̐[��������B �����l������邩�A���h����邩�� �@�����A���N�O�́u�����I�X�J�[�v�ᔻ�ȗ��A���X�ɑ��l���̐i��ł����A�J�f�~�[�܂̗��ꂪ�A���N�͂��������~������������B�o�D�S����̎�Ғ��R�l�����l�ŁA�m�~�j�[�܂Ŋ܂߂Ă��A���l�o�D�͑S�Q�O�l���̂R�l�ɂƂǂ܂����B �@�܂��A�ߔN�͔�č��l�̔o�D�����l����҂ɓ���̂��ʗႾ�������i���Ƃ���N�̓L���A���E�}�[�t�B�[���A���N�̓L�[�E�z�C�E�N�����ƃ~�V�F���E���[����܁j�A���N�͂S�l�̎�ґS�����A�u�ւ荂���ږ��̎q�v�̃]�[�C�E�T���_�i���܂߂āA�č����܂ꂾ�����B �@�ē܂̏����m�~�j�[���A�A���o�C���̂悤�ɃR�����[�E�t�@���W���i�w�T�u�X�^���X�x�j�������Ă����݂̂��B �@�Z�p������܂߂Ă��A���N�͑S�ʂɐl��I�}�C�m���e�B�̎�҂����Ȃ������悤�Ɏv���B����Ɠ����ɁA��܃X�s�[�`�œ����̃p�[�g�i�[�ւ̊��ӂ������l���i��������N���l����̂�����ǁj�A��������[���������B �@���l�������ꂽ�Ƃ����̂́A���t��������Δ��������i�Ƃ������Ƃł�����B�����A�{�e�̖`���Łu�ߔN�ł͏o�F�̎����v�������Ə������̂́A����Ӗ��A���̂������������Ƃ������邩���₱�����B�l�����͊F�A�E�B���E�X�~�X���N���X�E���b�N������悤�Ȏ��������A�_�̏�̔��j�������A�Ђ�����܂䂢����^���Ă����������������̂�A�{���̂Ƃ���ł́B �@�Ƃ���Ŕo�D����̃v���[���^�[�́A�O�N�̎�ܔo�D���A�j�������ւ��ēw�߂�̂��P��B�Ƃ��낪���N�́A�Ȃ����j�������ւ����A���o�[�g�E�_�E�j�[�E�W���j�A�������j�D�܂��A�f�B�o�C���E�W���C�E�����h���t���������D�܂��A�L���A���E�}�[�t�B�[���剉�j�D�܂��A�����ăG�}�E�X�g�[�����剉���D�܂悵���B �@�Ȃ�ł��ȁH�Ƃ����ƍl���Ă����̂����A�I�ՂɃG�C�h���A���E�u���f�B���剉�j�D�܂�������Ƃ���ŁA�������ȉ\�������ɕ����B���̐l�A�܂��y�[�y�[�������Q�O�O�Q�N�̎���ɁA�v���[���^�[�̃n���E�x���[�ɁA�����Ȃ�Ԃ�����ƌ��Â�����������Ƃ����u�O�ȁv������B �@�G�}�E�X�g�[�������́u��Q�v��������邽�߂ɒj���̂������|������߂������̂��Ƃ�����A����̂��b�Ƃ��Ă͂��Ȃ�ʔ����Ⴀ��܂����i���ہA�X�g�[���Ȃ��Î҂ɂ����������Ƃ�\�����ꂻ���ł͂���j�B �@�܂��A���ꂪ�������Ƃ���ƁA���d�Ȕ閧�ێ���搂�����̐R�����ʂ��A���O�ɘR��Ă������ƂɂȂ��Ă��܂��܂����ǂˁB �i�Q�O�Q�T�D�R�D�P�P�D�L�j ���A���E�y�C���`�S�̗��` A REAL PAIN �i�Q�O�Q�S�N�A�āA�����F���Y���ށj  �@���_���n�č��l�̐N���A�Ƒ��̃��[�c�����ǂ��ĉ��B�ցB���ꂾ�������ƁA�Ȃ��o�D���[�u�E�V�����C�o�[�̊ēE�r�{�́w�l�̑厖�ȃR���N�V�����x(2005)���v���o�����A���g�͂���قǎ��Ă��Ȃ������B �@�����A��������o�D�W�F�V�[�E�A�C�[���o�[�O���ēE�r�{�Ɏ剉�Ɛ���܂Ō��˂Ă��āA���܂��Ɍ���̂���w�l�̑厖�ȁ`�x�Ƃ͈���ăI���W�i���r�{�ł���炵���B��قǎv������̂���X�g�[���[�������̂ł��傤�ˁB �@����̎��́A���i�̂܂�ňقȂ�]�Z�퓯�m���A�S���Ȃ����c����ÂԂ��߂ɂm�x����|�[�����h��K�˂钿�����B�f�r�b�h�i�A�C�[���o�[�O�j�͐��^�ʖڂő��l�̋C�������C�ɂ�����^�C�v�����A����䂦�ɒN�Ƃ��[�������Ȃ��B�x���W�[�i�L�[�����E�J���L���j�͎��Ȓ��ŖT�ᖳ�l�����A�Ȃ������͂��爤�����B �@���Ղ��炱�̂Q�L�����̑Δ䂪���ɂ悭�`���Ă��邵�A����𐏏��ŏ��ɂ��Ȃ��Ă����B�������ɂ���c�A�[�K�C�h�⑊�q�����̑��`���ߕs���Ȃ��B �@������S�̂Ƃ��āA�u�o�D�̗]�Z�ɂ��Ă͂��܂������Ă���ȁv�Ɗ������̂����A����ɂ͍m��I�ȈӖ������ł͂Ȃ��A�ے�I�ȈӖ�������B �@���Ƃ��x���W�[�̕���������u�閧�v�ɂ��ẮA���e�I�ɂ�����ƒ��Ȋ������������A������f�r�b�h���c�A�[���Ԃɖ\�I���闬������X���˂ɉ߂��Ȃ��������B�����x���W�[�̐��i�j�]�Ԃ�́A�u������L�����v�Ƃ����ݒ�ɐ����͂����������邩�ǂ����̃M���M���̐��������悤�ɂ��v���B �@����ł��l�I�ɂ́A�x���W�[�݂����Ȑl�Ԃɑ���f�r�b�h�̑A�]�ɋ����ł����ȁB�c�A�[���ԂƂ̕ʂ�ہA�x���W�[�Ƃ͐e���Ɍ��t�����킵���K�C�h�i�w�G�}�j���G���x�̓ڂƓ���l���Ƃ͎v���Ȃ��E�B���E�V���[�v�j���A�f�r�b�h�ɂ͗�V�����������ɂ������肵�����A�����������ł������Ə����Ă����ЂƃR�}�i�ƁA��������A�C�[���o�[�O�̔߈��ɖ�������u�̕\��j�����E�E�E�B �@�Ȃu����̔��͑����ł͂Ȃ����S�v�Ƃ������t���v���o������B�����������̂́A�����炭�����f�r�b�h�^�̐l�Ԃ����炾�낤���B �i�Q�O�Q�T�D�Q�D�P�X�D�L�j �U�E���[���E�l�N�X�g�E�h�A THE ROOM NEXT DOOR �i�Q�O�Q�S�N�A�X�y�C���A�����F���Y���ށj  �@�]�_�Ƃ̐���簂͂Q�O�P�W�N�ɓ������E�𐋂������A�Q�l�̒m�l�ɂ��������Ă����B�N��I�ɂ�����I�ɂ��������ɋt�炦�Ȃ������Ǝv���邻�̒m�l�����́A�x�@�Ɉ��������A���s�P�\�t���Ƃ͂����L�ߔ������Ă���B �@���͎������̂��̂��Δے肷�闧��ł͂Ȃ�����ǁi�����Đl�ɂ͍K���ɐ����錠���Ƌ`���ƏK��������B�Ȃ�Ό��ɍK���ɐ������Ȃ��l�X���A������̂���߂悤�Ƃ��邱�Ƃ�N�Ɏ~�߂��悤�B�܂��A�u����ł͌��ɐ����Ă��邨�O�͂���ȂɍK���Ȃ̂��H�v�Ɩ����ƁA���Q�a�̃K�L�ǂ���낵���u�t�c�[�v�Ɠ����邵���Ȃ��̂�����ǁj�A����͖��f�Șb���B �@�N���Ɏ~�߂Ăق����Ă킴�킴���b�V���A���[�̉w�œ��g���E����Ă���҂����Ƃ͈Ⴂ�A�������́A�ӎv���̂͋��ł������Ǝv����B�Ȃ�A�Ȃ�������l�Őg���������A�m�l���������ނ悤�Ȃ��Ƃ����Ă��܂����̂��B �@�܂��Ĕނ��˗������̂́A�P�Ȃ�u���͂��v�ł͂Ȃ��A�����I�ȍ�Ƃ����Ȃ�͂�����Ƃ����u����`���v���B����Œm�l�������s��ɕt�����ƐM���Ă����̂��Ƃ�����A���܂�Ƀi�C�[�u���ƌ��킴��܂��B �@�ƂȂ�ƁA��͂�Ƃ�Ő����̂��A�����P�Ɏ₵���������A�܂��͕|�������̂��ƍl����̂����R���낤�Ȃ��B�������Ƃ�����{���̃G�S�ł���B �@�y�h���E�A�����h�o���ē��ŐV��Ŏ��g�̂́A�����́u���͂��v���˗����ꂽ���˗������Q�l�̏���������S�������B �@��Ƃ̃C���O���b�h�i�W�����A���E���[�A�j�́A�v�X�ɍĉ���e�F�̃}�[�T�i�e�B���_�E�X�E�B���g���j����s���̕a�ł��邱�Ƃ�ł���������B�����Ď������鎞�ɗׂ̕����ɂ��Ăق����Ɛ����āA�����Ȃ�����}�[�T�Ɠ������n�߁E�E�E�B �@�}�[�T�������̂́u����`���Ȃ��v�̈˗������A�������̗�Ɠ��l�A��������G�S�C�X�e�B�b�N�ł��邱�Ƃɕς��͂Ȃ��B�Ƃ�łł��Ȃ��Ȃ炵�Ȃ��ł�ƁA�C���O���b�h�݂̂Ȃ炸�A�ϋq�̑������ᔻ�I�Ȏv������������Ƃ��낤�B �@���͂���Ȃ���A���Q�l�ʼn߂����Ō�̓��X�ɂ́A�����ɂ��A�����h�o���炵���G�X�v�����B������Ɩʔ����Ǝv�����̂́A�C�͂��ނ��āA���e�������Ȃ��A�{���ǂ߂Ȃ��A���y�����������Ȃ��Ƃ�����ԂɊׂ����}�[�T���A�V�[�����ς��ƁA�C���O���b�h�ƃ\�t�@�ł��났�A�o�X�^�[�E�L�[�g���̂c�u�c���ςď��Ă����ł��ˁB �@�C�s�̃W���[�i���X�g�������������A�m�I�Ȋ��������ЂƂ������Ȃ��قǔ敾���Ă��A�h�^�o�^�쌀�Ȃ�y���߂�B�A�����h�o���̉f��l�Ƃ��Ă������������Ɋ_�Ԍ�����ƌ�������A���ق��������낤���B �@�A�����h�o���������O�̓ł��̂��������V�[�����I�ՂɁB�}�[�T���u�{���v�𐋂������Ɓi�����A�u����o���������������Ƀ}�[�T�͐�����C�͂����߂��܂����Ƃ��v�Ȃ�Ă��s����`�I�ȓW�J�ɂ͂Ȃ�Ȃ��j�A�߂��݂ɕ��Ă����C���O���b�h�́A���낤���Ƃ��ʂ̋��ʂ̗F�l����u�}�[�T�Ɂw���͂��x���𗊂܂ꂽ���ǒf�����v�ƕ��������B�F����ӋC�Ɋ����ďd����ڂ��������̂ɁA�����������ł͂Ȃ������ƒm�����C���O���b�h�̋����͂������肩�B �@���̂��Ɣޏ����A���E�Ƃ��̛��d�߂��ƍl����x���i�A���b�T���h���E�j�{���j����A����簂̒m�l�̂��Ƃ��i����̂ŁA�A�����h�o����A�]�ނ炭�̓C���O���b�h�����}�[�T�ɏ����ȗ����Ƃ��悤�ȕ����ŁA������Ђ˂�����Ăق����������B �@�}�[�T�̎���ɓo�ꂷ��A�}�[�T�̖����ɂ��N���������͂��B�u�����Ԃ�悭�����炾���̏��D��T���Ă����ȁv�Ƃ��u�e�B���_�E�X�E�B���g���ɏ��D�����Ă��閺�����������H�v�Ǝv���Ă��܂������A�ǂ�����l����������炵���B�u�}�[�T���\��̂����ɐ��i�N��̂����傫���Ȃ��j���v�Ƃ����ݒ肪�����Ă����̔z�����B �@����̓A�����h�o���̈Ӑ}�I�ȕ����ł͂Ȃ��Ǝv�����A����ȃX�E�B���g���́u��݂�����v�Ԃ�����Ă�����A����̑O���A����|�p�ƃ��C�[�Y�E�u���W�����̎h�J��i���A���肰�Ȃ��ǂɊ|�����Ă����̂��v���o�����i�`���̉摜�Q�Ɓj�B�����Ɏh�J���ꂽ�����͂Ƃ����A���H�A�X���p�قōs��ꂽ�u���W�����W�̕���ɂ��Ȃ��Ă����Ƃ��肾�B �u�n������A���Ă����Ƃ���@�����Ƃ����ǁA�f���炵�������� �v �i�Q�O�Q�T�D�Q�D�P�X�D�L�j �Q�O�Q�S�N�i���́j�x�X�g�P�O�I �@�Q�O�Q�S�N�̉f�拻�s����i���ɗm��j���ł��傫�������Â����̂́A�Ō�̂S�J���قǂ̑��������B �@���������V�^�R���i�̐����畽���ɕ������N���Ƃ����̂ɁA�Ȃ����X���ȍ~�A�A�j���������V��č��f�悪������قǂ�������Ȃ��Ȃ�A�����Ȃ����J��i���A�ǂ��炩�ƌ����Θb�萫�̔������̂���ɁB �@���������n���E�b�h�ɉ����N�������̂��B�u�R���i�ŎB��Ȃ��v�Ƃ����ň����͂��łɒE���Ă����͂�������A�Q�O�Q�R�N�̔o�D�g���Ƌr�{�Ƒg���̃X�g�������ɗ��ĉe�����y�ڂ����̂��낤���B �@����Ȏ���������āA�Q�O�Q�S�N�̊ӏܖ{���͂S�Q�{�ƁA�R���i�Ђ̉Q���������Q�O�Q�P�N�ȗ��̂T�O�{����B �@��������x�X�g�P�O��I�̂�����A�����]�����Â߂ɂȂ������͔ۂ߂Ȃ��B �@����͕č��f��T�{�A�p���f��P�{�A�t�����X�f��P�{�A�ĉp����P�{�A�X�y�C��=�t�����X����̃A�j���f��P�{�A�����ĉ��N�Ԃ肩�Ń����L���O���肵�����{�f�悪�P�{�i���吻��́w���^�C���X���b�p�[�x�j���B �@�ȉ��Ƀ��X�g���f�ڂ��邪�A��N�ǂ���u�ǂ��������v�ł͂Ȃ��A�u�ӏ܂������v�ł��B �P�@�w����Ȃ���̂����x �Q�@�wDOGMAN �h�b�O�}���x �R�@�w�I�b�y���n�C�}�[�x �S�@�w������v���e���_�[�x �T�@�w�z�[���h�I�[�o�[�Y �u���Ă��ڂ�̃z���f�B�x �U�@�w�t���C�E�~�[�E�g�D�E�U�E���[���x �V�@�w�t�H�[���K�C�x �W�@�w�V�r���E�E�H�[�@�A�����J�Ō�̓��x �X�@�w���^�C���X���b�p�[�x �P�O�@�w���{�b�g�E�h���[���Y�x �i�Q�O�Q�T�D�P�D�Q�D�L�j ���{�b�g�E�h���[���Y ROBOT DREAMS �i�Q�O�Q�R�N�A�X�y�C�������A�����F���������j 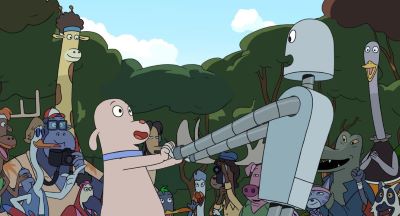 �@�X�y�C���o�g�̃p�u���E�x���w���ē��A�W�O�N��̃j���[���[�N��ɎB�����Q�c�A�j���B�i�P�j���E�ρi�Q�j�A�[�g���[�N�i�R�j�X�g�[���[�̂��ꂼ��Ɍ���ׂ��_�������Ėʔ����B �i�P�j�\���m���s���łĂ����茢�̐��E�̂��b�Ȃ̂��Ǝv���Ă������A�W���J����w�r�h�m�f�^�V���O�x�V���[�Y�Ɠ��l�A�S�b���݂ŁA�َ팋��������̐��E�B �@�����A�b���r�I�傫�Ȓ��ނ͌㎈�œ��s���A�l�ԂƂ��Ă̐������c��ł���̂ɑ��A�n�g�̓n�g�Ƃ��āA���͋��Ƃ��đ��݂���ܒ��ĂȂ�ł��ˁB �@�������w�r�h�m�f�^�V���O�x�ƈ���ăZ���t�͈�Ȃ��A���������{�b�g�������甭����̂͑��Â������x�B����ł��i���邢�́A����䂦�Ɂj���E���̊ϋq���������A���������ɂ��邱�Ƃ��ł���i���Ⴀ�Ȃ�Ŏ����|��҂�����̂��ƌ����A��ʂɕ\������Ă���p����|�A�ƊE�p��Ō����u���������v�����邽�߂��B �@����A�ʔ̂̏��i�ɉ߂��Ȃ����{�b�g�̗���͂ƌ����A�ʂɓ��������ɏ]�����Ă���킯�ł͂Ȃ��A���L�҂ƑΓ��B���܂��Ɉӎv������������Ƃ���A���������Ƃɖ�������i���̑����͈����ł�������I�j�B �@�E�E�E�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ��킩���Ă����Ƃ���Łu�����v�Ǝv�����B�{��̃^�C�g���ɂ́u���{�b�g���o�Ă��閲�v�����ł͂Ȃ��A�u���{�b�g�����閲�v�Ƃ����Ӗ����������̂ł��ˁB �i�Q�j�n�g�̎���Ču���F�Ɍ����Č�������̂����ǁA�����Ǝ��̂Q�{�̃o���h�݂̂Ō����ɕ\�����Ă���̂ɐ���������B �@�~��V�[���ł͌����̌`�������Ⴊ�����~��Ă�����̂�����A�{���͂��܂�Ȃ��Ȃ���i�Ȃ̂ɁA�ǂ����g�����A���������̂ɁB �i�R�j��l���̌ǓƂȌ��i�h�b�O�j�ƁA���̖���̐e�F�ƂȂ������{�b�g���A�䂦�����Ĉ�����A���ꂼ��ɍĉ���Ȃ�����A�V���Ȏ�����l�ԊW�i����Ȃ��ē��������{�b�g�W�j�ɖ|�M����Ă����B �@�x���w���ē̃X�g�[���[�e�����O����`����Ă���̂́i���j���Ƃ�����]���Ƃł͂Ȃ��Ă��A�ЂƂ��ѕʂ�Ă��܂����݂����ς���Ă��܂��̂��Ƃ������ƁA�����āi���j��x���Ă��܂������̂́i�w�i�ɂ��т��щf�郏�[���h�E�g���[�h�E�Z���^�[�̃c�C���^���[�̂��Ƃ��j���ɂ͖߂��Ȃ��̂��Ƃ������ƁB �@��ɋ������摜�͂Q�l�i�Ƃ������A�P�C�ƂP��j���K���̐Ⓒ�ɂ������V�[���̈�R�}�����A���X�g�߂��łQ�l�������_���X���i�ʂ̏ꏊ�Łj�x��V�[���̐Ȃ��Ƃ�������ǂ����낤�B �@���{�̃A�j����Ƃ�������������A�قڊԈႢ�Ȃ��h�b�O�ƃ��{�b�g���ĉ�E���������Ă����ɈႢ�Ȃ��B�������x���w���ē͂����͂����A�P�C�ƂP��͐V���ȃp�[�g�i�[�Ƃ̊W�ɒ�����s�����i���̓_�ɂ����āA�h�b�O�ƃ��{�b�g�Ƃ̊W�́A�P�Ȃ�F��ł͂Ȃ������̃��^�t�@�[�Ȃ̂��낤�Ǝv���j�B �@���������w�g�C�E�X�g�[���[�S�x�ł́A�Ō�ɃE�b�f�B��������̏����Ǝv����悭���ʂ����B���{�Ɖ��Ă̐��_���̈Ⴂ�̂悤�Ȃ��̂������܂��ˁB ���I�}�P�̈ꌾ�� �@���łɂ����ɂȂ������ɂ̓W���[�N�Ƃ��Ď���Ă���������Ǝv�����A����͑̏d���߂̉��l������l�����ɁA�_�C�G�b�g�����ӂ�������ł����邩�ȁi�j�B �i�Q�O�Q�S�D�P�Q�D�P�W�D�L�j �z���C�g�o�[�h�@�͂��܂�̃����_�[ WHITE BIRD �i�Q�O�Q�S�N�A�āA�����F��c���T���j  �@��������������������Ɖ��ƂȂ��s�ސT�ȋC�����Ė��x���S�n�������Ȃ��Ă��܂��̂�����ǁA�����A�z���R�[�X�g�f��ɂ͌��삪�����B���̂悤�Ɋ���̋N���ɖR�����A�X�y���K�[���̒j�ł��A���̎�̉f���O�ɂ���ƌ������S��h���Ԃ��A���ɂ͋`���ɋ���Ă�����ړ����M���Ȃ邱�Ƃ�����B�l�I�ɂ̓��_�����Ƃ����_���l�Ƃ��A���̂Ȃ�����Ȃ����ǂˁB �@�Q�O�P�O�N���w�T���̌��x�́A����ȗ��܃z���R�[�X�g�f��̈�Ⴞ�������A���́w�z���C�g�o�[�h�@�͂��܂�̃����_�[�x�ŕ`�����̂́A����̃q���C���Ɠ����T���Ƃ������O�������A��͂��̉��̃t�����X�ŕ�炵�Ă������_���l�����̉ߍ��ȉ^�����B �@���Ȃ݂Ɏ����Ⴂ���ɂ́u�z���R�[�X�g�̓i�`�X�̃V���p���h�C�c�����ł��������l���ƍ߁v���Ɗ��Ⴂ���Ă������A�w�T���̌��x��w�f�B�t�@�C�A���X�x�i2008�j�A�w�Ɓi�����j�A�낤�x(2017)�Ȃǂ̏�������邤���ɁA���_���l���̓t�����X�Ⓦ�����܂ރi�`�X�̐�̉��S��ōs���Ă������Ƃ��w�B �@�ǂ̍������A���Ƀ��_���l��ł�������ł��A�i�`�X���x�����Ă�������ł��Ȃ��A���_���l�����e���ɑ������܂��A�ނ�̏��L����s���Y����Y��D���邩��Ƃ��������Ɍo�ϓI�ȗ��R�ŁA�i�`�X�ɋ��͂��Ă�����ł��ˁB �@������҂����ɊO���f��̊ӏ܂����߂�傫�ȗ��R�̂P�́A����Ȃӂ��Ɏ����m�����L�����邱�Ƃɂ���B �@����������ł́A�ǂ̍��ɂ����̂��Ƃɋ^���{��������A�댯��`���ă��_���l�������悤�Ƃ����l�X�������i�̂��Ǝv���j�B �w�z���C�g�o�[�h�@�͂��܂�̃����_�[�x�́A�����炭�~�h���e�B�[�����炢���Ǝv�����l���̃T�����A���e�Ɛ����ʂ�A���g�͋��F�̉Ƃɂ����܂���B�r�ɏ�Q�������̋��F�W�����A���ɁA����܂ŃT���͂���قǓ���I�ł͂Ȃ��A�ނ��땎�̓I�Ȃ������ŌĂ�ł����قǁB����ł��W�����A���Ƃ��̗��e�͐e�g�ɏ����Ă�����ł��ˁB �@����ɐڂ����T���̊��ӂƏ�Ȃ����Ȃ������ɂȂ������G�Ȋ�����A�ςĂ��邱����܂Őg�������������Ȃ�قǂ��B �@����ȃW�����A������x���������������V�[��������B�T�X�y���X�̋����E�����ƂɂȂ�̂ŏڂ����͏����Ȃ����A��ނɂ�܂ꂸ�T�����Ȃ���W�����A���̐S��A���Ă��邱����ɂ��ɂ݂��ē`����Ă���ꖋ�B���ɂƂ��ẮA�������{��ň�Ԃܑ̗B����|�C���g�������B �@����Ȑ��������ɂ��ꖕ�̋~��������B�Ƃ������A����҂̂q�E�i�E�p���V�I�͈ꖕ�̋~����^���Ă���Ă���B �@�W�����A���̉Ƃ̔[�����������o���Ȃ��Ȃ����T���́A�����ɒ�߂�ꂽ�Ԃ̉^�]�Ȃɏ��A�W�����A���Ɠ����Ƃɋ�z���s���y���ނ̂��B�Ɍ���Ԃ̒��A�e�G�V�тȂǂ𗘗p���āA���̊Ԃ̈��炬�����o���Q�l�B�������h�̃}�[�N�E�t�H�[�X�^�[�ē炵���A���Ƃ��������V�[���������B �@���āA����ȂQ�l�̗F�����Ɉ��ɓ]�����Ă����̂͂������R�ȗ���Ɍ�����킯�����A�ϋq�͂��̐�Ƀn�b�s�[�G���h���p�ӂ���Ă��Ȃ����Ƃ�m���Ă���B�Ȃ��Ȃ炱�̕���́A�V�����}��������̃T���i�w�����E�~�����j���A�����q�ɐ펞���̏o���������Ƃ�������q�\���ɂȂ��Ă��邩�炾�B �@�W�����A���Ɠ������������̑����q���A�c��̉��l�ɂ��Ă���܂ʼn����m�炸�ɂ����Ƃ����O��ŕ��ꂪ���n�߂�ꂽ�ȏ�A�������̓n���n��������A���ɂ̓z�b�Ƃ����肵�Ȃ�����A���炩���ߖ��ꂽ�ߌ��Ɍ����ċN���]�������ǂ邵���Ȃ��B �@�����A�{��́A���̓_�ɂ����Ă��܂��w�T���̌��x�Ɠ��l�ɁA��Ȑl�̖��O�ƁA���̏��p�ɂ�����镨��ł������̂��B �i�Q�O�Q�S�D�P�Q�D�P�R�D�L�j �h���[���E�V�i���I DREAM SCENARIO �i�Q�O�Q�R�N�A��=���A�����F���䂩����j �@�E�f�B�E�A�����ḗw���[�}�ŃA���[���x(2012)�ł́A���x���g�E�x�j�[�j�����镽�}�Ȓ��N�j�����R���Ȃ����͂�����Ă͂₳���悤�ɂȂ�A�ŏ��̌˘f����E���Ę������܂��悤�ɂȂ����Ƃ���ŁA���������悤�Ɍ�����������Ȃ��Ȃ�Ƃ����s�𗝂Ȉꖋ���`����Ă����B �@����A�w�h���[���E�V�i���I�x�Ńj�R���X�E�P�C�W���������̂́A�Ȃ����吨�̐l�̖��̒��ɓo�ꂷ��悤�ɂȂ����n���ȑ�w�����|�[���B���̎������|�[�����g�␢�ԂɁA�����Ċϋq�Ɏ���ɖ�������Ă����A�܂��A���ɏo�Ă��邻�̒j�̐��̂��|�[���Ȃ��w�����ł���ƁA�ނ�m��Ȃ��l���ɂ܂łЂ��Ђ��ƒm��n���Ă�����A�̉ߒ���`�����������́A���[�����X�ɂ��āA�Ȃ��Ȃ��ɃX�������O���B �w���[�}�Ł`�x�̃x�j�[�j���l�A�|�[�������u���̐l�v�ƂȂ邪�A�����͒P�Ȃ�T�ώ҂��������̒��̃|�[�����A����ɖ\�͔ƍ߂�I�\�s��Ƃ��n�߂�ɋy�сA�������E�̃|�[���܂ł����͂���������A�E�����H�X����r�����ꂽ��A�����点��ʂĂ͓��̓I�\�͂ɂ��炳�ꂽ�肵�n�߂�B�x�j�[�j���u���̎����v�ɖ߂��������������̂ɔ�ׁA�|�[���̐l���͊��S�ɔj��Ă��܂���ł��ˁB �@���̂�����͂܂�Ő����̃��u�L���A����N���́u��z�w�̌Y���v���Ƃ������炢�̕s�𗝁E���~�X�Ԃ肾�B�Ƃ͂����A���̃|�[�����u�����Ɛт�F�߂�ꂽ���v�Ƃ��u�������o�������v�Ƃ��������F�~�������ȁA����ł��Ď������܂������n�߂Ă������Ȃ��Ƃ����A�����Ă݂�u���͂܂��{�C�o���ĂȂ������v�^�̑����ł��邽�߂ɁA����قǓ���S�͗N���Ă��Ȃ��B �@���̂Ƃ���A�|�[�����g�͑��l�̖��ɏo�邩�o�Ȃ�����A�����łǂ�ȍs������邩�ɂ܂������ӔC���Ă��Ȃ��ݒ�B�]���Ĕނ̐l�i�����Ɋւ��Ȃ��A�{���͓����đR��ׂ��͂��Ȃ̂����A�ϋq�����������c���Ȃ��̂ł���B �@�s�𗝌��ɈӖ��⋳�P�����ݎ��K�v�͕K�������Ȃ��킯�����A�l�����Ă͂₵�Ắu����v���A�������Ǝv���Ύ�̂Ђ�Ԃ����悤�Ƀo�b�V���O����}�X�R�~��r�m�r�ւ̕��h���A���̓^������ǂݎ�邱�Ƃ��\��������Ȃ��ˁB�@����Ă��铖�l���{���ɒ@�����ׂ����Ƃ����ł������̂��A�܂��A���̔��͔Ƃ����߂Ɍ������Ă���̂����A������������Ɍ���߂�K�������邱�Ƃ͖��ʂł͂Ȃ��B �@���āA��������͉f��̓��e�Ƃ͒��ڊW�̂Ȃ����ʘb�B�Љ�I�M�p�������̓����������|�[���ɒǂ������������邩�̂悤�ɁA��{�I�ɂ͂���܂Ŗ����ɂȂ��Ă���Ă����ȁi�W�����A���k�E�j�R���\���j���A�ŏI�ՂɂȂ��ė�������B�|�[�����Ƃ���ǂ����������肩�A���̒j���Ɨǂ����ɂȂ��Ă��܂���ł��ˁB �@�ŁA�����J�b�g�����f���ꂽ���̐V���Ȓj�������Čl�I�ɏ��Ă��܂������ǁA�Ȃ�ƕ���̏��ՂŁu�|�[���ƊO�������Ă���v�ƌ���ꂽ�Â����̒[���ŁA�|�[���̍ȂƂ͂��Ƃ��ƌ𗬂��Ȃ������l�Ȃ̂ł���B �@���̐́A�͍��ޕێq�́i���邢�͒|���܂��́j�u�������^�C�v�̐l���D���ɂȂ��Ă��܂��^�h��鉳���S�悭����ł��傤�v�Ɖ̂�������ǁA���ۂ̐l�Ԃ̍s���ɑ����čl����A�u�������^�C�v�̐l�v���Ƃ������Ђ������D���ɂȂ邱�Ƃ����A�ނ��듯���^�C�v�̐l�����x���J��Ԃ��D���ɂȂ邱�Ƃ̕������|�I�ɑ����̂ł͂���܂����B �@���Ƃ��̘b�A�ڂ̂ς����肵�����q���D���ȖʐH���j�q�́A�����玟�ւƖڂ̂ς����肵�����q�ɂ̂ڂ��邵�A�_�����Y�Ɏア�_�����͉��x�ς��������܂���Ă��A�܂��_�����Y�ɓ��ꂠ����B �@���̈ꎖ������Ă��A�u���̐��ɂ�����l�A�Ԃ����Ō��ꂽ�^���̑��肪����v�Ȃ�Č����͓x���������f�^�������Ƃ͂�����ؖ�����邾�낤�B�^�C�v�̎��Ă���ِ��Ȃ�Đ��̒��ɂ�����ł�����̂����A�������͂��̑唼�𐫒�����Ȃ��D���ɂȂ����炳�B �@���Ȃ������Ȃ��̔z��҂�I�̂́A���̐l���u������l�̉^���̑���v����������ł͂Ȃ��A�u�D���ȃ^�C�v�ِ̈��̂����A���܂��܂��̃^�C�~���O�ł����ɂ����l�v����������ł���H�@���͂����ӂ߂͂��Ȃ��B �@�����Ƃ��A���Ȃ������Ȃ��̉�����ɉI舂ɂ���Ȃ��Ƃ����������̂Ȃ�A�|�[���݂����ɒǂ��o����A�C�������Ȃ��Ɏ����l�����Ȃ��̉Ƃɏo���肵�Ă���Ȃ�Ă��ƂɂȂ肩�˂Ȃ��̂ŁA���ӂ��K�v���B �i�Q�O�Q�S�D�P�Q�D�Q�D�L�j ���^�C���X���b�p�[ �i�Q�O�Q�R�N�A�����f��Ёj  �@���̏H�����炢����A�Ȃ����m��̌��J�{�����}�����A�������i�̊i���S�̓I�ɗ����Ă���B�������ŃV�l�R���̔ԑg�Ґ��̓��o�C�o�����J�삾�炯�B�R���i�ЂɌ�����ꂽ�ꎞ���ɓ��l�̎S��ɂȂ������Ƃ͋L���ɐV�������A�����ɗ��ėm�悪�����Ă��Ȃ������͉��H�@�n���E�b�h�̔o�D�g���Ƌr�{�Ƒg���̃X�g�ŋ����́A�����������ꂽ���̂Ǝv���Ă������B �@�d�����Ȃ��̂ŋv�X�ɓ��{�f������Ă݂����A���̎��吻���i�A�e���r�h���}�̑��҂��炯�̃��W���[��i��萔�i�ʔ�������Ȃ����B �@����Ƀ^�C���g���x�����Ă��������̉�Ôˎm���A���㌀�B�e���̎a�����Ƃ��Đ����錈�ӂ�����Ƃ����̂�������A�X�g�[���[�ɂ͏�����A�܂���A�g������A���ӂ��قǂ̎��㌀������B�Ƃ�킯�N���]���́u�]�v�̂Ƃ���Ŏ�l���̑O�Ɍ�����X�^�[�̑f���ɂ́A�܂���������˂��ꂽ�B �@��l�����i�P�j���D�Ղ�̃C�x���g�|�X�^�[�����āA�����̐g�ɋN�������Ƃ��������藝���E���ς��Ă��܂�����A�i�Q�j�����̑f����N�ɂ��ł������Ȃ������肷�邠����́A�܂��A�s���R�Ƃ����Εs���R���B����ł��X�g�[���[��]������ł́A����炪���ɑt�����Ă���A�����I�ɂ̓I�t�r�[�g�ȏ�������ł���B �i�R�j��l�����a�������u�]����Ƃ�����Ԃ̖������A�����̏��ēւ̗��S�𗍂߂邱�ƂŁA���c�~��ē��G�X�Ə��z�����B�E�w�t�ɒ�q���肵����l�����A�a����i�����������Ă��A���{�\�I�Ɏa��Ԃ��Ă��܂��M���O�ɂ͑���B �u�[���v���u�Z���t�̂�����v���u������v�Ƃ��������㌀���҂̏o���R�[�X���A�ߑ��⏊���ς��������^�[�W���Ō����Ă����V�[���͎��ɂ������B���㌀���c�m�`�ɂ��荞�܂ꂽ���{�l������A���X�Ɛ������Ȃ��Ă����ꂾ���œ`���̂ł��ˁB �@����Ȃ���o�Ă����o�D�����͒m��Ȃ�����肾�������A����̐V���q��i�R���n�ؖ�j�ɂ���A������̑�X�^�[�i�y�ƃm���}�T�j�ɂ���A���b�D���ȏZ�E�v�Ȃɂ���A���C�ȏ��ēɂ���A���ɐ����͂̂���L�����`���Ă���Ă���B �@�����łӂƋC�ɂȂ�̂́A���c�ē��i�P�j���ɂ��̊��荞�݂Ȃ��甃���肪�����A���吻�삹����Ȃ������̂��A����Ƃ��i�Q�j�w���b�L�[�x�̎��̃X�^���[���݂����ɁA�S�������ŃR���g���[������������������ɔ���n���Ȃ������̂��̂ǂ���Ȃ̂��Ƃ������ƁB�O�҂��Ƃ�����A���͖ҏȂ����ق��������B�����ƃl�[���o�����[�̂�����҂������N�p���Ă��������Ă�����A�����q�b�g���Ă����Ǝv�����ǂˁB �@�N���C�}�b�N�X���g�^���h�����ɂȂ��Ă����ߒ��́A����܂����Ȃ�̖����ł͂��邪�A�O�A�������Ղ�̎E�w�Ɖ��Z�ɂ͎l�̌܂̗��������킹�Ȃ����͂��B�������钼�O�Ɏ�l���Ƒ�������P�O�b���炢�ɂ�ݍ����V�[���̋ٔ����͂������Ƃł͂Ȃ��A�u�����₱���ňÓ]�E�I�����v�Ƃ��v�������A�ē͂���Ȋ��͑ł����A���U�@�ł�������ƍU�߂�B �@����ł��čŌ�̍Ō�̓M���O�̓�i�I�`�ŁA�ӏ܌㊴���ق����肳��₩�B���ē��̍��q�䂤�̂��A�{�쎩�̂̏��ē��͂��߁A�������̗����d���ŃN���W�b�g����Ă���̂����������B�����Ɠ��l�A�����Ԃ��щ���Ă�����ł��傤�ˁB �@�Ȃ��A�{��̃^�C�g�����w���X�g���b�p�[�x�ƊԈႦ��������ꕔ�ɂ���悤�ł��̂ŁA�����ӂ��������B �i�Q�O�Q�S�D�P�Q�D�Q�D�L�j �V�r���E�E�H�[�@�A�����J�Ō�̓� CIVIL WAR �i�Q�O�Q�S�N�A��=�p�A�����F���Y���ށj  �@���O���C���[�W���Ă����̂́A�g�����v�Ƃl�`�f�`�������N�������f�ƍ����̐K�n�ɏ�����A�u���b�J�C�}�[��G�����b�q���̂��o�J�ȃh���p�`�f��B�Ƃ��낪���������Ă݂�A���X�N���ڂ݂邱�ƂȂ���n�ɔ�т��ސ��W���[�i���X�g�̐^���ȃh���}�������B �@�f�悪�����J�������_�ŁA���łɃV�r���E�E�H�[�i����j�͖����B�����ŏ������o���l���o���o���ȂS�l�̃W���[�i���X�g���A�P��̎Ԃɓ��悵�āA��s���V���g����ڎw���B�얞�����V�L�ҁA��������̒j���L�ҁA���̓����̓`���I�J�����}���i�L���X�e���E�_���X�g�j�A�삯�o���̃J�����}���i�P�C���[�E�X�s�[�j�[�j�ƁA��v�o��l���̃}���A�[�W���͏�X�B���̘V��j�������X���s����]�R��ނ�����ŁA���[�h���[�r�[���ɕ���͐i�s����B �@�r�p���������݂��e�������匚�����̋K�͊��͈����B�ŏI�Ղł̓��V���g���̌����ꂽ��p�����ɂȂ邵�A����̕��ʂ��������B�ǂ��܂ł��Z�b�g�łǂ����炪�b�f�Ȃ̂��͕s�������A�Ƃɂ������p�X�^�b�t�Ɍh�ӂ�\�����B �@���a�}���̃e�L�T�X�B�Ɩ���}���̃J���t�H���j�A�B�������{�R�̒��S�Ȃ̂̓~�X�}�b�`�������邪�A�u����͌����ł͂Ȃ��G�ł�����v�Ƃ����G�N�X�L���[�Y��\�����邽�߂ɁA�����Ă��������̂��ȁB�F���A���݂����ɐg���ł����ݍ������������B �@���āA�S�l���ꂼ��Ɍ�����͂��邪�A��͂�L���ɂȂ�̂͊ј\�����o�Ă����_���X�g�ƁA�g���n�h�����𗈂ĕ����Ă��邩�̂悤�Ɍ�����i�Ⴋ���̃N���X�e���E�X�`���A�[�g�ɂ������j�X�s�[�j�[�Ƃ̑��Ȏt��W���낤�B �@�����ƌ����Ȃ�A���Ԃ�A���b�N�X�E�K�[�����h�ē���ԕ`�����������̂́A�삯�o���J�����}���́i�K�������m��I�ȕ�������ł͂Ȃ��A�����̋�݂����j�����Ȃ�ł��ˁB �@���Ղ̔ޏ��̓V���b�L���O�Ȍ��i��O�ɃJ�������\�����Ȃ��قǂ̃i�C�[�u�������A���ՂɌ������ɂ�ĉ��O�Ō��������Ȃ��Ȃ�ĈӊO�Ƀf�L���ʂ��B�㔼�̎R��ʼn�ȏC���������������́A�_���X�g�Ƃ̊W���t�]�������̂悤�ɑ�_�ɁB �@�Ƃ͂����������ϋq�ꓯ�́A�u�����Ƃ�������Ɗ��ꂽ���炢�̎�������Ԋ�Ȃ��v���Ƃ͏d�X���m�B����ŗ��Ƃ����Η\������悤�ɒ��߂Ă���ƁA���`��A�Ă̒肾�����B�_���X�g�����ɂȂ�W�J���̂͂��܂�Ƀx�^�Ȃ�Ȃ��̂Ǝv�킹�����邪�A����ׂ��͂��̒���ɃX�s�[�j�[�����s�����B�t�����ǂ�����z�����A�l�Ԑ������E�ƓI�Ȑ��i�����j��D�悳����W���[�i���X�g�������ɂ���B �@�O���Ƀ_���X�g�����ɂ����A�u���₵�Ă�����肪�Ȃ�����A�������͂����L�^�ɓO����v�Ƃ������t���A�d�w�I�ɋ��ɔ���B �i�Q�O�Q�S�D�P�O�D�Q�Q�D�L�j �G�C���A���F�������X ALIEN: ROMULUS �i�Q�O�Q�S�N�A�āA�����F���퐶�j  �w�G�C���A���x�V���[�Y�Ƃ����e�n�w�̐���E�z���̃C���[�W�������������ǁA������A�f�b�h�v�[���������Ă����悤�ɁA�f�B�Y�j�[�����ɕ������킹�Ăe�n�w���B���ʁA�E���o�������悩��@��o���ꂽ�̂Ɠ��l�A�G�C���A�����܂��A�f�B�Y�j�[�����ӂ̋�����`�ɏ���āA�F���̕Ћ����珢�҂���邱�ƂɁB �@�V���[�Y�Ō����i�`�u�o�͏����āj�ʎZ�R�߂ɂȂ邾���ɁA���ʂȂ疼�̒m�ꂽ�o�D���N�p���ēƎ��F���o�������Ȃǂƍl����͂��B�Ƃ��낪�o�ꂵ���̂́A�ӊO��A�����ɋ߂����U�l�g�B����ōŌ�܂ŋ��S�͂��ۂĂ���ȂƂ��Ԃ���Ȃ��猩�n�߂����A�������́w�h���g�E�u���[�Y�x�̃t�F�f�E�A���o���X�ē��B���I��鍠�ɂ́u�V���ȃ��v���[�v�̓��������Ƃق��ł����B �@�`���̐A���n�V�[�N�G���X�����w�G�C���A���x���w�u���[�h�����i�[�x���v�킹����肾�������A�U�l�g���F���ɔ�ї����Ă���͉ߋ���̕��͋C���p���B���������������ł���F���D��X�e�[�V�������ɁA����q���ɕ����̖��������o���X�g�[���[�\�����A�ς�҂̋ٔ�����ۉ��Ȃ��������Ă�B �@������ߋ���Ɠ��l�ɁA�{��ł��A���h���C�h�i�f�r�b�h�E�W�����\���j���A�X�g�[���[�̋N���ݏo���d�v�Ȗ�����S���Ă����B �@���������A�ߋ���Ƃ����A���ɑ����i�K�ŁA��P��̖^�o��l���i���v���[�ł͂Ȃ��j����݂������Ă����̂ɂ́u�������v�Ǝv�����ȁB����Ŗ����̂U�l�g�̕��ꂪ��C�ɐg�߂Ȃ��̂ɂȂ����B�����܂łɉ��x����ʂɂ͉f���Ă����̂����A�炪�����Ă��Ȃ��������̂�����A���̂��킩�������ɂ́A�Ȃ�����u�������v�������B �@�ݒ�Ŗʔ����Ǝv�����̂́A���ՁA�u�G�C���A���ɂ͖ڂ��Ȃ��A���Ƒ̉������m���ďP���Ă���v�Ɣ�������Ƃ���B����Łu������̉��Ɠ����x�܂ŏグ�A���𗧂ĂȂ��悤�ɍs����������v���Ęb�ɂȂ�킯�����A��������ČQ��Ȃ��G�C���A���ǂ��̊Ԃ�Â��ɐÂ��ɂ��蔲���Ă����l�́A�i���킸�Ƃ��ꂽ�j�w�h���g�E�u���[�Y�x���B �@�܂��A�A���o���X�ē��A�������ɓ�Ԑ����̓}�Y���Ǝ��o���Ă����l�q�B�䂦�ɒ����͂���𑱂��Ȃ��������A��ʂɂ����ẮA�����������������������ȂƂ���������Ȃ������X�B �i�]�k�Ȃ���u�̉��Ɠ������x�v�Ƃ��������́A�r�����Ȃ��ߍ��Ȋ��Ƃ��Đݒ肳�ꂽ���̂Ǝv����B�Ƃ͂����A�������N�̓��{�ɂ����ẮA�P�Ȃ�Ă̕������ɂȂ�������Ă܂����ǂˁB�j �w�G�C���A���x�V���[�Y�̓`���ɑ���A�N���C�}�b�N�X�͓�i�\���B�����A�l�I�ɂ́A���̈�i�ڂ̕��ɁA��芅�т����B �u���_���̑̉t�őD�̂Ɍ�������A�e�͂���ǂ��G�C���A���͌��ĂȂ��v�Ƃ�������B�Ƃ��낪�d�͂��J�M�ɁA�ӕ\��˂����A�C�f�A�ŁA�V�q���C���i�P�C���[�E�X�s�[�j�[�j����n��E�����ł��ˁB�{��̍��肽�����A���Ղ��炵�����d�͂���ɂ��Ă����̂́A���̕����������̂��B �@�l�ԂƃG�C���A���Ƃ̃n�C�u���b�h�̓L���������ŕ|���Ȃ��������i��R��ɏo�Ă������Ƃ̃n�C�u���b�h�̕������i�A�Ռ��I�j�A���f���ɂԂ���Ƃ����^�C�����~�b�g�ݒ�͂܂�Ō����Ă��Ȃ��������Łi�����āA�ǂ݂̂��P�b�ł������G�C���A���̌Q�ꂩ�瓦����������j�A�P�`���������Ƃ�����Ȃ��ł͂Ȃ��������A�܂��͖����̂����f�B�Y�j�[�ŃG�C���A���̃X�^�[�g�B �@����A�g�����X�h�������Ȃ�A������܂��ςɂ�������Ȃ����낤�ȁB �i�Q�O�Q�S�D�X�D�P�X�D�L�j �t�H�[���K�C THE FALL GUY �i�Q�O�Q�S�N�A�āA�����F�ъ����j  �@���N�ς��f��̒��ŁA�����܂ł̃i���o�[�����B �@�h�h��ȃA�N�V�����A�n�C�Z���X�̏��A�����点�C���̗����͗l�A���藈�錠�͎҂̉A�d�B�v�f�ɕ���������A�ǂ������Ă��ڐV�����̓[���Ȃ̂����i�j�A��ԂɊ�����̂͌ÏL���ł͂Ȃ��A�n���E�b�h��������̉��������B�܂��Ɍ�y�f��̉������s�����ł��ˁB �@��l���J�b�v���̎B�錀���r�e�f��i���͋C�́w�f���[���x�����A�b�͒f�R�ʔ������j���X�^���g�V�[�����ڂȂƂ���Ɏ����Ă��āA�{�̕����ł����ς��i��ς����A�N�V�����̘A���B�����肵�Ă���ɂ͂Ȃ��B �@����ɂ͍ĉ��̃��C�A���E�S�Y�����O�i�X�^���g�}���j�ƃG�~���[�E�u�����g�i�V�l�ēj���A�����f��̃X�y�[�X�J�E�{�[�C�ƃG�C���A���K�[���̐S�����߂ɉ������āA�X�^�b�t�E�L���X�g�̖ʑO�Ō݂��̖{�����Ԃ��������X���~�̂����ȂA������|�̋ɂ݂������B �@�A�[�����E�e�C���[���W�����\���i�f��X�^�[���j�̏��o��V�[���̌������ɂ������o�����ˁi�����̕��ɂ����Ăق����̂ŁA�����ďڂ����͏����܂���j�B �@�Ō�Ɂi�G���h�N���W�b�g�ɂ��P�J�b�g����������Ă������j�X�^���g�}�����������S�Y�����O�́A���̂܂��X�^���g��S�������{���̃t�H�[���K�C�����ɑ傫�Ȋ��т��B �@�ȉ��͗]�k�B�R���i�Ђ̐��N�Ԃ́A�T�}�[�V�[�Y���ɓ���ƃA���R�~�⋰���̂悤�ȃu���b�N�o�X�^�[�n�̑�삵�����J���ꂸ�A��X�̂悤�ȑ�l�̗m��t�@���͂��Ȃ�ɂ����Ă��܂����B �@���̓_�A���N�̓T�}�[�V�[�Y���ɓ����Ă��A�w�t���C�E�~�[�E�g�D�[�E�U�E���[���x�A�w�c�C�X�^�[�Y�x�A�����āw�t�H�[���K�C�x�Ƃ������m��t�@�����҂̍�i�����X�ƌ��J����Ă���B �@����A�n���E�b�h�͂悤�₭�{�i�I�ɒE�R���i�𐋂����悤�ł��ˁB�悩�����悩�����B �i�Q�O�Q�S�D�X�D�P�R�D�L�j �c�C�X�^�[�Y TWISTERS �i�Q�O�Q�S�N�A�āA�����F����L�K�j  �@�W���̌㔼�͖����̂悤�ɗ��J�x���狏����䕗���ɂ������A���̘b��삪����Ɍ��ɍs�����B�~����͎̂d�����Ȃ�����ǁA�A��̓d�Ԃ��~�܂����Ⴝ��n��������ȁi�܂藋��䕗���|���āA�����ɔ�т��߂��Ƃ����\�}�j�B �@���܂��ɍ����̃V�l�R���͗m��ɗ₽���A���J�Q�T�ڂɂȂ�ƃ��[�j���O�V���[���̃V���[�ɉꂪ���B�d�Ԃɏ��Ȃ��Ɖf������ɍs���Ȃ��h�c�ɕ�炵�̐g�Ƃ��ẮA�͂Ȃ͂��\�肪�g�݂Â炢�B �@����Ȃ킯�ŁA���肩��P�J���ȏ�������Ă���A���i�s���Ȃ��f��قł悤�₭�ӏ܂ɋy�ׂ��̂����A���`��A�҂����ꂽ���A���]���傫�������B �@���͔�Ȃ��̂���I�Ƃ��������̘b�ł͂Ȃ��i96�N�Łw�c�C�X�^�[�x���������ɂ͐����s�v�ł��ˁj�B �@�����Ɗ̐S�ȃX�g�[���[��L�����̍�肪�A������邭�炢�ɎG�Ȃ�ł���B �@���Ƃ��Ύ����Ԃ�H�ʓd�Ԃ����������Ă���̂Ɠ����J�b�g�ŁA�l�Ԃ������ē����Ă����i���肦�ˁ[����I�j�B �@���邢�̓N���C�}�b�N�X�Ɍ�������ʂŁA��������������u�����Ăт�����v���߂����ɒ��Ɍ������B��������Ȃ����Ƃ��炢�A�I�N���z�}�l�Ȃ炨�O��Ɍ����Ȃ��Ă��m���Ă���āI �@�q���C���̋C�ۊw�҂��������f�C�W�[�E�G�h�K�[���W���[���Y�́A�ꕔ�ōD�]�݂��������ǁA�����猩��Ɓu�炾���̏��D�v�Ƃ�����ہB���̒��x�̔�����������A�c�O�Ȃ���n���E�b�h�ɂ͑|���Ď̂Ă�قǂ���i���ہA�`���̃V�[�N�G���X�Ŏ��ዾ���q���A�G�h�K�[���W���[���Y�Ƃ܂��������^�C�v�̔������������j�B �@���Ƃ��璲�ׂĂ݂���w�U���K�j�̖��Ƃ���x�Ɏ剉�����q���Ƃ킩�������A�ӏܒ��͂܂������v�����������B��ۂ�������ł��ˁB �@�ޏ��̏o���V�[���ř��ڂ��ׂ��́A���Ď������w�F�����̎��ɐӔC�������āA���Ƃ̔[���ŋ����V�[�����炢�ł͂Ȃ��������B �@���Ƃ̕�e���Ɏv���������u�d�q�v�̃A�r�[���o�Ă����͉̂��������������A���m��ʒj�i�O�����E�p�E�G���j�����܂�ɖ��x���ɉƂɓ���Ă��܂��̂ŁA�������ɕ@���B �@���̃p�E�G���́A���̂Ƃ���剉�삪�����Ă���悤�����ǁA���̐l�A����ς����Ƃ������A�w�g�b�v�K���x�݂����ȃ��C�o�������炢��������������Ȃ��H�@�{��ł��A������Y�������O���̕����A�P�ʂɓ]�����㔼���������������Ă����悤�ȁB �@�G���f�B���O�̋�`�V�[���ŁA�ԂɎ����������ϑ��p�̃M�~�b�N���A�ނ��ړI�O�g�p�����V�`���G�[�V�����͖ʔ����������ǂˁB�{���ɂ���Ȃ��Ƃ���z����������f�疜�����ǁA�����͋����܂����B �i�Q�O�Q�S�D�X�D�P�R�D�L�j �f�b�h�v�[�����E�����@���� DEADPOOL & WOLVERINE �i�Q�O�Q�S�N�A�āA�����F����L�K�j  �@���N���O�ɃA���R�~�f��͑��Ƃ����g�Ȃ̂ŁA�{��̐��E�ς�p���f�B���悭�킩��Ȃ��Ƃ��낾�炯�B����ł��u�e�n�w���f�B�Y�j�[�ɔ�������ĉ]�X�v�Ƃ����y�������l�^�̘A���ɂ̓j���}��������ꂽ�B �@���ł���ԃE�P���̂́A�f�B�Y�j�[�̃L���v�e���E�A�����J���J���I�ŏo�Ă����̂��Ǝv������A���͂e�n�w�̂��̐l�������E�E�E���ăl�^���ȁB �@�I�Ղɓo�ꂷ��S�l�̏����l���܂߂āA�{��͏����䂭�e�n�w�A���R�~�f��ւ̔҉̂������̂�������Ȃ��ˁB �@�ŁA���������w�k�n�f�`�m�^���[�K���x(2017)�Ŏ��E�����@�������{��ł��s����`�I�ɕ���������Ă̂��A�e�n�w���f�B�Y�j�[�ɔ������ꂽ���Ƃ̕��Y���������킯�����A�����̓}���`�o�[�X�������o���āA���̐��������Ă���B �@�������A�����J�Ƀf�b�h�v�[�����������̃��j�o�[�X�ŕ����̃E�����@�����Ɖ�\�\����A���R�~�ǂ���̒�g���E�����@�����i�j���O���Ȃǂ��ā\�\��ԋ������ȓz��I��ł�B �@�ł����A��ʘ_�Ƃ��ă}���`�o�[�X���āu����v���Ǝv���܂��H �@�ЂƂ���A�^�C���g���x���ʼn��ł�����ɂ��Ă��܂��r�e��삪�����A�ϋq�Ƃ��Ă͑傢�ɃV�������������������B����T�C�h�̐l�Ԃɂ͕֗��Ɍ�����̂�������Ȃ�����ǁA���ł�������Ď��͂���قǖʔ����Ȃ��B�Q�X�̋ɂ݉������̂��悤�ɁA���ȊO�Ɂu���v�����Ă͂����Ȃ����A���҂͉i���Ɏ���ł��Ȃ���Ȃ�Ȃ���B�����łȂ��Ȃ牽�̐l�����H �@���̈Ӗ��ɂ����āA�}���`�o�[�X���āu�y����̃^�C���g���x���v���Ǝv���B �E�E�E�Ƃ����悤�Ȃ��Ƃ���S�Ԃ₫�Ȃ���ӏ܂��Ă�����A���̂����ɓ��̃f�b�h�v�[�����܂���������|�̂��Ƃ�����ׂ�o�����B �@���������A�킩���Ă�Ȃ���ȁA����I �o�r �Ȃ�قǁA�A�_�}���`�E���z���̊[���́A�݊�ɂ��s��ɂ��Ȃ�킯���B �i�Q�O�Q�S�D�X�D�P�R�D�L�j �t���C�E�~�[�E�g�D�E�U�E���[�� FLY ME TO THE MOON �i�Q�O�Q�S�N�A�āA�����F�`�I�L�^���j  �@�\���҂��������̈�ۂ́u����w�J�v���R���P�x�v���Ċ������������A����͗v�f�̂����ꕔ��������ł��ˁB �@����̍L���ƊE�l�ɕ������X�J�[���b�g�E���n���\�����A�t�H�[�h�E���[�^�[�X�̖�����ɏ�肱�݁A煘r�Ԃ���⊶�Ȃ���������I�[�v�j���O�ŁA���݂̓I�b�P�[�B��������������A���e���|�悭����Ă��邩��A�ޏ��������炵�����{�̖�l�i�E�f�B�E�n�����\���j�̕s���ȓo��V�[����������B �@�剉�o�D����������˂�ƁA���X�ɂ��Ď������q�[���[���������A�ςĂ�����̓V���������B���������̋���Ƃ��Ȃ����n���\���́A�{�f�B�̋Ȑ������łȂ��A�I�c���̏o�������������낤�ȂƎv���i�ߑ���Ɋւ��ẮA��������������ʂ����悤�Ɍ����邯�ǂˁi�j�B�����A���ւ����H�j�B �@���䂪�t�����_�̃��P�b�g���ˊ�n�Ɉڂ��Ă���́A���_�Ɛ����Ƃ��ė����邽�߂Ȃ��i��I�Ȃ��ޏ��ƁA�����ȑł��グ�ӔC�ҁi�`���j���O�E�e�C�^���j�Ƃ̊ԂŁA������A�Η�����A�B��������A���}���X����̖��уT�[�r�X�B�T�X�y���X����������҂�܂Ԃ��A�V���A�X�Ɍ��߂�Ƃ���͂����茈�߂��ł��ˁB �@�ォ�璲�ׂĂ݂���A�ē̃O���b�O�E�o�[�����e�B�͐��씨�̎d�������������l�����A�r�{�Ƃ̃��[�Y�E�M�����C�Ɏ����Ă͓��Ɏ��т̂Ȃ��l���B������v���A�Q�l�Ƃ��]�݂������ŗǂɋ߂��d�������Ă��ꂽ��Ȃ����ȁB �u�[�݂��Ȃ��v�ƕ]����l�ɂ͏���Ɍ��킹�Ă��������B�f��ɂ����ẮA��ʑ�O�Ɂu�����A�ʔ��������v�ƌ��킹�邱�Ƃ����`�Ȃ̂ł��B �@�Ƃ���ŁA�{����ςĂ��āA�v���������D�ɗ��������Ƃ�����B �@����́A�\�A���Ȃ����ʒ��������s���Ȃ������̂����B �@�������̂Ƃ���A�č��̃A�|���P�P�����P�X�U�X�N�Ɍ��ʂւ̈�ԏ����ʂ����Ĉȍ~�A�\�A�͂Ȃ�����������݂邱�Ƃ������Ȃ��Ȃ����B �@���̗��R�Ɋւ��āA����܂ł́i���āA���������I�ȏソ��������Ă�킯�����j�A�P�ɂ��̋Z�p���Ȃ��������炾�ƁA�i�C�[�u�Ɏv������ł����B�������ł͂Ȃ��A�����̈�ʐl�������Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�����A�F���J�������ɂ����āA��ɕč��Ɉ����Ă����\�A�ɁA���ꂾ���̋Z�p�̒~�ς��Ȃ������͂��͂Ȃ���ł���A�悭�l����B �@�����Łw�t���C�E�~�[�E�g�D�E�U�E���[���x�̃E�f�B�E�n�����\���̓o�ꂾ�B��߂������{�E���̖��ɕ������ނ͌����B�u���̃v���W�F�N�g�ɂ͕č��̈АM���������Ă�B�S���E�Ɏ��s���g���p�h����킯�ɂ͂����Ȃ�����A����Ɍ��ʒ�����͂����t�F�C�N�摜�𗬂��v�ƁB �@�����Ȃ̂��B�\���ȋZ�p�����邩�琬������Ƃ͌���Ȃ��B�Ȋw�ɂP�O�O���͂Ȃ��B�P��ڂ́u���s�v�Ŗ��_��o���A�Q��ځA�R��ڂŐ�����ڎw���Ȃ�Ă̂��퓹���B�A�|���P�P�������܂��܂P��ڂ̒���Ő����ł����̂́A�C�[�O�����R���ꐡ�O�Œ����ł������Ƃ��܂߂āA�����ɋ��R�ƍK�^�ɕ����Ă���B �@�Ƃ��낪�\�A�̗��ꂩ�炷��ƁA�č����ꔭ�ڂŐ��������ȏ�A��������������Ɠ������Ƃ�������Ȃ��Ȃ����B�u�Q��ڂ̎��݂Ő������܂����v�Ȃ�Ă��ƂɂȂ�����A�����ǂ��납��p���B���ɂQ��ɂP��͐�����������Z�p���������Ƃ��Ă��A�Ȋw�ɐ�͂Ȃ��ȏ�A�����ł����s����\���̂��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ȃ����������ł��ˁA�����ƁB�АM���������Ă邩��B���̂�����̎���́A�l�ޏ��̉F����s�̐�����A�g�p�Y�h�K�K�[�������x�ƍĂщF���ɑ���o���Ȃ��Ȃ��Ă��܂������ƂƎ��Ă���B �@������l����ƁA���ɃC�[�O���𑀏c����A�[���X�g�����O�D�����u�����v������̂����d���Ă�����A���邢�͔R����Łu���̂������v�ƂȂ��Ă�����A���̐��J����Ƀ\���[�Y�����ʈ�ԏ����ʂ����Ă����E�E�E�Ȃ�ė��j�����蓾���̂ł͂Ȃ����ƁA�ӂƂ���Ȃ��Ƃz�����T�T���N�ڂ̂V���ł������B �i�Q�O�Q�S�D�V�D�Q�R�D�L�j �w�N���C�G�b�g�E�v���C�X�x�̐��Ԋw  �@���Ăɑ�R�삪���J���ꂽ�f��w�N���C�G�b�g�E�v���C�X�x�V���[�Y�B��P�삩���т��ē�Ȃ̂́A�s�q�Ȓ��o�������̃G�C���A���ǂ����A����ړI�ɐl�Ԃ��E���̂����B �E�z�炪���̂�H���Ă���l�q�͌����Ȃ��B �E�w�F���푈�x�̂悤�ɘA�ꋎ��킯�ł��Ȃ��B �E�{�Ɓw�G�C���A���x�V���[�Y�̂悤�ɗc�̂̏h��ɂ����Ă��Ȃ��B �@�����ł���ΊX���イ���g���p���l�h�̂Ȃ����̂Ŗ��܂��Ă��܂������Ȃ��̂����A���ۂɂ͂��̊Ԃɂ����̂͏����Ă���B �@�ƂȂ�ƍł��W�R���̍��������́A�u���肪�����܂ōl���Ă��܂���ł����B���߂��Ȃ��܂ܑ�R��܂ŗ��Ă��܂��܂����v�Ƃ������Ƃ��낤�i�j�B �@����Ȃ����Ȃ�Ȑݒ�Ői�߂��Ă����������낤���A���̃G�C���A�������̍s�����āA�n����Ɏ��݂���ߐH�b�����̍s���Ɣ�ׂ�ƁA���炩�ɗ��ɔ����Ă����ł���B �@�ߐH�b�̐��Ԃ��ʂ���A�i�P�j�Q��ŕ�炵�A���͂������Ď������邩�A�i�Q�j�P�Ƃŕ�炵�A�꒣�肩�瓯�ނ�r�����邩�̂ǂ��炩���B �@���̓_�A���̃G�C���A���͖��W���čs�����邱�Ƃ����Ƃ킸�A���ޓ��m�ő����l�q�������Ȃ��̂ŁA���炩�Ɂi�Q�j�ł͂Ȃ��B �@����ƂĈ���Ȑl�Ԃ��P���i�ɂȂ�ƁA�Ă�Ńo���o���ɏW�܂��Ă��āA���ɎE�������Ȃ̂ŁA�K�������i�P�j�ł��Ȃ��������B�H�����߂ɎE���Ƃ������؎����͂Ȃ��̂ŁA���͂������C���Z���e�B�u�͐����ɂ����̂ł��傤�ˁB���̂����P�Ƃł��e�Ղɓ|����ア�푰�i�l�ԁj��ɂ��Ă���킯�����B �@�l����H������A��̂����炩�̌`�ŗ��p�����肷�邽�߂łȂ��̂��Ƃ���A�z��͂Ȃ��l�Ԃ��E���̂��H �@���ɍl������̂́A�E�C���u��y�̂��߂̎���v�ł���\�����B���ہA��X�l�Ԏ��g��������s�����A�����̒��ł��m�\�̍����`���p���W�[�Ȃǂł́A�ߐH���邽�߂ł͂Ȃ��A�V�т̈�Ƃ��ď����������s�����ώ@����Ă���Ƃ����B �@�����A��y��V�тƂ����̂͋C���炵�ɂ�邩��ʔ����̂ł����āA���𗧂Ă�l�Ԃ����邽�тɎE���܂����Ă�����A�����炸�O�����Ⴂ�܂���ˁB �@������������Ƃ��ẮA�w�G�C���A��vs�v���f�^�[�x(2004)�̒��ŁA�Ⴂ�v���f�^�[���u�ʉߋV���v�Ƃ��ăG�C���A�������Ƃ����ݒ肪�������B�����A�������̃v���f�^�[���G�C���A�����F�E���ɂ��悤�ȂǂƂ͍l���Ȃ��������A���������l�Ԃ͔�͂����āA�ʉߋV��̑ΏۂɂȂǂȂ�Ȃ����낤�B �@�����Ŏ��ɕ��シ��̂́A�E�C���z��́u�{�\�ɑg�݂��܂�Ă����v�Ƃ����\�����B����Ȃ�l�����������O�����ƂȂ��E�C�𑱂���i�Ƃ������A�ނ��둱�����ɂ͂����Ȃ��j���R�ɂ͂Ȃ�B �@�Ƃ͂����A������n����̕ߐH�b�̍s���ƈ�����ׂ�ƁA�傫�ȋ^�╄������B�Ƃ����̂��A�쐶�������Ė��ʂȑ̗͈͂�؎g��Ȃ��炵���B���������Ă��鎞�����A��J���Ċl����T���������A�댯��`���ďP�����������肷�邪�A�����������Ă���A���܂łł��؉A�⑃���ŋx��ł�B �@�Ȃ��Ȃ�A�����鐶���ɂƂ��Ă͎����̈�`�q�̃R�s�[�������悭�c�����Ƃ������{�|�ł���A�����W����悤�ȗ]�v�Ȗ{�\��ˑR�ψقŐg�ɂ��Ă��܂����̂��́A�����ɔs��ē�������邩��B �@���̃G�C���A���������i���Ȃ킿���`���[�h�E�h�[�L���X�������Ƃ���́u��`�q�̏�蕨�v�j�ł���ȏ�A���ʂɑ̗͂����Ղ���悤�ȍs�����{�\�ɑg�݂��܂�Ă���Ƃ͍l���Â炢�B �@�Ō�ɍl������̂́A���̃G�C���A�������҂��̈ӂ̂܂܂ɓ�������A�����̈ӎu�Ƃ͖��W�ɐl�Ԃ���|���悤�Ƃ��Ă����\�����B �@���̉��҂��́A���ނ̉��Ȃ̂�������Ȃ����A�َ�̎x�z�҂Ȃ̂�������Ȃ����A���̂̂Ȃ��_�Ȃ̂�������Ȃ��B �@�������z�炪���������������ʂ̉����ɖ�����ꂽ�葀��ꂽ�肵�āA�V���b�J�[�̐퓬���̂��Ƃ��l�Ԃ��P���Ă���̂��Ƃ���A�ꌩ�ړI���Ȃ��A�̂Ƃ��Ă̑�������������ɂ��ĎE�C�𑱂��闝�R�������ł���C������̂��B �i�Q�O�Q�S�D�V�D�Q�O�D�L�j �N���C�G�b�g�E�v���C�X�F�c�`�x�P A QUIET PLACE: DAY ONE �i�Q�O�Q�S�N�A�āA�����F���Y���ށj  �w�N���C�G�b�g�E�v���C�X�x�V���[�Y�̑�R��ɂ��đO��杁B���Ԏ��Ƃ��Ă͑�Q��̖`�������Ƃ����炭�����ŁA���̓��킩������ւ̋}�]��`���������Ԃ͐��ۂ������N�₩������������A����T�C�h������ڂP�{�Ɏd���Ē��������Ȃ�̂��[���ł���B �@�������P�`�Q��ڂ̃N���G�C�^�[�̃W�����E�N���V���X�L�[���A�x�������Ƒ��̕���Ƃ��Ă�����\�z�����̂ɑ��A����Ń��K�z���������p�����}�C�P���E�T���m�X�L�ḗA�P�̌ǓƂȍ��Ƃ��̃y�b�g�̕���ɕϊ������B���傤�ǔނ̑O��w�o�h�f�^�s�b�O�x�������ł������悤�ɁB �@�q���C���̓z�X�s�X�Ŏ�����҂����T�~���i���s�^�E�j�����S�j�B���m�̃��[�x���i�A���b�N�X�E�E���t�j��Ɗό��ɏo�����Ă���Œ��ɃG�C���A���̏P�����n�܂�̂����A�w�o�h�f�^�s�b�O�x�̗v���v���Ŏ���̃j�R���X�E�P�C�W�ɗ��E���t�́A����͏��Ղ����̓o��ɂƂǂ܂�B �@���[�x�������ł͂Ȃ��B�T���m�X�L�̓T�~���Ɉ����ȁu�݂苴���ʁv�ȂǗ^�����A�Ɍ����ɂ����Ă����l�Ƃ̐G�ꂠ��������铹����܂���B�r���ŏo������c���Z���Ƃ͑��X�ɕʂ�A�����荇�����p���l�G���b�N�i�W���Z�t�E�N�C���j�����炭�͎��Ɉ�����̂��B �@����ȃT�~���ł�������A���̏Ռ��̃��X�g�V�[���́u����v���Ǝv�����ˁB�u�݂�Ȉꏏ�ɖ��E�����܂����Ƃ��v�ł��A�u���Ԃ̖����~�����߂Ƀq���C�����]���ɂȂ�܂����Ƃ��v�ł������Ȃ��A�v���c�����Ƃ������Ȃ��Ȃ����P�̍����A�����ЂƂ�̂��߂ɁA�����ЂƂ�őI�A����Ӗ��ł̑������B��Ɍ������Q�O�ɋt����ăT�~�����}���n�b�^����k�サ���̂́A�������т邽�߂ł͂Ȃ��A�����ׂ��ꏊ�ɂ��ǂ蒅�����߂������̂��B �@�����ς̈قȂ�ϋq�́u���������I���͔߂����v���́A�ʂẮu�����Ȃ��v���̂Ɣ�������̂��낤���ǁA�T�~���̒u���ꂽ�́w�[���E�O���r�e�B�x�Ŏ���ɐ�����ӗ~�����߂����T���h���E�u���b�N�Ƃ͖��炩�ɈႤ���Ƃ𗝉����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@�B�e�̖ʂŐ���������̂́A���ՂɖK����x�̌Q�O�p�j�b�N�V�[���B�H����f���T�~�����A�J�����͎��瓮�����Ȃ���A�o�X�g�V���b�g���炢�̑傫���ʼn��X�ƒǂ��B�����炭�S�����b�f�ł��낤�w��̔j��ƎE�C�̏�i�́A�]���Ă��̃T�~���̗��e����_�Ԍ����Ă�����x�Ȃ̂����A���ꂪ�u�����N���Ă���̂��킩��Ȃ��v�Ƃ������ʂ������āA�t�ɔ��^���B �@����Ő���������Ȃ��Ǝv��ꂽ�V�[�������X�������̂ŁA���Ƃ݂��������Ǘ����Ⴈ���B �E�ŏ��Ƀo�X���P��ꂽ�Ǝv������A���̃J�b�g�ł̓T�~������̉E���������o�܂݂�ɂ��č~��Ă����B���������C�ɂȂ邱�Ƃ�����Ȃ�A�u�Ȃ��E���g�������o�ɂ܂݂ꂽ�̂��v���������J�b�g���~�����B �E�T�~�����C�������������������\���قǂ̊ԂɁA�u�����o���ƏP����v�Ƃ����d��ȏ���҂ɂ��A�����ԌR�p�@�ɂ��m��n���Ă���B���₢�₢�₢��A���ꂪ�m�F����A���m�����ɂ͏��Ȃ��Ƃ������͂����邾�낤�B�����܂ŏȗ�����̂͊ϋq�ɊÂ��������B �E���l�ɁA�����ɉB�ꂽ�Z���������������R�͎������ɂ͖��������A�P�`�Q����ςĂ��Ȃ��ϋq������̂����A�܂��P�`�Q����ς��ϋq�ɂƂ��Ă��A�菇�Ƃ��Đ������ׂ���������Ăق����Ƃ����v��������B���Ƃ��Ζ��̕��Ɂu�����ɓ���������������͋߂Â��Ă��Ȃ������́v�݂����Ȃ��Ƃ����킹��ƁA�w�G�C���A���Q�x�̃j���[�g�݂����ȋ��͂ȃL��������ꂽ�͂��Ȃ̂ɁB �E�G�C���A���̂�����肵�������͂��������悭�`���Ă��邯�ǁA��������ǖʂ��ѓn�����肷�铮���́A�w�X�p�C�_�[�}���x�V���[�Y�̍ŏ��̍��ɕC�G����t�ق��B�V�����u�e�w�Z�p��������܂��傤��B �E�T�~��������A�p�[�g�ɗ������V�[�������邪�A���փ}�b�g�̉��ɒu�������Ȃ����ǂ����m���߂�i���ʁA�����炸�Ƀh�A���R�j��j�悤�ȕ`�ʂ�����̂ŁA�������{���Ɏ���Ȃ̂��A�K���ɑI���l�̉Ƃɉ������낤�Ƃ��Ă���̂����͂����肵�Ȃ��B���̂ւ���������w�^�N�\���Ǝv���B �E�T�~���̂��߂ɖ��T���ɏo���G���b�N���A��ނ̔畆�݂����Ȏ����̊ۂ����̂�����B������G�C���A���̗��Ȃ̂��Ǝv������A����Ă��������ǂ��͂��������A���̃P�o�P�o�������̂�H�ׂ����Ȑ����B����ȏ�̐����͂Ȃ��������A��S��ւ̊܂݂Ȃ̂��H �E�T�~���̃J�[�f�B�K���ƃG���b�N�̃W���P�b�g���������ꂽ���R�����R�Ƃ��Ȃ��B�Ƃ������A�T�~���̕��ɂ͂������闝�R�����������Ƃ͂��Ƃł킩�������A�G���b�N���ق��Ă���������͕̂s���R���Ǝv�����B�����ł��Ȃ��̂ɁB���Ȃ݂ɃG���b�N�͍ŏI�Ղ܂ŗ��V�Ƀl�N�^�C����߂Ă���B���������Ȃ�Ō�܂Łu�������p���l�v�̃X�e���I�^�C�v��ʂ��Ăق��������ȁB �E��Q��ōő�̂�������L�����������W���C�����E�t���X�[�́A����Łu���x���W����v������̂��Ǝv������A����ς肽���������ƂȂ���ł��ˁB�ނ���w�F���푈�x����]�p�����Ǝv����\���˂�w�������Ⴄ�B�ŁA���̋֒f�̍s�ׂ�ڌ����Ă��܂����q�ǂ��Ƃ̊W���A����܂�������������Ȃ���B �@�Ō�ɂP�`�Q��ƍ���Ƃ̑傫�ȈႢ�������P�w�E����ƁA�N���V���X�L�[�͓o��l�������Ɂi���Ƃ��Ή䂪�q�̖����~�����߂Ƃ������j��ɕK�v�ȏ�ʂł��������o�����Ȃ������B �@�Ƃ��낪�T���m�X�L�͉J���ɕ���ĉ�b����������A���ɂ��Ԃ��ăX�g���X���U�̋��т��グ��������ƁA���Ɉ����ɋ֊���j��B �@����ɉ�����N���V���X�L�[�́u�T�����߁A�킩���ĂȂ��ȁv�Ƌ�����݂Ԃ�����������Ȃ�����ǁA���l�Ɏd����C����Ƃ����̂͂����������ƂȂ̂�ˁB �i�Q�O�Q�S�D�V�D�P�X�D�L�j �z�[���h�I�[�o�[�Y�F�u���Ă��ڂ�̃z���f�B THE HOLDOVERS �i�Q�O�Q�R�N�A�āA�����F���Y���ށj  �@�܂��͐l�Ԃ́i�Ƃ������A���Ȃ��Ƃ����́j�L���͂������ɂ����������Ƃ������b�B �@�`�����爫�K�L�ǂ����|�[���E�W�A�}�b�e�B�̉����鋳�t���w���āA�u�Ύ����A�Ύ����v�ƉA����@���B���ہA���̃n�i���搶�͎Ύ��Ȃ̂ŁA�u���₨��A�r�{�̃f�r�b�h�E�w�~���O�\���͎Ύ��̃W�A�}�b�e�B�ɓ��ď��������̂�����H�v�Ȃǂƍl���Ȃ���ӏ܂��Ă����̂����A���Ƃ��瑼�̕��̕]��ǂ�ŁA�֎q����]�����������ɂȂ����B���̎Ύ����āA�R���^�N�g�����Y�ɂ�郁�C�N�������I�H�@����܂Ŏ��̓W�A�}�b�e�B�̏o�������f��̉������Ă����̂��B �@���琻��E�r�{���肪���Ď�������f����B��̂��ʗႾ�����A���N�T���_�[�E�y�C���ē��A�{��ł͒������ق��ēƂ��āA���K�z���݂̂�S�������͗l�B �@�����f�悪�n�܂����u�Ԃ���ڂ�D����̂́A�����Ђ̃��S��[�e�B���O�\���A�l���N���W�b�g�Ȃǂ̏o���������������g���Ȗ��ɂȂ��Ă��邱�ƁB����w�i���V�O�N�ゾ����A����ɍ��킹�ē����̉f�敗�ɂ����̂ł��傤�ˁB���̗V�ѐS�͍Ō�܂ŊѓO����Ă���A�G���h�N���W�b�g�����[���A�b�v���邱�ƂȂ��A�ꖇ�ꖇ�A�\������Ă͏����Ă����B �@�S�����̒j�q�Z�ŁA������ɂ��N���X�}�X�x�ɂɎ���ɋA��Ȃ����k�̂���������������ꂽ���t�n�i���B�ŏ��͂����������k�����l�����̂ɁA���ꂱ�ꂠ���ăA���K�X�i�h�~�j�N�E�Z�b�T�j�Ƃ������k�ƃ}���c�[�}���ŋx�ɂ��߂����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�^���ւƁA���Ղ͗����悤�ɘb���i�ށB �@���i�ȃn�i���ƃX�|�C�����ꂽ�A���K�X�́A�ŏ��͐��Ɩ��ł��邩�̂悤�Ɍ�����B�Ƃ��낪���t���Ԃ���������Ă�����ȃn�i���ƁA���k�̊Ԃł��Ǘ����Ă���A���K�X���A�Ԃ��荇���A���ɂ͒ɂ��Ƃ�����������Đ������߂����̂����邤���ɁA�u������A�ӊO�Ǝ������̓��m�Ȃ�Ȃ��́v�Ǝv���Ă���̂��A�����̖��B�I�ՁA�n�i�����w������ɕ������u���v�ƁA�A���K�X�����e�Ƃ̊Ԃɕ�����u�����v�����炩�ɂȂ�ɋy��ŁA�������Q�l�͓��u�I�t�툤�ɋ߂��J�Ō���Ă����B �@�r���̒i�K�ł́A�n�i���ƃA���K�X�̂��ꂼ��ɏ������y�����ރV�[�������邪�A����͂����ɂ͐[���肵�Ȃ��B�����l�̃��A���[�i�_���@�C���E�W���C�E�����h���t�j���܂߂��R�l�̎�v�o��l���݂̂ŁA������������������Ă���i�����h���t�͖{��ŃA�J�f�~�[�������D�܂��킯�����A���`��A���Ȃ�w�J���[�p�[�v���x�̃_�j�G���E�u���b�N�X�𐄂��ȁj�B �@�����Ė{��̓�_��������Ȃ�A �i�P�j�A���K�X���̃Z�b�T���A���{�l�̖ڂɂ͂ƂĂ����Z���ɂ͌����Ȃ����Ƃ��B���N��œ�\���Ă���Ƃ��������łȂ��A���łɔw�͍������A�e�̗����ŏ����قǃi�C�[�u�Ȑ��i�ɂ͌����Ȃ���ł��ˁB�p�u���b�N�E�X�N�[���̃{���{�������A�X�����̃`���s�����̕����������������B �i�Q�j���X�g�߂��Ńn�i�����A���K�X�̋��n���~�����߂ɂƂ����s���E���f���A�i�ꉞ�͋���������ǁj���������x�^�ł͂Ȃ��������B���ꂪ�ē��g�̊��ł������Ȃ�A�i�n�b�s�[�G���h�Ƃ͌��킸�Ƃ��j�����������܂������������Ă��ꂽ�̂ł͂Ȃ����ƁA�y�C���̉ߋ�������D���鎄�ɂ͂����v����B �i�R�j�����P�A������_�̔��e�ɓ���Ă����̂��ǂ����킩��Ȃ����A���̕�����āA���Ԃ�u���オ���䂾�����琬�����Ă��Ȃ�������i�v�Ȃ�ˁB �@�Ƃ����̂��A�{��̃X�g�[���[�̋��͂Ȑ��i�͂ɂȂ�̂́A�l�����ꂽ�L�����p�X�őދ��ɑς��邱�Ƃ��悵�Ƃ����A��������Z����p�j������A�낭�ɒm��Ȃ��l�̉Ƃ̃N���X�}�X�p�[�e�B�[�ɍs������������A�u�Љ�Ȍ��w�v�ɘA��čs���Ă���Ɨv�������肷��A���K�X�̏ő����ɂق��Ȃ�Ȃ����炾�B �@�ˁH�@����w�i�����ゾ������X�}�z�Ƃv���|�e���őދ��͊ȒP�ɉ����ł��Ă��܂����낤���A��҂̃R�~����x���i�i�ɏオ���Ă��邩��A���l�̃p�[�e�B�[�ɂȂǍs��������Ȃ���������Ȃ��B���ɋ��t���Љ�Ȍ��w�ɘA��Ă��Ă��ƌ����Ă��A���k�̕����f��i���邢�́u���ۂ�v�j�̂ł͂Ȃ����B �@������l����ƁA�ϋq�ɂ��������הO��������Ȃ��悤�A�y�C�����I�[�v�j���O�̏u�Ԃ���ϋq���V�O�N��Ƀ`���[�j���O�������̂́A���ɐ����������Ǝv����̂��B �i�Q�O�Q�S�D�V�D�X�D�L�j �S�̈� THE ZONE OF INTEREST �i�Q�O�Q�R�N�A�ā��p���|�[�����h�A�����F���Y���ށj  �@���̖���̈�Ԃ̃L���́A�i�ӊO�Ɍ��߂�����Ă���\�������肻�������ǁj���h���t�E�w�X�Ƃ��̍Ȃ���ӂŌ��_����V�[������Ȃ����Ȃ��B �@�]�����܂������Ƃ�������v�B�艖�ɂ��������݂̊��ɂ�������z���C�ɂȂꂸ�A�u���Ȃ������P�g���C�����炢������Ȃ��́v�Ƃނ����ȁB�v����������m����ƁA�Ȃ́u�����ǂȂ�ׂ��A���Ă��Ăˁv�Ƌ}�ɂ����炵����������B �@�������������o����������A���c�M�q�⋴�c���q�̃z�[���h���}�ɏo�Ă��Ă����������Ȃ��قǕ��ՓI�ȁA�s��̕v�w�̕��ꂾ�B�����ł�������A���ꂪ���̎c���Ȃ܂ł́u���҂ւ̖��S�v��`�����X�g�[���[�̒��ɔz�u���ꂽ�Ƃ��A�ς�҂͂��Ƃ��悤���Ȃ�����ƕs������������ɂ͂����Ȃ��B�u���O�炪�l�̔����ȁv�ƁB �@�J���k�f��Ղ�A�J�f�~�[�܂ō��]�����{��́A��Q����풆�̃A�E�V�����B�b�c���e���̗גn������B�W���i�T���E�O���C�U�[�ḗA���̌��������畷�����Ă���e����ߖA�����̂ڂ鉌�Ȃǂ���َؖE���A�D��Ŗ������肽�ƒ됶�����c�ގ��e������Ƃ̊�ȓ�����A�V�j�J���ɒW�X�ƕ`���B �@����Ȗ{�Ƃ͕ʂɁA�������ē̈Ӑ}���v�肪�����V�[�����}������Ă���̂��A�{��̓����B  �@���̈�Ⴊ�A�ł̒��ŁA����̓y��ɉ����߂���A���A�Ɋۂ�����_�X�Ɨ��Ƃ����肷�鏭����`�����V�[���ł��ˁB�f���̎����������������̃V�[���Ƃ͈���Ă��āA�������̂̓������甭�����Ă���悤�ȁA�s�v�c�ȉ摜�ɂȂ��Ă���B���܂��ɏ����̓����v�������d�����������ɉ��O�ōs�����Ă���̂ŁA�{���ɂ��ꂪ�ł̒��̏�i�Ȃ̂��i��ڂ������̂��A�N�́H�j�A���w�I���������������Ԃ̏�i�Ȃ̂������R�Ƃ��Ȃ��B �@���̈�Ⴊ�A�ł̒��ŁA����̓y��ɉ����߂���A���A�Ɋۂ�����_�X�Ɨ��Ƃ����肷�鏭����`�����V�[���ł��ˁB�f���̎����������������̃V�[���Ƃ͈���Ă��āA�������̂̓������甭�����Ă���悤�ȁA�s�v�c�ȉ摜�ɂȂ��Ă���B���܂��ɏ����̓����v�������d�����������ɉ��O�ōs�����Ă���̂ŁA�{���ɂ��ꂪ�ł̒��̏�i�Ȃ̂��i��ڂ������̂��A�N�́H�j�A���w�I���������������Ԃ̏�i�Ȃ̂������R�Ƃ��Ȃ��B�@�ӏ܌�ɃE�F�u�ŏ��������Ă݂���A�ǂ����w�X��ƂƂ͊W�̂Ȃ����W�X�^���X�̏������A���_���l�ߗ��̂��߂ɐH�ו���u���Ă����p��`���Ă����炵���B�ēA����Ȃ炻���������Ă���Ȃ��Ƃ킩��܂���āB���͂Ă�����w�X�Ƃ̖����g�p�l���Ƃ���v���Ă����B �@���ꂩ��A�w�X�v�l�̕�e�����R�Ǝ��H��������A���Ԃ�������Ă��Ȃ�������Ȃ��B���̍s��ɓ{���āA����ɋA���Ă��܂����킯�ł͂Ȃ��������B���̂��ꂳ����A���v�w�̖��S�����L�ł���l�̂悤����������B �i�Q�O�Q�S�D�U�D�P�O�D�L) �}�b�h�}�b�N�X�F�t�����I�T FURIOSA�FA MAD MAX SAGA �i�Q�O�Q�S�N�A�����āA�����F�A���[�������j  �@���[��A���Ȃ�c�O�ȑ��҂ɂȂ��Ă��܂����B�O��w�}�b�h�}�b�N�X�@�{��̃f�X���[�h�x�Ɣ�r���Ă̎c�O�|�C���g���v�����܂܂ɗ��Ă݂悤�B ������̃L���X�e�B���O�� �@����Ȃ��Ƃ������Ɛ����ʎ�`�҂̂�������Ă��܂���������Ȃ�����ǁA�O��ōł��g�j���Ղ�h���ǂ������̂́A�u�������ɂ͊ւ��̂˂����Ƃł������܂��v�Ƃ����ԓx����������̃}�b�N�X�i�g���E�n�[�f�B�j�ł͂Ȃ��A�͂�ꂽ�������Ɏ��R��^���悤�Ǝ���̖���q�����t�����I�T�i�V���[���[�Y�E�Z�����j�������B �@���̃t�����I�T�̎Ⴂ�����A�j���E�e�C���[���W���C��������ƕ��������A�Ȃ�a������������˂��B�Z�������ǂ����������N�Z�̂Ȃ����l�ł���̂ɑ��A�A�j���͗ǂ������������I�Ȋ炾���B�܂��A�Z�������i�Ƃ������Z�����̉�����t�����I�T���j�A�X���[�g�̂悤�Ƀo�����X�̗ǂ��̋낾�����̂ɑ��A�A�j���̃t�����I�T�͌������ׂ������āA�����ɂ��n���������B �@�C���[�^���E�W���[�̃n�[�����ɂł�����Ȃ�ʂ����A���̎���������̎q�����̖��@�̍����n�тŃT�o�C�o���ł���悤�ɂ͌����Ȃ��B ���L�����N�^�[�̗��݁� �@�O��́u�P��vs���ʁv�̏c�������ł͂Ȃ��A�}�b�N�X�A�t�����I�T�A�E�H�[�{�[�C�̃j���[�N�X�i�j�R���X�E�z���g�j�Ƃ�������̈قȂ�g���I���A���ʂ̓G�Ɛ키���ŐM������݁A�������a�������Ƃ����������G�킾�����B �@���̓_�A�{��̓q���C���̖����ɂȂ�W���b�N�i�g���E�o�[�N�j�̑��݊��������ɂ������B�t�Ɉ��ʂ��W���[�ƃf�B�����^�X�ɓ����Ă��邪�A����������������̂����s�������̂������ȂƂ���B ��������̍\���� �@�O��̓�x�i�Ƃ����������j�ɂ킽��E�H�[�^���Nvs�u�W�R�c�̍U�h��́A�^�Ɏ�Ɋ�����o���f���ŁA�u������}�b�h�E�}�b�N�X���Ă������̂��H�v�Ƃ�������̉��^�̐����A�܂邲�Ɛ�������C���p�N�g���������B �@�������ɓ������Ƃ͂ł��Ȃ��Ǝv�����̂��A�{��ł͂����O���̎R��ɂƂǂ߁A�V���ȃM�~�b�N������������Ă���B�����āA�������ɍ��x���������邱�Ƃ͂ł����̂����A �i�P�j�E�H�[�^���N�̃n���h��������̂��t�����I�T�ł͂Ȃ������̂Ŋ���ړ��̓x���������������A �i�Q�j�㔼�̖{���̃N���C�}�b�N�X�ɁA�i�����܂ł��l�̊��z�ł͂��邪�j������錩���ꂪ�p�ӂ���Ă��Ȃ������B�c�O�B �@�V���Ȉ��ʃf�B�����^�X�ɃN���X�E�w���Y���[�X�������Ă�����A�t�����I�T�̕�e���ɃA�{���W�j�[�n�̃`���[���[�E�t���C�U�[�i�w������v���e���_�[�x�ő��݂�m��������B�Z�����Ƃ��A�j���Ƃ����Ă��Ȃ����ǂˁi�j�j���N�p������ƁA�W���[�W�E�~���[�ē̑��ς�炸�̑c�����͊�����ꂽ�̂����B �i�Q�O�Q�S�D�U�D�P�O�D�L�j ������v���e���_�[ ANYONE BUT YOU �i�Q�O�Q�R�N�A�āA�����F�i��̎q�j  �@�v�n�v�n�v�́u�n���E�b�h�E�G�N�X�v���X�v�Ŏ��O���āA�傢�Ɋy���݂ɂ��Ă������B���̔��r�L�j�͔����ł��傤�B �@�ł��W���J���Ă݂�ƁA���{�ł̏�f�ق͈ӊO�ȂقǏ��Ȃ��A�u�n���E�b�h�E�G�N�X�v���X�v�������ł���ɂȂ������A���������n��������������ꂪ���܂�̂ł͂Ȃ����ƁA������ƐS�z�ɂȂ����ȁB �@����A�������ɂˁA �i�P�j�L���X�g�̒m���x�͂���قǍ����Ȃ����A �i�Q�j���炷�������ǂނƁA���Ȃ������������B �@������\�j�[�E�s�N�`���[�Y�̂悤�ȑ��̔z���ł���ɂ�������炸�A���ƃT�C�h���ϋɓI�Ɏ�������Ȃ������̂�������Ȃ��B �@����ł����ɍ��Ή��x�ł��C�����悭�ς���̂��A��Ԃ̒�Ԃ���䂦��B�����Ė{��́A�ʐ����̃��u�R�����́u��ʁv�Ƃ܂ł͌���Ȃ�����ǁA���Ԃ��͖��炩�Ɂu�ʁv���́A�ނ����X�̃f�L�������B �@�V�h�j�[�E�X�E�B�[�j�[�̃t�@�j�[�E�t�F�C�X�Ƃ����ȃo�X�g�͂ǂꂾ�����Ă��Ă��O���Ȃ����A������̃O�����E�p�E�G�����A�E�B���E�O���b�N�ē̖��@�ɂ�����ƃi�C�X�K�C�ɑ��ς��B�N���[�Y�D��̃_���X�V�[����A������x�������Z�b�N�X�V�[���̂悤�Ȍ�����͎��ɔ������B���Ă������A�����Q�l�̃r�~���[�ȐS�̓������A�S�҂�ʂ��čׂ₩�ɂ������Ƃ��Ă����B�i�����Β�x���̃M���O�����ꂱ��ł������A�S�̂̕]���Ȃ��قǂł͂Ȃ��j�B �@�����ăf�[�g���[�r�[�Ƃ��Ă͐\�����̂Ȃ���{�ł���A�z���̃\�j�[�͏��q���E�Ӎ�����ɔY�ސ��{�ɓ��������āA�i���ȏȐ��E�Ȃ�ʁj���J�Ȑ��E�����t����Ηǂ�������Ȃ����ȁB����A���r�L�j�̐��b�Ԃ͌����ɋy���A�l���̂P�O�R���Ԃ������ɑ����i�ł͂������B ���t�L�P�� ��ʂɉf�肱�ޕ��⍻�l�̗������A�ē��̋L�q�A�{�̃^�C�g���Ȃǂ𗘗p���āA������Ƃ����x��Ƃ������A���߂̏͑�̂悤�Ȃ��̂�ǂ܂���H�v���y�����B ���t�L�Q�� �G���h���[���ŗ����̂��L���X�g�ꓯ�ʼn̂��̂����ǁA�����p�̏��݂��Ď��^�����킯�ł͂Ȃ��A�{�Ғ��̊e��ʂ��B�e��������ŁA�����ɏo�����Ă����o�D�������o���o���ɉ̂������̂��Ȃ��ł���̂ł��ˁB ���ꂪ�L�[���獇�킹�Ă��Ȃ��āA�݂�ȑS�R��肶��Ȃ��āA����ł��G���f�B���O�̑�c�~�Ńz�b�R�������C�����ɂȂ��Ă��邩��A�Ȃ������ĂĐS�n�悵�B ���t�L�R�� ����������邩�Ǝv�����ǁA�ŏ��̏o��̂Ƃ���łQ�l���u������ׂ肵�Ȃ���Q���������i���G�b�`���Ȃ������j�v���ĂƂ�����A�O���b�N�ē̐[�d�����������Ă����_�Ȃ̂ł́B �i�Q�O�Q�S�D�T�D�P�U�D�L�j �}���E�|���̂Q�O���� 20 DAYS IN MARIUPOL �i�Q�O�Q�R�N�A�E�N���C�i���āA�����F���{ꤐ��j  �@�A�J�f�~�[�ܒ��҃h�L�������^���[�܂���܂������B�u�{���͂��̂悤�ȉf��͍�肽���Ȃ������B���V�A�̐N�����Ȃ��������Ƃɂ������B���ɗ��j�͕ς����Ȃ����A�f��͋L���ƂȂ�A�L���͗��j�����v�Ƃ����~�X�e�B�X���t�E�`�F���m�t�ē̐����ȃI�X�J�[��܃X�s�[�`�͖Y�ꂪ�����B �@����͂`�o�ʐM�̃E�N���C�i�l�L�҂ł���`�F���m�t���A�Q�O�Q�Q�N�Q���̃��V�A�̐N�U�J�n����Q�O���ԁA�����̒��}���E�|���ɓ��݂Ƃǂ܂�A�댯�����m�Ō��n�̎S������ێЉ�ɔ��M���悤�ƕ��������L�^�ł���B �@�푈�͋ƖC������n�܂�B��R���{�݂��������Ȃ���������A�q�ǂ����܂ޑ�ʂ̏d���҂����X�ƕa�@�ɔ�������Ă����B �@������ɂ͎ԑ̂ɂy�̃}�[�N���L������Ԃ������B�n���̊J�n���B�E�N���C�i�R���ǂ�قǂ̖h�q�̐���~���Ă����̂��͂킩��Ȃ����A�{����������A�����Ȃ���A���H���t���[�p�X�ɋ߂������悤�Ɏv����B �@�`�F���m�t�������ރ`�[�����a�@�����_�ɂ��Ă������Ƃ�����A���}���u��~�����u�ɖz�������ÃX�^�b�t�̌��g�Ԃ�͌J��Ԃ��`�����B����͐k�Ђ�p���f�~�b�N�̍ۂɂ�����ꂽ�A�{���ɓ��̉�������i���B �@�����������ł͐l�S���r�p���A���X�ŗ��D���͂��炭���J�����o���B���̏��ŃT�b�J�[�{�[�����������낤�Ƃ���j�̋������ƁA�Ƃ��ς₵�������X��̔ߒɂȋ��т́A�푈�̂����ʂ��A�ے��I�ɂƂ炦�Ă����̂ł͂���܂����B �@����������Ȃ��Ȃ�����̂�͍��Ɂi��������ƌ������́j�������ޗl�q���A�����Ԃ�Ɠm��Ɏv�����B�Ƃ͂����A���C�e�������Ă��邩���킩��Ȃ����ň�̏����ɏ]�����Ă����l�������A�N���ӂ߂��邾�낤���B �@���E�Ɍ������`�F���m�t�ǂ̏�M�́A�ʐM����̈����Ŏ���ɍ�����ɂ߂Ă����B�����čŌ�ɂ́A�^�悵���L�^�}�̂��̂��̂��A���V�A�̐�̒n��˔j���Ď����o������Ȃ��Ȃ�B���܂ōl�������Ƃ��Ȃ���������ǁA�x�g�i���푈��C���N�푈�ł͌��n����̉f����������͂��Ă����̂�����A���̓_�������A���݂̕����Z�p�I�ɑޕ����Ă��H �@���d�Ԃ��P�[�^�C���s�ʂɂȂ钆�ŁA�����d���Ƃ��Ďg�����߂����ɁA�l�X���|�[�^�u�����d�@�ŃP�[�^�C���[�d�����R�}�́A�Ȃ��ߖ����t�B�N�V�����̈��ʂ̂悤�Ɏv�����B �@��J���ēd�g���E���A�א�ő���o�����f�����A���V�A������t�F�C�N���ƌ��߂���ꂽ���Ƃ́A�W���[�i���X�g�ł���`�F���m�t���������������������悤���B�����A�����ɓ͂����f���́A�ʂ����ă`�F���m�t�̎v�����\���ɓ`�����̂��H �@���̃h�L�������^���[�f��̐���E�ēE�i���[�V���������ׂĂ��Ȃ����`�F���m�t�́A�s��Ȏ�ނ̎��Ԃ�m�点����^�f���̍��ԍ��ԂɁA�e���̂s�u�j���[�X�����������̔z�M�f������Ƃ��̘^���}�����Ă���B �@�ނ��Ȃ����������\����I�������̂��͂킩��Ȃ��B�P�Ɂu�������̎B�e�����f�����A�������Đ��E���̃��f�B�A�ŗ�����A�^����`�������v�ƌւ肽�������̂�������Ȃ��B �@�������A�����������Ƃ��܂�������B�ς�҂̎�ςɓ������Ă���悤�Ȗ{��̐��X�����f���ɔ�ׂ�A�s�u�j���[�X�Ő���ꂽ����́\�\������ʑ̂��f���Ă���̂ɂ�������炸�\�\���܂�ɒf�ГI�E�q�ϓI�ł���A����䂦�Ɋ�ɋ��������������l���̂悤�Ɋ������Ă��܂��̂��B���̓_���w�E���A�����i���邢�́A���Ȃ��Ƃ��c�O����j�Ӑ}���A�`�F���m�t�ɂȂ������ƌ�����邾�낤���H �@�����Ɏv�����������Ƃ��A�������� �ӂƈ�����Ƃ����肵�A�ЂƂ܂�莋����L���邱�Ƃ���������B�J�킩�炷�łɂW�O�O���ɂ킽���Ă��̐푈�ɑ̌����Ă���l�X�̖ڂɂ́A���́u��ςɓ������Ă���悤�Ȑ��X�����v�h�L�������^���[�f�悳�������A�u���܂�ɒf�ГI�E�q�ϓI�ȑ��l���v�̂悤�ɉf��̂ł͂Ȃ����ƁB �@�������P�l�̐l���̋��C�̂��߂ɁA�����n���ɓ������܂�Ă���s���Ɨ��R���m�����̖�������킸�ɂ͂����Ȃ��B �i�Q�O�Q�S�D�S�D�Q�X�D�L) �p�X�g ���C�u�X�^�ĉ� PAST LIVES �i�Q�O�Q�R�N�A�ā��A�����F���Y���ށj  �@���O�ɗ\���҂Ƃ��炷������������ł́A���܂�ʔ������ɂ͎v���Ȃ��������B����ł��A�J�f�~�[�܍�i�܃m�~�l�[�g�����A�ꉞ�`�F�b�N���Ă��������ƌ���ɑ����^�̂��������E�E�E�B �@���ǁA�����̑���ۂ��������������Ƃ��m�F���������ɏI����Ă��܂����B���̗\���҂𐧍삵�����́A�悭�����ΐ����ȁA���������Θr�̈������������悤���B �@�����A�u����͂��܂��I�v�ƕG��ł����Z���t���P�������̂ŁA���Y�����˂ď����c���Ă������Ǝv��������B �@�P�Q�̍��ɍD�������Ă����j�q�w�\���ƁA�R�U�ɂȂ��Ă���ĉ�����������̃m���������B�u�v�Ƃ͂悭�P���J����B�Q�{�̖��P�̔��ɐA����悤�Ȃ��̂�B���݂�������L����ꏊ��T���Ă�v �@�������Ė����B���̉ߒ��łQ�̍��͕��������������ݍ����̂��낤���A�t�ɂǂ��炩�A�܂��͑o��������L���Ȃ��Ɣ�������ƁA�͂�Ă��܂�����A�A�ؔ��������Ă��܂����肷��̂ł��傤�ˁB �@���āA�Ɛg�̎����������Ń��^�t�@�[���u�߂��Ă��A�������Đ����͂͂Ȃ�����ǁB �@����ƍŌ�ɂQ�l���^�N�V�[��҂�ʂ̉��o���A�Ȃ��Ȃ��ʔ������̂��������B���߂͉����тɕ����ɗ����Ă����w�\���ƃm�����A�����̂܂܁A����A���߂炢�����ɐ����Ă�����ˁB �@�����A�N���������ĂQ�l�������������ꂾ���A���g�̌l�I�ȑ̌����f�扻�����炵���Z���[�k�E�\���ḗA�����͂��Ȃ��B�Ƃ������A�����Ȃ��B����ɐ旧�Q�l�̑N��ȍĉ�V�[���́A���̏�ʂ́u�t�̕����v�ɂȂ��Ă����킯���B �@���n�G���[�g�炵���w�\�����A�낭�ɉp�ꂪ�b���Ȃ����Ƃɂ��������ǁA���Ƃ���l����A����������Ă̐ݒ�ł���ˁB�w�\�����p��y���y����������A�v�ƃw�\�������ꂼ��ɕ����a�O��������A�ʎ�̉f��ɂȂ��Ă������낤�B�m�������_���n�̕v�ɐ��������Ƃ���A���̏����̒j�͂����܂Łu�؍��l�I�Ȋ؍��l�v�łȂ���Ȃ�Ȃ������̂��B �i�Q�O�Q�S�D�S�D�Q�X�D�L) �S�[�X�g�o�X�^�[�Y�^�t���[�Y���E�T�}�[ GHOSTBUSTERS: FROZEN EMPIRE �i�Q�O�Q�S�N�A�āA�����F�A���[�������j  �u�A�C�E�n�u�E�A�E�S�[�X�g�E�g�D�E�o�X�g�I�iI have a ghost to bust!)�v �@�Ђ�[�A�J�b�R�����B�P�T�̃q���C���A�t�B�[�r�[�i�}�b�P�i�E�O���[�X�j���A�S�[�X�g�ގ��̍Œ��Ɂu�댯���������o���ȁv�ƕ�e���猾���A�v�킸�������Č��ɂ���Z���t�ł���B �@����I�ɂ́u���ɂ͑ގ����ׂ��S�[�X�g������v�Ƃ����Ӗ����������A����ł͌ł��ăZ���t�ɂȂ�Ȃ��̂ŁA���ʂ́u�S�[�X�g��|���Ȃ���v������̎����ɂ���Ƃ���B�Ƃ��낪������Ăсi���Ƃ��Ύ��Ɂj�p����ƁA�P�O�l���X�l�́uI have to bust the ghost.�v�݂����ȉp�앶�����邾�낤�B�I���W�i���̃Z���t�̐�Ƃ͔�ׂ�ׂ����Ȃ��B �i�A���[����������̌���p�����́A�܂��ʂ̔��f����u���̓S�[�X�g�o�X�^�[�Ȃ̂�v�݂����Ȗ�ɂȂ��Ă����j �@���̃t�B�[�r�[�́A�O��w�S�[�X�g�o�X�^�[�Y�^�A�t�^�[���C�t�x����n�܂����V�V���[�Y�̒��j�B�v�t���f��ɏo�Ă��鐬�їD�G���q���āA�C���~�ȓz���E�U���z���̂ǂ��炩�ł��邱�Ƃ��唼�Ȃ̂ɁA���̗��n���q�̓r�r�b�h�ȔY�݂⏝��������A�����Ɗ���ړ����ł����l���Ƃ��đ��`����Ă���̂��|�C���g�����B �w�A�t�^�[���C�t�x�ł͋��V���[�Y�̌n���i�Ƃ��������j�������W�F�C�\���E���C�g�}�������K�z�����B�������A�{��ł͂��̋r�{�Ƃ������M���E�L�[�i�����ē�q���B����ŕ��͋C���ς�����Ⴄ��Ȃ����ƈꖕ�̕s�����������ɑ����^���A�W���J����ΞX�J�������B�X�g�[���[���̂͑������Ȃ��̂ɁA�O�쓯�l�A���邵�A�n���n���ł��邵�A�S���������Ȃ��B����ς�f��́A�����B�邩�ł͂Ȃ��A�����ɎB�邩���厖�Ȃ�ł��ˁB �@�P�s����������Ƃ���A���̐V�V���[�Y��Q�e�ł̓t�B�[�r�[�̕�e�i�L�����[�E�N�[���j�ƁA���̃p�[�g�i�[���̃|�[���E���b�h���A���̃S�[�X�g�o�X�^�[�ɂȂ��Ă������Ƃ��B �@�O��ł́A�����Ƃ�����ɂȂ�Ȃ���l�����i���V���[�Y�̌����܂ށj��K�ڂɁA�K�L���`���������劈��̂��ő�̂��y���݂��������ǂˁB �i�Q�O�Q�S�D�S�D�Q�X�D�L) �I�b�y���n�C�}�[ OPPENHEIMER �i�Q�O�Q�R�N�A�āA�����F�Γc�q�j  �@�ߔN�̃N���X�g�t�@�[�E�m�[������i���āA�w�C���Z�v�V�����x�w�C���^�[�X�e���[�x�w�e�l�b�g�x�̂悤�ȃI���W�i���r�e�͓Ƃ�悪��őދ����邯�ǁA�w�_���P���N�x��w�I�b�y���n�C�}�[�x�̂悤�Ȏj�����r�F�����f��͒����Ă����O���Ȃ��B����Ƃ���҂̘H���ōs���Ă����Ƃ������ȁB �@���āA��f���ԂP�W�O���̖{��́A���m�ȏ͗��Ă����Ȃ��������̂́A������́i�P�j�O�����i�Q�j�}���n�b�^���v��i�R�j����������̂R���\���ɂȂ��Ă��������B�u�����̊J���҂̓`�L�f��v���Ƃ���v���Ċώn�߂���A���ɂ͂�����A���̂����̂P���ƂR���́A�ނ���u���b�h�p�[�W�ɋꂵ�߂�ꂽ�l���̉f��v�Ƃ����F�ʂ����Ȃ�F�Z����ł��ˁB �@�ŁA�����Ȃ����͎̂�l���̃��o�[�g�E�I�b�y���n�C�}�[�i�L���A���E�}�[�t�B�[�j���X�g���[�Y�Ƃ����l�i���o�[�g�E�_�E�j�[�E�W���j�A�j�Ɋׂ��ꂽ����炵���Ƃ������Ƃ͂��ڂ낰�Ȃ���킩��̂����A������͂��������A���̃X�g���[�Y�����҂ŁA���݂̃I�b�y���n�C�}�[�Ƃǂ�Ȋm�����������̂���m��Ȃ����̂�����A�����ɂ��Ă����̂ɐ���t���B �@���܂��Ƀm�[�����́A���̂P���ƂR���ɂ͂قƂ�NJɋ}����炸�ɁA�Z���X�p���ł�����V�[���Ǝ��Ԏ���ς��Ă����i�ҏW�̃W�F�j�t�@�[�E���C���͖{��ŃI�X�J�[���l���j�B�i�`�j�I�b�y���̐l�����قڎ��n��Œǂ����V�[���Ƃ͕ʂɁA�i�a�j�I�b�y�����W�F�[�\���E�N���[�N�ɍU�߂��Ă���Ԏ��R��݂����ȃV�[������A�i�b�j�Ȃ������m�N���ŎB��ꂽ�ۃe�[�u���̉�c�V�[������ŁA�i�a�j�Ɓi�b�j���ǂ�������ŁA�ǂ̎��Ԏ��ɓ���̂�����悭�킩��Ȃ��B �@����������āA�ӏ܂̓r���Łu�^��_�����悤�v�Ƃ��u�������̃Z���t�̊܈ӂ́H�v�Ȃǂƍl����������Ō�A�����܂���p�����ɘA�˂��鎚����ǂݗ��Ƃ��B�������ڂꂽ���Ȃ�������A�f��قɍs���O�Ɍ���{��\�K���邱�Ƃ��K�{�Ȃ̂������B �@�ΏƓI�ɁA�I�b�y�����}���n�b�^���v����w������������`������Q���́A�i�a�j��i�b�j�̃V�[�������܂荷�����܂��A�P�P�̃V�[�N�G���X�߂ɂ������茩���Ă�������B �@�ӊO�Ȃ��ƂɁA�����܂ŗ���ƃI�b�y���������̓V�˂Ԃ������G�s�\�[�h�͂قƂ�Ǔ��炸�A�ނ�����̋��������`�[���̃����o�[�𑩂˂�}�l�[�W�����g�̎d���������Ȃ�B���ꂪ�����ɋ߂��Ƃ�����A���ۂɌ����������ɓ������̂͑S�ĂƓ��������炩���W�߂�ꂽ�g�b�v�Ȋw�҂����̕��Ƃƃ`�[�����[�N�ł���A���̈Ӗ��ł̓I�b�y���ЂƂ���u�����̕��v�ƌĂԂ̂́A�ǂ������������m�ł͂Ȃ��悤�ȋC�����Ă����ȁB �@�����̌����{�݂Ń`�[�����������������߂Đ��������邭����́A�����炭�m�[�������ł��͂���ꂽ�����B�Â萫�̃m�[�����̂��Ƃ�����A�Z�b�g����������N���������Ƃ��A�j���Ɛ������ʂ悤�ɍČ������̂ł͂���܂����B �@���̎��A���_�ʂ�̌��ʂ��o�Ȃ�������A��C�����サ�Ēn���S�̂��ŖS���Ă����\�����������Ȃ�ď��߂Ēm�����B����܂��āA�I�b�y�����G���f�B���O�ŃA�C���V���^�C���ɂԂ₭�ꌾ�̏Ռ��x�Ƃ�������I �@�A�J�f�~�[�剉�j�D�܂���܂����}�[�t�B�[�́A��܃X�s�[�`�Łu���̉f��͌�����������l���̕��b�B��X�͍����ނ̐��E�ɐ����Ă���v�ƌ�����̂��������A����͂܂��ɂ��̝{���̈ꌾ�̃}�C���h�Ȍ��������������̂ł��ˁB �@���Ȃ݂ɓ��{�̉f��t�@������ԕq���Ɋ��������̂́A���Ԃ������̍���c�̃V�[�����������낤�B���̑O��ɂ͈ӊO�ȃZ���t�����ȃZ���t���ڔ������B���Ƃ��u�h�C�c���~���������A�l�ލő�̋��Ђ͌���������X���g���v�u�������P�Ŗ��Ԑl���P�O���l���E�����̂ɁA�N���R�c�������N�����Ȃ��č����S�z���v�u�P���ڂ͈З͂������邽�߁A�Q���ڂ͂܂��܂��������Ǝv�킹�邽�߂ɗ��Ƃ��v���`��A�n��Ȃ̂��A���ۂ̔����Ȃ̂��킩��A���낢��ȈӖ��ŋ����[���B �@����ɔ�ׂ�A����������̏j���̃V�[���ŃI�b�y�������ł��̎��̂ɑ���˂����ނ悤�Ȍ��o������̂́A�m�[�����ēɂ��Ă͗ތ^�I�ɂ�����\���������Ǝv���B �@�A�J�f�~�[�܂ł̓I�b�y���̂Q�Ԗڂ̍Ȃɕ������G�~���[�E�u�����g���������D�܌��ɂȂ������A����������ۂ����̂́A�ނ���ŏ��̍Ȃ��������t���[�����X�E�s���[�̕��B �@���Y��`�҂̌𗬉�Ŏ�������I�b�y���ɐ��������Ă��āA�m�I�������I�ȉ�b�����킵�A���̓��̂����Ƀx�b�h�C���B�R��ʂł��Ă���Œ��ɏ���Ƀx�b�h���痣�ꂽ���Ǝv���A�{�I�ŃT���X�N���b�g��̖{�������Ă��āA�I�b�y���Ɍ���ʼn��ǂ����Ȃ���A�Ăсi�a�f�����̂��Ƃ���́j�����̐K��������ł����B �@�����͔n����d�˂��f��t�@���Ȃ̂ŁA�j�̎ː���҂����ɃZ�b�N�X�𒆒f�����Ⴄ�����A�O����̋����ɗ~��鏗���A����������i�Ɏv���邯��ǁi���ꂼ��w�X�p���O���b�V���x�̃e�B�A�E���I�[�j�ƁA�w�����_�ƃ_�C���ƗD�����z��x�̃W�F�C�~�[�E���[�E�J�[�e�B�X�j�A�Ⴂ�ϋq�̖ڂɂ́A�ޏ��̌����̂P�P���A����ȃt�@���E�t�@�^�[���̂���Ɍ������Ȃ��������B �@�{�삪�q�P�T�Ɏw�肳��Ă����̂́A���{�̗ǂ��q���č��ɕ��Q�e������ĂȂ��悤�ɂ��邽�߂ł͂Ȃ��A�P�Ƀs���[�˂�����̔Z���߂̔G��ꂪ�����邩�炾������ł��ˁB �i�Q�O�Q�S�D�S�D�T�D�L�j �Q�O�Q�S�N�I�X�J�[�i�C�g�E�E�H�b�`���O�I  �@���n���ԂR���P�O���ɋ��s���ꂽ�A�J�f�~�[�����́A�w�I�b�y���n�C�}�[�x����v����̑������l���i�P�R����Ńm�~�l�[�g����V����Ŏ�܁j�B�w����Ȃ���̂����x�i�P�P����Ńm�~�l�[�g����S����Ŏ�܁j�����̗�����E�������Ă������Ƃ����}���ɁB �@���{���́w�N�����͂ǂ������邩�x�����҃A�j���܁A�w�S�W��-1.0�x�����o���ʏ܂����ꂼ���܂�������ƂȂ����B���߂łƂ��������܂��B�����A�c�O�Ȃ��ƂɑO�҂̊W�҂͒N�����T�ɏo�Ȃ��Ă��炸�A��҂̎R��M�ē͉p��̃X�s�[�`���e��p�ӂ��Ă����Ȃ���A���x���������ă��^���^�ɂȂ��Ă��܂����B���{������{�l�A���{�����ɑ���D�ӂƌh�ӂ����コ����܂��ƂȂ��@��Ȃ̂ɁA�Ȃ�Ƃ��������Ȃ����Ƃ��B ���T�ˉ��n�]�ǂ��肾�����o�D���偄 �@����͔o�D�S����̃v���[���e�B���O�����ɐV�@�����̗p���ꂽ�B�e����Ƃ��ɉߋ��̃I�X�J�[��҂��T�l���o�d���A���N�̃m�~�j�[�T�l�����ꂼ��Љ�{���������߂������Ƃ�����`���i�䂦�ɍP��̒j���̂������|�������͍̂�ꂸ�j�B �@����Ɏ����`���́A�������Q�O�P�O�N�i�Q�O�O�X�N�x�j�ɂ��̗p���ꂽ�L�������邪�A���̔N�́u���������ҁv�̓I�X�J�[��҂���Ȃ������͂����B���͂₩�Ȃ肤��o�������ǁA�w�P�V�̏ё��x�Ŏ剉���D�܌��ɂȂ����L�����[�E�}���K�����A����ŋ��������s�[�^�[�E�T�[�X�K�[�h���Љ����Ȃ��������ȁB�l�I�ɁA������}���K�������C�ɓ��肾�����̂ŁA���������͐h�����Ċo���Ă���B �@�������ď������D�܂���܂����̂́A�w�z�[���h�I�[�o�[�Y�^�u���Ă��ڂ�̃z���f�B�x�̃_���@�C���E�W���C�E�����h���t�B�o�D�S����ł͗B��A���l�̎�҂ƂȂ����B���łɂR�V�Ȃ���A����܂ł���قǑ傫�Ȗ������Ă��Ȃ����D����Ȃ̂ŁA�u�����Ɖ����Ⴄ���̂ɂȂ肽���������ǁA���鎞�A�����炵�����Ă�������̂��ƋC�Â����v�ƁA�܂�ŐV�l���D�̂悤�ɏ��X�����A�܂Ȃ���̃X�s�[�`�ɁB �@�ΏƓI�ɏ����j�D�܂̃��o�[�g�E�_�E�j�[�E�W���j�A�i�w�I�b�y���n�C�}�[�x�j�́A���͂⏕���ł͖�s���Ƃ������炢�̃L�����A�̎����傾����A�X�s�[�`���]�T�^�X�B�ˑ��Ȃǂłǂ�ꂾ���������̂��Ƃ��O�l�ɒm���Ă��邾���ɁA�u�ێ߂����Ă��ꂽ�v�ٌ�m�Ɋ��ӂ�����邨�ӂ������B �@�����悤�ȃL�����A����̕����Ŋ����̃X�s�[�`��������҂�������܂���킯�����A�_�E�j�[�E�W���j�A�͂��������z�Ȃ̂����炵�傤���Ȃ��B�ނ��܂��u�����炵���v���邱�Ƃ����ł��Ȃ��̂ł��ˁB �@�剉�j�D�܂͓������w�I�b�y���n�C�}�[�x�̃L���A���E�}�[�t�B�[���Q�b�g�B�o���쎩�̂̐����ɉ����āA����i�ɋ��͂ȑR�n�����Ȃ������K�^�ɂ��b�܂ꂽ���B �@�X�s�[�`�ł́u���̉f��͌�����������l���̘b�B��X�͍����ނ̐��E�ɐ����Ă���B���a��z���l�X�ɂ��̏܂�����܂��v�Ɣ����B�픚���E���{�̍������炷��Ƃ����ꐺ�ق��������悤�ɂ��v�����A��i���̂Ƃ��̃X�^���X���܂����Ă��Ȃ��̂ŁA����ȏ�̃R�����g�͕t���ɂ����B �@�剉���D�܂̍ʼnE���́w�L���[�Y�E�I�u�E�U�E�t�����[���[���x�̃����[�E�O���b�h�X�g�[���ŁA��܂���ΐ�Z�����D�Ƃ��Ă̊ȉ����ɂȂ�Ƃ��낾�������A�W���J����w����Ȃ���̂����x�̃G�}�E�X�g�[�����R�x�ڂ̃m�~�l�[�g�ɂ��ĂQ�x�ڂ̎�܂���������B���Ȃ݂ɑ��̂R�o�D�͂���������̎�܂ŁA�_�E�j�[�E�W���j�A�ȊO�͌��ɂȂ�̂����߂Ă������B �@�X�g�[�����g�����I��\�����Ă����̂��A�d��ł͂��Ȃ苻���C���B�h���X�̔w���̃W�b�p�[����ꂽ���Ƃ�\�I���A�u���A�悭�������ăp�j�b�N�ɂȂ�́B����Ń����S�X�i�����e�B���X�ēj�ɂ͋q�ϓI�ɂȂ�ƌ���ꂽ�B�m���Ɏ����̂��Ƃ������Ă��Ă��_���ˁB�`�[���̈���Ƃ��ėǂ����̂�ڎw���̂��A�f����̑�햡��v�ƈ��A�B�����ł��ꂾ���i�̂Ȃ��E������������Ă��A�ēɂ͍��݂͂Ȃ��悤�ł��ˁB �����Ԃ̂��y���݁� �@�E�����ꂽ�ƌ����A���Ԃ́u�ɂ��₩���v�R�[�i�[�Ŗʔ��������̂́A�ߋ��̎������܂˂ăX�g���[�L���O������\�肾�����W�����E�V�i���A���O�Ƀu�������Ƃ����ݒ�B �@��N�ɑ����Ďi��߂��W�~�[�E�L���������A��ނȂ��i�Ƃ����ݒ�Łj��Ҕ��\�p�̕�����n���Ă��ƁA�V�i�͂�����g���ă}�b�`���ȑ̂̋Ǖ������B���A�J�j�����Ń}�C�N�̑O�֍s���B �@�����ŁuCostume�E�E�Eis important�i�ߑ��͑���j�v�Ɛ�o���̂��������B����҂��e���r�����҂��A�����ŏ��߂ăV�i���ߑ��܂̃v���[���^�[���������ƂɋC�Â��킯�ł��ˁB �@���l�ɉ��������̂́A�G�~���[�E�u�����g�ƃ��C�A���E�S�Y�����O�������ȕ��͋C�ŗ���ʁB���ꂼ��w�I�b�y���n�C�}�[�x�Ɓw�o�[�r�[�x�ŏ����܌��ɂȂ��Ă����Q�l�Ȃ̂ŁA�u���C�o���W�������Ē��������v�Ƃ����ݒ�ɂȂ��Ă����͗l���B �@�ǂ��炩�Ƃ����ƍU���ɏo�Ă����̂̓u�����g�̕��ŁA�i�S�Y�����O���w�o�[�r�[�x�Ō����Ă����j�u���̕��͓��ꃁ�C�N����Ȃ��́H�v�ƃc�b�R��A�i�O����̌��ʂ��������j�u�������C�o������Ȃ������ˁv�ƌ���������B �@���̐����͎����̑O���ɔ�I���ꂽ���̂��������A����܂Ō��Ă݂�A�Ȃ�قǁw�o�[�r�[�x�̊��F�������Ȃ�̂��[���Ȃ̂������B �������F�͔Z�������̂����������̂��� �@���ہA�I�X�J�[�i�C�g�̍ŏI�Ղ�����ē܂ƍ�i�܂́A����������n�]�ǂ���Ɂw�I�b�y���n�C�}�[�x���l���B�o�D�S����̂����R�l������܂��������Ƃ͂��łɏq�ׂ����A�ē܂̃N���X�g�t�@�[�E�m�[�������܂��A�W�x�ڂ̃m�~�l�[�g�ɂ��ď��߂ẴI�X�J�[������ɓ��ꂽ�B �@�����A�O�肾�����Ǝv����̂ɁA�d��̃m�[�����͎����ė�ÁB�e���ʂɂ��Ȃ����ӂ̌��t���q�ׂ�ƁA�u�f��E�̈Ӌ`���������ƔF�߂�ꂽ�̂́A���ɂƂ��ĂƂĂ��傫�Ȃ��Ƃł��v�ƁA�D�����I�Ȉꌾ�Œ��߂��������B �@�����̊J���҂Ƃ����������c�������ł��낤��ނŃI�X�J�[���ˎ~�߂Ȃ���A���̎�܍�̓��e�ɑ���v�������咣�͓��ɂȂ��悤�Ɍ������ˁB���f��ɂ͖��x������肪�����ς������ǁA�m�[�����{�l�͈ӊO�ɑދ��Ȑl���Ȃ̂�������Ȃ��B �@���̓_�͍�i�܂̎�܃X�s�[�`�������m�[�����̍ȂŁA����v���f���[�T�[�̃G�}�E�g�[�}�X���܂����l�B��͂�e���ʂɌ^�ǂ���̊��ӂ��q�ׂ������ŁA�I�b�y���n�C�}�[���m�⌴���ɂ��Č��y���邱�Ƃ͈�Ȃ������i�����P�l�̃v���f���[�T�[���Z�����A���������A�m�[�����͐���w�̈�p�ɖ���A�˂Ă��Ȃ���A���͂�}�C�N�̑O�ɂ����������j�B �@����̍�i��܂��āA�u�����F�̔Z�������������v�ƋL�����f�B�A������ꂽ���A���̈�ۂ͂��̋t�ŁA�u�ނ��됭���F�����������v�Ɗ�������B �@�E�N���C�i�ƃp���X�`�i�Ő�����܂�Ȃ�����ɂ���Ȃ���A��v����̎�܃X�s�[�`�Ő����I�Ȕ����̔��e�ɓ���̂́A�O�q�̃L���A���E�}�[�t�B�[�̂��ꂪ�h�����ċ���������x�B �@����ȊO�ł� �i�P�j�w���^�}���E�|���̂Q�O���ԁx�Ƃ����܂��ɃE�N���C�i�푈���ނƂ����i�Œ��҃h�L�������^���[�܂��������҂��A�u�{���͂��̂悤�ȉf��͍�肽���Ȃ������B���V�A�̐N�����Ȃ��������Ƃɂ������B���ɗ��j�͕ς����Ȃ����A�f��͋L���ƂȂ�A�L���͗��j�����v�ƁA�i�����̂���ۓI�������B �i�Q�j�w�S�̈�x�ō��ے��ҏ܂��l��������҂́A�C�X���G���ƃp���X�`�i�o���̋]����J�����錾�t���q�ׂ����̂́A����قNj������t�ł͂Ȃ������悤���B �@�i��̃W�~�[�E�L�������͏I�ՂɃh�i���h�E�g�����v�𝈝�����W���[�N�����Ă������A�n���E�b�h�ł̓��_�����{�̑��݊����傫�������ɁA���ƃC�X���G�������ޖ��ƂȂ�ƁA�N���������������Ⴄ�̂�������Ȃ��ȁB �i�Q�O�Q�S�D�R�D�P�Q�D�L�j �l�N�X�g�E�S�[���E�E�B���Y NEXT GOAL WINS �i�Q�O�Q�R�N�A�āA�����F�q��Վq�j  �@���̉f��Ɋւ��ẮA�l�I�ɏ��X�x������v����������ɂ����Ȃ����Ƃ��������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �@�Ƃ����̂��A�����Ɋ�Â����̃h���}��i�ɂ́A��s����h�L�������^���[�ł�����A������J�����ꂽ���̂Q�O�P�S�N����̃h�L�������^���[�w�l�N�X�g�E�S�[���I�^���E�Ŏ�̃T�b�J�[��\�`�[���@�O�R�P����̒���x�̎����|���S�������̂́A���ł��Ȃ��A���̎����������炾�B �@���̌�A�����f���|��ƂƂ��ď����Ɏ��т�L���Ă���A�z����Ђ�������Ă��A�u���Ⴀ�h���}�ł������|��҂Łv�ƁA�����̂�����ڂ��������̂�������Ȃ��B�����Ȃ�Ȃ������̂́A�ЂƂ��Ɏ����g�̕s���Ɖc�Ɖ���̒v���Ƃ���ł���܂��B �@�Q�O�O�Q�N�v�t�̃I�Z�A�j�A�n��\�I�ŁA�I�[�X�g�����A�ɂO�R�P�̎S�s���i�����ė̃T���A��\�́A���y�d���������ăI�����_�o�g�̃����Q���V�ē����ق���B�����������₷���ēƁA�����ɂ��̂�т肵�����̕����͐��Ɩ��ŁE�E�E�B �@����E�ēE�r�{�̃^�C�J�E���C�e�B�e�B�i�j���[�W�[�����h�o�g�j�́A�������̏o���ł���|���l�V�A�����ւ̈������邩��A��L�̃h�L�������^���[���h���}������C�ɂȂ����̂��낤�B����͂킩��B �@�킩��Ȃ��̂́A�T�b�J�[�ɑ��鈤��܂�Ō����Ă���悤�Ɍ����邱�ƁB�������ɂ���̓R���f�B�f��ł���A�ٕ������C�f��ɂ��Ȃ��Ă��邯�ǁA�T�b�J�[�f��ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��B�T�b�J�[���낭�ɒm��Ȃ����肪�A�T�b�J�[���낭�ɒm��Ȃ��n��i�č���I�Z�A�j�A�j�̊ϋq�Ɍ����č�����̂������������B �@���̕��A�����Q���̍Ȃ��č��T�b�J�[����̊������Ȃ�ĉˋ�̐ݒ�����Ă�����A�G���U�x�X�E�L���[�u���[�����X�ɂ�鎀�̎�e�ߒ����M���O�����Ă�����A���C�e�B�e�B���g�������Ȑ_�����������Ă�����ƁA�u�ɂ��₩���v�͐������B �@�����A�h�L�������^���[�ł���������������킩��Ƃ���A���ɂȂ����o������l�����̂ɂ���Ȃ�ɖL���ȕ���̍z��������̂�����A�����Ǝ����ɒ����ɋr�F���Ă���Ă��悩������Ȃ����ȁB �@�����Q�����̃}�C�P���E�t�@�X�x���_�[�̓h�C�c�Ɖp���Ƀ��[�c������A���R�T�b�J�[�ɂ͂���Ȃ�ɏڂ����͂�������A������Ă���Ȃ��������H �@�܂��A���^�V�I�ɂ́A�w�^�Ɍ��������Ă�����A�`���ŏq�ׂ�������������w����Ă������Ƃ��낤����A�V�j�J���Ɍ���A���̒��x�̍�i�ŗǂ������ƌ�����̂����ȁB ���Q�l�� �h�L�������^���[�Łw�l�N�X�g�E�S�[���I�^���E�Ŏ�̃T�b�J�[��\�`�[���O�R�P����̒���x�̊��z��������  �i�Q�O�Q�S�D�R�D�P�Q�D�L�j �T���E�Z�o�X�`�����ցA�悤���� RIFKIN'S FESTIVAL �i�Q�O�Q�O�N�A�����ā��ɁA�����F�����t�q�j  �@����T�b�J�[���{��\�̍U���̎��ɂȂ낤�Ƃ��Ă���v�ی��p�����A�X�y�C���ł̃v���f�r���[����̂R�V�[�Y���́A�����Ǝ��ӂ̘A���������B���僌�A���E�}�h���[�h�ɐЂ�u���Ȃ���A�����炱����̒����`�[���Ƀ����^���ɏo�������X�B �@����ȋv�ۂ̍˔\��{�i�I�Ɋo���E�J�Ԃ������̂��A�Q�O�Q�Q�|�Q�R�V�[�Y�����犮�S�ڐЂ������A���E�\�V�G�_�Ƃ����N���u�������B�����A�o�X�N�n���̕������Z�ȓs�s�A�T���E�Z�o�X�`������{���n�Ƃ���Í��ł���B �@�E�f�B�E�A�����ē̍ŐV��́A���H�ƍ��ۉf��ՂŗL���Ȃ��̃T���E�Z�o�X�`����������B����N���Q�O�Q�O�N������A�v�ی��p�̊���Ɨ��߂���`�ȂǑł��A�����Ƒ����ɓ��{���J����Ă��悩�����悤�Ɏv�����A���ꂪ�ł��Ȃ���l�̎�����[�d������炪�������̂ł��傤�ˁB �@���ۂ̂Ƃ���{��̍ő�̌����́A�Â����B�f�������Ȃ��������ƃ��[�g�i�E�H�[���X�E�V���[���j���邲�ƌ���悤�ɂȂ邨�����Ȗ��B���[�g���g��F�l�������o�ꂷ�邻���̖��̓S�_�[���A�g�����t�H�[�A�u�j���G���A�x���C�}���Ƃ������I�[���h�}�X�^�[�����̌���̃p���f�B�A�p�X�e�B�[�V���ɂȂ��Ă���̂����A���ƂȂ��Ă͂��̌��l�^��m��Ȃ��ϋq���唼�Ȃ̂�����A�ʔ����������B �@��������I�ɂ��̕��ʂ̉f��ɂ͏ڂ����Ȃ��̂ŁA�S�_�[�����̃W�����v�J�b�g��A�u�j���G���́w�F�E���̓V�g�x�A�I�[�\���E�E�F���Y�́w�s���P�[���x�Ȃǂ����������M���O�ɂ��ڂ낰�Ȃ���C�Â������x�B���`�ށA����ł̓}�j�A�������邾�낤���A���Ă��킸�����͏オ��܂��B �@�������A�A�����͂���������ʑ�O�̚n�D�┽�����d�X���m���Ă��Ȃ���A�����đ��ޑ���Ђ�����Ԃ��Ă݂��Ă���킯���B�����烂�[�g�̎��͂̓o��l�������́A�u�����t���́i�܂�p���i�ł͂Ȃ��j�f��ȂςĂ����邩�v�Ƃ������A�A�������g�����^�R�ɂȂ��Ă���{���L���A���[�g�i���A�����̃A�o�^�[�j�ւ̝����Ƃ��Ă����Ό��ɂ���B���̎��s����V�j�V�Y�����A�E�f�B�E�A������i�̂P�̐^�����ł͂���̂�����ǂˁB �@������A�����f��̓o��l���ɂ����Ό�����ތ^�����A���[�g�́\�\�Ȃ̕��C�^�f�ɋC������A����ŏo���������ɂƂ��߂����肷�鑭�l�ł������Ł\�\�u�l���̈Ӗ��́H�v�Ƃ��u�l�͂Ȃ�������̂��H�v�Ȃ�Ď����I�ȋ^�������Đ����Ă���i�������܂����͂��畂���Ă��܂�����ł�����̂����j�B �@����ȃ��[�g�ƏI�Ղɓo�ꂷ�鎀�_�i�N���X�g�t�E�o���c�j�Ƃ̑Θb�̒��ɁA�Ȃ��Ȃ��ܒ~�̂���Z���t���������B �@�Q�l�͂�������u�l���͖��Ӗ����v�Ƃ����_�ň�v����̂����A���[�g��������u�l���͋���ۂ��v�ƌ���������ƁA���_�͑����ɔے肷���ł��ˁB�u�l���͊m���ɖ��Ӗ������A�K����������ۂȂ킯�ł͂Ȃ��B�l�͈���Ƒ��A�d���Ƃ�����rewarding distractions�i�������̓�����C���炵�j�ŁA�l���߂邱�Ƃ��ł���̂��v �@���`�ށA�唼�̐l�X���l���ōł���Ȃ��́A�Ђ��Ă͐l�����̂��̂ƍl���Ă���u����Ƒ��A�d���v�́A�E�f�B�E�A�����Ɍ��킹��A�{���I�ɖ��Ӗ��Ȑl���́g�C���炵�h�ł���A�P�Ȃ�g���߂����h�ł��������i�j�B �i�Q�O�Q�S�D�Q�D�P�Q�D�L�j ����Ȃ���̂��� POOR THINGS �i�Q�O�Q�R�N�A�p�A�����F���Y���ށj  �@�`���̓S�V�b�N�z���[���̌������B�E�B�����E�f�t�H�[�����͂����炯�̊�ŏo�Ă���̂ŁA�Ă����胁�A���[�E�V�F���[���̐l���l�Ԃ̂������Ȃ̂��Ǝv������A�O�Ȉ�ł��镃�e�ɐl�̎������ꂽ���ʁA�����Ȃ����̂��Ǝ���ɔ�������B �@���̃o�N�X�^�[���m�A���e�̋s�҂ɓ{��⍦�݂��点��ǂ��납�A�ނ���Ȋw�ɍv���ł������Ƃ��ւ炵���v���Ă���l�q�B�����Ď������O�Ȉ�ɂȂ�A�㔼�g�͏b�ʼn����g�͒��ށi���邢�͂��̋t�j�Ȃ�Ċ�V��Ȑ��������ʂɍ���Ă���B�V�˓I�Ȏ����Z�p�ƁA�����ϗ��̌��@�͕��e����Ȃ�ł��ˁB �@����̃x���i�G�}�E�X�g�[���j���A����ȃo�N�X�^�[�搶�̑n�앨�̂P�B�̂̓����┭�����܂�ŗc���ŁA�}�i�[��G�`�P�b�g���Ă�ł킫�܂��Ă��Ȃ��̂́A������}���Ĕ]�����������ɁA���̑ٓ��ɂ����Ԃ�V�̔]���ڐA�������߂��B �@�o�N�X�^�[�ɐS�������w���}�b�N�X�i���~�[�E���Z�t�j�́A�x���̍s���̋L�^�W�Ƃ��Čق��A�₪�ĉ��t�̊��߂Ńx���ƍ��邱�ƂɁB�Ƃ��낪�u��������܂ŌN�̑̂ɂ͐G��Ȃ���v�Ɛ錾����悤�Ȍ����N���ł��������߁A�܂������ɖڊo�߁A�u�I�i�j�[���o�������v��ԂɂȂ��Ă����x���͗~���s���B�����Ɍ��ꂽ��ϕٌ�m�̃_���J���i�}�[�N�E���t�@���j�́A�`���������x����D������B �@�o�N�X�^�[�ƃ}�b�N�X�ɕی삳��A�O�o���قƂ�Nj�����Ȃ������x���̌��t�́A�����S�ʂ̉B�ꂽ�{�����]���������ĂĂ���̂ł͂Ȃ��������B�u�}�b�N�X�ƌ�������B�ł��A���̑O�Ƀ_���J���ƃ��X�{���ɍs���B���̂��Ƃ�S�R����Ă���Ȃ����Ȑl�����ǁA�Ȃy����������Ȃ��H�v �@���`��A�����̗~���ɐ����Ȃ������������������A�s�����Ȓj�ǂ��̎q�ǂ����A�L�j�ȗ��A�ۂ�ۂݑ����Ă�������A���܂ł����Ă��N�Y�ǂ��̈�`�q���A���̐����瓑�����ꂸ�ɂ����ˁB �@�x���ƃ_���J�������X�{���ɒ������Ƃ���ŁA���m�N���������f���̓J���[�ɓ]���B����w�i�̓r�N�g���A���̂͂������A���X�{�������̃P�[�u���J�[�͂܂�Ŗ����s�s�̂��ꂾ�B �@�B�e�ē̃��r�[�E���C�A���́A�O���S�X�E�����e�B���X�ēƑg�w�����É��̂��C�ɓ���x�Ɠ��l�A������Y�𑽗p�������j�[�N�ȉ����������B �@���Ոȍ~�̌����́A�u�A���W���[�m���ɉԑ����v�̎�l����f�i������x���̋}�����Ԃ�B���Ղł́ubella want go out.�v���́uWho is you?�v���̂Ɠ��{�l���݂́i�H�j�p���b���Ă����x�����A����Ɍ�b�����@���͂邩�ɐ������ꂽ�p���b���悤�ɂȂ�B�����āA����ȏ�ɐ������ꂽ���{��g�ɂ��A�����Ȃ鑩�������������ꂽ�A�������������ւƕς���Ă����B �@�C�̓łȂ̂́A�V��Ŏ̂Ă���肾�����x���ɂ���u������ɂ����}�[�N�E���t�@�����B���˂悤���A�����낤����̍Ղ�B�����������͖߂�Ȃ��B�I�ՂɃT�v���C�Y�o�ꂷ��x���́i�{���́j�v�̖��H���܂߂āA�Ȃ�قǁA����Ȃ���̂����Ƃ́A���͂�����̂��Ƃł��������B �@����ɂ��Ă��A����܂ł̃L�����A�ł͂قƂ�ǃk�[�h�������Ă��Ȃ������G�}�E�X�g�[�����A�悭�����ꂾ���������炩��ƒE���܂������ˁB �i�Q�O�Q�S�D�Q�D�P�Q�D�L�j �͂�t KUOLLEET LEHDET�^FALLEN LEAVES �i�Q�O�Q�R�N�A�t�B�������h���ƁA�����F�Γc�q�j  �@�ē��ސ錾�����Ă����t�B�������h�̋S�ˁA�A�L�E�J�E���X�}�L�̂U�N�Ԃ�̕��A��B �@�A���T�̓X�[�p�[�̃��W�W�A�z���b�p�͂R�j�E��̍H���B�J�l���Ȃ���Ί�]���Ȃ��A���͂�Ⴍ���Ȃ��u���[�J���[�̏��ƒj���A���R�o����āA�䂩�ꍇ���A����Ⴄ�^���B �E�E�E�ƁA����Ȃ��炷�������������ƁA��C�̕t���������h���}���Ǝv����������Ȃ����A���₢��A�J�E���X�}�L�ꗬ�̃��[���A�₭�����肪�����Ɏd���܂�Ă���̂ŁA�����ĐH�����邱�Ƃ͂Ȃ��A�ނ���ӏ܌㊴�͒g�����B �@���̈��B�݂��̖��O���m��ʂ܂܁A���߂Ĉꏏ�ɉf����ς����̕ʂ�ہA���͒j�ɓd�b�ԍ���������������n���i���̎��ɁA���߂炢�����ɃL�X���悤�Ƃ��鏗�̕�����A�����O�ł͂Ȃ��j�Ŏ�j�̂������Ȃ����A�ǂ���������L�����Ƃ���j�B �@�Ƃ��낪�j�͂��̃������B���~�̉\���ɓq���ĉf��ق̑O�ŘA���҂�������̂����A���͈���Ɍ���Ȃ��B�����ǐ�����A�j�����łɋA������Ƃł悤�₭������ʂ肩���������́A���̏�Ɏ̂Ă�ꂽ���т����������̋z���k�ɖڂ𗯂߁A�u������v���Ďv����ˁB���܂��A���܂�����E�E�E�B �i���Ȃ݂ɂQ�l�����߂Ċς��f��́A�z���b�p�̑I�]���r�f��́w�f�b�h�E�h���g�E�_�C�x�ŁA����͎����V�^�R���i�ً̋}���Ԗ����Ɋς��ꔭ�ڂ̍�i�ł��������B�u���҂͎��Ȃ��v�Ƃ����^�C�g���������A�ǂ��̂Q�l�̐����l�Ƃ��d�Ȃ邩���B���ہA�Q�l�Ƃ��N�r�ɂȂ邽�тɂ����Ǝ��̎d���������āA�Ќ������̂��ł�����ˁj �@�J�E���X�}�L�̕`���w���V���L�́A�ǂ������g���ȃ��[�h�������ς��B����̃W���[�N�{�b�N�X�͔N�㕨�����A�o��l�������̉Ƃɂ̓e���r�ȂǂȂ��A�N�������W�I���Ă���B �@�Ƃ��낪�A���̃��W�I����A���V�A�ɂ��E�N���C�i�N�U�̃j���[�X�����x���J��Ԃ�����Ă���̂ŁA����͂܂��Ɍ��ݐi�s�`�̃h���}�Ȃ̂��Ɗϋq�͒Ɋ�����d�g�݁B�J�E���X�}�L�����A�������R�̏��Ȃ��Ƃ��ꕔ���A���̋`���ɂ��������Ƃ͑z���ɓ�Ȃ��B �@�J�E���X�}�L��i�̂������ɘR�ꂸ�A�剉�̂Q�l�͈�l�ɉǖفB�F�l���m����l���m���ʂ�ہA�������킸�ɈႤ�����Ɂi�܂��ʂ̍��ƉE�Ɂj�n�P�Ă����V���b�g�Ȃ́A�ނ̐ꔄ�����݂����Ȃ��̂ł��ˁB�J�b�R�����킠�B �@�����Ƃ�́u���Ⴀ�ˁv�u�܂����T�v�u�C�����Ăˁv�u�d�b���邩��v�݂����Ȗ��ʌ������킳�Ȃ���f�[�g����ƕʂ���Ȃ����S�҂Ȃ̂ŁA�ނ̂��������V�[�������邽�тɁA�傢�Ȃ�J���`���[�V���b�N�ƁA�ꖕ�̑A�]�������Ă��܂���B �i�Q�O�Q�S�D�Q�D�P�Q�D�L�j �_���E�}�l�[�@�E�H�[���X��_���I DUMB MONEY �i�Q�O�Q�R�N�A�āA�����F���{�T�[�j  �@�č��̃l�b�g�f����łȂ������l�����Ƃ������A�Ηz�̉�Ђ̊�������Ăɍw���B���̂��߁A���̉�Ђɋ���d�|���Ă����w�b�W�t�@���h���呹���o���āE�E�E�Ƃ����Q�O�Q�P�N�̑����́A���{�̈�ʎ��ł����Ă����Ƃ���B����A�����m��Ȃ������̂́A���̌f���ɖ��m�ȌĂт����l�������Ƃ������Ƃ��B �@�l�����Ƃ̃L�[�X�i�|�[���E�_�m�j�́A��Ɖ��l���s���ɒႭ�]������Ă���Ɗ������Q�[���X�g�b�v�Ђ̊����r�m�r�̓���Ő����B������������̍��̓����Ƃ����������ɉ��ƁA�����͂��肶��㏸���A�ŏ��̓n�i�����������Ă��Ȃ������w�b�W�t�@���h�В��̃P�C�u�i�Z�X�E���[�Q���j�͓��ݏグ��]�V�Ȃ����ꂩ����B�������P�C�u�����Ŏ���ƁA�����̌l�����Ƃ����p���Ă����l�b�g�،���Ђ��������������Ȃ��Ȃ��āE�E�E�B �w�A�C�A�g�[�j���x�w�N���G���x�̃N���C�O�E�M���X�s�[�ḗA�������˂Ĉ�ڒu���Ă��閼��B���b�����Ƃɂ������̕���ł́A�r�F���������{�ؕ����ɁA�c��̌�����Ȃǂ̋L�^�f���Ȃǂ��D������A��ʂ̃j���[�X�ł͓`�����Ȃ����X���X�̓��������ʂ���B �@�A�_���E�}�b�P�C�ē̎�ɂȂ�w�o�C�X�x��w�}�l�[�E�V���[�g�x�ƕ����I�ɂ͋��ʂ���쌀�@�����A�w�o�C�X�x�͋������̂���s�J���X�N���������A�w�}�l�[�E�V���[�g�x�̎�l���͓V�˓I�ȃt�@���h�}�l�W���[�A���Ȃ킿�u�P���̑�������v�̑��ɑ�����l�Ԃ��B���̓_�A�{��͔�͂ȃ_�r�f�����͂������ăS���A�e��|�����̂�������Ɏd���Ă��Ă���B �@�����A�L�[�X�̌Ăт����ɉ������l�����Ƃ����́A���ꂱ�������ɂ����̂��낤�B�������M���X�s�[�́A�q�����̊Ō�t��Y�̏��q�w���A���ۂɃQ�[���X�g�b�v�̓X�܂œ����Ă���X���Ƃ��������l�̌��I�ȓo��l����z���āA���̑��̂��\�����Ă���B�����������ƂŐH���Ă���悤�ȃJ���X�}�����Ƃł͂Ȃ��A�R�����҂����Ȃ�Ƃ����₵�āA�����ł���炵���y�ɂ��悤�Ɗ肤�f�l�O���肾�B �@���̔ނ炪���s�����̊܂݉v����ɂ��ĕ�������������A�����Ƃ����Ԃɂ���������ďő����ɕ�ꂽ�肷��`�ʂ͔��^�B�����ϐl�����l�D���̂���L�[�X�̃L���������܂��āA�ϋq���ނ�̈���ɉ�������C���ɂȂ�i���Ȃ����w�b�W�t�@���h��x���`���[�L���s�^���̏d���łȂ�������j�B �@�����̐����Ɋe�o��l���̎��Y�z�������œ���̂����A�ŏI�I�ɑ��̌l�����Ƃ��������Ȃ�̎��Y��z���Ă����̂ɑ��A�A�����J�E�t�F���[����������Ō�t���������̗܂��炢�̋��z�ɂƂǂ܂��Ă����B�z������ɁA�����������}�������Ƃ���ŁA�ł��Ĕ��蒍�����o�����������ł��傤�ˁB �@�����āA���ꂪ�ԈႢ���������ǂ����́A�����܂ł����ʘ_�ł������Ȃ��B�L�[�X���l�D�������邩�ǂ����Ƃ͖��W�ɁA�u�����Ŕ������҂�����������Ƃꂽ�v�Ƃ������ʂɂȂ邱�Ƃ����Ă��蓾���B��قǂ́u�_�r�f���S���A�e��|������v�Ə��������ǁA�����ɂ͔ނ̌Ăт����ɉ������l�����Ƃ̐������A�ߌ���쌀���W�J���ꂽ�ɈႢ�Ȃ��̂��B �@���Ȃ݂ɖ{��̕���ƂȂ����ꎞ���ɂW�O�h���ȏ�ɂ܂ŋ}�L���Ă����Q�[���X�g�b�v�̊����́A��v�Ȋ����w�����j��ō��l�t�߂ɂ����T���i�Q���X���j���݁A�P�S�D�U�U�h���܂ʼn������Ă���B�����A�G���f�B���O�ŃE�n�E�n��Ԃ������o��l���������A���̌�ɂǂ����ŗ��v�m�肵�Ȃ���A�A�����J�E�t�F���[���Ɠ����Q��ł����Ƃ������Ƃ��B�������A���͓���B �@�Ȃ��A�{��̃^�C�g���ł�����u�_���E�}�l�[�iDUMB MONEY�j�v�ɂ́A�����̎����ł́u�����ȓ����v�Ƃ����j���[�g�����Ȗt�����Ă����B �@�������Ȃ���u�l�����Ƃ̓v���ɐH�����ɂ���邾���v�ƌ����ōĎO�J��Ԃ���Ă���_�Ɋӂ݂�A����͂����炭�v���̓����Ɩڐ��őf�l�����������\�����낤�B�����ł���Ȃ�A�u�����҂̃J�l�v���炢�̂����ƃX�g���[�g�Ȗ�����������܂���ˁB �i�Q�O�Q�S�D�Q�D�P�Q�D�L�j �Q�O�Q�R�N�i���́j�x�X�g�X�I �@�ߘa�T�N�Ƃ������g�R���i�S�N�h�ƌĂ����������藈��悤�ȋC�������N�A����ł̊ӏܖ{���͂T�R�{�ɂƂǂ܂����B �@�u���b�N�o�X�^�[��i�ɃX�N���[����Ɛ肳���T�}�[�V�[�Y���͗�N�A�ӏܖ{��������̂�����ǁA�ċx�݂��I����āu�����A�|�p�̏H�v�ƂȂ����Ƃ���ŁA���e�̃_�u�����@���畃�e�̘V�l�z�[�������A����ɂ͂��̋}���ƃr�b�O�C�x���g���d�Ȃ�A�f��ӏ܂ǂ���ł͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂�������ȁA��N�́B �@����Ȓ��œ��M�����̂́A�ӂ��w�ׂ̓�ԊقŊς���i�����ɂP�X�{���߂����ƁB���������Z��ł���̂��h�c�ɂ�����A�ӂ��w�ׂł�����ς�c�ɂȂ̂����A�����Ō����q���[�}���g���X�g��V�����e��V�l�}�J���e�ɂ�����悤�ȃ~�j�V�A�^�[�n�̉�����A�ߔN�͂��̌���ł������������ς���f���Ă����̂ł��ˁB��L�́u���Ƃ̎���v�ʼn��o�����܂�ł��Ȃ����������ł́A���ɂ��肪���������B �@�܂��A��Ԋق�������J���͑����x�߂ɂȂ�̂�����ǁB �@���Ȃ݂ɍ��N�̓x�X�g�P�O�ł͂Ȃ��x�X�g�X��������B���ɐ����Ɂi�싅���݂Ȃǂ́j�Ӗ��͂Ȃ��A�K���ɑ��肵�Ă�������X�{�c�����̂ŁA�ʓ|�����炻�̂܂܌f�ڂ����Ƃ������Ƃł��B �@�č��f�悪�S�{�A���B�f�悪�S�{�A�ĉp���삪�P�{�Ƃ�������B��Ɛ��̋����ē̍�i�����߂Ƀ����N�C���������A�G���U�x�X�E�o���N�X�ḗw�R�J�C���E�x�A�x�͂��ꂵ�������B�l�I�ɂ͂Q�O�Q�R�N�̃x�X�g�ɐ����Ă��������삾�B �@�Ȃ��A�f�ڏ��͗�N�̂��Ƃ��u�ǂ��������v�ł͂Ȃ��A�u�ӏ܂������v�ł��B �P�@�w���ׂĂ��܂������܂��悤�Ɂx �Q�@�w�R���y�e�B�V�����x �R�@�w�E�[�}���E�g�[�L���O�@�������̑I���x �S�@�w�G���U�x�[�g�P�W�V�W�x �T�@�w�A�X�e���C�h�E�V�e�B�x �U�@�w�R�J�C���E�x�A�x �V�@�w���X�g�E�L���O�@�T�O�O�N�z���̉^���x �W�@�w�E�H���J�ƃ`���R���[�g�H��̂͂��܂�x �X�@�w�U�T�^�V�b�N�X�e�B�E�t�@�C�u�x�i�Q�O�Q�R�N�A��) �@�\���҂̋��������� �Ă�����^�C���X���b�v�����Ǝv�������A���ۂɂ͂U�T�O�O���N�O�ِ̈��l����l���B�������`���Ŏ�l���̉F���D��j�����f���Q���A�Ō�ɂ́u�N�����m�邠�̑�覐v�ւƂȂ����Ă����B�Ȃ�قǁA����́u�V�O�v�ł��u�V�T�v�ł��Ȃ��A�u�U�T�imillion years ago�j�łȂ���Ȃ�Ȃ������̂ł��ˁB �@�X�g�[���[����@�܂���@�̘A���B���Ăĉ����āA��l�ő�����Ǝv�����݁A��x�͎��������ӂ����A�_���E�h���C�o�[���A����܂Ƃ��ɂȂ肻���ȏ����������������߂ɁA�������Ď��ʂ킯�ɂ͂����Ȃ��Ȃ�Ȃ�ĐS���`�ʂ�����ڂ������Ȃ��B �i�Q�O�Q�S�D�P�D�P�R�D�L�j �E�H���J�ƃ`���R���[�g�H��̂͂��܂� WONKA �i�Q�O�Q�R�N�A�ā��p�A�����F�ݓc�b�q�j  �@���̒��ɂ́A�u�ʂɍ����͂Ȃ����lj��ƂȂ��݂�Ȃ��^�����Ǝv���Ă��邱�Ɓv��A�u�^�����Ƃ����v���Ă��Ȃ��̂ɁA�Ȃ��������̐l�̏펯�ɍ��肱�܂�Ă���悤�Ȃ��Ɓv�����R�Ƃ��đ��݂���B���t�^����ʂ̐��i�f�f�Ȃ͂��̓T�^��ł��ˁB �@���邢�͌��̏K����s���Ɋւ��锼�Ȓm���Ȃ������B�č��̓����R���f�B�f��Ȃǂ��ςĂ���ƁA�N�����{�[���𓊂��邽�тɁA���˓I�ɂ����ǂ������Ă��܂��o��g���h���Ȃ��悭�o�Ă���B �@���ꂩ��ŋߊς�����f��ł́A�l�Ԃ̌��t��b����悤�ɂȂ��������u��l�̖��߂ɕ��]����͍̂D�����v�Ȃ�ăZ���t��f���Ă����B�ǂ�����Œ�ϔO�̎Y���ł���A�ʂɂ��ׂĂ̌������������킯�ł͂Ȃ���ł��傤���ǂˁB �@���āA���������u���������A���邠��v�̂P�ɁA���͗X�֔z�B�l�����݂�����Ƃ����̂�����i���{�ł͂���قǕ��y�����Œ�ϔO�ł͂Ȃ�����ǁA�č��l�́g�펯�h�ł͂����Ȃ�ł��ˁj�B�w�|�X�g�}���x(1997)�ŃP�r���E�R�X�i�[���������X�֔z�B�l���A�q�[���[�ƂȂ��Ă݂�Ȃ̑O�ʼn������Ԃ��ɁA�u���͂Ȃ��Łv�ƌ����Y����̂�Y��Ȃ������B �w�E�H���J�ƃ`���R���[�g�H��̂͂��܂�x�ɂ́A���́g�펯�h���t��Ɏ�����M���O���g���Ă��ď킹����B�e�B���V�[�E�V�������������l�����I���r�A�E�R�[���}���̌o�c����h���ɓ��h����ƁA�h���̎��������ނɂ��Ȃ肩�����ł���B����ƃV���������H���A�u�l�̃Y�{���͗X�։�����̂��Â�����ȁv �@���������X�֔z�B�l���P���̂́A�����i�Ƃ���l�l�j�̃e���g���[�ɓ����Ă���菓��҂�ǂ��o�����߂��B�X�֔z�B�l������\�\�܂��Ă�X�֔z�B�l�̕��𗈂��z������\�\�P���Ƃ����̂ł́A�܂������b���t�ŁA���Ƃ����������炠��Ⴕ�Ȃ��B �@�������b�����Ղɓ���ƁA���[�������i�[�ɏ悹�����ɂ��̃Y�{���̐�[��ǂ����������邱�Ƃŋ���ȋ@�B���쓮������Ȃ�ē�i�I�`���B�|�[���E�L���O�ēɂ́A���Ѝ��z�c�P�������グ�����B �@���āA���͂Ȃ��Ă���ȃ}�j�A�b�N�ȓ_��_�]���Ă���̂��H�@�ϐl���ƃo���Ȃ��悤�ɁA�����������ʂ̊��z�������Ă������B �@�V���������������̂́A�w�`���[���[�ƃ`���R���[�g�H��x�i2005�j�ŃW���j�[�E�f�b�v���������E�B���[�E�E�H���J�̎Ⴂ���B�ނ��܂��A����قlj������ɂ��������ϓ��ɂ��Ȃ��Ă��Ȃ���������̑O��杂ł��ˁB �@�Ƃ͂����A�V�������̃E�H���J�͂��łɃ`���R���[�g�E�l�Ƃ��Ă����p�t�Ƃ��Ă��J�Ⴕ�Ă���l�q�B�������ϓ��̃f�b�v����V��ȍs�����Ƃ��Ă��ʂɋ����͂��Ȃ��������A�ق��̓_�ł̓E�u�ȃV�������E�E�H���J���A��������Ŗ��p����g����V�[���ɂ͈ӊO��������B�������A�E�H���J���Ė��@�g���������̂��ƁA���߂Ď��������B �w�p�f�B���g���x�V���[�Y�̃L���O�ḗA���A���h�E�_�[���ƃe�B���E�o�[�g�����R���r��g�O��̃_�[�N�ŃV�j�J���ȕ��͋C����]�����A�z���őO�����Ȉ��Ɏd���ĂĂ���B����t�@���͐H������Ȃ���������Ȃ�����ǁA�����܂ŕʕ����Ɗ����A����͂���ł�����Ȃ����ȁA����B���͌l�I�Ɍ�������Ȃ��B �@�~���[�W�J���E�V�[���̃Z�b�g�f�U�C�����ؗ킾���A�V�������̉̏����i���E�}�Ƃ܂ł͌����Ȃ����j�y��_�̓N���A�B�q���[�E�O�����g���E���p�����p�������ʼn����Ă����Ƃ͎v��Ȃ����A�I�����W�F�̔��ɗΐF�̔����������̃L�������A�ӊO�ɔ��������ڂ����Ă��邱�Ƃ��킩��J�b�g�Ȃɂ́u�������v�ƙ��ڂ����B �@�V�������̃E�H���J���J��Ԃ����̂́A�u�X�e�L�Ȃ��Ƃ͂��ׂĖ�����n�܂�v�Ƃ����|�W�e�B�u�ȃ��b�Z�[�W�B�ߘa�ɉ�������Ă���A�ǂ��������O�Ƃ��ɗǂ��Ȃ����Ƃ��肪�N�����Ă��銴�����邯��ǁA�q�ǂ��������i���Ă̎q�ǂ��������܂߂āj���߂Ė���`���鐢�̒��ł����Ă��ꂽ��悢�Ǝv���B �i�Q�O�Q�R�D�P�Q�D�P�V�D�L�j �R�J�C���E�x�A COCAINE BEAR �i�Q�O�Q�Q�N�A�āA�����F��s����j  �@���₠�A�G���U�x�X�E�o���N�X�ēA�f���炵���B���̂Ƃ���u�����ē����Ȃ��L�c�߂̔��l���D�v�Ƃ����|�W�V��������������}�[�S�b�g�E���r�[�ɒD���Ă��܂����������������ǁA���ꂾ���y���܂��Ă��炦���當��͂Ȃ���B �@�����l�����^�@���瓊�������R�J�C�����A�쐶�̃N�}���H�ׂĂ��܂��A�������Ď��X�Ɛl���P�������B���b���̂ł͂��邯��ǁA���ǂ���ł͂�������킹�Ă���邵�A�X�����[�`�ʂł͂����ƃn���n�������Ă���邵�A�X�g�[���[�^�т̊ɋ}�����Q���B�N�}���\���郍�P�[�V�����������A�X�A�r�W�^�[�Z���^�[�A���A�ȂǂȂǑ��ʂȂ̂ŁA�O�����苏���肵���肷�邢�Ƃ܂͂܂������Ȃ��B �@����ɑf���炵���͓̂o��l�������̑��`�Əo������ł��ˁB�����ӋC�����Ǒ��߂Ȃ����w���J�b�v���A����������V���O���}�U�[�i�P���[�E���b�Z���j�A�U�킵�������������悤�Ƃ���{�X�i�̃��C�E���I�b�^�j�A�����������̑��q�i�I�[���f���E�G�A�G�����C�N�j�A�^�t�ŋ`���S�̋����q���i�I�V�F�A�E�W���N�\���E�W���j�A���A�C�X�E�L���[�u�̑��q�j�Ƃ�������v�L�����́A�������炸���͓I�B �@���ۂ̊W�҂�����قljf��I�Ȑl�����肾�����Ƃ͎v���Ȃ��̂ŁA���̓_�̓o���N�X�Ƌr�{�ƃW�~�[�E�E�H�[�f���̑z���͂ɋA���ׂ����тȂ̂��낤�B �@�ނ炪����Ɉ�Ȃ���e�������Ɨ��݂A���ɉ^����������������A���������N�}�̉a�H�ɂȂ����肵�Ȃ���D��グ�Ă�������́A�ǂ��Ӗ��ła���f��̎��|�B�Ԕ����ȓz��@�����Ȃ�Ȃ��z���珇�Ɏ���ł����Ƃ����\�����A�ϋq�ɉ��Ƃ���������̂�����i����������Ăq�P�T�{�Ȃ�ł����ˁj�B �@���X�g�Ŕ��������Ƃ���������Ă����`���s�����̃A�[�����E�z���f�[�́A���߂Č�����҂��������A�T������b�N�E�F������Ԃ点���悤�Ȃ�����Ɩʔ������͋C�̎�����B�u���낵���N�}���ގ�����Ă߂ł����߂ł����v�̃G���f�B���O�ł͂Ȃ��Ƃ�����A�}�S�̃A�j�}���p�j�b�N���Ƃ̑傫�ȈႢ���B �@���āA�k�C���ł́A���̉āA�\�̃q�O�}�u�n�r�n�P�W�v�̎ˎE���m�F���ꂽ�B���X�̕��������A�{���A�̎��Ȃǂ���H�Ƃ���q�O�}���A���ꂾ���������P���̂͐q��ł͂Ȃ����Ƃ炵���B �@�N���W��������ݒ��ɁA���N�����قǂ̃R�J�C����u���Y�ꂽ�l���܂��H �i�Q�O�Q�R�D�P�O�D�P�X�D�L�j �G���U�x�[�g�P�W�V�W CORSAGE �i�Q�O�Q�Q�N�A�I�[�X�g���A=���N�Z���u���N=��=���A�����F���Y���ށj  �@�^�C�g�����[���̃G���U�x�[�g���N�ł��邩��m���Ă���̂́A���̓��{�ł͕�˂̃t�@���ƁA�Ő��E�j��������l���������Ȃ̂ł͂���܂����B���͂��̂ǂ���ł��Ȃ��̂ŋq�Ȃł܂������̌ܗ��������������A����͂���őz���������Ėʔ����ӏ܂ł����B �@����͂ǂ����A���a�̍��ɐ��E�j�̎��Ƃŕ������������I�[�X�g���A���n���K���[�̓�d�鍑���Ă�B���E�j�I���`�̊ϋq�i�����j�̖ڂɂ́A�G���U�x�[�g�̓n���K���[�̏o�g�ŁA���������ŃI�[�X�g���A�̍c�܂ɂȂ������Ɍ������B�c�����Ƃ͂����n���K���[��ʼn�b���邵�A�v�ł���c�邩��u�n���K���[�͉䂪�鍑�ɉ��������o�����H�v�ƁA���x���ӂ߂��Ă��邩��B �@���Ƃ�������T�C�g�Ŋm�F�����Ƃ���A�ޏ��͎��ۂɂ̓o�C�G���������̉����o�g�ŁA�n���K���[�ɂ͒P�ɃV���p�V�[���Ă��������炵���B�ł��A���Ⴂ�����犨�Ⴂ�����܂܂ŁA����ɑz����c��܂��Ċy���߂�̂��f��̗ǂ��Ƃ���ł���ˁB �@�Ȃɂ��낱�̍c�܁A�v�̍c������w���������A�t�F���V���O�ł���{������Ⴄ�����B�U�߂��e�[�u�����h���ƒ@���Ėق点�悤�Ƃ��悤���̂Ȃ�A���������h���ƒ@���Ԃ����Ⴄ�Ȃ̂��B���{�̐퍑����̉����l�Ƃ͂����ԃC���[�W���Ⴂ�܂��ˁB �@�����������b�̃h�C�c��A�O�q�̃n���K���[��ɉ����āA�C�M���X�̌����l�̂Ƃ���ɍs���Ήp���b�����A�f��������t�����X�l�ɂ��ڒʂ�������t�����X���b���B�����������{�l�ł���A���R�l�Ȃ̂ł���B �@����ȁu���l�`����v�ł����Ȃ��ޏ������炱���A�����ȍc���̂��������A�]�܂ʉ���ɒ�R�����ɂ͂���ꂸ�A���ɂ킪�܂܂Ŕj�V�r�ȐU�镑���ɑł��ďo��̂��낤�B���j���Ɍ`����Ă͂��邪�A����͌���ɒʂ��鏗���f��ł�����B �@�剉�̃r�b�L�[�E�N���[�v�X�́A�ǂ�������܂ł̏o����ł͍Ⴆ�Ȃ������Ɍ����������������A�{��ł͈ӊO�ɍ��M�ȃI�[�����B����ł͕s�f�̑��ɏ���Ă��܂����M�w�l�́u�l���̔��v���]���Ƃ���Ȃ��\������i�f���Ă������A�����̂S�O�Ƃ́A�����̈�҂��u��ʏ����Ȃ畽�ώ����ł��v�Ɛi������N��j�B���N�Z���u���N�̏o�g�����ɁA���B�I�ȕ��͋C�ɂ��s���͂Ȃ��B�N���[�v�X���g�����N�S�O�ƁA�ǂ��^�C�~���O�ŗǂ��Ɍb�܂ꂽ��ۂ��B �@���ڂ��ׂ��́A�I�[�X�g���A�̏����ē}���[�E�N���C�c�@�[���A�K����������𐳓��I�ȗ��j���Ɏd���ĂĂ͂��Ȃ����ƁB �@�����b�Ȍ�����������ƁA������ƃw���e�R�ȏ�ʂ��ڔ������Ȃ�ł���B �P�j���Ƃ��Ζ`������₽��Ɩj�q�Q�̗��h�Ȓj�����肪�o�Ă���Ȃ��Ǝv���Ă�����A�c��É����x���b�Ƃ�������Č������B�t���q�Q��������ł��ˁB  �Q�j�c�܂̂S�O�̒a�����B�ۂ��P�[�L�̎l���Ƀ��E�\�N����������ł���̂ŁA���ꂶ��ꑧ�ł͐��������Ȃ��ł���Ǝv���Ȃ��猩�Ă�����A���]���P�[�L����]�����āA���Ԃɏ������Ă����B���l�^�Ȃ���ӊO������B �R�j�d�b�������c����鍑���̂Ō}����V�[���A�̂��Ă����̂͌��݂̃h�C�c���̂̃����f�B�[�������B�������̎��̓n�v�X�u���N�Ƃ��̂�����e�Ȃ�ł��ˁB�m��Ȃ�������B �S�j���ՁA�G���U�x�[�g�������̋��ʼn����̒��x�i�ɂ悶�o���ʂ�����B�J�����̎��p�ɂ͑��������āE�E�E�Ƃ����W�J�͌ォ��킩��̂����A�ē͂�����L�Ԃ̔��Α�����A�܂�ő��l���̂悤�Ɉ����̉�ŎB���ł��ˁB���ʂȂ猈�ӂȂ���S�Ȃ�̕\����A�b�v�łƂ炦����A���g����n�ʂ������낷�V���b�g����ꂽ��A��������l���𑋊O�̃J��������ǂ����肷��ł��傤�ɁB �T�j�{�a�̒��ɃG���U�x�[�g�̓���������悤�ȓV��̒Ⴂ�������P����B�ޏ��̐S���I�NJ���\�������Z�b�g���Ƃ����߂ł��邪�A�K������������������o�ɂ͂Ȃ��Ă��Ȃ��̂ŁA���ۂɓV��̒Ⴂ�������������̂��ǂ������f�����Ȃ��B �U�j���Ȃ�����}���̂̉̎����A�Ȃ�����{�̃h�C�c��ł͂Ȃ��A�S���p��ŁA�������Ȓ������㕗�B�����錀���Ȃ炻����킩����ǁA�����̊y�m���M�^�[��n�[�v��t�łȂ���̂��Ȃ܂ł��A�S�R�P�X���I�I����Ȃ��B �@����Ɍ����Ȃ�A�q���C���Ə����������ŏI�ՂɃC�^���A���s�ɌJ��o���V�[���ł́A�^�g�D�[���������N���[�Y�D���A���炩�Ɍ���̎Y�����B �@�N���C�c�@�[�ēA�G���U�x�[�g�ɏ���Ƃ����Ȃ����R�l�ł��ˁB�@ �i�Q�O�Q�R�D�X�D�X�D�L�j �t�@���R���E���C�N FALCON LAKE �i�Q�O�Q�Q�N�A�������A�����F����a�q�j  �@���������P�S�ɂȂ鏭�N���A�ΔȂ̔����n�łP�U�̏����ƍĉ�E�E�E�B�Ƃ�����g���A���������ǂ�ȉf�悩�z�������܂��ˁB �@���ہA���N�o�X�e�B�A�������w�Z��w�N���炢�̒�ɐڂ��鎞�́u�S�\���v�ƁA�����N���G�̔N���̃{�[�C�t�����h�����Ɉ͂܂ꂽ���́u���\���v�̑Δ�Ȃ́A���Ղ��炤�܂��\���ł��Ă����Ǝv���B �@�����A�S�̂Ƃ��Ă͊��҂����قǂ���Ȃ��B�o�X�e�B�A���́u����a�v�Ԃ���A�N���G�̏������Ԃ�����r���[�B�M���҂̗H�삪�����Əd�v�ȃ��`�[�t�ɂȂ�̂��Ǝv�������A������P�Ȃ鏬�l�^�̈���o�Ȃ��B �@�̐S�v�́u���^�E�Z�N�X�A���X�v�I�ȗv�f���A���{�l�̊��o���炷��ƂQ�l�Ƃ����I�ɃI�[�v�������āA������ɂȂ�Ȃ���ˁB�N���G�̓o�X�e�B�A���ɕ��C�ʼn����p�������邵�A������̉ʂĂɂ���X�Łu�����āv������������B����ł́u�B���ȗ��v�ȂǗU���Ȃ����A���L���������Ă��Ȃ��ł���B �@���̌������l����ɁA�����炭�ē̃V�������b�g�E���E�{����������������ĂƂ��낪�����Ȃ����Ȃ��B�����Ă��܂��A�ϋq���o�X�e�B�A���ɂ��܂�����ړ��������Ă��Ȃ��̂ł���B�܂��A����������������A�u�j�ǂ���A����ȂƂ��Ɋ���ړ����Ă�˂��v�Ƃ���ɁA�m�M�ƓI�Ɂu���̖ڊo�߁v�f��̒���X�J�����\��������B �@�t�ɏ����ēƂ��Ă̖ʖڂ����@����Ă����V�[�������Ȃ��Ƃ��P�����āA����̓o�X�e�B�A���ƃN���G���u���̐��ň�ԕ|�����Ɓv��������������ʁB �@�j�̎q�Ƃ����̂͌Í��������킸�A�z������A����������ʂŁu�e�ɃI�i�j�[�������邱�Ɓv�ȂƓ�����킯���B����A���̎q�Ƃ����̂͌Í��������킸�N�������l�тĂ��邩��A�����ڂ����Ă���Ȃ��Ƃ��Ԃ₭�B �u�ǂ��ɂ������̋��ꏊ���Ȃ��C������́B�ꐶ���̂܂܂Ȃ�Ȃ����Ǝv���ƁA���܂�Ȃ��|���Ȃ�v �@���E�{����������ē����̂́A�ЂƂ��ɂ��̐Ȃ��r�r�b�h�Ȉꌾ���B�肽���������炾�����̂�������Ȃ��B �i�Q�O�Q�R�D�X�D�X�D�L�j �A�X�e���C�h�E�V�e�B ASTEROID CITY �i�Q�O�Q�R�N�A�āA�����F�Γc�q�j  �@�|�b�v�ȐF�ʐv�ƃZ�b�g�A���ȃL���X�g�A�l��H�����ؗ��āA���ɃV�j�J���Ŏ��ɒg���ȓƓ��̃Z���X�E�I�u�E���[���A�B�E�F�X�E�A���_�[�\���ē̎��Ɩ��Ē��̍�i���E�́A����ł��ς�炸�S�J���B �E�E�E�Ƃ����_�͊m���Ȃ��A�f�p�ɋ^��Ɏv�����Ƃ��P�B���h�ē̌��I�Ȏv�����ɋ^���悵�Ă��F�������Ƃ����ǁA���̉f��A����q�\���ɂ���K�v�����������H �w�t�����`�E�f�B�X�p�b�`�x���Q�O���I�㔼�̃p�����A�w�O�����h�E�u�_�y�X�g�E�z�e���x���P�X�R�O�N��̓�����ɂ��Ă����悤�ɁA��������ʂɁu�P�X�T�O�N��̕č��쐼���ŋN�������Ɓv�Ƃ����ݒ�ʼnf������A����ŕK�v�\���������̂ł͂Ȃ��������H �@������ɊḗA�{�ł��鍻���̒��ł̏o�������A�������ƈʒu�Â��āA�J���t���ȃV�l�X�R�T�C�Y�ŎB�e�B���̕��䌀�̍���ł��錀��Ɓi�G�h���[�h�E�m�[�g���j�║��ēi�G�C�h���A���E�u���f�B�j�̏o����ʂ��A���m�N���̃X�^���_�[�h�T�C�Y�ŕ`���������B �@����䂦�ɖ{����u��d�\���v�ƕ]�����]�����������ǁA���ۂɂ̓u���C�A���E�N�����X�g����������肪����ɂ��̈�i��ʂɂ��āA����Ƃ║��ē̎��͂ɋN����h���}���A�{�Ƃ͕ʌɊϋq�Ɍ�蕷������`�������B�܂肱��́A�ނ���u�O�d�\���i��d�̓���q�j�v�̃h���}�Ȃ�ł��ˁB�Ȃ��o����]�҂ɑ��Ė̐�������Ȃ���������A���d�̓���q�\���ɂ��Ė�����L���X�g�𑝂₵���݂������i�j�B �i���Ȃ݂ɁA�������܂��w���e�R�ȂƂ���Ȃ̂����A�ނ痠���̓o�ꂷ��Z�b�g�̕����A�{���A���䌀�Ɛݒ肳�ꂽ�����̒��̃Z�b�g���������ƕ��䌀���ۂ��j�B �@���āA���̃I�[���X�^�[�f��̒��j���Ȃ��̂́A���������J�����}�����̃W�F�C�\���E�V�������c�}���Ə��D���̃X�J�[���b�g�E���n���\���ł���̂�����ǁA�����ɍ���́w���[�����C�Y�E�L���O�_���x�ȗ��A�A���_�[�\�����v�X�Ɏq�ǂ�������劈�����L�b�Y�f��ł��������B �@������R�g���̃K�L���`���������A�Ƃ������Ђ�������l����������������ł��ˁB �i�P�j�P�g�ڂ̓o�X�����̓r���ō����̒��Ɋʋl�߂ɂ��ꂽ���w�Z��w�N�����B��펖�Ԃ����Ƃ������ɏ��낤�ƕK���̎Ⴂ�����t�i�}���E�z�[�N���C�[�T���E�z�[�N�ƃ��}�E�T�[�}���̖��j���A���C�Ɏ���U�߂ɁB �i�Q�j�Q�g�ڂ̓V�������c�}���̊w��O�̂R�l���B�������G�W�v�g�̉����������̂��A��e�̈�D���������^�b�p�E�F�A��������̒n�ʂɖ��߂悤�Ƃ��ẮA���e��c���i�g���E�n���N�X�j��|�M����B �i�R�j�R�g�ڂ́A���̂R�l���̌Z�M��n���\���̖����܂ނT�l�̓V�˒��w�������i�`���ʐ^�j�B�ނ�͖{��̉B�ꂽ������B �@�Ȋw�܂̕\�����邽�߂ɂ��̍����̒��ɂ���ė����T�l�́A�����ł�������a�^������̔N��ł���Ƃ���Ɏ����Ă��āA�����ǂ����Ď��͂Ƃ���܂�Ȃ��߂Ȃ��B�ނ���������Ă����e�������炵�āA�u���̎q���V�˂łȂ�������A�ǂ�قNJy���������Ƃ��v�ƍl���Ă���ӂ����B���̂T�l�������u�ߎS�ȋ����v�ɂ��铯�N��̒��ԂƏ����A�����܂��ӋC��������z�b�R�����ƌ�������I �@����厖���̂��߂ɐ��{�ɕ������ꂽ�����̒��ŁA�m�b�ƃ`�[�����[�N�����炵�A�S�Ăɐ^�������[�N����̂��A���̓V�ˎ��������B�ނ�͎����̐e�⏗���Ȋw�ҁi�e�B���_�E�X�E�B���g���j���܂ގ��͂̑�l�������A����������蓪�������̂�m���Ă���B�����Ď��͂̑�l���������̎�����m���Ă���̂��A�悭�m���Ă���B����ȋ��S�n�����̒��ŁA����ł������ɐ܂荇�������悤�ƁA���X���Ȃ��Ɋ撣���Ă���B����͑z�������ǁA�A���_�[�\���ē��g�����������V�ˎ��̂P�l�������̂ł͂���܂����B �@���Ȃ݂Ɂi�P�j�`�i�R�j�̎q�ǂ��������A����������R�z���ł���Ȃ���A��l�����Ɂi�����Ɂj������ꂽ���Ƃɂ͑f���ɏ]����������A�A���_�[�\���ē̑P�ӂƗǎ����������čD�܂����Ƃ���B �i�Q�O�Q�R�D�X�D�X�D�L�j �T��}�[���E MARLOWE �i�Q�O�Q�Q�N�A�A�C�������h=�X�y�C��=���A�����F�D�z�q�q�j  �u�Ӂ[��A���[�A���E�j�[�\���̃t�B���b�v�E�}�[���E���ˁv�Ƃ����v���Č��ɂ�������A�N���W�b�g������n�߂Ă���j�[���E�W���[�_���ē삾�ƋC�������B�l�I�ɂ́w�u���C�u�����x(2007)�ȗ�����B �@����͂P�X�R�X�N�̃J���t�H���j�A�B���P�n�̓A�C�������h�ƃX�y�C���������悤�����A�Ԃ�t�@�b�V�������܂߂āA�����̕��͋C�����܂��Č�����Ă���B�勰�Q�̉e����܂��E���Ă��Ȃ������̂��A�}�[���E�������ɕ�����X�Łu�d����T���ɗ����̂��H�v�Ɛq�˂���̂��ʔ����B �@�q���C���̓_�C�A���E�N���[�K�[�ŁA���q���C���̓W�F�V�J�E�����O�Ƃ����a���B���̂Q�l�͂����ݍ����Ă��������q�̖Ȃ̂����A�u�����h�̐F�������p�[�}�̃J�[�����قړ����B�Ȃ̂ɖ{�l���������͂��N�����̂��ƂɐG��悤�Ƃ��Ȃ��̂��A�Ȃ�Ƃ��V���[���ȃ��[�h�������B �@�n�[�h�{�C���h��i�̓`���ɑ����āA�ؗ��Ăɂ͗���ƑΗ��A�U��Ɩ\�͂��Q�����A�T��ΒT��قLjӊO�Ȏ�����V���Ȉ��}���N���ďo��B������m���Ƀ}�[���E���炵���͂���̂�����ǁA����ŁA���掟��Ɂu�����ɂ��p�^�[�������Ȃ���܂����v�Ƃ��������ɂ������Ă���B�˗��l���t�@���E�t�@�^�[���ł���_����n�܂��āA�����͕�̏L���������ł��ˁB �@��������̂͂��A����̓��C�����h�E�`�����h���[�ȊO�̍�Ƃ��������w�����O�E�O�b�h�o�C�x�̌��F���҂Ȃ̂��Ƃ��B �@����ł��}�[���E�ق��̓o��l�������������킷�Z���t�́A�`�����h���[��ɂЂ˂�ɂЂ˂��������������A���Ă���Ǝ��R�Ƀj���}�����Ă��܂��B�����������������Ă���ƁA���̈Ӗ������ݎ���܂łɁA�������R�����炢��ɐi��ł��܂��Ă��邱�Ƃ�����̂ł����ӂ��B �@���������Ђ˂����Z���t�Ƃ����̂́A���̂܂ܖĂ��ϋq�ɓ`���Â炢���A���Ƃ����Ċ��ݍӂ�������Ɩ��킢�����Ȃ��Ă��܂��B�����|��҂���͂��������ɋ�S�������Ƃ��낤�B �@�{�Ƃ͑S�R�W�Ȃ������ł����P�������̂́A���Ă̓^�o�R���ǂ�قǗL���ȃR�~���j�P�[�V�����̃c�[���ɂȂ��Ă����̂��Ƃ������ƁB���Ă���ƁA�T���ɂP�炢�̊��ŁA�}�[���E�����X�̓o��l���Ƃ̊ԂŃ^�o�R�����ߍ����A�b�̒[�����J������A�C�������i�K�������P�ӂƂ͌���Ȃ����j�ʂ����킹���肵�Ă���B�Ƃ������A�j�[���E�W���[�_�������̂悤�ȉ��o�������Ă���B �@��������Ă���ƁA����Љ�ɃR�~�������������肪�������̂́A�^�o�R���z���K�����p�ꂽ�̂�����Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv����قǁB �@�܂��A���̓j�R�`�����łł��R�~����ł��Ȃ��̂ŁA�ʂɋi���V���ɖ߂��Ăق����Ƃ͎v���܂��ǂˁB �i�Q�O�Q�R�D�W�D�U�D�L�j �E�[�}���E�g�[�L���O�@�������̑I�� WOMEN TALKING �i�Q�O�Q�Q�N�A�āA�����F�䌴�ޒÎq�j  �@�\���m�����قƂ�ǎd���ꂸ�Ɋς��̂ŁA�J�n����S�O����ƂX�O����̓�x�A����̍��Ȃ���]�����������ɂȂ����B �@����́w�Y���W�����E�u�b�N�^�ڌ��ҁx(1985)�Ɠ��l�ɁA�@�B�����Ƃ͖����̕�炵�𑗂��Ă���炵���R�~���j�e�B�B���������͋����������ꂸ�A�������n�}���ǂނ��Ƃ��ł��Ȃ��B �@������ŁA��O���A�w�^������19���I���炢�̘b�����Ȃ��Ǝv���Ă�����A���ɑ����i�K�ő�Q������̕���ł��邱�Ƃ������B�ʂẮu�Q�O�P�O�N�̍����������v�܂ʼn���Ă����B�Q�O�P�O�N�Ȃ�āA�����̊Ԃł͂Ȃ����B�ǂ��łǂ�����A����ȑf�p�ȕ�炵���ێ��ł���̂��H �@�P�������̉��l���f�͔����ɂ��Č������A�T���E�|�[���[�ē̃X�g�[���[�e�����O�͊ϋq�ɑ��Ă��Ȃ�s�e�B�j���ɋs����ꂽ�����������u�����v���u�키�v���u��������v���c����̂��{��̑�����A�o�����̐����͏����̊ȒP�ȃ��m���[�O�ɂ���Ă݂̂Ȃ���A�������Q�l���鏭���̂����̂ǂ��炪����Ȃ̂����A��������肩����u���Ȃ��v���N���w���̂����A���炭���Ȃ��ƌ����Ă��Ȃ��B �@���c�ɎQ������̂͂R�̉Ƒ��̏������������A���ꂼ��̖𖼂≏�ʊW�A�R�̑I�����̂ǂ�𐄂��Ă���̂����`���Ŗ������ꂸ�A�ςĂ��邱����͖��̒���i�ނ悤�B�W�F�V�[�E�o�b�N���[�ƃN���A�E�t�H�C�̊炪�܂��Ђǂ����ԈႦ�₷���̂Łi���������H�j�A�Ȃ����獬����������B �@���Ăĉ����āA�킩��Ȃ��̂͂��̃R�~���j�e�B�̍����`�Ԃ��B�ǂ������������́A�����_���ɒj�������Ƀ��C�v����A���܂����q�ǂ����Y�܂���Ă���炵���B �@�Ȃ�����Ƃ����V�X�e�������݂��Ȃ������I�ȋ����̂Ȃ̂��Ǝv������A�ꕔ�̏����ɂ͕v������l�q�B����Ȃ�Εv�╃�e���A�Ȃ►�̈��S���i������������Ύ����̟����⏊�L�����j��낤�Ƃ��Ă��悳�����Ȃ��̂����A�j���͊F�A�u�����ɑ���x�z�ҁv�Ƃ��������T�C�h�ɗ����Ă���悤�Ȃ�ł��ˁB���ꂪ���b�����Ƃɂ����b���Ƃ������ƂɁA�����ƈ�a�����ւ����Ȃ��B �@��x�ڂɃV�[�g����]���������̂́A�W�������邱�Ƃɂ��������������u��\�����𗊂�ɕ��p��m��v�ƌ����o�������B���������A�k�Ă̘b��Ȃ��������I�@��������w�W�����E�u�b�N�x�ɐ���ς�A���t�����Ă����B �@�씼�������䂾�Ƃ킩�������_�ŁA���̓I�[�X�g�����A���j���[�W�[�����h�̘b���Ǝv�������A����A�����|������ꂽ�䌴�ޒÎq����̕��͂�q�ǂ����Ƃ���A����̓{���r�A�ɏZ�ށu���m�i�C�g�v�̘b���Ƃ����B�Ǖ��ɂ��āu���m�i�C�g�v���Ȃ��m�炸�A�Ă������Z���̂��Ƃ��Ǝv������A���ׂĂ݂���L���X�g�������h�̈�h�̂��ƁB�l��I�ɂ͉��B�n�̈ڏZ�҂炵���B �@���[�ށA��Z���Ȃ�킩�邯�ǁA���l�̒j�����A�Q�P���I�Ɏ�����A����ȑO�ߑ�I�ȉ����Ɛl���ӎ���ێ����Ă���Ȃ�āB�E�E�E�ƁA�����l���Ă��܂��̂́A�������A�܂��ʂ̐���ςł���킯�����B �@��炵�Ԃ�̑O�ߑ㐫�Ƃ͑ΏƓI�ɁA�P�O�l�قǂ̓o��l���ɂ�铢�c�́A�����قNjߑ�I�����ݓI�B���ł��ЂƂ���P������̂́A��͂����̃��[�j�[�E�}�[�����낤�B�]�܂ʔD�P���������A�{��Ƌ�Y����S�ɔ�߂��l���ɕ����Ȃ�����A���₩�ŗ��m�I�Ȍ������I�n�����Ȃ��B �@����Ɍl�I�ɂ́A�W���f�B�X�E�A�C�r�[�ƃV�[���E�}�b�J�[�V�[��������N���̓o��l���i��̎ʐ^�̉E�[�̂Q�l�j����ۂɎc�����B�����ƌo���m�ɗ��ł����ꂽ�ޏ���̌��t�́A�܂��Ɏ�ʁB���̕��A��������˂��t�����V�X�E�}�N�h�[�}���h���A�V���̊���Ԃ�����Ɉ����Ă���B �@���̉�b���A����ɖ|�Ă��Ă��ʔ�����������Ȃ��ˁB �@�ÐF�̃v�����g�n�ł��낦���ߑ��f�U�C�����G��B �i�Q�O�Q�R�D�U�D�P�S�D�L) ����ł����͐����Ă��� UN BEAU MATIN �i�Q�O�Q�Q�N�A���A�����F�葩�I�q�j  �@���A�E�Z�h�D���������l���̃T���h���ɂ́A�u�V���O���}�U�[�v��u�L�����A�E�[�}���i�ʖ�ҁj�v�Ƃ������������B�������A���̕���̗��ւɂȂ��Ă���̂́u�s�ωf��v�Ɓu�V�l���f��v�Ƃ����Q�̑��ʂ��B �y�s�ωf��z �@�v�Ǝ��ʂ��ĂT�N��ɏo������̂́i�����ɂ͍ĉ�炵�����j�A�Ȏq����j�N���}���i�����r���E�v�|�[�j�B�������A�܂��A�T�^�I�ȗD�_�s�f�j�ŁA�T���h���ɂȂт������Ǝv���A�Ȃ̌��ɖ߂�����ƁA�S�R������܂炸�B�G���f�B���O���}���Ă��Q�l�̋A���́A�悤�Ƃ��Č����Ȃ��B�Ȃ��ݕ������̂s�u�h���}�u���Ȃ������Ă���Ȃ��Ă��v�ƃ_�u�镔�����B �@�N���}���̍Ȃ��o�ꂵ�Ă���A�܂��ʂ̕���ɂȂ������Ǝv�����A�~�A�E�n���Z���������ē͂�����̑I���͎��Ȃ������B�䂦�Ɋϋq�́A�T�˃T���h���̘f����₵���A�������Ȋ�]�ɐS���邱�ƂɁB �@�Q�l�̗��݂́A�m���ɂq�P�T�w�����ނȂ��̃��x���B���߂ẴR�g���ς��ƂŁA���炷�郌�A�̗��̂�w�ォ��Ƃ炦���V���b�g�Ȃ�āA�h�~�j�N�E�A���O���́u�O�����h�E�I�_���X�N�v��A�}���E���C�́u���y��k�[�h�v�������œ����o���������Ɨʊ����B �@����A�k�[�h�̃V�[����������Ȃ��B�q���C�����H�n������`���̃V���b�g���炵�āA���������グ��o�X�g�̗ʊ��ɃC���ł����������������Ⴄ�B���łɁw�t�����`�E�f�B�X�p�b�`�x�ŁA�l�����͂��́g���g�h�����Ă��܂�����ˁB �@����ł��āA���^�͂��܂�t�F�~�j���Ƃ͌����Ȃ��x���[�V���[�g�B�l���ɔ敾�����q���C���̋����B�ɗ\��������I�[�v�j���O���B �y�V�l���f��z �@���̂Ƃ���̃t�����X�f����ςĂ���ƁA�u���܂ł����Ă����˂Ȃ��V�l���Љ���ɂȂ��Ă���̂́A���{�����ł͂Ȃ���ł��ˁv�ƁA�����Ύv���B �@�N�w���t�������T���h���̕��e�i�p�X�J���E�O���S���[�j���A���͂ƒm�͂������āA�������������������ԂɁB�������Ė{�l�����������Ɋ������܂�Ă���̂��킩��Ȃ��܂܁A�a�@��{�݂�]�X�Ƃ���u�s����Ȃ��V�l�v�Ɖ����B���C�̓łł͂��邯��ǁA�u���͎��ʂ܂Ŏ���ŕ�炷�I�v�ƌ�������Ȃ������A�Ƒ��ɂƂ��Ă̓}�V�����ȁB �@�T���h�����N���}���Ɂu�����R�O�N����܂��t�������Ă��āA�������Ɠ����a�C�ǂ�����A���y���̈ӎv�\�����ł��邤���ɃX�C�X�ɘA��čs���āv�ƍ��肷��V�[���́A���N����������̃\�t�B�[�E�}���\�[�剉�w���ׂĂ��܂������܂��悤�Ɂx�Əd�Ȃ����B�S����l�X�̑����������v���Ă���̂ɁA�u�ǂ�ȂɂЂǂ���ԂɂȂ��Ă�������ׂ��A�������ׂ��v�Ƃ���l���������܂��ɎЉ�̎嗬���߂Ă���̂͂Ȃ����낤�H �@�T���h���̉Ƒ��̂P�l�́A�ӎv�a�ʂ�����Ȃ������������V�l�������A���݂������u�]���r�v�ƕ\���B�����ł́A���������u�]���r�V�l�v�������T���h���̕��e�̋����ɖ�������ł���p���J��Ԃ��`�ʂ����B �@�����̃V�[���̈Ӗ����^�Ɋϋq�ɓ˂�������̂́A���������X�g�߂��ɂȂ��āA�{�݂����������T���h���̋A��ۂɁA���̕��e���L���ɂ��܂悢�o�Ă����Ƃ����B���b�O�ɕʂꂽ����̎����ł͂Ȃ��A�����ɂ���͂����Ȃ��V��̌��ۑ���̖����Ăԕ��e�B����Ȏp�ɁA�T���h���̒��ʼn��������̂��B��ނɂ�܂ꂸ���̂Ƃ��ޏ������i���邢�͎��Ȃ������j�s�����A�ς�҂̋���������B �i�Q�O�Q�R�D�U�D�P�S�D�L) �s�`�q�^�^�[ TAR �i�Q�O�Q�Q�N�A�āA�����F�Γc�q�j  �@���z���]������ �Ƃ������肪�\�l�\�F�ɂȂ肻���Ȉ��B��f���ԂP�T�W�����̒��ڂł���Ƃ���ɂ����Ă��āA�N���V�b�N���y�ւ̑��w��ꗬ�I�P�́g�y�c�������h�ɂ��Ă̒m�����A�l�ɂ���Ă��Ȃ�Ⴄ�ł��傤����ˁB �@���y�ɂ͑f�l�̕M�҂̏ꍇ�A�ł���ې[�������̂́A���ɑ����i�K�œo�ꂷ�郍�V�A�l�`�F���X�g�́u�ٕ����v�������B �@�����炭�m�M�ƓI�ȍ�ׂ��Ǝv�����A�g�b�h�E�t�B�[���h�ē͖{��̏o�������h�L�������^���[�E�^�b�`�ŎB���Ă���B �i�P�j�ׂ�����������ʈ�t�ɋl�߂����قȃI�[�v�j���O�^�C�g���B�����ɉf���Ȃ��ő}�������y���[�̐�Z����炵���s�v�c�ȉ̐��i������P�Ȃ�̐��łȂ��A���̘^����ʂł��邱�Ƃ��������鉹���������Ă���j�B �i�Q�j�q���C���ł��鏗���w���҃��f�B�A�E�^�[�̑����ʂɂ킽��ƐтX�ƕ��ח��Ă�i��ҁB����ɑ����^�[�ւ̌��J�C���^�r���[�f���B �i�R�j�y�c�̌��C���i���ȁH�j�ɂ�����^�[�̍u�`���i�Bᒂɏ�����P�l�̒j�q���C���ځE�ԐڂɃp���n�����Ȃ���A�i���̂���K�i�������c���ɕ������^�[���Ƃ炦�����̉f���B �@���������������́A�ꌩ����ƁA�����I�ȃi���[�V������p�����^�C�v�̃h�L�������^���[���̂��́B�u�P�C�g�E�u�����V�F�b�g��������ˋ�̎w���ҁv�ł͂Ȃ��A�u���f�B�A�E�^�[�Ƃ������݂̉��y�Ɓv�������ɂ���悤�ȍ��o�����o����B�����ȉ��Z�҂ł͂��邪�A�O���I�Ȍ��̔����u�����V�F�b�g�Ƃ������D�̎��������A���̓_�ɂ͈���Ă��邾�낤�B �@������菓����Ă���̂��A�Ⴋ���V�A�l�`�F���X�g�̃I���K�i�\�t�B�E�J�E�A�[�j���B�ޏ��̓o���G�}�ɁA����܂ł̃h�L�������^���[�E�^�b�`���A��C�Ɂu�h���}�v�ɓ]���Ă�����ł��ˁB �@�I���K�̏��o��V�[�����炵�āA���łɂ����B�g�C���̋��̑O�ɗ����Ă����u�����V�F�b�g���A���Ƃ�������Ă����J�E�A�[��ڂŒǂ����~�����ȕ���Ƃ�������B���łɓ����̑�P�o�C�I�����Ɓu�v�w�W�v�ɂȂ��Ă���^�[�́A���g�̗~�]�ɑ��鐳�������_�Ԍ�����u�Ԃ��i�}�������˔\�����l�����āA���X�ɂ��Ă��������Ƃ��낪����܂���ˁj�B �@����̕��ʃI�[�f�B�V�����̐R�����ɁA���҂̂P�l���u�g�C���Ŗڂ��������̎Ⴂ���v�ł��邱�Ƃ��A����肪���肩�猩�����^�[�B���̂��Ɣޏ�����邠��s���́A���͂�q�ϓI�ȃh�L�������^���[�E�^�b�`�ŕ`���ꂽ�l���̂���ł͂Ȃ��A�t�B�[���h�ē����ӂɍ���������l���̂��ꂾ�i������O�����j�B �@�������B �@�O�q�̓����������Ă���ԂɁA�N���V�b�N���y�ɂ͂Ƃ�Ɖ��̂Ȃ������{�Ȏ������̓��ɂ��A���y����鎞�ɂ́u�����y�c�������N�Ɂ����z�[���Ł����̎w���̉��ɉ��t�����}�[���[���ǂ����炱������v�ƌ����̂��Ƃ������y�Ƃ����̏펯��y�_���e�B�V�Y��������ɍ��荞�܂�Ă����B �@�I���K�͂��̓_���܂��A��������ƂԂ��̂ł���B���y�E�ɂ����錠�Ђ��}�ɒ��ăI���K�ɋ߂Â����Ƃ���^�[�ɑ��A�O�L�̒j�q���C���̂悤�ɉ���i�����āj�ɏo�悤�Ƃ���ԓx�Ȃǔ��o���������A�I���K�͂��Ƃ��h煂�������ɗ�␅�𗁂т�������i���̋�̗��������ăE�Y�E�Y���邪�A�\���m���Ȃ��Ō���������ɖʔ����̂ŁA�����Ńl�^�𖾂������Ƃ͍T���܂��j�B �@�t�B�[���h�ē��I���Ȃ̂́A�I���K�������́u������q�v�Ȃ̂��A�^�[��j�ł�����ׂ��^���̎�ɂ���đ��肱�܂ꂽ�u���̓V�g�v�Ȃ̂����A�O�ꂵ�ĞB���ɂ��Ă��邱�Ƃ��B�A���m�t�X�L�[�́w�u���b�N�X�����x�Ō����A���傤�ǃ~���E�N�j�X�̖����Ȃ�ł��ˁB �@������ɂ��Ă����ʂ͓����B�l�ԊW���܂߂Ă����邱�Ƃ��ӂ̂܂܂ɂ��A���ʓI�ɏ��Ȃ���ʐl�X�������Ă����^�[�́A�������ď��߂Ĉӂ̂܂܂ɂȂ�Ȃ��ɐڂ��A�^���̊K�i�݂͂����n�߂�B �@�������u�����V�F�b�g�剉�́w�u���[�W���X�~���x�́A�܂�Œ��g�̂Ȃ��Z���u���̓]����`�����V�j�J���R���f�B���������A�{��̃q���C���� �Ȃ܂��˔\�Ɍb�܂�Ă��邾���ɁA�]���Ԃ肪�������ɁX�����i��҂Ȃ�u�C�^���v�ƕ\������Ƃ��납�j�B �@���āA����͔ߌ��Ȃ̂��A����Ȃ̂��A����Ƃ��쌀�Ȃ̂��낤���B �i�Q�O�Q�R�D�T�D�Q�V�D�L�j �`�h�q�^�G�A�@�@AIR �i�Q�O�Q�R�N�A�āA�����F�ё��j  �@�G���[���X�̑�J�ĕ��́A���W���[�U�V�[�Y���ڂ����Ŋ���B���V�[�Y���̂l�u�o��܂ɑ����āA���I�t�ɂ͂v�a�b�œ��{�`�[����D���ɓ����ȂǁA���ς�炸�L�T�ɓ����Ă���B �@�����A�����̃G���[���X�͂��̊ԁA�D���ǂ��납�A�v���[�I�t�o�����x�����Ȃ킸�A��J�͂��̉ؗ�Ȍo���ɑ僊�[�O�̗D���g���t�B�[��t�������邱�Ƃ��ł��Ă��Ȃ��B�ŏ��Ƀ��W���[�ɓn�鎞�_�ŁA�����L�[�X��b�h�\�b�N�X�̂悤�ȋ����`�[���ɓ����Ă���Ύ���͂܂�������̂��낤���i����ɂ̓M�������ǂ������̂��낤���j�A�������A����ł͓��ȂǂƂ����u�r�����m�v�ȗv�]�͊ԈႢ�Ȃ��َE����Ă����͂����B �@���̓_�A�G���[���X�͖싅���T�[�J�X���f�B�Y�j�[�����h�̃A�g���N�V�����̂P�̂悤�ɍl���Ă���`�[���B���̐���̐l�Ԃ́A�����c�����Đǘr����̃W���E�A�{�b�g�ƌ_�����Ƃ��o���Ă���B �@�G���[���X�ɂƂ��Ă͓����ǘr������A�����������̉��͒j��Ђ��ʏ��ȂǂƓ���́u�L�����m�v�Ȃ����u�l�p���_�v�B��J�����W���[�ł������т��Ă���ꂽ�̂́A�K�������D�����`���Â����Ă��Ȃ��A����Ȏ㏬���c�ɍݐЂ��Ă�������Ȃ̂��B��J���{���Ɂu�l�v�ȏ�̎��т������Ă��܂����̂́A�����c�ɂƂ��Ắu���ꂵ����Z�v�ɗނ��邱�Ƃ��������낤�B �w�`�h�q�^�G�A�x�̓o�X�P�E�̃��W�F���h�ƂȂ����}�C�P���E�W���[�_�����m�a�`���肷��O��Ɂ\�\�܂�^�̃X�[�p�[�X�^�[�ɂȂ�̂��A��������ŏI���̂��A�܂��N�ɂ��\�z�����Ȃ����������Ɂ\�\���̃X�|���T�[�_��̊l����ڎw�����p��[�J�[�����̕�����`�������b���B �@�o�X�P�V���[�Y����ł͌㔭�������i�C�L�̎Ј��A�\�j�[�i�}�b�g�E�f�C�����j�́A�u�����h�͂⎑���͂ŏ���R���o�[�X�ƃA�f�B�_�X�̓�僁�[�J�[�ɋ�`���Ȃ߂���������X�B����ł����܂��o�܂��A�܂��͎Г���������āi���Ђ̐g�̏�ɍ����������������x���̑I��ł͂Ȃ��j�啨�W���[�_�����^�[�Q�b�g�ɂ��邱�Ƃ�����B�����Ċ����̃V���[�Y��ނɗ�������̂ł͂Ȃ��A�W���[�_���̖����������V�u�����h�u�G�A�W���[�_���v�𗧂��グ��v���W�F�N�g�𐄂��i�߂�B �@���̈���ł́A�W���[�_���Ƃ��A�|�Ȃ������B�����������Ă���W���[�_���̕�e�i�r�I���E�f�C�r�X�j�ɁA���g�̔M�ӂƃA�C�f�A�𐽎��ɓ`����B���̌�̐����ȃv���[����ʂ̓n�C���C�g�̂P�B�p�ӂ��������������Ă��Ȃ��ƌ����A�\�j�[�͊��i����낵���A�Ԃ����{�Ԃ̃X�s�[�`�ɑł��ďo��̂��i�L���O�q�t�̗L�������������������Ƃ���O���̕������A�����őN�₩�ɉ�������j�B �@�₪�ă\�j�[�ɃW���[�_���ꂩ��̋g�i���łɒm��ꂽ����������A���������Ă��l�^�o���ɂ͓�����܂��j�B�����܂ł̓W�J���������ł́A��҂��W���C�A���g�L�����O���ʂ��������̂�������杂��B�\�j�[�͂��̐l�I���͂ƍs���͂������āA��U�s���Ɏv��ꂽ�ǂ��U�������B�q�Ȃ̊F�l�A����Ɗ��т��E�E�E�B �@����͂������A�W���[�_���ꂩ��̂��̓d�b���I���ʂ����ɁA��Ȃ˂���������n�߂�B���ẮA�Ɣޏ��͌��t���p���̂��B�u�G�A�W���[�_���̎��v�̈�芄���𑧎q�ɕ��z���Ăق����v�ƁB �@�V���[�Y�̃r�W�l�X�ɂ͖�O���̊ϋq���A�\�j�[�ƃW���[�_����̂���肩��A�X�|���T�[�_��ɂ��������t�я�����t����̂͑O�㖢�����������Ƃ�m��B�A�|�Ȃ��ŃW���[�_���Ƃɓˌ������\�j�[�̌��������āA�W���[�_������܂��A�㗝�l��ʂ��ʏ�̎葱���܂��A�C�`���o�`���Œ��ڃi�C�L�ɓˌ����Ă����̂��B �@��������͎��̑z�������A�_������̑��́u�ʏ�v�̃I�t�@�[�݂̂��r����A�R���o�[�X��A�f�B�_�X�ƌ_�������W���[�_���Ƃɂ͗L����������������Ȃ��B�������A������ł����̗L�͑I��ƌ_��ł����僁�[�J�[�Ȃ�A���Ђ̗��v����邻��ȏ����͂����ǂ���ɏR�������낤�B �@�W���[�_���Ƃ͂�������z���āA�A����肪�o��قǂ��̌_���~�������Ă���㔭�̃i�C�L�ɁA�ٗ�̕t�я�����˂������B��J�ĕ������K�ʂ�[���h�V���[�Y�i�o�̉\���ɂЂƂ܂��ڂ��Ԃ�A�ٗ�̓������e�����ł��낤�G���[���X�ɔ��H�̖�𗧂Ă��悤�ɁB �@���b�����ɂ������̉f����A�\�j�[���͂��߂Ƃ���i�C�L�̖ʁX�̒ɉ��ȉ�����̕���ƌ��邱�Ƃ́A��������ʂŐ������B���������̉A�ɂ́A�v���X�|�[�c�E�Ɨp��ƊE�Ƃ̊W�Ɉ��v�����N�������A�{���̏��҂������Ƃ������Ƃ��B�㐢�ɗǂ��e���ƈ����e���̗������c���̂��A�v���̏�Ȃ̂�����ǁB �i�Q�O�Q�R�D�S�D�Q�U�D�L�j �U�E�z�G�[���@�@THE WHALE �i�Q�O�Q�Q�N�A�āA�����F���Y���ށj  �@�ߔN�A������Ă����u�����_���E�t���C�U�[�ɁA�i�����炭�J���o�b�N�܍��݂́j�A�J�f�~�[�剉�j�D�܂������炵�����B�ēE����̃_�[�����E�A���m�t�X�L�[�́A�t���C�U�[���S�����Ɂw�n���i�v�g���x�V���[�Y�ŋ����������C�`�F���E���C�Y�̌��p�[�g�i�[���B���āA���̃L���X�e�B���O�A���R�Ȃ̂��A���P����Ȃ̂��H �@��l���̃`���[���[�́A�Ȏq�����Ȃ���A�����̋����q�A�����Ƃ̈��ɑ��������w�u�t�B�Ƃ��낪�A�����ɐ旧����A�X�g���X�����~���n�H���J��Ԃ������ɁA���⎩�炪�Q�V�O�L�����̋��̂ɁB�������߂����Ƃ��ӎ������`���[���[�́A17�ɂȂ������G���[���W�N�Ԃ�ɌĂяo�����E�E�E�B �@����̓`���[���[�̃A�p�[�g�̂݁B�o���肷��o��l���͂قڂT�l�����ƁA�܂�ŏ��Ԃ�̕��䌀�̂悤�Ȃ��炦���B �E�E�E�Ǝv������A���͕��䌀�����������B�A���m�t�X�L�[�̑n��ł͂Ȃ����A�����̃A���m�t�X�L�[��i���A�͗������₷���������ȁB �@��ʂ̃A�X�y�N�g��́A���Ⓙ�����S�F�R���炢�ł͂Ȃ��������B�J�b�g�̕ς��ڂɂ���ẮA�X�N���[���̍��E���]���Ă���̂��ڗ������B���Ẳf��قȂ�J�[�e���������ĉB�����Ƃ���ł��ˁB �@�����V�l�X�R�ȂŎB������A�������������Ԃ����������ꃁ�C�N�̋��̂��A���ΓI�ɍׂ��������Ⴄ����ȁB �@�T�l�̓o��l���̓���̓`���[���[�ƃG���[�A���ȁA�`���[���[�̖ʓ|��������ƂȂ����Ă���Ă���Ō�t�i�A�����̖��j�A������菓����Ă����V���@���̐鋳�t�B �@���̂T�l���T�l�Ƃ��₽��Ǝ��Ȏ咣�������A�ΐl�W�ł��₷���������Ȃ��^�C�v�Ȃ̂��B�ނ炪���낢��ȑg�ݍ��킹�łԂ��荇������A��������������A�����������肵�悤����Z���ȉ�b���A������B���ɂ������ȓ��{�l�݂̈ɂ͑���������邩������Ȃ��B �@�ӏܑO�ɂ́A�^�C�g���́w�U�E�z�G�[���x�̓`���[���[�̋��납�痈�Ă�����̂Ƃ���v���Ă������A���͂��ꂾ���ł͂Ȃ������B�n�[�}���E�����r���́u���~�v�������ŏd�v�Ȗ�����S���Ă�����ł��ˁB�`���[���[�͉��N���O�ɃG���[���������u���~�v�̊��z���������]�����A������x���ɂ������Ă����炵���B �@�Ƃ��낪���̃G���[�Ƃ����̂��A�Ƃu�`�ꖺ�Ȃ킯���B�o�ꓖ�������A�u����Ꭹ�����̂Ă����e�Ɖ���甽�R�����ȁv�Ǝv���Ȃ��猩�Ă������A���X�ɔޏ������̐��̂��ׂĂ�ł���炵�����Ƃ��I��ɂȂ��Ă���B���e�Ɏ̂Ă�ꂽ���䂦�ɁA�����܂ŋ��܂��Ă��܂����̂��A����Ƃ����������S���q�������̂��B �@��e�ɂ����u���v�ƌ`�e����邱�̃e�B�[���G�C�W���[���A�A���m�t�X�L�[�͗e�ՂɊ���ړ��̑ΏۂƂ͂��Ȃ��B�Ō�͕����̐S���ʂ��ė܂̘a���E�E�E�Ȃ�Ĉ����ȑ�c�~�ɂ͎����Ă����Ȃ���ł��ˁB �@����ł����̑P�ӂ�M�������`���[���[�́A���s��Ȃ��ł͗����オ�邱�Ƃ����܂܂Ȃ�Ȃ��̂ɁA�G���[�Ɂi�S�g���ʂŁj���݊�낤�Ɨ����オ��A�����āE�E�E�B �@���̃��X�g�J�b�g�̒��O�́A�펯�ł͐����ł��Ȃ����Ƃ��N����V�[���̉��߂́A�f��t�@�����]�Ƃ̊Ԃő傢�ɕ��c���������Ƃ��낤�B�܂��A�A���m�t�X�L�[�̎B��f�悪���c�������Ȃ����ƂȂǂ���܂��ǂˁB �i�Q�O�Q�R�D�S�D�Q�U�D�L�j �Q�O�Q�R�N�I�X�J�[�i�C�g�E�E�H�b�`���O�I  �@���N�x�̃A�J�f�~�[�����́u�G�u�G�u�����v�ɐȊ����ꂽ�B�m�~�l�[�g���ꂽ�P�O���咆�̂V����Ŏ�܁B�������i�A�ēA�剉���D�A�������D�A�����j�D�A�r�{�A�ҏW�Ƃ�������v�e�܂��Q�b�g�����̂�����A����ȏ�̙F��͖]�߂܂��B �@�ēR���r�̃_�j�G���Y�i�_�j�G���E�V���C�i�[�g�ƃ_�j�G���E�N�����j�͌��ǁA�r�{�܁A�ē܁A��i�܂̏��ɎO�x�o�d�������A���Z����̋��t�Ɋ��ӂ��q�ׂ�Ȃǁi����ȉf��l�͖ő��ɂ��Ȃ��j�A���̂��тɕ������O�������Ȃ��X�s�[�`���I�B�Ƃ�킯�_�j�G���E�N�����ɂ��u�V�˂Ƃ͒d��ɂ���l�����l�ł͂Ȃ��A������Ƃ��琶�܂����́v�Ƃ����ē܂̃X�s�[�`�͊�����^�����B �@��i��܂̍ۂɁA�����P�l�̒����n�̃v���f���[�T�[���u���g����g�[�L���[�̐l�X�v�Ɋ��ӂ�����Ă����͈̂ӊO�������ȁB�����A�W�A�n�Ƃ͌����Ȃ���A���炩�ɒ��،��̐F�̋�����i�Ȃ̂ɁB �@���Ȃ݂ɍ�i�܂̍s���́A�n���\���E�t�H�[�h���v���[���^�[�Ƃ��ēo�ꂵ�����_�Ŏ������������B�w�C���f�B�E�W���[���Y�^���{�̓`���x�i84�j�Ńt�H�[�h�Ƌ��������L�[�E�z�C�E�N�������A��ܔ��\��̒d��Ŋ�Ԃ܂����Ƃ��B ���A�E�g�T�C�_�[���낢�̔o�D�w�� �@�����Ȃ�O�N�̒j���̎�҂��������|���Ńv���[���^�[�߂�o�D����܂́A���N�͂Q�̗��R�ŕϑ��I�ɂȂ����B �@�܂��͏�������B��N�̏����j�D�܂̎�҂����o��Q�����g���C�E�R�b�c�@�[�������Ƃ����āA�������������D��҂̃A���A�i�E�f�{�[�Y�ƃy�A�œo�d���A�Q�l�Œj���̏����o�D�܂\����`���ɁB �@���ʁA�����j�D�܂̓L�[�E�z�C�E�N�����A�������D�܂̓W�F�C�~�[�E���[�E�J�[�e�B�X�ƁA�Ƃ��Ɂw�G�u���V���O�E�G�u���E�F�A�E�I�[���E�A�b�g�E�����X�x�̏o���҂��h�����B �@�N�����͎��g���x�g�i������������Ƃ�A�ꎞ�͗����ɓ]���������ƂȂǂɐG��A���Ȃ̗�܂��ł��Ɂu�A�����J����h���[���v�������Ƃ�܂Ȃ���ɃX�s�[�`�B�J�[�e�B�X���g�����Ɩ����h�L�������Ȃ���A�u�吨�̐l�ƈꏏ�ɂ����ɗ����Ă���v�ƌ��A�����Ē����ȉf��l���������e�ɃI�}�[�W����������B �@�剉������܂��ϑ��B�Ȃɂ����N�̒j�D��҃E�B���E�X�~�X���A�r���^�����̂��߂Ɂu�o�ցv��ԂȂ̂Łi�i��̃W�~�[��L���������A�������ĎO�W���[�N�ɂ����j�A��N�̏��D��҂̃W�F�V�J�E�`���X�e�B�����A�Q�O�O�P�N�̓���҃n���E�x���[�ƂƂ��ɒj�����܂\�����B �@�剉�j�D�܂́w�U�E�z�G�[���x�̃u�����_����t���C�U�[����܁B�Q�O�O�O�N��ɓ����Ă���̕s����U��Ԃ�A���ɂ܂����l�q�Ŋ��ӂ��q�ׂ�B���ꃁ�C�N�ŊO�������ς�����̓I�X�J�[�ւ̋ߓ��̂P�����A����ɉ����āA���N�͂���قNj��͂ȑΗ���₪���Ȃ��������Ƃɂ��b�܂ꂽ���B �@�剉���D�܂́w�s�`�q�^�^�[�x�̃P�C�g��u�����V�F�b�g��}���āA��������w�G�u�G�u�x���̃~�V�F���E���[����������B�A�W�A�n���D�Ƃ��Ďj�㏉�̉������B�X�s�[�`�ł̓I�X�J�[�����f���āA�u���Ɏ������N����������A����͂��Ȃ������̊�]��\���̂�����ł���A���͂��Ȃ��Ƃ������ł��B�����ď���������A�w����͉߂����x�Ȃ�ĒN�ɂ����킹�Ȃ��Łv�ƁA�D�����g���Ȟ������B���ꂪ���N�̑S��҂̒��ŁA�ł����h�ȃX�s�[�`��������Ȃ����ȁB �@�������Ĕo�D����̂S�܂́A��o�g�Ŏq�����̃N�����A�W�������i�F���j�f��̏��D�ƌ���ꂪ���������J�[�e�B�X�A�d���ɂ��Ԃ�Ă����t���C�U�[�A�}���[�V�A�o�g�ō��`�f��Ƀ��[�c�������[�ƁA�n���E�b�h�̃A�E�g�T�C�_�[���肪��܂����B�e�l���J���o�b�N�������胊�x���W������������ɔ�߂Ă����̂ł��ˁB������l�Ҏl�l�Ɂu����������߂Ȃ��ŁB�����K�����Ȃ�����v�I�ȃX�s�[�`�������ɂ����Ȃ��������R�͑z���ɓ�Ȃ��B �@�����Ƃ��A���͕�������������ǓI�Ɍ���`�^�̐l�ԂȂ̂ŁA�ނ�̃X�s�[�`�Ɋ��������A���̂ǂ����Ő��߂��v��������Ă��܂��̂ł����ǂˁB�u���Ȃ����͂��܂��ܖ������Ȃ����P���ɓ��ꂽ���ǁA���̉A�ł͂X�X���̐l�X�����j��đޏꂵ�Ă�����ˁv�ƁB �����l���ƒE�R���i�� �w�G�u�G�u�x�̊W�҈ȊO�ł��A�^�C�o�g�̃z���E�`���E�i�w�U�E�z�G�[���x�j���������D�܌��ɂȂ�����A�C���h�f��w�q�q�q�x���̋ȏ܂���܂�����ƁA���N�͑����ăA�W�A�̔N�B �@���̔��ʁA���l�̃m�~�j�[���o�D����Ōv�Q�l�������Ȃ�������A�ē܌�₪�S���j����������ƁA�܂����둽�l���ɋ^�╄���t����ꂽ�B�i��̃W�~�[��L�������́A�̂������炻����t��Ɂu���N�͑��l���ɔz�����ăA�C�������h�l�o�D���吨�m�~�l�[�g����Ă���ˁv�Ƃ̃W���[�N�����B �@�����̃I�[�v�j���O�����A���̃L��������퓬�@���痎���P�~���������Ƃ����̍ق���������A�S�̂Ƃ��Ă͗]�v�ȁu�ɂ��₩���v�̏��Ȃ��V���v���Ȏ��T�������B�w�C�j�V�F�������̐���x�ɏo�Ă������o�������o������A���o���ʏ܂̃v���[���^�[�̃G���U�x�X�E�o���N�X���A�N�}�̒�����݂Ɨ��肵���̂��ڗ����Ă������炢���B �@����͂����炭�R���i�ȑO�Ɠ����u�S����ꋓ���\�v�̑̐��ɖ߂��āA���Ԃ������Ă������߂����������낤�B�t�Ɍ����n���E�b�h�͊T�˃R���i�Ђ����������̂��ȂƁA�f��t�@���Ƃ��Ă͏����ӂ������������悾�B �@�������W�F�V�J�E�`���X�e�B�������́A�i�d��͕ʂɂ��āj�q�ȂŊϗ����Ă���ԁA�L���l�ł͗B��}�X�N�𒅂����܂܂������B��b�����ł�����l�Ȃ̂��ȁH �@����A�҂Ă�A�J�������������Ă��Ȃ����ɂ́A���̗�Ȏ҂�������������}�X�N�𒅂��Ă����̂��낤���H �i�Q�O�Q�R�D�R�D�P�S�D�L�j �t�]�̃g���C�A���O�� TRIANGLE OF SADNESS �i�Q�O�Q�Q�N��X�E�F�[�f��=��=��=�p�A�����F��c���T���j  �@�V�^�R���i�Ђ̉Q���ɂ́A�l�Ɛl�Ƃ̐ڐG�@������炷���Ƃ��ŏd�v������A�����s����X�|�[�c�C�x���g�̂悤�ȁu�s�v�s�}�v�̍Â��́A�����ݒ��~�ɒǂ����܂ꂽ�B �u�l�Ԃ炵���m�I�Ȋ������s�����Ɓv�����A�u�Ƃɂ��������Ȃ����Ɓv�̂ق����D�悳�ꂽ�킯�ł��ˁB �@�Ғœ����̔]�́A�ċz��S�����i��]���A�^�����ߋ@�\��S�����]�A�v�l��L�����i���]�̏��Ŕ��B���Ă����Ƃ���Ă���B�V�^�R���i�̊����h�~��Ƃ́A�Ɍ�����u�Ƃ肠������ޓI�Ȕ]�i�]���⏬�]�j�����������āA���������̔]�i��]�j�̓I�t�ɂ��܂��傤��v�Ƃ����[�u�������킯���B �@�J���k�f��Ղ̍ō��܂���܂����w�t�]�̃g���C�A���O���x�́A���O�̐�`�������Ă���ƁA�N���[�Y�D�̓�j�̕���ł���悤�Ɏv����B����͌����ĊԈႢ�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��̂�����ǁA���͂����ɂ��ǂ蒅���܂ł����Ȃ蒷����ł��ˁB �@����ɐ旧���A��������ʕȂ̋����o��l���������A�{�ƊW����̂��A�Ȃ��̂��悭�킩��Ȃ����������X�ƓW�J����킯���B�h���}���o�Ƃ̑卪�m���u�Ƃ�ł��Ȃ�����������č�����R���g�W�݂����ȉf��v�ƕ]����̂�������B �@����ȁu�R���g�v�̈�Ⴊ�A�`������Q�߂̃V�[���Ō��킳���t�@�b�V�������f���̃J�b�v���̉�b�B���X�g�����ŐH�����I�����Q�l�̃e�[�u���ɓ`�[���^��Ă���ƁA���͌��Ȃ��t�������ĉ��ςȂǒ����Ă���B�j�͂�ނȂ��x��������������̂����A�v�������āA�����咣����B�u�����͌N���������Č����Ă���ˁB�ʂɂ������ɂ����킯����Ȃ����ǁA�l�͐��ʖ����ӎ��ɔ���ꂸ�A�����̊W�ł������v �@����ɑ����āA�Ԃ��ꂽ���̏o�����N���W�b�g�J�[�h��������������A�莝���̌������S�R����Ȃ�������Ƃ����X�b�^�����_������̂����A�������ڂ����̂́A���̂���ɐ悾�B �@���ǁA�j�������̃J�[�h�Ŏx�������ς܂������ƂɁA���̓j�����Ə��āA�{����R�炷�B�u�����ꎄ�͒N���̎q�����o�Y���A�d�����x�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ��B���̎��Ɏ���{���邾���̍b�㐫�̂���j�łȂ���A�t�������Ă����Ԃ̖��ʂ�v �@�����Ŗ{�e�̘b�̃}�N���ɖ߂�킯�����ǁA�u���ʖ����ӎ��ɔ���ꂸ�A�����̊W�ł������v�Ƃ����j�̎咣�́A���S�ɕ����I���l�ς̗̈�ɂ���A�����Ƃ͒��ڊW�̂Ȃ���]�̉c�݂Ȃ�ł��ˁB�����琶���邩���ʂ��́\�\���Ƃ��Ε�e���Ԃ������ǂ�����Ĉ�ĂĂ��������Ƃ����\�\�ł́A�u�s�v�s�}�v�̂��ƂƂ��ĖَE�����\��������B �@���鏗�̎咣�͔]���⏬�]�̉c�݂��B�َE�����瑦�A���Ɋւ�邩��A�������Ȃ鎞�ɂ��X�C�b�`�����邱�Ƃ͂Ȃ��B �@�ǂ��炪����̃W�F���_�[�v�z�ɍ��v���Ă��邩�Ƃ����A���S�ɒj�̎咣�̕����B�����Ď����g���A�j�����肪����I�Ɏx���������鋌�K�ɒ�R���o������x�ɂ́g�J���I�h�ȍl�����������Ă���B �@�����������������o�Y��S���Ƃ��������w�I�{���̑O�ł́A�j�������ȂǂƂ��������I���O�͐������ł��܂��̂�������Ȃ����Ɓ\�\�����ăW�F���_�[�����_�̐K�n�ɏ���Ă��邾���̊F����́A�ʂ����Ă��̌��R���鎖���ɋC�Â��Ă���̂��ȂƁ\�\�f��̖{��Ƃ͂��قNJW�̂Ȃ����́u�R���g�v�ŁA���������čl��������ꂽ�ЂƂƂ��ł������B �i�Q�O�Q�R�D�R�D�P�S�D�L�j ���ׂĂ��܂������܂��悤�� TOUT S'EST BIEN PASSE�^EVERYTHING WENT FINE �i�Q�O�Q�P�N�A�����x���M�[�A�����F���Y���ށj  �@�W�T��ڑO�ɂ��Ĕ]�����œ|�ꂽ�A���h���B�d����Q�����䂪�g�ɐ�]���A�����Ɉ��y���̎�z�𖽂��邪�E�E�E�B �@���āA���̉f����D���ɂȂ�邩�ۂ��́A�ЂƂ��Ɂu�I��点�Ă���B����ȏ�ԂŐ����Ă������Ȃ��B����Ȏ��͎��ł͂Ȃ��v�Ƃ����A���h���i�A���h���E�f���\���G�j�̋��тɋ����ł��邩�ۂ��ɂ������Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���B �@���͑傢�ɋ����ł���̂ŁA�����i�\�t�B�[�E�}���\�[�j�Ǝ������A�S�Ɋ������o�����A���e�̊肢���Ȃ��ɔے肵�Ȃ��������ƂɍD�����������B �@�����悤�ȗ���ɂȂ������҂ɁA�u������߂Ȃ��Łv�ƌ����Ⴂ�Ȍ��t��������Ƒ����Î҂����ɂǂ�قǑ������Ƃ��B���ۂ̂Ƃ���A���҂͎����炵����������������߂����Ȃ�����A�ϋɓI�Ȗ�������]�ނ̂��B�u�����������Ă�Ɠ����{�P�āA�����̈ӎv�\�����ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��v�Ƃ����A���h���̌��t���A���̓_��������������Ă���B �@�����A�ēE�r�{�̃t�����\���E�I�]���́A�����������b�Z�[�W����i�ɐU�肩��������A�Љ�ϊv�������炵�Ă�낤�ȂǂƈӋC���肷��ӂ��ł͂Ȃ��A���[���A�������ĒW�X�ƃv���b�g��Ԃ��Ă�����ł��ˁB�u�l�͂����l����B�ʂɂ݂�Ȃɓ��ӂ��Ă����Ȃ��Ă��������ǂ��v�Ƃ��������ŁA�����܂ł��y�₩�B�w�o�k�`�m�V�T�x�̖^�ē̂悤�Ɍ�����`�I�ł͂Ȃ��B �@���ꂪ�؋��ɁA�I�]���͔��Δh�́u�����錄�v���̈ӂɂ�܂��Ă��銴��������B�P�͗c�����̒����ƕ��e�Ƃ̊W���A�K���������ɖ��������̂ł͂Ȃ������ƏL�킹���z�V�[���B����ł͒����́u���������Ă��Ȃ�����A���͈��y���̎�z�������Ă���̂��낤���H�v�Ǝ��₹���ɂ͂����Ȃ����낤�B����A���ۂɂ����Ȃ̂��H�@���`�ށA�l�������܂��ˁB�l��������f��Ƃ����̂́A��{�A�ǂ��f��ł��B �@�����P�́A���J���ɂ킽�錀���̎��Ԍo�߂̒��ŁA�A���h��������Ȃ�ɉ��Ă����_�B�ނ́w�C���Ԗ��x��w�~���I���_���[�E�x�C�r�[�x�̎�l���̂悤�ɂ܂����������Ȃ��܂܂ł͂Ȃ��A�܂��w�݂Ȃ���A���悤�Ȃ�x�̎�l���̂悤�ɖ������ɖ`����Ă���킯�ł��Ȃ��B�ނ���x�b�h����Ԉ֎q�ւƍs���̕����L����A�u���̉��t������Ă��玀�ʂ�v�Ȃǂƌ����o���킯���B �u������߂Ȃ��Łv�h�̘A���́A���ꌩ�����Ƃ��A�������Ă̕���ł���ƃc�b�R��ł���ɈႢ�Ȃ��B����ł��I�]���́A�A���h���Ɏ����̌��ӂ����͕ς������Ȃ���ˁB���̂��Ƃɂ���ċt�ɁA�u�{�l�̎��Ȍ��茠�d���悤��v�ƁA���₩�ɁA�������u�����ɑi�������Ă���悤�Ɏv����B �@���łɌ����A�A���h���͔]�����ő̂��s���R�ɂȂ����킯�����ǁA�����̓��{�l�͐l�̂̑ϗp��������قǒ������ɂȂ��Ă��邩��A���ɕa���ɖ`���ꂸ�Ƃ��A�����̐l���P�Ȃ�V�������Łu����Ȏ��͎��ł͂Ȃ��v�Ƃ�����ԂɊׂ��Ă����B�I�]����������u�������̎l�����v�Ȃ�Č������Ƃ͌��킸�ɁA������������҂̎��Ȍ��茠���܂��A���������d����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B �@���̉f��̖M��́w���ׂĂ��܂������܂��悤�Ɂx�Ƃ�����]�`�����ǁA�����u���ׂĂ����܂������܂����v�Ƃ����ߋ��`�̈Ӗ��ɂȂ�炵���B�܂��ɂ��̌���ǂ���A�����������@������Ă��Ȃ��t�����X������ł���ɂ�������炸�A���Ɩ��̌v��͎����ăX���[�Y�ɐi�s����B �@�a�@�����牡������������A�x�@���玖��悳�ꂿ�������ƁA�m���ɏ����ȋN���͂���̂�����ǁA���Ɍ��I�Ȕ�u������ł��Ȃ��A����ނ�̂܂ܒʉ߁B�Ō�̍Ō�Ɍ���I�ȃs���`�ɂ��������邪�A���̂ǂ�ł�Ԃ����햾�������Ȃ���c�~�ƂȂ�B���������A�ǂ�����Ă��̏�Q�����z�����H�i�܂��A���������Δh�̐l�����ɂƂ��ẮA����́g�s���`�h�ł��g��c�~�h�ł��Ȃ��̂ł��傤���ǂˁj�B �@�����̃I�]����i�̋���ȓł��C���l����A�E�\�̂悤�ɂ������Ȃ��W�J���B�킸���ɃI�]���_�Ԍ�����Ƃ���ƌ����A�A���h���������̗��l������āA���f�̍ȁi�V���[���b�g�E�����v�����O�j�Ƃ̕v�w�W��₦���܂����炵�����Ƃ��炢���B �@�v���A�I�]�����{��œW�J���鑸�����ւ̗i����āA�Q�C�̃R�~���j�e�B�̈�ʎЉ�ɑ���p���Ɠ����Ȃ̂�������Ȃ��B�܂�u�l��Ɏ^�����Ă���Ƃ͌���Ȃ�����A���߂ĕ����Ă����Ă����v�Ƃ�����ł��ˁB���������l��`�I�ȍl�������āA�I��I�v�w�ʐ������F�߂悤�Ƃ��Ȃ����{�Љ�ł́A�Ȃ��Ȃ�������Ȃ��̂�������Ȃ�����ǁB �@����ɂ��Ă��A���ɂ���ĉE���ʍs�����@���������@�������肷�邱�Ƃɂ͉���^��������Ȃ����ǁA���ɂ���đ����������@���������@�������肷��͕̂s�v�c����ˁB�����l�Ԃ̖��Ȃ̂ɁB �@�P�������ł͂Ȃ��A�P���ɖʔ����Ǝv���B �i�Q�O�Q�R�D�R�D�T�D�L�j �A���r�A���i�C�g�@�O��N�̊肢 THREE THOUSAND YEARS OF LONGING �i�Q�O�Q�Q�N�A��=�āA�����F���Y���ށj  �@���@�̃����v������������A�����疂�l���o�����E�E�E�B �@�̘b�́u�A���W���Ɩ��@�̃����v�v�͂���Ȃӂ��ɂ��Ďn�܂����B���������ɐݒ肵�����̉f�扻��i�́A�����������b�����Ƀp���f�B�ɂ��Č�����B�@ �@�_�b��`���̌����҂ł���A���V�A�i�e�B���_�E�X�E�B���g���j�́A�u����̃C�X�^���u�[���ŁA�����Ƃ͒m�炸�ɃK���X�r�ɕ����߂�ꂽ���l�i�C�h���X�E�G���o�j�������B�A���r�A��ƃM���V���ꂵ���b���Ȃ���ԂŌ��ꂽ���l�́A�e���r�ƃp�\�R������m�����z�����A�����܂�����p�ꂪ�y���y���Ɂi���������w�X�v���b�V���x�̐l�����A�e���r����p�����������o������ȁj�B �@�����Ƃ��A�����̗���ɒ�R�̂Ȃ�����Ȗ��l���A�A���V�A�����ŕr�����������̂��m������A�������ɃQ���i��������Ȃ����ȁi������Ə��鏬�l�^�Ȃ̂ŁA�����͂����ĕ����܂��j�B �@����o���Ɋo���Ă���A���r�A���i�C�g�̖��l�́A�u�����v���������Ă��ꂽ��Ƃ��ĂR�̊肢�����Ȃ��Ă�낤�v�ƁA�ォ��ڐ��Ő\���o���͂��B �@�Ƃ��낪�{��̐ݒ�ɂ��A���l�̓\���������ɂ�����ꂽ���������߂ɁA�N���̂R�̊肢�����Ȃ���K�v������̂ł��ˁB�łȂ��ƍĂу����v��r�ɕ����߂��Ă��܂�����A���Ƃ��Ă��肢�����킹�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���l�̂ق����K���Ȃ킯���B �@�������A����܂ł̂R�O�O�O�N�Ԃɖ��l���������������Ȃ��҂����́A�R�̊肢��������O�Ɏ���ł��܂�����A�����Ă͂����Ȃ��m�f���[�h�����ɂ����肵�āA���Ƃ��Ƃ����s�B���x�����͂Ǝv����߂����l�́A�A���V�A�����s���邱�Ƃ̂Ȃ��悤�A���g�̐���Ȑg�̏�b�����n�߂�B �@�ēE�r�{�̃W���[�W�E�~���[�́A�Q�l����b�����킷�������E�ƁA���l���`�����J��L�����z�V�[�����c���ɂȂ��B���l�̌��t�́A�O�҂ł́u�n�̃Z���t�v�ƂȂ�A��҂ł́u�Ɣ��v�ƂȂ邪�A���҂̂Ȃ��ƃo�����X�������Ȃ��i�����Ƃ��A���̓_�Ɋւ��Č����A�^�[�Z���́w�����̉����x�̐▭�ȃZ���X�E�I�u�E���[���A�ɂ͋y�Ȃ����j�B �@�A���V�A�Ɋւ��Čl�I�ɖʔ����Ǝv�����̂́A�ʂꂽ�v�Ɋւ�����̂��t�@�C���p�̔��Ɏ��߂āA�˒I�ւ��܂�����ł����Ƃ���B�I�ՁA�ޏ��͖��l�ƕʂꂽ���ɂ��������Ƃ�����B �@����͌��������̎��ɂƂ��Ă͂Ȃ��݂̂�����i�Ȃ�ł��ˁB�N�x���ɕ��������A�t�@�C���p�̎��[�ɂɈڂ��B�����̏ꍇ�́u�P�N�ۑ��v�u�R�N�ۑ��v�u�i�v�ۑ��v�Ȃǂɕ������Ƃ������̂ŁA�u�A���V�A�̌��v�͉��N�ۑ��Ȃ̂��낤�H�v�Ȃǂƍl���Ă�����A���R�ɋq�ȂŖj���ɂB �i���S�K�N�����̌����L�^���p�����ꂽ�ȂǂƂ������������̉�������ɂ���o���������A����͕ʂ̘b�j �@�ȉ��̓l�^�o���ɂȂ�̂ŁA�����̕��͂����ӂ��������B �@�A���V�A�̂Q�߂̊肢������A�����ŃA���V�A�������邱�Ƃɂ������l�́A����Ɍ��N�Ȃ��Ă����B�����˂��A���V�A�́u���̐��E�ɖ߂��āv�ƍŌ�̖]�݂������̂����A�����Ŗ��l�̕r���K�`���b�Ɗ����̂ł��ˁB �@���}���`�b�N�ȊÂ����̎��́A���̎��A���l���A���V�A�̊肢�����₵�āA�u�����ɂƂǂ܂�A���̐g���s���Ă����Ȃ������������܂��v�Ƃ����ӎv�\�����������̂Ɗ��Ⴂ�������A�G���f�B���O�܂Ō���ƑS�R�����������Ƃł͂Ȃ������B�R�߂̊肢���������i�ʂ�����j�A���l�����͂�\���������̎i�������v��r�ւ̍S���j���玩�R�ɂȂ������Ƃ��������̂������B �@�r������A���V�A��������R�ɂȂ������l�́A�C���������������A���V�A�̂Ƃ���ɂ���ė���W�S���̂悤�ȑ��݂ɁB������ăA���V�A����������̂Ă�����A����Ӗ��A�c���Ȃ̂���Ȃ��������H �@�܂��A�A���V�A�{�l������Ŕ[�����Ă���悤����������A�ʂɍ\��Ȃ���ł����ǂˁB �i�Q�O�Q�R�D�R�D�T�D�L�j ���̂��� L'EVENEMENT �i�Q�O�Q�P�N�A���A�����F�ێR����j  �@���m�ƌ��������A�z���͂̌��@�ƌ��������A���₵���َ��������w�\�̏��̂Ȃ������܂ܔr�o����Ă���Ƃ͎v��Ȃ������B����͑s��ł��ˁB �@���J�Ȃ��ŋ߁A�u���ޒ����v�̏��F�ɓ����Ă��邪�A�����ɕ��p�҂��̌�����̂́A�C���[�W����قǃC�[�W�[�Ȃ��Ƃł͂Ȃ���������Ȃ��B�ł���l�͂����Ɣ�D���܂��傤�B �@�ē̃I�[�h���C�E�f�B���@���́A�\�����ʔD�P���������q�w���A���k�̏ő��ɖ��������B���₪��@����������A�A���k�͂������P�l�őŊJ�̓��������ɒT��B��t�ɋ������A���͂ő~ং��A���ɂ͈łَ̑t�̌��ցB�u���T�ځv�Ƃ������������X�Ƒ}�������\���́A�܂�ŕώ�́u�^�C�����~�b�g�^�v�T�X�y���X���B �@�剉�̃A�i�}���A�E���@���g�����C�̒m�I�ňӎu�̋������Ȋ炾�����A��ʂْ̋��������₪��ɂ�����������B �@���������{��Ƃ͕ʂɁA�l�I�Ɏ��̈�ۂɎc�����̂́A�e�������̃��A���Y�����B �@���Ƃ��A�i�P�j���̃N���C�}�b�N�X�Ńq���C���̖����~�����̂́i���䂦�Ɋ��������ċ��Ƃɖ���郊�X�N�킹�Ă��܂����̂́j�A���܂��܋��̐����������䂦�Ɂu�������܂�āv���܂������̏��w���������B �@���邢�́A�i�Q�j�Ǘ������̃q���C�����ŏI�I�Ɂu�łَ̑t�v�ɂȂ��Ă��ꂽ�̂́A�u���łɔD�P���Ă�Ȃ�ꔭ�������Ă���Ă���������v�Ɣ���悤�ȃQ�X�Ȓj�F�B�������B �i�P�j�̃V�[���ŁA��x�̓q���C�������̂Ă��e�F���삯���Ă��ꂽ��A�i�Q�j�̃V�[���ŕ�e�܂��� ��������オ�����ɂȂ��Ă��ꂽ�肵����A���炩�ɃX�g�[���[��A��茀�I�ɂȂ����͂��B �@�ł��A�l�̐����āA���Ă��Ă����������̂ł���ˁB�P�O�O���̑P�l�ł��A�P�O�O���̈��l�ł��Ȃ��l�X���A�����ɗ����ꂽ��A�ӂƋC������N�������肵�Ȃ���A���R���l����������A�t�ɏ������肵�Ă���킯���B �@���̓_�ŁA�����̈�b�͌���҃A�j�[�E�G���m�[�̑n��ł͂Ȃ��A�ޏ��̎��̌����̂��̂������̂ł͂Ȃ����Ǝv�킹��B���Ȃ��Ƃ��쌀��̃X�e���I�^�C�v�ɂׂ͊��Ă��Ȃ��B �i���łɌ����Ȃ�A�q���C�����g�����������g����ȂƂ��낪�����āA�P�O�O���̊���ړ��͂ł��Ȃ��q�ł���ˁB�j �@���āA���������S�҂���Ђ��Ђ��Ɠ`����Ă���̂́A�������@�A�^�u�[�Ƃ���l�����̗��s�s���B�������̍זE�����A���łɂ��̐��ɐ������l�Ԃ̑I����K�������R�A���d�����ׂ��ł���͂����B�{��̎���w�i�͂P�X�U�O�N�ゾ�������A�������A����́u�ߋ��̈��K�v�ł͌����ĂȂ��B �@���ہA���E��̐�i������č��̏��������ɂƂ��Ă��A�������N�A���̖��͂܂��Ɂu�������ɂ����@�v�ɂȂ����B�g�����v�������ŕێ�E���x�����̃o�����X���傫�����ꂽ�ō��ٔ����̍\���䂪�ς��Ȃ�����A�č��̏��������́\�\�����đ����̏ꍇ�A���������������\�\����H���A�l����_�ɐU�邱�ƂɂȂ�B �@�V���O���}�U�[�ɂȂ��Đ����ی�ŕ�炷���Ƃ�ǂ��Ƃ���悤�ȏ����͂�����������Ȃ����A�N���������ł͂���܂���ˁB �@�Ō�ɂP�d���̋��������Ă��炤�Ȃ�A�u��ƂɂȂ肽���v�ȂǂƂ����g�y�������b�h���q���C���Ɍ����点���̂͗]�v�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��������B �@���ꂪ�m�[�x���܍�ƃG���m�[�̎��`�I��i�ł��邱�Ƃ�m��Ȃ��ϋq�ɂƂ��ẮA�u��������D�P����悤�ȋ����ȏ��w���̋Y�ꌾ�v�ɂ����������Ȃ��������낤����B �i�Q�O�Q�R�D�P�D�R�O�D�L�j �L�����[�v�l�@�V�ˉȊw�҂̈��Ə�M RADIOACTIVE �i�Q�O�P�X�N�A�p�A�����F�N�c�����j  �@�����A�Ȃ�����قǃf�L�̗ǂ��f�悪����قǗ������Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂��낤���B��f�ِ�����s���ł���������قǂŁA�P�O���̕��蓖���ɂ́A������������Ȃ���ςɂ������Ƃ����Ȃ킸�B����ł��N������ɉ���̓�ԊقŐh�����ӏ܂ł��A�u�����A����ς茩�����Ȃ��ėǂ������v�Ƌ����Ȃʼn��낵�����悾�B�L���̌��������V�[���Ƃ����i�D�́g�Z�[���X�|�C���g�h�܂Ŋ܂܂ꂽ��i�Ȃ̂ɁA�L�m�t�B�����Y����͂������������̃X�N���[�����m�ۂł��Ȃ������̂��낤���B �@�E�E�E�ƁA�ŏ��͔z����Ђɕ�������������Ȃ������A����N���Q�O�P�X�N�ł��邱�ƂɋC�Â��ĕs����p�����B�R�N�Ԃ����u����Ă����Ǎ���T���x�[�W���A�Ȃ���Ȃ�ɂ�������J�ɂ������Ă��ꂽ���Ƃ����ł��A�\���L�m�t�B�����Y������̂��đR��ׂ��������̂����B �@���킸�ƒm�ꂽ�m�[�x���܉Ȋw�ҁA�}���[�E�L�����[�̕]�`�f��B�ޏ��̓`�L�{��u���Ă��Ȃ��w�Z�}���ق͂Ȃ��Ǝv�����A�}���W�����E�T�g���s�ē͊w�������̓`�L�ɂ͏�����Ă��Ȃ��v�l�̚ʗ_�J�Ȃɂ��G��Ă���B �@�����A�̂�������}���[�i���U�����h�E�p�C�N�j�������Ȃ������炠��Ⴕ�Ȃ��B��S�Ǝ��M�͖��X�Ȃ���A�v���C�h�������A���n��̓w�^�B�A����肪�o��قǎ����⌤�����ւ̎x�����~�����̂ɁA�N�ɑ��Ă��u����������͗��܂Ȃ����ǁA���������]�ނȂ�x�������Ă����Ă��������B�����������ɂ͌��o�����Ȃ��łˁv�Ƃ����B��Ƒ��Ԃ肾�B����͂����A�ʂ̈Ӗ��ł́g�S�[���E�K�[���h�ł��ˁB �@����ȃ}���[�ɗB��A�������ʂŊS����̂��A�v�ƂȂ�s�G�[���i�T������C���[�j���B�B��Ƒ��̃}���[���A�ނɂ����͂��肰�ȁ`����������A�v���[�`���������肷���ˁB �@�Q�l�́u��������ȂǂƂ��������Ȃ��͎̂����Ă��܂����v�Ƃ���ɐ�啪��̉�b�����킵�A����ɂ���ĂȂ���w���݂��ւ̌h�ӂƎv���[�߂Ă����B���̂�����̃V�[�N�G���X�́A�㎿�̃\�t�B�X�e�B�P�[�V�����ƃ��[���A�ɖ����Ă����B �@�T�g���s�ē͂P�P�O���̍�i�̒��ɁA�L�����[�v�l�̐l���̑S�e�����Ɏ�ۂ悭�D�荞��ł݂���B�Ȋw�҂Ƃ��Ẳh���B�����Ȃ邪�䂦�Ɍy������A�v�̉A�̑��݂Ƃ��Ĉ����Ă��܂��t���X�g���[�V�����B���甭���������˔\�Ɍ��N���ނ��܂�����i�v�ɑ������ꂽ�V�[���ł̃p�C�N�̜ԚL�́A����҂̋��������ނ���j�B �@�����A�s���Ȏ����m��Ȃ������̂́A�}���[���v�̎���A�Ȏq�����̓����ƕs�ϊW�Ɋׂ������ƁA�����Ă���ɂ��m�[�x���܂̏^�𐁂�����قǂ̋t���𐢊Ԃ��痁�т���ꂽ���Ƃ��B�~��p�ɗ��낤�Ƃ���قǁA�S�v�s�G�[���������Ȃ���ł���B�l�̐S�͕��G�ł��ˁB�̐l�`�œǂg�L�����[�v�l�h�ł͂Ȃ��A�f��́g�}���[�E�X�N�E�H�h�t�X�J�h�������ɂ���B �@�T�[�r�X���_�����ȃT�g���s�́A����ɏI�Ղɂ��傫�ȕϓ]��p�ӂ��Ă����B�}���[�͖��C���[�k�i����܂���̃m�[�x����ҁB�A�j���E�e�C���[���W���C���������^�������ȖōD���j�ɉ�������`�ŁA���g�̌��������ݏo�����ȈՃ����g�Q�����u���g���A��n�ɕ����̂��B �@����͔ޏ������ӔC�ȏۉ�̓��̏Z�l�ł��邱�Ƃ���߁A�����ƕv���Ȃ��������┭���ւ́u���Ƃ��O�v���A�g�������Ă����u�Ԃł��������낤�B �i�Q�O�Q�R�D�P�D�Q�W�D�L�j �Q�O�Q�Q�N�i���́j�x�X�g�P�O�I �@�Q�O�Q�Q�N���Ɍ���Ŋӏ܂����f��̖{���́A��������傤�ǂT�O�{�������B���̂����̃x�X�g�P�O���A��N�̂��Ƃ��u�ǂ��������v�ł͂Ȃ��A�u�ӏ܂������v�ɋ����Ă����܂��B �@������Ɠ��M���Ă��������̂́A�V�Ԗڂ́w�x���t�@�X�g�x���ς��̂��R���R�P���ŁA�W�Ԗڂ́w�����ƋU��x�͂X���Q�U���������Ƃ��������B�N���Ԃ��Ă���B �@���̊Ԃ́A�������@����������Ă����킯�ł��Ȃ���A���܂��ܖʔ����f��ɏo��Ȃ������킯�ł��Ȃ��A�m��̌��J�����̂��������Ă�����ł��ˁB����ɂ������Ă����̂́i�P�j�A���R�~�A�����A�g�b�v�K���Ȃǂ̃u���b�N�o�X�^�[��i���A�i�Q�j�P�ٌn�̒n���ȏ��i���ɓ�ɕ�������A���̒��Ԃ́A�命���̗m��t�@������Ԋς����]�[���̉f��͐�����قǂ������B �@���������l�܂��Ă����ǔ��V���̂���L����ǂ�Ŕ[���������ǁA�ŋ߂̃V�l�R���͓��������҂ł���������Ώd���邽�߁A�����̍�i�̓X�N���[���̊m�ۂɋꂵ�ނ悤�ɂȂ��Ă���̂��Ƃ��B������T�}�[�V�[�Y������f��̃V�[�Y���ɂȂ�ƁA��l�̊ς�����i�����ꂩ��쒀���ꂪ���Ȃ̂ł��ˁB �@����͗R�X�������Ԃł���B �P�@�w�t�����`�E�f�B�X�p�b�`�@�U�E���o�e�B�A�J���U�X�E�C���j���O�E�T���ʍ��x �Q�@�w�S�[�X�g�o�X�^�[�Y�^�A�t�^�[���C�t�x �R�@�w�R�[�_�@�����̂����x �S�@�w�I�y���[�V�����E�~���X�~�[�g �\�i�`���\�������́\�x �T�@�w�K���p�E�_�[�E�~���N�V�F�C�N�x �U�@�w�I�[�g�N�`���[���x �V�@�w�x���t�@�X�g�x �W�@�w�����ƋU��x �X�@�w�k�`�l�a�^�����x �P�O�@�w�X�e�B���E�H�[�^�[�x�i�Q�O�Q�P�N�A�āj �@������J���ɂ͌����������A�K���v�n�v�n�v�ŏE�����B���̙l�߂𐰂炻���Ɩz�����镃�e�i�}�b�g�E�f�C�����j�A����ȕ��e���������Ƃ��Ȃ����i�A�r�Q�C���E�u���X�����j�B���o�D�̉��Z�͂ƃg���E�}�b�J�[�V�[�ē̉��o�͂����Q�B �i�Q�O�Q�R�D�P�D�P�O�D�L) �A���X�e���_�� AMSTERDAM �i�Q�O�Q�Q�N�A�āA�����F����L�K�j  �@�����Ƃ����̂́A���ɏ���������ł͂��邯��ǁA���ɖ���ȏ�ɃE�\�������B����ł��f���Ƃ��ϋq���A�ق��Ă��������邵���Ȃ���ł���ˁB�����āA�����Ȃ��́B�ς��悤���Ȃ����́B �i�N�G���e�B���E�^�����e�B�[�m�́w�C���O�����A�X�E�o�X�^�[�Y�x�ŁA������Ɨ��j�����҂��Ă��܂������A����͋H�L�Ȉ��j �@���̃}�[�N�E�g�E�F�C�����A�����Ə����̈Ⴂ�͉����ƕ�����āA�u�����ɂ̓��A���e�B���K�v�Ȃ��_���v�Ɠ����������ȁB �@����͂P�X�R�O�N��B�E�l�̔G��߂𒅂���ꂽ�o�[�g�ƃn�����h�́A�������č����t�@�b�V�������悤�Ƃ���閧���Ђ̉A�d�Ɋ������܂�E�E�E�B �@���āA�{��̑�����ǂ�A�܂�Łu���ʃ��C�_�[�v�V���[�Y���B������ɁA����̓q�g���[�⃀�b�\���[�j���䓪���������ɁA�č��Ŏ��ۂɊ�Ă�ꂽ�A�d�Ȃ̂������B �@�I�[�v�j���O�ƃ��X�g�V�[���Ŏ��b�ł��邱�Ƃ����Ȃ���A���邳�^�̉f��t�@������u�X�g�[���[���x�^������v�Ɣ��ꂽ�ɈႢ�Ȃ����A�i�J��Ԃ����j���ꂪ�����Ȃ̂�����d���Ȃ��B �@�����ŊēE�r�{�̃f���B�b�h�E�n�E���b�Z���͂ǂ��������H�@�閧���Ђ�������b�́i�܂�{���Ȃ畨��̍����ƂȂ�ׂ��j�����́A�e�ɉ�������o�[�g�E�f�E�j�[���ɔC���A������ʂ�}�t�̕����ŁA�g���v���剉�̃N���X�`�����E�x�C���i�o�[�g�j�A�}�[�S�b�g�E���r�[�i�o�����[�j�A�W�����E�f�r�b�h�E���V���g���i�n�����h�j���c�����s�ɓ��������B �@��炪�O�l�O�́A��͏㗬�Љ�牺�̓X�����X�܂ŋ삯����A��Ȃ���Ȃ����肻���ȃX�p�C��Y���A�������ȕx���₻�̔��l�Ȃƒ��X���~�̋삯���������킷�i�}�C�N�E�}�C���[�Y�A�}�C�P���E�V���m���A���~�E�}���b�N�A�A�j���E�e�C���[���W���C�ق��̋����w���A�܂����j�B �@����ɂ͊e�l�̗����͗l��A�o�[�g�Ƌ`���̉Ƒ��Ƃ̒����ȃz�[���h���}�܂ŗ��ݍ����A�P�R�S���Ԃɂ킽��j���Ƌ����̃h���}�́A�܂�ł������ᔠ���Ђ�����Ԃ������̂悤�Ȃɂ��₩�����B �w�A���X�e���_���x�͂܂��A�����͂��́g�C���N���[�W�����h��̌�����f��ł��������B�ӏܑO�ɖ`���̎ʐ^���������A�u���̂����A�ǂ̂Q�l�������W�ɂȂ�ł��傤�H�v�ƕ����ꂽ��A�����Ă��̐l�͔��l�Q�l�̖��O�������邱�Ƃ��낤�B�Ƃ��낪�ǂ������A�����͂Ȃ�Ȃ���ł��ˁB �@���Ԃꂽ�o�[�g�ɂ����Ƃ���ŁA���l�̍Ȃ����g�ł���Ȃ���A���������l�����̃C���}�i�]�[�C�E�T���_�i�j�Ɏ䂩��Ă����B���������A������Č������^���Ȃlje���`���Ȃ��P�X�R�O�N��̘b����ˁB �@��͂�C���}�����݂������w�E����悤�ɁA�u�̐S�Ȃ̂͒N��K�v�Ƃ��Ă��邩�ł͂Ȃ��A�N��I�Ԃ��v���Ă��ƂȂ̂��낤���B �@���̎���g���I�́A�ِl�����ł͂Ȃ��A�폝������Q�҂����r�˂��Ȃ��B�o�����[���n�����h�����ƒm�荇�����͖̂��a�@�Ń{�����e�B�A�����Ă��������������A��t�̃o�[�g�͎���E�ڂ������Ă��Ȃ���i���邢�́A�����Ă��邪�䂦�Ɂj�S���𒍂��Ő폝�҂̎��Âɓ�����B �@�������A�����łȂ���Ȃ�Ȃ��̂��B�����āw�A���X�e���_���x�́A�I����Ă݂�A�D���v�z�𐄂��i�߂��i�`�Y���ւ̃A���`�f��ɑ��Ȃ�Ȃ��̂�����B �@�Ƃ���ŁA����͂���Ƃ��Ăł��ˁA�x�C���̉E�ڂ͋`��i�Ƃ����ݒ�j�Ȃ���A���ڂɍ��킹�č��ڂ�������_�������ĂB �i�Q�O�Q�Q�D�P�P�D�P�O�D�L�j �X�y���T�[�@�_�C�A�i�̌����@�@SPENCER �i�Q�O�Q�P�N�A�p=�`��=��=�āA�����F�쓈���ގq�j  �@�`���A�H���œ���q�˂�q���C���̉p���a�肪�킴�Ƃ炵���āi�܂�łm�g�j���h���q���C���̕������j�A�Ȃ��č��l�̃N���X�e���E�X�`�����[�g���N�p���ꂽ�̂��ȂƎ���Ђ˂�B�ł��A����ƂȂ邨���~�ɒ������ޏ����A���������o�[��g�p�l�Ɨ����킹����A�g�C���ŃQ�[�Q�[�f�����肷��̂����Ă�����A�m���ɓK�����Ǝv������B����A���̐_�o�ǓI�ȏ������̓N���X�e���̏\���Ԃ��B �w�_�C�A�i�x(2013)�̃i�I�~�E���b�c�Ɠ��l�A�N���X�e�������Ƀ_�C�A�i�ܖ{�l�Ɗ炪���Ă���킯�ł͂Ȃ��̂����A���Ă��邤���ɂ���炵�������Ă���̂��f��̗́B�㔼�Ɉڂ鍠�ɂ́A�P�U�T�Z���`�̔ޏ��̌��p�܂ł��A�P�W�O�Z���`���炢�������_�C�A�i�܂� �����₩�Ȃ����f�i�������B�B�e�ǁA���Ȃ茤����H�v���d�˂��Ǝv���B �@�p�u���E�����C���ēȉ��̐���w�́A���������̑��ꂵ����v�̕��C�ɋ�Y����q���C���̐S����A���J�ɁA���J�ɕ`���Ă���B�������A�����Ɂu�_�C�A�i���P�ʁA���������ʁv�Ƃ����\�}��ǂݎ��̂́A�K�������������Ȃ����낤�B��ÂɌ���A�u����vs�_�C�A�i�v�̍\�}�ɑ��鐻��w�̗���́A���������j���[�g�������B �@���ہA�o��l���̂P�l�́A�_�C�A�i�ɑ��A�u�����̕��X�͂��Ȃ����C�ɂ����Ă����܂��v�ƁA�^���ɐi�����Ă�����B����w�̓_�C�A�i�܂�����I�ȁu��Q�ҁv�Ƃ͂����A�����ɂ���Ắu�P�ɉ��������ɓK���ł��Ȃ��������s�ҁv�ɂ�������`�ʂ����Ă����ł��ˁB �@�o�C�A�X�̂Ȃ��ϋq�̒��ɂ́A�u�����̃��[���A�Ȃ���̏d�v���炢�ق��ď��������A�s�o�n�ɍ���������p�ӂ��Ă��炦��̂�����A�ނ���y����Ȃ����A�ʓ|�����������Ȃ��v�Ɗ������������������͂����B �@�NJ��Ɓi����Ӗ��A�c�t�ȁj�����S����g����ȐU�镑���������ɂ����Ȃ��q���C�����A�v�̃`���[���Y�i�W���b�N�E�t�@�[�V���O�j�͌����ʼn��x�������������߂�B���ɂ͂��̃`���[���Y���A�u�q���C���̂����ߖ��v�Ƃ������A�u�����̋`���ƐӔC�����ꂽ�҂̖��v�Ɍ������B �u���ɂ͂������Ȃ����Ƃ����āA���˂Ȃ��̂��v�Ɣނ��������A���̑Ώۂ͕K�������L�W���̂��Ƃ����ł͂Ȃ��A�u�{���ɍD���ȔN��̏�����������߁A���h���͂������ǂ������čD���ł͂Ȃ��Ⴂ���ƌ������邱�Ɓv���܂܂�Ă����悤�Ɋ�����̂ł���B �@���������ƁA���ẴG���U�x�X�����̎�����A�`���[���Y�c���q������قǃX���[�Y�ɉ����������p�����̂́A���ɂƂ��ċ����������B�u�s�ς��ĉ�炪�v�����Z�X���ꂵ�߂��`���[���Y�͔���A���̑��q�̃E�B���A�����q�ɑ��ʂ�����ׂ����v�Ƃ������_�����˂Ă������ƕ����Ă������炾�B �@�������ڗ��������Ή^���Ȃǂ��N����Ȃ����������Ɋӂ݂�A�_�C�A�i�܂̎���Q�T�N���o�āA��ʂ̉p�������ꎞ�̃q�X�e���[��Ԃ�����߁A�u�ǂ������ǂ�����������ȁv�ƍl���n�߂Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���ˁB���̉f��ɂ́A���Ȃ��Ƃ������I�ɂ́A����ȋ�C������肱�܂�Ă���悤�Ɋ�������B �@�I�n�A�d�ꂵ�����͋C�Ői�ލ�i�����A�㔼�A�p�ЂƂȂ������Ƃ��q���C�����K���V�[���ň�x�����NJ�����蕥����B����E��`�T�C�h�Ɍ��킹��A�����̓q���C�����u��匈�S���ł߂��v�R��ł���̂��낤���A�c�O�Ȃ��玄�ɂ͂��̓_�����܂�`����Ă��Ȃ������B �@�������Ȃ���A�c�����̎����̌��e�Ƌ��������悤�ɑS�͎�������q���C���̃����^�[�W���́A���ꂾ���ʼnf���Ƃ��Ẵp���[�ɖ����Ă����ˁB������O��̃V�[���ƕ���I�ɐ������Ă��悤�����܂����A�{���̃_�C�A�i�܂�����ȕ��ɑ������Ƃ� �Ƃ��Ă��v���Ȃ��낤���A�f��I�ɂ͂���Ő����������̂��낤�Ǝv����B �@�f��̗ǂ���_���邱�Ƃ��āA�{���Ɉ�ؓ�ł͂����Ȃ��B �@�����A�_�C�A�i���B��S��������Q�l�̉��q�ƐG�ꂠ���V�[���́A�ꌩ����ƒg�����ɖ����Ă����B�����E�B���A���ƃn���[�̌����m�鎄�����̖ڂɂ́A�����ɃV�j�J���Ȃ��̂���d�f���ɂȂ炴������Ȃ��B �@�������яo�����n���[�͂Ƃ������A����c���q�ƂȂ����E�B���A���̐S���ɂ́A�����̃`���[���Y��������̂Ɠ����������o�傪�ԈႢ�Ȃ����邾�낤�B�ł͂Ȃ��L���T�����܂́A�_�C�A�i�܂��K���ł��Ȃ��������ƂɓK���ł��Ă���̂��B�Ȃ��ق��đ̏d�v�ɏ���̂��B �@������l���鎞�A�u���ǂ͌�������Ɩ{���ɍD�������Ă��邩�ǂ����̈Ⴂ����Ȃ��́H�v�Ƃ��������b�Őg���W���Ȃ����_�����ɕ����ԁi��قǁu�����̃��[���A�Ȃ̂�����v�Ə��������ǁA�v�w���̈�����������āA���Ƃ̃��[���A�̃Z���X��ь�������X��������܂���ˁA�����Ȃ炸�Ƃ��j�B �@���������A�������ɐg�߂Ȃǂ����̍��̍c���ł��A�j�܂͓K���ł������ǁA�l�܂͓K���ł����ɂ���̂ł���ˁB�E�E�E���A���݂܂���A������ǂ����ƌ�������͂������܂���B �i�Q�O�P�P�D�P�O�D�P�W�D�L�j �k�`�l�a�^�����@�@LAMB �i�Q�O�Q�P�N�A�A�C�X�����h���X�E�F�[�f�����|�[�����h�A�����F�k���L�q�j  �@���₠�A���̌����ɂ͋������B�u�[���������H�v�Ƃ��u�C�ɓ��������H�v�ƕ������ƌ��������Ă��܂����ǁA�u�\�z�O���������낤�H�v�Ɩ����A�܂��ɑR��B���̏d�X���������ƁA�r�X�������Â����̎�����́A�������������R�I�ȑ��݂��Ɨ\�����Ă��܂����B �@�Ԃ�V���u����v�ɘA��o���ꂽ�V�[���͓�B�l���ł͕����グ���Ȃ����낤����A�l�R�Ȃ̓����̂悤�Ɏ��������킦�ĉ^�̂��ȂƂ����̂��A���̑z���ł��B �@�Ƃ���Ŗ{��̗\���ғ��ł��̎q�̗����p�����炵�Ă��܂��Ă����̂͑厸�s�������̂ł͂���܂����B���ꂪ�Ȃ���A�o�Y����ɂ��̎q���Ŏ��ꂽ�v�w�̔������A����قǕs���R�ɂ͊����Ȃ������͂��Ȃ�ł���B���̏�ʂł́A�������܂ꂽ�̂��ϋq�ɂ͒���Ă��Ȃ������̂ł�����i�{���Ȃ�A�Ԃ�V���A��o���ꂽ�O�q�̃V�[���ŁA�ϋq�͏��߂Ă����m��A�V���b�N�Ƌ����Ɍ�������͂��������j�B �@�Ƃ��낪�����̊ϋq�͗\���҂��Ɍ��Ă��܂��Ă���̂ŁA�a���̏u�ԁA�v�w�̊ԂŁu�����A����́H�v�u���Ȃ��A�܂������̎��q�c�W�ƁH�v�u����ȉ������͐������Ă�����v�u�����A��Ă�����v�I�Ȃ���肪���킳��Ȃ��̂��s�v�c�łȂ�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B �@���̌�ɓo�ꂷ��v�̒���A���̎q�����ʂ̐l�ԂłȂ����Ǝ��͔̂F�����A�ǂ�Ȍo�܂ł���Ȃ��̂����܂�Ă����̂��ɂ��Ă͓��ɒNj�����f�U�肪�Ȃ���ł��ˁB �@����͂��Ȃ킿�ē�r�{�Ƃ��i���Ԃ�m�M�ƓI�Ɂj��������������Ă��邩��Ȃ̂����A���̂��Ƃɂ���Ă��̍�i�ɓƓ��̃I�t�r�[�g�Ȗ��킢���t���������Ă��邱�Ƃ��w�E�ł���B�����炭���̕���́A�u�~���s���̔_�v���r�ƈꔭ�����āv�݂����ȉ��i�ȃW���[�N�̑��݂��Ȃ��A�ǂ����̃p���������[���h������Ȃ̂ł��傤�B �@���łɌ����A�\���҂̏o�����ł����Ȃ�u�q�ǂ���S�������v�w�v�ƃi���[�V�������Ă��܂����̂��}�~�X���Ǝv���B�����̕�Q��̃V�[���ŏ��߂Ă��̂��Ƃ��킩��悤�A���������u�q�ǂ��̂��Ȃ��v�w�v�ƌ����ɂƂǂ߂�ׂ��������B���Ղ́u���ԗ��s�v�̉�b���A���̂����ŕ����Ƃ��Ă̌������キ�Ȃ�����������ˁB �@����ɂ��Ă����̓��������͎��ʂ������̂��A�b�f�������̂��B�`������A�n�Q�͌����ɎB�e�҂̓s���ɍ��킹�Ĉړ����邵�A�b�ɂ̗r�����͂�����ăJ�����ɖڐ��𑗂�B���ɗr�͂��܂蓪�̗ǂ��Ȃ��Ɠ������ƕ����Ă���̂ŁA���ʂ��Ƃ�����A�������܂Ō������Ƃ���������̂͂����������Z�p���Ǝv���B �i�e�[�u���ɒ������m�I�~�E���p�X�̃o�X�g�V���b�g�̉����A�����ۂ̐�[�����������Ă����J�b�g����Ŗʔ��������B���ꂾ���ŁA�����ۂ𐂒��Ɏ����グ�������l�R�������ɓ����ė������Ƃ��`����ł���ˁj �@����A�b�f���Ƃ�����A��\�Z�̖k���f�悪�w�r�[�X�g�x�̃��C�I���ɂ����ʃ��A�������o���Ă����_�ŁA������܂��������B����Ő����Ȃ��Ȃ��Ĕo�D���R�l�����g���Ȃ������̂��E�E�E�Ƃ����̂͂��傤���Ȃ��W���[�N�ł����ǁB �i�Q�O�Q�Q�D�P�O�D�P�O�D�L�j �����ƋU���@�@THE DRY �i�Q�O�Q�O�N�A���A�����F���Ԉ����j  �@���{�ł͌���@��̏��Ȃ��I�[�X�g�����A���̃~�X�e���[�f��B���o���̂���o�D�̓G���b�N�E�o�i�Ɓi�����������Ă���w�A���r�������X�x�̂e�a�h�{�����������Ǝv���o�����j�L�[�A�E�I�h�l�������o�Ă��Ȃ����A�ԑR����Ƃ���̂Ȃ��X�g�[���[�^�тŁA�l�S�������������点��悤�Ȋ����n�т̈Õ����A�ς�҂ɓ˂�����B �@�I�[�v�j���O���炢���Ȃ�ڂ������̂́A���R�ł������L����n�̋�B���B���̊Ԋu�Œn�ʂɏc�Ȃ������Ă���̂ŁA�ŏ��́u���̐����ȁv�Ǝv���̂����A�J�����̍��x��������ɘA��āA�n�w�ƕ��䂾�����D��Ȃ����R�̑��`���Ƃ킩��B�܂�͕����ǂ���u����������Ă��Ȃ��v�L��Ȓ��F���r��n�Ȃ�ł��ˁB �@��l���̘A�M�{�����A�[�����i�o�i�j�́A�Q�O�N�Ԃ�ɂ��������ƒn�ɋA������B�e�F�̃��[�N���Ȏq���E���A���E�����Ƃ̕�������߂��������A�A�[�������g�����ẴK�[���t�����h�����܂ɁA�ǂ���悤�ɒ����o���o�܂�����E�E�E�B �@���݂̎����Ɖߋ����r������������̂́A�n�[�h�{�C���h��i�̉������̉����B�Ƃ�����u�܂����v�̎v�����������˂Ȃ��Ƃ��낾���A���E�I�x�X�g�Z���[���Ƃ��������̌���i�W�F�C���E�n�[�p�[��j�̃f�L���ǂ��̂��A���o�[�g�E�R�m���[�ē̎�r�̂Ȃ���Ƃ��A���̂P�P�V���̍�i�Ɋɂ݂�j�]�͂قƂ�ǂȂ��i���Ղ����͌��݂Ɖ�z�V�[���̍s���������������ď����X�g���X�������邪�j�B �@��l����������悤�Ɏ����̐^���ɔ����Ă����ɘA��A�������Ȑl�����������ȓ��������A�����Ǝv��ꂽ�l���܂ł��v��ʔ閧��\�I����Ă����W�J�͋ɂ߂ăT�X�y���X�t���B���݂Ɖߋ��̗������ŁA�ϋq���U��̐^���ւƃ~�X���[�h�����������A�Ō�ɂ��̗������ǂ�ł�Ԃ���ۂ͂��������B �@�{�i�������ɂ��肪���ȃL�������`�̌y�����Ȃ��A��v�Șe�������͊F�A����Ȃ�ɉA�e���[���B�l�I�ɂ͂Ƃ�킯�A�I�h�l�����������c�ɒ��ɂ������P�l�́i�Ǝv����j�x���Ɏ䂩�ꂽ�B�V�Ăł���Ȃ����͂��S�苭�������ނ́A�NJ������咣���ăA�[�������ז����Ă���ł��Ȃ��A�t�ɘA�M�{�����̌��Ђɖӏ]����ł��Ȃ��A�����̉����Ƃ����u���v�v�̂��߂ɁA�����ȑԓx�Ŏ�l���ɋ��͂���B�䂦�ɁA�A�[�����ɉߋ��̎����̋^������������V�[���ł́A���̌x�����ϋq�̃A�o�^�[�ɂȂ�B �@�A�{���W�j�[�n�̏��D�����������̍Ȃ��܂������B�P�Ȃ�[�����Ǝv������A�H���ɏ�������l���ɁA�u�v��s���ǂ����p�����珳�m���Ȃ��v�ƁA��������B���h���̂ł���B���̕v�w����l���ɕʂ̉f����������A���������ʔ������̂ɂȂ邩������Ȃ��ˁB �i�Q�O�Q�Q�D�P�O�D�P�D�L�j �u���b�g�E�g���C���@�@BULLET TRAIN �i�Q�O�Q�Q�N�A�āA����:���Y���ށj  �@�ɍ�K���Y�̏����u�}���A�r�[�g���v���n���E�b�h���f�扻�B �@���݂܂��l�^�o�����炯�ł��B�����\�K���Ă���ς��̂ŁA���҂��r�������~�]��}�����܂���B�����̕��A���ǂ̕��͂����ӂ��������B ���ؑ��F�����ǂ�ۂ��珟��Ɍ|�l�̖ؑ��S��̂悤�ȃI�b�T�����v���`���Ă����̂ŁA�f��ł̃A���h�����[�E���H�̓V���[�v�������ۂł��ˁB ���ؑ��i���j�F���̐l���ɂ܂��T�v���C�Y�v�f������̖��͂̂P�������̂����A�f��łł͖`������^�c�L�V���A�������X�J�[�t�F�C�X�ŏo�Ă��Ă��܂��̂ŁA�T�v���C�Y�v�f�͊F���ƂȂ�B �@�^�c�L�V�A�����Ԃ�č��̉f���s�u�h���}�ɏo�Ă��邯�ǁA���x�A�p��̃Z���t�͏��Ȃ��ł��ˁB �������i�^���W�F�����j�F�J���I�o���̃`���j���O�E�e�C�^���������Ō����Ă����悤�ɁA�A�[�����E�e�C���[���W�����\���̉p���a�肪�J�b�R�����B�K�C�E���b�`�[��i�Ȃǂł����Ȃ��݂̒ʂ�A���}���܂������Ă�R�b�N�j�[�a��ɂ͓Ɠ��̖��͂��B����n�߂��V�����̉����ɔ�я��Ȃ�Ĉꖋ�́A�������Ɍ���҂͏����Ă��Ȃ������i�j�B ���E�G�i�������j�F����ł͒��g�E�����ŁA�u�����Ƃ͑��l�Ȃ̂ɌZ��ƊԈ����v�Ƃ����ݒ�B�䂦�Ɂu�w���X�̋i���X�v���̂����K���̃}�[�N�i�x����j�ƃg�~�[�i�����x���j�̂悤�ȃR���r���v���`���Ă����B�N��o���܂��ˁB  �i���E�̂Q�l���}�[�N�ƃg�~�[�ˁj �i���E�̂Q�l���}�[�N�ƃg�~�[�ˁj�@�Ƃ��낪�f��łł̓A�t���J�n�̃u���C�A���E�^�C���[�E�w�����[�������Ă���A�Ԉ���Ă��A�[�����E�e�C���[���W�����\���ƌZ��ɂ͌����Ȃ��B���̃������A���X�ɑޏꂵ������Ƃ͈Ⴂ�A�f��łł͍Ō�̌�����������Ă����B ���ԏ��F���̃������Ɍ������D��ꂽ�̂��A�}�V�I�J�̉������ԏ��������B����ǂ���Ȃ烉�X�g�ł����݂�������Ƃ��낾�������A��͂���{�l�L���X�g�͂����v�����B ���X�Y���o�`�F����������n�L���X�g�������̂Ŋ��҂��������A���������Ƃ���̓W���[�J�[�̃}�h���i�i�U�W�[�E�r�[�c�j�Ɏ����Ă����ꂽ�B�ł���e�n�z�q��������N�p���āA���̂܂ܖ\�ꂳ���Ăق����������B ����������F����H����A�����ܗւ̃}�X�R�b�g����Ȃ������̂��B  �����q�F����ł͒j�q���w�����������A�f��łł͎Ⴂ�����ɐݒ�ւ��B����҂͂��̃L�����̎����̕`�ʂɂ��Ȃ�̎������₵�Ă������A�f��łł͂����ς��̂āA����Ŕޏ��̏�ԖړI�ɑ傫�ȕύX���������B�������W���[�C�E�L���O�̓J���t�H���j�A���܂�Ȃ̂ɁA�p���a��Řb���Ă����悤�ȁB ���z���C�g�E�f�X�F���q�ƘA�����đ傫���ς�����̂����̃L�����̈����B����ł͒[�����������A�f��łł̓��X�{�X�������B����Ŗ�����A�O���l�̐ݒ�ɕς�����ł��ˁi���{�l�o�D�ɂ�点��Ƃ�����n�ӌ����炢�������҂����Ȃ��j�B�Ō�͒E�������V���������s�̒��Ƃɓ˂����ނƂ����g���f���W�J�B�e�o��l���̋A���������ĞB���ɂ�������҂̋����͂����ɁH ���V�����i���f�B�o�O�j�F����Ŏ���̐��i�ݒ�͑������x�A����Ɍh�ӂ������Ă����͗l�B���r�����ǃc�L�̂Ȃ��E�������u���b�h�E�s�b�g���D�������B�����A����ǂ���̎E���̎�����Ƃ��܂�ɂ������菟�������̂ŁA�E�w�̑��ʂ͉��{�����ɂ��Ȃ��Ă��܂����ˁB�^���W�F�����Ƃ̑Ό��̍Œ��Ɏԓ��̔������琅�����V�[���ɂ͑唚�B �i�Q�O�Q�Q�D�X�D�P�P�D�L�j �x���t�@�X�g�@�@BELFAST �i�Q�O�Q�P�N�A�p�A�����F�q��Վq�j  �@�����_�łQ�O�Q�Q�N���̊ӏ܍�̃x�X�g�����B �@�P�l�X�E�u���i�[�̔����`�I�ȍ�i�ł���{��́A�k�A�C�������h�̎�s�x���t�@�X�g�̉������i����n�܂�B�ȑf�ȃe���X�n�E�X(�������Z��)�A�Ǝ��┃�����Ƃ������s��̕�炵���c�ޏZ�������A���������Ŕ�ь������A��y���A�W�c�ő�����q�ǂ������B�ߏ����݂�Ȓm�荇���ł��邱�Ƃ�A�e�˂̃g�C�������O�ɐ݂����Ă��邱�ƂȂǂ����܂��āA����ݒ�͂P�X�U�X�N�Ȃ���A�ނ���T�O�N�ギ�炢�̓��{�������������i�ɂȂ��Ă���i�T�O�N��̓��{�����m���Ă���킯�ł͂Ȃ�����ǁj�B �@����Ȗ��邢�q�̓I�Ȍ��i���A�ꔭ�̔��������_�@�Ɉ�]�B�P�X�U�O�N���܂�̃u���i�[�̕��g�ł���X�̏��N�o�f�B���A�@�h�R���ɂ��e���Ɩ\���̉Q���ɓ������܂��B���̖�����ÁA���킩������ւ̓]���͈������B���̏Ռ��x�́w�N���C�G�b�g�E�v���C�X�x��Q��̃I�[�v�j���O�ɂ��䌨���悤���A�����炪�G�C���A���̏P����`�����r�e�������̂ɑ��A������͔����I�O�Ɏ��ۂɋN����A���������̐l�X���L�����鎖���B�u���i�[�͏��N�̖ڂɉf�����\�k��S��A���ɓ����������⋩�ѐ����r�r�b�h�ɂƂ炦�A�ϋq���u���Ԃɕ���̐��E�Ɉ������ށB �@������k�A�C�������h�R�����J�g���b�N�n�Z���ƃv���e�X�^���g�n�Z���̏Փ˂ł��������Ƃ́A������x�̐���ȏ�̐l�ԂȂ�N�����m��Ƃ���B�����ăo�f�B���������܂ꂽ�\���́u�v���e�X�^���g�n�̑����n��ɏZ�ރJ�g���b�N�n��_�������́v�ł��������Ƃ������ɐ��������B �@���ڂ��ׂ��́A�o�f�B�̈�Ƃ��v���e�X�^���g�ł��邱�Ƃ��낤�B�z���R�[�X�g�ɂ���A�q���V�}�ɂ���A���̎�̔ߌ���`�����n���i�ɂ́A�u��ҁ^��Q�ҁv�̎��_����u���ҁ^���Q�ҁv������������̂������Ȃ肪���B����A�{��̏ꍇ�́A��ʂɂ́u���ҁv�ƌ��Ȃ����v���e�X�^���g�n�́A�������u���Q�ҁv�ɂ͂Ȃ�܂��Ƃ���ǎ��h�̐S��ɒ��J�Ɋ��Y�����ƂŁA�l�Ɛl�Ƃ��������Ǝ��̂̋��������A�����Ȏ��_���畂������ɂ��ꂽ�B �@�����ƌ����Ȃ�u�@���ȂƂ������̂�M���邱�Ƃ̋��������v�ƌ����Ă�������������Ȃ��ˁB����������ƃu���i�[�́A�u�@���͊Q�����v�Ɗ��j���郊�`���[�h�E�h�[�L���X�ɓ������Ă���̂�������Ȃ��B�N���̏]�o������u�p�g���b�N��V���[���Ƃ������O�̒j�̓J�g���b�N������C�����ȁv�ƌ���ꂽ�o�f�B���A�u�T���͂ǂ����̏@�h�ɂ����邯�ǁA�ǂ������炢���́H�v�ƕԂ�������̒��ⓚ�ɁA���̂��Ƃ��\��Ă���悤�ȁB �@���Ȃ݂ɂ��̏]�o���̓v���p�K���_�ɏ悹���₷���A�����h�v���e�X�^���g�W�c�̐K�n�ɏ���āA�o�f�B�ɖ\���◪�D�̕Ж_��S�������肷��B���������ƃP���E���[�`�̉f�敗�̈�厖�ɕ��������Ⴄ���ǁA�X�N���[���Ŏ��ۂɓW�J�����̂́A�����Ŏ��������ʂ̃I���p���[�h���B�o�f�B�̑c���̓Ɠ��̃��[���A�Z���X�ɂ�������|�B�u���i�[�̃o�����X���o�ƃR���f�B�E�Z���X�̟��E���ɒE�X���邵���Ȃ��B �@���{���Ɍ����Ύ����u���i�[�Ɠ��w�N�Ȃ̂ŁA�w�����P�O�O���N�x�̃��N�G���E�E�F���`�A�A�|���P�P���̌��ʒ����A�e���r�ŗ����u�T���_�[�o�[�h�v�Ƃ����������̍d��̕����Ɂi�������͏����������̂́j���D��U��ꂽ�B �@����ȁu���邠��v���Ƃ͗����Ȃ���A���������ɂ����̂ł͂��������m��Ȃ��u���ҁv�̎��_�╶���ɐG����邱�Ƃ��A�O���f����ς�i�����Ďq�ǂ������Ɋς���j�Ӌ`�̂P���B �@���Ƃ��Ύ����܂߂����ϓI�ȓ��{�l�́A�u�k�A�C�������h�͉p���̈ꕔ�v���ƒP���Ɏv���Ă��܂���ˁB�Ƃ��낪�A�����ɏZ�ރo�f�B�̂��ꂳ��́A�u�����h���ȂɈڏZ������A���������͕̎�����A�a����o�J�ɂ����v�Ǝv���Ă�B�܂�ޏ��̓A�C�������h�l�Ƃ��Ă̊m�ł���A�C�f���e�B�e�B�������Ă���킯�ł���B�p���Ђ́A������v���e�X�^���g�Ȃ̂ɁI�@�ւ��A�����ȂB �@�����P�ʂ̗��������ƁA�����ŃN�\�܂������َq�̑�\�݂����Ȍ����������Ă���u�^�[�L�b�V���E�f���C�g�v�́A�u�i���j�A���v�V���[�Y�̎��j�����Ԃ𗠐��Ăł��H�ׂ����������َq���B������ǂq�ǂ������́A����������������̂Ǝv���Ă��邱�Ƃ��낤���ǁA�ĊO�����ł��Ȃ��݂����ł��ˁB �@�o�f�B����芪������[���c����i�L�A�����E�n�C���Y�ƃW���f�B�E�f���`�j�◼�e�i�W�F�C�~�[�E�h�[�i���ƃJ�g���I�[�i�E�o���t�j�̃L�������`������Ȃ��B���e�͂��ꂼ��Ɍ��_���_���������A�����Ċ����ł͂Ȃ��l���̂悤�����ǁA�אl�ɕs���ȓG�ӂ������Ȃ��Ƃ��A�q�ǂ����������Ƃ������玶�����Ƃ������A�l�ԂƂ��Ĉ�ԑ�Ȃ��Ƃ͂����Ƃ킫�܂����l����������A�ϋq�Ƃ��Ă����S���ăo�f�B��C���Ă�����B���łɐ��ς�肵�����Z�������A�s���ȎЉ���ƒ���̂���Ⴂ�Ɂi�X�̃o�f�B�ȏ�́j��@���������A�ł���͈͂ŗc�������낤�Ƃ���B �@���Ȃ݂Ƀn�C���Y�ƃh�[�i���́A�u���i�[�Ɠ������x���t�@�X�g�o�g�B�o���t���_�u�������܂�̃A�C���b�V�����B�L���X�e�B���O���n���ⓖ���̋�C����m��l�d���������̂�����������B �@�f���`�����̓C���O�����h�̃��[�N���܂ꂾ���A��e�̓_�u�����o�g�������͗l�B�G���f�B���O�߂��ŁA�V�����炯�̈��ߌ��̂悤�Ȋ���A�b�v�ɂ��ꂽ�f���`���A�o�f�B��Ƃɗ������𑣂��J�b�g�͖Y�ꂪ�����B �@���e���烍���h���Ɉ����z�����ƌ����āA�u��x���t�@�X�g���痣�ꂽ���Ȃ��I�v�Ƌ������o�f�B���������A���̃��f������u���i�[�́A�����Ď����̐l����L�����A�����߂Ƀ����h���Ɉڂ����B�u�Z�݊��ꂽ�y�n�𗣂ꂽ���Ȃ��v�Ȃ�āA���̂�m��Ȃ��q�ǂ��̊����ł����Ȃ������̂��B���������̔��҂��������āA�����ȃ��f�B�A��n�������̂��u�Z�݊��ꂽ�y�n�v�̎����𐁂����܂Ȃ���A�Ƃ��ƂƐV���ȓy�n�ŐV���Ȑ������n�߁A�V���ȍK��������ł��邾�낤�ɂˁB �@���������A�����̖Â��q�����̏t�A��w�𑲋Ƃ��A�e���𗣂�Ă������B�Ȃ����n�����̋����q�������̂ŁA���̃N�\�݂����ȓc�ɒ��Ɉꐶ������Ă��܂��̂ł͂Ȃ����ƁA�����Ƃ��Ċ뜜���Ă������A�K���Ȃ��ƂɞX�J�������l�q���B���E�͉\���ɖ����Ă���B�ޏ��̑O�r�ɍK������Ƃ��B �i�Q�O�Q�Q�D�S�D�P�O�D�L�j �I�[�g�N�`���[���@�@HAUTE COUTURE �i�Q�O�Q�P�N�A���A�����F���Y���ށj  �@�����́u�������畉���v�Ȃǂ� �����Ԃ���҂����������Ă���ƘR�ꕷ�����A�����������傤���Ȃ��A�����q�Ȃɔ�����Ăł��ς��Ă��ׂ��f�悪���ꂾ�B �@�G�X�e���i�i�^���[�E�o�C�j�̓N���X�`�����E�f�B�I�[���̃I�[�g�N�`���[������œ������j�q�����̃g�b�v�B�W���h�i���i�E�N�[�h���j�͒�E�������Ȃ��n�����ږ��B������A�o�b�O���Ђ�������ꂽ�G�X�e���́A�����Ԃ��ɗ����W���h�ɂ��j�q�Ƃ��Ă̍˔\�����o���E�E�E�B �@�ēE�r�{�̃V�����B�E�I�n�����́A�u�����E�Ɨϗ���ۂ��ƂŊm�ł��鋏�ꏊ�����E�l�v�u�Љ�ɋ��ꏊ�����������Ȃ���ҁv�A�u�Ό��̂Ȃ����j�q�i���o�[�Q�v�u�ږ������̃i���o�[�R�v�A�u�Ⴋ�q���C������Ă悤�Ƃ����l�̃q���C���v�u���Ɋ��邾���̕�e�v�Ƃ������d�w�I�ȑΏ̎���݂��A�������]���̑@�ׂȃh���X��D��������悤�ɁA���J�ɕ����a���ł����B �i���܂�ɒ��J������̂ŁA�u�V�i���I�w�Z�ŏK�������ȏ��ǂ���ɏ������݂����v�Ƃ̈�ۂ�����قǂ����A�������͂��������r�ł͂Ȃ��A�S�̂Ƃ��Ă͂ƂĂ��茘���B�j �@���Ƃ��p���̃A�g���G�ł̃G�X�e���̌�������́A�ޏ����P�̎d���ɒ��N�ł����݁A�ꗬ�̒m���Ǝ�Ƃ�g�ɂ��A�Ђ��Ă͏�i����̐M����A��������̑��h���������Ă����ߒ��������Č����邩�̂悤���B �@����ȃG�X�e���Ȃ�����A���K���Ƃ��ē����n�߂��W���h�ɂ��������ڂ���킯�����A���l������҂��ꂽ�o���̂Ȃ��W���h�́A�x�����J��Ԃ��A���ɂ͎�Ȃ̈������̂�������B��]�����o���ɂ������ň�����������ŁA�͂Ȃ��玩���̐l����������߂Ă��܂��Ă���̂ł��ˁB �@�f�B�I�[���̃A�g���G������p���̒��S���ƁA�W���h���Z�ލx�O�̒��T���h�j�Ƃ̑Δ�ɂ����ڂ������B�T���h�j�́A��X�T�b�J�[�t�@���ɂƂ��Ă̓X�^�b�g�E�h�E�t�����X�i�t�����X�̍������Z��j�̏��ݒn�Ƃ��Ă��Ȃ��݁B�������ߔN�͈ږ����������A�k�A�t���J�̈ꕔ�ƌ��܂����悤�Ȍ��i�ɂȂ��Ă��邻�����B �@�ٖ́w���m�̎����@�ږ��E�A�C�f���e�B�e�B�E�C�X�����x�ɂ��A�u�p���̒��S���ɂ���l�X�́A�T���h�j�Ƃ����n�����Ɗ�������߂�B�ނ�͑吹���������ɂ��邱�Ƃ͒m���Ă��邪�A�����ĖK�˂悤�Ƃ͂��Ȃ��B�X�^�b�g�E�h�E�t�����X�E�X�^�W�A����ʂɂ���A�ނ炪���̒n��ɋ߂Â����R�͊F���ɋ߂��̂��v�Ƃ����ɂȂ��Ă���B���_�����̎{�݂��C�X�����ߌ��h�ɏP������鎖�����p�����Ă���Ƃ��B���������\���m���������Ŋӏ܂���A���l���_�����k�̃G�X�e�����W���h�̂��߂ɉ��x�ƂȂ��T���h�j�ɑ����^�Ԃ��Ƃ̎��Ӗ����A����w�̏d�݂������ē`����Ă��邱�Ƃ��낤�B �@���ӂ������̂́A�G�X�e���ƃW���h�̊W���u�x�߂��vs�n�����ҁv�̍\�}�ł͌����ĂȂ����Ƃ��B�w�͂ƌo���ɂ���Đ�����g�ɂ����Ƃ͂����A�G�X�e�������F�͂����Ȃ����j�q�B�������Љ�I�n�ʂ����ɍ����킯�ł͂Ȃ��A�����Z��n�ɂ��Z��ł��Ȃ��B�u�������ŋ������̂��߂ɂ����g���āA���ꂵ���́H�v�ƁA�W���h�ɂ������낳���ꖋ������B �@�����A��ɐE�����邱�ƂŎ�������߂Ă����G�X�e���̐����l�́A�������ƁA�������m���ɃW���h����������B�����Ďd���̂��߂Ɏ��q�Ƃ̊W�����������A���N�܂ŊQ�����G�X�e�����A�t�ɃW���h�𒆐S�Ƃ����ږ��̒��Ԃ������x����悤�ɂȂ��Ă����B���̂�����́w���m�̎����x�̋L�q�܂���ƁA�����������z��`�I�ɂ����銴�͔ۂ߂Ȃ��B�������f��Ƃ����t�B�N�V�����ŗ��z������āA���̎x�Ⴊ���邾�낤���B �@�I�Ջ߂��܂Ń{�[�C�b�V���ȃS�c�������蒅�Ă����W���h���A�Ō�ɃV�b�N�ȍ����܂Ƃ����p�́A�m���ɖ��͓I�������B�u�����炵�����т����Ɓv�����Ă͂₳�������ł͂��邯��ǁA�u�ς�邱�ƁA���ݏo�����Ɓv���A�l�ɂ́\�\���ɎႢ�l�ɂ́\�\�����悤�ɑ�Ȃ�˂Ɖ��߂Ďv�킹���҂ł������B�u�E�F�����C�h�v�Ƃ́A�܂��ɖ{��̂悤�ȉf��̂��߂ɂ���`�e��ł͂���܂����B �i�Q�O�Q�Q�D�S�D�P�O�D�L�j �Q�O�Q�Q�N�I�X�J�[�i�C�g�E�E�H�b�`���O�I  �@����͖{���Ɂu�n�v�j���O�v�������̂��H�@�E�B���E�X�~�X�̃r���^�����̂��Ƃ��B �@���n���ԂR���Q�V���ɊJ�Â��ꂽ�A�J�f�~�[�܂̎����́A�����h���r�[�V�A�^�[�ɖ߂��A�I�X�J�[���̎�n�����ĊJ�B�S�N�Ԃ�Ƀz�X�g�����u���Ƃ������Ì^�̑̍قɁB�������A���̃C�x���g�{���̉₩���⟭�E���ɂ͌������A�ǂ������q�̋������ЂƂƂ��������悤�Ɍ������B �@�܂��̓z�X�g�i�Ƃ������z�X�e�X�j�̏����R�l���C�����Ȃ��B���W�[�i�E�z�[���A�G�C�~�[�E�V���[�}�[�A�����_�E�T�C�N�X�̂R���D�́A���{�ł̒m���x���Ⴂ���Ƃ���������Ă��A�ǂ����^����ꂽ�Z���t�������Ă��邾���̑���l�`�݂����Ɍ����A���ꂾ���̃r�b�O�C�x���g���d���ł͂Ȃ�������ۂ��B �@���́u�^����ꂽ�Z���t�v�ɂ��Ă��A��N�ɑ����ėD�G�ȃW���[�N��Ƃ��ق��Ȃ������炵���A���i�Ȃ��̂�A�X�x���Ă�����̂����������B�u�N���ςĂ��Ȃ��f��̂c�u�c��z����B�w�Ō�̌����ٔ��x�ˁv�Ƃ��A�u���V���E�{�[������l���Ȃ̂ɑS�R���Ȃ��f����B��Ȃ�ăA�[�����E�\�[�L���͂���������v�Ƃ������Ă��A���`��A�܂��������Ȃ��킯�ł͂Ȃ�����ǁA�f����̂���ՓT�̃W���[�N�Ƃ��Ă͂ǂ��Ȃ̂��H�@�V���[�}�[�ɃX�p�C�_�[�}���̕����������ă��C���[�Œ݂����ꖋ�Ȃǂ��A���o����ł����Ɩʔ����ł����̂ł͂Ȃ����ȁB  �@���������C�����Ȃ��̋ɂ߂��ƌ�����̂��A�X�~�X�̃r���^�����������B���T���㔼�ɂ������������Ƃ���Œ��҃h�L�������^���[�܂̃v���[���^�[�Ƃ��ēo�ꂵ���N���X�E���b�N���A�q�Ȃɂ����W�F�C�_�E�s���P�b�g���X�~�X�̊ۊ��蓪�����āA�u�w�f.�h.�W�F�[���Q�x���y���݂��v�Ɣ����i�����܂ł��Ȃ��w�f.�h.�W�F�[���x�̓f�~�E���[�A���ۊ��蓪�œo�ꂵ����i�j�B����ƃW�F�C�_�ׂ̗ɍ����Ă����E�B���������������Ƃ����̂ɂ����ƒd��ɏ����āA���b�N�ɕ���ł��������̂�����A�N�����đ�{�ɉ��������Z���Ǝv���B�J�������[�N�����̂��߂ɗp�ӂ��ꂽ���̂Ɍ��������A�f��̊i���V�[���Ɠ��l�A�u�������悤�Ɍ�����v�A���O���������B���b�N�̃��A�N�V�����Ԃ���A�{���ɉ���ꂽ�悤�ɂ͌����Ȃ��������B �@�ǂ����l�q�������������Ɗ������̂́A�q�Ȃɖ߂����X�~�X���A�S�������t�܂Ŏg���ă��b�N��l�|�����������ƁB���̎��_�ł͂܂��u�q�h�����o���Ȃ��v�Ǝv���Ȃ��猩�Ă����������������A�����̕ŃW�F�C�_���E�яǂɋꂵ��ł��邱�ƁA�����ăX�~�X�̕��䗐���ƃr���^�����o�ł͂Ȃ��������Ƃ�m�����B�ƂȂ�ƃ��b�N�̔������A�p�ӂ��ꂽ�W���[�N�ł͂Ȃ��A�A�h���u�������̂��낤�B �@�a����B���Ȃ��W�F�C�_�̗E�C�ɂ͌h�����邯�ǁA����������Ȃ̂�����E�B�b�O���炢�����Ă���悩�����̂ɂˁB����A�ޏ��͑S�R�����Ȃ��킯�ł����B�X�~�X���A���ɐ������˂��̂Ȃ�A���Ƃ���y���ʼn���悩�����̂��B���������X�Ԃ����R�ƌ����Ă��܂��ƁA�u�ف[��A�L�F�l��ȂɍD������������邩�炱���������ƂɂȂ�B�w�����A�J�f�~�[�܁x�̂܂܂ɂ��Ă������ق����I�V�����ł悩��������H�v�Ƃ������l�����`�҂̐����ǂ����炩�������Ă������ł���ˁB �@�X�~�X���w�R���J�b�V�����x(2015)�Ŏ剉�j�D�܂Ƀm�~�l�[�g����Ȃ��������Ɓi�y�сA����ɔ����_�c�j���A�A�J�f�~�[������l���ɑǂ��傫�Ȃ��������̂P�Ƃ��Ȃ��Ă��������ɁA����̏o�����͔���Ƃ��������悤���Ȃ��B �@�ȉ��A���Y�^�����˂āA��v�ȏ܂̎�܌��ʂ��B �����ے��҉f��܁w�h���C�u�E�}�C�E�J�[�x �@���{�f�悪�w������тƁx�ȗ��̎�܂��ʂ������A�ē܂��i�܂͓������B�R���Ԃ�������{�f�悪�ʔ����Ƃ͎v���Ȃ��̂ŁA�����g�͖����ł��B ���̋ȏ܃m�~�l�[�g�i��܂͂����j�w�t�H�[�E�O�b�h�E�f�C�Y�x �@�l�I�ɖ|��Ŋւ������i�B�ǂ����Ŕz�M����Ă���̂������H�@�E�N���C�i�o�g�̎剉���D�~���E�N�j�X���v���[���^�[�߂����A�u���̐��E��ɂ͋C���ǂ��v�Ƙb���ɂƂǂ߁A�u���V�A�v��u�E�N���C�i�v�Ƃ��������������ɂ��Ȃ������B���̎�҂�v���[���^�[�����̒��ɂ��A�E�N���C�i�ւ̎x����i������A���V�A������肷��l�́A�ӊO�ȂقǏ��Ȃ��B�����ɔz���≓�������Ă����̂��낤���B ���������D�܁@�A���A�i�E�f�{�[�Y�w�E�G�X�g�E�T�C�h�E�X�g�[���[�x �@�O����̌��ʂɈ�킸�A��{������܁B�X�s�[�`�ł́A�I���W�i����œ����������������^�E�����m�Ɂu���Ȃ��̃A�j�[�^�����̂悤�ȃA�j�[�^�����ɓ����J�����v�Ɗ��ӂ����B�u�N�B�A�̃A�t���E���e���n�v�ƁA������Љ�B �������j�D�܁@�g���C�E�R�b�c�@�[�w�R�[�_�@�����̂����x �@���ۂɒ��o��Q�����ނ��A�W�҂̖��������Ď�܁B�X�s�[�`�̓��[���A����������b�ōs�����B ���剉���D�܁@�W�F�V�J�E�`���X�e�C���w�^�~�[�E�t�F�C�̓��x �@���Z�h���D�̏���܁B�X�s�[�`�ł́u����������ɕ��f����悤�Ȗ@�āv��ᔻ���A�ǓƂ�������l�X�ւ̘A�т�\�������B���N�̎�҂����̒��ɂ����ẮA�����Ȃ������I�ȃX�s�[�`�������B ���剉�j�D�܁@�E�B���E�X�~�X�w�h���[���v�����x �@�r���^�����̂S�T����ɁA���n�]�ǂ���I�X�J�[���l���B�u���������d�������Ă���Ƒ��l���爫��������ꂽ��A�ςȉ\�𗧂Ă�ꂽ�肷��v�ƁA�ォ��U��Ԃ�A�������ɐ��_�I�ɉ������߂���ł��˂Ǝv����X�s�[�`�������B �@�ł��A�����̎������A�b�v�ɍv���������ȗ܂Ȃ���̃X�s�[�`�́A�����Γr�ꂽ��A�����R�����g�̌J��Ԃ��ɂȂ����肵�Ă����ɂ�������炸�A���X�T�����ɂ킽���đ����Ă��A�Ō�܂Œǂ��o�������f�B���炳�ꂸ�B�w�h���C�u�E�}�C�E�J�[�x���_������ē������Ƃ����Ԃɒd�ォ��ǂ�ꂽ�̂ɔ�ׂ�ƁA���Ƃ��s�����Ȉ����������B�܂��A�p���ꍑ��Ƃ��Ȃ���҂��āA��N�A�����ɒǂ��o�������f�B��炳�ꂪ���ł����ǂˁB ���ē܁@�W�F�[���E�J���s�I���w�p���[�E�I�u�E�U�E�h�b�O�x �@�O�N�̃N���G�E�W���I�ɑ����ď����ē���܁B�w�p���[�E�I�u�E�U�E�h�b�O�x�͂�����܂߂ĂP�P����Ƀm�~�l�[�g����A��i�܂̍ʼnE���ł����������A��܂͊ē܂݂̂ɂƂǂ܂����B ����i�܁@�w�R�[�_�@�����̂����x �@�ŁA��i�܂���������̂������Ƃ������邱�̈��B�m���ɗǍ�E����ł͂��������ǁA��͂茆��̗̈�ɂ͓͂��Ȃ������t�����X�f��̒����ȃ����C�N�����ɁA�l�I�ɂ͉ʂ����Ď�܂ɒl�����i�������̂��A���^�₾��B������������������Ȃ�A��Q�����o�D�������N�p�����_���A�t���ʓI�ɍ�p�����̂ł͂Ȃ����Ƃ��v����B �w�R�[�_�@�����̂����x�͋r�F�܂���܂������A�I���W�i���r�{�܂�������̂́A��i�܌��ł��������w�x���t�@�X�g�x�������B���̗�������łɊӏ܂����g�Ƃ��ẮA�ނ����҂̂ق�����i�܂ɒl�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���邯�ǂȁi�P�O�{�̌���̂����A�w�p���[�E�I�u�E�U�E�h�b�O�x���܂ނT�{�͖����Ȃ̂ŁA����ȏ�̂��Ƃ͌����Ȃ��̂����j�B �i�Q�O�Q�Q�D�S�D�P�O�D�L�j �K���p�E�_�[�E�~���N�V�F�C�N�@�@GUNPOWDER MILKSHAKE �i�Q�O�Q�P�N�A�����Ɓ��āA�����F�����b�q�j  �u�X�N���ł́w�R�T�T�x�v���Ǝv������A���ɂ͂�����A�w�O�����A�x���ЂƂ܂ݓ��ꂽ�u�V�X�^�[�t�b�h�Łw�W�����E�E�B�b�N�x�v�������Ƃ����������B�q���C���i�J�����E�M�����j�Ƃ��̕�i���i�E�w�f�B�j�A��̗F�l�����i�A���W�F���E�o�Z�b�g�A�~�V�F���E���[�A�J�[���E�O�M�[�m�j�Ƃ�������v�ȓo��l���͑S���E�����B���̔ޏ��炪�A�Q����Ȃ��ďP���Ă���g�D�̎h�q���������������Ɠ|���Ă����Ƃ����A�a���f��̖��͖��ڂ̃A�N�V�����E�t�F�~�j�X�g�E�R���f�B���B �@�V�s�̃i���H�b�g�E�p�v�V���h�ḗA����Ƃ�����O�A�i�����j��M���O���Ԃ�����ŁA�ϋq�T�[�r�X�ɂ���s�����B �@���Ƃ��q���C���̃T���́A���Ղ����_�b�T�������O�R�[�g�Ǝ���x��̖X�q�œo�ꂷ����̂́A���X�ɓG����M�����O�ɋ�������A�{�E�����O�E�W���P�b�g�ɒ��ւ����������ˁi��̎ʐ^�Q��)�B���ւ�����������ɂ͉������R������낤�Ǝv���Č��Ă��Ă��A����Ȏ���̐�������������A�M�����O�͓��m�������ĂƂ��ƂƎ��ʁB���Ԃ�p�v�V���h�ēɂ��Ă݂�A�q���C�����J�b�R�悭�����邽�߂ɃT�i�M���璱�ɒE�炳���������̘b�ŁA����I�K�R���Ȃ�ĕʂɂǂ��ł��������Ƃ������̂��낤�B �@�T�����������Ȉ�҂���u���r���}�q�����v�Ȃ𒍎˂����̂��܂������B���͂����Ɖ���Ă��邵�A���͒��蒵�˂���ł���̂ɁA�r���������Ȃ��Ȃ��Ȃ�Ă���킯�Ȃ����A������^�ʖڂɔᔻ����͖̂����Ă��̂��B���͂ł͘r���グ���Ȃ��T�����A�̂���]���������S�͂Řr�������グ�A�M�����O���e�����Ă����o�J�o�J�����𑶕��Ɋy���߂A����ł����B�u���������A�r�̓}�q���Ă�̂ɁA�Ȃ�ň��������������v�Ȃǂƃc�b�R�~����ꂽ�肵�Ȃ���ˁB �@���Ղ̎R��ƂȂ�̂̓o�Z�b�g�ƃ��[�ƃO�M�[�m���c�ސ}���قł̎��������A�G���������e����������܌g���Ă���Ƃ����̂ɁA�����̏e����ł͏I���Ȃ��B����`�F�[�����g�����G�O�������킪�����ɍ������܂��i�������ło�f�P�Q�Ƒ��������j�B����܂�����I�ɂ͕K�R���Ɍ����邪�A�f��I�ɂ̓u���{�[���B���̒��ɂ́u����I�K�R���͖������Ă��邯�ǁA�f��I�Ȗʔ����̂Ȃ��v��i��A�u����I�K�R���������Ă��邽�߂ɁA�f��I�ɖʔ����Ȃ��v��i���������B�����猾���̂��������ǁA�f������Ă����������{���ɓ����ˁB �@�������e��i���ǂ̔��e�Ɋ܂܂�邩�́A��ΓI�Ȑ_�̊������킯�ł͂Ȃ��A����l���ꂼ��̊�����f��̌��A�Z���X�E�I�u�E���[���A�̓x�����Ō��܂�̂ŁA�b�͂Ȃ�������B�����b�A�{����u����I�K�R���������Ă��邽�߂ɁA�f��I�ɖʔ����Ȃ��v��i�ɕ��ނ���������ԈႢ�Ȃ����݂���Ǝv���E�E�E�B �@�`���ōX�N���ƒ����������A�o�Z�b�g�����[���O�M�[�m���w�f�B���A�A�N�V������i�ł͎��я\���̏��D�����B�L���̂��铮���Œj�ǂ��������玟�ւƒn���ɑ���B����͈Ӑ}�������ǂ����肩�ł͂Ȃ����A���l�A���l�A�A�W�A�n�Ɛl��o�����X�������ł��ˁB�C����̉Q���Ƀ��[�ƃO�M�[�m�ɉ����������₫�����킳���A���I�ȊW���ق�̂�ɂ��킹��T�[�r�X���_���D�܂����B �@�ޏ������̐}���ق́A�����ق�������ꂽ�����قƌ��܂����悤�ȓ����f�U�C�����܂��T�C�R�[�B�������{���J���A���蔲�����y�[�W�ɏe�킪���[����Ă���B���낦�Ă���̂̓G�~���[�E�u�����e�A�W�F�[���E�I�[�X�e�B���A�A�K�T�E�N���X�e�B�Ƃ�����������Ƃ̖{�����炵���_���A�����ɂ��V�X�^�[�t�b�h�f��I�Ńj���}�������Ⴂ�܂���ˁB �@���̐}���ق���ł͂Ȃ��A�E������Ȃ̃N���j�b�N��_�C�i�[�����X�Əo�Ă���̂́A���炩�Ɂw�W�����E�E�B�b�N�x�̉e�����낤�B�E�F�C�g���X���i�[�X���芵�ꂽ���̂ŁA��F��ς����ɓ�����ŎE���������̏e��a����B �@�_�C�i�[�ł̍ŏI����ŁA�����ʘH�����ɃJ���������Ƀp�������Ȃ���A���E���������̖\��Ԃ�������t���[���ɏo�����ꂵ�Ă����J�b�g�Ȃǂ́A���Ȃ���̂̊G�����B�o��l���������J�[���W�I��g�ђ[���̋Ȃ��A���̂܂܃V�[���̏�L�����̐S��ɂ҂�����n�}���������ȂƂȂ鉉�o���S�����B�ēA�o�D�w�͂������A�r�{�A�B�e�A�ߑ��A�Z�b�g�f�U�C���A���y�Ȃǂ̎�v���傪�����݈ꗬ�̎d���������A����͋ɂ߂��ґ�Ȃa���f��Ȃ̂ł������B �i�Q�O�Q�Q�D�R�D�Q�U�D�L�j �I�y���[�V�����E�~���X�~�[�g�^�i�`���\�������� OPERATION MINCEMEAT �i�Q�O�Q�P�N�A�āA�����F�I���Ƃݎq�j  �@�o��l���̂P�l�����炭�����̂܂܃i���[�V����������f��Ƃ����̂����X�����āA���ꂪ���������i�Ƃ���ŁA�u���[�A���̌���́����������̂��v�ƋC�Â��u�Ԃ��n���ɍD���B�{��̏ꍇ�́A���ꂪ�C�A���E�t���~���O�����i���킸�ƒm�ꂽ�W�F�[���Y�E�{���h�̐��݂̐e�ŁA��풆�͎��ۂɏ�Ζ����������ƂŒm����j���Ƃ����̂�����A�C�������Ă���B�u��͍�Ƃ��炯�v�Ƃ�����������ɂ������o�����B �@��Q����풆�̎��b����ށB�V�`���A���U�����v�悵�Ă����p����́A�U�����������������̂𒆗����ɕY�������A�i�`�X�ɏ㗤�n�_������点����ɏo��B���s���ƂȂ��������^�M���[�����i�R�����E�t�@�[�X�j�ƃ`�������[��сi�}�V���[�E�}�N�t�@�f�B���j�́A�z�[�����X�̎��̂B������A��������莆���U��������Ƃ�����������i�߂邪�A�\�����ʓ�肪���X�Ǝ���������E�E�E�B �@�ē̃W�����E�}�b�f���́A���̐��I�̊������鎖�̓^������ł͂Ȃ��A�����̏������������i�����{�R�Ƃ͂��炢�Ⴂ���j���s�`�[���̋�Y���������т��A�����ă����^�M���[�ƃ`�������[�A�����̏����W�[���Ƃ̎O�p�W���A�O�O�ɕ`�ʂ����B �@�l�I�ɂ̓`�������[�i�Ԃ��Cholmondeley�ł���B�ǂ߂܂���ˁj�̏���Ԃ肪���|�C���g���������ȁB�����A�ŏ�����W�[�����D���Ȃ̂����������Ȃ���B�����Ǐ����Ă�͖��x���N�ł��Ȃ��Ȏq�����ɍ��ꂿ�Ⴄ��ˁB���̃����^�M���[�ƃW�[���̕s�ρi�����j�W�A�ʂ����Ă��̉f��ɕK�v���������낤���B �@�q���C���̃P���[�E�}�N�h�i���h�́A��ɂ���Đ␢�̔����Ƃ����킯�ł͂Ȃ�����ǁA�Ɠ��̕��͋C�������o���B�����Ȃ̂��B���Ă�����A���͖��S�l��������ƁA�`�������[�N��|�M���܂��肾�B���������̐l�A�d�����ł���B�K�v�ɔ����āA���̂̂������肳����{�[�C�n���g���Ă���V�[���Ȃ�āA�����A�E�X�ł����B �@���̓���i���̂ƁA�������肳��̕ĕ��j�����������[���E�}�N�t�@�f�����A���҂Ƃ��Ă����҂Ƃ��Ă������ɍv��������Ƃ����Δ�̂���������肩�����B�㗤���Ɍ������͑D��̔ނ̃J�b�g�́A�I�[�v�j���O���ƍ�팈�s���̓�x�A�J��Ԃ���Ă���B�O�҂ł͔ނ����҂Ȃ̂��܂��ϋq�͒m��Ȃ��̂�����ǁA�f��̕��@��m��҂ɂ͔ނ̏d�v�x�������Ɠ`���悤�ɎB���Ă���̂��i�v���̉f�扮�Ȃ瓖�R���Ȃ��ׂ��^�X�N�ł͂��邯��ǁj���_�����B �i�Q�O�Q�Q�D�R�D�Q�U�D�L�j �R�[�_�@�����̂����@�@CODA �i�Q�O�Q�P�N�A�ā��������A�����F�Óc�R�I�q�j  �@�t�����X�f���w�G�[���I�x�i2014�N�j�̂قڒ����ȃ����C�N�B�Ƒ��̒��ł�����l�����̏������A���̂܂܉Ƒ����x����l���𑗂邩�A����ǂ��ė������̊����ɔY�ށB���o��Q�҂̉ƒ�͐�������Z�b�N�X�����₩�܂����Ƃ����������|�C���g���܂߁A�ؗ��Ă�o��l���͂قڈꏏ���B �@�����A�w�G�[���I�x�̂��炷�������Ԃ��Ă݂āA�P�d�v�Ȑݒ肪�ύX����Ă���̂ɋC�������B����͕���i�����āj�ł���Ƃ̐E�Ɓi���_�Ɓ������j�ł��Ȃ��A�q���C���i�G�~���A�E�W���[���Y�j�̂��傤�������킩��Z�ɕς���Ă������ƁB�ēE�r�{�̃V�A���E�w�_�[�́A����ɂ���ČZ�M�ɂ���ȃZ���t�����킹�邱�Ƃ��\�Ȃ炵�߂��B�u�Ƒ������邩����Ĕڋ��ɂȂ�ȁB���O�����܂��܂ł����̉Ƒ��͕��a�������v �@�������w�A���W���[�m���ɉԑ����x�̃`���[���[���V�˂ɂȂ�O�́u���a�v�Ǝ������̂ɂ��v���āA���X���߂ɍ����Ă��܂��Z���t�ł͂���B�ł��A��������Č���҂��v�������Ȃ����z��_���A����ɋC�Â����Ă����̂��A���̎�̍�i�̎g���Ȃ̂��낤�Ƃ��v���B �@�����A�u���܂ꂽ����̂��Ȃ��������҂��ƒm���āA��ĂĂ����邩�Ƌ��낵���Ȃ����v�Ƃ������ꂳ��i�}�[���[�E�}�g�����j�̃Z���t�́A�������ɃM���O�ł���ˁH�i�w�G�[���I�x�ɔ�ׂāw�R�[�_�x�ł̓}�W�x�����������C�����邪�j�@����Ƃ��A�����l���邱�Ƃ����łɌ����҂̎v�����݂Ȃ̂��낤���H �@�����̐ݒ肾���ł͂Ȃ��A�Љ����܂��A�w�G�[���I�x��̂W�N�Ԃň�_�A�傫���ω������B���Ȃ킿�u�����O�P�A���[�v�Ƃ������t����������s���������Ƃł��ˁB���߂Ɍ��t���肫�B�w�G�[���I�x�ł̓q���C���̗������Ɉꖕ�̂킾���܂���������l�X���A�w�R�[�_�x�ł͂�苤���ł���悤�ɂȂꂽ��������Ȃ��B������Љ�̐i���ƌĂ����ĉ��ƌĂڂ����B �i�Q�O�Q�Q�D�Q�D�P�W�D�L�j �t�����`�E�f�B�X�p�b�`�@�U�E���o�e�B�A�J���U�X�E�C���j���O�E�T���ʍ� THE FRENCH DISPATCH OF THE LIBERTY, KANSAS EVENING SUN �i�Q�O�Q�P�N�A�āA�����F�Γc�q�j  �@�t�����X�l���D���ăX�S����Ȃ��B�|�p�����̕K�R�����̂Ə����邳�����Ƃ����킸�ɁA����ȉf��ł�������E�����Ⴄ��ł��˂��B �@���A�u����ȉf��v�Ƃ����̂́u���A�E�Z�h�D�قǂ̗L�����D���킴�킴�w�A�k�[�h��������悤�ȃW�������̉f�悩��i�j�v�Ƃ����Ӗ��ł���A��i���̂̉��l�����Ƃ��߂���̂ł͂���܂���B �@�E�F�X�E�A���_�[�\���ē��ĂA���̂P�O�W���Ԃ̒��ɐ�����Ȃ����炢�̎�����V�т�d�|�����Ԃ�����ł��܂���ˁB�ވꗬ�̋Â�ɋÂ�����ʍ\���͌����ɋy���A�A�j����D������A���m�N���A�J���[�A�p�[�g�J���[�����݂ɐ�ւ��A��ʂ̃A�X�y�N�g����߂܂��邵�������ւ���i�X�^���_�[�h�E�T�C�Y�̉�ʂł͏o���ʒu�܂Œ����A�E�A���Ƃ�����j�B�F�ʂ��ς��������ɂ��̌��ʂ��킩�邯�ǁA�A�X�y�N�g��̕ύX�Ӑ}�ȂNj��ݎ���Ă����獡�x�̓X�g�[���[��Z���t�����ɓ���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂ŁA����͌���A�^��Ō��Ԃ������Ȃ��B �@���ł��ʔ����������̂́A�����ɍ������܂�Ă����ꌩ�X�`�[���ʐ^�̂悤�ȃV���b�g�B�G���̌f�ڎʐ^���C���[�W���Ă���̂��낤���A�悭�悭����Ύʂ��Ă���l���������Ă���킯�ł���B����ɂ�������炸�A������ł���i�悤�Ɍ�����j���̂́A�i�s�����ɔ�ё����邱�Ƃ��A�d�͂ŗ������邱�Ƃ��Ȃ��~�܂��Ă���B�ēA�w���e�R�����܂��B �@�����A���肱�݂����v�f�����܂�ɑ��������̂��A�����̃p�[�g�ɕ������ꂽ����́A���ꂼ��ɖ��͂��������̂̐[�݂ɂ͌������B�ߍ�́u���P���v��u�u�_�y�X�g�v��u���[�����C�Y�v�ɂ́A���ꂼ��ɃG���[�V���i���Ȍ����ꂪ���������ǂˁB �@���̂Ƃ���̃A���_�[�\����i�́A�P�P�̃J�b�g�ɐ��荞�܂����������̈�r�B��ʂ̋��X�ɂ܂Ŗڂ�z��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ŁA�������肷��Ǝ������ǂݐ�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��i�|��̐Γc�q�����̐ӔC�ł͂���܂���j�B�Q�s���̓��Ɍ��邱�Ƃ͔��������ł��ˁB �@���Ăĉ����āA����́i���Ȃ�m�I�ȕ��̂́j�G���L�����L�҂��ǂݏグ��Ƃ����̍ق̃��m���[�O�������A�����͓��R�������t������A�b�����t�̃_�C�A���O�ɔ�ׂāA�܂��܂����ɓ���ɂ����B�ŋߑ����Ă���Ƃ��������ł̋��Ȏ�҂����́A�`���̃A���W�F���J�E�q���[�X�g���̃i���[�V���������ł���グ�ɂȂ��Ă��܂��������B �@�A���_�[�\����i�̂܂��ʂ̓����́A��삲�Ƃɓ���́i����ł��ĉˋ�́j�N��Əꏊ�i���Ƃ��ߖ����̓��{�A�R�O�N��̒����A�U�O�N��̃j���[�C���O�����h�n���̓��Ȃǁj��I�肵�A�ēȂ�ł͂̐F�ɐ��ߏグ�����E�ς�����Ă���Ƃ���B����ł̓C���^�[�l�b�g���o�ꂷ��ȑO�́A���Ȃ킿���̎G����w���^�������C���������̃t�����X����������`�ɂȂ����B �@�䂦�Ɋ�{�͉p���i�Ȃ̂����ǁA�������Ƃ�����ʂŃt�����X��̃Z���t�����ꂱ�ނ킯�ł��B���̏ے��ƌ�����̂����Y���̃V�[���̃��A�E�Z�h�D�ŁA�����h���}�`�b�N�Ȓ��[���t�����A�ϋq���G�L�]�`�V�Y���Ƃ������̉��Ɋ����B��������������������e�̃Z���t����Ȃ����ǁA�t�����X��Ō����Ɩ��ɓN�w�I�ɕ�������̂͂Ȃ��H �i�Q�O�Q�Q�D�Q�D�P�Q�D�L�j �S�[�X�g�o�X�^�[�Y�^�A�t�^�[���C�t�@�@GHOSTBUSTERS: AFTERLIFE �i�Q�O�Q�O�N�A�āA�����F�A���[�������j  �@�W�O�N��Ƀq�b�g�����l�C�V���[�Y�̑��ҁB�Ƃ͂����\���m���Ȃ��Ŋӏ܂����̂ŁA�o��������u��l����Ƃ̂��c���������āA�R�l�̌��c�S�[�X�g�o�X�^�[�̂����̒N�Ȃ낤�H�v�ƃ��N���N�����B�ł��A���̐g�ɒ���������A�C�e���ŋC�Â��ׂ��ł����ˁB �@���Ȃ݂ɂ��̃}�b�P�i�E�O���C�X���Ďq�́w�A�C�A�g�[�j���x�̎q���炵���B���́i��l�Ȃ炸�Ƃ��j���^�ŕς��c�B �@���i���ɗ��n�j�̍D���Ȏq���N���X�ŕ����Ă��܂��̂́A���Ă���Ȃ����ۂ炵���B��l����Ƃ̂��ꂳ��́A����Ȗ��t�B�[�r�[��S�z���āuDon't be yourself�i�����炵�����Ȃ��Łj�v�Ȃ�Đg���W���Ȃ����t�Ŋw�Z�ɑ���o���B �@�ŏ��͂��ꂪ�u�N���������炵�����Ă��Ă����̂��v�Ƃ����瑊�Ȃ͂�茾�t�̃A���`�e�[�[�Ƃ��Č����Ă���悤�ɕ��������̂�����ǁA���ꂪ�i�ނɘA��āA���₢��A����ς肱��́uBe yourself�v�̕��ꂾ���Ǝv���������B���l����ǂ������邩�Ȃ�ċC�ɂ����ɁA����A�����C�ɂ��Ȃ�����A�����̊S��M�ӂ�Nj����Ă����t�B�[�r�[�͑f�G���������́B�c�����S�[�X�g�o�X�^�[�ł��邱�Ƃ��B���Ă�����e�ɁA�u�����Ȋw�҂̌��������Ă��邱�Ƃ��ǂ����ċ����Ă���Ȃ������̂��v�Ƌl�ߊ��V�[���ɂ͂����Ɨ����B�����Ȃ�ƁA���̃_�T�����^�������Ⴆ�Ȃ����̎q���ǂ�ǂ�L���C�Ɍ����Ă���̂�����A�s�v�c�Ȃ��̂ł��B �@���āA���������u�����Ƃ����ɗ����Ȃ���l������K�ڂɁA�q�ǂ��������劈�邨�b�v���Čl�I�ɑ�D���B�Z�M���G�N�g�P������ăS�[�X�g��Ғǂ��A�����u�e���v���ƎԊO�ɔ�яo���A���̗F�������S�[�X�g�E�g���b�v�𓋍ڂ������W�R���J�[�����������钆�Ղ̌�����Ȃ�āA�����T�C�R�[�ł���B �@�G���f�B���O�ł��A�I���W�i����̋ؗ��Ăɉ�A���Ă����Ȃ���A�����������҂�����傽���ɂ͉��̎d���������Ă��Ȃ����ˁi�j�B �@�Ƃ���ŁA����Ώ����ł���Q�O�P�U�N�̏����Łw�S�[�X�g�o�X�^�[�Y�x���ł��Ȃ��������ƁA���Ȃ킿�n�����h�E���C�~�X�ւ̍��ʂ̋V���A�g�{��̎q�h�ł���W�F�C�\���E���C�g�}���ē͂���Ă���B �@�Q�O�P�S�N�ɖS���Ȃ������C�~�X�́u�o���v����\�ɂ���u�e�w�Z�p�̐i���ɂ͋������肾�B���������C�g�}���́A������e�����������C�~�X�ɁA���҂Ǝ��҂̋��E���z��������悤�Ȃ��Ƃ͌����Ă��Ȃ��̂ł��ˁB�����B �i�Q�O�Q�Q�D�Q�D�P�Q�D�L�j �Q�O�Q�P�N�i���́j�x�X�g�P�O�I �@�V�^�R���i�E�C���X�����ǂ̖҈Ђ͑O�N����p���B�u�G�v�̐��̂��킩���Ă���ɘA��āA�u�f��قɍs���̂͂���قǑ傫�ȃ��X�N�v���ł͂Ȃ��������ˁv�Ƃ����ӎ��͍L���������̂́A�������T�C�h�̃n���E�b�h�̓���������A���{���J�����m��̖{�����L�тȂ������B����ɓd�Ԃɏ��Ȃ��Ɖf��قɍs���Ȃ��N�\�n���ݏZ�҂Ƃ��ẮA�������ɉď�̑�T�g�̂��Ȃ��ɏo�����̂͂��߂��ꂽ���ˁB �@���ǁA�P�N��ʂ��Č���Ŋӏ܂����{���͂S�O�{���傤�ǁB�Q�O�Q�O�N�̂Q�X�{���͑��������A�܂��܂��R���i�O�ɂ͂قlj����B�Q������V�j�A�����Ŋӏ܂ł���i����Ӗ��A�g�z�z�ȁj�g���ɂ��Ȃ����̂ŁA�Љ������킾�����班�Ȃ��Ƃ��T�P�y�[�X�ŊςĂ��Ă����������͂Ȃ��������B �@�n���E�b�h�̑��X�^�W�I��f���Ƃ����x�݁ior������߁j���[�h�ɓ����Ă��邹���������Ă��A�S��h���Ԃ���悤�ȍ�i�Ƃ̏o������Ȃ������B���́u���[�r�[�E�U�E�u�[�r�[�v�Ɋ��z��Ԃ�����i���N�ԂT�{�����Ȃ������Ƃ��������ɁA���̂��Ƃ��[�I�ɕ\��Ă��܂���ˁB �@�x�X�g�P�O��i�̐��썑�����Ă��A���L�̂Ƃ���ĒP�Ƃ͂R�{�̂݁B���̂����Q�{�͎剉�����ꂼ�ꍋ�B�l�Ɖp���l�B�c��P�{�͕č��l�̎剉�����A�͉p���l�ŁA���䂪�����h���B���ɂ�����ɉp��������ł����i�������A�Ȃ��������ău���e���F�̋����p�[�\�i���E�x�X�g�P�O�ɂȂ����B�p���̉f��E�����đ����R���i�ɖ|�M����Ă���͂��ł����ǂˁB �@���X�g�͗�N�ǂ���u�ǂ��������v�ł͂Ȃ��A�u�ӏ܂������v�ł��B �P�@�w�Q�P�u���b�W�x�i�Q�O�P�X�N�A�����āj �@���������`���h�E�B�b�N�E�{�[�Y�}���̎剉��B�ނ��������Y�������łȂ��A�����ƂQ�l�̐l��������������`����Ă����̂ŁA�I�Ղ܂ŋٔ������r��Ȃ������B �Q�@�w�W�F���g�������x�i�Q�O�P�X�N�A�p���āj �w���b�N�E�X�g�b�N�`�x�قǂ̔j��I�ȃp���[�͊������Ȃ��������̂́A���������u�L�ۖ��ۂ����藐��v���ă^�C�v�̉f����B�点��ƁA�K�C�E���b�`�[�͖{�̏o���܂��ˁB �R�@�w�A�����i�C�g�̖ڊo�߁x �S�@�w�t�@�[�U�[�x �T�@�w�N���G���x �U�@�w�v���~�V���O�E�����O�E�E�[�}���x�i�Q�O�Q�O�N�A�p=�āj �u���̘b�A�ǂ��Ɏ��܂��ł����H�v�Ǝv���Ȃ���ςĂ���ƁA���܂�ׂ��ꏊ�����������݊O���Ȃ���A�~��꓾�Ȃ��ޗ��Ɍ������ĒĂ��Ă����B���̂�����̗\�z�̗���Ԃ肪�܃��[�X�ŕ]�����ꂽ�䂦�B �V�@�w���~�j�Z���X�x �W�@�w�L���b�V���g���b�N�x�i�Q�O�Q�P�N�A�ā��p�j �@�K�C�E���b�`�[��i�Q�{�ڂ̃����N�C���B�`������R���̂P���炢�̂Ƃ���Ŏ��Ԏ����T�J���O�ɖ߂�ƁA����܂Ō����Ă������E����ς���B���̒��j���Ȃ����b�`�[�ꗬ�́u�����ʁE�ʎ��_�Č��e�N�v�͖{��ł����Ɍ��ʓI�B �X�@�w���X�g�i�C�g�E�C���E�\�[�z�[�x�i�Q�O�Q�P�N�A�p�j �@�N���]���́u���v�Ɏ���܂łǂ�ȃW�������̉f��Ȃ̂������悭�킩��Ȃ����A����Ȃ��Ƃɂ͂��\���Ȃ��ɍ�i���E�Ɉ������܂��B�v�剉�̂Q�l��������ĉ��X�Ɠ���ւ�葱����V�[���̐ꖡ�Ƃ�������B �P�O�@�w�p�[�t�F�N�g�E�P�A�x�i�Q�O�Q�O�N�A�āj �@���ɘV�l��삪�e�[�}�̃s�J���X�N������鎞��ɂȂ������B���̈��Ƃȏ��㌩�l���w�t�@�[�U�[�x�̖ꂳ��ƑΌ������������́B �i�Q�O�Q�Q�D�P�D�W�D�L�j |
![]() �@�Q�O�P�U�`�Q�P�N�́u���[�r�[�E�U�E�u�[�r�[�v��
�@�Q�O�P�U�`�Q�P�N�́u���[�r�[�E�U�E�u�[�r�[�v��
![]() �@�Q�O�P�P�`�P�T�N�́u���[�r�[�E�U�E�u�[�r�[�v��
�@�Q�O�P�P�`�P�T�N�́u���[�r�[�E�U�E�u�[�r�[�v��
![]() �@�Q�O�O�U�`�P�O�N�́u���[�r�[�E�U�E�u�[�r�[�v��
�@�Q�O�O�U�`�P�O�N�́u���[�r�[�E�U�E�u�[�r�[�v��
![]() �@�Q�O�O�Q�`�T�N�́u���[�r�[�E�U�E�u�[�r�[�v��
�@�Q�O�O�Q�`�T�N�́u���[�r�[�E�U�E�u�[�r�[�v��
![]() �@�l���������������������f�ڂ̉f��]��
�@�l���������������������f�ڂ̉f��]��
![]() �@�g�b�v�y�[�W�ɖ߂�
�@�g�b�v�y�[�W�ɖ߂�